- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.1387 芸術・芸能・映画 『映画という《物体X》』 岡田秀則著(立東舎)
2017.02.07
『映画という《物体X》』岡田秀則著(立東舎)を読みました。
「フィルム・アーカイブの眼で見た映画」というサブタイトルがついています。 著者は1968年愛知県生まれ。東京国立近代美術館フィルムセンター主任研究員として、映画のフィルム/関連マテリアルの収集・保存や、上映企画の運営、映画教育などに携わり、200年からは映画展覧会のキュレーターとして活動。また映画史ライターとして、学術書から一般書まで世界・日本の映画史を踏まえたさまざまな論考、エッセイを発表しています。本書は、北九州市門司にある映画史料館「松永文庫」の松永武氏から頂戴した本です。本書の中に「松永文庫」が紹介されています。
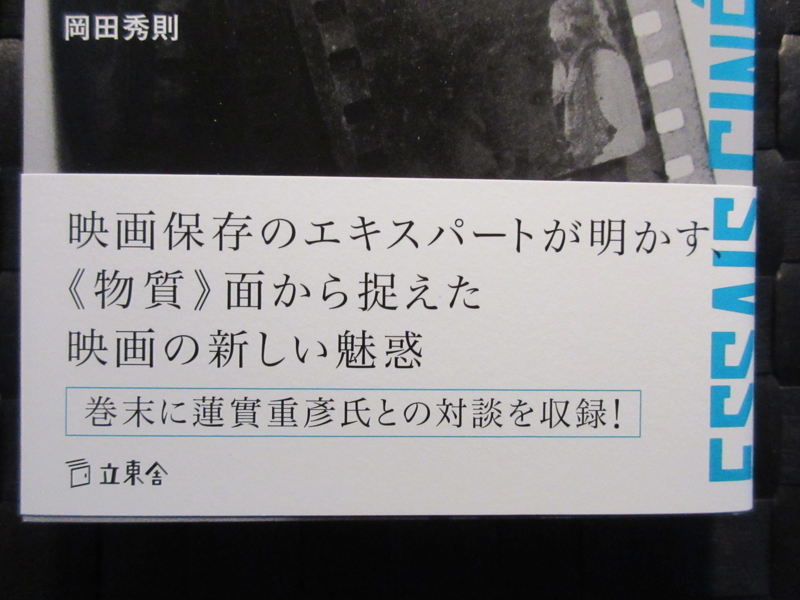 本書の帯
本書の帯
本書のカバー表紙には、写真家・中馬聰が可燃性のナイトレート素材の映画フィルムを撮影した「Nitrate Film」が使われています。 帯には「映画保存のエキスパートが明かす、《物質》面から捉えた映画の新しい魅惑」「巻末に蓮實重彦氏との対談を収録!」と書かれています。また帯の裏には「見てない映画も、愛せますか?」というコピーとともに以下のように書かれています。 「映画フィルムは牛からできている? 助けないと爆発する? ツンと酸っぱくなる? 遠い旅に出て帰ってこない? そんな、不可思議だけれども愛らしい『物質としての映画』と日々向き合う著者がたどりついた『すべての映画は平等である』という新しい視座。7万本以上の映画を所蔵するアーカイブの現場から生まれた斬新な映画マテリアリズム・エッセイ!」
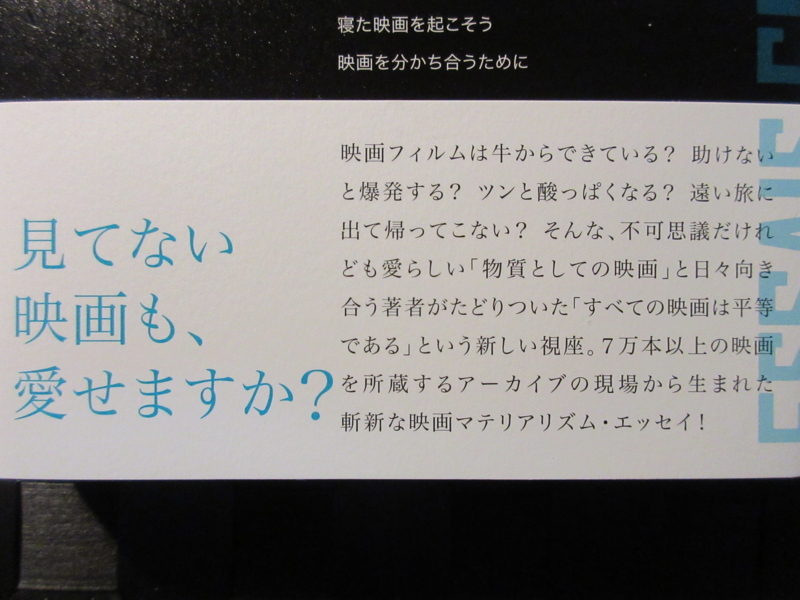 本書の帯の裏
本書の帯の裏
さらにカバー前そでには、以下のような内容紹介があります。
「過去の文化遺産を保存・運用する『アーカイブ』。その仕事は現在ますます注目を集め、21世紀は『アーカイブの時代』とも呼べるでしょう。本書は、そのアーカイブを映画という分野で担ってきた著者による、『物質としての映画』にまつわるエッセイ集です。曰く、映画フィルムは牛からできている。映画フィルムは正しく救わないと爆発してしまう。映画フィルムはしばしば遠い旅に出てしまう。そんな不思議なお騒がせ者だけれど、フィルムの映画こそ未来に残すべき本物の『映画』なのです。 本書では、そんな映画の赤裸々な姿が、土地や歴史を縦横無尽に行き来しながら語られます。そして、映画アーカイブの基本思想は『すべての映画は平等である』。小津安二郎も成人映画も区別なく、7万本以上の映画が快適な環境で未来へ引き継がれてゆく映画アーカイブの収蔵庫は、そのような映画への新たな視座を生み出す場所でもあります。巻末には蓮實重彦氏との対談を収録!」
本書の「目次」は、以下のようになっています。
はじめに「 生まれたからには、すべて映画は映画」
第1章 なぜ映画を守るのか
すべての映画は平等である
「映画を守ろう」と言ったのは誰?
日本では映画は保存しないようです、とアラン・レネは言った
映画が危険物だったころ
地域映像アーカイブの可能性
映画は牛からできている
映画館を知らない映画たち
“私たち”の映画保存に向かって 対談:石原香絵
第2章 フィルム・アーカイブの眼
映画は密航する
映画は二度生まれる
観たことのない映画に惚れた話
いまなぜ映画館が必要なのか
ジョナス・メカスの映画保存所に行った
寝た映画を起こそう
映画を分かち合うために
私のシネマテーク修業日記 ノンフィルムの巻
第3章 映画保存の周辺
小さな画面、大きな画面 ある映画館の100年
ノスタルジーを超えて
我らが「紙の映画」?チラシとパンフレット礼讃
映画はなくても映画史は立ち上がる
3D映画、敗北の歴史
シネマテークの淫靡さをめぐって 対談:蓮實重彦
はじめに「 生まれたからには、すべて映画は映画」の冒頭を、著者は「映画には『魔』が潜んでいる」として、以下のように書き出しています。
「映画は、もう120年もずっと作り続けられてきた。120年というのも大変な数字だが、それだけの間、切れ目なく誰かが映画作りに携わり、ノンストップで映画を増やし続けてきたという事実がもっとすごい。日本の場合も、あの1945年8月15日の敗戦日でさえ、映画業界は新作の試写をしていたという記録が残っている。その日から1週間、全国の映画館は休館したが、その後再び映写機にはフィルムがかかり、以降今日まで新しい映画を見せるという行為がストップした日は1日もない」
どんな新作映画にも、終わりには長々とクレジットタイトルが流れ、その映画に関わった人の名前がずらりと並びます。これをそれなりの集中力を持って見つめるという著者は、以下のように述べます。
「恐ろしいことだ。落胆させられた映画にも、これだけの数の人間が関わっている。つまらない映画を作りたいと思う人はいない。現場の誰もが、この映画を面白いものにしようと精魂を傾けたはずだ。それでも映画は、全員がベストを尽くしたからといって必ず良い方向に進むとは限らない。絵画や写真なら、作家本人の責任だけで済むが、映画はそうはゆかない。あまりに多くの人を巻き込んでしまう。その意味で映画と言うのは、実に不思議な創作物ではないか」
また、「映画を『良い/悪い』から解放する」として、著者は述べます。
「この無数の映画を、つまらないままでもいいから救う方法はないものだろうか。どんな映画も、一度この世に生まれ出たからには、映画としての誇りを持つべきだろう。予算の大小も、ジャンルの違いも、スターが出演しているかどうかも、絶えず世の注目を浴び続ける小津安二郎作品も、概ねおじさんたちの短期記憶に終わっただろう成人映画も関係ない。時に神聖であったり、下品であったりするが、映画はいつも私たちの近くにある」
第1章「なぜ映画を守るのか」の「すべての映画は平等である」では、「田中小実昌の教え」として、著者は以下のように述べています。
「面白くない映画を我慢して見ることで人間は深みを増す、と書いたのは作家の田中小実昌である。映画鑑賞はとかく時間を食うが、人生は一度しかない。金を払ってつまらない映画を観ることは、できれば避けたい。もし映画が、食堂のようにサービスの後にお金を支払う場所だったとしたら、金銭授受をめぐるトラブルは格段に増えることだろう。自分の場合、貧乏性のせいか、途中で席を立つことは滅多にない。先に払ったからには、一応最後まで観たいとは思う。それで人間的に成長できたら、そんなに有り難いことはないが・・・・・・」
続けて、著者は以下のように述べています。
「しかしこの言葉の持つ含蓄はもっと深いようだ。むしろ『すべての映画を見ることはできない』という厳然たる事実におののいた人間だけが口にできる、特別なセリフなのかもしれない。それは、クォリティを云々するまでもなく大量の映画がこの世に生まれ出ていること、そして、それが映画の本質であるという諦念を歓びとともに受け入れること、を意味するのではないか。時に驚くほど即物的な思考をめぐらす田中小実昌のことだから、ひょっとすると彼の頭の中には、人を途方に暮れさせる『すべての映画』という観念が渦巻いていたのかも知れないと思う」
そして、「すべての映画は平等である」という言葉について、著者は以下のように述べるのでした。
「映画のアーカイブで働く人間が時々意識するだろうこの言葉は、声を張り上げて言う『スローガン』ではない。むしろ、大量のフィルムを受け取って、うず高く積み上げられたリールを日常的に目にする人間が率直に発する声なき肉声である。フィルムが積まれた場所には、やや殺伐とした空気や、非日常的な光景だけにやや神秘的な気分も漂っている。だが、その先にもう1つの愛情を感じられる瞬間がふと訪れる。つまりこの時、1つ1つの映画が面白いというより、”映画”と名づけられたこの体系全体に愛着を感じている。そこでようやく、私は映画アーキビストの仲間入りができたような気がしたのだ」
「映画が危険物だったころ」では、「映画史の《原罪》として」として、著者は以下のように物質としての映画について述べています。
「義歯、櫛、眼鏡のフレーム、ビリヤード球、ブラシの柄、ナイフの柄、シャツのカフス、洋服のカラー、靴、ピアノの鍵盤。これらは、かつて映画の仲間だった。いずれも、ジョン・ウェスリー・ハイアットたちが発明した史上初のプラスチック素材、商品名「セルロイド」の使い道である。真綿が硝酸と化合して硝酸セルロース(セルロース・ナイトレート)という物質になることは19世紀の前半から知られていたが、1869年、これに樟脳を加えると弾性に富む強い物質ができ、さらに加熱すると軟化して可塑性の大きなものとなることが発見された。その結果、本来は高価な材質で作られるべき品々がこの時代、次々とこの安価な代用素材に取って代わられた。しかし映画フィルムだけは、「代用品」ではなかった。発明の瞬間からこの素材を使っていた。いや、映画はむしろこの素材をあてにして発明されたと言ってもいい」
かつての映画フィルムは爆薬とほぼ変わらない化学的組成をしていました。このセルロイド類は、いったん着火すると燃え尽きるまで消火ができないという性質を持っていました。燃焼に空気中の酸素を要さないので、たとえ水中に沈めてもそれ自体はジリジリと燃焼を続けます。従って、発火した場合は、延焼を食い止めることに力を注ぐしかありませんでした。著者は以下のように述べます。
「仮にリュミエール兄弟によるシネマトグラフの発明(1895年)を映画史の始まりとみなすとして、不燃性のフィルムが実用化される1950年代まで、映画史のおよそ半分がこの危険な”新素材”に支配されていたことになる。発明の時点で映画がすでに背負わされていたこの重荷。映画保存の世界では、ナイトレート・フィルムはしばしば映画史の《原罪》とも呼ばれる」
「ナイトレート文学/ナイトレート映画」として、著者は「それにしても、そんな危険な素材が映画史の前半を覆い尽くしていたとは、逆に言えばロマンティックにも思われてくる。破滅と魅惑、2つの属性に引き裂かれそうなこの時代の映画は、人間の想像力をそれなりに刺激したようだ」と述べます。 そして、川畑康成の『雪国』を日本の誇る「ナイトレート文学」として紹介します。この作品の結末は、村の繭倉で起きた火事の場面ですが、繭倉の二階で映画の上映をしていたのでした。映画フィルムの発火が原因の火事だったのです。
また、著者は「ナイトレート映画」についても以下のように紹介します。
「もちろん映画も、そのロマンティシズムを易々と利用した。その典型的な一例が、イタリア映画『ニュー・シネマ・パラダイス』(1988年)ではなかったろうか。日本で可燃性フィルムの話をすると、この映画の名を挙げる人はことのほか多い。映画の中で、老映写技師アルフレードは映画館の火災で失明する。だがのちに映画館が再建されると、子どもの頃から彼を敬愛してきたトトが映写技師になる。トトの代になれば、フィルムはもう不可燃性素材になっている。アルフレードはそれを聞いて『進歩はいつも手遅れだ』とこぼすのだ」
「映画は牛からできている」では、著者はフィルムの成分について以下のように述べます。
「フィルムの乳剤は、ゼラチンの中に、溶かした感光材料を固定したものである。だのにこのゼラチン、人工的な合成技術が未だになく、すべて牛骨・牛皮などの動物原料から抽出されているという。しかも、ゼラチンは牛1頭からわずか3キロほどしか取れない。もしこの世界に牛たちがいなかったら、映画も写真もない・・・・・・。私たちがこれまで映画館のスクリーンに見てきたのは、どれもこれも牛の体内物質を通過した光の跡なのである」
また、「『デジタル・ジレンマ』とは」として、著者は以下のように述べます。
「『映画とは何か』という問いには、当然ながら単一の答えはない。だが、そこに『牛だ』という答えを付け加えられたことを、映画は誇りとするべきだろう。隆盛を極めるインドの映画業界は、果たしてフィルムが聖なる動物の死骸からできていることをどれほど知っていたのだろうか。そして、いまや到来したデジタル時代の映画は、要するに『牛のいない映画』と定義することができる。もっとも製造されるゼラチンの大半は食用なので、牛の視点からデジタル時代を憂える必要はないのだが、それでも私たちは、20世紀芸術が持ちえた大らかな物質的ロマンティシズムをこうして失ってゆくのである」
続けて、著者は以下のように述べています。
「さらに付け加えれば、その即燃性を恐れられたナイトレート・フィルムのベースの組成は、綿火薬のそれとほぼ同じ硝酸セルロースである。1941年の日本で、海軍から爆薬製造のために硝酸の大幅な割り当て増加を要求された政府が、映画界のドンたちを呼びつけ、民間に回す硝酸はない、製作会社を直ちに統合して製作本数も制限せよと言い放ったエピソードは、日本映画史をかじった人間にはよく知られている。フィルムか爆薬かの二者択一。要するに映画は、かつて”爆薬”でもあったのだ。 つまり、あえて乱暴な言い方をすれば、映画とは爆薬の上に牛の体内物質を塗りつけたものだったわけだ。将来、私たちはその奇妙な事実を忘れてしまうのだろうか。そして、映画が”もの”であった時代を、映画が”情報”になってしまった時代はいかに回顧するのだろうか」
第3章「映画保存の周辺」では、「映画はなくても映画史は立ち上がる」として、著者は以下のように「松永文庫」を紹介しています。 「2009年には、北九州市在住のコレクター松永武氏が所有する映画資料を同市が引き受け、11月、門司市民会館内に『松永文庫』をオープンさせた。その後2013年7月には門司の玄関口である『旧大連航路上屋』に拡充移転して機能をさらに充実させている」
著者は、さらに「松永文庫」について以下のように述べています。
「そこには具体的なドキュメントが、人の声が、建造物の記憶が、用意されていなければならない。北九州の『松永文庫』の所蔵コレクションで特に大きな価値を感じるのは、戦前期に地元の劇場がそれぞれ発行していた週刊の映画館プログラムであり、地元の興行主が保存していた資料である。この小さくて薄っぺらな映画館プログラムは、どの地域においてもローカルな映画史の姿を教えてくれる最高のドキュメントである。地方の『館プロ』は東京ではまず入手が困難であり、また活用の面でも、その地域にあってこそ生きてくる資料だ。『過去』を『現在』として、すぐに眼前に引き出せること。それに名前をつけたものを私たちは『アーカイブ』と呼ぶのではないか。だから、『アーカイブ』はむしろ『レトロ』とは逆のベクトルを持つ概念だと感じる」
「3D映画、敗北の歴史」では、「映画技術の『冷戦』」として、米ソ映画界の3D映画開発競争の歴史を紹介しながら、著者は以下のように述べます。
「人類は、数センチ離れた2つの眼を有している。そのことから、両眼に見えているものの微妙な違いを映画に再現しようと、幾多の人間たちが巨大な期待をかけてきた。われわれの世界と同じ視界を持つ次世代の映画、というこの上ない売り文句を謳いながら、ドラマやモンタージュよりも”出っ張る”という行為が優先されたばかりに、『未来の映画』たる権利を半永久的に失い続けているハイ・テクノロジー。時代ごとに、熱意ある人間が取り組んでは挫折し、大きな勝利を収めた人物などどこにも見当たらない。自由市場を拒絶したソ連だからこそ他国よりは命脈が保たれたものの、1990年代前半にはロシアの70ミリシステム『ステレオキノ70』も終焉を迎える。大型スペクタクルとしての3D映画は、ソ連の解体とともに去ってゆく。核兵器や宇宙開発には並びようもないが、3D映画もまた冷戦の産物だったのである」
「あとがき」で著者が書いている映画についての記述が素敵です。 映画に対する愛情に溢れています。以下の通りです。
「映画はどれも人間の作ったものだけれども、いまや映画たちだけで手を取り合って、ひとつの夢想国を作っているのだと思う。そこはもう人知の及ばない領域だから、人間が勝手に入っていいはずはない。そこでは彼らの方が人間よりずっと偉い。僕らにせいぜいできることは、ひとつひとつの映画に対する福祉を考え、それを実行に移すことだけである。それだけで充分にスリリングなことなのだ、と今ならば言える。映画は、私たちの通俗を、通俗のまま美にしてくれる表現法なのだから、いつまでも仲良くしていたいと思う。これからもどうぞよろしく」
拙著『死を乗り越える映画ガイド』(現代書林)で、わたしは映画の本質について書きました。わたしは映画を含む動画撮影技術が生まれた根源には人間の「不死への憧れ」があると思います。 映画と写真という2つのメディアを比較してみましょう。写真は、その瞬間を「封印」するという意味において、一般に「時間を殺す芸術」と呼ばれます。一方で、動画は「時間を生け捕りにする芸術」であると言えるでしょう。かけがえのない時間をそのまま「保存」するからです。 本書『映画という《物体X》』はメディア論ではなく、マテリアル論として映画を語った一冊ですが、とても新鮮な読後感を与えてくれました。