- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2011.06.30
『翼』白石一文著(光文社)を読みました。
著者はわたしの愛読する作家の1人で、すべての作品を読んでいます。
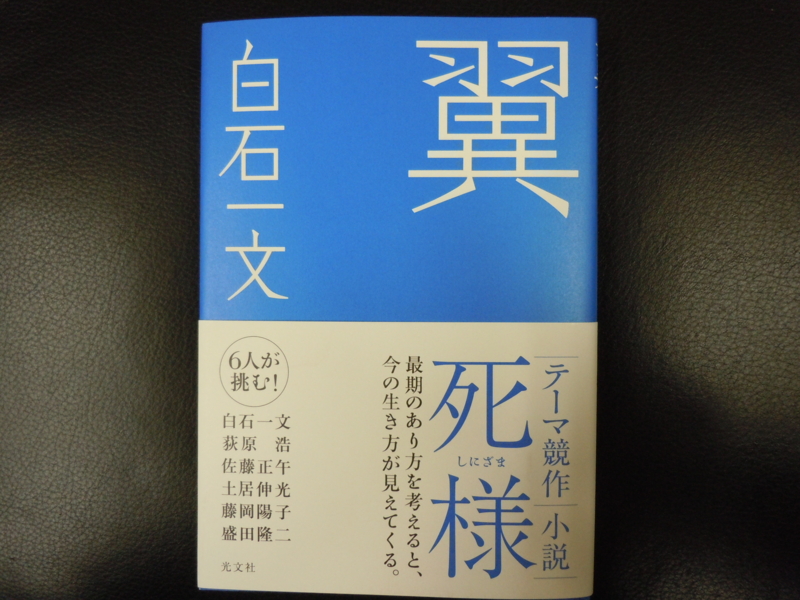
「愛」と「死」正面からを見つめた傑作
物語の主人公は、「浜松光学」という企業に勤務するキャリア・ウーマンの田宮里江子。彼女は、職場近くのクリニックで長谷川岳志と再会します。医師である岳志は里江子の親友・聖子の夫で、夫婦には二人の子どもがいます。里江子は学生時代、聖子から恋人として岳志を紹介されたことがありました。
その初対面の翌日、里江子は岳志から呼び出され、「きみと僕とだったら別れる別れないの喧嘩には絶対にならない。一目見た瞬間にそう感じたんだ」と言われます。そして、岳志はなんと「結婚してほしい、聖子とは別れる」と言うのです。あまりにも唐突な話に、当然ながら里江子は動揺します。岳志の真剣な態度から、悪ふざけでもなく至って真面目なことは分かりました。
しかし、もちろん里江子は岳志の想いに応えることはできません。そして、そのことを聖子には黙っていました。そのまま結婚した岳志と聖子は渡米します。その後、就職後の里江子の転勤などもあって、里江子と聖子は疎遠になっていました。
里江子の体調不良から10年ぶりに偶然出会った岳志の心は、まったく変わっていませんでした。岳志は、自分の直観を信じて、里江子とともに生きたいと願います。その里江子は、真実の人生を求めながらも、自分に正直になることができません。
本書は、非常に奇妙な運命にある2人の「愛」と「死」の物語です。一読して、『ほかならぬ人へ』と本書は同じテーマだと気づきました。著者の直木賞受賞作である『ほかならぬ人へ』には、「ほかならぬ人へ」と「かけがえのない人へ」という2編が収録されています。いずれも、自分の愛するべき真の相手を求める物語です。そして、いずれの物語も「恋愛の本質」を克明に描いています。
「ほかならぬ人へ」には、「ベストの相手が見つかったときは、この人に間違いないっていう明らかな証拠があるんだ」、「人間の人生は、死ぬ前最後の1日でもいいから、そういうベストを見つけられたら成功なんだよ」などの主人公の青年の言葉が出てきます。
本書『翼』では、すでに妻子がいる男性が「ベストの相手」を見つけてしまった運命を悲劇的に描いています。そのとき、自分ならどうするのか? 「死に様」がテーマですが、むしろ読者に対して「生き様」を問う小説かもしれません。里江子の両親はすでに亡くなっています。冒頭に、朝日を里江子が「太陽さん」と呼ぶシーンが出てきます。太陽を「さん」付けで呼ぶことは、死んだ父が唯一教えてくれたことでした。
父は生前、「俺たちがこうして生命もらったのも、生きていけんのもみんな太陽さんのおかげやけんな。むかしの人は、そのことばよう知っとらした。やけん、お日さん、お天道さん、と必ずさん付けで太陽さんのことば呼んどった。お前たちも絶対、太陽なんて呼び捨てにしたらいけんぞ」と、いつも里江子に次のように言っていたのです。
太陽の名を冠した社名の会社の社長を務めるわたしとしては、「この父親、いいこと言うなあ!」と思ったことは言うまでもありません。それから、里江子の母親の七回忌の法要が営まれた場面も印象的でした。
法要は、15人程度のささやかな集まりでした。母方の伯母と叔父夫婦、いとこ夫婦が2組、その子供たちが3人。それに母の友人が2人と弟の職場の同僚が1人。母の61年の人生を取り巻いていたのは、死んだ父を除けばせいぜいそれくらいの人数でした。里江子は、「人間に必要なのは広々とした人の輪ではなく、深々と重く限定的な絆のような気がする。たとえば配偶者であり、子供たちであったり」と考えます。
このくだりも、わたしの心に強く残りました。著者の小説の特徴として、作中に形而上的な会話が出てくるということがあります。それは本書でも例外ではなく、里江子の元上司だった城山という営業本部長と里江子との間で哲学的な話題が繰り広げられます。
酒席がお開きになる頃、城山が「人は死んだらどうなると思う?」と里江子に唐突に問いかけます。里江子は「完全な無」と答えるのですが、城山は「完全な無ってどんな無なのかな」とあらためて問うてきます。里江子は小さい頃から、死とは「記憶の消滅」だとずっと思ってきました。
そのため、「何も覚えていない状態なんじゃないですか。すべての記憶が消去されてしまうっていうか」と城山に対して答え、「共有されたデータっていう送信済みのデータっていうか、そういう記憶は当然他のメモリーに残るので、その意味では関係者全員の死をもって完全な無になるのかもしれないですね」と語ります。
さらに里江子は、「死」と「記憶」についての自分の考えを述べるのです。
「たとえば私が死んでも、本部長は生前の私のことを憶えてらっしゃるでしょう。もちろん記憶は薄れ、曖昧にはなっていくでしょうし、たとえば今夜のことなんて私と二人で会ったという事実さえ記憶には残らないでしょうけれど、でも、私という人間がいたことやそれに伴うある程度の私に関する情報は本部長ご自身が亡くなるまで本部長のメモリーに残ると思うんです。だとすれば、そうやって多かれ少なかれ私と関わった人が全員死んでしまわない限り、私という人間のデータは部分的にでも残存しますよね。ということは私が完全に死ぬためには私のことを知っている人間が死に絶える必要がある。つまり私は、私自身と私の関係者全員が亡くなった瞬間に完全に死んでしまうんだと思います。それが完全な無ということではないでしょうか」
里江子は、さらに「死」と「記憶」について語り続けます。
「だから誰もが亡くなった人のお墓を建てて先祖供養するんですよ。自分が死んで、自分という人間が存在したことを誰一人憶えていなくなったら、それこそ自分が生れてきたことが丸々無かったことになってしまいます。それがみんなすっごく怖くて仕方がないんです。私たちが写真や映像を撮ったり、日記や本を書いたり、大きな建物を建てたり、銅像を飾ってみたりするのも、そうやって自分が生きた証を残すことで何とかして完全な無に飲み込まれるのを避けたいからじゃないでしょうか」
里江子の話に感心していた城山ですが、「ということは、死んだら、その本人の記憶というか意識というか、そういうものはきれいさっぱり無くなってしまうんだろうか。あとに残るのは遺体と生き残った人間たちの思い出だけってことか」と問いかけてきます。
その問いに対して、里江子はこのように述べます。
「私はそうだと思います。よく霊を見たとか、誰かが夢枕に立ったとかいう話がありますが、そういうのは生前のその人の意識が、言ってみればこの世界全体の意識のデータベースのようなものにまだかろうじて残っていて、そのデータが何らかの偶然で私たちの意識回路に侵入することで起きてるんじゃないでしょうか。つまりそれはあくまでその人の過去の意識であって、死んだ人がいまも生きつづけて何かを伝えているわけじゃないんだと思います」
実際にこんな哲学的発言をスラスラと述べるOLがいたら、驚きですね。まるで故・池田晶子を彷彿とさせる「哲の女」ですが、里江子の「死」と「記憶」についての考え方はわたしとも非常に近いものでした。おそらくは、著者自身がそう考えているのだと思います。
その里江子を「ベストの相手」と見初めた岳志も、彼女に劣らず理屈っぽい男です。医師である岳志は、「患者の病気を治したくない」と語って、里江子をびっくりさせます。この非常識とも取れる発言について、岳志は次のように述べます。
「だって、みんな、自分の生命を粗末にしてるし、身体のことなんて何も考えちゃいない。患者と日々付き合ってみて僕は心底そう思うよ。正直な話、世界中の医者が話し合って、風邪だけでいいから、診療を一切拒否すればいい。数年それをやっただけで、この世界はいまよりずっと良くなると確信するね。誰もが健康のありがたさに目覚め、余裕を持って生きることの大切さを知り、風邪程度の病気で死んでいく世界中の子供たちに同情できるようになる。患者はわがままで自分勝手すぎる。自分では何の努力もせずに、僕たちのことを奴隷か何かのように思って『さあ、この病気を治せ』と要求ばかりだ。大した金も払ってないくせにすっかり旦那気取りだよ。そういう医者任せの医療が、人々から本当の健康を奪っている気がして仕方がない。そんなくだらない現実のお先棒を担がされているようでときどき自分がイヤになるんだ。一度、医者なんて職業がこの世界から完全になくなってしまえばいいんじゃないかな。そうすれば人間は否応なく病気や健康について本気で考えなくてはいけなくなるからね」
岳志はまた、本書のテーマである人間の「死に様」についても次のように語ります。
「人間はどんな人生を送ったとしても、最後にはちゃんと死ねるんだ。そしてそれだけで充分なんじゃないか。僕たち医師がやれることは患者さんがちゃんと死ぬお手伝いをすることだ。むろん、助かる生命は全力で助けなきゃいけない。でもそうやって生き長らえたとしてもいずれはまた僕たちのところへやって来て最期を迎える。僕たちはさいわい、そうやって死んでいく患者さんたちの姿を間近で見ることができる。いつも大切なことを学んでいる気がするよ。自分の番になったときに緊張したり怯えたりしないですむように、患者さん一人一人が死にざまというものを僕たちに教えてくれてるんだ。そういう意味では、医師は自分が死ぬとき、結構みんなちゃんと死ねるんじゃないかと思う」
「何が一番のおしえだと思いますか?」という里江子の問いに対して、しばらく考えてから岳志は「むずかしいけど、死は人間にとってやすらぎだってことだろうね」と答えます。そして、岳志は続けて次のように述べます。
「人が死ぬ姿をずっと見てきて、いつもそう思うんだ。初めて自分が担当した患者さんが亡くなったときからずっと変わらない。死ぬことで僕たちは何か重い荷物を下ろせるんだよ。自分を縛っている鎖から解き放たれるっていうのか。人の死に立ち会うたびにそういう実感がある」
この岳志の発言が、本書のテーマである「死に様」についての著者の見事な所信表明になっていると思いました。
さて、このように理論的な岳志なのですが、彼は里江子とどうしても一緒に生きたいと強く訴え、その理由について以下のように語ります。
「僕は家族なんてちっともほしくなかったんだよ。誰もいらない。親だって兄弟だって友だちだって恋人だって、誰一人いらないし、いらなかった。結局、僕はきみとしか一緒にいたくない。きみと共に生きて、きみと共に死ぬ。僕の人生にはそれしかないと思うんだ。そういう自分の人生が果たして特殊なのか、それとも誰もがそうであるべきなのか、僕にはよく分からない。でもね、ここまで端から見れば幸福な人生や家庭を営みながら、それでも自分がちっとも幸福にならないというのは、逆に言えば、それだけ僕ときみとの仲が運命的なんじゃないかと思う。誰ともうまくやれないからこそ、きもとだけはうまくゆくようになっている気がする。僕は思うんだ。運命の相手とは出会うだけじゃきっと駄目なんだよ。最も大事なことは、この人が運命の相手だと決断することだ。そう決める覚悟を持ったときに、初めてその相手は真実の運命の人になるんだと思う。たった一人、この人とだけ生涯仲むつまじく暮していくんだ、と決める。たった一人、この人とだけ真実の喜びを分かち合うんだ、と決める。そしてそれを万難を排してやり遂げようとする。お互いがそういう覚悟を持ちつづけている限り、人生というのは果てしなく豊かになっていくんだと僕は信じている」
この岳志のメッセージを里江子は受け取ることができませんでした。「私はそんなご大層な女じゃないわ」と彼の申し出をきっぱりと拒否するのです。ネタバレになるので詳しくは書けませんが、物語は悲劇的な結末を迎えます。里江子は「千億の翼となって岳志を助けるべきだった」と強く後悔します。彼を真に理解できるのは自分しかいないと悟った彼女は、最後にこう思うのです。
「彼は愛に生きようとしたのではなかった。彼は愛によって生きる以外に生きるすべがないと絶望したのだ。だからこそ、彼は言った。『最も大事なことは、この人が運命の相手だと決断すること』なのだと。その相手として彼は、十三年前の今日、この私を選んでくれた。その理由は他愛なかった。『きみと僕とだったら別れる別れないの喧嘩には絶対にならない。一目見た瞬間にそう感じた』からだと。しかし、実はそう言われたとき、私にはその一言の重みが充分に分かっていた。彼は言ってくれたのだ。『きみだけは何があっても僕は赦そう』と。彼は私と恋をしたかったわけでも、愛し合いたかったわけでもないのかもしれない。彼は、私と一生を共にしたかったのだ。それゆえに一度は『たとえ恋愛や結婚に結びつかなくても、きみがずっとそばにいてくれるのなら、それでもいいんじゃないか』と思い直した。彼はただ私と共に生き、私と共に死にたかっただけなのだ」
わたしは、本書を「愛」と「死」を正面から見つめた傑作だと思います。「死に様」はもちろん、本書には「生き様」も、「愛し様」や「信じ様」も描かれています。死ぬのが怖い人、そして愛されるのが怖い人は、ぜひ本書をお読み下さい。
