- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.1057 哲学・思想・科学 『唯脳論』 養老孟司著(ちくま学芸文庫)
2015.04.10
『唯脳論』養老孟司著(ちくま学芸文庫)を再読しました。いま執筆中の『唯葬論』の参考テキストとして復習したのです。
著者は1937年神奈川県鎌倉市生まれの解剖学者。62年、東京大学医学部卒業。卒業後解剖学教室に入り、その後東京大学医学部教授。95年、退官。現在は、東京大学名誉教授です。2003年に刊行された語り下しの著書『バカの壁』が空前の大ベストセラーになりました。
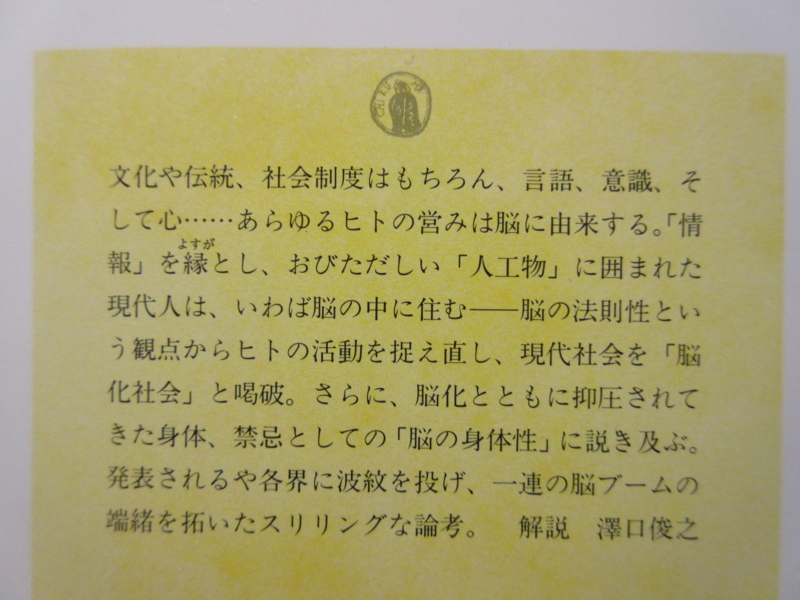 本書のカバー裏
本書のカバー裏
本書のカバー裏には、以下のような内容紹介があります。
「文化や伝統、社会制度はもちろん、言語、意識、そして心・・・・・・あらゆるヒトの営みは脳に由来する。『情報』を縁とし、おびただしい『人工物』に囲まれた現代人は、いわば脳の中に住む―脳の法則性という観点からヒトの活動を捉え直し、現代社会を『脳化社会』と喝破。さらに、脳化とともに抑圧されてきた身体、禁忌としての『脳の身体性』に説き及ぶ。発表されるや各界に波紋を投げ、一連の脳ブームの端緒を拓いたスリリングな論考」
本書の「目次」は、以下のようになっています。
「はじめに」
唯脳論とはなにか
心身論と唯脳論
「もの」としての脳
計算機という脳の進化
位置を知る
脳は脳のことしか知らない
デカルト・意識・睡眠
意識の役割
言語の発生
言語の周辺
時間
運動と目的論
脳と身体 エピローグ
「引用文献」
「おわりに」
「文庫版あとがき」
「解説」(澤口俊之)
「はじめに」の冒頭には、以下のように書かれています。
「現代とは、要するに脳の時代である。情報化社会とはすなわち、社会がほとんど脳そのものになったことを意味している。脳は、典型的な情報器官だからである。都会とは、要するに脳の産物である。あらゆる人工物は、脳機能の表出、つまり脳の産物に他ならない」
また続けて、著者は次のように書いています。
「伝統や文化、社会制度、言語もまた、脳の産物である。したがって、われわれはハード面でもソフト面でも、もはや脳の中にほとんど閉じ込められたと言っていい。ヒトの歴史は、『自然の世界』に対する、『脳の世界』の浸潤の歴史だった。それをわれわれは進歩と呼んだのである」
「唯脳論とはなにか」では、著者は以下のように述べます。
「ヒトが人である所以は、シンボル活動にある。言語、芸術、科学、宗教、等々。これらはすべて、脳の機能である。われわれはお金を使い、衣服や帽子、アクセサリーを身につけ、車にお守りを吊し、ゴルフ道具を担ぎ、碁やマージャンで暇を潰す。これらはすべて『具体化したシンボル』であるが、これもまた、すべて脳のシンボル機能に発する。
われわれの社会では言語が交換され、物財、つまり物やお金が交換される。それが可能であるのは脳の機能による」
そして著者は、次のように「唯脳論」という考え方を示します。
「ヒトの活動を、脳と呼ばれる器官の法則性という観点から、全般的に眺めようとする立場を、唯脳論と呼ぼう。ヒトが人である所以は、大脳皮質が発達するからである。後に述べるように、そこからヒトのシンボル機能が発生する。ヒトの脳と動物の脳が異なることは、誰でも知っている。ゴリラの脳とヒトの脳を机の上に複数個並べて見れば、素人でもただちに両者を識別するであろう。しかし、それはそれだけのことだとも言えるのである。つまり、ヒトの脳もゴリラの脳も、見ようによってはさして違わない。唯脳論は、ヒトとゴリラの類似と差異とを説明しようとする」
著者は、「ヒト」について以下のように述べます。
「ヒトはなぜ社会を作るか。レヴィ=ストロースは『交換』のためだと言う。そうかもしれない。では、なぜヒトは交換をするのか。その基盤を成すものは脳である。脳は信号を交換する器官である。それこそが、ヒトが交換を行なう理由である。ヒトが『無意識』に作り出すものは、ヒトの身体の投射となる。そうエルンスト・カップは言った。もっと正確に言おう。『ヒトの作り出すものは、ヒトの脳の投射である』と。社会もまた然りである」
「心身論と唯脳論」では「心は脳から生じるか」という問題が取り上げられ、著者は以下のように述べています。
「循環系の基本をなすのは、心臓である。心臓が動きを止めれば、循環は止まる。では訊くが、心臓血管系を分解していくとする。いったい、そのどこから、『循環』が出てくるというのか。心臓や血管の構成要素のどこにも、循環は入っていない。心臓は解剖できる。循環は解剖できない。循環の解剖とは、要するに比喩にしかならない。なぜなら、心臓は『物』だが、循環は『機能』だからである。
たとえばこの例が、心と脳の関係の、一見矛盾する状態を説明する。脳はたしかに『物質的存在』である。それは『物』として取りだすことができ、したがって、その重量を測ることができる。ところが、心はじつは脳の作用であり、つまり脳の機能を指している。したがって、心臓という『物』から、循環という『作用』ないし『機能』が出てこないように、脳という『物』から『機能』である心が出てくるはずがない。言い換えれば、心臓血管系と循環とは、同じ『なにか』を、違う見方で見たものであり、同様に、脳と心もまた、同じ『なにか』を、違う見方で見たものなのである。それだけのことである」
「脳と身体 エピローグ」では、著者は以下のように述べます。
「社会とは、すなわち脳の産物である。岸田秀氏は唯幻論を説く。ヒトは本能が壊れた動物である。それが生きていくためには、本能に代わるものとして幻想が必要である。幻想は各個人のうちにあり、社会はその共通部分を「共同幻想」として吸い上げることによって成立する。これはもちろん、唯脳論の一種と言ってもいい。本能は脳に記録されたものであり、幻想もまた脳の産物だからである」
ここで「共同幻想」とか「唯幻論」などの言葉が出てきました。そう、本書で展開されている「唯脳論」は明らかに吉本隆明の『共同幻想論』や岸田秀の『ものぐさ精神分析』に始まる一連の「唯幻論」についての著作から影響を受けていると言えるでしょう。
しかし、「幻想」を生み出す主体として「脳」を持ってきたところに著者の思想のオリジナリティがあります。著者は述べます。
「脳化=社会が身体を嫌うのは、当然である。脳はかならず自らの身体性によって裏切られるからである。脳はその発生母体である身体によって、最後にかならず滅ぼされる。それが死である。その意味では、『中枢は末梢の奴隷』である。その怨念は身体に向かう。善かれ悪しかれ、そこに解剖学が発生する循環がある。解剖学の背景は単純ではない。
抑圧されるべきものは、まだ存在する。ヒトの社会は、その成立の最初から脳化を目指していた。社会が支配と統御に尽きるのは、そのためである。それが言語であり、教育であり、文化であり、伝統であり、進歩である。そこでの問題は、自然対人間ではない。その段階はとうに過ぎてしまった。個人対個人でもない。そんな問題は、動物ですら解決している。さもなければ、動物も社会もここまで存続してきていない。資本家対労働者ではましてあり得ない。そうした思想は、すべてピント外れであることが証明されてしまった」
そして著者は、「われわれ自身の社会」として、以下のように述べます。
「かつてわれわれの祖先は、身体性のより強い社会すなわち戦乱の世の後に、同じく支配と統御を目指す、新社会を構築し直した。そこでは、死体は社会の『外部』に置かれたのである。むろんそこには、死体を扱う『身分』が公式に存在する。しかしそれは『正当なる支配と統御』すなわち『士農工商』の『外にある』という形で統御された。いまだにわれわれは、その伝統を背負っている。それはなにも社会問題としての差別だけを指しているのではない。われわれの祖先は、はなはだ極端なことに、脳から身体性を抜いてしまったらしい。おかげでわれわれの社会は、『本来の健康なる社会』すなわち『統御可能な脳の機能のみを集約するものとしての社会』となった。それは、社会から制度的にも死体を放逐することによって、ローマの平和よりも長い、世界でもっとも『平和な』時代を築いたのである」
「解説」で生物学者で脳科学評論家の澤口俊之氏は、本書について以下のように述べています。
「養老氏の主張の大きなポイントは『心』が脳の機能である、ということ、そして、人間の心=脳が作った『社会』や『文明』に脳の仕組み・構造が浸透している、ということだ。一方、脳と対置される『身体』は、脳の作った社会(脳化社会)から抑圧されており、そのため、身体は脳化社会に反逆する可能性を秘めているのである」
澤口氏は唯脳論を「数千年に一度の理論」と絶賛した上で、オリジナルな唯脳論は「世界は脳の産物である」などとは言っていないことを念押しします。しかし、唯脳論を現代脳科学の観点・成果から拡大解釈すれば「世界は脳、脳は世界」であるとして、以下のように述べています。
「心を含めた世界は脳の産物であり、脳が『外化』したものである。ドイツ観念論の系譜を引き、マルクスにも影響を及ぼしたフォイエルバッハは『世界とは精神が外化したもの』と述べた。その通りだ。そして、精神とは脳の活動である。だから、世界は脳が外化したものである。だとすれば、世界をみれば脳がわかることになる。つまり、世界は脳を理解することによって理解できるし、脳を探求することによって世界への理解は深まることになる。『拡張唯脳論』の要諦はここにある」
澤口氏は、さらに「拡張唯脳論」について述べます。
「こう捉え直した『拡張唯脳論』によって、人間に関わる諸学問は統合できると言っても過言ではない。哲学で問題になってきた『観念論』と『経験論』との対立などは雲散霧消してしまう。数千年に及ぶ『心身論』の論争もまたしかりである。哲学だけではない。心理学も社会学も倫理学も・・・・・・、かなりの学問が『拡張唯脳論』によって統合されるはずだ。人間に関わる諸学問のベース(原理・枠組み)は『拡張唯脳論』で必要かつ十分である!」
澤口俊之氏といえば、現在は「ホンマでっか!?TV」への出演で有名ですが、まさか『唯脳論』の解説を書いているとは知りませんでした。ビックリ!
さて、じつに25年ぶりに読み返してみて、本書は「脳がすべて」と誤読される可能性があると思いました。しかし、本書のテーマは「思考の中心に脳を置いた場合、何がわかるか」です。著者の養老氏自身が対談で「脳がすべてなんてバカな話はない」と語っています。わたし自身の考えを述べるなら、『ハートフル・ソサエティ』(三五館)の「脳から生まれる心」にも書いたように、脳から心が生まれ、心の源が脳であることは疑うべくもないとは思いますが、やはり脳だけではないとも思います。脳イコール心ではないということです。
かつてフランスの哲学者アンリ・ベルクソンは『物質と記憶』のなかで、脳をハンガーにたとえ、心をそこに掛ける上着にたとえました。つまり、脳機能が駄目になればハンガーが壊れて上着が掛けられなくなるように心にも異常をきたすけれども、心は脳に支えられてはいてもそのものではないというのです。一時期、脳と心はそれぞれハードウェアとソフトウェアにたとえられることが多かったです。脳がCDやDVDなどのハードディスクだとしたら、心とは音楽や映像といったソフトであるというのです。
アメリカのペンシルヴェニア大学において、医学部と宗教学部の双方で教鞭をとるアンドリュー・ニューバーグによれば、脳と心の関係は、海と波の関係に似ているといいます。波の実体をなす海水と、海水に形と動きを与えるエネルギーのどちらかが欠けても波が存在しえないのと同じ意味で、ニューロンの機能と実体のどちらが欠けても心は存在しえないというわけです。わたしには、このアナロジーが一番しっくりくるように思います。
いずれにせよ、本書『唯脳論』は物の見方を変えてくれるというか、知的刺激に富んだ非常に面白い本でした。