- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2015.08.27
『葬送の仕事師たち』井上理津子著(新潮社)を読みました。
著者は1955年生まれの奈良市出身のライターです。
人物ルポや旅、酒場をテーマに執筆してきたそうです。
主な著書に『遊郭の産院から』『名物「本屋さん」を行く』『旅情酒場をゆく』『はじまりは大阪にあり』『大阪下町酒場列伝』『さいごの色街 飛田』などがあります。ずいぶんコテコテのテーマの本ばかりですね。
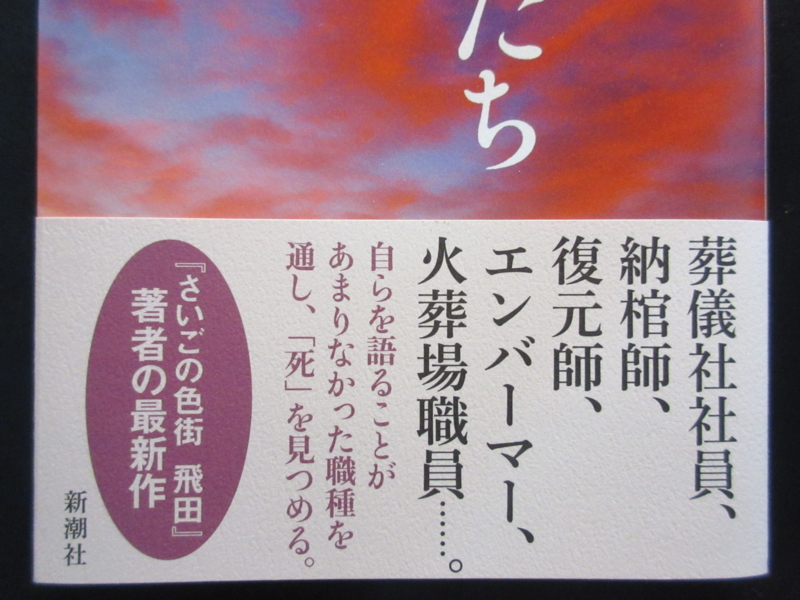 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「葬儀社社員、納棺師、エンバーマー、火葬場職員・・・・・・。」「自らを語ることがあまりなかった職種を通し、『死』を見つめる。」「『最後の色街 飛田』著者の最新作」と書かれています。
この「自らを語ることがあまりなかった職種」というフレーズに「覗き見趣味」的な匂いを感じ、ちょっと嫌な予感がします。
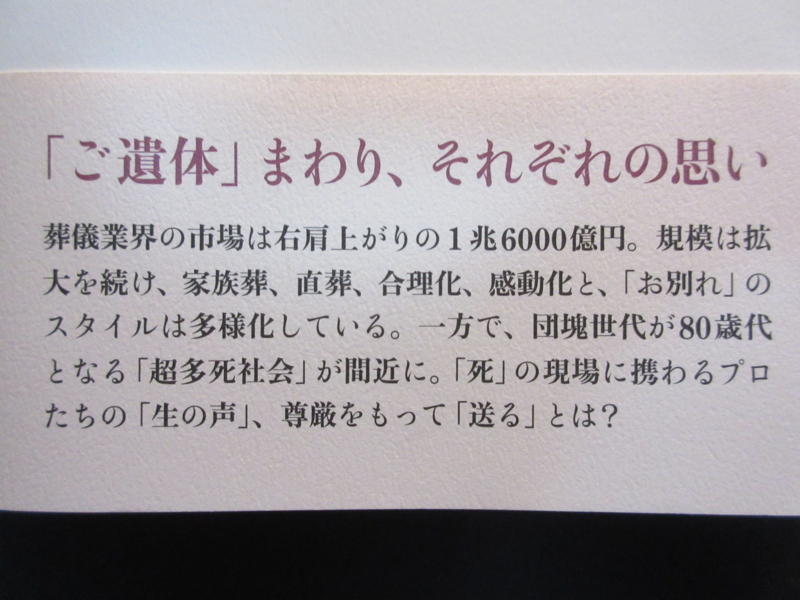
本書の帯の裏
本書のアマゾン内容紹介には、以下のように書かれています。
「葬儀業界の市場は右肩上がりの1兆6000億円。規模は拡大を続け、家族葬、直葬、合理化と、その形態は多様化している。
一方で、団塊世代が80歳代となる『超多死社会』が間近に。
死』の現場に携わるプロたちの『生の声』、尊厳をもって送るとは?
自らを語ることがあまりなかった職種を通し、葬送の実際をルポする」
本書の「目次」は、以下のような構成になっています。
第一章 「葬儀のプロ」を志す若者たち
第二章 それぞれの「葬儀屋稼業」
第三章 湯灌・納棺・復元の現場
第四章 エンバーマーたち
第五章 火葬場で働く人々
第六章 「超多死社会」に向けて
「あとがき」
「主要参考文献」
第一章「『葬儀のプロ』を志す若者たち」には、冠婚葬祭互助会のサン・ライフメンバーズさんが運営する神奈川県平塚市にある日本ヒューマンセレモニー専門学校が登場します。同校は、 葬儀のプロとしての「フューネラルディレクター」と遺体修復技術者である「エンバーマー」を育てる学校です。その授業内容や教師・生徒の人となりなどが紹介されています。ちなみに、わたしのブログ記事「サン・ライフに学ぶ」で紹介したように、わたしは2013年2月19日に日本ヒューマンセレモニー専門学校を訪問しています。サン・ライフメンバーズの竹内惠司会長、比企武社長とも親しくさせていただいています。

日本ヒューマンセレモニー専門学校での記念写真
その日本ヒューマンセレモニー専門学校に通う19歳の女性について、本書には次のように書かれています。
「祖父の晩年、父との関係があまりよくなかったようで、『おじいちゃん・おばあちゃんち』とは疎遠になっていたが、盆や正月に行き来した幼い頃に『優しいおじいちゃん』だった思い出を胸に、父母と遠路かけつけて葬儀に参列した。その葬儀の担当者が女性で、一人でいた自分に何かと優しい声をかけてくれた。その人の司会進行の中で、じつは父が祖父の連れ子だったこと、”祖母”と自分は血のつながりがなかったことを知る。
『他の方法で知っていたら、当時の私は動揺していたかもしれません。でも、葬儀社のその女性担当者は、楽しいことも悲しいこともあった祖父の人生を、感情を込めてナレーションしてくれて感動したんですよ。今思うに、おかげで、子どもながら祖父の人生に共感できたのだろうと思います。大人になったら私もあの人のような仕事をしたいと、12歳で決めていました』」
また、著者が「学校に来て一番良かったのは?」と問うた大卒の青年は、しばらく考え込んだ後、「原価2万円ほどの棺が、7万円とか8万円とかの値段で売れるのを知ったことです」と答えたそうです。周りの学生が「なんてことを言うの」という困惑の顔になりましたが、彼は「すみません、僕、喋るの下手で」と頭をかき、ぼそぼそと次のような言葉を補足しました。
「葬儀社は、目に見えない仕事をいっぱいするとわかったんです。亡くなった方に、お棺でどうやってお休みいただくか。着替えやご納棺などの実務もあるけど、それだけじゃなくて、大切な方を亡くして悲しんでいるご遺族を心で支える部分が、棺の原価と売り値の差額だと思います。ご遺族に何万円分もの満足をいただく、すごい仕事。だから本当に一所懸命にやらなきゃいけない。そんなふうにわかったのは、この学校に来たからだと思うんです」
第6章「『超多死社会』に向けて」の冒頭は、次のように書かれています。
「団塊の世代が80歳代になる2027年以降、『大量死』の時代がやって来る。2013年の死者数は約126万8千人だが、国立社会保障・人口問題研究所によると、2030年には27パーセント増の約161万人、2040年には32パーセント増の約167万人が亡くなり、大量死のピークとなると推測されている」
いま、家族葬、直葬が増え、葬儀にお金をかけない傾向というものが指摘されています。ここで「直葬」の名付け親である葬送ジャーナリストの碑文谷創氏(「SOGI」編集長)は「密葬を温かいイメージに置き換えたのが家族葬ですが、明確な定義はなく、現在、会葬者数2、3人から80人くらいまでに拡散しています」と言い、さらに次のように述べています。
「今後は、高齢単身者や、高齢期を共に過ごすのが肉親に限らないというケースの増加によって”家族”の概念が変わり、従来の家族中心から血縁を超えた近親者を中心とした葬儀へ移行するとも考えられます。葬儀の簡素化に興味を持つ世代のトップが60代、2位が70代、3位が50代。皆、『子どもに迷惑をかけたくない』と口を揃えますから、当然、小規模化が加速するでしょう」
経済産業省は、2012年の冬、「安心と信頼のある『ライフエンディング・ステージ』の創出に向けて」という調査を行いました。
それによれば、約7割の葬儀が葬儀専用の会館で行われ、葬儀費用(宗教者への費用を除く)は50万円以下が61.1パーセントでした。また、会葬者は50人以下が35パーセント、51~100人が32パーセントとなっており、67パーセントが100人未満でした。
このデータを受けて、著者は「業界の先細りが懸念される中、葬儀社やその周辺の業界に、どんな新しい動きが出てきているのか。キーワードは、『一日葬』『合理化』『感動化』のようだ」と述べています。
「あとがき」には、わたしの名前が登場します。著者は、「葬式無用論」と「葬式必要論」の論争について触れ、以下のように述べています。
「『葬式は、要らない』(島田裕巳著、幻冬舎)に端を発する、葬式費用が高いの、葬儀社が阿漕だのといった論調が目立つようになった。一方、葬儀関係者からは、『葬式は必要!』(一条真也著、双葉社)、『お父さん、「葬式はいらない」って言わないで』(橋爪謙一郎著、小学館)などの出版が相次ぐ。応酬だ。双方の主張とも、なるほどと思う面も、誇張しすぎではと思う面もある。議論は、しないより、したほうがいいに決まっている」
しかし、時代はすでに『0葬』(集英社)と『永遠葬』(現代書林)の「永遠の0」論争に移っていることは周知の事実です。本書の発売は今年の4月ですから、『永遠葬』はまだ刊行されていなかったとはいえ、『0葬』はすでに大きな話題になっていました。この「0葬」についてもまったく触れられていません。あまりにも情報が古い!
そもそも、この本、参考文献が古過ぎます。本書の「参考文献一覧」を見ると、わたしが四半世紀以上も前に『ロマンティック・デス~月と死のセレモニー』(国書刊行会)で使ったテキストがずらりと並んでいます。「日本の葬儀史」でも書こうというなら話は別ですが、「いまの葬儀業界」をレポートしようというにはお話になりません。とにかく著者の不勉強ぶりが随所に目につき、これでは本書にも登場する竹内惠司会長の講演を聴いたり、碑文谷創氏の著書を読んだほうがずっと有意義ではないかと思います。
それでは、なにゆえ、著者は「葬儀」という自身が事情に明るくない業界について書こうと思い至ったのか。想像するに、『さいごの色街 飛田』の続編となるテーマを探していたのではないでしょうか。著者のこれまでの執筆テーマを見ても、「異界探訪」とか「マイノリティの世界」みたいな感じのものが多く、その延長線として「葬儀」が選ばれたとしたのであれば、非常に不愉快です。本書の中にも業界で働く人々を強引に「差別」と結びつけたような箇所が散見できました。もちろん、そこに愛情があれば、そういった視点で本を書くのは自由ですが、本書の著者には「偏見」は感じられても「愛情」や「敬意」は感じられませんでした。
厳しいようですが、これが本書を読んだわたしの率直な感想です。
