- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.1162 哲学・思想・科学 | 心霊・スピリチュアル | 死生観 『シュタイナーの死者の書』 ルドルフ・シュタイナー著、高橋厳訳(ちくま学芸文庫)
2015.12.21
『シュタイナーの死者の書』ルドルフ・シュタイナー著、高橋厳訳(ちくま学芸文庫)を再読しました。『
『唯葬論』の参考文献として読みました。わたしのブログ記事「ルドルフ・シュタイナー展」にも書いたように、シュタイナーはわたしの最も敬愛する思想家の1人であり、最も影響を受けた思想家の1人でもあります。
 シュタイナーは最も影響を受けた思想家の1人です
シュタイナーは最も影響を受けた思想家の1人です
シュタイナーは、1861年オーストリア=ハンガリー帝国の辺境クラリエヴェク生まれの神秘哲学者です。自らの思想を人智学(アントロポゾフィー)として樹立し、1914年にバーゼルの近郊ドルナハにゲーテアヌムを建設しました。以降ここを科学、芸術、教育、医療、農業の分野にいたる人智学運動の拠点とし、精神世界の分野に世界的な影響を及ぼしました。その後、ナチスの迫害などに遭いながら1925年に没しています。
また本書の訳者である高橋巖氏は、1928年東京生まれ。慶応義塾大学大学院博士課程修了。1973年まで同大学文学部哲学科、美学・美術史教授を務めておられました。現在は日本人智学協会代表ですが、まさに日本におけるシュタイナー紹介の第一人者です。
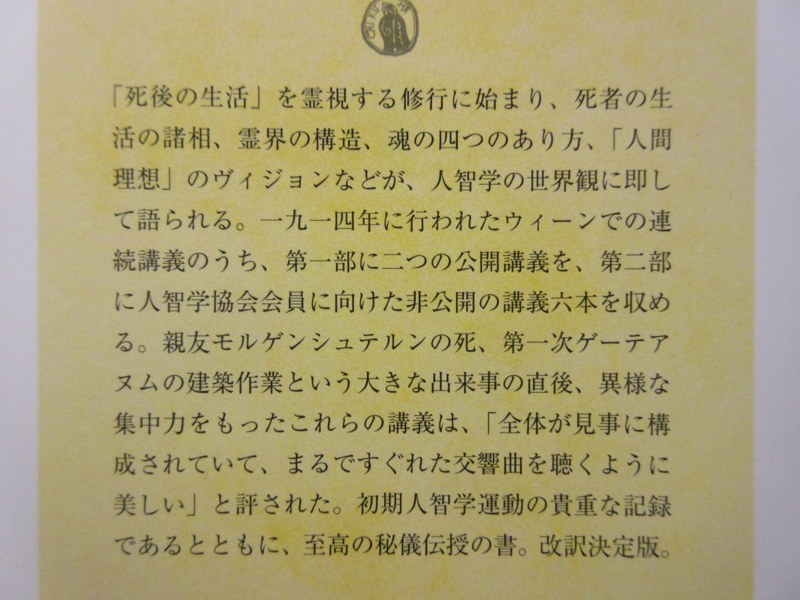 本書のカバー裏
本書のカバー裏
本書のカバー裏には、以下のような内容紹介があります。
「『死後の生活』を霊視する修行に始まり、死者の生活の諸相、霊界の構造、魂の四つのあり方、『人間理想』のヴィジョンなどが、人智学の世界観に即して語られる。一九一四年に行われたウィーンでの連続講義のうち、第一部に二つの公開講義を、第二部に人智学協会会員に向けた非公開の講義六本を収める。親友モルゲンシュテルンの死、第一次ゲーテアヌムの建築作業という大きな出来事の直後、異様な集中力をもったこれらの講義は、『全体が見事に構成されていて、まるですぐれた交響曲を聴くように美しい』と評された。初期人智学運動の貴重な記録であるとともに、至高の秘儀伝授の書。改訳決定版」
本書は二部構成で、第一部「霊学の課題と目標―現代人の霊的要求に応えて」「人間の生と死ならびに魂の不死について霊学は何を語るのか」、および第二部「人間の内的本性と死から新しい誕生までの生活」となっています。まず、ウィーンで開催された「霊学の課題と目標―現代人の霊的要求に応えて」と題する1914年4月6日の公開講義において、シュタイナーは以下のように述べています。
「霊学は近代自然科学の精神的作業を正しく受け継いでいこうとしているのですから、霊学を自然科学的思考の限りない成果と、広範囲な真理解明に敵対する思想だと思う人がいるとすれば、その考えは間違っています。その反対なのです。外的世界の認識のために自然科学が行ってきたことを、霊的世界の認識のために霊学は行おうとしているのです。ですから、世間の人はそう思っていないかもしれませんが、霊学は自然科学的思考方式の申し子なのです」
また、ウィーンで開催された「「人間の生と死ならびに魂の不死について霊学は何を語るのか」」と題する1914年4月6日の公開講義において、シュタイナーは「死」という霊的瞬間について以下のように述べています。
「死の門を通過する際に体験する、この死後最初の状態は、『記憶の向こう側へ行く』という言い方で表現できます。
私たちの記憶力が魂の中に生きる霊的なものの最初の現われであることは、今日の哲学者たちも理解しています。輝かしい成功をおさめたフランスの哲学者ベルクソンは、人間の記憶力の中に純粋に霊的なものを見ています。今日のほとんどすべての人の心を捉えている自然科学の偏見が過ぎ去ったならば、誰でもが記憶という魂の宝庫の中に、純粋に魂的・霊的なものへ到る通路の発端を見出すでしょう」
記憶の問題は非常に重要で、1914年4月9日から14日にかけてウィーンで開催された「人間の内的本性と死から新しい誕生までの生活」でも、シュタイナーは次のように語っています。
「実際に見霊意識の中で、霊視が始まり、霊的存在界の暗闇から最初の印象が浮かび上がってきますと、その印象は、性質といい、全体的な在り方といい、記憶内容と非常によく似ているのです。見霊意識による知覚が始まるとき、霊界からの啓示は、記憶像のように、しかし日常の記憶よりも無限に霊的なものとして、立ち現われてきます」
記憶とは何でしょうか。シュタイナーは言います。
「そもそも私たちの記憶像は、霊的体験の始まりです。それはすでに身体から離脱している最初のものなのです。とはいえ、記憶像に似た在り方をしてはいますが、霊的形姿の方がもちろんはるかに生きいきと霊界の深みから浮かび上がってきます。それは記憶内容とは異なり、私たちの体験内容の一部分なのではなく、未知なる内容を伴って、いわば記憶の背後から引き上げられてくるのです。物質界で体験したものが記憶像になるのですが、その一方で霊界からは未知なるものが引き上げられてくるのです」
シュタイナーは、その生涯において、一貫して「霊界」の真相を語りました。彼自身が霊的存在を見ることができた見霊能力者であり、霊界にも参入できたなどと言われていますが、次のように述べています。
「人類の歴史を遡れば遡るほど、人びとは今日のような精神能力を持たずに、一種の見霊能力を発揮して生きてきました。現代人の観察力は、当時の暗く夢のように体験された見霊能力から次第に発達してきたのです。今日でも、魂が根源的な原始段階にある人たちの思考と感情は、太古の根源的な見霊能力と結びついています。本当の見霊能力、つまり先祖返り的な原始の見霊能力は、今日ではますます稀少になっておりますが、文明から離れた田舎へ行きますと、かつての見霊能力を少しでも身につけている人びとに出会えます」
シュタイナーは「霊界」について学ぶことを訴え、次のように述べました。
「そもそも霊界について学ぶことは、神話、伝説、昔話などを正しく理解し、解決するための大切な導きの糸になってくれます。現代の精神文化は、霊学の一歩手前に立っていることを示しています。私の友人だった故ルートヴィヒ・ライストナーの著書『スフィンクスの謎』は多くの点で優れた問題意識をもって、『問いのモティーフ』を特に詳細に論じておりますが、著者は霊学的真実がこの問題に深く関わっていることを知っていたはずですのに、残念ながらそのような観点からは論じられていません」
特に、「執着の本質」についての以下のくだりには考えさせられました。
「私たちは毎夜、日常の生活から離れて、眠りにつきます。そしてふたたび目覚めるまでの時間を過ごします。その間、私たちは肉体から離れて、魂的・霊的なものの中にいます。私たちがそこからふたたび戻ってくるのは、この魂的・霊的なものの中で、私たちがふたたび戻ろうとする衝動をもって肉体を求めるからです。私たちは自分の肉体を渇望するのです。もしこの目覚めの過程が意識的に体験できたとすれば、私たちは目覚めようと欲している状態、目覚めようと欲しなければならない状態を理解するでしょう。つまり霊的・魂的なものの中に肉体への吸引力が働いているのですが、この力は死後においては、次第に力を失わなければなりません。そしてついにはまったく克服されなければなりません。しかしそのためには数十年を要するのです。その期間が前世との関係を克服するのに要する時間なのです。このように私たちは今述べた数十年間の死後の体験を、地上生活を再体験するという廻り道の上で、体験しなければならないのです」
「訳者あとがき」で、高橋厳氏は以下のように述べています。
「フランスの哲学者ベルクソンの記憶論を例にして、記憶が肉体に依存するものではなく、むしろエーテル体と結びついていることを論じ、死後に肉体から自由になった魂がまず自分を記憶内容として体験するということを、できるだけ知的にも納得できるものにしようと努力している。死者があの世で最初に体験することは生前の記憶内容全体の壮大なパノラマであって、それがこの世とはまったく異なる時間、空間の中で体験される。そしてそれと共に、死者の感情と意志もまったく変質して、それが新しい魂の環境とひとつになり、その中で魂は生前充たすことのできなかった思いを断ち切ることができずに、苦しみながら、何年もかけて次第に新しい魂に変化していく。そしていわゆる『宇宙の真夜中時』に到ると、そこからふたたび新しい誕生を迎えるのに必要な内的体験が始まる」
「訳者あとがき」の最後で、高橋氏はシュタイナーの思想に基づいて、死者への「供養」について以下のように述べています。
「死者となったその人に対しては、霊的に深い内容を持った書物、聖書やお経を読んであげること以上によい供養はないのです。生前の死者の姿を生きいきと心に思い浮かべながら、心の中で、または低い声で、死者たちに読んで聞かせるのです。そうすれば、それが死者に対してもっとも好ましい働きかけになります。そのような例を私たちは人智学運動の内部で数多く経験してきました。家族の誰かが世を去り、後に残された者がその死者に朗読して励ました例をです。そうすると死者たちは提供されたものを深い感謝と共に受け取ります。そしてすばらしい共同生活を生じさせることができるのです。まさにこのことにおいてこそ、霊学が実際生活の中でどんな意味を持ちうるのかがわかります。霊学は単なる理論なのではなく、人生に働きかけて、生者と死者の間の壁を取り除くのです。断絶に橋が架けられるのです。死者たちには読んで聞かせること以上によい助言はありません」
わたしは、これまで高橋氏が訳してきたシュタイナーの著作をほとんど読んできました。わたしのブログ記事「おみおくりの作法」にも書いたように、彼の人智学にはつねに「死者の存在」が前提としてあります。この映画の最大のテーマは「葬儀とはいったい誰のものなのか」という問いです。死者のためか、残された者のためか。ジョン・メイの上司は「死者の想いなどというものはないのだから、葬儀は残されたものが悲しみを癒すためのもの」と断言します。わたしは、多くの著書で述べてきたように、葬儀とは死者のためのものであり、同時に残された愛する人を亡くした人のためのものであると思います。
 わが書斎のシュタイナー・コーナー
わが書斎のシュタイナー・コーナー
シュタイナーは多くの著書や講演で、「あの世で死者は生きている」ことを繰り返し主張しました。今のわたしたちの人生の仲で、死者たちからの霊的な恩恵を受けないで生活している場合はむしろ少ないくらいです。ただそのことを、この世に生きている人間の多くは知りません。そして、自分だけの力でこの人生を送っているように思っています。シュタイナーによれば、わたしたちが死者からの霊的恩恵を受けて、あの世で生きている死者たちに自分の方から何ができるのかを考えることが、人生の大事な務めになるのです。葬儀を行う際には、このことを決して忘れてはなりません。
なお、本書は『唯葬論』でも紹介しています。