- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2016.02.21
『儀礼の象徴性』青木保著(岩波現代文庫)を再読しました。著者は日本を代表する文化人類学者であり、元文化庁長官でもあります。現在は大阪大学名誉教授、国立新美術館館長を務めています。1985年に本書『儀礼の象徴性』でサントリー学芸賞、90年に『「日本文化論」の変容』で吉野作造賞を受賞しています。
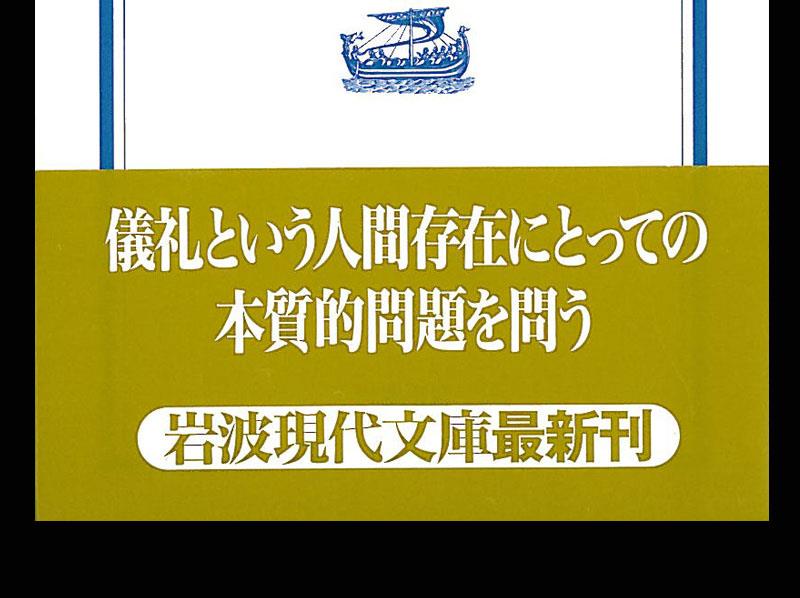 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「儀礼という人間存在にとっての本質的問題を問う」と書かれ、カバー前そでには以下のような内容紹介があります。
「タイの仏教儀礼や英女王の戴冠式などを例に、儀礼とコミュニケーション、儀礼のことば、儀礼と国家との関係を考察する。国家儀礼は国と社会の統合の中心を具体的に示す装置であることを明らかにし、境界状態、リミナリティ、コミュニタスといった概念によりながら、儀礼がいかに人間の存在にとって本質的な問題であるかを追究する」
本書の「目次」の内容は以下の通りです。
「プロローグ―儀式的動物」
1 儀礼とコミュニケーション
一.「あいさつ」と「拝礼」
二.儀礼と儀式
三.儀礼と遊び
四.象徴的コミュニケーションの2つの型
2 儀礼のことば
一.行為遂行的発言
二.「いうこと」は「なすこと」
三.「タンブンの儀礼」
四.パリッタの意味
五.ダーナと聖水
六.ことばと音と沈黙
七.儀礼の効果
3 儀礼と国家
一.タイ現王朝の二百年祭
二.戴冠式と社会学者
三.儀礼的起源
四.「劇場国家」
五.「社会主義国家」の儀礼
六.不可欠の装置
4 儀礼の解放・儀礼の拘束
一.タイ仏教の僧体験から
二.「境界状態」
三.「リミナリティ」の特性
四.コミュニタス
五.拘束
「エピローグ―儀礼の死と再生」
「岩波現代文庫版」あとがき
「プロローグ―儀式的動物」の冒頭には、「人間は儀式的動物である」というL・ウィトゲンシュタインの言葉が紹介されています。 今日の「文明」社会において、決して「呪術」は「合理化」されて消滅してはいないとして、著者は以下のように述べています。
「合理化は『呪術からの解放』を促すよりも、『呪術との併存』を促したのではないだろうか。そして、冒頭で触れた儀礼という問題がある。儀礼という現象も、当然『呪術からの解放』のための目録に入っていた。『儀礼は宗教と呪術とを結びつける』ということばがあるくらいだ。近代化―合理化の影響は、宗教自体の衰退をまねくことになった。しかし、儀礼は残った。既成宗教の衰退と新宗教の台頭とは、現代を彩る特徴の1つであるが、新宗教の特色は何といっても、その儀礼主義にある。その点では、儀礼優先は逆に現代人の信仰の特徴である。大教説や大思想の垂訓の時代は去った。いまや『いうこと』と『なすこと』を一体化した儀礼主義が覆っている」
また、儀礼について著者は以下のようにも述べています。
「それにしても、人は何故いつまでも儀礼に執着するのだろう。これに応えることは容易ではないにしても、儀礼という現象についてはそれを正面からとらえることがこれまでの社会と人間の科学においてはあまりに少なかったとはいえるであろう。それは社会の本質論からの逸脱と見なされる傾向があった。 しかるに、ウィトゲンシュタインは、フレイザーの呪術(儀礼)論を取り上げて、呪術を科学的に説明しようとするから錯誤が生ずるのだといって、その理解の仕方の根本的な誤りを指摘した。 『いかなる現象もそれ自体としてはとくに神秘的なものではなく、いかなる現象もわれわれにとって神秘的になり得るのであり、そして、ある現象が人間にとって深い意義をもつようになる、ということこそが、まさに人間の目覚めた精神の特質である』 ウィトゲンシュタインのこのことばには、彼が続けて『人間とは儀式的動物である』と仮りにいわなかったとしても、儀礼を理解するための十分な理論的前提があるといわなければならない。その限りにおいて確かに、『儀式的な行為の特質は、正しかろうがまちがっていようが、全然、意思、主張ではない』ということができる。ウェーバーもまたフレイザーのように『呪術』のもつ意味をとらえそこなったと見るべきだろうか。儀礼もまたそれを『科学的』に説明しようとしたときに、錯誤をもたらすものにちがいないのだ」
1「儀礼とコミュニケーション」の「二.『儀礼と儀式』」では、著者は儀礼について以下のように述べます。
「程度の差はあっても、まずいかなる社会であっても、明らかに『儀礼』は存在する。それが、『ハレ‐ケ』の対照のように、はっきりと日常の営みとちがった性質をもつことも事実である。ある社会現象が儀礼か儀礼ではないか、人びとは社会生活において、はっきりと区別している。タムバイアも、絶対的な基準はないが、相対的な対照区分ならできると主張している」
そして「儀礼」と「儀式」の違いという重要な問題について、著者は以下のように述べています。
「『儀礼』と『儀式』という、これまで社会人類学でさまざまに論じられてきた問題に対して、両者を分けて考える必要があるとすれば、一方の極に、超越的なまた象徴的な事象と大きくかかわる、旧来考えられてきた『儀礼ritual』をおき、他方の極に、『儀式』をおいて、パフォーマンスを含む日常的な出来事と重なるレベルを含むこととする。この全体を指して、儀礼ritualという用語をあてる。しかし、実際に用いるときには、時と状況に応じて、この2つのことばを、そこに示された形式と内容の性質によって使い分けてゆくということにしておく」
ところで、儀礼というものには現実的な効果があるのでしょうか。2「儀礼のことば」の「七.儀礼の効果」では、これまでの人類学における儀礼研究において、その効果に関して、2つの点が指摘されていると述べられています。その2つとは、1.儀礼を行なう者は、外的世界に効果が生ずることを意図している。2.儀礼は行為者が自らの経験に効果をおよぼすために行なうものである。そして、前者を、世界―外的効果、後者を個人(集団)―内的効果とすると、J・フレイザーが前者を、E・デュルケームが後者を代表していると著者は述べます。
また「儀礼のことば」は、きわめて「行為性」の強い性格を有するとして、著者は以下のように述べています。 「『儀礼のことば』の発するメッセージは、メタ・メッセージとして作用するが、それは『日常的現実』に対して『真実』というメッセージを運ぶ。この『真実』は儀礼という枠づけ内(フレーム)で発現するものであるが、それは『ことば』と『行為』を不可分のものとして、『いうこと』は『行なうこと』また『行なうこと』は『いうこと』という二重の定式を示すことで、『日常的現実』に対する『効果』となり、また『反省作用』となる。そして、『儀礼のことば』は言語の作用だけでなく、沈黙も含めた非言語の作用として、強いメッセージを発し、『見えるもの』の間だけでなく、『見えないもの』とのコミュニケーションを成立させようとするのである。
3「儀礼と国家」では、タイ現王朝の二百年祭のようすが報告されていますが、この読書館でも紹介した『人間』の著者であるドイツの哲学者エルンスト・カッシーラーの名前をあげられて、以下のように書かれています。
「エルンスト・カッシーラーは『現代の政治的神話の技術』を論じて、次のように述べる。
『すべての政治的行動は、その独特の儀式をもっている。しかも全体主義国家においては、政治的生活と無関係な私的領域はまったく存在しないので、人間生活の全面に、突如おびただしい新たな儀式が氾濫することになるのである。そうした儀式は、原始社会に見出されるのと同じ様に、規則的で、厳格な、仮借のないものである。あらゆる階級、性別、世代ごとに、それ自身の儀式をもたされる。いずれの人も政治的儀式を行ないながらでなければ、街路を歩くこともできないし、隣人や友人に挨拶することもできないであろう。そして原始社会におけるのと同じく、定められた儀式の1つでもおろそかにすることは、悲惨と死とを意味していた。幼い子供たちにおいてすら、これは単なる怠慢の罪であるとは見なされず、指導者および全体主義国家の尊厳にたいする犯罪となる』」
また、カッシーラーの発言について、著者は次のように述べています。
「カッシーラーが弾劾した『ナチス・ドイツ国家』は、現代史が経験した『文明国家』の中で、もっとも『祭儀的国家』としての性格を意識的に演出したものであった。ゲッベルスの天才と宣伝の技術は、何よりもナチス政権の劇的性格を際立たせ、統治のための『国家儀礼』を盛大に行なった。いまでは現代の広告技術の典範の1つともなっているこの方法は、『全体主義国家』と『独裁制』とが儀式的演出と組み合されたとき現代において果たす機能をあまねく示している。天才的な技術を用いて行なった場合、その効果の抜群な成功は疑いがない。『情報化』社会の管理技術に対する弱さは、すでに証明されている」
3「儀礼と国家」の「三.儀礼的起源」では、A・M・ホカートによる「国家の儀礼的起源」という考え方が紹介されます。社会が儀礼のための組織を作ることが、国家へと到る高度な政治組織の出発点であるという考え方です。著者は以下のように述べます。
「ホカートによると、儀礼の目的は宗教的畏敬を表現するものでも、恐ろしい魔力を追い払うためでもなく、生命―生活を安定させるための実用的な活動にある。高度な政治組織は何よりも多数の人間集団の生活を保証し安定させるためにあると、いうことができるであろう。ホカートの国家=儀礼組織節は、ニーダムが指摘するように、直接科学的に証明出来るという理論ではないにせよ、アリストテレスの『政治的動物』説やロックやルソーの『契約』説やヒュームの『争論』説と比べればはるかに蓋然性の高いものにつがいない」
また著者は、ホカートの「国家の儀礼的起源」説について、以下のようにも述べています。
「ホカートが『最初の王は死せる王であった』といっていることは大変示唆にとむ。死せる王を弔う葬儀がまさに国家儀礼として表現され、王権を定着させる。そこからまた『王は国家なり』という問題が出てくる。その王は儀礼を行なう者である。王と儀礼とは切り離せない。王と儀礼とが切り離されたとき、王は滅びる」 さらに、王と儀礼について、著者は次のように述べます。 「国王こそが儀礼を行なうものであり、王の儀礼は即ち国家的行事であり、国家とは究極のところその儀礼に集約されるという、そのもう1つの極端な場合を、ルイ14世治下のフランスの絶対王制国家に見ることが出来る。これは宮廷社会の洗練の極にあるそれ自体が完成された国の中の国であったが、国の中の国たるゆえんとはルイ14世が行ない臣下に命ずる『儀式』にあった」
4「儀礼の解放・儀礼の拘束」の「四.コミュニタス」では、この読書館でも紹介した『儀礼の過程』の著者であるヴィクター・ターナーが提唱した「コミュニタス」について、以下のようにB・マイヤーホフの説明を紹介しています。
「V・ターナーが使う”コミュニタス”という用語は、人間関係の相互性の1つのタイプを示すもので、それはほとんどどこにでも出現し、複合社会と単一社会、アーカイックとモダン、未計画と計画などの社会の差を問わず、ほとんどあらゆる種類の社会に見出される。こうしたコミュニタスという用語は、通常”コミュニティ”に付与される歴史的、時間的そして空間的な限定性はもたない。それに”コミュニタス”は”コミュニティ”に限定されず、他のいかなる社会関係のタイプよりも集中的だとか共同的だということもない」
つまり、コミュニタスは、”構造”との関係で理解されるわけです。
さらに著者は、コミュニタスについて以下のように説明しています。
「コミュニタス的特性を帯びる存在は、ターナーによると次のようなものである。それらは、儀礼の境界的段階にある修練者(通過する主体)、征服された土着の人びと、弱小民族、宮廷の道化師、聖なる乞食僧、よきサマリア人、千年王国運動、ダルマ(仏法追求)の放浪者たち、父系社会における傍系の母系、母系社会における傍系の父系、中世修道院の戒律、など種々雑多な現象となって発現する。そこに見られる共通の特徴は、『(1)社会構造の裂け目にある、(2)その周辺にある、(3)その底辺を占める』人間であり、集団であり、原理である、というのである」
そして著書は文化人類学者エドマンド・リーチの仕事を紹介しながら、以下のように述べています。
「リーチが明快に図式化した儀礼の2つの要素、厳粛と乱痴気、そして両者の変換は、人間と社会の存在論的なパラドックスを提示している。このパラドックスこそ、儀礼のあたえる『解放』と『拘束』に他ならず、両者ともにその絶対性において、『日常的現実』で受けとめられることのできない性質のものである。人間は、その絶対性に従うことは、一時的にはできても恒常的にはできない。だが、常に、『日常的現実』にあって、その絶対性をどこかで求めずにはいられない。儀礼は、その求める気持の”貯蔵庫”である。いつも使ってはならないが、必要なときに開けて使うのである」 儀式は、パフォーマンスや何らかのメッセージを発信するゆえ、国家の統合に不可欠なものであり、常に新たな創造や補強を繰り返していきます。しかし、儀式は拘束だけでなく、地位といった社会的束縛からの解放を与えるものでもあるのです。
本書で、著者は社会を「日常」と「非日常(儀礼)」の対立的存在として見ません。そうではなく、「儀式」と「遊び」の間に位置するものととらえています。そこで人間はどちらにも偏りすぎず、バランスをとりながら、社会秩序が保っているというのです。また儀式の強い拘束性ゆえ、それは国家の発生以前から存在し、そして、儀式を盛大に発展させていった政治組織が、国家の起源でもあると分析します。 本書を読むと、儀礼や儀式は「両義性」や「矛盾性」という言葉と切り離せないことが明になります。わたしは、本書と同じ岩波現代文庫化されている山口昌男先生の名著『文化と両義性』を再読したくなりました。
