- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2016.03.08
『世直しの思想』鎌田東二著(春秋社)を読みました。 これまで折口信夫の代表作である『古代研究』全4巻を紹介してきましたが、本書は「現代の折口信夫」とも呼ぶべき鎌田東二先生の最新作かつ集大成的作品です。わたしのブログ記事「鎌田教授退職記念講演会・シンポジウム」で紹介したように、「バク転神道ソングライター」こと宗教哲学者の著者が、教授を務める京都大学こころの未来研究センターを定年退職されました。それを記念して開かれた講演会およびシンポジウムに参加するために、わたしは京都に行きました。その懇親会のお土産が本書だったのです。
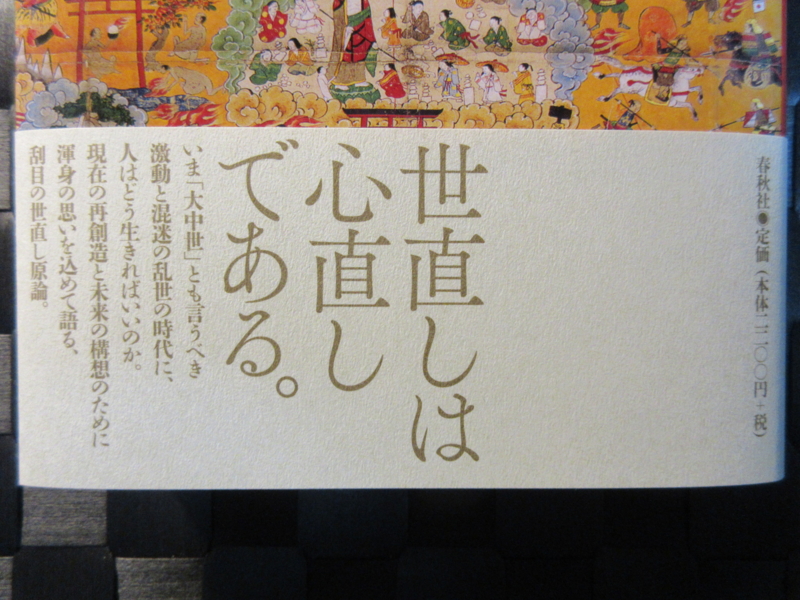 本書の帯
本書の帯
カバーには「熊野観心十界曼荼羅図」(三重県津市・大円寺蔵)の装画が使われ、帯には「世直しは心直しである。」と大書され、続いて「いま『大中世』とも言うべき激動と混迷の乱世の時代に、人はどう生きればいいのか。現在の再創造と未来の構想のために渾身の思いを込めて語る、刮目の世直し原論」と書かれています。
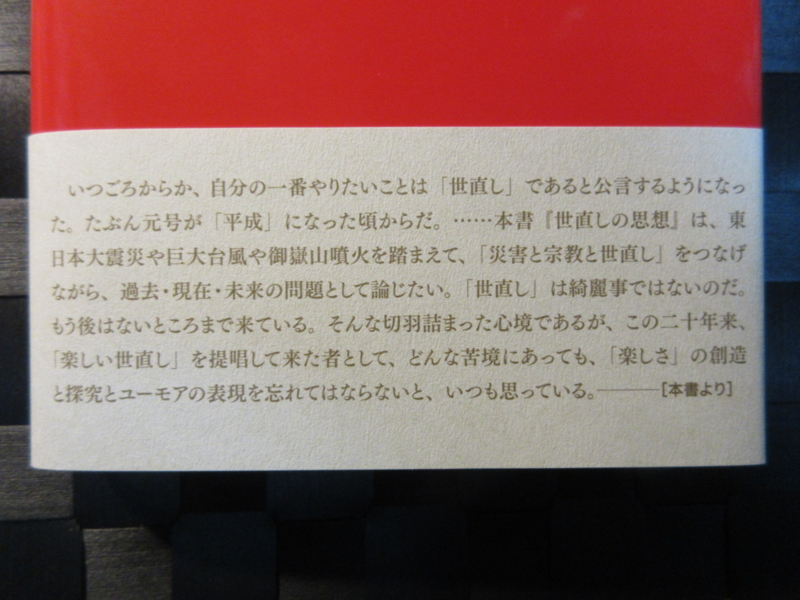 本書の帯の裏
本書の帯の裏
本書の「目次」は、以下のようになっています。
序章 「世直し」への希求と実践
第一章 世直しの思想
第一節 大本の「二度目の世の立て替え」
第二節 世直し思想の原点としての「岩戸開き」と「国譲り」
第三節 憲法十七条の世直し―「和」国の始まり
第四節 最澄と空海の仏教改革―「平安」の「心」の探求
第五節 「乱世」における「安心」を求めて ―鎌倉仏教と中世神道の「心」の探求
第六節 儒学革命の近世
第七節 現代世直し光―石牟礼道子『苦界浄土』
第二章 世直し芸術運動の冒険―柳宗悦と宮沢賢治と出口王仁三郎
第一節 芸術と宗教と世直し思想
第二節 ハレー彗星インパクト ―明治43年(1910)のスピリチュアルムーブメント
第三節 柳宗悦における宗教と芸術
第四節 宮沢賢治における宗教と芸術
第五節 出口王仁三郎における宗教と芸術
第三章 神道と世直し
第一節 「神道」とは何か
第二節 神道と仏教、あるいは神と仏の違い
第三節 「世直り」としての2つの清め―その1「禊・祓」
第四節 その2「歌による浄め」
第五節 言霊による浄め、音玉による浄め
第四章 震災と世直しと民俗芸能雄勝法印―東日本大震災後の雄勝法印神楽
第一節 震災復興と民俗芸能
第二節 東北被災地と民俗芸能 ―雄勝法印神楽と虎舞の復興過程
第三節 自然災害と祭りと浄め、
第四節 アート支援活動とこころの再生に向けて
第五章 世直しと教育と霊性的自覚
第一節 韓国儒学の学びから
第二節 『論語』と三種の学問
第三章 鳥山敏子の「臨床教育学」的実践と「霊性」的自覚
第四節 坂本清治の久高島留学センターの教育的実践と大重潤一郎の『久高オデッセイ』三部作
第五節 東京自由大学の教育実践
終章 スサノヲの到来
「あとがき」
「参考文献」
序章「『世直し』への希求と実践」の冒頭には、「いつごろからか、自分の一番やりたいことは『世直し』であると公言するようになった。たぶん元号が『平成』になった頃からだ」と書かれています。「平成」の典拠は『書経』の「地平天成」あるいは『史記』の「内平外成」などと言われています。しかし、著者によれば、「平成」という時代は、その典拠の趣意から大きく外れているといいます。「地平天成」「内平外成」どころか「地動天乱」「内動外乱」の大動乱の時代になったというのです。
著者は、現代の日本は「大中世」とも言うべき激動と混迷の乱世の時代であると訴えます。では、「大中世」とは何か。著者は以下のように述べます。
「わたしが主張する現代大中世論とは、一言で言えば、4つのチ縁の崩壊現象とそれを踏まえた再建への課題を指している。それはまず、地縁・血縁・知縁・霊縁という4つのチ縁の崩壊現象として現れてくる。限界集落を抱える地域共同体やコミュニティの崩壊。家族の絆の希薄化と崩壊。知識や情報の揺らぎと不確定さ。『葬式は要らない』とか『無縁社会』と呼ばれるような先祖祭祀や祖先崇拝などの観念や紐帯や儀礼が意味と力を持たなくなった状況。物質的基盤から霊的・スピリチュアルなつながりまで、すべてのレベルでチ縁が崩落し、新たな効果的な再建策やグランドデザインを生み出せないでいるのが今日の現状である」
この著者の発言には、わたしもまったく同感です。
わたしも、「葬式は、要らない」や「無縁社会」などは亡国のキーワードであると思っていました。そのようなところへ、2011年3月11日に東日本大震災が発生しました。「葬式は、要らない」「無縁社会」といった妄言は、M9の大地震が粉々に砕き、大津波が流し去ってしまった観がありました。遺体も見つからない状況下の被災地で、多くの方々は「普通に葬式をあげられることは、どんなに幸せなことか」と痛感したのです。やはり、葬式は人間の尊厳に関わる厳粛な儀式であり、遺族の心のバランスを保つために必要な文化装置であると確信します。このような問題について、わたしのブログ記事「無縁社会シンポジウム」で紹介した2012年1月18日に(一社)全日本冠婚葬祭互助協会(全互協)の主催で開催された「無縁社会を乗り越えて~人と人の”絆”を再構築するために」というシンポジウムで活発な議論が繰り広げられました。このシンポには著者もわたしも出演しましたが、わたしのブログ記事「無縁社会シンポジウム報道」のように、各種メディアでも報道されました。その内容は、『無縁社会から有縁社会へ』 (水曜社)として単行本にもなりました。
東日本大震災の発生は、著者の「世直し」への想いを強めたようです。 この「世直し」という言葉について、著者は以下のように述べています。
「日本の宗教史において、この『世直し』という言葉がリアリティを持っていたのは幕末維新期であった。その流れを受けた大本教(一般には「大本教」と呼ばれているが、正式教団名は「大本」)などの『民衆宗教』でも『世の立て替え立て直し』とか『世直し』の語が喧伝され、社会変革の運動となった」
さらに著者は、「世直し」という言葉について以下のように述べます。
「『世直し』という言葉はもともと『縁起直し』の意味で用いられ、江戸時代には『世直し大明神』も祀られたという。たとえば、『世直し大明神』とされたのは佐野善左衛門政言という旗本であった。天明4年(1784)、老中田沼意次の子、若年寄の田沼意知が江戸城中で佐野政言に斬りつけられ、数日後に死去するが、田沼意次の圧政に苦しんでいた江戸の庶民は、切腹を命じられた佐野政言を『世直し大明神』として祀った」
わたしも「世直し」には深い関心があります。わが世直しのキーワードは、「天下布礼」です。この語の「礼」には「人間尊重」という意味が込められています。しかし、つねづね「『人間尊重』は『人間偏重』に通じる危険がある」とわたしに対して訴え続ける著者は、以下のように述べています。
「現代世界において、人間だけに都合のよい『世直し』をするだけでは真の『世直し』とは言えまい。かつて『人類愛善会』を作った出口王仁三郎の『人類』とは、『人群万類』を意味したという。つまり、大本の説く『愛善世界』とは、『万教同根』思想に基づき、戦争のない世界のみならず、人種や宗教間の敵愾心を超えて和み合い、動物も植物も、草木花に至るまで万物がみな親和し合う『人類万類愛善』であった」
ここで著者が言うように「和み合い」「親和し合う」世界を創造することが「世直し」ならば、その目標とするコンセプトは「和」の一語に集約されます。 わたしは『和を求めて』(三五館)で「和」について書きました。 「和」は大和の「和」であり、平和の「和」です。 「和」といえば、「和をもって貴しとなす」という聖徳太子の言葉が思い浮かびます。内外の学問に通じていた太子は、仏教興隆に尽力し、多くの寺院を建立しました。平安時代以降は仏教保護者としての太子自身が信仰の対象となり、親鸞は「和国の教主」と呼んだことはよく知られます。 しかし、太子は単なる仏教保護者ではありませんでした。神道・仏教・儒教の三大宗教を平和的に編集し、「和」の国家構想を描いたのです。
著者も、聖徳太子の「和」の構想に注目します。 第一章「世直しの思想」の第三節「憲法十七条の世直し―『和』国の始まり」において、以下のように「和」の精神を説いた憲法十七条に言及します。
「1947年5月3日(憲法記念日)に施行された「平和憲法」と呼ばれる日本国憲法は、戦争の放棄と『恒久の平和』を謳い、主権在民や基本的人権、そして自由や平等を保障している。だがその『平和憲法』は『平和』の理念を語るだけで、どのような方法で『平和』を生み出すかについてその精神原理については触れることがない。が、『和』を生み出す『心』が示されなければ、人は何によってそれを実現することができるだろうか? 現今の日本国憲法は法と理念を説くのみで、それを支え維持する『心』についての洞察がない。しかし、『日本書紀』に記された『憲法十七条』は、『和』を生み出す精神原理が仏教や儒教の理論と具体的処方としてはっきりと示されている。それは極めて明確で、深い示唆と具体性に富む洞察に基づく精神原理と指針である」
かつて「憲法九条を世界遺産に!」という発言を行った学者とお笑い芸人がいましたが、わたしは賛同することはできませんでした。「日本国憲法」をよく読むと、日本語としておかしい個所をたくさん見つけることができます。日本の統治原理が謳われている憲法が、日本語としておかしいのは、それこそおかしいと思います。そして、そこには著者が言うように、「平和」の理念を語るだけで、どのような方法で「平和」を生み出すかについてその精神原理については一切触れられていません。「平和」を生み出す精神原理と具体的処方が明示された「憲法十七条」こそが世界遺産にふさわしいと思います。現在わたしは「朝日新聞」で「一条真也のこころの世界遺産」というコラムを連載していますが、いずれ「憲法十七条」を取り上げたいと思っています。「日本国憲法」をこよなく崇拝する朝日は嫌がるかもしれませんけど。(苦笑)
さて、「憲法十七条」には「平和」を生み出す具体的処方が示されています。 そこではまず仏教の存在が大きいのですが、著者は次のように述べます。
「『憲法十七条』に明確に示されているように、日本の精神史において、仏教の受容は『負の感情』の処理に大きな影響を与えた。その最初の明証が、憲法十七条における『和』と『嫉妬』の関係性であった。そこにおいて、『嫉妬』の処理と『和』の形成は、心と社会の安定ないし秩序形成の両極(軸)となっている。つまり、『心直し』が『世直し』と連動しているということを憲法十七条は明示している」
聖徳太子は、宗教における偉大な編集者でした。儒教によって社会制度の調停をはかり、仏教によって人心の内的平安を実現する。すなわち心の部分を仏教で、社会の部分を儒教で、そして自然と人間の循環調停を神道が担う・・・三つの宗教がそれぞれ平和分担するという「和」の宗教国家構想を説いたのです。この聖徳太子の宗教における編集作業は日本人の精神的伝統となり、鎌倉時代に起こった武士道、江戸時代の商人思想である石門心学、そして今日にいたるまで日本人の生活習慣に根づいている冠婚葬祭など、さまざまな形で開花していきました。
その石田梅岩についても、著者は第一章「世直しの思想」の第六節「儒学革命の近世」で触れています。梅岩の主著である『都鄙問答』の中の「性を知るは学問の綱領なり」「心を知る学問の初とす」「学問の至極というは心を尽くし性を知り、性を知らば天を知る」という言葉を紹介しています。さらに著者は、「神儒仏ともに悟る心は一つなり。何れの法にて得るとも、皆我が心を知る」「実の商人は先も立ち、我も立つ事を思うなり」という梅岩の言葉を紹介しています。その立場は、より包含的な神道も仏教も儒教もみな取り込んで、要は「我が心を知る」ことなのです。
石田梅岩の心学における精神的伝統は、二宮尊徳に受け継がれました。 二宮尊徳が力説したのは、人間社会に必要な「人道」のあり方です。 著者は、尊徳の説く「人道」について以下のように述べます。
「『天理・天道』のままに放置しておくとどうなるか。『荒地』になる。そこで放置をせずに、『政を立、教を立、刑法を定め、礼法を制し、やかましくうるさく、世話をや』く。それによってようやく『人道』が立ちゆく。『やかましくうるさく、世話をや』かないとだめだ。それが人の道というものである」
聖徳太子や石田梅岩は神道・仏教、儒教の共生を目指しましたが、二宮尊徳の場合もそれは同じでした。著者は述べます。
「二宮尊徳の宗教観は神儒仏習合思想で、究極的には三教(正確には二教一道)は『誠の大道』1つに尽きている。だから、神道というのも、儒教というのも、仏教というのも、畢竟、1つで、入口の相違にすぎない。上に登れば1つになる、といつも見上げていた富士山を例に挙げて説明する」
しかし、この神儒仏三教の匙加減となると、神道が半分で、儒教と仏教は各4分の1だといいます。これは、わたしも初めて知りました。 まことに面白いですが、やはり日本人の「こころ」の主柱は神道なのでしょう。神道が他の宗教を排斥しない平和宗教であったからこそ、仏教も儒教も日本に根付いたのだと思います。
さらに、「世直し」の思想家にして実践家であった尊徳を高く評価する著者は、以下のように述べています。
「二宮尊徳はキャッチフレーズの名人であるが、ここでも神儒仏三教の立場と意味と特色を一言で言い切り、比較している。神道は『開国の道』、儒教は『治国の道』、仏教は『治心の道』という言い方で。この言い方は直截かつ言い得て妙で見事である。 しかもその神儒仏総合論を誰にもわかるように、『神儒仏正味一粒丸』とか『三味一粒丸』とかと名付けて、それを服用したらどれほどの難病でもよくなるとか、噛んで含めるようにわかりやすく説明し、効用を説いた」
この「キャッチフレーズの名人」という言葉を、わたしは著者にこそ贈りたいと思います。著者は本書の第三章「神道と世直し」の第二節「神道と仏教、あるいは、神と仏の違い」にも紹介されていますが、「神は在るモノ/仏は成る者」「神は来るモノ/仏は往く者」「神は立つモノ/仏は座る者」など、秀逸なコピーセンスの持ち主で、いつも感服しています。
第一章「世直しの思想」の第七節「現代世直し光―石牟礼道子『苦界浄土』」で、著者は次のように述べています。
「大本は『世直し』宗教であった。その大本の出口王仁三郎の『霊学』の思想的源泉が平田篤胤の国学であったとすれば、『日本人の幸福の探求と実現』を目指した柳田國男の『民俗学』も同根であったと言える。そうした『霊学』と『民俗学』が交差し、『原始』の息吹きの中できわめて幸福かつ悲劇的に溶け合っているかに見えるのが石牟礼道子である」
ここで石牟礼道子の名が登場したのは少々意外でしたが、著者は「石牟礼道子は、顕幽の両界を覗き見、往き来しながら、凸と凹との反転と逆理を見つめ続ける。光と闇、仏と魔、病気と健康。煩悩と悟り。そのような現象的な二元対立を柔らかくねじり繋ぐまなざしをもって」と書いています。 これを読んで、わたしは先の教授退職記念講演会の最後でも石牟礼道子の歌が紹介されたことを思い出しました。
ここで「『霊学』と『民俗学』が交差」という言葉を目にしたわたしは著者の出世作である『神界のフィールドワーク』(創林社)を連想しました。もう数え切れないほど読み返したわが青春の愛読書ですが、サブタイトルが「霊学と民俗学の生成」でした。同書には賢治や王仁三郎が大きく取り上げられていますが、それは本書『世直しの思想』の第二章「世直し芸術運動の冒険―柳宗悦と宮沢賢治と出口王仁三郎」で再現されています。もっとも今回は柳宗悦というニュ―フェイスが新たに加わっていますが・・・・・・。
第一節「芸術と宗教と世直し思想」の冒頭で、著者は次のように述べます。
「柳宗悦(1889―1961)と宮沢賢治(1896―1933)と出口王仁三郎(1871―1948)は、それぞれ独自の「世直し」的芸術運動を展開した。柳は民藝運動、賢治は農民芸術運動、王仁三郎は民衆宗教芸術運動を。そしてそれぞれ日本民藝協会・日本民藝館、羅須地人協会、明光社という芸術運動集団を組織し、独自の芸術理念を掲げて芸術社会運動を展開した」
第二節「ハレー彗星インパクト―明治43年(1910)のスピリチュアルムーブメント」では、ハレー彗星の到来によって、世界中に騒動が巻き起こり、日本人も大いに影響を受けたことが興味深く紹介されています。 著者は「注意したいのは、ハレー彗星の影響によって地球規模の気象変化がどのように起こるのかまったく予測がつかなかったこともあり、この時、地球と生命の危機が強く意識せられ、世界同時性=地球的同時性が認識され始めたことである。19世紀以来の西欧諸国による植民地支配、通信・交通網の整備、新聞雑誌等の大衆メディアの隆盛によって、ハレー彗星到来は全地球的な問題となった。この時、地球という惑星の中で『世界は1つ』あるいは『惑星的運命共同体』という認識がリアリティを持ち始めたといえる。この年の大変化を、『ハレー彗星インパクト』あるいは『1910年問題』と呼びたい」と述べています。
第三章「神道と世直し」の第一節「『神道』とは何か?」では、日本を代表する神道研究者としての著者の本領が存分に発揮されています。著者は最初の神道と仏教の差異について、以下のように述べます。
「『仏法』とは『法』という教えの体系であるから、それを信じるか信じないか、信不信をはっきりと表わすことができる。しかし、『神道』はそのような『法』を持たず、教えの体系ではないから、信不信ではなく、『尊』か『軽(不敬)』の対象でしかない。つまりそれは、古来維持されてきた先祖伝来の伝承の集積だから、それを大事にするか大事にしないか、敬うか敬わないかという2つの態度しかない。信じるとか信じないとかというように、はっきりとその対象の真偽性を事分けることはできないという構えである。ここで、『教えの体系としての仏法(仏教)』と、『伝承の集積としての神道』との違いがはっきりと出ている」
そして、著者は恩師である小野祖教にならって、「表現(あらわれ)としての神道」を「神道の潜在供犠」として、次の7つの特性から位置づけます。
(1)「場」の宗教としての神道
(2)「道」の宗教としての神道
(3)「美」の宗教としての神道
(4)「祭」の宗教としての神道
(5)「技」の宗教としての神道
(6)「詩」の宗教としての神道
(7)「生態智」としての神道
さらに国学者の本居宣長の歌である「敷島の 大和心を 人問はば 朝日に匂ふ 山桜花」を紹介した後で、著者は日本の「こころ」について以下のように述べます。
「日本の『こころ』というものは、端的に言って、朝日の当たる里山で山桜の花がほのかにつつましくもきよらかに香っている、そのような『心』こそが『大和心』といえるような日本人の心なのである。これが、神道における最重要儀礼のひとつの『禊・祓』に様式化されていく感覚基盤である。清めの観念と儀礼は、このような『朝日に匂ふ山桜花』に象徴されるような純粋始源を本位とする『潜在教義』に裏打ちされている」
続いて、神道について、著者は以下のように述べています。
「神道とは、このような『潜在教義』性を持った『感覚宗教』であり、『芸術・芸能宗教』である。その感覚性や芸術・芸能性が、『祭り』という身心変容儀礼のワザとなっていく。『祭り』の主旨は、祭祀という『ワザヲギ』による生命力の更新・復活にある。その神話的起源が、天の岩戸の前で行われた神々による神事として、『古事記』や『日本書紀』や『古語拾遺』の中に語られている。その神事は、天の岩戸に隠れた(象徴的な死を意味する)天照大御神を甦らせ、再顕現させるために行なわれた。つまるところ、『死と再生(復活)』がメッセージとして表現されている」
それでは、宗教哲学者としての著者は、「宗教」の本質をどのように捉えているのでしょうか。それについては、以下のように述べています。
「わたしは、宗教をひとまず、『聖なるものとの関係に基づくトランス(超越)技術の知恵と体系』と定義している。宗教は『トランス(超越)』のはたらきを通して『こころ』や『たましい』の『深み』に降り立ち、その『底力』を引き出す『身心変容』のワザを持っている。そのワザには、物語(ナラティブ・神話伝承)、ないし儀礼と内観(自己を見つめる、インサイト、瞑想)、すなわち伝承を通して歴史的一回性を超えた神話的時間の中に参入するワザと、今ここの現実を精密にスキャニングしたりイメージ操作したりすることにより自己と世界の解像度をシフトするワザの2種があるが、日本においては前者を主に神道が、後者を仏教が担ってきた。そして、前者がシャーマニズムのトランス的な身心変容技法である神懸りを、後者が瞑想的な自己放下的な身心変容技法である止観や禅を開発した」
著者とわたしは「ムーンサルトレター」という満月の夜のWEB上の文通をもう10年以上ものあいだ続けていますが、2人の合言葉は「人類は神話と儀礼を必要とする」です。まさに神話も儀礼も「身心変容のワザ」であると言えるでしょう。他にも神道には禊・祭りといったワザがありますが、著者は「歌(詩)」というワザの存在を強調し、以下のように述べています。
「1300年という歴史を持つとされる最古のテキスト『古事記』は『歌物語』(折口信夫・武田祐吉)であり、歌謡劇であるが、拙著『古事記ワンダーランド』(角川選書、角川学芸出版、2012年)では、『古事記』をイザナギノミコトの『負の感情』の鎮めと浄めに発するグリーフ・ケアとスピリチュアル・ケアの歌謡劇ととらえた。そして、そのキー・キャラクターとなるスサノヲノミコトに始まる出雲神話を『怪物退治と歌の発生』という観点から解読した」
さらに宗教においては「場」の問題、すなわち「聖地」が重要です。 著者は、「聖地」についても以下のように述べています。
「聖地とは、『聖なるモノの示現するヌミノーゼ的な体験が引き起こされる場所』であり、そこには『生態智』と呼ぶことのできる知恵と力が宿っているがゆえに長らく祈りや祭りや籠りや参拝や神事やイニシエーションなどの儀礼や修行(瞑想・滝行・山岳跋渉等)が行われてきた。そのような場所は、太古の記憶を場所の記憶として蔵した聖なるものの出現地にして、魂を異界へと飛ばし、つなぎ、浄化し、活性化するタマフリ・タマシヅメの力を持つ。人間にとって根源的ないのちと美と聖性に関わる宇宙的調和と神話的時間を感じとる場所である」
本書の中でわたしが最も興味深く読んだのは、第五章「世直しと教育と霊性的自覚」でした。第一節「韓国儒学の学びから」の冒頭を、著者は以下のように書き出しています。
「ほとんどの人が儒教を倫理道徳だと理解している。ご多分にもれず、わたしもそのような1人であった。だが、最近、『儒学は道徳の学ではなく、美学である』という認識と意見を韓国で聞いて目を見開かされた。わたしは儒教についてずいぶん表面的で一般的な理解しかしていないのではないかとも反省させられた」
この著者の言葉は、人類史上で孔子を最も尊敬し、「礼」を求めて生きているわたしにとってこの上なく嬉しい言葉でした。「おおっ、鎌田先生、やっとわかってくれましたか!」と叫びたい気分でした。
著者が儒教に対する見方を改めたきっかけは、韓亨祚韓国学中央研究院教授の「儒学は道徳の学ではなく、美学である」という観点と主張でした。著者は以下のように述べています。
「わたしは毎朝、石笛や横笛や法螺貝や雅楽の龍笛を奉奏するので、儒学が人倫修養の根幹に『礼楽之道』を置いていることに関心を持っていた。『礼記』『大学』には『修身斉家治国平天下』(自分の行いを正し、家庭を整え、国を治めれば、天下を泰平に導き統治することができるようになる、という儒教の根本思想)と書かれているが、ではその『修身』とはどのようにして可能かと言えば、同じ『礼記』の『楽記篇』にあるように、『楽は天地の和、礼は天地の序』であるから、天地万物の世界秩序を確かなものとするためには『楽』を奏して『天地の和』を実現しなければならない。この『楽』すなわち音楽の演奏が単なる楽器演奏に留まらない人間形成、人格修養の道であることを儒学・儒教は一貫して主張し実践し続けてきたのである。 天地人の調和を調律する『礼楽』としての儒学の本質。そして韓国儒学の『養生法』。この道徳的修道と美的・芸術的修練との連携・連動に基づく『儒学は美学である』という主張こそ、未来倫理となり得る思想だと思ったのである」
この「儒学は美学である」という思想は、わが父である佐久間進の生き方に強く感じます。父には『人間尊重の「かたち」』(PHP研究所)という著書がありますが、もともと「人間尊重」としての「礼」を追求して冠婚葬祭互助会であるサンレーを50年前に創業しました。その父は、著書『わが人生の「八美道」』(現代書林)の「まえがき」に以下のように書いています。
「八正道とは、みなさまもよくご存知のように、お釈迦様の言葉です。 お釈迦様が、人間の生き方として『八』の正しい道を示されました。 私は、自らの人生を振り返り、自分の人生をどう表現したらいいだろうか、と考えることがあります。果たしてお釈迦様が示された『八つの正しい道』を歩めただろうか? 精進努力を惜しんだつもりはありませんが、『八正道にはほど遠いなあ』と反省するばかりです。 では、自分の人生で何を目指してきたのか。人として、男として、夫として、父として、経営者として、業界のリーダーとして、自分は何を追い求めてきたのか。美―『美しさだったかな』という思いに至りました」
父は冠婚葬祭業の傍ら、小笠原流礼法を学び、さらに今年からは利休以前の茶道として知られる小笠原家茶道古流の会長に就任しました。
『わが人生の「八美道」』(現代書林)の「まえがき」で「礼法を学び、おじぎを極め、会社を興し、すべてが『美』を追い求めてきた気がします」という一文に続いて、父は以下のように述べています。
「『正しいか、正しくないか』―私にはわかりません。 『美しいか、美しくないか』―これはわかりません。 『美』を唯一無二の基準にして、生きてきたような気が致します。 自然の美しさに学び、心の美しさに涙し、無理のない美しい流れを大切にしながら生きてきました。ささやかではありますが、その行いのすべてが、今日ある私の姿です。良し悪しは他人様に評価して頂きたいと存じます。 私は自分の生き方を『八美道』と名づけてみました。まだ発展途上の私です。自らの道、『八美道』を今しばらく追い求めていくつもりです」
鎌田先生は本書『世直しの思想』をサイン入りで父に送って下さいました。 父は、本書を興味深く読み、「わが意を得たり」と思ったことでしょう。
第二説「『論語』と三種の学問」では、著者は常々、学問的探究に次の三種があると考えてきたと述べますその三種とは以下の通りです。
(1)道としての学問―人格形成・人間性涵養を目指す。
(2)方法としての学問―知性練磨・認識機能亢進・新知見獲得を目指す。
(3)表現としての学問―学問的問いを誌や物語や演劇で表現するワザを研く。
この「三種の学問」については、先の教授退職記念講演でも語られました。 さらに、講演では学問についての示唆に富んだ話を伺うことができました。
著者の肩書は「宗教哲学者・民俗学者」となっています。
なぜ、宗教哲学と民俗学を並べているのか?
まずは宗教哲学のほうから説明すると、宗教学とは個別の宗教現象などを研究する経験主義の科学という性格を持っています。しかし、宗教哲学は対象そのものを捉えて、その本質を探り、抽象的な思考をするものです。「宇宙とは何か」「心とは何か」「鬼とは何か」といったテーマにも取り組みます。それは、数学と天文学をミックスしたような抽象的な学問なのです。 一方の民俗学ですが、特定の地域の祭であるとか習俗であるとか、徹底してローカルなテーマを扱います。この「蟻の目」ともいうべき緻密な現場主義が民俗学にはあるのです。
著者は、「宗教哲学はマックスであり、民俗学はミニマムであり、わたしは両方を求めたい」と述べました。わたしは、これはまったく経営にも通じる考えだと思いました。経営には「理念」と「現場」の両方が必要だからです。「理念」だけでは地に足がつかないし、「現場」だけでは前に進めません。マックスとミニマム、鳥の目と虫の目、理想と現実・・・・・・著者が学問で追及していることは、すべて経営者としてのわたしの課題でもあったのです!
その意味で、わたしは「経営も学問である!」と悟りました。けっして経営学のことではありません。経営という行為そのものが学問なのです。
それから本書には「臨」という語についての興味深い記述がありました。 もともとは「臨床教育学」の視点から「臨」について考えたという著者は、以下のように述べています。
「『臨』の付く熟語には、『臨海、臨死、臨戦、臨発、臨終、臨別、光臨、降臨、駕臨、哀臨、臨機応変』などがあっても、いずれものっぴきならない、逃れることのできない当事者性や代替できない『此れ性』を表わしている。『臨』という字の偏の『臣』は会意文字で、下に伏せてうつむいた目を描いた象形文字であるという。そこで、『臨』という字は『臣(伏せ目)+人+いろいろな品』という組み合わせになり、人が高いところから下方の物を見下ろすことを示すこととなって、『高いところから下を見る』とか、『面と向かう』とか、『物事や時期に当面する』とか、『他人の来ることを表す敬語』とか『死者のところに集まって泣く、その儀式』とかの意味に用いられるようになる」
この最後に出てくる「死者のところに集まって泣く、その儀式」という意味こそは、『唯葬論』(三五館)という本を書いた唯葬論者であるわたしにとっては非常に重要なのですが、著者は続けて次のように述べます。
「このような『臨』という意味性を持つ『臨床の知』とは、ある事態や状況に『孔を開ける知』であり、『孔の開く時(機)』である。その『場』において、その『場』の関係性の中に、風孔を開け、チャンネル(回路・水路・通路)を開き、身体を媒介として通じ合い、多次元的に対話する、開かれた身体知のいとなみ、それが『臨床の知』であり『臨地の知』である」
さらに著者は、「『臨床』や『臨地』の『知』に欠かせない『臨機応変力』とは、『遊行性』と『即(速)性』となる。その時その場で組み立て、編集し、即座に、即応・対応する。『即身・速身、即心、即席、即位、即物、即答、即応、即決、即座、即戦、即時、三諦即一(「空・仮・中の三諦は本来ひとつである」とする天海が開いた天台教学である山王一実神道の教義)、即非、色即是空・空即是色』などなど、『即』のロゴスとパトスの『即身=即心』の流れに身を任せて生き切ること。それが『臨機応変』を生み出す『臨床教育学』の場の知である」と述べています。 この大いなる「臨」の思想の展開には圧倒されました。ぜひ「佐久間庸和の天下布礼日記」の「こころの一字」で「臨」を取り上げたいです。
臨床教育学の実践者として、著者は2013年に亡くなった鳥山敏子を取り上げます。彼女は宮沢賢治とルドルフ・シュタイナーの教育実践を目指し、前人未到の「東京賢治シュタイナー学校」を設立しました。その賢治とシュタイナーの思想的共通性が本書には書かれているのですが、さらに驚いたことに孔子とシュターナーの共通性まで言及されているのです。 かつて、わたしは『孔子とドラッカー』(三五館)というハートフル・マネジメント論を書きましたが、まさか「孔子とシュタイナー」とは!
第三節「鳥山敏子の『臨床教育学』的実践と『霊性』的自覚」において、著者は次のように述べています。
「孔子は『十有五にして学に志す』と言ったが、この15歳という境界年齢は、シュタイナーの発達課題理論にしたがえば『感情』から『思考』の育成に転換していく時期に当たる。その時期に思考力を育成する『学に志す』ことは、孔子の観点とも一致する。シュタイナーは言う。『子どもの魂の中にあれこれいろいろなものを注ぎ込んではなりません。そうではなくて、子どもの精神の前に畏敬の念を持つのです。この精神は自分自身で成長していきます。私たちの責任は、子供たちの成長を妨げる障害物を取り除き、その精神が自分自身で成長していくきっかけをつくってあげることなのです』と」
続けて、著者は以下のように述べています。
「『志学』という探究が始まれば、おのずと、それぞれの発達年齢と課題に応じて、『而立』『不惑』『知命』『耳順』『従心』に至ると考えた孔子とシュタイナーは驚くほど近くにいる。孔子もシュタイナーも精神の自己成長に信を置き、それを妨げることこそがもっとも非教育的・反教育的な事態だと考えている。孔子が『五十にして天命を知る』と言う時、そこに『天』に向って『畏敬の念』を抱いて立っている『精神』がある。その『精神』が『天命』を聴き取るのだ。その『精神』を『霊性』と言い換えることもできる」
この一文を読んだわたしは、心の底から感動しました。
そして、宮沢賢治です。賢治は大正15年(1926)に羅須地人協会を設立し、その設立宣言書として『農民芸術概論綱要』を作成しました。その「序論・・・・・・われらはいっしょにこれから何を論ずるか・・・・・・」の中で、この羅須地人協会では、「近代科学の実証と求道者たちの実験とわれらの直観の一致に於て論じ」つつ、世界全体の幸福を追求し、「世界が一の意識になり生物となる方向」に「求道」的に自我意識の宇宙進化を目指し、「銀河系を自らの中に意識してこれに応じて行く」ことが謳われています。著者は、以下のように述べます。
「1926年設立当時、このマニフェストを真に理解した人がどれくらいいただろうか? ほとんど皆無であったと思われる。だがもし『銀河系を自らの中に意識して』生きている宮沢賢治がルドルフ・シュタイナーの教育論や『アーカーシャ年代記』を知ったとしたら、大いに共感した可能性はある」
そして、著者は日本文化の本質について以下のように喝破します。
「日本文化においてもっとも日本的な芸能・芸術形式といえる能はイザナミの負の感情を引き継ぎ、死を媒介とした天の岩戸の前の『祭り』や『神懸り』から始まる。そのすべてにスサノヲが関与し媒介している。『祭り』も『神楽』も、その起源においても現在相においても、『死と再生』を志向し、『平家物語』などに多くの題材を採る能も、死によって怨霊化した霊を慰める鎮魂劇を核としている。その能(申楽)の『翁』『千歳』『三番叟』の三者関係も、スサノヲ的翁童身体の変奏、すなわち創造と破壊と祝福と笑いである」
 熱唱するバク転神道ソングライター
熱唱するバク転神道ソングライター
著者は、「3・11」の大惨事を経験した日本人は、日本の神話的創造力の根源をなす「スサノヲの力」をもう一度「爆発」させなければならないと訴えます。それができなければ、この混迷と闇を突破することはできないだろうというのです。著者は本書の最後を「その『スサノヲの力』の『爆発』を『世直し』の原動力として引き出し、歌い続けたい」の一文で締め括っています。
 本書を読んで「こころの未来」が見えました!
本書を読んで「こころの未来」が見えました!
スサノヲ、聖徳太子、最澄、空海、本居宣長、石田梅岩、二宮尊徳、宮沢賢治、出口王仁三郎、シュタイナー、そして孔子・・・・・・本書は「神界」をフィールドワークした後に「現世」に生還してきた著者による「世直し」マニフェストであり、その実践報告でもあります。 今後の日本「世直し」には「グリーフケア」の分野が最重要になってくるような気がしてなりません。不肖の「魂の弟」であるわたしは、これからも著者の「楽しい世直し」の道をともに歩いていく覚悟です。 京都大学こころの未来研究センターを定年退職された著者ですが、本書を読み終えたわたしには確かに「こころの未来」が見えました。
