- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2016.03.18
『古代都市』フュステル・ド・クーランジュ著、田辺貞之助訳(白水社)を読みました。1864年にストラスブールで出版された歴史学の古典です。 デカルト的懐疑を史学に適用し、古代の歴史家や詩人たちが遺した古代についてテキストに基づいて、古代ギリシアや古代ローマの社会における最初期の諸制度の起源を分析しています。
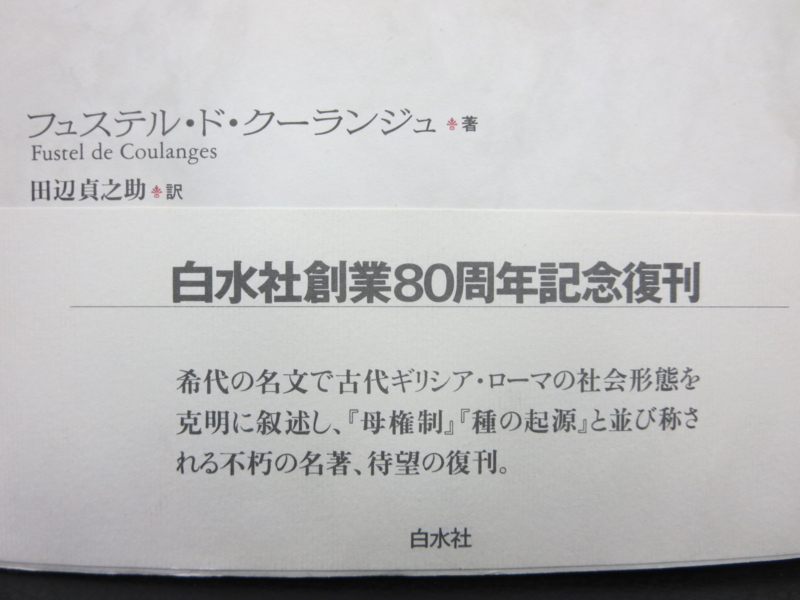 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「白水社創業80周年記念復刊」と大書され、続いて「希代の名文で古代ギリシア・ローマの社会形態を克明に叙述し、『母権制』『種の起源』と並び称せられる不朽の名著、待望の復刊」と書かれています。本書がいかに重要な書物であるかがよくわかる帯のコピーです。たしかに、ものすごい本でした。ページ数も560ページ以上あります。
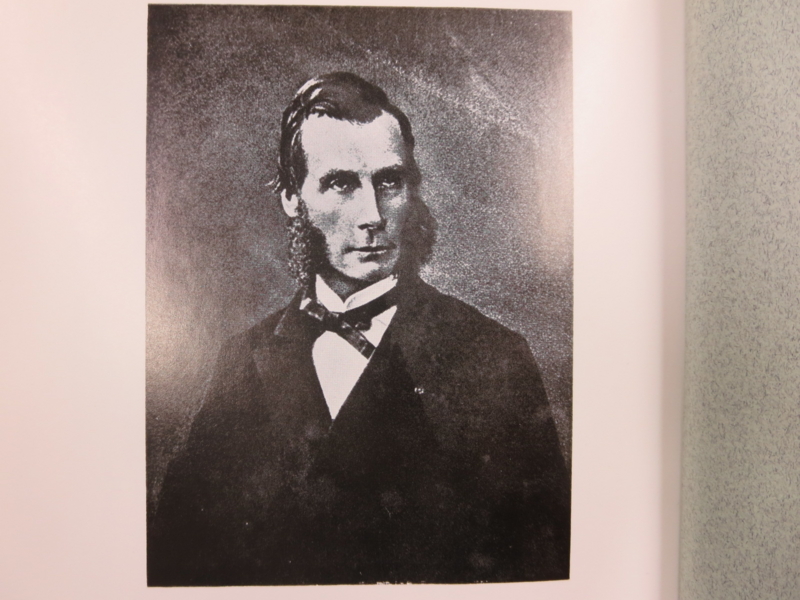 著者の写真
著者の写真
著者は、19世紀のフランスの歴史家です。祖先はブルターニュ出身で、父や祖父は海軍士官を務めました。1830年にパリで生まれ、生後1年3ヶ月で父を失っています。53年にエコール・ノルマル・シュペリウールを卒業すると同時に、アテネ・フランス学院の研究生に選ばれ、2年間をアテネで遊学しました。彼はキオス島を好んで訪れ、それは処女作「キオス島についての覚書」として結実しています。帰国後、5年間を中学教師として過ごしましたが、60年にストラスブルク大学の教授に任命されました。
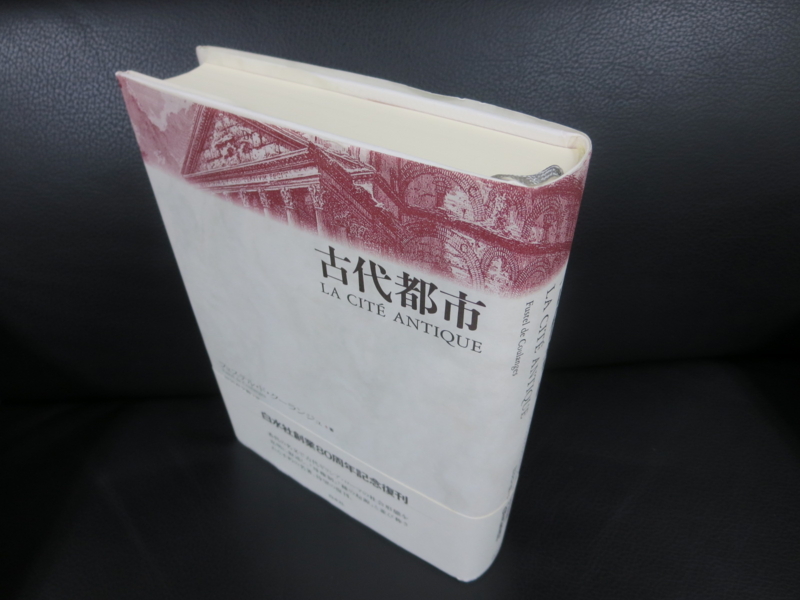 この厚さを見よ!
この厚さを見よ!
代表作である本書『古代都市』は、大学で行われた連続講義によるものでした。当時クーランジュは無名であり自費出版で600部が公にされたに過ぎなかったといいます。70年、文相であり歴史家でもあったヴィクトール・デュリュイの推薦により母校のエコール・ノルマルの教授に任命されました。78年にソルボンヌ大学に転じた後、80年にはエコール・ノルマルの校長となり、83年にソルボンヌに復帰しています。非常にハードな学問人生を送った結果、過労から病気になり、89年に59歳でパリに没しています。
 わが書斎の田辺貞之助の翻訳書コーナー
わが書斎の田辺貞之助の翻訳書コーナー
訳者の田辺貞之助は日本を代表するフランス文学者の1人で、エミール・ゾラ、モーパッサンなど自然主義文学作品を多数訳したことで知られます。その一方で、ユイスマンス、テオフィル・ゴーティエなどの幻想文学の翻訳も多く手がけ、わたしはそのすべてを読んでいます。特に、ユイスマンスの『彼方』は日本人が翻訳したフランス文学の最高傑作であると思っています。本書『古代都市』の訳文は平仮名を多用しており、非常に格調高く、ロマンの香りが漂っていました。
本書を一読して、わたしは心の底から驚愕しました。 わたしが知りたかったことがすべて書かれていたのです。「これは、100%わたしのための書物だ」と思いました。そんな経験は、50年以上生きてきたって、滅多にありません。死者崇拝と儀式がいかに人間の文化や文明そのものに影響を与えてきたが詳しく述べられています。本当は、『唯葬論』(三五館)を脱稿する前に本書を読みたかったです。
『唯葬論』は、わたしの活動の集大成ともいえる内容で、死者と生者の関係性すなわち「葬」こそが人類の存在基盤であり、発展基盤であることを訴えています。「宇宙論」「人間論」「文明論」「文化論」「神話論」「哲学論」「芸術論」「宗教論」「他界論」「臨死論」「怪談論」「幽霊論」「死者論」「先祖論」「供養論」「交霊論」「悲嘆論」「葬儀論」の18章から構成されているのですが、じつは刊行後に「政治論」と「経済論」も書くべきであったと後悔していました。本書『古代都市』の読了後はさらに「家族論」「都市論」「国家論」「法律論」を加えたいと思いました。いつの日か、全24章から成る『定本 唯葬論』を上梓したいです。でも、次回作である『儀式論』(仮題、弘文堂)を執筆するまさに直前に本書を読めて本当に良かったです。この1冊で、他の参考文献100冊分に相当します。それほど、すごい本でした。
本書の「目次」は、以下のような構成になっています。
「薦辞」中川善之助
「訳者序」田辺貞之助
「フュステル・ド・クーランジュ論」シャルル・セイニョボス
緒言「古代人の制度を知るためには、その最古の信仰を研究する必要があることについて」
第一編 古代の信仰
第一章 霊魂と死との信仰
第二章 死者の崇拝
第三章 聖火
第四章 家族宗教
第二編 家族
第一章 古代家族の構成原理をなす宗教
第二章 婚姻
第三章 家族の永続について ―独身の禁止、不妊の妻の離婚、兄弟姉妹の不平等
第四章 養子と離婚
第五章 親族関係とローマ人のいう男系親について
第六章 所有権
第七章 相続権
第八章 家族内の権威
第九章 古代の家庭道徳
第十章 ローマとギリシアの氏族
第三編 都市
第一章 支族と部族
第二章 あたらしい宗教的信仰
第三章 都市の形成
第四章 都会
第五章 都会建設者の崇拝。アエネアスの伝説
第六章 都市の神々
第七章 都市の宗教
第八章 祭儀と年代記
第九章 都市の政治。国王
第十章 行政官
第十一章 法律
第十二章 市民と外国人
第十三章 愛国心。追放
第十四章 自治の精神について
第十五章 都市のあいだの関係。戦争、平和、神々の結盟
第十六章 連盟。植民
第十七章 ローマ人、アテナイ人
第十八章 国家の絶対権。古代人は個人の自由を知らなかった
第四編 革命
第一章 貴族と被護民
第二章 庶民
第三章 第一次革命
第四章 貴族階級の都市支配
第五章 第二次革命。家族組織の変化、長子権の消滅、氏族の解体
第六章 被護民の独立
第七章 第三次革命。庶民が都市にはいる
第八章 私法の諸変革。十二表法。ソロン法典
第九章 政治上の新原則。公共の利益と選挙権
第十章 富による貴族階級構成の企図。民主政治の樹立。第四次革命
第十一章 民主政治の諸法則。アテナイの民主政治の例
第十二章 スパルタの諸革命
第五編 都市政体の消滅
第一章 あたらしい信仰。哲学による政治上の法則の変革
第二章 ローマの制覇
第三章 キリスト教が政治の諸条件にあたえた変革
「訳者略注」
「原著索引」
「訳者序」で、田辺貞之助は以下のように述べています。
「『古代都市』は六ヵ月で編集されたもので、古代文献に関する個人的な知識にもとづいた独創的な著作であるが、決して考証の書ではない。そのくわだてるところは『ギリシア・ローマの社会がどんな原理と法則とによって支配されていたかを示す』ことにあった。この書物をつらぬく関心は『これら古代の国民と近代社会とを永遠に区別する根本的な相違』をあきらかにすることであった。彼の言葉によれば、『われわれを少年時代からギリシア・ローマ人のあいだに生活させるわが国の教育制度は、彼らをたえずわれわれと比較する習慣をあたえる。・・・・・・そこからおおくのあやまりが生じる。・・・・・・これら古代の国民に関する真理をつかむためには、われわれ自身のことを考えずに研究することが賢明である』。古代の諸制度は、おのおの切りはなして研究する場合には、『難解で、奇妙で、説明にくるしむ』。しかし、これを古代の信仰と対照してみると、すぐにきわめて明瞭になる」
本書の第一編で、フュステルはギリシア人、ローマ人、インドのアーリア人などの古代人たちのきわめて古い信仰を探ります。それは後世の儀式やさまざまな信仰のうちに痕跡をとどめている信仰であるということを明らかにします。第二編では、この原始的な信仰から、所有および相続の機構とともに家族が生じることを明らかにします。第三編では、自然の諸神を崇拝する宗教が家族をあわせて都市をつくり、さまざまな儀式、行政官職および法律が生れたことを明らかにします。第四編では、信仰が変化し、その変化が革命を生じて、相次ぐ四度の革命が古代都市をくつがえしたことを明らかにします。最後の第五編では、古い信仰がほろびて、それと同時に都市政体が消え去ったことを明らかにします。そのあいだの進化は、著者の「われわれは信仰の歴史をあきらかにした。信仰が確立するとともに、人間社会が構成され、信仰に変化をきたして人間社会は一連の革命をけみし、信仰がきえて社会は相貌をかえた。これが古代の法則である」という言葉に集約されています。
緒言「古代人の制度を知るためには、その最古の信仰を研究する必要があることについて」の冒頭で、著者は次のように述べています。
「私はこの書物で、ギリシアとローマの社会が、どんな原理と法則とによって統治されていたかをのべるつもりである。私がギリシア人とローマ人とをおなじ研究にまとめたのは、この両国民が元来おなじ民族から派生し、分離したとはいえおなじ言語に属する語法をかたるとともに、本質的に共通の制度をもち、かつまた、それぞれ類似した一連の革命をへてきたからである」
その緒言の最後では、著者は以下のように述べています。
「こころみに、ペリクレス時代のギリシア人とキケロ時代のローマ人とを観察してみよう。彼らはその心の奥底に太古の幾世紀の正確な痕跡と確実な足跡とをおさめている。キケロ時代の人々は、(私はとくに庶民階級についていうのであるが)、伝統にみちた想像をもっていた。その伝説は遠い太古から由来したもので、当時の人々の考え方の証跡を保存し、それを世紀から世紀へつたえたのである。ひとつの語根の本質的な意味は、ときとしてふるい世論や風習をしめすことがある。思想はかわり、記憶はうしなわれるが、言語はきえさった信仰のうごかしがたい証人として、後世にのこる。また、彼らは犠牲献祭や葬式や婚礼のときに特殊の儀式をおこなうが、その儀式が人そのものよりもふるいことは、彼らの信仰とまったく無関係になっているのをみてもあきらかである。しかし、彼らが遵奉する儀式や朗誦する祈祷文をさらにくわしく観察するならば、そこに、彼らより15世紀も20世紀も以前の人類の信仰の痕跡を見いだすことができるであろう」
人類の歴史の最初には、まず儀式の存在があったのです。
第一編「古代の信仰」の第一章「霊魂と死との信仰」の冒頭には、以下のように書かれています。
「ギリシア・ローマ史の末期にいたるまで、きわめてふるい時代にはじまったとおもわれる思想と風習との一団が庶民階級のあいだにのこっていた事実をみとめるが、これによって、人類が自分の性質や霊魂や死の神秘についてどんな考えをいだいていたのかを、知ることができる。 ギリシアやイタリアの住民の根源をなすインド・ヨーロッパ民族の歴史をできるだけ遠くさかのぼってみても、この民族がみじかい現世のあとですべてが無に帰してしまうと考えていた証跡は見いだすことができない。はるかな太古の時代にあっても、人は哲学者があらわれるまえから、現世ののちには他界の生活があると信じていた。そして、死というものを肉体の消滅とはおもわずに、単なる生命の転化とみていた」
また、古代ギリシアおよびローマにおける埋葬の儀式について、著者は以下のように述べています。
「埋葬の儀式は、遺骸を墓にほうむると同時に、生命あるものをいっしょにおさめるかのように古代人が信じていたことを、あきらかにしめしている。宗教的儀式をつねに非常に正確かつ入念にのべたヴェルギリウスは、ポリュドロスの葬礼の物語を、『われら霊魂を墓所におさむ』という言葉でおわっている。この言葉は、オヴィディウスや小プリニウスの書物にもみられる。それは霊魂についてこれらの著作家のいだいていた思想が、たまたまおなじ表現をとらせたわけではなく、かような表現が記憶しがたい太古から言語のなかにつづいていたためで、したがって、これはふるい民間信仰を立証するものである」
なぜ、古代人たちは葬送の儀式を重視したのか。著者は述べます。
「みすてられた霊魂はやがて悪意をおこし、遺骸と霊魂とに墓をあたえさせるために、疫病をおくり、収穫物をあらし、あるいはあさましい姿をあらわしなどして、生きているものどもをくるしめた。幽霊の信仰はここから生じた。古代人のあいだでは、墓をもたない霊魂がきわめて悲惨で、霊魂は墓をえてはじめて永久の幸福をえると、すべてのものが信じていた。したがって、葬送の儀式は悲嘆を誇示するためのものではなく、故人の安息と幸福とをねがう手段にほかならなかった。さらに注視すべきことは、単に遺骸が地中にうめられるだけでは不十分で、そのうえ、伝統的な儀式をいとなみ、きまった祈祷文をとなえなければならなかったことである」
著者は「古代人が葬礼の儀式と祈祷文とをどんなに重んじていたかをいくつかの具体例で示した後、以下のように述べています。
「この儀式や祈祷文を省略すれば、霊魂はまよいでて生きているものに姿をあらわすのであるから、霊魂が墓におさまって安住することができるのは、まったく儀式と祈祷文との功徳によるのであった。また、古代人はかような功徳をもつ祈祷文と同時に、その反対の効力をもつ呪文をもっていた。すなわち、霊魂を呼びおこして、一時墓からぬけださせる呪文である」
続いて、著者は以下のように述べています。
「古代作家の著作をみると、当時の人々は死後に儀式が型どおりにおこなわれないことを、非常におそれていたようである。これは実に切実な心配であった。人々は死そのものよりもむしろ葬礼がおこなわれるかどうかを心配した。それは永遠の安息と幸福とが葬礼に左右されたからである」
これなど、まさに、『唯葬論』で訴えた「問われるべきは『死』ではなく『葬』である」というテーゼそのものです。
さらに著者は、葬礼の儀式について、以下のように述べます。
「古代の都市では重犯罪人を処罰するのに葬礼不許可の刑をあたえたが、これは極刑とみられていた。この刑罰は肉体よりむしろ霊魂そのものを罰したので、霊魂にほとんど永劫の刑をあたえるものであった。 しかし、ここに注意すべきことは、死者の住所について、いまのべたのとは別の意見が、古代人のあいだにおこなわれていたことである。すなわち、彼らはやはり地下ではあるが、墓よりもずっと広大な地域を想像したのである。そこでは、あらゆる霊魂が遺骸から遠くはなれ、それぞれ群をなして生活し、前世でなした行為の善悪にしたがって、刑罰や褒賞があたえられた。しかし、かような信仰は先にのべた葬礼の儀式とはあきらかに矛盾している。それは埋葬の儀式がはじめられた当時には、まだ地獄や極楽の信仰が発生していなかった証拠である。古代の最初の思想は、死者が墓のなかで生活し、霊魂が肉体とはなれずに遺骸のうめられた土地の一画と永久にむすびつくというのであった。しかもまた、冥界にいった死者は現世の功罪を報告する必要がなく、ひとたび墓にはいれば褒賞も刑罰も期待すべきではなかった。これはたしかに粗雑な思想ではあるが、しかし来世という概念の揺籃をなすものであった」
このように、地下の生活は、現世とあまり違いませんでした。しかし、死者は食物を必要としたのです。人々は一年じゅう期日をきめて、それぞれの墓に食物を捧げました。
第二章「死者の崇拝」の冒頭には、以下のように書かれています。
「かような風習は太古からおおくの行動律をうんだ。死者は食物と飲み物とを要求するから、その要求をみたすことは、生きているものの義務であると考えられた。死者に飲食物をささげる心づかいは、人間の気まぐれや変わりやすい感情にゆだねられるべきではなく、まったく義務的なことであった。そして、そこに一個の完全な死の宗教がたてられた。その経典ははやく消滅したけれども、儀式そのものはキリスト教が勝利をしめるまでつづいた」
続いて、著者は次のように述べています。
「まず、死者は神聖なものとされていた。古代人はさがしだせるかぎりの敬虔な形容詞を彼らにささげて、『善良な』、『神聖な』、『至福な』などとよび、人類が敬愛あるいは畏怖する神格へよせる最大の尊敬をささげた。古代人の考えでは、死者は神であった」
ギリシア人は死者に対して「地下の神」と呼び、ローマ人は「生霊(マネス)の神」と呼びました。墓はそれらの神の神殿でした。この死者の崇拝はギリシア人、ラテン人、サビナ人、エトルリア人のあいだに見られましたが、またインドのアーリア人にも認められました。『リグ・ヴェーダ』の賛歌もこれを記していますし、『マヌの法典』もこの崇拝を人類最古の信仰のように語っています。著者は次のように述べています。
「この死者の宗教はアーリア民族のもっともふるい宗教であったらしい。彼らは因陀羅(インドラ)あるいはゼウスを考えだして崇拝するまえには、死者をまつったのである。死者をおそれ、死者に祈りをよせたのである。宗教の感情はここからはじまったようにおもわれる。人類がはじめて超自然の思想をいだいて、可見の世界のかなたに希望をはせようとしたのは、おそらく死を眼前にみた結果であろう。死は最初の神秘であった。死は人類を他の神秘の領域にみちびきいれた。そして、人類の思考を可見の世界から不可見の世界へ、一時的事象から永遠の事象へ、人間性から神性へと向上させていったのである」
第三章「聖火」の冒頭には、以下のように書かれています。
「ギリシア人やローマ人の家には祭壇がすえてあって、すこしの灰ともえる灰とが、つねにそなえてなければならなかった。夜も昼もその火をたやさないのが、家長の神聖な義務であった。祭壇の火がきえると、その家には災いがおそう。毎晩人は炭火がもえゆきないように、灰をかけておく。朝眼がさめると、まずその火をかきたて、木の枝をのせて火力をさかんにする。祭壇に火がきえるのは、全家族が死滅したときである。竈がきえるのと家がたえるのとは、古代人のあいだでは意味をおなじうする表現であった。 祭壇に火をたやさないこの風習が、ふるい信仰と関係のあることはあきらかである。この風習についてまもられた宗規と儀式とは、これが意味のない習慣ではなかったことをかたっている」
火の儀式は、そのまま食事の儀式につながります。 著者は、古代人にとっての食事について以下のように述べます。
「食事はとくに宗教的な行為で、神がつかさどることであった。パンをやき食物を調理するのは神であった。食事の初めと終わりには、神に祈りをあげなければならなかった。食事をはじめるまえには、祭壇に食物のお初をささげた。酒をのむまえにも、祭壇に酒をそそいで灌祭をおこなった。それは神の分け前である。神も食卓に列して飲食することを、だれもうたがわなかった。事実としても、炎がそなえられた食物にやしなわれるかのように、もえさかってゆくのをみなかったであろうか。こうして、人と神とは食事をともにした。それは神聖な儀式に、神と人とは食事によって相通ずることができたのである。このふるい信仰は、時とともに人の心からきえたが、ホラティウス、オヴィディウス、ユヴェナリスなども、なお竈のまえで食事をし、灌祭や祈祷をおこなった」
さらに著者は、以下のように述べています。
「確実なことは、ギリシア人やローマ人の祖先である民族に、はるかな太古の時代から、死者と竈とを礼拝する信仰があった事実である。この古代宗教は物質的自然界に神をもとめずに、人間そのもののうちに神をもとめ、礼拝の対象として、われわれのうちにある不可見の存在を、すなわち肉を生かしかつ支持する精神力・思考力をえらんだのだった。 この宗教はいつまでもおなじ権力で人を支配していたわけではなく、時とともに徐々におとろえていったが、決して消滅してはしまわなかった。これはアーリア民族の黎明期と時をおなじうして発生したもので、したがってその内臓にふかくくいいっていた。ギリシアはオリンポスのはなやかな宗教もこれを根こそぎにすることができず、それにはキリスト教の出現をまたなければならなかった」
第四章「家族宗教」では、著者は以下のように述べています。
「死者の崇拝は、キリスト教徒の聖者崇拝とはまったくちがっていた、この崇拝の第一の規則は、おのおのの家族によって、血縁ある死者に対してだけなされることである。葬礼は、宗教的には、近親者だけでいとなんだ。きまった時期におこなわれた供養の儀式も、家族だけが列席する権利をもち、他家のものは全部厳重に除外された。死者は一家のものの供物しかうけず、子孫の礼拝だけをのぞむと信じられていた。その家に属さないものが儀式に列するのは、生霊の安息をみだすことであった。したがって、法律は他家の墓地にちかよることを禁じていた。たとえ不注意からにせよ、墓に足をふれることは非常に不敬な行為で、かような罪をおかしたものは死者の怒りをしずめるとともに、わが身のけがれをきよめなければならなかった」
まるで現代日本で流行している「家族葬」を肯定するかのような記述ですが、忘れてはならないことは、この家族宗教はギリシアやローマでもすでに消え去っているということです。これは、いわゆる「家族カルト」ですね。 著者は次のようにも述べています。
「古代人が死者の礼拝を指示した言葉は意味深長である。ギリシア人は『パトリアゼイン』といい、ラテン人は『パレンターノ』といった。どちらも『親しき父よ』という意味である。それは供物と祈願とがただ各自の祖先にだけささげられたからである。死者崇拝は実際に祖先崇拝であった。ルキアヌスは俗間の意見を嘲笑しながらも、彼のいった『死後に息子をのこさなかったものは供物をうけとることができぬ。したがって永遠の飢えにさらされる』という言葉は、一般人の考えていたことをあきらかに説明している。インドでも、ギリシアと同様に、死者への供物はただ直系の子孫だけからささげられるべきであった。インド人の法律は、アテナイの法律とおなじく、神饌の儀式には、たとえ友人でも、他家のものが列席することを禁じた」
各家族はめいめい墓地を持っており、死者はそこへ憩いに行きました。 著者は、古代人の墓地について以下のように述べています。
「血統をおなじうするものはそこにほうむられ、他家のものはだれもはいることをゆるされなかった。諸種の儀式や周年祭はその墓のまえでいとなまれた。家族の各人は神となった祖先の姿をそこにみるようにおもった。古代にあっては、墓は各家族の所有地のなかにおかれた。しかも、ある古代人の言葉によれば『子孫のものが家への出入りの都度祖先にであって祈りをささげることができるように』墓は宅地の中央、戸口からあまり遠くないところへきずかれた。こうして祖先は家族のあいだに現存していた。祖先は目にこそみえないが、つねに家庭内にあって、生前と同様に家族の一員であり、その父であった。不滅で、幸福で、神格をそなえた祖先は、地上にのこした子孫の生活に関心をもって、その欲するところを知り、弱点をおぎなった。まだ生きてはたらいているもの、すなわち、古代の表現にしたがえば、まだ一生の年貢をおさめきらないものは、支持者と指導者とを身ぢかくもっていた。それは祖先たちである。彼らは困難にであえば祖先のふるい知恵にすがり、悲嘆にくれては慰めをねがい、危険にであっては庇護を、過失をおかしては許しをもとめた」
さらに著者は、古代の家族宗教について以下のように述べています。
「この家族宗教には、一定した宗規も共通の儀式書もなかった。おのおのの家族は、その点で、完全な独立をたもっていた。外部のどんな権力もその礼拝や信仰を規制する力がなかった。家長がすなわち祭司で、祭司のあいだに階級の別はなかった。ローマの神官長やアテナイの執政官は、家長がその宗教儀式を完全にはたしているかどうかをたしかめる権利をもってはいたが、家長に対してすこしの変更でも要求する権利がなかった。『儀式にしたがって献祭を執行せよ』というのが絶対の規則であった。各家族は特殊の祭式と別個の行事と祈祷の呪文と賛歌とをもっていて、家父だけがその唯一の代表者であり、また神官であった。そして、彼だけがその宗教をおしえる権利をもっていたが、それは父子相伝で、息子にかぎられていた。儀式や祈祷文や賛歌はこの家族宗教の根幹をなしていたが、それは世襲の神聖な財産で、家族はこれをだれにもわけず、他家のものにもらすことすら禁じていた。インドでも同様であった。『家につたわり、父よりうけた賛歌のゆえに、我は外敵に対して強し』と婆羅門(バラモン)教徒はいっている」
第二編「家族」に進みます。第一章「古代家族の構成原理をなす宗教」で、著者は以下のように述べています。
「古代家族の成員を融合したものは、血統や感情や体力よりもさらに強力ななにかであった。それは竈と祖先との信仰である。そしてこの信仰は、全家族を現世と他界とを通じて一体となるにいたらせた。古代の家族は自然の結合である以上に、宗教的な結合であった。したがって、女は結婚の神聖な儀式によっておなじ宗教に帰依させられたうえでなければ、決して真の意味で家族の一員とはみとめられなかった」
著者によれば、古代ギリシア語は「家族」を示すのにきわめて意味深長な言葉を使ったそうです。それは「エピスチオン」という言葉で、「竈のかたわらにいるもの」という意味でした。家族とは、同じ竈神に祈り、同じ祖先に神饌を捧げる人々の一団のことだったのです。
第二章「婚姻」の冒頭では、著者は「家族宗教が設定した最初の制度は、おそらく婚姻であったろう」と書き、続けて以下のように述べています。
「ここに注目すべきことは、男子から男子へつたえられた竈神と祖先との崇拝は、しかしながら決して男子だけに属していたものではないことである。女子も祭祀にたずさわった。娘としては父の、妻としては夫の宗教行為にしたがった。 この事実だけみても、古代人のあいだの夫婦結合の本質を推察することができる。ふたつの家族は、たとえならんでくらしていようとも、別々の神をもつ。その家族のひとつで、わかい娘は幼時から父の宗教にあずかり、竈神をまつり、日々に灌祭をおこない、祭日には花や葉飾りで竈をかざり、そしてこれに保護をねがい、恩恵を感謝する。父祖の竈神は彼女の神である」
続けて、著者は以下のように述べています。
「この娘に対して隣家の若者が結婚を申しこんだとすると、娘にとっては、父の家をでて他家にはいるという以外に、別の重大な問題がある。それは父祖の竈をすてて、夫の竈にいのらなければならないことである。彼女は宗教をかえて、他の儀式を実行し、別の祈りを口にしなければならない。少女時代の神とわかれて、未知の神の主宰にしたがうことになる。彼女は婚家の神を尊崇しながら、同時に実家の神を信奉しつづけようと希望することはできない。この宗教では、おなじ人物がふたつの竈と二系の祖先とをまつることをゆるさないのが、うごかすことのできない鉄則であったからなのである。ある古代人は、『結婚するやいなや妻は父祖の家族宗教とはまったく関係をたち、夫の竈神に生贄をささげるべきものである』といっている」
著者は、古代人における結婚について以下のように述べています。
「古代人の思想の奥にわけいれば、夫婦の結合がどんなに重大であり、この問題に対する宗教の干渉がどんなに必要であったかが理解できよう。それゆえ、わかい娘が今後遵奉する信仰に帰依するために、神聖な儀式にのっとる必要があったのは当然である。出生によってむすばれていない竈神の侍者となるためには、叙品式あるいは養子縁組ともいうようなものが必要ではなかったであろうか。 結婚はかように重大な結果を生ずる神聖な儀式であった。ギリシア・ラテンの著作家は、結婚を意味するのに、宗教的な儀式をしめす言葉をつかう習慣になっていた。アントニウス皇帝時代のポルックスはわれわれの知らない古代文学に通暁していたが、そのいうところによれば、古代にあっては、結婚を『ガモス』という特定の名でよぶかわりに、単に神聖な儀式を意味する『テロス』であらわしたそうである。これをみても、古代では結婚が神聖な儀式のなかでももっとも重要なものであったことがうかがわれるのである」
ところが、この結婚を司った宗教は、ジュピターやジュノーやその他のオリンポスの神々ではありませんでした。著者は次のように述べます。
「儀式は神殿でおこなわれるのではなく、めいめいの家であげ、これを主宰するのは家の神であった。実際には、上天の神々の宗教が優位をしめるようになった時代には、人々は婚礼の祈りのさいにもその神々を祈願せずにはいられなくなり、さらに、婚儀にさきだって神殿におもむいて神々に生贄をささげ、それを婚礼の序式とよんだが、儀式のおもな部分は、つねに竈のまえでおこなうべきであった」
本書によれば、ギリシア人の婚礼はいわば三幕から成り立っていました。 第一幕は娘の実家の前で、第三幕は夫の家の竈の前で、第二幕は両家のあいだの道中で行われ、それぞれ「婚約の式(エンギユエーシス)」、「納めの式(テルス)」、「「輿入れの式(ポンペー)」と呼ばれたそうです。ローマの結婚もギリシアとよく似ていて、同じく三段に分かれていました。すなわち、「引渡し(トラジチオ)」、「輿入れ(デドウクチオ・イン・ドムム)」、「分食式(コンフアレアチオ)」です。
これを知ったわたしは、自身のブログ記事『結納力』で紹介したブックレットに書いた内容を思い出しました。すなわち、もともと日本人の結婚式とは、結納式、結婚式という2つのセレモニー、それに結婚披露宴という1つのパーティーが合わさったものだということです。日本でも結婚は三段に分かれていたのです。結納式、結婚式、披露宴の三位一体によって、新郎新婦は「結魂」の覚悟を固めてきたのです。今では結納式はどんどん減っていますが、じつはこれこそ日本人の離婚が増加している最大の原因であると思います。
古代ギリシアおよびローマでは、結婚の儀式をすませた男女は、同じ信仰のうちに結ばれました。著者は以下のように書いています。
「妻は夫とおなじ神々や儀式や祈祷や祭祀をもつ。したがって、法律学者がわれわれに保存した『婚姻は神の法と人の法との結合なり』とか、『女は人のものと神のものとをあわせたるなり』とかいうふるい結婚の定義が生ずる。それは妻も夫とおなじ宗教をもつからで、妻は、プラトンがいうように、神々がみずからその家にみちびきたもうたのである。 かようにして結婚した妻はやはり死者を崇拝する。しかし、彼女が神饌をささげるのは、自分の祖先に対してではない。彼女にはもはやその権利がない。結婚は彼女をまったく実父の家族から分離させ、宗教的な関係も一切たたれてしまう。彼女がいま供物をささえげるのは夫の祖先に対してである。彼女は彼らの家族の一員となり、彼らは彼女の祖先となった。結婚は彼女を更生させ、今後彼女は夫の子となるのである。法律学者も『義理の娘(フィリエ・ロコ)』といっている。人は二軒の家のものでありえないように、ちがう家族宗教に属することはできない。妻はまったく夫の家と宗教とに帰属する。この規則がもたらす結果は、やがて相続法のうちに見いだされるであろう」
結婚を神聖視するこの制度は、インド・ヨーロッパ民族にあっては、家族宗教と同じく古いものでした。その儀式について、著者は述べます。
「婚礼の儀式は非常に荘重で厳格をきわめ、古代人がかような盛儀は各家族ともただひとりの女に対してしかゆるされもせず可能でもないと信じていたのもおどろくにたりないであろう。したがって、この宗教は一夫多妻をゆるすはずもなかった。 またかような結婚が解消できないものであり、離婚がほとんど不可能であったことも理解できる。ローマ法では、『売買式結婚(コエンプチオ)』や『時効式結婚(ウースス)』の場合には、容易に離婚をゆるしたが、宗教的儀式によった結婚の場合には、離婚は非常に困難であった。この種の離婚には別の神聖な儀式が必要であった。宗教による結合は宗教によってとくよりほかに道がなかったからである。『分食式(コンフアレアチオ)』は『拒食式(デフアレアチオ)』によらなければとりけすことができなかった」
第五章「親族関係とローマ人のいう男系親について」の冒頭では、著者は「親族」について以下のように述べています。
「プラトンは親族とはおなじ家の竈をまつるものの団体であるといっている。プルタルクスは兄弟とはおなじ生贄をささげ、おなじ父祖の神々をいただき、かつ墓をともにする権利をもつ男たちのことであるとする。デモステネスはふたりの男が親族であることを証明しようとするときには、おなじ祭祀をいとなみ、おなじ墓に神饌をささげる事実をあきらかにした。実際に、親族を構成する要素は家族宗教であった。ふたりの男はおなじ神々とおなじ竈とをまもり、おなじ神饌をささげるときには、親族と称することができた」
第六章「所有権」では、墓について以下のように述べられます。
「墓は古代宗教では非常な重要性をもっていた。一方では祖先の祭祀をおこなうとともに、他方では、祭祀の主要な儀式、すなわち神饌奉献は、祖先のいこうその場所でいとなまなければならなかったからである。したがって、家族はそのひとりひとりが順次にいこいにゆくべき共同の墓をもっていた。墓に対する規則は竈に対するのと同様であった。二個の竈をおなじ家屋内におくことがゆるされなかったように、二組の家族をおなじ墓におさめることもゆるされなかった。死者を家族の墓以外にほうむるのは、その墓のなかに他家のものの遺骸をうめるのと同様に不敬のふるまいであった。家族宗教は生前も死後もおのおのの家族を分離させ、共同生活のあらゆる形態を厳重にとおざけた。また、家が密接していてはならなかったように、墓も相接してはならなかった。どの墓にも、家とひとしく、一種の隔墻がきずかれていた」
墓は、家族と土地との不可分な関係を、すなわち所有権を確立しました。
墓の所有権は、人間生活の所有権に発展しました。著者は述べます。
「おのおのの家族に所有権をあたえた神々は、家の神々、すなわち竈神と生霊とであった。人の心に絶対の権威をふるった最初の宗教は、また人間生活に所有権を確立した恩人でもあった。 私有権が家族宗教として無視できない制度であったことはあきらかである。この宗教は住居と墓とを他家から孤立させることを命じ、そのために、共同生活は不可能であった。またこの宗教は竈を土地に固定させ、墓を破壊したり移転したりしてはならないと規定した。それゆえ、もしかりに所有権を廃止するならば、竈は常住の場所をうしない、家族は混同し、死者は見すてられ、祭祀もたえるであろう。家族はうごかすことのできない竈と永久の墓とによって土地を所有した。土地にはいわば竈と祖先との崇拝がふかくしみこんでいたのであった。かようにして、古代人は彼らの知能にとってあまりにも困難な問題を解決する苦心をまぬがれることができ、ただ信仰の力によって一挙に所有権の観念にたっしえたのであるが、この権利こそあらゆる文明の基礎をなすものであった。人間はこれによって同時に自分を改善したからである」
最初に所有権を保障したもの、それは法律ではなく宗教だったのです。
第三編「都市」に進みます。 第三章「都市の形成」の冒頭には、以下のように書かれています。
「部族は家族や支族とひとしく独立した団体として構成されたものである。部族は独自の祭祀をもっており、その祭祀には他人がくわわることをゆるさなかった。部族が成立すれば、どんな家族も新規にそれに加入できなかった。そしてまた、ふたつの部族がひとつに融合することもゆるされなかった。各部族の宗教がそれに反対したからである。しかし、数個の支族が結合して部族をなしたように、数個の部族も、それぞれの祭祀を尊重するという条件でたがいに連合することができた。この連盟が成立した日に、都市がうまれた」
また、著者は以下のようにも述べています。
「古代の信仰は祖先崇拝を人類に命じた。祖先崇拝は家族をひとつの祭壇の周囲にあつめた。これから最初の宗教や最初の祈願、義務の観念および道徳が生じ、所有権が設定され、相続順位が確立したが、あらゆる私法と家族制度のすべての規則もここから派生したのであった。ついで、信仰が大きくなり、人々の結合もこれにならって大きくなった。人類はめいめいのあいだに共通の神があることを知るにしたがって、ますます大きな団体に結合する。家族内で発見され設定された諸規則が順次に支族や都市に適用されていった」
インド、ギリシア、およびエトルリアの伝説では、神々が社会法則を人類に啓示したといいます。社会法則は神々の所産であり、その神々は人間の信仰が生んだものだったのです。
第四章「都会」では、著者は都会について以下のように述べています。
「われわれが古代史家の著作をよんでまずおどろくことは、あらゆる都会が、たとえどんなにふるくても建設者の姓名と建設の日時とを知っていると主張することである。これはどの都会もその誕生を記念した神聖な儀式の思い出を無視できなかったためで、各都会は毎年犠牲奉献によって記念日をいわったのである。アテナイもローマと同様に、その誕生日をことほいだ」
第五章「都会建設者の崇拝。アエネアスの伝説」でも、著者は述べます。
「都会の建設者は、都会の存立を左右する宗教的行為を成就したものである。彼は永遠に聖火がもえつづくべき竈を設置し、祈祷と儀式によって神々を勧請して、あたらしい都へ永久に定住させたものである」
「おのおのの都会にとっては、その総説当時の追想ほど記憶にのこるものはなかった、紀元2世紀にパウサニアスがギリシアを訪問したとき、各都会は建設者の名をその家系と生涯のおもな事績とともに彼にじゃたることができた。この名と事績とは市民の記憶からきえなかった。それが宗教の一部であって、年ごとの神聖な儀式にさいして回想されたからである」
第六章「都市の神々」では、著者は以下のように述べています。
「古代にあっては、あらゆる社会の紐帯をなしたものが祭祀であったことをみすごしてはならない。家族の祭壇が一家の人々をその周囲に結合させたように、都市はおなじ守護神をもち、おなじ祭壇にむかって宗教的儀式をおこなう人々の集団であった」
「各都市はその都市だけに属する神々をもっていた。それは通常原始的な家族宗教の神々とおなじ性質のものであった。その名称も同様に『守護神(ラーレス)』、『家の神(ペナテース)』、『精霊(ゲニウス)』、『守霊(ダイモン)』、『神人(へロス)』などとよばれた。すべてこれらの名称のもとには、人間の霊魂が死によって神格化されていた」
ある神を専有する都会は、その神が他国人を保護することを喜ばず、また他国人の礼拝をも許しませんでした。著者は以下のように述べています。
「少数の聡明な人々をのぞいては、一般の古代人が神をもって全宇宙にはたらきをおよぼす唯一無二の存在だと考えていなかったことは、みのがせない事実である。彼らの無数の神々は、おのおのの小さな領域をもっていて、あるものは家族を、他のものは氏族を、別のものは都市を支配した。それは彼らのそれぞれの摂理に相応する世界であった。全人類にあまねき神については二、三の哲学者だけが察知できたにすぎない。エレウシスの神秘教は、もっとも奥義に徹した聡明なものにこそ、全人類の神を暫見させたかも知れないが、俗人は決してそのような神の存在を信じなかった。人々はながいあいだ神とは個人的に自分をまもる力であると考えていた。そして各人各集団は自分の神をもとうとのぞんだ」
古代都市は宗教都市であり、儀式都市でした。 さらに、著者は以下のように述べています。
「各都市は他国のどんな権力にも服従しない神官の団体をもっていた。ふたつの都市の神官のあいだには、なんの関係も交際もなく、また知識や儀式の交換もおこなわれなかった。ひとつの都会から他の都会へうつれば、そこにちがう神と教理と儀式とを見いだす。古代人も儀式書をもっていたが、ある都市の儀式書は他の都市のものとおなじではない。各都市にはそれぞれ祈祷や宗礼をしるした書物があったが、それは厳密にされ、他国人がそれを一瞥しても、自国の宗教と運命とを危険におとしいれると信じていた。こうして、宗教はまったく地方的で、各都市の市民のものであった。この言葉を古代の意味にもちいれば、各都市に特有のものだったのである。一般に、人々は自分の都市の神々しか知らず、ただその神々だけを崇拝した。アイスキュロスの悲劇で、一外国人がアルゴス人に『余は君の国の神々をおそれぬ。余はなにも彼らに負うところがない』と言っている言葉は、あらゆる人々のいえることであった」
第七章「都市の宗教」の第一節「公共の聖餐」の冒頭、著者は以下のように書いています。
「家の祭祀のおもな儀式が犠牲奉献とよぶ聖餐であったことは、まえにのべたとおりである。祭壇で調理した食物をくうことは、人が宗教的行為にあたえた最初の形式でもあったようにみえる。神と霊交しようとする欲求は、神を招待して分け前をささげるこの食事によってみたされたのであった。 都市の祭祀のおもな儀式も、また同様の性質をもつ聖餐であった。聖餐は守護の神々に敬意をあらわすために、すべての市民が共同でおこなわれなければならなかった。この公共の生産をいわう習慣は、ギリシア全土にあまねくおこなわれ、都市の禍福はこの儀式の成就にかかっていると信じられた」
これらの聖餐は『オデュッセイア』でも描かれ、アテナイ最古の伝説の中にもあらわれています。著者は以下のように述べています。
「その宗教的儀式がどんなものであるかは、食事のあいだにおこなわれた行事をみれば容易に理解できる。会食者はみな頭に冠をいただいたが、宗教上の厳粛な儀式の場合に、木の葉あるいは花の冠をかぶるのは古代の習慣であった。彼らは『おおくの花で美しく身をかざれば、ますます神の御心にかなう。しかし、冠をいただかずに生贄をささげれば、神は面をそむけたもう』といい、また、『冠は幸福な前兆の使者で、祈祷はこの冠を先ぶれとして神のもとへおくる』ともいった。会食者は、おなじ理由から、白色の衣を着用した。白色は古代人にとっては神聖な色で、神々をよろこばせるものであった」
第二節「祭典と暦法」では、以下のように述べられています。
「おのおのの都会は儀式によって建設され、その儀式は、古代人の考えでは、国家の神々を城壁のうちに定住させる効力をもっていたが、その効力は毎年祭典をいとなんで更新する必要があった。この祭典は生誕の日とよばれて、全市民がこぞっていわわなければならなかった。神聖なことはなにによらず祭典をもよおす機縁となった。都会の城郭をまつる祭があって、これを『アンブルバリア』といい、領土の境界をまつる祭があって、これを『アンバルヴァリア』といった。これらの日には、市民は白衣をまとい花冠をいただいて盛大な行列をつくり、祈祷をとなえながら都会や領土のうちをねりあるいた。先頭には数名の神官が生贄の動物をひいてすすみ、祭典のおわりにこれをほふって神にささげるのであった」
本書には、古代都市で行われた儀式についても紹介されています。 第三節「人別調査と潔斎式」には以下のように書かれています。
「都市の宗教のもっとも重要な儀式に、潔斎式というものがあった。これはアテナイでは毎年おこなわれ、ローマでは4年ごとにおこなわれた。この儀式の種々の行事やその名称は、この儀式が神に対して市民のおかした罪を消滅する効果のあったことをしめしている。実際、きわめて複雑な形式をもつこの宗教は、古代人にとっては恐怖の的であった。心の誠実とか意図の潔白とかいうことは大して問題ではなかった。宗教が無数の規定にもとづくこまかしい行事からなっていたから、人はつねになにかの手おち、怠慢あるいは過失をおかしはしなかったかと心配しなければならず、どれかの神の怒りや恨みをうけていないと確信することができなかった。それで、人の心をやすめるためには、罪をあがなう献祭が必要であった」
第四節「議会、元老院、裁判所、軍隊などでの宗教、凱旋式」では、古代都市で行われた凱旋式について以下のように書かれています。
「勝利のあとではつねに盛大な献祭をいとなんだが、これは凱旋式の起原である。ローマ人の凱旋式はよく知られているが、ギリシア人のあいだでも同様にさかんにおこなわれた。この習慣は勝利を都市の神々の功績に帰するという考えから生じた。戦いにさきだって、軍隊はアイスキュロスの著書にみる、つぎのような祈祷をささげた。―『われらが国土に鎮座し、これを所有したもう神々よ。もし戦いわれらにさいわいし、わが国土のすくわるるならば、神々の祭壇に雌羊の血をそそぎ、雄牛の生贄をまいらせ、槍をもってえたる戦利品を神々の広庭にたてまつることをちかわん』。この約束のために、凱旋将軍には犠牲奉献の義務があった。軍隊はその儀式をいとなむために都会にかえり、ながい行列をつくって『トリアンボス』とよぶ賛歌をうたいながら神殿におもむいた」
第八章「祭儀と年代記」では、著者は宗教について述べています。
「宗教という言葉の意味は、現在とはまったくちがっていた。この言葉によって、われわれは一連の教理と神についての教義とわれわれの内部や周囲にある神秘に対する信条とを意味するが、古代人にあっては、儀式、宗礼および外的な礼拝行為を意味した。教義はけっしておもきをおかれず、そのおもな部分は宗礼で、これが義務となって絶大の権力をふるった。宗教はみずから宗教をつくって、かえってそれに拘束された。そして極度に宗教をおそれて、これを推理することも論議することもできず、また正視することさえかなわなかった。神々や神人や死者は人間に物質的な礼拝を要求したので、人々は小心翼々として負担をはらい、そして神々の友情を維持しようとした。というよりむしろ、神々から敵視されないように心をくだいた」
このように、宗教においては教義よりも儀式が先にあったのです。
都市にとって、なによりも儀式や祭祀が最重要問題でした。それらが都市の歴史をつくっていったといっても過言ではありません。 著者は、以下のように述べています。
「どんな都市でも、歴史上の事実をわすれてもよいとは考えなかった。歴史にふくまれることはすべて祭祀と関連していたからである。実際に、歴史は都市建設の業によってはじまり、まず建設者の神聖な名をしるした。そして都市の神々すなわち守護の神人たちの伝説によって継続し、さらに、おのおのの祭祀の年代と起原と理由とをおしえ、難解な儀式をのこらず説明した。国家の神々がその力や慈悲や怒りをはっきりとしめした非凡のわざはすべて歴史に記入された。神官がたくみに凶兆をさけたり、神々の怒りをしずめたりしたときの儀式も記載された」
第九章「都市の政治。国王」では、以下のように書かれています。
「ホメロスとヴェルギリウスとはたえず神聖な儀式に従事していた国王についてかたっている。デモステネスによれば、アッティカの古代の王は都市の宗教が命ずるすべての犠牲奉献をみずからおこない、クセノフォンによれば、スパルタ王はラケダイモーンの宗教の首長であった。エトルリアの世襲族長は同時に行政官であり、軍事上の統領であり、かつ祭司長であった。 この事情はローマの国王についても同様である。伝説はつねに国王を神官としてしめしている。その第一のものはロムルスで、彼は『卜占の術に長じ』、宗教的儀式によって都会を建設した。その第二はヌマである。ティトゥス・リヴィウスによれば、彼は祭司の職務の大部分をおこなった。しかし、彼は後継者がしばしば戦争をおこなう必要から、かならずしもつねに犠牲奉献の世話をすることをゆるされない事態になることを予想して、国王がローマをはなれるときにその代役をつとめる祭官をもうけた。かようにして、ローマの神職は、古代の王権の放射物にほかならなかった」
これらの国王兼神官は宗教的儀式によって即位しました。 そして、ローマの行政官も儀式によって選ばれました。 第十章「行政官」では以下のように書かれています。
「行政官の選任に関する第一の原則は、キケロのいった『儀式によって指名さるべし』ということであった。選挙から数ヵ月をへて、もし儀式の一部が無視されたり、または十分におこなわれなかったりしたことを元老院にうったえでるものがあれば、元老院は執政官に退位を命じ、執政官はすなおにその命令にしたがった。こうした例はきわめておおい。その二、三の場合には、元老院が不適任なまたは邪意ある執政官を除外することを希望したためだとおもわれるのもあるが、大部分の場合は、これに反して、元老院が宗教上の配慮以外の動機をもっていたと考えることができない」
さらには、法律も儀式と深く関わっていました。 第十一章「法律」の冒頭には以下のように書かれています。
「ギリシア人とローマ人にあっては、インド人と同様に、法律ははじめ宗教の一部であった。都市のふるい法典は、法律上の規定と同時に礼拝式や祈祷をふくんだ集大成であった。所有権や相続権の法規が、犠牲奉献や墓や死者礼拝に関する規定とまじっていた。 王法と称して、ローマ最古の法典の現代にのこるものは、市民生活の関係を規定するとともに、祭祀のことにも関連している。ある法律は罪ある婦人が祭壇にちかづくことを禁じ、他のものは一定の料理を聖餐にもちいることを禁じ、またあるものは凱旋将軍が都会に帰還したときにおこなう宗教的儀式をさだめている。十二表法の法典はこれよりあとのものだが、葬儀に関する宗教上の儀式についてこまかい規定をのせている。ソロンの著作は同時に法典であり、憲法であり、儀式書であった。これは結婚の儀式や死者の礼拝とともに、犠牲奉献の順序や生贄の価格をもさだめている」
法律について、著者はさらに以下のように述べています。
「法律はながいあいだ成文であらわされなかった。そして、信仰や祈祷の方式とともに、父から子へつたえられた。それは家族あるいは都市の竈にまつわって永続した神聖な伝統であった。人がこれを成文にしたとき、法律は儀式書という神聖な書物のうちにかきいれられて、祈祷文や儀式の次第と雑居した。ヴァロはトゥスクルム市のふるい法律を引用しているが、それをその都市の儀式書のなかでよんだといっている。ハリカルナススのディオ二シオスはローマ最古の文書をしらべた人であるが、ローマでは、十大官の時代以前に成文化されたわずかの法律は、宗教上の書物のなかに見いだされたといっている。のちには、法律も儀式書と分離して別にかかれるようになったが、習慣上神殿のうちにおかれて、神官が保管した」
これらの法律は、成文であるとないとにかかわらず、きわめて短い条文におさめられていたそうです。形式からいえば、モーセの書の唱句や『マヌの法典』の「スロカ」の形式と比較できるといいます、その条文は明らかに韻を踏んでいたとか。アリストテレスによれば、法律は成文となる前には朗誦されていました。このことは言語の中にも痕跡をとどめており、ギリシア人は法律を「歌(ノモイ)」、ローマ人は「詩句(カルミナ)」と呼びました。
第十五章「都市のあいだの関係、戦争、平和、神々の結盟」では、平和条約を結ぶときにも儀式が重要な役割を果したことが述べられています。
「平和条約をむすぶためには、宗教的な儀式を必要とした。『イリアス』のなかにはすでにつぎのようなことがしるされている。―『神聖な軍使は神々への誓約のしるしとさだめられた供物、すなわち小羊と葡萄酒とを神前にそなえる。軍の長官は手を生贄のうえへおいて、神々にかたり、約束をおこなう。そののち、彼は生贄をほふって灌祭の酒をそそぐ。そのあいだに、軍隊は『不滅なる神々よ、この生贄が刃のもとにたおれたるごとく、なんびとにても誓約にそむくものの頭をうちくだきたまえ』という一定した祈祷の言葉をとなえる』。同様の儀式はギリシアの全歴史を通じて存続した。ツキディデスの時代にも、条約は犠牲奉献によってむすばれた。人民の統領は片手をほふられた生贄のうえにおいて一定した祈祷の言葉をのべ、神々に誓約をする。各国の国民はそれぞれ自分の神々に祈願し、固有の誓言をとなえた。神々によせるこの祈祷と誓約は条約をむすぶ当事者を拘束した。ギリシア人は『条約に署名する』とはいわずに、『誓約の生贄をころす』または『灌祭をいとなむ』といい、現代語で条約署名者というものをあらわそうとするときには、古代の歴史家は『これは灌祭をおこなえるものの名なり』といった」
第十七章「ローマ人、アテナイ人」には以下のように書かれています。
「われわれはローマ人の生活で宗教がどんな地位をしめるかを研究しなければならない。その家は現代の神殿にひとしかった。彼らはそこに自分の祭祀と神々とを見いだした。竈も神であり、壁も入口も神であり、畑をかこむ境界も神であった。墓は祭壇で、祖先は神格をおびる存在であった。 彼らの日々の行為はどれもみな儀式で、一日の全部が宗教に属していた。朝な夕なに竈神にいのり、守護神にいのり、祖先にいのった。わが家への出入ごとに、これらのものに祈祷をささげた。食事も家の神々とともにする宗教的行為であった。子供の出生、家族宗教への導入、元服、結婚、およびこれらの事件の周年祭は、すべてみな礼拝の厳粛な行為であった」
これを読んで「ローマ人は日本人に似ている」と思わない日本人はいないでしょう。まるで日本民俗学の本を読んでいるようです。本書の「薦辞」で法学者の中川善之助が「読んで行くうちに、これは是非日本でも広く紹介さるべき名著であると熱々思った。古代のギリシアやローマや印度の人たちが考えたり信じていたりしていたことの中には如何にも吾々と似ているものが多いのである」と書いたのも納得できます。
最後は、第五編「都市政体の消滅」です。第三章「キリスト教が政治の諸条件にあたえた変革」の冒頭には「キリスト教の勝利は古代の終末を画するものである」という一文が置かれ著者は以下のように述べています。
「キリスト教の出現とともに、宗教的感情はまた往時の隆盛をとりもどしたが、そればかりではなく、従来よりも高尚で、物質的性質のすくないものとなった。昔の人々は人間の霊魂や自然の偉力を神としたが、いまや神は、その本質において、人間の性質および自然の世界とはまったく無関係のものであると考えられはじめた。神は画然と可見の自然のそとに、そしてまたそのうえにおかれた。従来、人はめいめい勝手に自分の神をつくり、家族および都市と同数の神が存在したが、いまや神は唯一のもの、無限なもの、普遍的なものとしてあらわれ、その唯一の神だけが世界に生命をあたえ、人の心にある崇拝の欲求をみたすべきものと考えられはじめた」
続けて、著者は以下のように述べています。
「古代のギリシア・イタリアの人民にあっては、宗教はほとんど宗礼の総合にほかならなかった。それはなんの意味もみとめすにくりかえした一連の儀式であり、言葉がふるくなってなんのことやらわからないものさえある一団の方式であり、時代から時代へつたえられ、単に古代のものであるという理由だけで神聖視された伝統にすぎなかった。しかし、あたらしい宗教は、整然たる教義の集成で、信仰心に対する大きな対象となった。これは従前のように外形的なものではなく、主として人の心のうちに居をしめた。物質的ではなく、精神的であった。キリスト教は崇拝ということの性質と形態とを一変した。すなわち、人々は神に飲食物をささげることをやめ、祈祷もまた呪文という方式から脱出して、信仰上の一行為となり、敬虔なねがいとなった。人々の心と神とはいままでとちがった関係をむすぶようになって、従来の神々に対する畏怖は、唯一の神に対する親愛の情とかわった」
さらに、著者はキリスト教の神について、以下のように述べます。
「この神にとっては、もはや外国人というものは存在しなかった。たとえ外国人が参拝ないし列席しても、神殿や犠牲献祭をけがすわけではなかった。神殿はいやしくも神を信ずるものならばだれにでも開放された。また宗教そのものが世襲の財産ではなくなったので、神職も世襲ではなくなった。祭祀ももはや秘密とされず、儀式、祈祷、教義などもかくされるようなことがなくなった。いや、それどころでなく、かえって宗教教育がおこなわれ、単にもとめるものにあたえられたばかりでなく、すすんで一般のものに伝授され、非常に遠い土地にいるものや、きわめて冷淡なものにまでも積極的にときおよぼされた。布教の精神が従来の排他的な法則にとってかわったのである」
そして、この巨大なスケールを持つ本書は以下の一文で終わっています。
「このようにして、家族は家族宗教をうしなったために、組織と律法とを変更したが、これとひとしく、国家も公式の宗教をうばわれたために、人民を統御する種々の規則を永久に変更するようになった。われわれの研究は古代の政治と近代の政治とをわけるこの限界でとどまらなければならない。以上、信仰の歴史についてのべてきたが、信仰が確立して、人類社会が構成され、信仰の変化にともなって、社会に一連の革命がおこり、信仰が消滅して、社会は相貌を一変した。古代を律する法則は、要するにこのようなものであった」
この大著を読んで、わたしが得たものはあまりにも大きいです。『儀式論』執筆のための構想も、本書を読んだことで、ようやくまとまりました。この文章も文字数が約2万3500字となっており、読書館の書評においても過去最大となりました。
