- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2016.04.04
次回作『儀式論』(弘文堂)の参考文献として、『呪術・科学・宗教・神話』マリノフスキー著、宮武公夫・高橋厳根訳(人文書院)を読みました。著者のブロニスラフ・マリノフスキーは、ポーランド出身のイギリスの人類学者です。本書は1948年に発表された論文を集めたもので、日本版は1997年に刊行されています。翻訳は、前半部の「呪術・科学・宗教」を高橋厳根氏が、後半部の「未開心理における神話」を宮武公夫氏が担当しました。
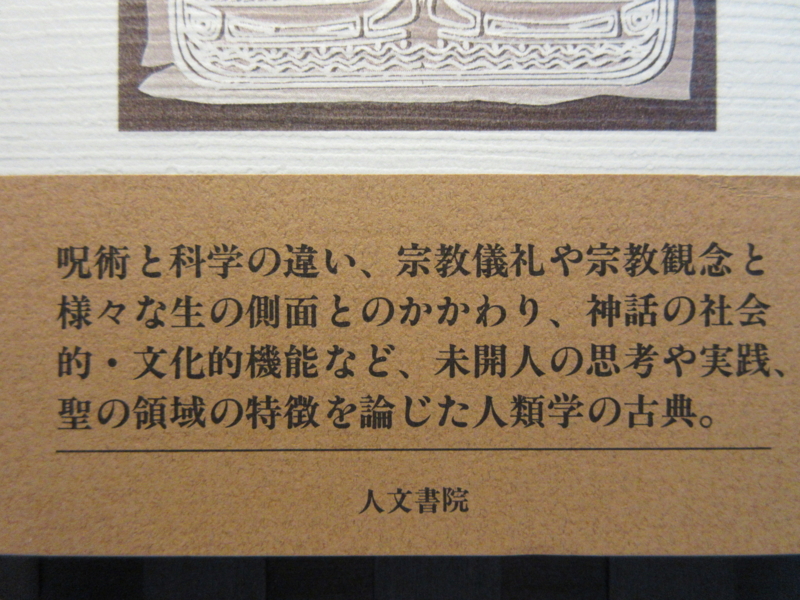 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、以下のように書かれています。 「呪術と科学の違い、宗教儀礼や宗教観念と様々な生の側面とのかかわり、神話の社会的・文化的機能など、未開人の思考や実践、聖の領域の特徴を論じた人類学の古典」
著者は1884年、オーストリア=ハンガリー帝国領だったクラクフ大公国の首都クラクフ(現在のポーランド)に生まれました。父は貴族でありスラヴ語の教授でしたが、著者が幼い頃に死亡し、母との2人暮らしを送りました。ヤギェウォ大学で数学と物理学を専攻し、1908年に学位を取得。その後ライプツィヒ大学で2年ほど学び、そこでヴィルヘルム・ヴントの民族心理学に影響を受けました。人類学に関心を抱いた著者は、この読書館でも紹介した『初版 金枝篇』の著者であるジェームズ・フレイザーなどの研究を知り、当時人類学でもっとも有名だったイギリスへの渡航を決意。10年にロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)で人類学を研究しました。
13年、著者は、アボリジニについての文献研究を『オーストラリア・アボリジニの家族』として発表します。翌14年には、作曲家のカロル・シマノフスキと並んで幼少の頃からの親友の1人であったポーランドの作家スタニスワフ・イグナツィ・ヴィトキェヴィチとともにオーストラリアを旅行するが、同年に第一次世界大戦が勃発、イギリスはドイツに宣戦布告しました。オーストリア国籍だった著者はイギリス領内で敵国人扱いされ、出国が不可能となりました。しかし、パプアニューギニアに行くことは可能でした。著者は、最初にマイルー島、次にニューギニア島東沖にあるトロブリアンド諸島のフィールドワークに取り掛かります。その後、長期にわたって現地の人々と行動を共にし、その生活の詳細な観察を行うこととなりました。こうして、人類学研究に初めて参与観察と呼ばれる研究手法が導入されたのです。
19年、著者はメルボルンへ帰り、化学者の娘だったエルシー・ロザリン・メーソンと結婚しました。24年からはロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで人類学の講座を取得し、27年には主任教授に就任します。その後、第二次世界大戦が勃発すると、アメリカ合衆国に定住し、イェール大学の客員教授となりました。34年、『未開社会の構造と機能』の著者であるラドクリフ=ブラウンら若い人類学者たちとアフリカ総合研究プロジェクトを立ち上げ、アフリカの南部と東部にフィールドワークを兼ねた調査旅行に向かいます。41年から42年までメキシコのオアハカ州の調査旅行に出掛けました。そして、42年にイェール大学のあるコネチカット州南部の街ニューヘイブンで死去しました。
本書の「目次」は、以下のようになっています。
序(ロバート・レッドフィールド)
呪術・科学・宗教
第一章 未開人とその宗教
第二章 周囲の環境に対する人間の理性的支配
第三章 未開人の信仰と崇拝に見られる生と死と運命
1 宗教の創造的行為
2 未開人の生にとっての神
3 人間の自然に対する選択的関心
4 死と集団の再統合
第四章 未開的崇拝の公約・部族的性格
1 儀礼と呪文
2 呪術の伝統
3 マナと呪術の効力
4 呪術と経験
5 呪術と科学
6 呪術と宗教
未開心理における神話
ジェームズ・フレーザー卿への献辞
第一章 生活における神話の役割
第二章 起源神話
第三章 死と輪廻の神話
第四章 呪術神話
第五章 結論
「訳者あとがき」
「序」で、人類学者のロバート・レッドフィールドはその冒頭を以下のように書きだしています。
「今日ブロニスラフ・マリノフスキーほど見事に、人間が生きるという血の通った現実と科学の行う冷徹な抽象とを同じ一つの理解の枠組の中に収めてしまう者はいない。彼が書く一行一行が、私たちとは縁遠いはずの人びとのことをまるで隣人か兄弟であるかのように理解するということと、人類一般についての概念的。理論的理解とをつなげるのに、欠かすことのできない結び目となっている」 さらに、レッドフィールドは次のように述べています。 「マリノフスキーを読む者は、宗教・呪術や科学・儀礼や神話などについての一連の概念を手にし、トロブリアント諸島の人びとに鮮烈な印象を覚え理解を深めながら、そこでの生のありかに魅了されていくのだ」
「呪術・科学・宗教」の第三章「未開人の信仰と崇拝に見られる生と死と運命」の1「宗教の創造的行為」で、著者は儀式を行う目的について、以下のように述べています。
「誕生後の儀式、例えば新生児の披露や祝賀の宴会などには別に目的はない。それはある目的に対する手段ではなく、目的そのものである。それは母親や父親、親族、はたまた共同体全員の感情を表現していて、この儀式が先取りをしているような未来の出来事があるわけではなく、それをもたらそうとか避けようとかいう意図があるわけでもない。こうした違いはとりあえず、呪術と宗教を区別する目印になるだろう。呪術的行為ではその根底にある考えや狙いが常に明確で率直であり確固としているのに対して、宗教的儀式では何らかの目的がそれに続いて起こる出来事に託されているわけではない。社会を研究する者にとって可能なのは、ただ機能、つまりある行為の社会的な存在理由を確定することだけである。未開人は常に呪術的な儀礼の目的を明確に述べることができるが、宗教的儀式については、それを行うのはそれを説明するという神話があるのだと言うことだろう」
著者はイニシエーション儀礼を取り上げ、その主な機能について、「この儀式は、未開社会での伝統の並ぶものなき力と価値の儀礼的・演劇的な表現であり、また、この力と価値を各世代の人びとの心に焼き付けるのに役立つと同時に、部族の知恵を伝え、伝統の連続性を保証し、部族の結束を維持する極めて有効な手段である」と述べています。
また、著者はイニシエーションについて以下のように述べます。
「イニシエーションは、典型的な宗教的行為である。そして、今や儀式とその目的は一体であり、その目的が行為の成就そのものに含まれていることがよくわかるだろう。と同時に、社会の中でのその行為の機能を、その集団と文化に測り知れない価値を与える精神的な習慣と社会的な慣例を創造するという点に見いだすことができるのである」
さらに、著者は結婚式について以下のように述べています。
「宗教的儀式のもう1つの型である結婚の儀礼も、それ自体が目的であって、一時的な生物学的事実に加えて、超自然的に承認された絆(愛情、経済的なまとまり、子供の出産と養育をするうえでの生涯続くパートナーシップを目指した男と女の結びつき)を創り出す。この結びつき(一夫一婦婚)は人間の社会に常に存在し続けてきた―とは、近年の人類学が『乱婚』や『集団婚』のような古びた幻想的な仮説に対抗して説くところである。一夫一婦婚に価値と聖性を付与することによって、宗教は人間の文化にもう1つの可能性を開いた」
2「未開人の生にとっての神」では、儀式における食というものに注目し、著者は以下のように述べます。
「食べることは未開人にとって、礼儀作法や特別な規則や禁則、そして私たちにはわからないほど広範な感情的緊張を伴った行為だということである。食料が途切れることなく続いていくか、あるいはそれが全体的に減少することを避けるための食の呪術を別にしても(そして、ここでは、食物の獲得に関する様々な形式の呪術のことには全く立ち入らないが)、食物は明確な宗教的性格をもつ儀式でも顕著な役割を果たしているのである」
続いて、著者は儀式における食について以下のように述べます。
「儀礼的性格をもつ初物の奉納や収穫の儀式、季節ごとの大祭では、収穫物は積み上げられて展示され何らかの方法で神聖化されるが、こうした儀式は農耕社会の人びとの間では重要な役割を担っている。狩猟民や漁労民は、大きな収穫や漁や猟の解禁を祝うために祝宴や儀式を催すが、そこでは食物は儀礼的にとり扱われ、それによって動物たちや魚たちの気持ちを宥めたり、それに対して崇拝の念を表したりするのである。このような行為はどれも、食物に大きな価値を見いだす共同体の喜びを表現していて、宗教はこの行為を通じて人間の日頃の食事に対する敬意の態度を神聖なものにするのである」
著者はさらに、未開人にとっての食について以下のように述べます。
「食物は未開人にとって周囲の世界からの恩恵の徴であり、豊饒が神の存在の最初で最も基本的な暗示なのだから、未開人は供犠を通じて精霊や神々と食物を分かち合うことによって、既に感じていながらもそれが何であるかよくはわからない神の恵みの力を、彼らと分かち合うことになる。このように、未開社会では供犠の捧げ物の起源は贈与の心理に求めることができ、贈与物は神の恵みである余剰を通じた霊的交流に対して贈られるのである」
続いて、著者は聖餐について以下のように述べます。
「聖餐も、同じ精神的態度の別の表現であるにすぎず、それは生を維持し新たにする行為―すなわち、食べるという行為そのものという、最も適切な仕方で行われる。しかし、この儀礼は未開人の間では極めて稀であるようで、聖餐の秘蹟は通常、食の未開真理がもはや見られない段階の文化に浸透していて、そこでは違った象徴的・神秘的意味を獲得している。おそらく、十分確認済みで、ある程度細部まで知られている聖餐の唯一の事例は、オーストラリア中央部に住む部族のいわゆる『トーテム的秘蹟』であり、これにはさらい特別な解釈を必要とするだろう」
4「死と集団の再統合」では、服喪について以下のように述べられています。
「死の直後の服喪は、死体を囲んで行われる。死体は恐れられたり避けられたりするどころか、ふつう敬意のこもった関心の的となる。死者を抱きかかえるなど、その人の敬意を試したりするような儀礼的な決まりがあることも少なくない。時には、死体は座った人びとの膝に抱えられて、撫でられたり、抱き締められたりする。同時に、こうした行為は通常、危険かつとてもいやなことと考えられていて、それをする者がある程度犠牲を払って初めて達成される義務である。しばらくすると、死体に然るべき処置を講じなくてはならない。剥き出しの、あるいは閉じられた墓に土葬する、穴や何かの台、木のうろ、荒野の地面の上などに放置する、火葬する、カヌーに乗せて水葬にする―こうした仕方は、死体処置のよくある方法である」
著者は、ここから以下のような論点を導いています。
「未開人には矛盾した二重の性向があり、一方では死体を保存し、それが傷つかないようにしたりその一部をとって置いたりする。そして他方では、それらを始末し、目の届かない所へ追いやり完全に抹殺したいという欲望があるのである。ミイラ化と火葬はそれぞれ、この二重の性向を表す両極端の表現である。ミイラ化や火葬、あるいはいかなる媒介的な手段も、それが信仰の気まぐれによって決定されたとか、伝播と接触だけの仕組みによって普遍性を得た、しかじかの文化がもつ歴史的様相であるなどと見なすことはできない。と言うのは、こうした習慣には明らかに、後に遺された親族や友人、恋人の基本的な態度である、死者が残したものへの追慕や死がもたらしたおぞましい変化に対する嫌悪や恐怖の念が表現されているからである」
また、未開人の死に対する態度について、著者は以下のように述べます。
「未開人は極度に死を恐れるが、それはおそらく人間と動物とに共通の何らかの深層に根ざした本能の結果であろう。彼はそれを終わりとして認識することを望まず、完全な停止や無化の観念に向き合うことができない。未開人にとって魂やその存在の観念は身近なものであり、タイラーによって発見されたような事例がそれを示している。人間はそれを手にして魂の連続性と死後の生を信じるに至り、そのことで慰められる。だが、この信仰も死の影に常に潜んでいる希望と恐れの両極をもつ複雑な感情の働きの中では、そのままであり続けるわけにはいかない」
続けて、著者は以下のように述べています。
「希望をささやく慰めの声や、不滅へのあくなき欲望、自分自身の無化に向き合うことの困難(場合によっては、それはほとんど不可能と言ってもよい)に対して、他方では執拗で恐ろしい予感がある。感覚による証明、すなわち、死体のおぞましい腐敗と見た目に明らかな人格の消失―このような身の毛もよだつ恐怖に本能的に促されて、人間は分化のどの段階においても何らかの無化の観念、何らかの隠れた恐れや不吉な予感に脅かされているようだ。そして、ここ、この感情的な力の働き、この生と最終的な死との究極的な矛盾の中に宗教が入り込み、肯定的な信条や慰めとなるような考え、不滅、肉体とは独立した魂の存在、死後の生の持続に対する追悼とそれとの霊的交流、先祖の霊への崇拝では、宗教はこうした人を救う信仰に実体と形式を与えるのだ」
第四章「未開的崇拝の公約・部族的性格」の2「未開信仰の道徳的効力」では、とりわけ宗教的な行為である死の儀礼に言及し、著者は「ここでは宗教への希求は個人的危機、つまり人間なら誰しも恐れを感じる死から生じる」として、さらに次のように述べています。
「個人が信仰と儀礼に慰めを見い出すのは聖糧の秘蹟、つまり人生の旅の最終段階で与えられる最後の慰めの他にはない―そして、この慰めはあらゆる未開宗教でほとんど普遍的に見られる行為である。こうした行為が向けられるのは、あの圧倒的な恐怖、人の心をむしばむ疑念であって、未開人がそこから自由でないのは文明人と同じことである。こうした行為は、死後の世界というものがあってそれは現在の生よりも悪いものではなく、それどころかむしろ良いものであるだろうという希望を確かなものにする」
続けて、著者は「儀礼的なもの」について、以下のように述べます。
「全て儀礼的なものは、この信仰、死にゆく者が必要としその最大の葛藤の中で得られる最大の慰めとなる境地を表現している。そして、この肯定的態度の背後には数の重みと厳粛な儀礼の華やかさがある。と言うのも、全ての未開社会では、既に見たように、死を契機として共同体全体が集まって死にゆく者の世話をし、その人に対する様々な義務を果たすからである。こうした義務はもちろん、死にゆく者とのいかなる感情的な共感を生むものではない―死者との共感などただ単に、破壊的なパニックにつながるだけだ。逆に、一連の儀礼的行為は死にゆく者を襲うかもしれない最も激烈な感情と対立したり矛盾したりすることがある。事実、集団の行為は全体として救いと不滅の希望を表現している。と言うのはつまり、それは個人の中で葛藤する様々な感情のうちの唯一つを表現したものにすぎないのだ」
さらに著者は、宗教的儀式について以下のように述べます。
「宗教は生きた行為に基づくもので、そうした行為全てが協力関係にある集団の公的な関心のありかたを決定しているのだから、あらゆる宗教的儀式は公的なものであり集団によって行わなければならない。人生の転換期の全てを含む重要な活動は未開社会の公的な関心を呼び起こし、呪術的・宗教的を問わずあらゆる儀式が用意されている。何かの活動のために集まるか、あるいは転換期を画す出来事に集合した人たちと同じ社会集団が、儀礼的行為を執り行う。しかしながら、こういった抽象的な議論は、それがいくら正確であるからと言っても、ここまでの具体的な記述から得てきたような宗教的行為の公的な実行の仕組みについて、本当の洞察を加えるのを可能にしてくれるわけではないだろう」
第五章「呪術の技術と信仰の力」の2「呪術の伝統」では、著者は以下のように述べています。
「呪術はその現れが人間的であるばかりでなく、その目的となる主題も人間的である。それは主として、猟や畑仕事、漁、交易、恋愛、病気、死といった人間の活動や状態と関連している。それが向けられるのは自然というよりも、人間の自然に対する関係と自然に影響を与える人間の活動である。さらに、呪術の効果は普通、呪力に影響された自然の産物としてではなく、何かを特別の呪術的なもの、自然が生み出すことができずに呪術の力だけがもたらすことのできる何かとして伝えられる。重篤に陥った病い、情熱的に燃え上がる恋愛、儀礼的交換への欲望などの人間の身体と精神に現れる現象は、呪文と儀礼が生み出したものである。だから呪術は自然の観察やその法則に関する知識に由来するものではなく、人間が原初の時からもっていたもので、ただ伝統だけを通じて伝えられ人間の望む結果をもたらす自律的な力を肯定するのだ」
6「呪術と宗教」では、呪術と宗教の違いについて、以下のように述べます。
「何が呪術と宗教の違いなのだろうか。私たちの立場からすれば、そこには非常にはっきりとした具体的な違いがある。私たちの定義によれば、聖の領域の内部では呪術は後に続くと期待される特定の目的に対する手段以外の何物でもない行為からなる実用的な技術である。一方、宗教はそれ自体が目的の充足であるような自己完結的な行為の集まりである。さらに、この違いをもっと深い層にまで辿ることができる。呪術という実用的な技術は限界をもち制約のある方法を備えていて、その中で呪文、儀礼、パフォーマーの体調が、お決まりの陳腐な三角関係を形作っている」
続けて、著者は以下のように述べています。
「宗教は、複雑な諸相や様々な目的を抱えながら呪術のような単純な方法はもたず、その統一性を見ることができるのはその行為の形でも、あるいはその主題の統一性ですらなく、むしろそれが満たす機能や信仰と儀礼の価値である。さらに、呪術の信仰はその単調な実際的な性質に見合って極めて単純である。それはいつも、ある特定の効果を特定の呪文や儀礼によって引き起こす人間の力の肯定である。他方、宗教には信仰の超自然的世界の全てがある。数多くの精霊や悪霊、トーテムや守護精霊、部族神の恵みの力、未来の生の幻視は、未開人にとって超自然という第二の現実を生み出している。宗教の神話はまた、はるかに多様で複雑であるとともに創造的である。それは通常、信仰の様々な教義を中心とし、それを宇宙起原論や文化英雄譚、神々を半神たちの偉業の叙述へと発展させるのである。呪術でも神話は重要であるが、それは人間の原初の時代の達成を繰り返し自慢するものである」
続けて、呪術について、著者は以下のように述べます。
「特定の目的に対する特定の技術である呪術は、そのうちのどの形態をとってみてもかつて人間の所有となったものであり、世代から世代への直接的な継承関係を通じて伝えられる必要があった。それは原初の時代から専門家たちの手に委ねられていて、人類最初の職業は呪術師や妖術師である。他方、未開状態の宗教は全てを含むものであり、そこでは誰もが等しく積極的な役割を担っている」
さらに、著者は以下のように述べています。
「呪術と宗教のもう1つの違いは、妖術での黒と白の働きであるが、未開段階の宗教は善と悪、恵みの力と災いの力の間にほとんど違いがない。この2つの力の対立が直接的な量的な結果を目指す呪術の実際的な性格によるものであるのに対して、未開宗教は本質的に道徳的でありながら、運命のいたずらによる癒し難い出来事や超自然的な力や存在を扱う必要に迫られているため、人間がしたことの解決はそこには含まれていない。怖れがまず最初に宇宙に神を創ったという格言は、人類学的視点から見れば明らかに真実ではない」
そして、呪術について、著者は以下のように述べるのでした。
「呪術は未開人に数多くの既成の儀礼的な行為や信仰を提供し、それとともにあらゆる重要な仕事や転換期となる状況での危険な落差を埋めるのに役立つような確実な精神的、あるいは実際的な技術を与える。そのおかげで、人間は自信をもって重要な任務を果たし、怒りの衝動、憎しみの苦悩、報われない恋や絶望、不安に対する冷静さと精神的安定を維持することができる。呪術の機能は、人間の楽観主義を儀礼化し、恐怖に対する希望の勝利によって信仰を高めることにある。呪術が表現するのは、人間にとっての、疑念に対する自信の、動揺に対する沈着の、悲観主義に対する楽観主義のより大きな価値なのである」
著者は、呪術の効力の信仰に関する3つの要素について紹介しています。
1・音声的な効果。風のうねりや雷の轟き、荒れ狂う海、様々な動物の鳴き声のような自然界の音の模倣。
2.欲望の対象となったものを呼び覚まし、特定し、あるいはそれに対して命令を下すための言葉の使用。
3.神話のなかの、呪術を与えてくれた先祖や文化英雄への言及。
第五章「結論」で、神話について、著者は以下のように述べます。
「神話は明らかに物語(narative)でもあり、従って文学的側面をもっている。その側面は、ほとんどの学者によって過度に強調されてきたが、しかしまた、完全に無視されるべきものではない。神話は叙事詩や、ロマンスや、悲劇の萌芽を含んでいる。そして、神話はそれらの中で、住民の間の創造的な天才や、文明的ともいうべき意識的芸術によって描かれる。これまで、いくつかの神話はほとんど叙述的表現を持たず、劇的な出来事を含まない、乾燥した簡潔な記述に過ぎないことを見てきた。またほかの神話は、愛の神話や、カヌー呪術や外洋航海の神話のように、非常に劇的な物語である。もし紙数に余裕があるのなら、鬼を殺し、母親の仇を打ち、幾つもの文化的課題を成し遂げる。文化英雄ツダヴァの長く手の込んだ冒険談を繰り返すことが出来るのだが」
続けて、著者は神話の文化的機能について以下のように述べるのでした。
「それらの物語を比較すれば、なぜ、ある形式の神話が文学的な入念さをまとい、他のものは芸術的に不毛なまま留まっているかを示すことができるかもしれない。単なる社会的優位性や、法的資格や、リネージや地域的要求の弁護は、人間感情の領域の奥深くまでは導いてくれないし、そのことによって、文学的価値の要素を欠いているのだ。他方、呪術や宗教における信仰は、人間の最も深い欲望や、恐怖と希望や、情熱や感傷と深く結びついている。愛と死の神話、不死性の喪失や、過ぎ去った黄金時代と楽園からの追放の物語、近親相姦や邪術の神話などは、悲劇や、叙事詩や、ロマンティックな物語といった芸術的形式に関与する真の要求と共に働いているのだ。信仰との密接な関係を説明し、儀礼と伝統との親密な関係を明らかにする」
