- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2016.05.03
5月3日は「憲法記念日」ですね。
こんなことを書くといろんな人から怒られそうですが、わたしは日本国憲法にあまり関心がありません。憲法よりも神話に関心があります。執筆中の『儀式論』の中に「神話と儀式」という一章を設けているからです。というわけで、『神話と宗教』W・F・オットー著、辻村誠三訳(筑摩書房)を読みました。「古代ギリシャ宗教の精神」というサブタイトルがついています。
本書はローヴォルツ・ドイツ百科叢書の第15巻として、1957年に刊行されました。原題は《Theophania》で、「神の顕現」を意味するギリシャ語です。デルフォイにはその名の祭りがあり、アポロンその他の神の像が開帳されたといいます。日本語版は1966年に刊行されました。
著者のワルター・フリードリヒ・オットーはドイツの古典文献学者で、『ギリシャの神々』などの著書があります。1874年チュービンゲン近郊のヘッヒンゲンに生まれ、1958年に84歳をもってチュービンゲンに没しました。ギリシャ・ラテンの古典文献の第一人者として広く認められましたが、20世紀を代表する神話学者であるカール・ケレーニイは「オットーはニーチェとともに、文献学者でありながら、ドイツ哲学史の上に確固たる地位を要求しうる思想家でもあった」と述べています。

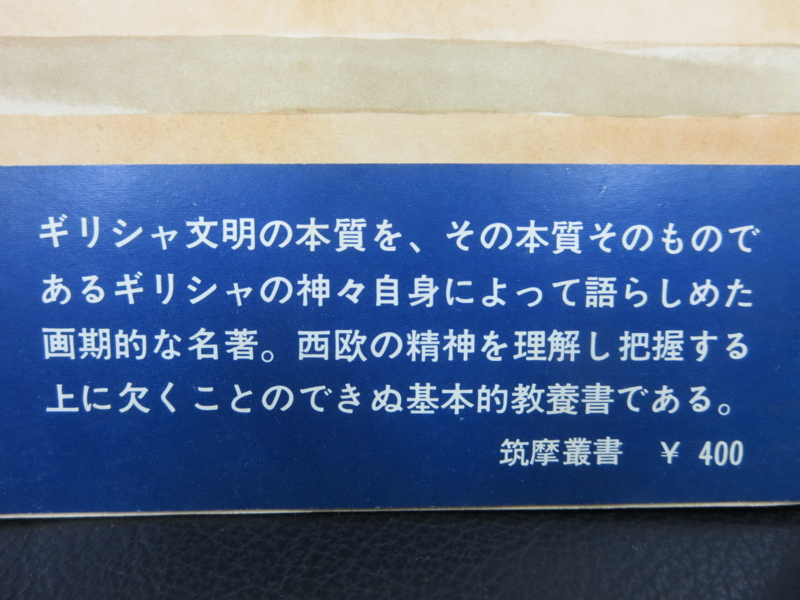 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、以下のように書かれています。
「ギリシャ文明の本質を、その本質そのものであるギリシャの神々自身によって語らしめた画期的な名著。西欧の精神を理解し把握する上に欠くことのできぬ基本的教養書である」
本書は序章、第一章、第二章から構成されていますが、重要なことはほとんど序章で述べられています。その序章の最初には「ギリシャの神々は今のわれわれにはもう関わりを持たないのだろうか」として、冒頭に以下のように書かれています。
「われわれはギリシャ人の建築、彫刻、文学、哲学、科学など彼らの残した偉大な作品をほめたたえる。ギリシャ人はヨーロッパ精神の確立者であり、ヨーロッパ精神は昔から、その決定性の度合においては大小さまざまなルネサンスによって、くりかえしギリシャ人の許にたち返ろうとしたことをわれわれは知っている」
続いて、著者は以下のようにギリシャ人の偉大さについて述べています。
「ギリシャ人が殆どあらゆる分野において、凌駕しがたきものを、すべての時代に妥当する模範的なものを、独自の仕方で創造したことをわれわれは認める。ほんのいくたりかの名をあげてみても、ホメーロス、ピンダロス、アイスキュロスとソポクレス、ペイディアスとプラクシテレス、これらは今のわれわれにとっても第1級と認められる人物である。ホメーロスの叙事詩を読むとき、ホメーロスはわれわれのために書いたのではなかろうかとさえ思われる。ギリシャの神々の像や神殿の前にたたずむとき、われわれは大きな感動におそわれる。ギリシャ悲劇の畏るべき出来事をたどるとき、われわれは震撼を覚える」
しかし、続けて著者は以下のように述べるのでした。
「だが、神々そのものはわれわれにとってどうであろうか。諸々の立像や神殿がその存在を証している神々、彼等の精神がホメーロスの詩全体をくまなく統べている神々、ピンダロスの歌がたたえあげる神々、アイスキュロスとソポクレスの悲劇のなかで人間的現存在に基準と目標とを与えている神々、このような神々そのものは、もう今のわれわれには関わりを持たないなどということがはたしてありうるだろうか」
「神的なものは経験によってのみ知られ得る」では、著者は以下のように述べています。
「神は発明されうるものでも、考案されうるものでもなく、また表象されうるものでもなく、ただ経験によって知りうるだけだというのが、それである。
神的なものはそれぞれの民族に、それぞれの仕方で現われ、彼らの現存在に形相(Gestalt)を与えた。こうしてはじめて各民族が、それぞれ然るべきものとなりえたのである。だからギリシャ人も彼らに固有の神経験を受け取ったにちがいない。われわれは彼らの作品を高く評価しているのだから、そのギリシャ人に対して神的なものがどんな現われ方をしたか、と問うことはわれわれにとってなおさら重要なことにちがいない」
「ギリシャの神々の世界に対する軽蔑は何に由来するのだろうか」では、著者は以下のように述べています。
「古代ギリシャの神々の世界は、学問的には熱心に研究されている。だがそれは骨董的関心にすぎないのであって、骨董品以上の意味と価値とを有するものではないだろうか、という具合には人々は考えようとしない。過去のすべての大いなるものの常として、今のわれわれにもおそらく関わりを持ちうるものではなかろうか、というようには考えない。それほどに古代ギリシャの神神が軽んぜられるのはなぜだろうか」
その疑問に対する理由について、著者は以下のように述べます。
「その第1の理由は、いうまでもなく、それ以前のすべての宗教がもっていた寛容を捨てて、自分だけが真理であることを標榜するような宗教が勝利をおさめたことにある。その結果、ギリシャとローマの宗教をはじめとして、それまでのヨーロッパに行なわれていたその他の一切の宗教に属するもろもろの考えは、ただただ虚偽で破棄すべきものとされた」
「神々についての間違った解釈―粗野な誤謬の帰結」では、神話的的宗教について以下のように述べています。
「神話的宗教とは多神教のことである。多神教は神々の多数存在、此岸性、具象性、人間との類似性などのために、キリスト教(あるいはユダヤ教、回教)に育まれた人々にとって、唯一存在、超越性、全能、全知、至善としての真の神に対する感覚を全く欠くように思われている。それと共に、立法者、裁き手、贖罪者に対する宗教的に真摯な畏敬の念も、また欠けているように思われている。このことは、非常に魅惑的な形相をもつギリシャのオリュンポス諸神に、まず妥当する」
オリュンポスの神々は「神」と呼ぶにはあまりにも地上的にすぎるとして、著者は以下のように述べます。
「それゆえ、彼らの本質とその由来については、美学と科学的な進化論との判断に、ゆだねねばならないと人々は信じた。そこで、人間の思考力は初期の段階から、以後数千年の間に進化してきたとする理論が、真正な宗教研究にとって代った。発端は能うるかぎり粗野なものと考えられねばならない、というのが自明の前提であった。この考えは、唯一の超現世的な神があらゆる事物に先立って、人間に対して自己を開示したとする聖書の教えにも反する。だが、学問は神学に大いに寄与することとなった」
その理由について、著者は次のように述べています。
「というのも忌々しい異教の神々に対する信仰は、ほかならぬ粗野な誤謬から生まれたのだ、ということを厳密に証明してみせたからである。これこそ何たる誤謬であろう。注目すべきことに、これはほかならぬ論理的思考と実験とのなせる過誤であった。というのは、神話と祭儀の時代の人間も、とどのつまり19世紀の合理的、技術的人間以外の何ものでもありえなかった、と考えるのであるから」
「神話的解釈と深層心理学」では、著者は心理学の主張について以下のように説明しています。
「精神的に追いつめられた人間や、病人の夢だとか夢遊状態だとかを分析することによって、純粋な神話的心像を捉えることができ、これが神話の起源と本質とを理解するうえに、手がかりを与えてくれると。そればかりではない。夢の像は太古より伝えられた神話に現われる形相とたいへん似通っているので、同一の像の不思議な回帰を考えざるを得ないのだと。事実、これがアルキタイプ、つまり原像と名づけられ、いわゆる心の無意識の領域に、覚めた精神の与り知らぬままに幾千年も保存され、心がこれを必要とする瞬間、夢となって再生すると考えられているのである。この奇妙な経緯を説明するために、大昔に考えられた事、見られた事柄を驚くほど忠実に保存する能力をもった〈集合精神〉(Kollektivseele)なるものが仮定された」
しかし、このような深層心理学の主張を著者は認めません。
特に、夢の像が神話の形相に比べられるばかりか、同一でさえあるという主張はまったく正しくないとして、著者は以下のように述べます。
「深層心理学による神話解釈は一種の循環論法である。つまり証明しようとするものを前提としている。夢幻のなかで立証されるのを見とどけるべく、神話的なものという概念をあらかじめつくっておく。しかもこの概念は誤解の上に成り立っている。心の苦しみに襲われた人が、夢うつつの生活にあって母なる像に接し、そのうちに庇護された思いに安堵することはありえよう。しかし、この母なる像も古代の〈大いなる母神〉の形相とは、その名前以外に共通な点はないのである」
続けて、本来の神話について、著者は以下のように述べます。
「本来の神話ならばどんなものにも、なんらかの神が生き生きとしたその拡がりを伴って現われている。その神が何と呼ばれようと、また他の神々からどう区別されていようとも、それは個別的な威力といったものでは決してない。その神固有の開示に立つ世界の全存在を意味している。ある限られた活動領域に縛られた力を、われわれはダイモーンとか霊とかと呼ぶ。だが、いずれにせよそうした力の1つが、神にまで成長した、などとは進化論の空疎な主張にすぎない」
「神話の根源的現われ」では、著者は以下のように述べています。
「今だに多数の人々が、神話についての断定的な言葉を〈深層心理学〉に期待しているのだが、この心理学の考え方はすべて、神話とは対極の世界のものである。この心理学は人間を自分自身の許に投げ返すばかりで、開けた世界から輝き出る神々しい精神から人間を遮断してしまう。この点、深層心理学はまさに神を失った現代世界の産物である。現代では知的概念と実験とが問題とされるとき、〈自然〉という言葉が用いられ、精神状態の分析に際して、〈存在〉という言葉が用いられる。同様に、病める魂が光から遮蔽され、ひとりとなって自分の内で夢想するときに、神話とか根源像の永久回帰とかが云々される」
著者によれば、真の神話には真の創造力があります。そして、ここには不朽の形相が生まれます。人間が新たに形成されるのです。すなわち、本来の真正な神話は祭儀、つまり人間をより高い領域に高揚させる、荘厳な所作なしには考えられない、と著者は言います。
神話と祭儀について、著者は以下のように述べています。
「神話と祭儀との関係については、時代によってさまざまな考え方がなされてきた。まず最初は、神話こそ根本で、祭儀はいわばその演出として、これに付随したものとみなされた。合理的で技術的な解釈の方法が支配する時代になると、この関係は逆転した。今度は祭儀が根源的なものとなり、その形式はたいてい大昔にまでさかのぼるのに対し、神話は比較的新しい時代に現われるものとされた。祭儀は呪術から解釈できるもので、神話は祭儀の本来の目的行為がそのものとしては理解されなくなったとき、これを空想的に説明したものだと信じられた。ところが、今からほんの数十年前になって、これまで以上に周到な研究の結果、神話を伴わぬ祭儀は一般に存在しないこと、また過去においても存在するはずのなかったことが確かめられると、問題は改めて提起されねばならなくなった」
続けて、神話と祭儀の関係について、著者は述べます。
「祭儀を神話の単なる演出とみる、かつての見方に帰ることは不可能だった。なぜなら、今日にまで伝えられている祭儀が教えるとおり、祭儀は神話の出来事の単なる写しでは決してなく、十全な意味で、神話の出来事そのものであるからだ。さもなくば、救いの力を祭儀に期待することは、なんとしても不可能であろう。誤りは問題提起そのものに、つまり主従関係を問うたところにある。神話を伴わぬ真の祭儀がないばかりか、祭儀を伴わぬ真の神話もまた存在しない。両者は元来同じひとつのものである。この事実は両者を理解するうえに、決定的な意味をもっている」
さらに、神話について、著者は以下のように述べます。
「神話が明るみに出してくるもの、それは言葉においてしか現われ得ないものに限られるのではない、言葉におけると同様、むしろいっそう根源的に、人間の行為とか、いきいきとした創造的な造形とかのうちに現われるものも含まれる。この点で先入観にまどわされることさえなければ、神話と祭儀の両者が根本においてひとつものであることは、容易に理解されよう。祭儀のさいの身振り、姿勢、動きの感動的な崇高さを考えてみていただきたい。神殿建築と神々の像との語る壮大な言葉を思い起していただきたい。これらもまた、神話のもつ神的真理の直接的現われであって、人々が神の啓示の唯一のものとみなしたがる、言葉による告知にすこしも劣るものではない」
「神話の根源的現われ」で述べたことを、著者は以下のように要約します。
「神話の根源現象である、行なわれることと語られること、つまり狭義の祭儀と神話との関係についていえば、次のようになる。祭儀においては、人間が自ら神的なもののうちにまで高揚し、神々と共に生き、行為する。他方、狭義の神話においては、神的なものが自ら身をひくくし、人間的なものに化するのである」
二章の後に、著者は「古代ギリシャ人の宗教―百科辞典としての見出し語」という一文を置いていますが、一「資料について」の冒頭で以下のように書いています。
「ギリシャの宗教には教義も教典もなく、祭儀上の規律はあったものの、神々が存在するということ、したがって敬虔な態度が要求されること以外に何の信仰上の強制もなく、神的事物に関して独占的な知識をほこる僧侶階級も存在しなかったがために、われわれがたんにギリシャ宗教の儀式や慣例だけでなく、その精神を知ろうとするならば、今のわれわれには世俗的と見える著作家たち、とりわけ偉大な詩人たちに頼らざるをえない。世俗的といったが、これら詩人たちは現代の作家たちとは異なって、真理を告知する使命を自ら感じ、知に通じた神格であるムーサたちに真なるものの分かち与えられんことを切に願っている。いちばん古く、もっとも重要な証言はホメーロスの叙事詩と『ホメーロス讃歌』とである。つづいてヘシオドスの『神統記』『仕事と日々』および今は失なわれてしまった彼の作品から多くの断片がある。古い他の叙事詩はわずかの断片および簡単な梗概を除いて残念ながらみな失なわれてしまった」
