- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2016.05.07
『トーテムとタブー』ジークムント・フロイト著、西田越郎訳(人文書院『フロイト著作集』3所収)を読みました。「人類の歴史は息子たちによる父殺しにより始まった」という衝撃的な仮説を唱えた本で、世界中に大きな影響を与えました。セックス理論に偏った心理学者の荒唐無稽なトンデモ説のようにずっと思っていたのですが、『儀式論』の参考文献として本書を初めて通読し、考えが一変しました。こじつけのようでありながら、鬼気迫るまでの異様な説得力を持っています。そして、とにかく圧倒的に面白かったです。
 函入りのハードカバーです
函入りのハードカバーです
「トーテムとタブー」は人文書院の『フロイト著作集』第3巻の148ページから281ページに収録されていますが、この巻はフロイトの「文化・芸術論」をまとめたもので、函の帯には以下のように書かれています。
「人間が現実世界において満たすことを禁ぜられた、あるいは満たすことのできない諸々の願望をある独特な方法によって錯覚的・幻覚的に満たす心的手段の一つである芸術を多用的に分析する主要論文15篇を収録する」
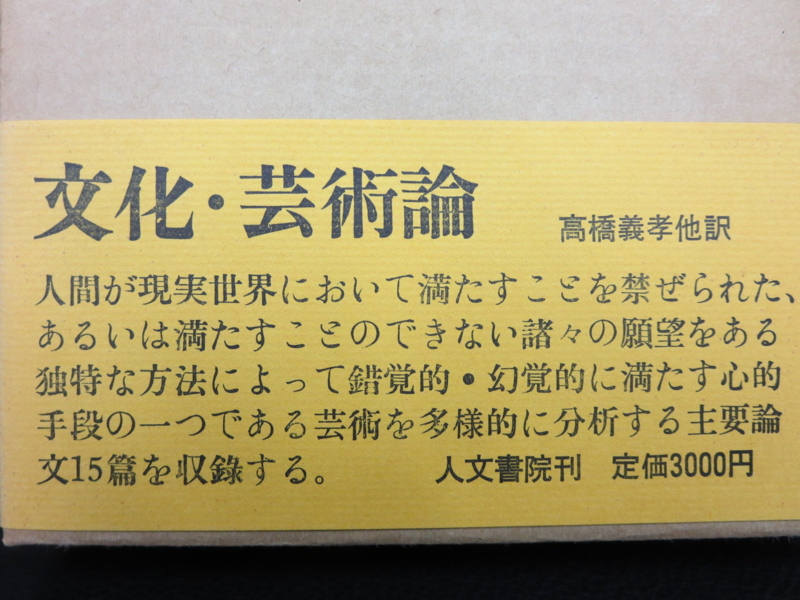 本書の帯
本書の帯
その主要論文15篇とは、「W・イェンゼンの小説『グラディーヴァ』にみられる妄想と夢」「詩人と妄想すること」「レオナルド・ダ・ヴィンチの幼年期のある思い出」「トーテムとタブー」「小箱選びのモティーフ」「無常ということ」「『詩と真実』中の幼年時代の一記憶」「無気味なもの」「否定」「ある幻想の未来」「ユーモア」「ドストエフスキーと父親殺し」「文化への不満」「火の支配について」です。このうち、「ある幻想の未来」や「文化への不満」などは名著として名高いですが、わたしはこれらは光文社古典新訳文庫版で読みました。
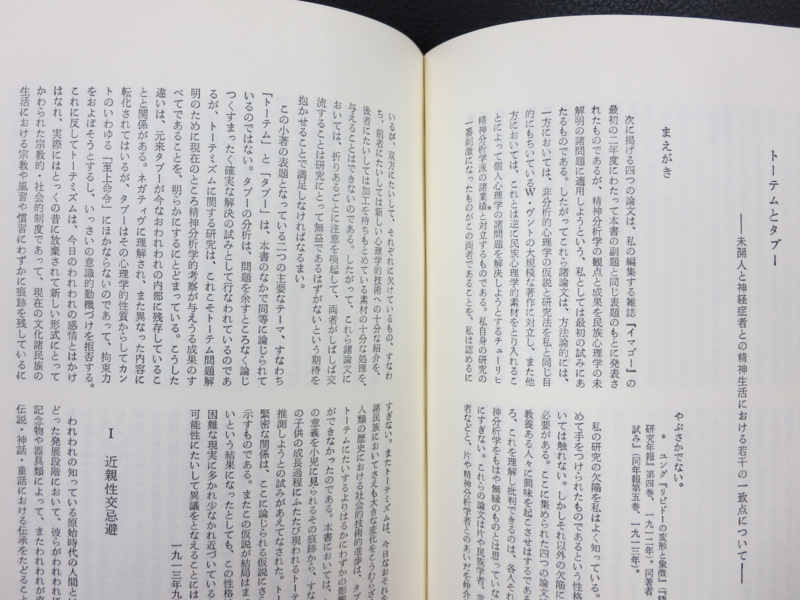 非常に興味深い内容でした
非常に興味深い内容でした
「トーテムとタブー」は1913年に書かれ、「未開人と神経症者との精神生活における若干の一致点について」という副題がついています。「目次」は以下の通りです。
「まえがき」
1 近親性交忌避
2 タブーと感情のアンビヴァレンツ
3 アニミズム・呪術および観念の万能
4 トーテミズムの幼児性回帰
1913年9月にローマで書かれた「まえがき」には、「タブー」と「トーテミズム」について以下のように書かれています。
「ネガティヴに理解され、また異なった内容に転化されてはいるが、タブーはその倫理学的性質からしてカントのいわゆる『至上命令』にほかならないのであって、拘束力をおよぼそうとするし、いっさいの意識的動機づけを拒否する。これに反してトーテミズムは、今日のわれわれの感情とはかけはなれ、実際にはとっくの昔に放棄されて新しい形式にとってかわられた宗教的・社会的制度であって、現在の文化諸民族の生活における宗教や風習や慣習にわずかに痕跡を残しているにすぎない。またトーテミズムは、今日なおそれを保持している諸民族においてさえも大きな変化をこうむらざるをえなかった。人類の歴史における社会的技術的進歩は、タブーにたいしてはトーテムにたいするよりはるかにわずかの影響しか与えることができなかったのである」
ここで、「トーテミズム」という言葉について説明したいと思います。
『世界大百科事典』(平凡社)の第2版では、「トーテミズム【Totemism】」について以下のように解説しています。
「未開社会に見いだされた,社会集団と動植物や事物の特定の種speciesとの間の特殊な制度的関係を,研究者たちはトーテミズムと呼んできた。その特定の自然種がトーテムtotemであるが,この語はアメリカ・インディアンのオジブワ族の言葉に由来する。はじめはトーテムの像として〈トーテム・ポールtotem pole〉を作るアメリカ・インディアン諸族に固有の習俗と思われていたが,トーテミズムという用語が生まれるとともに,オーストラリアやメラネシア,ポリネシア,インド,アフリカなど各地の事例が報告されるにつれ,19世紀後半から多くの研究者の関心を集めるようになった」
1「近親性交忌避」で、フロイトはトーテムについて以下のように述べます。
「トーテムになるのは、まず第一には血族の祖先であるが、ついでは血族の守護神・救済者である。これは血族に託宣を与え、平生危険とされているものであれば、自分の子供たちのことをよく知っていてそれを危険からまぬがれさすのである。そのかわり同じトーテムに属するものは、彼らのトーテムを殺さず(あるいは破壊せず)またそのトーテムの肉(あるいはトーテムが平生提供する亨用)を断つという神聖にして、自律的に罰する義務を負わされている。トーテム性格は個々の動物あるいは個体にではなくて、その種類に属する全個体に付属するものである。ときどき祭礼が行なわれ、そのさい、トーテムを同じくするものは、儀式的な舞踏によって彼らのトーテムの動作や特性を表現したり模倣したりするのである」
2「タブーと感情のアンビヴァレンツ」では、冒頭に「タブー Tabu」という言葉がポリネシア語であり、その意義は2つの相反する方向に分かれていると指摘されます。一方では「神聖な」「清められた」とかを意味し、他方では「無気味な」「危険な」「禁じられた」「不浄な」を意味しているのです。
ドイツの心理学者であるヴィルヘルム・ヴントは、タブーを「人類最古の不文法典」と呼びました。タブーは神々よりも古く、いかなる宗教もなかった時代にまでさかのぼると見られているというのです。
フロイトは「そもそも、なぜわれわれはタブーの謎に関心を向けるべきなのか?」と読者に問いかけ、その理由を以下のように述べています。
「私がいわんとするのは、心理学上のいかなる問題もそれ自体解決を試みる価値があるからという理由だけにもとづくのではなく、まだほかにもいろいろ根拠があるからなのである。ポリネシア未開人のタブーは、われわれがまず信じたがるほどに、われわれからかけ離れたものではなく、またわれわれ自身がしたがっている習慣的道徳的禁止が、その本質においてこの原始的タブーと親近性をもっているかもしれない、またタブーの解明はわれわれ自身の『至上命令』の曖昧な起源に照明を投じうるだろう、というような予感が許されるのである」
フロイトは、タブーとよく似た「禁止」という言葉について述べます。
「禁止のある部分は、その目的からしてただちに理解できるが、一方には、不可解、愚劣、無意味に思われる部分もある。われわれはこのような禁止を『儀礼』と呼ぶのであるが、タブーの慣習にも同様の相違が認められる」
そして、フロイトは、タブーの慣習と強迫神経症の一致を指摘し、以下のように述べています。
「強迫=禁止はタブーによる禁止と同じく、生活における極端な断念と制限をともなうものである。しかし強迫=禁止のあるものは、必然的に生ずる、すなわち強制的性格を有するある種の行為―つまり強迫行為―の遂行によって解消することができるのである。この行為が、償い・贖罪・防衛措置・浄めなどの性質をもっていることは疑いをいれないところである。この強迫行為のうちでもっとも普通に行なわれているのは、水で洗い落すこと(洗滌強迫)である。タブーによる禁止のある部分も同じようにして償われ、またその違反もこの種の『儀礼』によって償うことができるのである。そしてこの場合も、水による浄めがもっともよく行なわれるものである」
フロイトは、タブーの慣習と強迫神経症の症状との一致がもっとも明確に現われる諸点を以下のように要約します。
1 禁止の無動機性
2 内的強制による禁止の確立
3 移動性、および禁止されたものを通じての伝染の危険
4 儀礼的行為、すなわち禁止にもとづく戒律の発生
タブーは、トーテミズムとも深い関係があります。
フロイトは、両者の関係について以下のように述べています。
「タブーによる禁止のうちでもっとも古く、もっとも重要なものは、トーテミズムの基本をなす2つの法則、すなわち、トーテム動物を殺さないこと、および他種族のトーテム仲間との性交を避けるということである。
とすると、この2つの行為が人間のもっとも古く、かつ、もっとも強い欲望であるということにならざるをえないであろう。しかし、トーテミズム組織の意義と由来がまったく不明であるからには、そのことを理解することもできないし、したがって、これらの諸例に照らしてわれわれの前提を検討することもできないわけである。しかるに、個々の人間の精神分析的研究の成果を見るだけで、まったく確実なことがら、すなわち、精神分析学者が小児願望生活の節点、さらには神経症の核心なりとすることがらに注意をひかれるのである」
またフロイトは、なんと日本の天皇に言及します。タブー儀式による神聖な支配者の束縛と麻痺のもっとも顕著な一例として、数世紀以前の日本のミカドの生活様式を挙げるのです。もはや200年以上も昔のものであるがと断った上で、フレイザーの『タブー』に引用されているケンプファー(ケンペル)の『日本史』の以下のくだりを紹介します。
「ミカドは、自分の足で土に触れることはその威厳と神聖さにふさわしくない、と考えている。したがって、どこかへ出かけようとする場合は、人々の肩にかつがれて行かねばならない。ましてミカドはそのやんごとなき御身を外気にさらすなどということは、ありえないことであり、太陽は彼の頭を照らす光栄を有しないとされるのである。その身体のあらゆる部分に非常な神聖さが付与されているために、髪の毛を刈ったり、髦を剃ったりすることも、また爪を切ることも許されない。しかしあまりに見苦しくならぬように、人々は夜分彼の睡眠中にその身体を洗うのである。それは、このような状態で彼の身体から取り去られたものは、盗まれたものとしかみられないのであって、このような盗みは彼の威厳や神聖さを損なうことがない、ということになっているからである」
さらにフロイトは、ケンプファー(ケンペル)の『日本史』から引用します。
「もっと昔には、ミカドは毎朝何時間か王冠をいただいて玉座に坐っていなければならぬことになっていた。こうすることによってのみ、ミカドは国の平和と安寧を維持することができる、と考えられていたのである。万一不幸にして彼がその身体をどちらかに向けるか、あるいは、ちょっとのあいだその領土の一部に視線を向けたりすれば、戦争、飢饉、火災、疫病、その他の大災厄が起こって、国土を荒廃させることになろう」
フレイザーの『タブー』から古代ローマのタブーも紹介されます。
「古代ローマにおけるユピテル神の高級祭司フラメン・ディアリスは、きわめて多くのタブー規定を守らなければならなかった。馬に乗ってはいけなかったし馬や武装した者を見てもいけない。こわれていない指輪をはめることも、その衣服に結び目をつけることも許されなかった。小麦粉やパン種に触れてはならず、山羊、犬、生肉、豆、きづたなどの名を口にすることすら禁じられた。髪の毛は青銅の小刀で自由民だけが刈ることができ、刈られた髪の毛と切った爪は縁起のよい樹の下に埋めねばならなかった。死人に触れてはならず、無帽で戸外に出ることは許されない。などという具合である。その上、彼の妻フラミニカも彼女自身の禁止をもっていた。すなわち、彼女はある種の梯子を三段以上のぼってはならなかった。一定の祭日には髪に櫛をいれてはならなかった。彼女の靴の革は自然死をとげた獣の皮からとってはならず、屠殺されたか供犠された獣の皮でなければならなかった。もし彼女が雷鳴を聞いたなら、贖罪の犠牲を供えるまでは、彼女は不浄となるのであった」
さらに、フレイザーの『タブー』から古代アイルランドにおけるタブーも紹介されています。
「古代アイルランドの王たちは、きわめて風変わりな一連の制約のもとにおかれていた。それを守れば国はあらゆる祝福を与えられ、これに違反すればあらゆる災禍をうけるものと考えられていた。これらのタブーの完全な記録は『神権の書』Book of Rightsであり、そのもっとも古い手写本には1390年および1418年の年号が記されている。この禁止はすこぶる細目にわたり、一定の場所と一定の時間における特定の行動におよんでいる。王はこの町には一定の曜日に滞在できない、あの河はある時間には渡ってはならぬ、ある平原ではまる9日間の野営をしてはいけない、などという具合である」
ここで、フロイトは「タブー儀式」について以下のように述べています。
「タブーによる禁止を神経症の症候と比較しようとするわれわれの考察法の、もっとも有力なよりどころとなるのはタブー儀式そのものである。王の地位にたいするタブー儀式の意義はさきに論じたところであるが、この儀式が二重の意味をもっており、アンビヴァレントな傾向に由来するものであることは、その儀式のもたらす影響が初めからの狙いであったということを知りさえすれば明らかである。タブー儀式は王に栄誉を与えて普通人以上のものに高めるものではあるが、同時に、王の生活を苦痛に変え、耐えがたい重荷にし、王をして人民のおかれた状態よりもさらに悪い奴隷状態に陥れるものでもあるのだ」
フロイトは「死者のタブー」にも言及し、以下のように述べます。
「われわれの知るごとく、死者とは強力な支配者である。その死者が敵とみなされるときかされれば、それは驚きであろう。
死者のタブーは、伝染病との比較をなおも続けてもよいものなら、体多数の原始諸民族にあっては特殊な感染症をもつことを示している。このタブーはまず死者との接触によって生ずる結果のうちに、さらには死者をとむらう者の取扱い方のうちに見られる」
ここで、フロイトは「死者の名前を口にしてはならない」という奇妙なタブーを以下のように紹介します。
「原始人の服喪に関するタブー慣習のうちでもっとも異様であり、しかももっとも啓発的なものの1つは、死者の名前を口にしてはならないという禁止である。これは非常に広く行なわれており、多種多様な形をとっていて重要な結束をうんでいるものである」
この禁止が見られるのは、タブー慣習をもっともよく保存しているオーストラリアやポリネシアの土着民をはじめ、日本のアイヌなど広い範囲に及んでいます。
このタブーについて、フロイトは以下のように述べています。
「死者の名前を避けることは通例きわめて厳格に守られている。たとえば南アメリカの多くの種族では、死者の名前を遺族の前で口にすることは最大の侮辱とされている。これにたいする罰は、殺人行為にたいするものに匹敵するほどである。死者の名を口にすることがなぜかくも嫌悪されなければならないのか、さしあたってこれを簡単に推測することはできない。しかし名前を口にすることに関連した危険から、それをのがれるための多くの方策が生まれたが、それは各方面にわたって興味深く、意義のあるものである」
フロイトは、死者に対する感情について、以下のように述べています。
「死者にたいする感情、これは充分に確証されたわれわれの仮定からすれば2つ―情愛と敵意―に分裂しているのだが、この感情が死別のさいに2つとも現われるのである。一方は哀悼の念として、他方は満足感としてである。この2つの対立のあいだには、葛藤が起こらずにはいない。ところが対立するものの一方、つまり敵意は――その全部が、あるいはかなり大きな部分が――無意識なのであるから、葛藤の結果は、双方が互いに減算を行なって、剰余ができるように意識的に考慮するという具合にはいかない。たとえば愛する者から受けた侮辱なら許すというように。むしろその経過は、精神分析学で投射と呼びならわしている特殊な精神的メカニズムによって落着するのである」
続けて、フロイトは以下のように述べます。
「敵意、それについては何も知られていないし、また誰もさらに立ち入ってそれを知ろうともしないが、その敵意は内的知覚から外界へ投射され、このとき敵意を抱いたその人を離れて他の人に移っていくのである。われわれ遺族は死者と縁が切れたことを喜ぶようなことはしない。いや、それどころか死者を哀悼するのである。ところが奇妙なことには、死者は邪悪な魔神となって、われわれが不幸に見舞われれば満足をおぼえるのであり、またわれわれに死をもたらそうと努めるのである。ここにおいて生きている人々は、このような邪悪な敵にたいして自粛しなければならない。内的圧迫をまぬかれはしたものの、実はそれと引きかえに外部からせめたてられることになっただけなのである」
フロイトは、ヴントの以下の言葉を紹介します。
「世界各地の神話が悪魔のせいにしている諸作用のうち、まず圧倒的なのは有害な作用である。したがって諸民族の信仰においては、明らかに悪い方の悪魔が善意の悪魔より古いのである」
そして、フロイトは以下のように述べています。
「一般に悪魔という概念が死者とのきわめて重要な関係から得られたのだということは、いかにもありそうなことである。この関係に内在するアンビヴァレンツは、人類のその後の発展過程において、同じ根源から2つのまったく相反する心理的形態を生じさせた、ということのうちに現われている。その1つは悪魔や幽霊にたいする恐怖であり、もう1つは祖先崇拝である」
続けて、以下のように述べられています。
「悪魔がつねにごく最近死んだ人の霊だと考えられるということほど、哀悼の念が悪魔信仰の成立へおよぼした影響を証明するものはない。哀悼の念はきわめて明確な心理的任務を果たさなければなりません。つまり遺族が死者によせる追憶や期待をこれによって忘れさせようというのである。この作用が働き始めると苦痛がやわらぎ、それとともに悔恨や非難、したがってまた悪魔にたいする不安も減退することになる。
はじめ悪魔として恐れられた霊魂が、いまやもっと親しげな使命をになうことになり、祖先として崇められたり、助力を求めて呼び出されたりするのである」
タブーと強迫神経症とを比較したフロイトは、神経症の個々の形態と文化所産との関係がどのようなものであるか、また神経症心理学の研究がいかなる点において文化発展の理解に重要となるかが推測できると説き、以下のように述べます。
「神経症は一面において芸術・宗教・哲学の偉大な社会的所産との顕著にして深い一致を示しているが、他面においてそれらのもののいわば歪曲化されたものであるようにも思われる。ヒステリーは芸術創造のカリカチュア、強迫神経症は宗教のカリカチュア、パラノイアは哲学体系のカリカチュアであると、あえて言うこともできよう」
続けて、フロイトは神経症について以下のように述べます。
「こうした偏差は結局、神経症が非社会的産物であるということに由来する。社会で集団作業によって生みだされたものを、神経症は個人的手段によって成就しようとするのである。神経症の欲動を分析すればわかることであるが、神経症で決定的影響をおよぼしているのは、性にもとづく原動力であるのにたいして、これに対応する文化所産の基礎になっているのは、利己的要素と性愛敵要素との結合から生じた社会的欲動なのである。性的欲望は、自己保存の要求と同じやり方で人間を結合することはできない。性的満足は何よりもまず個人の私事なのである」
そして、フロイトは神経症について以下のように結論づけるのでした。
「発生的には、神経症の非社会的性格は、不満足な現実からもっと快楽に富む幻想世界へ逃避しようとする、神経症のきわめて根源的な傾向から生ずるものである。神経症者の忌避するこの現実世界には、人間の社会と、人間が共同して創造した諸制度とが支配している。現実からの離反は同時に人間共同体からの脱出なのである」
3「アニミズム・呪術および観念の万能」では、この読書館でも紹介したタイラーの著書『原始文化』やヴントの『神話と宗教』などを取り上げながら、アニミズムについての論考が行われます。「アニミズム」 animism という言葉の造語者であるタイラーは、アニミズムとは「霊的存在への信仰」 the belief in the Spiritual Beings を意味します。彼は、アニミズムによって、人間が神や死者、動植物、無生物などほとんどあらゆる存在に対して宗教的心意を示し、宗教的行動をとることの原初的な意味を根本的に明らかにしようとしました。万物が人間の信仰の対象となりうる理由について、タイラーは、人間は万物に霊魂が宿っていると考えているからだと考えます。ある未開社会においては思想家が病気や幻想、死について、非物質的な霊魂の観念を持ち出して説明しようと試みます。このことで霊魂は霊的存在の観念に発達してアニミズムが成立し、さらには神という観念へと発達することになります。タイラーは、このようにして確立される神は霊魂を擬人化したものであり、さらに神々の世界には階級が成立して神々は一つの神に統合されると論じます。つまりアニミズム、多神教そして一神教という発達の図式が描き出せると論じているのです。
このアニミズムについて、フロイトは以下のように述べます。
「未開人はどのようにして、このアニミズム体系の基礎たる独特な二元論的根本観念に達したのであろうか。それは、睡眠(夢をも含めて)やそれによく似通った死という諸現象を観察し、また各個人と密接な関係にあるこれらの状態を解明しようと努めたためだといわれる。なかでも死の問題が、この理論の成立する出発点になったにちがいない。未開人にとっては、生命の永続――つまり不死――は自明のことであったろう。死という観念は、後になって、しかもためらいがちに受け入れられたものである。いやそれどころか、われわれにとっても、死の観念は内容のつかめない完成不可能なものなのである。アニミズムの根本理念の形成にあたって、その他の観察や経験、たとえば夢像や彫像や反射像などについての考察や経験が果たしたかもしれない役割に関して、ひじょうに活発な議論が行なわれはしたものの、なんらの結論にも達しなかったのである」
また、思想体系としてのアニミズムについて、フロイトは以下のように述べています。
「アニミズムは1つの思想体系であって、それは個々の現象を説明するだけではなく、世界全体を唯一の関連として1つの観点から把握することを可能ならしめるものである。論者たちの説くところにしたがうならば、人類は時の流れにつれて3つのこうした体系、3つの大きな世界観を生み出した。すなわち、アニミズム的(神話的)世界観、宗教的世界観、および科学的世界観である。このうちで最初に創られたもの、すなわちアニミズムの世界観は、おそらくもっとも首尾一貫した遺漏のないもの、世界の本質を余すところなく説明するものである。この人類最初の世界観は、いまや心理学的理論となっている。それが迷信という形をとって価値を失ってしまっているにせよ、われわれの言語・信仰・哲学の基礎として生きているにせよ、この世界観がどれだけ現代の生活のうちに指摘されうるかを示すのは、われわれの意図をはみ出たことである。アニミズムそのものはまだ宗教ではないが、後の宗教の基礎となる前提条件を含むものだといわれるが、それはこの3つの世界観が段階的に連続していることによるのである。神話がアニミズムの前提の上に立っていることも明白である」
さらに、フロイトは魔法と呪術について以下のように述べます。
「魔法と呪術とは、概念の上で区別できるであろうか。いささか独断的に言語慣用の変動を無視するとすれば、それは可能である。魔法とは、本質的には、人間を扱うのと同じ条件で霊を扱うことによって、つまり、霊をなだめ、慰め、よろこばせ、おどし、その力を奪い、こちらの意志にしたがわせるなどすることによって、すなわち、生きている人間にとって有効と思われる手段によって、霊を意のままにする術のことである。ところが呪術はそれとは別物である。呪術は根本において霊とは無関係で、特殊な手段を用いるのだが、それはありふれた心理学的手段ではないのである。呪術がアニミズム的技術の、かなり根源的な、かなり重要な部分であることは、容易に推測できるであろう。なぜなら、霊を取り扱うべき方法の中には、呪術的方法もあるのであり、また自然の霊化が成就されていないと思われる場合にも、呪術は適用されているからである」
フロイトは、アニミズムや呪術におけるキーワードは「観念」であると指摘します。そして、観念について以下のように述べています。
「観念で行なわれることは、事物においても起こらねばならない。観念相互にある関係は、事物間でも前提とされるのである。思考は距離というものを知らず、空間的にどんなに遠いものでも、また時間的にどんなにへだたったものでも、やすやすと1つの意識作用にまとめてしまうのだから、呪術的世界もテレパシーによって空間的距離をとびこえ、また過去の関連を現在の関連のように取り扱うであろう。アニミズムの時代においては内的世界の映像は、われわれが認識していると思っているあの別の世界像を、眼に見えないものとせざるをえないのである」
そして、フロイトは以下のような名言を吐くのでした。
「呪術、すなわちアニミズム的思考方法を支配している原理は、『観念の万能』である、ということができよう」
この「観念の万能」という言葉から、わたしは「引き寄せの法則」を連想しました。拙著『法則の法則』(三五館)にも書いたように、人間の願いによって発動する「引き寄せの法則」こそ、宇宙で最も偉大な法則であると訴える人は多いです。大ベストセラーとなった『ザ・シークレット』の著者であるロンダ・バーンは、「この宇宙であなたが一番強力な磁石なのです。この世界では、あなたの中の磁石が何よりも強いのです。そしてその底知れない磁石はあなたの思考を通してあなた全体から放射されているのです」と書いています。磁力の放射によって何が起こるのか。それは、よく知られた言葉である「類は友を呼ぶ」といった現象です。人間が考えていることと似た思考を引き寄せてしまうのです。「引き寄せの法則」は他の簡単な言葉に言い換えることができます。すなわち、「思考は現実化する」です。自己啓発の世界における最大のスーパースター、ナポレオン・ヒルの言葉であり、彼による同名の著書も出版されています。「思考は似た思考を引き寄せる」「思考は現実化する」といった考え方は、実はここ百年以上のあいだ、手を変え品を変え、登場してきました。その源流をたどると、「ニューソート」というアメリカの思想運動にたどり着きますが、この思想の根底にあるものこそ「観念の万能」にほかなりません。すなわち、「引き寄せの法則」の本質とは呪術であると言えるでしょう。
4「トーテミズムの幼児性回帰」では、『セム族の宗教』の著者であり、トーテミズムについての論考を行なったウィリアム・ロバートソン・スミスについて、フロイトは以下のように述べています。
「1894年に死去したW・ロバートソン・スミスは、物理学、言語学、考古学の研究者として多面的で明敏な自由思想家であったが、1889年に公刊したセム族の宗教に関する著書の中で、いわゆるトーテム饗宴という独特の儀式は、そもそもの初めからトーテム制度に不可欠の構成要素をなしていた、という仮説を述べた。この推測のよりどころとして彼が当時利用できたものは、5世紀から伝わるその種の行為の記録がたった1つあるだけだったが、彼は古代セム族の供犠制度の分析によってこの仮説をきわめて確かなものとすることができたのである。生贄はある神的人格を前提とするのだから、ここでは、宗教的儀式という高い段階から帰納して、トーテミズムというもっとも低い段階を推論することになる」
ロバートソン・スミスは、祭壇の生贄が古代宗教の本質的な点であったことを指摘しました。生贄は、すべての宗教において同じ役割を演じているのですから、生贄の発生は、きわめて一般的であると言えるでしょう。この考えを踏まえて、フロイトは以下のように述べます。
「こうした生贄は1つの公的儀式であり、部族全体の祭事だったのだ。宗教は総じて全般の事件であり、宗教上の義務は社会的義務の1つであった。いずれの民族においても生贄と祭事とは同時であって、生贄には祭事がつきものであり、どんな祭事でも生贄なしに行なうことはできない。生贄祭事は、喜んで自己の利害を超越して、お互いが団結し神とも一体だということを強調する機会だったのである」
また、公的儀式としての生贄祭事について、フロイトは述べています。
「神聖な動物の生命を、種族仲間の生命として保護する畏怖があるにもかかわらず、ときどき儀式的な集会で、こうした動物を殺しその肉と血を部族仲間に分配することが必要とされるのである。この行為を命ずる動機は、生贄制度のもっとも深い意味をあらわしている。聞くところによると後代では、共通の食事をとること、体内に入りこんでくるものが同じ物質であること、これが食卓を同じくする人々のあいだに神聖な結びつきをつくるのであるが、最古の時代においては、このことの意義は神聖な生贄の実質にあずかるということだけであるらしい。犠牲死の神聖な秘儀というものは、こうした方法によってのみ、関与者相互間を、また関与者と神を結合する紐帯がつくられるのであるから、正当なものとされるのである」
さらにフロイト派、生贄動物について以下のように述べています。
「太古においては、生贄動物そのものが神聖であり、その生命は侵しがたいものであった。種族全体の参加と共犯のもとに、しかも神の現前においてしか、その生命を奪うことはできなかった。そしてその結果、その神聖な実質が供給され、それを食べることにより、部族仲間は相互の、また神との物質的同一性を確かめることができたのである。生贄は秘蹟であり、生贄動物そのものが種族仲間であった。実際、古代のトーテム動物、すなわち原始的な神そのもの、これを殺して食べることによって、部族仲間は自分が神に似たものであることを改めて思いおこし、確信をもったのである」
フロイトは、祭事について、以下のように述べています。
「祭事とは容認されたというよりはむしろ命令された放逸であり、儀式によって禁止を破ることである。人々がなんらかの規定によって楽しい気分になるから、乱痴気騒ぎをするわけではない。放逸ということが祭事の本質なのだ。つまり祭りの気分は、ふだん禁止されていることから解放されるために生ずるのである」
ここで、トーテム饗宴の問題は、フロイトの最も有名な理論である「エディプス・コンプレックス」に関わってきます。エディプス・コンプレックスとは、母親を手に入れようと思い、また父親に対して強い対抗心を抱くという、幼児期において起こる心理的抑圧のことをいいます。フロイトは、この心理状況の中にみられる母親に対する近親相姦的欲望をギリシア悲劇『オイディプス』(エディプス王)になぞらえ、「エディプス・コンプレックス」と呼びました。『オイディプス』は、主人公が知らなかったとはいえ、父王を殺して自分の母親と結婚(親子婚)したという物語です。
本書『トーテムとタブー』でも、フロイトは以下のように持論を展開します。
「トーテム饗宴の祝祭を引合いに出すことが、われわれに解答をあたえてくれる。ある日のこと、追放された兄弟たちが力をあわせ、父親を殺してその肉を食べてしまい、こうして父群にピリオドをうつにいたった。彼らは団結することによって、1人ひとりではどうしても不可能であったことをあえてすることになり、ついにこれを実現してしまう(これはおそらく、新しい武器の使用のごとき、文化の進歩が彼らに優越感をあたえたのであろう)。殺した者をさらに食ってしまうということは、人喰い人種にはあたりまえのことである」
続けて、フロイトは犯罪行為と結びついたトーテム饗宴について述べます。
「暴力的な父は、兄弟のだれにとっても羨望と恐怖をともなう模範であった。そこで彼らは食ってしまうという行為によって、父との一体化をなしとげたのである。父の強さの一部をそれぞれが物にしたわけである。おそらく人類最初の祭事であるトーテム饗宴は、この記憶すべき犯罪行為の反復であり、記念祭なのであろう。そしてこの犯罪行為から社会組織、道徳的制約、宗教など多くのものが始まったのである」
生贄の問題と深い関係にある宗教があります。それは、世界宗教であるキリスト教です。キリスト教は、古代世界にのり込んだときにミトラス教と競争することになりました。そしてしばらくは、どちらの神が勝利を占めるのか、分からない状態でした。自らはユダヤ教徒であったフロイトは、キリスト教について以下のように述べます。
「ミトラスの牡牛殺害についての叙述から、彼が父を生贄にすることをひとりでやってのけ、こうして兄弟たちを彼らに重くのしかかる共犯意識から救ってやるという、あの息子の役を演じたことはおそらく推論できるだろう。この罪意識をしずめるためのもう1つの道があり、それをまず歩んだのがキリストであった。キリストは歩みをすすめて、自らの生命を生贄に捧げ、それによって同胞たちを原罪からから救済したのである」
原罪の教えは、オルフェウス教から来ています。この教えは古代ギリシアの秘教の中で受け継がれ、そこから古代ギリシア哲学の諸流派の中へ入り込みました。フロイトは、原罪について以下のように述べます。
「キリスト教神話においては、人間の原罪とは疑いもなく父なる神にたいする罪である。ところで、キリストが自らの命を生贄にすることによって、人間を原罪の圧迫から救済するのだとすれば、キリストは、この罪は殺害行為だったという結論をわれわれに強いることになる。人間感情に深く根ざしている同罪の刑(タリオン)の法則によれば、殺人は他の生命を生贄にすることによってのみ償いうるものである。つまり、自己犠牲は、殺人の罪を犯したことを示すようなものである。だから、自らの命を生贄にすることが、父なる神との和解を招来するとすれば、償わるべき罪は父殺し以外のものではありえなかった」
フロイトは、以下のような結論を述べています。
「宗教、道徳、社会、芸術の起源がエディプス・コンプレックスにおいて出あうということである。これは、今日までわれわれの理解しえたかぎりにおいて、このコンプレックスがすべての神経症の核心をなしているという、精神分析学の結論と完全に一致している。民俗精神生活のこれらの問題も、父との関係がどうであるかというたった1つの具体的観点から解決されるなどというのは、私には大きな驚きのように思われる。おそらくは、もう1つの心理学的問題でさえも、これと関連をもたせることができるかも知れない。未来の意味における感情のアンビヴァレンツ、すなわち同一対象にたいする愛情と憎悪の並存が、重要な文化形成の根底にあるということは、われわれがたびたびの機会に示してきたことであった」
フロイトは、未開人と神経症者について以下のように述べます。
「未開人も神経症者と似た事情にあったのではないだろうか。未開人が心理的行動をとくに過大評価したのは、彼らの自己愛的組織の部分的現象だと、われわれがするのは正しい。とすれば、父にたいする敵意の単なる欲動や父を殺して食おうとする空想的願望の存在だけで、トーテミズムとタブーを創造した。あの道徳的反作用を生じさせるのに充分であったろう。こうしてわれわれは、誇ってしかるべきわれわれの文化財が、われわれのすべての感情を害する恐ろしい犯罪にはじまるとする必要性から免れたことになる。このさい、あの発端から現代にいたるまでの因果関係はなんらそこなわれることはない。なぜなら、精神的現実はこれらすべての結果の責任を負うに充分なほど、意味深いものであろうから」
そして、この驚くべき書物の最後を、フロイトは以下のように締めくくるのでした。
「われわれは、未開人について判断をくだすとき、神経症患者との類似にあまり影響されてはならない。両者のあいだの差異をも考慮に入れなければならない。両者、つまり未開人にしても神経症患者にしても、思考と行為のあいだには、われわれが行なうようなはっきりした区別が存在しないことは確かである。しかし、神経症患者はなによりも行動にとってかわるものである。未開人は抑制されていることはなく、思考はそのまま行為におきかえられる。すなわち、未開人にとっては、行動はいわばむしろ思考のかわりをするものである。だから、次の断定が絶対確実だとみずから保証しないにしても、われわれが論じているこの場合には、おそらくそう考えてもよいと私は思う、すなわち『太初に行いありき』と」
本書『トーテムとタブー』の最後を飾る「太初に行いありき」という言葉には大いに感銘を受けました。『旧約聖書』の冒頭にある「太初に言葉ありき」をもじったものでしょうが、まさに我が意を得た思いでした。原初の宗教においては、教義よりも先に儀式があったのです。まず、儀式があり、それから神話、宗教、芸術が生まれていったというのが、わたしの考えです。「エディプス・コンプレックス」をはじめ、すべてのフロイトの理論に賛同や共感することはできませんが、この「太初に行いありき」は執筆中の『儀式論』の背骨を通してくれたような気がします。わたしは思わず、「フロイト、すごすぎる!」とつぶやきました。
