- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2016.07.01
『聖婚』S・N・クレーマー著、小川英雄・森雅子訳(新地書房)を読みました。「古代シュメールの信仰・神話・儀礼」というサブタイトルがついています。古代オリエントの宗教思想や正月の祭りが現存する人類史上最古の詩歌を紹介しており、『旧約聖書』の「ソロモンの雅歌」を理解する上で必須とされています。1969年に刊行され、1989年に日本語訳が出ています。
著者は1897年に帝政末期のロシアに生れましたが、9歳のときにアメリカに移住しました。ペンシルヴェニア大学を卒業した後、シカゴ大学オリエント研究所やペンシルヴェニア大学で楔形文字の解読を通じて、古代シュメール文化、とりわけ宗教や文学の研究を続けました。その時期には、古代エジプト人とならんで地球最古の文明を建設したシュメール人の存在がすでに知られていました。解読された文書と出土物の量が増大するにつれて、この民族の歴史と文化の概略が明らかになりつつあったのです。著者は、この段階の代表的な学者として知られました。主な著書に『シュメール神話』『歴史はシュメールに始まる』『シュメール人とその歴史、文化、性格』『文明の始まり』などがあります。
本書の「目次」は、以下のようになっています。
「図版」
「前書き」
一、 シュメール人―歴史、文化、文学
二、 シュメール人の詩歌―反復、類似、形容語、直喩
三、 聖なる結婚―起源と発展
四、 聖なる結婚―求婚と婚儀
五、 聖なる結婚と「ソロモンの雅歌」
六、 聖なる結婚―死と復活
「註」
「用語解説」
「訳者あとがき」
「前書き」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。
「学界はこれまでほぼ1世紀にわたって、古代メソポタミアにも豊饒儀礼があり、その主要な登場者は牧人王ドゥムジと彼の愛する花嫁イナンナであることを知ってきた。前者は一般的にはその名前の旧約聖書中における表現によってタンムズとして知られ、後者はそのセム語による名前イシュタールによって知られている」
本書の白眉は第3章~第6章の「聖なる結婚」です。著者は述べます。
「第三章はこの儀式の起源と発展をとり扱い、その心理的裏付け、歴史的背景、そして何世紀にもわたる変化について記している。第四章はこの聖なるカップルの求婚と婚儀に関するシュメールの詩文や結婚式そのものについて何らかの光を投げかけてくれる詩文の翻訳からなっている。これら全ての詩文を調べてみると、聖婚の儀式というものは恍惚境をうたった相聞歌を伴う喜びの儀式であった。それは、一般に『ソロモンの雅歌』として知られる、聖書中の1巻の中にも集大成されている。第五章はこれらのシュメール語による恋愛抒情詩の幾つかの内容を紹介し、それらが形式、主題、モティーフ、そして時には用語法などで聖書中の『雅歌』に類似していることを指摘している」
続いて、著者は以下のように述べています。
「しかし、愛と情熱にもかかわらずこの結婚は、少くともドゥムジに関する限りはつらい、逆説的な悲劇として終ってしまった。最後の第六章の前半は『イナンナの冥界下り』の全文の校訂版である。それは最も錯綜し、最も想像力に富むシュメール神話の1つであり、ドゥムジの拷問、死、復活をもって終っている。この章の後半はドゥムジの悲劇的な死に関するさまざまな付加的な神話の内容を紹介している。そして最後に、ドゥムジの神話と福音書のキリスト物語の間に考えられる平行関係についての概観をしている」
一「シュメール人―歴史、文化、文学」の冒頭で、著者は以下のように書いています。
「古代シュメールの地は、現代のイラクの南半分、すなわち今日のバグダードからペルシャ湾に至る地域とほぼ一致する。その地の大部分は荒涼とした、風の吹きすさぶ沖積平野で、数千年にわたってティグリス、ユーフラテス両河が堆積したシルト(沈泥)からなっている。気候は暑く、乾燥し、土壌はそのまま放置されるならば、干からびて不毛である。しかし、もしシルトを含んで溢れ出すティグリス、ユーフラテス両河の氾濫水を集め、水路にひき込むという灌漑作業を施すならば、土壌は途方もなく肥沃で実り豊かなものとなり得る。多くの学者がその地を聖書に出てくるエデンの園と見做すのも不思議ではない。人類最初の高度な文明が栄えたのは、このシュメールの地であった。しかもその文明は、起源をうす暗い先史時代の過去にまでさかのぼると同時に、ほぼ西暦紀元の初頭まで何等かの形で在続していたのである」
古代シュメールの社会とは、どのような社会だったのでしょうか。
著者は、以下のように述べています。
「そこでは政治社会の忠誠心がもはや部族や氏族にではなく、共同体全体に向けられた。立派な神殿やジグラットが空高く聳え、市民の心を畏敬と驚嘆と誇りの念で満たしていた。そこにはまた、技術的発明、産業の専門化、商業活動などが成長し、発展する余地があった。シュメールの都市で最初に文字を書く効果的なシステムが考案され、発展させられた結果、通信・伝達に1つの改革がもたらされた。それは我々の時代のエレクトロニクスの発明品と同様に、予想や予期をすることが不可能なほど深刻な影響を人類の経済的、思想的、文化的進歩に与えた。シュメール人の思想、技術、発明は東西に伝播し、ほとんど全ての古代文明にその刻印を残したが、それはある程度までは、我々の時代にも及んでいる」
シュメールの社会における基本的単位は家族でした。
現在のわたしたちと同じですが、その構成員は愛と尊敬と互の義務によって密接に結ばれていました。著者は、以下のように述べています。
「結婚は両親によってとり決められ、婚約は花婿が(花嫁の)父親に婚資を贈るのと同時に合法的なものと見做され、しばしば粘土板に刻まれた契約書という形で完成した。結婚がこのように実利的なとり決めになってしまった一方では、結婚前の内密の求愛がまったく知られていなかった訳ではないということの幾つかの証拠もある」
続けて、著者はシュメールの結婚制度について述べます。
「シュメールでは、女性はある種の重要な法律上の権利を持っていた。例えば、彼女は財産を所有し、仕事に従事し、証人としての資格もあった。その反面、夫は比較的些細な理由で彼女を離婚することができたし、もし子供が生まれなかった場合には、もう1人の妻と結婚することも許されていた。子供たちは彼らの両親の完全な支配権の下にあった。両親は彼らを廃嫡したり、時には奴隷として売り払ってしまうことさえできた。しかし、通常子供たちは深く愛され、慈しまれ、両親の死に際してはその財産を全て相続した。養子は稀ではなかったが、彼らもまた非常な心づかいを受け、尊重された」
シュメール人たちは、亡くなった家族を埋葬しました。
著者は、シュメール人の死者儀礼について述べます。
「都市の郊外にも特別な墓域があったにもかかわらず、家の地下にはしばしば家族の死者たちを埋葬する墓室が設けられていた。シュメール人は死者の魂は冥界まで旅をし、そこで一種の無気力状態ではあるが、地上と同じような生活を多かれ少かれ続けるものと信じていたのである。それ故、彼らは死者と共に土器、道具、武器、宝石の類を埋葬した。王たちの場合には、戦車とそれを牽引する動物たちばかりか、時としては幾人かの廷臣、召使、侍従さえも一緒に埋葬した」
著者によれば、知的、精神的分野において、シュメールの思想家や賢者たちは、後に全オリエントの基本的な信条や教義となった宇宙論や神学を展開したといいます。それは以下のような内容でした。
「宇宙はある万神殿(パンテオン)の管理下にあると考えられていた。そしてこの万神殿は、形は人間に似ているが人間よりはるかに優れ、しかも不老不死である一群の生ある存在によって構成されていた。彼らは人間の目には見ることができないが、入念に練られた計画と適切に定められた法則に従ってこの宇宙を導き、支配していた。天、地、空、海、太陽、月、惑星、風、嵐、暴風雨、川、山、平野、都市、国家、畑、農園、灌漑水路などを管理する神々がいた。万神殿の主宰者は4柱の創造神であり、彼らは宇宙の四大構成要素である天空、大地、大気、海を支配していた。そのシュメール語の名は、アン、キ、エンリル、エンキである」
では、シュメール人たちは人間についてどう考えていたのでしょうか。
著者は、以下のように述べています。
「人間に関していえば、シュメールの思想家たちは彼らの世界観と同様、行き過ぎた信頼を人間やその運命に対して抱かなかった。彼らは人間は粘土で作られ、しかも唯一の目的のために創造されたと固く信じていた。その唯一の目的とは、人間が食物、飲み物、そして隠れ家を提供して神々に奉仕すれば、神々はその聖なる活動のために十分な余暇を持てるであろうということであった。また、人生は不安に悩まされ、危険につきまとわれるものであったが、それは人間が未来をあかさない神々によって定められた自分の運命を予知することができないからである、と信じられていた。しかし、それでも生は死よりはるかに好ましいものであった。というのも、死んでしまうと、すっかり無気力になった霊魂は暗く、荒涼とした冥界へと下降し、そこでの『生』は地上の生活の陰気で、不快な反映物に過ぎなくなったからである」
さらに、シュメール人の宗教について、著者は以下のように述べます。
「シュメールの宗教においては、個人的な祈祷や各人の信心が重要な宗教的行為と見做されていたが、公けの宗教儀式や祭式はより顕著な役割を果たしていた。祭儀の中心は神殿及びそこに所属する神官、女神官、歌手、楽人、宦官、聖娼たちであった。ここでは毎日、肥えた動物や野菜の供物と水、ビール、ワインの献酒が捧げられていた。それに付け加えて、新月の祭りやその他の月の祝典もとり行われた。最も重要なのは、長々と続く新年祭で、それは幾つかのケースでは聖婚の儀式で最高潮に達した。儀式の中で、在位中の王はイナンナ―生殖と豊饒の女神と結婚したが、後者は特別の女信者が代理を勤めるのが常であった。この結婚によって、王はドゥムジ―旧約聖書のタンムズと象徴的に同一視されたが、彼はシュメール人の伝説によれば、初期の頃の王の1人で、イナンナの夫として実在した人物であった」
三「聖なる結婚―起源と発展」の冒頭で、著者は聖婚の儀式について、以下のように述べています。
「聖婚の儀式は約2000年の間、古代オリエントのあらゆる地域で歓喜と狂躁のうちに執り行われた。そして、それは何の不思議もなかった! というのも、その儀式の背後にある思想は単純で、魅力的で、しかも非常に説得力があったからである。古代の黄金時代には、人ロの『爆発的増加』に対する恐怖心は存在しなかったので―王たちにとって、国民を幸福にし、繁栄させ、数を増やさせるために、情熱的で、魅力的な女神と結婚することは楽しい任務であった。実際、その女神は豊饒と多産を司り、国土の生産力と人間や動物の子宮の受胎力を支配する、心をときめかせる存在であった」
続けて、著者は以下のように述べています。
「しかし、この単純で、魅力的で、説得力のある信仰は既製品の―できあがった姿で始めからあった訳ではなく、何らかの理由でその信仰を考案し、発展させ、更にそれらに恒久的な制度化した形を与えようとする必要性、衝動、能力を持っていた人々もしくは文明が創り出したものであった。そしてこの聖婚の儀式を、最初に宗教的信仰心と儀式的実践との基本的要素として考案し、発展させたのは、前3000年紀初頭のシュメールの思想家、神官、詩人たちであったことは疑う余地がない」
五「聖なる結婚と『ソロモンの雅歌』」では、『旧約聖書』を読む上で重要とされている「雅歌」について以下のように述べられています。
「『雅歌』もしくは少くともその相当な部分は、最も古い時代からメソポタミアで勢力のあった地母神と太陽神とが再会し、結婚式をあげるという、古代ヘブライ人の儀礼を変形し、通俗化したものである。この聖婚は遊牧民であったヘブライ人が、彼らの隣人であり都市化されていたカナン人から受け継いだ豊饒儀礼の一部であったが、後者はそれをまたシュメール人のドゥムジ・イナンナ崇拝の変形であるアッカド人のタンムズ・イシュタール崇拝から借用していた」
続けて、著者は以下のように述べています。
「このことはまったく驚くには当らない。というのも、聖書学者たちによって繰り返し注目されてきたように、聖書の多くの巻にこの豊饒儀礼の痕跡が見出され、予言者たちの厳しい非難にもかかわらず、その種の儀礼はすっかり根絶するには至らなかったからである。実際、予言者たちでさえその儀礼から幾つかの象徴的表現を借用することをためらわなかったし、しばしば予言者の書の中では、ヤハウェとイスラエルとの関係を夫と妻として描写している。そのことはメソポタミアのイシュタール・イナンナのカナンでの姿である女神アスタルテとヤハウェとの間に聖婚がとり行われていたことを示している」
さらに、著者は以下のように述べるのでした。
「ミシュナ期、つまりほぼ旧約聖書の結集時代になってさえ、エルサレムの乙女たちは贖罪の日の終わりや『木々の祭り』の期間中に、葡萄畑に踊りに出かけたことが記録されている。そして、彼女たちは次のようにうたう若者たちに出会う。『やって来て、見つめてごらん、シオンの娘たちよ、ソロモン王とその婚礼の日に、彼の母なる人が彼にかぶせた王冠を。その日、彼の心は大喜びした』(「雅歌」3-11)。この記録もまた、古代へブライ人の聖婚の儀式のほとんど消えかかった、後世の残存物である」
さて、シュメールといえば、岩刻文字のペトログラフが思い浮かびます。
ペトログラフ(petro-graph)またはペトログリフ(petro-glyph)のペトロとは岩石、グラフ(グリフ)とは文字や文様を意味するもので、ギリシャ語語源の英語です。ペトログラフとは「先史時代から岩石に彫り残された文字や文様」のことで、世界中の先史時代遺跡から発見されています。最も古いものではベーリンジアから北米にかけて10万年前に発見されたもので、10万年前にモンゴロイドがベーリング地峡経由で北米に移動したとされる時期のものがあります。
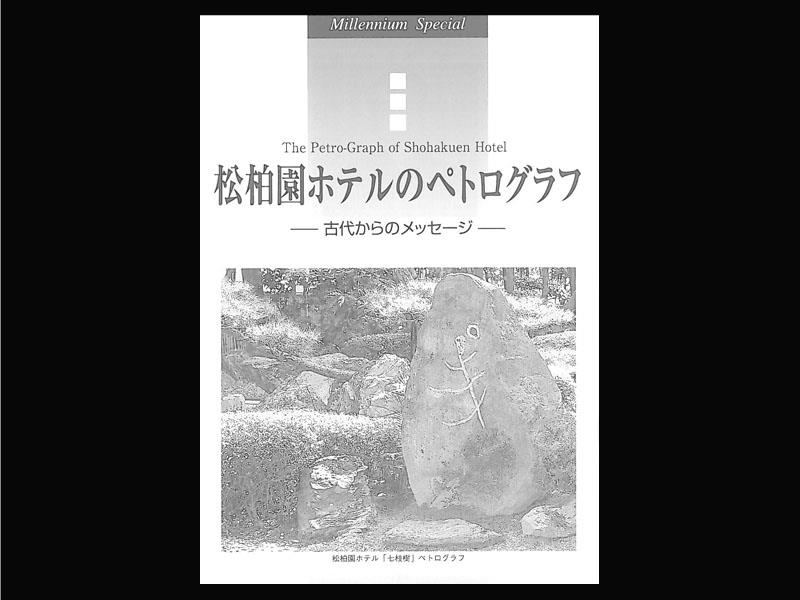 『松柏園ホテルのペトログラフ』のブックレット(2000年刊行)
『松柏園ホテルのペトログラフ』のブックレット(2000年刊行)
じつは、わたしが経営する北九州市小倉の松柏園ホテルの庭園からペトログラフの刻まれた巨石が発見され、大きな話題になったことがあります。『松柏園ホテルのペトログラフ』というブックレットで、日本におけるペトログラフ研究の第一人者である吉田信啓氏(ユネスコ岩石芸術委員、国際岩石学会連合日本代表、日本ペトログラフ協会会長)が書いています。
「昭和62年11月3日、小倉北区上富野の松柏園ホテルで日本ペトログラフ協会の武島和仁氏(古神道の宗教家)、稲富十四郎氏(下関市議会議員)、石井丈嗣氏(下関市教育委員会嘱託埋蔵文化発掘担当者)と私とで役員会を開いていた。ホテルロビーから見える人工滝の岩を眺めた武島氏が、『あれは気になりますね』と呟いた。たまたま夕日が斜めに射して、滝の組み石の1つを明るく照らしていた。そこで3人が角度を変えて眺めたところ、確かに線刻がある。それはどう見てもシュメールのウル、ウルク朝ゆかりの七枝樹に見える」
 松柏園ホテルの庭園で発見されたペトログラフ
松柏園ホテルの庭園で発見されたペトログラフ
続けて、吉田氏は以下のように書いています。
「岩は畳1枚大で厚さが50センチほどのものだが、精査したところ、やはり長さ50センチ、幅30センチほどの大きさの線刻があるのが確認できた。くだんの岩は、高さ2メートル、幅1メートル、厚さ60センチの花崗岩だが、その中央からやや右寄りに、古代シュメールで『豊穣』を意味する7本の枝のある『七枝樹』があり、その右上に直径約6センチの日輪を意味する盃状穴がある。盃状穴とは先史時代に世界中の主要な遺跡で見つかるもので多くは当時の太陽や星の信仰に関係するものとされる。但しハワイ諸島では『子孫の繁栄を祈る』ためのピコと呼ばれる同心円をつないだものや、盃状穴を連結したものがみられる」
 松柏園ペトログラフの説明板
松柏園ペトログラフの説明板
「驚いた吉田氏は、早速ホテルの村上マネージャー(当時)経由で佐久間進社長(当時)に連絡し、社長夫妻がすぐにかけつけ、『5000年も前の貴重なものが見つかるとは有難いこと』と大喜びされた。その場で日本古神道平安神殿鳥畑道場主催の武島和仁氏が祝詞を奏上し、お祭りした。祭祀が済んだ後で佐久間社長はその岩のいわれについて、『父の代に大分県の宇佐川の上流のどこからか庭師が運んできたものです』と説明された。実はこの一言が後で重要な大分県での発見に繋がる」
この大発見は、NHKニュースや各新聞でも大きく報道されました。わたしはこのとき社会人1年生として東京で働いていましたが、この報せを聞いて仰天したことを憶えています。処女作の『ハートフルに遊ぶ』(東急エージェンシー)にも書きました。
 松柏園のペトログラフについて書いた『ハートフルに遊ぶ』
松柏園のペトログラフについて書いた『ハートフルに遊ぶ』
ところで七枝樹とは、どういう意味があるのでしょうか。
吉田氏は、以下のように述べています。
「七枝樹マークは、世界最古のものとしてはメソポタミアにあったシュメールのウルクやウルなどの王朝では都市の守護神とされた『豊穣の神』の徴であり『生命の木』として崇敬された。七枝樹は紀元前5000年のシュメール語では『イシブ・イシェバ・ザサル・アメール』と呼ばれた。その意味は『霊験あらたかな3と4の枝の木』である」
「豊饒」や「生命」とは、つまるところ「産霊」ということです。
つまり、「結婚」です。松柏園の巨石に刻まれている七枝樹は「結婚」を意味するのです。この重要性を踏まえて、松柏園ホテルでは、スーパーリニューアルの際に、七枝樹の巨石を祭った「シュメールの結婚神殿」を新築することが予定されています。
「七枝樹」文様は国内では松柏園ホテルの他に、大分県宇佐郡安心院町の京石遺跡、福岡県粕屋郡宇美町の宇美八幡にある「韓石」、下関市彦島の杉田丘陵の「不思議な絵文字石」や広島県宮島の彌山頂上、岐阜県恵那市の笠置山頂上にある「見晴らし岩」、熊本県人吉市高塚山などで見つかっており、「シュメール由来の豊穣神信仰のしるし」とされています。
ペトログラフやロックアートは人類文化史解明の最古かつ最新の学術資料として活用されている。「七枝樹」ペトログラフ1つをとっても、それは既述したように「生命の木」として崇敬され、古代メソポタミアから古代中国、古代インドに同じ形状の線刻が見られ、崇敬の対象でした。それはメソポタミアにあっては「ナツメヤシ」とか「麦の穂」からデザイン化されたと言われます。ところがそれがインドに渡ると、菩提樹に代わり、日本では湯津楓(ユツカツラ)となって、綿津見神の居城である竜宮の門の樹木となり、非時香菓の若木ともなりました。
紀元前3000年紀のウルク王朝で使われた円筒印章に現われた「七枝樹を挟んで座る蛇女神キと牡牛神ハル」の蛇女神は、秦始皇帝の青銅器には同じく「蛇女神」として現われているし、日本では伊弉冉(イザナミ)の大神です。牡牛神(ハル)は日本では伊弉諾(イザナギ)大神に当てることが出来よう。もっとも仏教が日本に入ってからは牡牛神は牛頭(ゴズ)権現として須佐男命(スサノオノミコト)と重ねた捉え方に変わる。このように、ペトログラフ学の展開によって世界の文化史、宗教史が解明出来るのです。
なんという壮大なロマンでしょうか!
 『松柏園ホテルのペトログラフ』に、吉田氏は以下のように書いています。
『松柏園ホテルのペトログラフ』に、吉田氏は以下のように書いています。
「『古代世界に帰れ!』(Back to Ancient World)というモットーがここ10年来、ハーバード学派を中心とする欧米の学会で唱道され、世界のペトログラフ学者と研究機関は北極圏の氷に閉ざされた岩石はもとより、アフリカの原野、パプアニューギニアの峡谷、オーストラリアの砂漠、モロッコやサハラの砂漠、アリゾナの荒野、ボリビアやペルーの4000メートルを超える山地、中国は寧夏回族自治区の3500メートルの賀蘭山山塊、北東シベリアの極寒地、南太平洋の島々、ポリネシア諸島など考えられる先史文明の痕跡を求めて、あらゆる地点でペトログラフとロックアートを探索する。その目的は、『人類の文字文化のルーツを辿り、原点を突き止め、当時の世界信仰の中心に至れ。そうすれば宗教の派閥抗争のない世界平和が実現できるかも知れない』というロマンに他ならない」
宗教の派閥抗争のない世界平和の実現を!
そしてブックレットの最後で、吉田氏は以下のように述べるのでした。
「松柏園ホテルのペトログラフの岩を見るとき、その岩が人類文化史の重要ポイントの1つであるという認識を以て観察と思考の一時を過ごして頂きたい。なぜならそのような思考と思念の集積がやがて、一般化し日本中に広がった時、更なるペトログラフ資料の発見が予想されるし、それらの学術資料によって、『日本が人類文字文化の原点にあった。やはり日本は世界に冠たる神の国であった』という神話を超える哲学が導き出されるからである」
