- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2016.09.30
『人生を変える読書』美達大和著(廣済堂新書)を読みました。 「無期懲役囚の心を揺さぶった42冊」というサブタイトルがついています。そう、著者は、この読書館でも紹介した『死刑絶対肯定論』の著者でもあります。本書は、獄中からの「読書のすすめ」なのです。
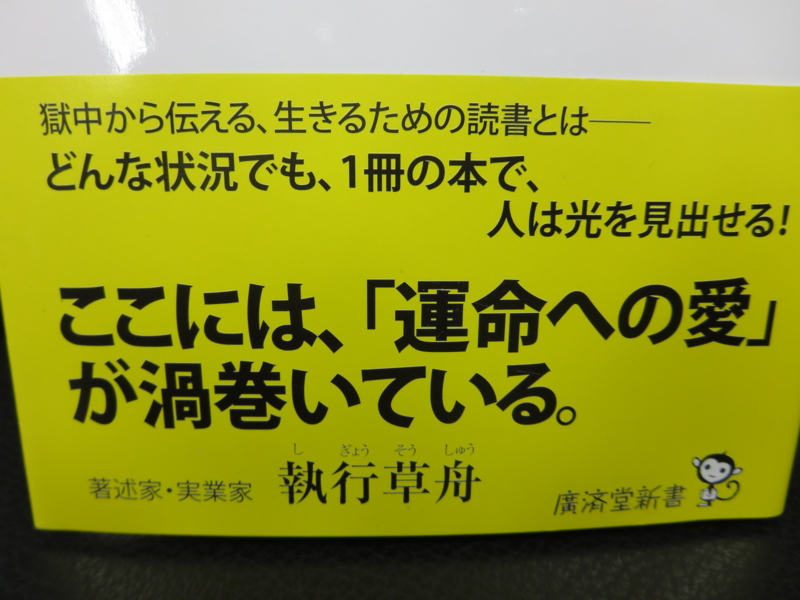 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「獄中から伝える、生きるための読書とは―どんな状況でも、1冊の本で、人は光を見出せる!」と書かれ、著述家・実業家の執行草舟氏の「ここには、『運命への愛』が渦巻いている」という言葉が紹介されています。
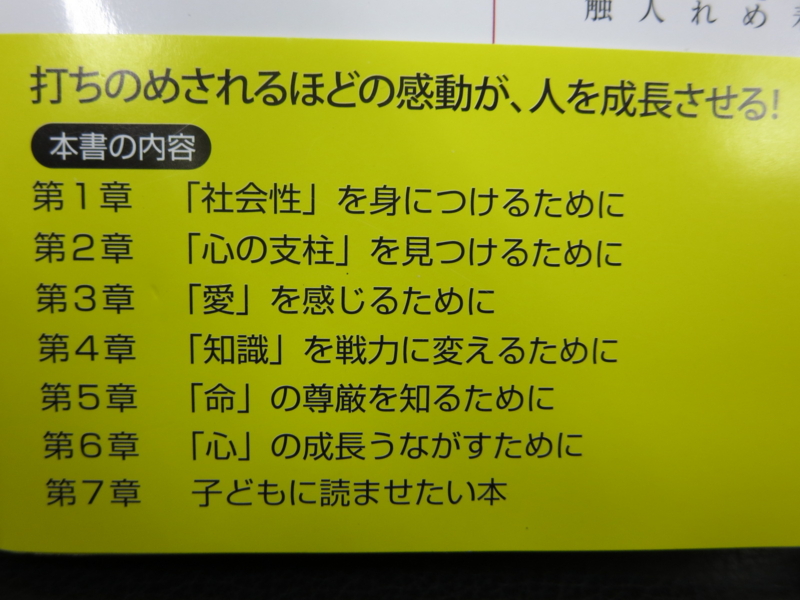 本書の帯の裏
本書の帯の裏
また、カバー裏には以下のような内容紹介があります。
「獄中で数万冊を読破する”本の虫”の著者が、読書を通じて辿り着いた答えは『本で人は変われる』ということ。本書では、生きるために必要な概念や知識が得られる本を、意欲や情熱が呼び覚まされる本を紹介。ビジネスや人間関係を好転させるための読書とは、人生を豊かにするための読書とはどういうものか、本書の持つ熱に触れ、自分だけの珠玉の1冊を、ぜひ見つけてください」
本書の「目次」は、以下のような構成になっています。
「はじめに」
第1章 「社会性」を身につけるために
コラム「獄中でする読書」
第2章 「心の支柱」を見つけるために
コラム「『速読』と『精読』の方法と、本の読み方について」
第3章 「愛」を感じるために
コラム「本の内容を記憶する方法」
第4章 「知識」を戦力に変えるために
コラム「知識はどのように活用すればいいか」
第5章 「命」の尊厳を知るために
コラム「専門書・学術書を読む時に大切なこと」
第6章 「心」の成長をうながすために
コラム「小説を読む時に大切なこと」
第6章 子どもに読ませたい本
コラム「自分に合う本の見つけ方」
「あとがき」
「獄中読書日記」
「はじめに」の冒頭で、著者は以下のように自己紹介をしています。
「私は美達大和と申します。現在、2件の殺人事件により無期懲役囚として、刑期10年以上の者が収容されるLB級刑務所に服役しています。殺人事件といっても衝動ではなく、計画して実行した確信犯でした。当時、妄信していた歪んだ信条によって決行したのです」
そんな無期懲役囚の著者ですが、以下のように書いています。
「私は”本の虫”で、社会にいた頃は毎月、単行本を100冊から200冊(盆や年末年始には300冊前後)、週刊誌20誌、月刊誌を80誌から100誌ほど読むのが、完全に生活の一部でした。服役した頃は、学習用のものも含めて、毎月8冊という著しい制限があったのですが、旧監獄法が平成18(2006)年に改正されて制限がなくなったので、月に80冊から120冊前後(最高は250冊)を、文字通り1分1秒を惜しんで読んでいます」
なぜ、無期懲役囚がそんなに本を読むのか。著者は述べます。
「アリストテレスの『形而上学』の冒頭に、『人間は知りたがる動物』ということが書かれていますが、それはまさに私のことで、小さい頃から何でも知りたがる”質問魔”だったのです。そのため、本もさまざまなジャンルにわたって読んできました。そういう読み方を重ねていると、ある日、別々の分野の知識、たとえばルネッサンスと活版印刷技術の関わりや、18~19世紀のベートーヴェンの音楽と哲学・文学の潮流の関係など、離れていたことが、予期せず有機体のようにつながります。ニュートンは、それを『巨人の肩に乗る』といいましたが、知の底で互いに関連性を持っていることを知った時、私は胸奥で快哉を叫んでいたものです」
アリストテレスとかベートーヴェンとかニュートンといった名がポンポン出てくるあたり、著者が単なる囚人ではないことがわかりますね。
また、著者は自身の生き方を振り返って、以下のように述べています。
「社会にいた頃は、稀少価値であらねばと働いた私は、20代半ばより10桁の収入を得て贅沢三昧の暮らしをしていましたが、拘置所の独居房(現在は単独室と呼称)に入った時、季節は冬で火の気のない部屋は、四六時中、吐息が白くなるほど、冷え冷えとしていました。その時、私は終戦後にソ連の収容所(ラーゲリ)に抑留された日本軍人の物語や、帝国ロシアやソ連の作家が書いたシベリヤ監獄の物語をあまた渉猟しては、己の寒さなど児戯に類するもの、何ほどのことでもないと笑い飛ばしていたものです。先人たちのように、マイナス40度、50度の中、満足な防寒着もなく、粗末な衣服で空腹に堪えつつ重労働をするわけでもなく、食事も不足することがない生活は、サナトリウムにでも入ったようなものだと、己に言い聞かせる日々でした」
そんな著者は、以下のように読者に訴えます。
「人はいくらでも変わり得るのです。本人さえ諦めていなければ。それまでの己の精神に新たな風をはらんで、違う世界を覗くことも不可能ではありません。本書はそんな本との出会いをしてほしいという、期待と確信を込めた1冊になりました」
著者によれば、1冊の本と出会うことで、気力・勇気・知恵を得て、自分を肯定できる、あるいは再発見できる書を、また精神のあり方や生き方に変化が起こるような、刺激を与えてくれる書を選んだとのこと。また、私自身があれだけ本を読みながら、なぜ愚かなことをしたのか、その変わらなかった部分や倫理を超えてしまった原因はどこにあるのか、加えて本を読むことで変わった面と変わらなかった面についても考察してみたそうです。
第1章「『社会性』を身につけるために」では、『影響力の武器[第二版]―なぜ、人は動かされるのか』ロバート・B・チャルディー二著、社会行動研究会訳(誠信書房)が紹介されます。心理のメカニズムから「説得」する方法を知るための本ですが、著者の美達氏は以下のように述べています。
「不動産業では初めに老朽物件をいくつか見せて失望させてから、それらよりましな本命物件を見せるという、コントラストの原理を使うのが常套手段です。また、外車販売で実際にあったことでは、プライスカードを他の車と間違えて、100万円近く高い値でお客さんと交渉したことがありました。途中で誤まりに気づいたのですが、価格が下がった途端、当初の予算を超えていたにもかかわらず、すんなり売れたのでした。お客さんとロールス・ロイスやフェラーリなど何千万円もする車の話をしたあと、数百万円の車を勧めると、大きな抵抗もなく買うという例もありました」
第2章「『心の支柱』を見つけるために」では、『ココダの約束―遺骨収容に生涯をかけた男』チャールズ・ハベル著、丸谷元人監修、北島砂織訳(ランダムハウス講談社)を紹介します。友との約束を果たすために人生を捧げた魂の記録ですが、この本について美達氏は以下のように説明します。
「主人公は西村幸吉。大東亜戦争中に、パプアニューギニアのポートモレスビー作戦に参加し、オーストラリア軍との壮絶な戦闘のあと、42名の部隊のうち唯一、生還しました。食糧もなく、マラリアに罹患しながら、不退転の決意で戦う中、ばたばたと斃れていく戦友たち。何倍もの人員を誇る敵に追撃された際、将校は負傷して動けない兵士にひと言も告げず、撤退を決めたのでした。その戦友たちに、西村はこう言ったのです。『もし、お前たちがここで死ぬようなことがあっても、俺たちが必ずその骨を拾って、日本にいる家族に届けてやるからな』これが、西村にとっての誓いとなりました」
第3章「『愛』を感じるために」では、『飛鳥へ、そしてまだ見ぬ子へ―若き医師が死の直前まで綴った愛の手記』井村和清著(祥伝社)を紹介します。愛する者のために「自分が今できることは何か?」を問う本ですが、美達氏は以下のように述べます。
「肺への転移により、著者は自分の死を目前のものと知り、『けるところまで歩いて歩いていこう』決心した日の夕暮れについての記述は美しいものでした。彼が目にした光景は、世の中がとても明るく、スーパーへの買い物客や子どもたちや犬や電柱や小石までもが輝いて見えたのです。自宅へ戻って見る妻も、手を合わせたいほど尊く見えた、とあります。これは親鸞が『可思議光』呼んだ光に出会った際の現象で、生への執着が消えて死への恐怖もなくなり、安らかで清らかな心ですべてを許し、感謝できるという状態です」
第5章「『命』の尊厳を知るために」では、『SHOAH ショア』クロード・ランズマン著、高橋武智訳(作品社)を紹介します。絶滅収容所から生還した人々の戦慄の命の記録ですが、美達氏は以下のように述べています。
「ナチス党員・ドイツ軍人にしても、人の心は持っていましたし、同じ仲間、家族に対しては人間と認識していたのです。殺さなければ自らの命が危ないという事情もありますが、人命がただの処理する対象・数となった意識が悲劇となりました。あの惨禍については時効はなく、元ナチスの隊員が今も逮捕されることがあるのです。ユダヤ人には賠償もしていて、区切りもついています。日本の戦争責任と謝罪について、ドイツの場合と比べられますが、日本は初めから非戦闘員の大量虐殺を国家として計画したことはなく、同列に語れるものではありません。残念ながら、日本は戦争に対しての総括に失敗したせいで、国論が二分されていますが、戦争においての国家が持つ両義性について、虚心に考察するべきです」
また美達氏は、『日本原爆詩集』大原三八雄・木下順二・堀田善衛編(太平出版社)も紹介しています。全人類に向けた被爆者の慟哭と、平和への声明の216篇の詩が集められた詩集ですが、美達氏は述べます。
「原爆は爆心地の人間を一瞬で痕跡もなく消してしまいます。実験でそれを知っていながら、アメリカは非戦闘員を含む大量殺戮のために使いました。たび重なる日本への空襲も原爆投下も、非戦闘員の死を前提として実行されたのです。これは当時のジュネーブ条約に明確に違反した戦争犯罪になりますが、日本は負けたために裁くことはできませんでした。被害に遭った人々の無念さだけが残ったのです」
さらに美達氏はの想いは募り、以下のようにも述べます。
「人間が何の痕跡も残さず、一瞬で消滅させられるというのは、個々の人間の尊厳すら与えられないということです。 何万、何十万という数字に置き換えられる死とは、何だったのでしようか。中には、子どもといえども軍需工場で働いていたから、空襲や原爆投下など仕方がないという低劣な思考の日本人もいるようですが、子どもである点を無視して、行為の本質ではなく、表面上のロジックでしか語れない愚かしさでしかありません。戦争を惹起したのは、子どもではなく大人でした。遺骨さえなく肉親を失い、現在も後遺症に苦しんでいる人が多いことを、日本人として思いやるべきです。そして、再び戦争にならないためにも、幻想や空理空論ではなく、実のある思考を持つ時ではないでしょうか」
わたしは、「人間が何の痕跡も残さず、一瞬で消滅させられるというのは、個々の人間の尊厳すら与えられないということです」という美達氏の言葉に深い共感を覚えました。そして、この言葉から、わたしは、この読書館でも紹介した島田裕巳氏の『0葬』の内容を連想しました。 現在の日本では、通夜も告別式もせずに火葬場に直行するという「直葬」が増えつつあります。あるいは遺灰を火葬場に捨ててくる「0葬」といったものまで注目されています。ただ、わたしたちは「直葬」や「0葬」がいかに危険な思想をはらんでいるかを知らなければなりません。葬儀を行わずに遺体を焼却するという行為は、ナチス・オウム・イスラム国の巨大な心の闇に通じているのです。そして、絶滅収容書所も原爆も0葬も、「何の痕跡も残さず」に人間を消滅させる行為にほかならず、絶対に許すことはできません。わたしは、『0葬』に対抗して『永遠葬』という本を書きました。ぜひ、美達氏に読んでいただきたいです。
そして、第7章「子どもに読ませたい本」では、『夏の庭』湯本香樹実著(新潮文庫)を紹介します。一人暮らしの老人と3人の少年の交流を描く清新な名作ですが、テーマは親しい人、身近な人の死です。少年たちは老人の死を体験するのですが、美達氏は以下のように述べています。
「昔と違って祖父母と住む家庭が減り、多くの人にとって『死』が身近でなくなってきています。それと共に老人の存在や、老人と接する機会も確実に減ってきました。子どもだけではなく、成人後も老人は自分と別の種類の人間だと思う人が少なくないようです。 加えて、ゲームやマンガなどにより、『死ぬということ』はどういうことなのか理解できず、リセットしたら生き返ると信じている子どもも珍らしくないと聞きます。そのような子どもたち、若者たちに老人の存在を身近に感じさせ、親しみを持たせると同時に、死の問題を自分で考えてみる、想像してみるきっかけとなる書です。より正しく言えば、死を考えるというのではなく、死を感じさせることが子どもにとっての『死の教育・死の存在』になります」
この美達氏の意見には、わたしもまったく同感です。 わたしは、子どもたちに「死ぬということ」を知ってもらうために、セレモニーホールでの少年少女向け模擬葬儀を計画しています。葬儀の場を体験することは、「命」について考える契機となり、大きな学びとなるはずです。この模擬葬儀を「いのちの教室」と名づけたいと思います。 それにしても、美達氏の見識には感服しました。この人は無期懲役囚でありながら、豊かな読書によって、「死生観」という最高の教養を身につけた方だと思います。思えば、佐藤優氏や堀江貴文氏も、獄中で大量の本を読破しています。古くは吉田松陰もそうです。獄中というのは、ある意味で究極の読書空間なのかもしれません。可能ならば、美達氏に拙著『永遠葬―想いは続く』(現代書林)を差し入れしたいです。
