- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.1401 宗教・精神世界 『大乗仏教概論』 鈴木大拙著、佐々木閑訳(岩波文庫)
2017.03.15
『大乗仏教概論』鈴木大拙著、佐々木閑訳(岩波文庫)を読みました。
著者は禅についての著作を英語で著し、日本の禅文化を海外に広くしらしめた仏教学者です。著書約100冊の内23冊が、英文で書かれています。哲学者の梅原猛氏は著者を「近代日本最大の仏教者」と評しました。1949年に文化勲章、日本学士院会員。名の「大拙」は居士号です。
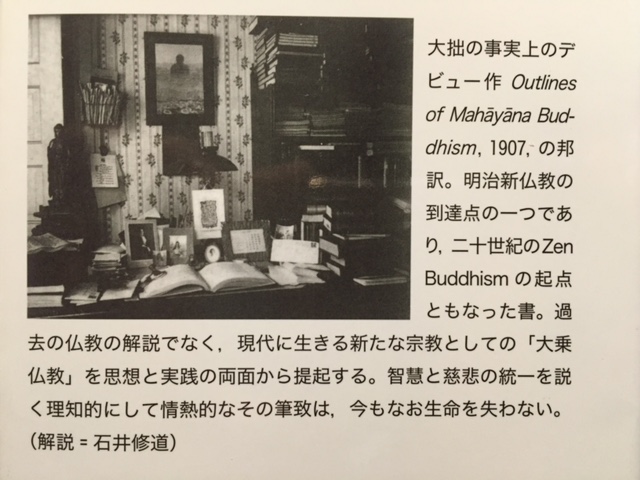 本書の表紙
本書の表紙
本書のカバー表紙には、以下のような内容紹介があります。
「大拙の事実上のデビュー作 Outlines of Mahayana Buddhism、1907、の邦訳。明治新仏教の到達点の一つであり、二十世紀のZen Buddhismの起点ともなった書。過去の仏教の解説でなく、現代に生きる新たな宗教としての『大乗仏教』を思想と実践の両面から提起する。智慧と慈悲の統一を説く理知的にして情熱的なその筆致は、今もなお生命を失わない。(解説=石井修道)」
本書は、37歳の大拙がアメリカ滞在時代、大乗仏教の意義とその理想を西洋社会に知らしめるために、満身の気概と情熱をもって執筆した作品です。大乗仏教の核心を経典類に拠りながら二分野に分けて論じています。すなわち、形而上学、思弁の学としての「思索的」な面と、教えに基づく実際の信仰の在り方、究極的な目的である衆生済度に至る道程としての「実践的」側面です。本書により初めて本格的に大乗仏教が西洋に紹介され、M・ウェーバーを始め、欧米の研究者に大きな反響を呼んだとされています。
本書の「目次」は、以下のような構成になっています。
「凡例」
「序」
序論
第一節 大乗仏教と小乗仏教
第二節 大乗仏教は仏陀の真の教えか?
第三節 大乗仏教の教義に関する誤った説
第四節 宗教の重要性
第一章 仏教の一般的特性
第二章 大乗仏教の歴史的性格
思索的大乗仏教
第三章 実践と思索
第四章 知識の分類
第五章 真如(bhutatathata)
第六章 如来蔵とアーラヤ識
第七章 無我説
第八章 業
実践的仏教
第九章 法身
第十章 三身説(仏教の三位一体説)
第十一章 菩薩
第十二章 菩薩道の十段階―我々の精神生活の階梯―
第十三章 涅槃
付録「大乗賛歌」
「注」
「訳注」(佐々木閑)
「訳者後記」(佐々木閑)
「解説」(石井修道)
序論の第一節「大乗仏教と小乗仏教」で著者は以下のように述べます。
「大まかに言うと、大乗仏教と小乗仏教の違いは次のようなものである。大乗仏教は自由で革新的だがあまりに形而上的すぎる点も多い。深い思索に満ちており、それが輝くばかりの卓越性を示すこともしばしばである。他方、小乗仏教は保守的な面が強く、多くの点で、単なる合理的倫理体系と考えることもできる、そういうものである」
続けて、著者は大乗仏教と小乗仏教の違いについて述べます。
「大乗とは『大きな乗り物』、小乗は『小さな、もしくは劣った乗り物』という意味であり、それは救済するための乗り物の状態を指している。このような区別を考えるのは大乗仏教徒の方だけである。彼らは、自分たちの方が革新的で、同化力にすぐれていると考えて、ライバルの同朋たちを、小乗仏教という好ましからざる名称で呼んだのである。当然のことながら、小乗仏教徒たちは、大乗の教義を仏陀の正統説として認めることを拒み、自分たち以外の仏教などあり得ないと主張した。彼らにとって大乗のシステムは、言うまでもなく一種の異端だったのである」
また、「創始者の真の教義を代表する仏教が2つ並んで存立するとは一体どういうことなのか」という問いに対して、著者は以下のように答えます。
「概して偉大な教祖の教えというものは非常に一般的で、幅広く、多面的なものである。それゆえ、弟子たちはそれをいろいろなかたちに自由に解釈することができるのである。この包括生があるからこそ、願うところも性格も修練のかたちも互いに異なる信者たちみんなが、それぞれに、師の教えによって心の欲求を満たすことができるのである」
さらに著者は、運動の創始者について以下のように述べています。
「運動の創始者というものは、その運動が知的なものであれ、霊的なものであれ、その細かい部分や、それがもたらす結果にまで思いをかける余裕などないのである。その運動の原理を同時代の人々に理解してもらい、基盤が確立した段階で、創始者としての役割は完了するのであって、残りの仕事はきちんと後継者たちが引き受けるのである。彼らはその仕事に着手し、細部にわたって仕上げていく。そしてその間、状況に応じて、必要とされるあらゆるかたちの変更、修正がなされていく。だからこそ、創始者が果たすべき役割は、必ず非限定的で包括的なものでなければならないのである」
続けて、著者は以下のように述べます。
「たとえばドイツ哲学の推進者としてのカントは、ヤコービ、フィヒテ、ヘーゲル、ショーペンハウアーといった実に様々な哲学体係の生みの親となったが、彼らはそれぞれに、カントによって非限定的あるいは暗示的あるいは間接的に語られた諸問題を発展させようと努めたのである。ユダヤ教に対抗する革命的運動の煽動者であったナザレのイエスは、後のキリスト教の博士たちのようなお定まりの神学教義など何も持っていなかった。彼の考えはきわめて非限定的であったため、大方の弟子たちは神の国の地上への出現に対して空想的な期待を懐いていたにもかかわらず、すでに直弟子たちの中にさえ一種の見解の相違を生みだしていたのである。しかしそういった外面的枝葉末節はいずれ消滅するものであって、一旦偉大な指導者によって呼び覚まされた運動の精神が、さらに強力で高尚なものへと成長していくことを押しとどめることはできない」
そして、著者は以下のように述べるのでした。
「同じことが仏陀の教えについても言える。彼が信者たちに植えつけたのは、現在では仏教として知られている宗教組織の構神であり、この精神に沿って、信者たちはそれぞれの願望や環境に応じて、その教えを発展させた。それが結果として大乗仏教と小乗仏教の違いを生みだしたのである」
大乗仏教とは何か。「大乗仏教の定義」として、著者は述べます。
「大乗とは、進歩的精神に触発されることによって、仏陀の教えの真の重要性と矛盾しない限りにおいて、その本来の視野を拡大した仏教なのであり、別の宗教的・哲学的信念を同化することで様々な性格・知的資質の人々を一般広範囲に救うことができるとなれば、いつでもそれを実行してきた仏教なのである」
第二節「大乗仏教は仏陀の真の教えか?」では、著者は「成長しない生命など存在しない」として、以下のように述べます。
「仏教の中の大乗という宗派が、外部インド社会の宗教・哲学体系から取り込まれた要素をなにほどか含み込んでいるのは間違いない。しかしだからどうだと言うのか。キリスト教にしたところで、いわゆるユダヤ、ギリシャ、ローマ、バビロニア、エジプトおよびその他の異教思想の融合体ではないのか。実際、健全で強い宗教というものは、発展過程において、常に変化しつづける外界に自己を適応させ、はじめはその存在を脅かすかに見える様々な要素を内部に取り込んできたという意味で、歴史的なのである。キリスト教の場合、この同化・適応・改造の過程は、その最初期段階から続いてきた。その結果、今日のキリスト教においては、外見を見る限り、その元の形がすっかり変形しているため、それが原形の忠実なコピーであるなどと考える者は誰もいないであろう」
第四節「宗教の重要性」では、著者は「信仰の内容は多種である」として、以下のように述べています。
「宗教の恒久的要素は、人の心の最奥に秘められている神秘的感情から起こるものであり、主にその感情によって構成されている。そしてその神秘的感情が目覚めた時には、人格の全体を揺さぶって、大きな精神的革命を引き起こし、ついには人の世界観を全く変えてしまうのである。この神秘的な感情が知的な言葉で表現され、その概念が形式化された時、それは明確な信念の体系となる。普通それが宗教と呼ばれるのだが、正しくは教条主義すなわち宗教の知性化された形と呼ぶべきである。一方、宗教の外的なかたちは、個々人の美的感情のみならず、時とともに進む知的、道徳的な発展によって主に決定される可変要素によって構成されている」
続けて、著者は仏教とキリスト教の共通性について述べます。
「したがって、真のキリスト教徒と啓発された仏教徒との間には、我々の存在の土台を構成する内奥の宗教的感情を認めるという点で共通性を見いだせるかもしれない。ただし、この同意点があるからと言って、彼らが信仰の概念と表現に関するそれぞれの独自性を放棄することは決してないのであるが。私が確信することは以下のことである。すなわち、もし仏陀とキリストの生まれた場所が逆だったとしたら、ゴータマはユダヤ教の伝統主義に反抗するキリストとなっていたかもしれないし、一方のキリストは仏陀となって、無我や涅槃、法身といった教義を説いていたであろうということである」
また、著者は仏陀とキリストに言及しています。
「仏陀もキリストもそうである。彼らは、どんどん堕落し続け人間性の発展をおびやかしていた当時の既存の制度に対抗する思想と感情の具体的な代表者であったにすぎない。しかし同時にまた、それらの思想と感情は『永遠の魂』の噴出である。それは時として、歴史的な偉人とか世界の大事件を通して、その意志を荘重に告げ知らしめることがある」
仏教とキリスト教の両方の要素が入った神秘主義思想として、ブラヴァツキー夫人が創始した「神智学」が有名です。第一章「仏教の一般的特性」では、著者はその神智学に言及して以下のように述べています。
「ある神智学者たちによって教示された、ある種の天界的存在を霊魂と同一視するという不合理は、名称とそれに対応する対象との混同に原因がある。霊魂、あるいは世俗の考えによればそれと同じものだとされている我というものは、ある種の精神的共同作業に対してつけられた名称である」
続けて、著者は抽象名詞について、以下のように述べます。
「抽象名詞というものは、我々の知的活動を効率化するために発明されるものであり、当然のことながら、具体的な物質世界の中にある個別存在とは違って、それには対応する実在がない。世俗の者たちは、その抽象名詞成立の歴史をずっと忘れてきた。特定の名称に対する特定の客観的実在や具体的事物を見つけだすことにずっと慣れてきたため、そういった素朴な現実主義者たちは、名前というものは、その性質とは無関係にどんなものでも、この感覚世界の中にそれと対応する具体的な事物を持っているものだと想像する。彼らの観念論あるいはいわゆる心霊主義とは、実際には粗雑な物質主義にすぎない。それこそ彼らが、無神論であり、不道徳でさえあるとしてひたすらに恐れる考えではないか。まさに無知の呪いである」
実践的仏教の第九章「法身」では、「より詳細な特徴づけ」として、著者は以下のような仏陀の言葉を紹介しています。
「汝ら、仏陀の息子たちよ。それは太陽のようなものである。太陽の光が地上のあらゆる生き物にもたらす恩恵は計り知れない。たとえば、闇を一掃することですべての草木、穀類に滋養を与え、湿気をなくし、天空を輝かすことで空中のすべての生き物に恩恵を与え、その光線が水中へと進み入ることで美しい蓮を開花させ、一切の姿形あるものを照らして、地上のあらゆる活動を成就させる。なぜかというと、太陽からは生気を与える無限の光線が発せられているからである」
第十一章「菩薩」では、著者は「菩提心の覚醒」として述べています。
「菩提心はあらゆる衆生の心の中にあるが、諸仏のうちにおいてのみ完全に覚醒し、その純粋なる雄々しさをもって活動している。一方、世俗の人々にあっては、菩提心は眠ったままであり、覚醒しないままに官能の世界と交わることで、みじめで不自由な状態にある。この点を解き明かす際に大乗仏教徒が好んで用いるのは、菩提心を天上に輝く月の光に譬える比喩である。それは次のようなものである。雲1つない夜空に月が銀色に輝く時、その姿は地上の水満の1粒1粒、水面の1つ1つに映し出される。揺れる木々の葉の上におかれた白露に映るなら、それは枝にかかる無数の真珠にも見え、日中のスコールでたまたまできたのであろう点在する小さな水溜まりに映れば、地上に落ちた星々のきらめきにも見える」
続けて、著者は以下のように述べています。
「それら水溜まりには泥に濁ったものやきたなく汚れたものもあるが、だからといって月光が自分の清浄な姿をそこに映すことを拒否するなどということはない。その月影は、牛が渇きをいやし白鳥が汚れのない羽をひたす、清浄で静まりかえった透明な湖面に映るものとなんら変わるところなく、完全である。どのようなかたちであれ、水のあるところならどこにでも、夜の女神の神々しい姿は現われる。菩提心もこれとまったく同じである。ほんのわずかなりとも心の温みのあるところならどこにでも、その状況に最適のかたちで菩提心は必ずその姿を輝き現すのである」
菩提心すなわち智慧の心はどのように覚醒するのか。
それは以下の四条件によって覚醒すると、著者は紹介します。
一.諸仏のことを考えること。
二.物質的存在の過失を省察すること。
三.衆生が生きている悲しむべき状況を観察すること。
四.如来が最高の悟りによって獲得した諸々の徳を目指すこと。
そして第十三章「涅槃」では、「結論」として本書全体の最後に、『華厳経』巻14の以下の一節を紹介しています。
「太陽神は、世界をあまねく照らしながらも見返りを求めることなどなく、そこにひとり悪人がいるからといって、その荘厳なる輝きの堂々たる顕示を中止することもなく、また、ひとり悪人がいるからといって、一切衆生の救済を放棄することもない。私の行為もこれと同じである。私の功徳をすべて廻向することで、私は同朋の全員を幸福に安楽にしたいのだ」
わが社の「サンレー」という社名には「SUNRAY(太陽光線)」という意味がありますので、この言葉は非常に心に沁みるものがありました。
「訳者後記」では、佐々木閑氏が『大乗仏教概論』について、大拙の全集に含まれない本邦未訳資料の中、若き日の鈴木大拙が自己の仏教理解を西欧に向かってはじめて正面切って主張したという点で、きわめて重要な位置に置かれるべき著作であるとして、以下のように述べています。
「鈴木大拙37歳。10年を越すアメリカでの修練も終わりに近づいたこの時、達意の英語力を自在に駆使しながら、西欧社会に大乗仏教の真髄を紹介するというスタイルのもとに自己の境地を存分に語った本書は、その後、鈴木が国際的活動を展開する、その原点となるものであった」
ベルギーの仏教学者ルイ・ド・ラ・ヴァレー・プサンは、本書に対して非常に厳しい批判を加えました。一体どのような内容か。佐々木氏は述べます。
「鈴木が自己の思想のベースとした日本仏教そのものが、本来のインド大乗仏教とは異質な仏教であり、それは仏教というよりむしろヴェーダーンタなどのヒンドゥー教哲学に近いものだという結論である。鈴木は、その日本仏教の特性を用いてインドの大乗仏教を説明しようとした。しかしインドの場合、仏教と平行して、より日本仏教に近い形態を持つヒンドゥー教という宗教が存在しているため、インド大乗仏教、ヒンドゥー教、鈴木の仏教思想という三者を比較することになり、その結果、『鈴木の思想はヒンドゥー教の方に近い』ということがはっきり目立ってしまうのである。つまり本書が示しているのは、「鈴木の思想がベースとしている日本仏教は、インド大乗仏教よりもむしろヒンドゥー教に近い考え方をする」という事実なのである」
また、佐々木氏はプサン批判後の大拙について以下のように述べます。
「鈴木はプサンの指摘を受けて、本書で示した思想の、過度にヴェーダーンタ的な部分をそぎ落とし、しかもそれを日本人に特有の思想という新たな装いのもとに西欧に紹介した。それゆえ西欧は、それを自分たちの価値観を脅かすライバルではなく、遠い未知の世界からもたらされた不思議な来客として安心して受け入れることになった。こうして、後の鈴木の思想は、キリスト教的価値観をまっこうから否定する敵対者としてではなく、むしろキリスト教的な要素を認めたうえで、そこに日本的オリエンタリズムの芳香を加えた穏やかな嗜好品として西欧に広まっていったのである」
さらに、佐々木氏は仏教について以下のように述べています。
「仏教は2500年前、釈迦によりインドで生み出された宗教である。それははじめ、比較的少量の聖典を依りどころとして運営されていた。その聖典とは、阿含という名で一括される経典群と、出家修行者の日常規則を決める律と呼ばれる規則集である。阿含と律、この2種の聖典を絶対権威とする初期の仏教は、現在の仏教世界に見られるような幅広い多様性を持つ宗教ではなかった。すなわち本来の釈迦の教えというものは、ある特定の狭い幅に限定される教義を主張するものだったのである。この、宗教としては全くあたりまえの形態をもってスタートした仏教が、ある時期激変する。特定の教義にこだわらず、様々に異なる考えを広く受け入れていく寛容な宗教へとその姿を変えたのである。その結果が、大乗仏教と呼ばれる新しい宗教形態の発生である」
大乗経典は建前としては釈迦の直説であるとされます。
しかし実際にはそれらは、ある特定の作者のインスピレーションを核として作成される著作物でした。「そのインスピレーションは、それ自身としては作者個々人の体験に基づく個別のものであり、釈迦の教えとは直接の関係はない」と佐々木氏は喝破します。そして、以下のように述べます。
「ある特定のインスピレーションを感得した人たちの中で、その体験を文章として表現できる能力のある人は、それを釈迦の真の教えとして聖典化しようと考える。あくまでそれは釈迦の直説という健前での表出であるから、『私の個人的思想はこうだ』といった言い方にはならない。語られるのはあくまで釈迦の思想である。『ある時、お釈迦様は次のように語られました』というスタイルで、彼は自己の体験を聖典化していくのである」
続けて、佐々木氏は聖典について以下のように述べています。
「そこでは、すでに存在している先行聖典、たとえば阿含や律、あるいはその時までに広がっていた別の大乗経典などの文言、スタイルが取り込まれ、そこに作者独自の見解を示す文章が適宜埋め込まれることで、全体として、『釈迦の直説というスタイルをとりながら、内容は作者独自の体験を表現する』新しい聖典が生み出されることになる。このプロセスの繰り返しが、膨大な大乗経典を集積していったのである。鈴木大拙の『大乗仏教概論』を訳してみて、私はこの本が、現代において生み出された新たな大乗経典であると感じるようになった」
そして最後に、佐々木氏は以下のように述べるのでした。
「本書を、仏教学という学問世界の中に含めず、仏教という宗教の流れに置いてみるなら、それは『般若経』や『法華経』などの経典と同レベルに並ぶ『大拙大乗経』とも呼ぶべき新たな聖典の誕生を意味していると思うのである。そしてその後も続々と出版された大拙系経典群は、多くの熱狂的信者を獲得し、大拙系仏教は今も脈々と生き続けているのである」