- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.1548 芸術・芸能・映画 『能 650年続いた仕掛けとは』 安田登著(新潮新書)
2018.04.24
『能 650年続いた仕掛けとは』安田登著(新潮新書)を読みました。下掛宝生流能楽師の最新刊です。著者には、この読書館でも紹介した『異界を旅する能』などの著書があります。
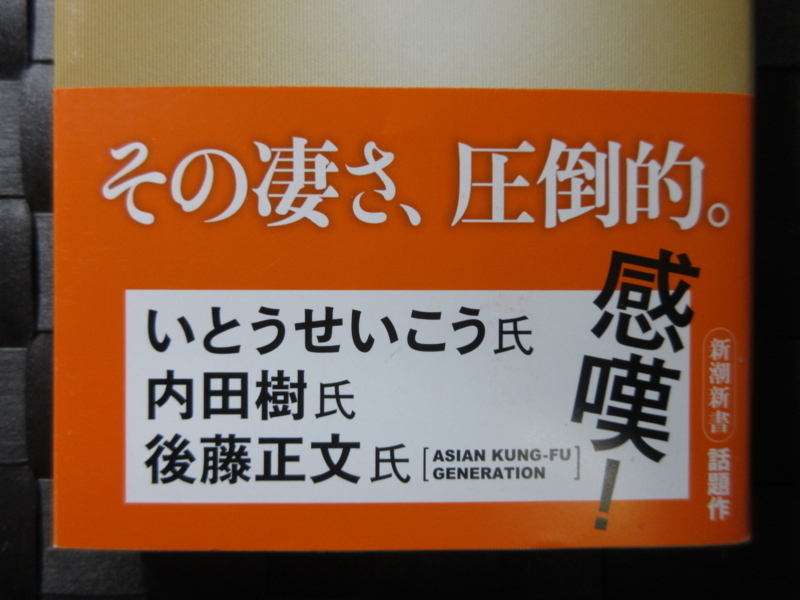 本書の帯
本書の帯
帯には「その凄さ、圧倒的。」というキャッチコピーが躍り、「いとうせいこう氏 内田樹氏 後藤正文氏[ASIAN KUNG-FU GENERATION]感嘆!」と書かれています。
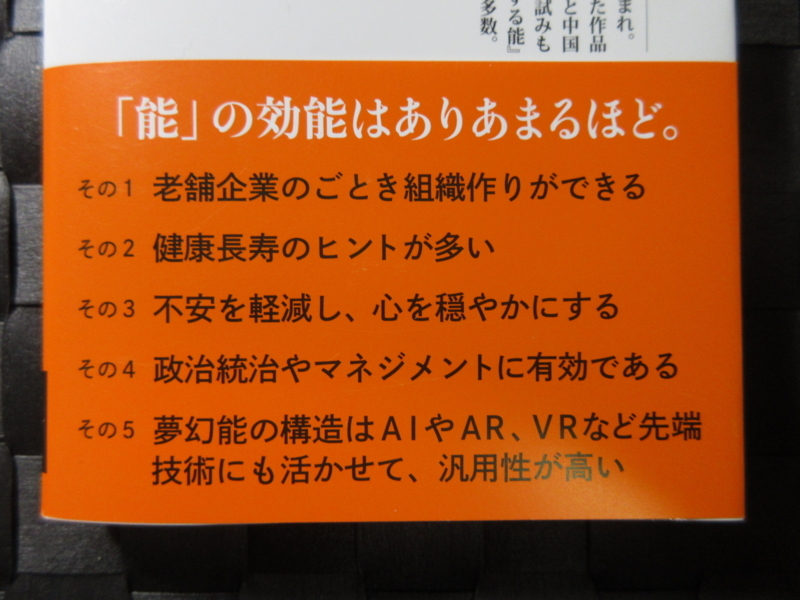 本書の帯の裏
本書の帯の裏
また帯の裏には、「『能』の効能はありあまるほど。」として、以下のように書かれています。
その1 老舗企業のごとき組織作りができる
その2 健康長寿のヒントが多い
その3 不安を軽減し、心を穏やかにする
その4 政治統治やマネジメントに有効である
その5 夢幻能の構造はAIやAR、VRなど
先端技術にも活かせて、汎用性が高い
さらにカバー前そでには、以下のような内容紹介があります。
「なぜ650年も続いたのか。足利義満、信長、秀吉、家康、歴代将軍、さらに、芭蕉に漱石までもが謡い、愛した能。世阿弥による『愛される』ための仕掛けの数々や、歴史上の偉人たちに『必要とされてきた』理由を、現役の能楽師が縦横に語る。『観るとすぐに眠くなる』という人にも、その凄さ、効能、存在意義が見えてくる一冊。その真髄をわし摑みにできる、類書なき最強入門書!」
本書の「目次」は、以下のような構成になっています。
「はじめに」
第一章 能はこうして生き残った
第二章 能はこんなに変わってきた
第三章 能はこんなふうに愛された
第四章 能にはこんな仕掛けが隠されていた
第五章 世阿弥はこんなにすごかった
第六章 能は漱石と芭蕉をこんなに変えた
第七章 能は妄想力をつくってきた
第八章 能を知るとこんなにいいことがある
(付録)「能を観たい、習ってみたい、知りたい」方へ
「はじめに」で、著者は次のように述べています。
「能を芸能として大成させたのは世阿弥ですが、信長、秀吉といった戦国時代の雄のみならず、式楽化(公式行事で使う芸能として認定)し政治のシステムに組み込んだ徳川幕府、それを強固にした歴代の将軍や大名たち、明治の功労者たちに至るまで、各時代のトップが推奨した理由は、トップマネジメントのための芸能として優れているからにほかなりません。松尾芭蕉や夏目漱石の創作が能に裏打ちされていることは、あまり知られていませんが、事実です」
第一章「能はこうして生き残った」では、著者が能楽師として日々演じ、また自分なりに能について学ぶうちに、社会資源として、能には大きく5つの効能があると考ええるようになったと述べています。そして、次の5つの効能を紹介します。(その1)「老舗企業」のような長続きする組織作りのヒントになる(その2)80代90代でも舞台に立っているほどなので健康長寿の秘訣がある(その3)不安を軽減し、心を穏やかにする効能がある(その4)将軍や武士、財閥トップが重用したように、政治統治やマネジメントに有効(その5)夢幻能の構造はAI(人工知能)やAR(拡張現実)、VR(仮想現実)など、先端技術にも活かせて、汎用性が高い
(その1)の老舗企業のごとき営業形態について、著者は「初心」という言葉を取り上げて、以下のように述べています。
「初心の『初』という漢字は、『衣』偏と『刀』偏からできており、もとの意味は『衣(布地)を刀(鋏)で裁つ』。すなわち『初』とは、まっさらな生地に、はじめて刀(鋏)を入れることを示し、『初心忘るべからず』とは『折あるごとに古い自己を裁ち切り、新たな自己として生まれ変わらなければならない、そのことを忘れるな』という意味なのです」
「初心」という言葉を使ったのは観阿弥・世阿弥が初めてではないそうです。しかし、世阿弥は「初心忘るばからず」を繰り返すことによって、「初心」の精神を能の中に仕掛けました。著者は「この仕掛けにより、能は長く続くことになったと言っても過言ではないでしょう」と述べています。また、「世阿弥はさまざまな仕掛けを能の存続のために施しており、650年間続いたのは、そのおかげだといいます。世阿弥の作った器が非常に優れていたからだと言えるでしょう」とも書いています。
(その5)「夢幻能の構造はAIやAR、VRなど先端技術にも活かせて、汎用性が高い」では、著者は以下のように述べています。
「能は、『現在能』と『夢幻能』とに二分できます。『現在能』というのは、生きている人のみが登場するもの。『夢幻能』は、旅の僧などの『ワキ』(主人公のシテ方の相手役となり、演技を引き出す役割)が、名所やいわれのある場所を訪ねると、主人公である『シテ』が謎の人物として現れ、その土地に関連する話を始めるというもの」
だいたい、シテは老人や女性の姿をしており、自分が何者かをほのめかすと、ふっと舞台から消えます。ワキがそのまま待つと、今度は消えた謎の人物が、幽霊、神、精霊など、非現実的な、本来の霊的な姿で再び現れ、舞を舞ってまた消えて行きます。夢幻能という名称は、ワキの夢の中に霊が現れることからついたとも言われていますが、著者は「世阿弥が完成させた他の演劇にはない珍しい構造で、能を能たらしめています。というのは、幽霊が出て来る演劇は世界に多いのですが、幽霊が主人公となる演劇様式はあまりないからです」と述べています。
第二章「能はこんなに変わってきた」では、能の歴史が説明されます。
世阿弥は「猿楽はもとは神楽なのだが、末代のもろもろの人々のために、神の示偏を除いて申楽にした」と書いていますが、世阿弥は能の源流が、神事芸能である神楽にあると考えていました。このあたりは拙著『儀式論』(弘文堂)の第七章「芸能と儀式」でも言及しています。
興味深いのは、能という言葉は、もともとは「する」とか「できる」という意味だったそうです。それがやがて歌舞伎を意味するようになり、江戸時代までは「能」といえば歌舞伎一般を指す言葉として使われていたとか。著者によれば、現在の能につながる「猿楽」のほかにも、農耕行事から生まれた「田楽」や、幸若丸(室町時代の武将、桃井直詮の幼名)が作った「幸若」など、さまざまな「能」があったそうです。能の役者のグループを「座」といいますが、猿楽能では奈良で活躍した「大和猿楽四座」が、現在の能の流儀の母体となっています。
第四章「能にはこんな仕掛けが隠されていた」では、さまざまな能の仕掛が明かされています。たとえば、「能面が真実の顔を生み出す」として、著者は以下のように述べています。
「日本は仮面大国です。能面だけではなく、雅楽で使うさまざまな面、神楽面などなど、その量においても、その精巧さにおいても群を抜いています。
能面が角度によってまったく違う表情を見せることはよく知られています。しかし、これは下を向けると悲しい顔、上を向けると喜んだ顔になるといった、ああすればこうなる的なものではなく、演じ手の微かな動きや見る人の心理状態によってその都度違った表情になるという不思議な造形になっています。能面作家の方に聞くと、まぶたや涙袋などの精妙な彫りがその造形を保っているという」
能面の目的は「変身」です。能には神がかり的な要素がありますが、変身とはまさに神がかり、しなわち憑依です。能面は憑依を可能にするための装置でもあるのです。
また、たとえば「謡で全国誰とでも話せます」として、結婚式で「高砂や~」と謡を謡う風習についても言及されています。
「ひと昔前までは結婚式だけでなく、成人式や還暦のお祝いなど、人生の節目のさまざまな儀式が謡で進行されていました。謡が堪能で、儀式の作法や次第にも精通していた『差配人(あるいは指図人)』という人が、そういう儀式の進行の差配もしていた。今でいえば、会場の担当者と披露宴の司会者を兼ねていたようなものです。このような形の儀式は、最近まで日本各地で見られました」
第五章「世阿弥はこんなにすごかった」では、「愛されてナンボ」として、能が650年以上も続いてきた秘密の核心が明かされます。
「650年以上続いている能は、世界に冠たる『老舗』です。その根底にあり、流儀は違っても能楽師が大切に思っている思想が、世阿弥が説いた『衆人愛敬(しゅにんあいぎょう)』です。この思想を根付かせたのも、世阿弥の功績です。能に通じた人に面白いのは当然として、知らない人にも面白い芸が大事だ、と言うのです。『わかる人にわかればいい』というのではなく、どんな人にも愛される芸、それを目指し、様々な芸風を打ち出し『多角化』していきます」
これを世阿弥は「目利き」と「目利かず」という言葉を使って説明したそうで、著者が以下のように解説してくれます。
「芸はうまければよいというものではない。うまい役者は目利きの目には適いますが、目利かずにはその芸のよさがわからないから、その目に適わない。しかし、それ以上にうまい役者ならば、目利かずの目にも『面白い』と思うような演じ方ができるはずだというのです」
「世阿弥の時代には、客の顔ぶれを見て、演じる直前に演目を変えることもあったそうです。それこそ現代の寄席のようです。今の能は、演目と演者が事前に決まっているので、簡単に演目を変えられませんが、しかし可能な範囲でやってみると面白いのではないかと、考えることもあります。その場で、相手を見てやる『衆人愛敬』は、演者の成長にとっても大事です」
第六章「能は漱石と芭蕉をこんなに変えた」では、「死者の鎮魂をする」として、著者は以下のように述べています。
「なぜ主人公の武士たちが修羅場や地獄に堕ちる能を、江戸幕府は庇護したのか。この疑問について考えてみましょう。本来ならば、支配階級の武士たちが堕ちていくなどという話はあまり歓迎されないように思えます。幕府という『勝者』の側が、なぜわざわざ非業の死を遂げた敗者をテーマにした能を認めていたのか。それは敗者たちを鎮魂するという狙いがあったからです。あるいは、敗者たちのたたりを怖れて厄落としをしたとも考えられます。そうして見ると、日本の芸能には非業の死を遂げた者の魂を鎮めるものが結構多い」
このテーマは、拙著『唯葬論』(サンガ文庫)でも展開しています。能は死者のための芸能でもあるのです。
第七章「能は妄想力をつくってきた」では、著者は「能にハマる人の多くには、時々、『見える』感覚があるのではないでしょうか」と問いかけます。「あの橋掛りを、つーっと歩く役者に目が吸い寄せられているうちにその感覚が刺戟されるのか。面が喚起する感覚を、その意識につなげるのか。囃子の音が眠っていた脳内ARを発動させるのか」として、さらに著者は次のように述べるのでした。
「現在、能を『つまらない』と思う人が多いというのは、ある意味では当然のことでしょう。能は、見ている方が一定のラインまで踏み込んでいかないと実感できないものだからです。漫然と聞いていても面白くないようにできており、『ここまで来い』と能の側が待っている。そのラインを何かの拍子で越えた時に、脳内AR装置が発動して見えないものが見えてくる。いや、それだけではなく、それができれば昔の物語を日常生活で味わって生きるようになり、『もののあはれ』を知るようになる。繊細な情緒を持つことで、人生を豊かなものにできるのです」
本書は、いわゆる能の入門書です。
能の入門書はこれまでにも数多く刊行されていますが、本書は650年続いた能の構造や効能を解明して、それを「いまに活かす」ことを前提にしています。能を過去のものではなく、「今に生きる」そして「今に活かせる」芸能として見ているのです。「今に生きる」そして「今に活かせる」ことこそ、能に限らず、古典の真髄ではないでしょうか。
著者は「イナンナの冥界下り」「天守物語」の上演や「天籟能」主催と、多彩な活躍をしています。わたしも一度、著者の舞台をライブで観てみたい!