- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2020.04.26
今回の「ステイホーム週間」を「読書週間」と陽にとらえて、大いに本を読みましょう!
『オカルティズム』大野英士著(講談社選書メチエ)を読みました。「非理性のヨーロッパ」というサブタイトルがついていますが、西洋神秘主義の本質を解き明かす名著でした。著者は1956年東京生まれ。東京大学文学部仏文科卒。早稲田大学大学院文学研究科仏文学専攻博士課程満期退学。パリ第七大学大学院でジュリア・クリステヴァに師事。2000年、文学博士号(ドクトル・エス・レットル)取得。専門はフランス文学。現在、早稲田大学ほか非常勤講師。
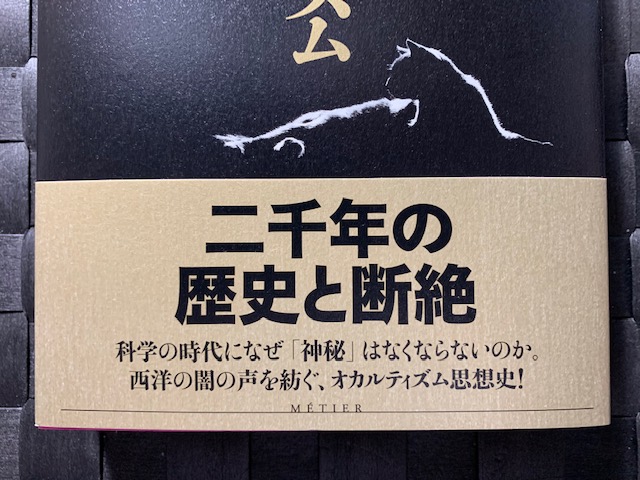 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「二千年の歴史と断絶」「科学の時代になぜ『神秘』はなくならないのか。西洋の闇の声を紡ぐ、オカルティズム思想史!」と書かれています。また帯の裏には、「古代・ルネサンスから現代に至る過程で世界観は何度も変貌した。(……)それにもかかわらず、現代に至るまで、オカルティズム・エゾテリスムの血脈は絶えることなく存続した。我々はそうした諸現象をあるがままに辿り、なにゆえ人はここまでオカルトに惹かれるのか、(……)人間の隠れた欲望の布置と共に示すことにしたい。――本書『オカルティズムとは何か』より」と書かれています。
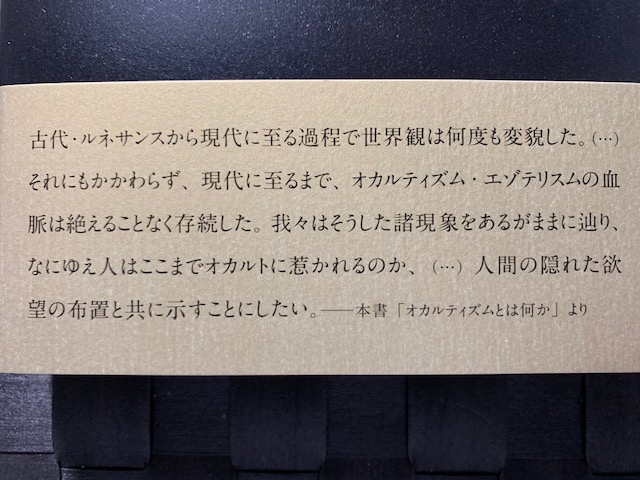 本書の帯の裏
本書の帯の裏
カバー裏表紙には、以下の内容紹介があります。
「ヘルメス文書、グノーシス、カバラー、タロット、黒ミサ、フリーメーソンやイリュミナティなどの秘密結社、そしてナチ・オカルティズムとユダヤ陰謀論……」古代から現代まで、オカルトは人間の歴史と共にある。一方、『魔女狩り』の終焉とともに近代が始まり、その意味合いは大きく変貌する――。理性の時代を貫く非理性の系譜とは何か。世界観の変遷を闇の側からたどる、濃密なオカルティズム思想史!」
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
序章 毒薬事件――悪魔の時代の終焉と近代のパラドクス
第一章 オカルティズムとは何か
第二章 オカルティズム・エゾテリスムの伝統
第三章 イリュミニズムとルソー――近代オカルティズム前史
第四章 ユートピア思想と左派オカルティズム
第五章 エリファス・レヴィ――近代オカルティズムの祖
第六章 聖母マリア出現と右派オカルティズム
第七章 メスマーの「動物磁気」とその影響
第八章 心霊術の時代
第九章 科学の時代のオカルティズム――心霊術と心霊科学
第十章 禍々しくも妖しく――陰謀論を超えて
終章 神なき時代のオカルティズム
序章「毒薬事件――悪魔の時代の終焉と近代のパラドクス」では、「魔術の終焉」として、著者はこう書いています。
「フランス国王ルイ14世の宮廷を騒がせたこのスキャンダルが、オカルティズムの歴史の中で、なぜ重要なのか? それはこの事件がカトリック教会ではなく初代警視総監という国家官僚の手によって裁かれたことにある。この事件の時期は、フランス・ヨーロッパにおける『魔女狩り』が終焉した時期に符合している。またこの事件の結果として『魔女』『魔法』『悪魔』といった概念が、少なくとも宗教裁判の対象からはずされ、黒ミサのような『魔術』と深い関わりをもっていた媚薬や惚れ薬、毒薬などが、国家管理の手に移され、いわゆる『薬局方』の制定を招いたからだ」
続けて、魔女狩りについて、著者は、「フランスにおける魔女狩りの最後の波は1670年から72年に訪れている。この時期、フランス北西部ノルマンディー地方のエーユ・デュプュイにおける魔女裁判では34人の『魔女』が死刑宣告を受けた。しかし、この時、ルアン高等法院議長クロード・ベロは告発の軽薄さを批難する手紙を著し、1672年には国務院がすべての魔女裁判の停止を命令する。そして『毒薬事件』の終結を受ける形で1682年8月に発布されたルイ14世の勅令により、毒薬を含む『薬品』の製造販売が登録制になる、つまりこの事件を機に現代まで続く『薬局方』が成立した。また、同じ勅令によって『黒ミサ』や『占い』『魔術』『悪魔崇拝』等これまでカトリック教会の『異端審問』によって断罪されてきた行為が、文字通りの『魔術』ではなく、単なる『迷信』への荷担として国家の裁判所で断罪されることとなった」と述べています。
さらに著者は、毒薬事件について、「毒薬事件は、ルーダンやノルマンディーのような農村部で起こったまうに『魔女狩り」』としてではなく、絶対王政の発展する中心都市パリを舞台に起きた『犯罪事件』として処理された。首謀者である産婆ラ・ヴォワザンも『悪魔崇拝』の罪ではなく『殺人』と国王に対する『大逆罪』として処断された。しかし地方と都市との違いはあれ、『毒薬事件』においても、魔女狩りにおいても、狙い撃ちにされたのは、まず、『生命』を司る女たち、『産婆』や『民間療法』に従事する女たちだったことはここで記憶しておいてもよいだろう」と述べるのでした。
第一章「オカルティズムとは何か」では、「今なぜ『オカルティズム』か」として、著者は「『宗教的真理』――キリスト教・仏教から、オウムのような新興カルトまで含めて、宗教が『顕教』として提示する『教理』とは別に、その宗教が限られた入信者・秘儀伝授者にのみ伝える奥義としての『オカルティズム的真理』――と、『科学』との間の対話の可能性は、現代においてほぼ閉ざされているといってよい。オカルティズムはせいぜい宗教学や宗教社会学の片隅でわずかに扱われているにすぎない。ヨーロッパ、アメリカでは、そうしたオカルティズムの分野にもまだしも、それなりの関心が払われ、オカルティズム関係の講座をもつ大学もあり、現在でも年間十本内外のオカルティズムに関する博士論文も書かれている。ただそれでも全体から見れば例外的位置づけにとどまっている」と述べています。
続けて、著者は日本におけるオカルティズム研究にも言及し、「日本の学界では、欧米以上に実証的な科学主義の伝統が妨げになって、特に自然科学の分野からオカルティズム研究はほぼ完全に追放された格好だ。しかし、19世紀末から20世紀初頭の一時期、オカルティズムは偏奇な興味に駆られたごく少数の科学者が人知れず取り組むというマイナーな研究対象ではなく、キュリー夫妻をはじめ、ノーベル賞を受賞したクラスの一流の学者たちが真剣に取り組むメジャーな研究対象だったのだ」と述べます。
そして著者は、「本書は、オカルトを肯定も否定もしない。本書で試みるのは、変遷する世界認識の枠組みの中に、オカルティズムを、人間の歴史に刻まれた社会現象として記述することだ。それが、今後、失われた科学との対話を再開するよすがともなり、また、新興宗教をも含めたオカルトや超常現象に対する相対的な距離の取り方を我々に学ばせてくれることになるだろう」と述べるのでした。
著者は、「オカルティズムの歴史と『近代』の問題」として、オカルティズムの歴史を大まかに要約し、「古代(エジプト、メソポタミア、ギリシア)の宗教儀礼に始まり、ヘレニズム期に、古代以来の宇宙論を背景として、魔術・占星術・錬金術として一応の体系化をみる。これらはキリスト教の台頭によって一旦は抑圧され、異教・異端あるいは悪魔主義と結びついた黒魔術としてわずかな命脈を維持するが、ルネサンスの古代復興にともない、ルネサンス魔術として復興する。しかし、古代復興の一面である、聖書をギリシア語・ヘブライ語の原典で理解しようとする人文主義により生じた宗教改革、キリスト教の新旧両陣営への分裂は、大規模な宗教戦争や魔女狩りを引き起こし、多くの犠牲者を生み出した。一方、ルネサンス魔術は、同じ時期、天体観察や錬金術から生じた『近代』科学の発展、特に、『コペルニクス革命』によって、その理論的な基盤を脅かされると共に、その後、次々に新しい知見を発見し続ける『近代科学』や『医学』との絶えざる緊張関係に置かれる」と書いています。
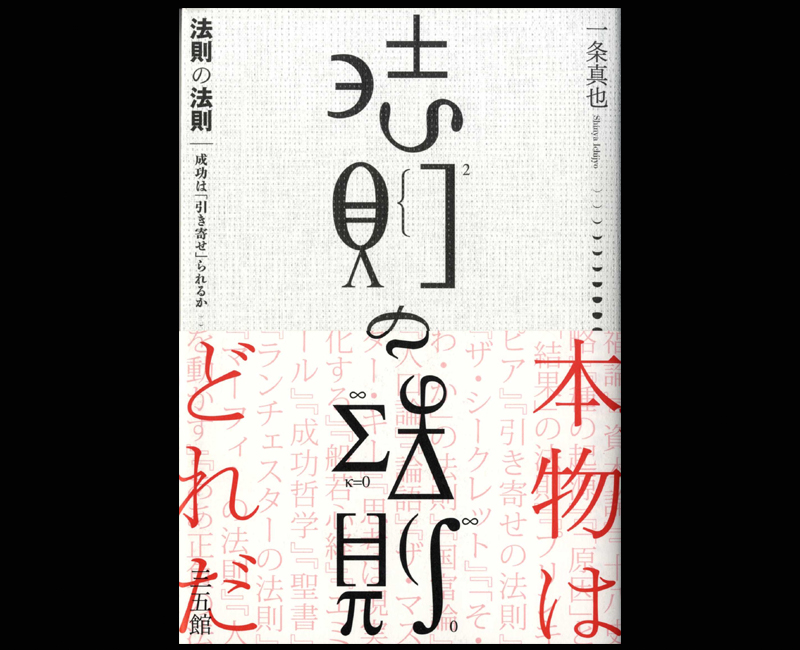 『法則の法則』(三五館)
『法則の法則』(三五館)
このあたりは拙著『法則の法則』(三五館)でも詳しく説明しました。魔術も宗教も科学も「法則」の追求にほかなりません。続けて、著者はオカルティズムの歴史を要約し、「19世紀以降、こうした近代科学を乗り越えるオカルティズム側の抵抗として、『動物磁気』『心霊術』が流行する。19世紀から21世紀の現代に至るまで、オカルティズムによって『発見』された『超能力』『超常現象』『超心理学』を、近代科学を超える新たな認識のパラダイムとして認知させようという努力が延々と続けられる。その一方、オカルティズム・エゾテリスムを、旧来のキリスト教・ユダヤ教を超えて、チベット仏教を含む仏教、ヨガ、イスラム神秘主義等、様々な神秘主義的諸潮流と習合させ、新たな宗教的地平を切り拓こうとする動きが顕著となる」と述べます。
第二章「オカルティズム・エゾテリスムの伝統」の冒頭では、「ルネサンス期のオカルティズム・魔術再興」として、著者は以下のように述べています。
「オカルティズム・魔術には、歴史を通じて明らかに2つの流れがある。1つは高等魔術というべきもので、古くはピュタゴラス、アリストテレス、『ヘルメス文書』などに遡り、ルネサンスの人文主義が復活させた古代宇宙論の流れを汲む魔術・占星術・錬金術の伝統だ。一方、こうした高等魔術の伝統とは別に、中世ヨーロッパの農村社会には、ヨーロッパとは異なる文化伝統をも横断する形で民俗的呪術・魔術の層が存在していた」
また著者は、ルネサンスについて述べています。
「ルネサンスはヤコブ・ブルクハルト『イタリア・ルネサンスの文化』(1860)以来、古典古代を再興した運動として理解されてきた。しかし、アビ・ワールブルクに率いられた研究者集団、いわゆるワールブルク研究所に属する研究者による一連の研究、特に、フランセス・A・イエイツによって、ルネサンスの復興した古代とは、単にギリシア・ローマの古典古代一般ではなく、ヘレニズム期――すなわちアレクサンダー大王の東方征服以降、エジプト・メソポタミアのオリエント文明とギリシア文明が独特の融合を遂げたヘレニズム期であり、オカルティズム・魔術が浸透した古代末期の哲学・宗教思想であったということが広く理解されるに至った。具体的には、新プラトン主義、ヘルメス主義、グノーシス派といった思潮であり、それらを理解し補強するに資する限りで、ギリシアに淵源しながらも、ビザンツイスラム圏で発展した魔術、錬金術、占星術の類である。これに、さらに、紀元1世紀に起こった民族離散以降、旧約聖書に表現されたヤハウェという人格神の概念を離れ、エン・ソーフと呼ばれる非人格神をめぐる独特の神秘主義体系を発展させてきたユダヤ神秘主義が加わる。いわゆるカバラーだ」
さらに著者は、「ルネサンスのオカルト神秘主義に浸された思想圏を『永遠の哲学』(命名は1540年のアゴスティノ・ステウコによる)ないし古代神学と呼ぶが、そのルネサンスが想定した哲学者・古代賢者の系譜は、古い順番にエノク-アブラハム-ノア-ゾロアスター-モーセ-ヘルメス・トリスメギストス-ブラーフマン僧-ドルイド-ダヴィデ-オルフェウス-ピュタゴラス-プラトン-シビラの占術者の順になるという。従って、コシモやフィチーノがプラトンに先がけて『ヘルメス文書』を訳すというのは当然すぎるほど当然の判断だった」と述べています。それらの背景には、マクロコスモス(大宇宙)とミクロコスモス(人間)との照応(コレスポンダンス)の原理が働いているとの思想がありました。つまり、星辰と人間の間には、それを媒介する精気によって通信が生じ、星辰が人間の健康や運命に影響を与えるという考え方です。
そのマクロコスモス-ミクロコスモスの問題について、著者は「自然魔術とダエモン魔術」として、こう述べています。
「マクロコスモス-ミクロコスモスの問題を考える際、古代哲学の宇宙観、四元素説、霊魂観などを限りなく折衷的に受け入れたルネサンスにおいて、マクロコスモスとミクロコスモスの間の『照応』に基づき、前者(宇宙)の後者(人間)に対する影響と、後者(人間)の前者(宇宙)に対する魔術的な『操作』を可能にする『物理的』『心霊的』原理が存在しないわけではなかった。その1つが、アリストテレス以来『真空』を許さないとされた宇宙にあって、宇宙霊魂と人間の肉体を繫留する実体的な媒介と考えられた精気(プネウマ=スピリトゥス)であり、もう1つが星辰信仰の背後に哲学者・魔術師が信じていたダエモン(ダイモン)と呼ばれる霊的人格である」
続けて、著者は以下のように述べています。
「精気論はルネサンスの自然哲学・占星術・錬金術に通底し、照応を物質的なレベルで担保する役割を果たすことによって自然魔術の支柱となる考え方だ。一方、ダエモンは『降霊術』という儀礼・儀式を伴うことによってより広範で強力な『魔術』を施術者に与えることになる。しかし、正統的なキリスト教神学の立場からすれば、ダエモン魔術は異教由来の『悪魔』=『悪霊』、まさに『悪魔』の力を借りることになり、到底容認できる限度を超えることになる。もっとも、原始キリスト教がローマ化される過程で、エジプトの女神イシスをはじめとする異教の大地母神と密接な関係をもつ聖母マリア信仰や、数多くの聖人信仰などの形で異教との妥協は図られていた。また偽デュオニシオス・アレオパギテスは『天上位階論』(天使論)において星辰に付属するダエモンを守護『天使』に読み替えることで、一神教の教理と異教との間に一定の調和をもたらそうと試みていた」
そして著者は、「オカルティズムに対する感性の変化」として、「ルネサンス魔術、民俗魔術、魔女狩りを通じて極端な形で体系化された悪魔や魔術に関する『知的』『民俗的』生成物は、プロヴァンスで栄えたトルバドール文学により発生した俗語(ロマンス語)による想像力を駆使したフィクションの一形式として18世紀に創造された『小説』という新しい語りの1つの要素として、『あり得ない過去』あるいは『あり得べき過去』に逆投影される。いわゆる『ゴシック・ロマン』の誕生だ。悪魔はゴシック・ロマンの中で『霊感を中世や騎士道、キリスト教に仰ぐ』という意味でのロマン派の幻想の一部に『転落』するのだ」と述べるのでした。
第五章「エリファス・レヴィ――近代オカルティズムの祖」では、「『魔術原理』の秘密」として、著者はこう述べています。
「タロット・カードは、ソロモン王の治世から伝わるカバラーの奥義書である。世に信じられているようないかさま師や占い師の手慰みではなく、熟練した魔術師なら、タロットの操作によって、人間、宇宙の全ての現象を予知できる。神自身が必然の摂理に従うように、偶然現れたかにみえるタロットの組み合わせは、真理を表す根源的な言=宇宙の必然と『照応』によって結びついている。照応・類比の原理の前では、いかなる偶然も必然に転化する。魔術師の『想像力』によって産み出されたタロットの組み合わせは、宇宙の必然の言語化であり、それを担保するのは、ここでも『アストラル光』である」
また、「稀代の魔術師」と呼ばれたエリファス・レヴィについて、著者は「エリファス・レヴィは、クール=ド=ジェブラン、エテイラの発想を引き継ぎ、このカード・ゲームは『トートの書』に他ならず、『古代の民の聖なる書物のすべてに霊感を授け』、『その図形と数字の照応の正確さの故に、全幅の信頼をもって使用することができる』とする。しかし、一方で彼は、クール=ド=ジェブランもエテイラも『この不可思議な書物の中に隠された一切を見つけ出す寸前までいった』が、それを『正しく理解し得なかった』と批判している。要するに、エリファス・レヴィこそが、この『不可思議な書物』のカバラー的真理を初めて正しく理解し、読み解いたというわけだ」と述べています。
さらに興味深いことに著者は、エリファス・レヴィが「悪魔」の存在を認めていないことを指摘し、「すなわち、悪魔崇拝の『黒魔術」は、マニ教という『奇怪な邪教』の影響下、ゾロアスターの教義を曲解し、『普遍的均衡を構成する二力という魔術の法則』をもとに、『非論理的な頭脳の持ち主が、能動的神格に屈服しつつも敵対する一種の否定的神格を想定する』に至ったものにすぎず、『不純な二元論が生み出され、「神」を分割するという狂気の沙汰に及』んだために生じたものである」と述べます。
続けて、悪魔信者について、著者は述べます。
「悪魔信者は、善が完全に否定される様態が現実に存在しうることを信じたために、虚妄の神を創造し、魔宴を催してこれに祈願するしかなくなった人々のことであり、魔女狩りや悪魔祓いを挙行した多くのカトリック教徒・神父は、実は、自分たちの信じていることとは逆に、『神』の対抗者である『悪魔』の存在を信じる悪魔教の信者にすぎない。悪魔とは『1つの人格ではなく』『道から外れた1つの力』であり、『邪悪な意志によって形づくられた一種の磁気流』、言葉を換えて言えば、邪悪な意志によって形成されたアストラル光こそが、『悪霊』つまり『悪意や過失によって生ずる』『盲目的な力』を生じさせるのだ」
さらに、著者は以下のように述べています。
「19世紀末『カバラの薔薇十字』を組織したパピュス、スタニスラス・ド・ガイダ、ジョゼファン・ペラダン、また、イギリスの魔術結社『黄金の夜明け』に拠った自称魔術者たち、なかでもアレイスター・クローリー等、エリファス・レヴィに影響を受けた魔術師・魔導師たちは、いずれも、こうしたエリファス・レヴィの主張を――自分の方が師よりもさらに『真理』に接近しえたと主張することはあっても――ほぼ無批判に受け入れた。それは伝統を捏造し、偽りの根拠を『自らの権威』に基づいて正当化するというエリファス・レヴィの手法をも含めて承継したことを意味する。魔術の真理がエジプト以前に遡り、また、相互に必ずしも連絡のない文明を横断して、同じ『真理』が見出され、最終的にはそれは『カバラー』なり『グノーシス』なりに行き着く……という思考方法をも含めて彼の様式に倣ったのだ」
続けて、著者は以下のように述べるのでした。
「例えばその中には、ヒンズーの導師に直接『秘儀を伝授』されたと主張するロシア出身のブラヴァツキー夫人もいたし、現代に至るさまざまなニューエイジ・グループ、新宗教の教祖、さらにはライト・ノベル、マンガ、アニメ、ゲームなどの魔法ものにまで共通する。要するに、イリュミニスト同様、自分の『妄想的』世界観がそのまま真理として具現し、教祖や作者の数だけ、新たな『宇宙』や『宇宙の真理』が出現するのだ」
第六章「聖母マリア出現と右派オカルティズム」の冒頭では、「『出現』の伝統」として、著者はこう述べています。
「フィリップ・ミュレーのテーゼによれば、大革命後の19世紀、左派=社会主義陣営はオカルトの側に『転落』した。しかし、オカルトに『転落』したのは左派だけではなかった。右派、すなわち、革命後の王政復古によって再び権力の座についたブルボン王家を取り巻く王党派、『王権神授説』によって旧体制に『形而上学的』『倫理的』な正統性を保証していたカトリック、ようやくフランスに芽生え始めた産業革命によって階級として地歩を固めつつあり、秩序と財産の保証を求めていた地主・大ブルジョワなども、別の形でのオカルティズムにはまり込んでいたのだ。その中で最も重要な役割を果たしたのが、『聖母マリアの出現』というオカルト現象である」
また著者は、「横山茂雄は『稲生平太郎』名で書いた『空飛ぶ円盤』論、『何かが空を飛んでいる』のなかで、『当然のことながら、19世紀以前だって人々は空に何かを見ていた。古今東西を問わず、空に変なものが飛ぶのを見た人は少なくなかった。ただ、昔は、基本的にはこれ(空飛ぶ円盤)を乗り物だなんて誰も考えはしなかった。(……)災厄や宗教的奇蹟の到来を告げる超自然的な予兆だと解釈されたのである』と指摘し、マタイ伝に現れたキリスト誕生を告げる星、ジェフリー・オブ・モンマスの『ブリタニア列王史』に記されたウーサー、アーサーの王位就任を告知する不思議な光、さらには日本近世随筆に現れる『光り物』の伝説などを列挙している。もちろん、ヨーロッパにおいて、この時代以前に聖母をはじめ『聖なるもの』の出現の伝統がなかったわけではない」と述べています。
さらに著者は、「19世紀の『聖なるもの』の出現において特徴的なのは、『何か変なもの』が空を飛ぶというのにとどまらない。もちろん、後でみるように、そういう例も含まれていなかったわけではないのだが、さらに顕著なのは、それが目の前に人の姿をとって顕現し、『王党派』的な預言を行うというところにあるのだ。確かに、彼らの預言が、多くの歴史家が指摘するように、カトリック=王党派の政治的陰謀やあからさまな詐欺によって『演出』されていた事実は否めない。しかし、それにもかかわらず、ここで問題となる聖母マリアをはじめとするこの時代の『聖なるもの』の出現が、教育を受けていない見習い修道女や羊飼いなど民衆出自の若年者に多く体験されたことが端的に示すように、主として民衆起源の現象である点を強調しておくことは無意味ではあるまい。大革命によって崩壊し、キリスト教権の支配が弱まった農村社会において、民俗的で古代以来のさまざまな民間信仰を含みこんだ多様な想像力が解放されたのだ」と述べるのでした。
第七章「メスマーの『動物磁気』とその影響」の冒頭では、「メスマーと動物磁気」として、著者はこう述べています。
「ある意味、オカルティズムそのものは、古代から連綿と続く人間の一傾向、欲望として一貫して存在してきたとも言える。すなわち、人智を超越した超自然的な力、しかも正統キリスト教の枠組みに収まりきらない異教的・異端的な『力』にすがって、有限に定められた『人間』の生命や富、知の限界を超えたいという願望だ。逆に、17世紀後半以降、カトリシズム、プロテスタンティズムを問わず、キリスト教の縛りが緩まるにつれて、そうした超自然的な力への憧れは強まり、またキリスト教正統からの抑圧を離れてオカルティズムはさらに多彩になったとも言える。しかし、特に19世紀以降の『近代』オカルティズムには、前の時代のオカルティズムとは異なる2つの特異な現象が関与してきた。そして、この2つの現象が、その後のオカルティズムのあり方を決定的に変えていくのだ」
第八章「心霊術の時代」では、「ハイズヴィル事件」として、1847年のアメリカで起こった有名なポルターガイスト事件を取り上げ、著者は以下のように述べています。「おそらくこの事件の背後には新大陸アメリカの社会的・宗教的特性が働いている。メイフラワー号による清教徒=ピューリタンの移民に端を発するアメリカは、独立戦争を経て、独立国としての地盤を固めると共に、19世紀に入ると産業革命による経済発展により東部沿岸州から内陸部にかけての急速な開発や人口移動が起こり、社会構造・階級構造が劇的に変化しつつあった。1820年代には、ジョージア州ダーロネガで金鉱が発見され、最初のゴールドラッシュが起こり、1830年にはそれに伴う先住民の強制移住を可能にするインディアン移住法が可決される。また産業革命の結果、産業資本主義が発達しつつあった北部諸州と、アフリカからの黒人奴隷労働に基づくプランテーション経済に基盤を置いた南部諸州の対立も徐々に深まりつつあった。その中で、人間の原罪を強調し、厳格なピューリタン信仰に根ざした精神風土に変化が現れると共に、メソジスト教やシェーカー教、クリスチャン・サイエンスなどの新宗教が組織され、旧大陸由来のスウェーデンボルグの神秘思想やメスメリズムが浸透し、ハイズヴィル事件の先駆となるアンドリュー・ジャクソン・デイヴィス(1826-1910)のような超能力者(=千里眼)の活動も見られるようになる」
また著者は、「心霊術の展開」として、こう述べます。
「ハイズヴィル事件が「心霊術」の歴史にとって創始的な意味をもったのは、単にポルターガイスト事件に遭遇したにとどまらず、その背後に存在すると考えられるあの世の霊との間に再現性のある交信、意思の疎通を可能にした(とフォックス姉妹が主張した)点にある。これが『心霊術』のいわば定義といえよう。ちょうどハイズヴィル事件の数年前の1844年に発明されたモールス信号のように、心霊術では『死後』の世界から『霊』とみなされる理性的存在が直接自らの体験や知識を現世の人間に語りかけてくるわけだ。
もう1つ、心霊術を考える際に重要な点がある。ポルターガイスト現象におけるラップ音等、心霊術における超常現象は、物理的に検証し、解明することができるということだ。これは、一種の近代性である。心霊術の成功を考える時、この物理的・科学的な検証可能性は後の時代まで、常に焦点となっていることを心に留めておくべきだろう」
1960年から90年にかけて、心霊術やアメリカやヨーロッパを問わずに爆発的に流行しました。その中には、多くのスター霊媒が注目を集めました。イギリスのダニエル・ダングラス・ホーム(1833-1886)はその代表的な人物です。著者は「ダニエル・ダングラス・ホームは、ホーム伯爵家10代目当主の庶出の孫にあたり、『ヨーロッパ王侯の霊媒』であると自称していたが、実のところは、アメリカ出身で、ハイズヴィル事件の熱狂を利用して、個人的な魅力と巧みな弁舌で、子ども時代から『霊媒』として売り出した。彼については、熱狂的な支持者と逆に彼を詐欺師呼ばわりする者とが相半ばした。どちらかと言えば、華奢な女性的な容姿で、そのため、反対派からは男色者の疑いを掛けられていたという。心霊術の熱心な研究者で、やはり男色者として知られたウィンダム・トーマス・ウィンダム=キン・アデアー子爵(1841-1926)は、イギリスにおけるホームの第一の保護者だったが、彼の証言によれば、ホームが、水平に横たわったまま、空中を浮遊して、一階の窓から抜けだし、近くのツツジの茂みから花を摘んで、別の窓から部屋に戻るのを目撃したという」と述べています。
「心霊主義の影響と意義」として、著者は述べます。
「D・D・ホームのような極端な例は別にしても、霊媒の中には霊の『物質化』やテーブルをはじめとする物体や霊媒自身の身体の空中浮遊、透視、テレパシー、未来の出来事の予言など、かつての動物磁気=催眠療法同様、あるいはそれ以上の『超常現象』を実現したと主張する者が続出した。心霊術の流行は、動物磁気をめぐる1840年代の近代科学との論争における一連の敗北――動物磁気=催眠療法師たちは自分たちの敗北を認めていなかったが――以来、社会の周縁部に追いやられていた動物磁気信奉者たちに再び彼らの主張を活発にさせた。動物磁気=催眠療法と心霊術=交霊術とは被催眠者=霊媒を文字通りの媒介としてある種の連続性を持っていた。いわば動物磁気の育んだ素地に心霊術=交霊術という新たな要素が接ぎ木された形だ」
続けて、著者は以下のように述べています。
「但し、同じような『超常現象』を共有していても、心霊術=交霊術の文化圏においては、その背後に死者の『霊』を想定するだけに、そのオカルト性は一層強まったといえるだろう。また心霊術の発見は、ロマン派の影響下からルネサンス高等魔術の復活を試みたエリファス・レヴィから、聖母マリアの出現を契機に独自の異端を発展させ、文学者ユイスマンスに影響を及ぼしたブーラン元神父のようなオカルト右派に属するものに至るまで、他のオカルト諸潮流や、精神医学・生理学・神経医学など、大学やアカデミーに拠った真面目な学問研究や思想にも多大な影響を及ぼしていくのだ」
心霊術はフランスの教育学者アラン・カルデックによってカトリシズムやヘルメス学派の高等魔術に代わる新時代の宗教として理論的に体系化されました。著者は、「心霊術の体系化――アラン・カルデック」として以下のように述べます。
「オカルティズムの観点からすれば、カルデック理論の特質は、1850年代後半、エリファス・レヴィの『アストラル光』と並んで、『流体』をその理論的な支柱に据えたことによって、動物磁気においてすら周縁化しつつあったこの物質=媒体にあらためて人びとの関心を向けたことにある」
続けて、著者は以下のように述べます。
「また、神の創造というドグマは否定しないまでも、霊の『輪廻』という従来のキリスト教には異質の教義を取り入れることによって、ヨーロッパ中心主義的宗教観を正し、ブラヴァツキー夫人やルドルフ・シュタイナーの神智学など、心霊術とも深い関わりを持ちながら、より汎神論的な新宗教、さらには現在につづくニューエイジなどへの道を切り拓いた。ブラヴァツキー夫人の神智学は、カルデックの理論とは別個の立場から、心霊術が切り拓いたオカルティズムを体系化し、さらに、エリファス・レヴィやカルデックには欠けていた、大衆的新『宗教』の組織化を成し遂げたという意味で歴史的に重要な役割を果たしている。またそこに含まれる人種論を通して、ナチ・オカルティズムの形成にも多大な影響をもたらしたという側面を有している」
さらに著者は、「ブラヴァツキー夫人の神智学――オカルト的シンクレティズム」として述べています。
「死者や幽霊との『対話』は、『死後の世界』の実在を信じたい人々にそれなりの根拠を与えはしたが、その内容は凡庸なものが多く、霊媒の商業化・ショー化によってますます画一的になる傾向があった。人々は既成のキリスト教の教義を越える『真実』を求めて心霊術を受け入れたわけだが、心霊術に対しても、単に霊との交流にとどまらず、より客観的、体系的な理論と、宗教的組織、あるいはさらに『それを超える何か』を求めたのだ。こうした要求に答える形で出てきたのが、メアリー・ベーカー・エディの『クリスチャン・サイエンス』、トーマス・レイク・ハリス(1823-1906)による『ザ・ブラザーフッド・オブ・ザ・ニュー・ライフ』など、ニューエイジの先駆となるような新興宗教だ」
神智学という「宗教」の開祖であるブラヴァツキー夫人の主著が『シークレット・ドクトリン』です。同書について、著者は「『シークレット・ドクトリン』というある意味、19世紀エゾテリスムを集大成した著作の内容が、アニー・ベサントという人格・品性に優れたスポークスウーマンを通じて広められることにより、稀代の『詐欺師』ラヴァツキー夫人の生前の悪評は忘れられ、ブラヴァツキー夫人の『心霊術師』、『オカルト理論家』としての側面だけが拡大され、聖別されていくのだ。この意味で、アニー・ベサントが、植民地宗主国であるイギリス人としての政治的・社会的限界はありながら、若いインド人と次々と親しくなり、ヒンズー神秘主義、さらには、ヒンズー民族主義の理解者・同伴者・援助者として振る舞い、マハトマ・ガンジー(1869-1948)に至るインド独立運動に一定以上の影響をもたらし続けたことは無視できない」と述べています。
さらに、著者は『シークレット・ドクトリン』について、「形式的には『ジャーンの書』の7つのスタンザの注釈という体裁をとる。『ジャーンの書』とはブラヴァツキー夫人によれば、キリスト教、ヒンズー教、仏教、儒教等東西のあらゆる宗教に通底する悠久の古代の真理を伝える実在の書物である。『ドクトリン』全体は3部に分かれ、カオスから宇宙が生成する過程、および、近代科学がそれをいかに誤って解釈しているかを証明する『宇宙生成論』。ダーウィンの進化論を下敷きに、それに上書きするような形で、人間の進化・文化を語る『人間生成論』。これにその両者を総合する第3部が続く。ただし、アニー・ベサント編による第3部については、ブラヴァツキー夫人を特別視する原理主義的な神智学信者からはその権威が疑われているという」と述べています。
そして、著者は『シークレット・ドクトリン』について、「19世紀末から20世紀初頭にかけて、オカルト陣営において『シークレット・ドクトリン』あるいは神智学の権威が高まり、その影響が強まるにつれて、ブラヴァツキー夫人のこうした人種論が、当時の人種偏見、特にユダヤ人差別を助長し、横山茂雄によれば、ナチ・オカルティズムの形成にも影響を与えたという。ブラヴァツキー夫人あるいは彼女の後継となったアニー・ベサントが、イギリスの植民地主義に対しヒンズー民族主義を支持し、それが、結果的にはブラヴァツキーの『失脚』を越えて『神智学』を生き延びさせることに繋がったとすれば、これは、歴史の皮肉だろうか?」と述べるのでした。
第九章「学の時代のオカルティズム――心霊術と心霊科学」の冒頭を、著者は「19世紀エピステーメー転換と近代オカルティズムの矛盾」として、「19世紀末がオカルトの歴史においても転機になったことは疑いがない。心霊術が1869年のカルデックの死によって、1つの時代の終焉を迎えたこと以上に、この時期、従来の『実証主義』にもとづく『科学』に対する懐疑が深まり、カトリシズムの復興や神秘主義・精神主義への傾斜が生じたことがその背景となっている」と述べています。
著者によれば、こうしたパラダイム転換を受ける形で、この時期、従来の「実証主義」にもとづく「唯物的」な「科学」、あるいは、それと対をなす「人間機械」的な人間観に対する懐疑が広がりました。カトリシズム復興にとどまらず、ウィリアム・ジェームズ(1842-1910)、フリードリッヒ・ニーチェ(1844-1900)、ジークムント・フロイト(1856-1939)、エドムント・フッサール(1859-1938)、アンリ・ベルクソン(1859-1941)、ジョン・デューイ(1859-1952)、レオン・ブランシュヴィック(1869-1944)など広義の神秘主義・精神主義的傾向をもった哲学・思想が一斉に開花したのです。
このような19世紀末について、著者は「19世紀末といえば、耽美主義、退嬰主義、デカダンスなど、心身ともに病的なイメージをもって語られることが多いが、むしろ、『病んで』いたのは、19世紀という世紀そのものである。たとえば、娼館とは切っても切れない梅毒に感染していた人間の割合は、19世紀を通じ、成人男性の80パーセントに達していたという数字がある。逆に19世紀末とは、唯物論、観念論を2つながら克服しっっ、病的な世紀としての19世紀を清算する動きが強まった時代という認識を持つ必要がある」と述べます。
この時期、心霊術側にも大きな変化が起きつつありました。「心霊科学の誕生」として、著者は述べています。
「イギリス、フランスを中心に、ますます精密になる科学の基準に照らし、『霊』や『死後の世界』の存在を前提とした『宗教的』解釈を離れて、厳密な実験を通して、動物蕊気・心霊学の圏域で発現する『超常現象』『超能力』を検証しようという運動が生じたのだ。1882年、英国心霊学協会を母胎に、エドモンド・ロジャース(1823-1910)、ウィリアム・フレッチャー・バレット(1845~1926)、スタントン・モーゼス(1839-1892)、フレデリック・マイヤーズ(1843-1901)らにより、心霊研究協会(the Society for Psychical Research)が創設され、功利主義哲学者であるヘンリー・シジウィック(1838-1900)が初代の会長に就任した。いわゆる『心霊科学』ないし『超心理学』の誕生である。ちなみに心霊研究協会設立の翌年、1883年、シジウィックはナイトブリッジ大学の倫理哲学教授になっている」
「心霊科学を支える論理」として、著者は、20世紀初頭、心理学は3つの潮流に分かれていたことを紹介します。1つは、ヴィルヘルム・ヴント(1832-1920)に代表される実験心理学、もう1つは、シャルコー、フロイトに代表される精神病理学・精神分析。もう1つは心霊科学で、著者は「こうした文脈の中で、心霊科学は、時代の新しい精神主義の一翼を担う形で、当時を代表する哲学者・心理学者・思想家も含んだ多くの人々の関心を引いた」と述べます。
当時の「心霊科学を支える論理」を、著者は「心霊研究協会の中心人物だったフレデリック・マイヤーは識閾下の自我の理論を提唱し、そのレベルにおいては、肉体を離れた他者の意識が交流しあうことに『超常現象』の原因を求めようとした。またルネ・シュードルは、心霊術には反対の立場だったが、死者をも含む他者の記憶が残存し、他の個体が残っている記憶・思念を捕捉することが可能だと考えることによって、霊媒現象を説明しようとした。ある人間の『思考』が分解されると、その思考は解放された後、再結集し、他の人間の心的意識と結合し新たな総合を形づくる。こうして神経組織を介さず、思考が転移する『開放回路』を構想したのだ」と紹介しています。
このルネ・シュードルの「開放回路」について、著者は「この考えは、ベルクソンの『創造的進化』『物質と記憶』における『エラン・ヴィタル(生命の跳躍)』と同じではないにせよ、彼の発想に少なからず影響を与えているという。ベルクソン思想のエソテリックな源泉というわけだ。このあたりの議論は、ベルクソン思想全体との関係で問い直さなければならない重要な、またベルクリニスムの中で最も議論の余地のある問題を含んでいるが、メウストによれば、ベルクソンは、『科学経験』の拡大によって明かにされた『心霊現象』が、生命の緊張が極限まで弛緩した『物質』的様態を突き破って噴出する『生命の躍動』という彼の人間観・生命感に1つのヒントを与えると考えていた」と述べています。
さらに、著者は以下のような紹介も行っています。
「ジョゼフ・マックスウェル(1858-1938)は、『有機的個人性』理論により、言語化しうる個人意識に還元できない更に大きな自我意識を提唱した。催眠によってもたらされる夢遊病(夢中遊行)体験は、単に個人意識の崩壊ではなく、そこから間接的に知られるより包摂的な意識の存在を予想させるとする。これは、後のユングの『集合的無意識』や、ニューエイジ等で語られる主体がさらに大きな真の自我に取り込まれる『太洋感覚』などとも共通する考え方といえるだろう」
近代オカルティズムを俯瞰して、著者は「キリスト教という、西欧にとって知的・『霊』的生活を律してきた啓示宗教が、唯物主義、進化論等、近代そのものともいえる『世俗化』によって、命脈を絶たれた後、なお、死後の生を信じ、霊魂の不滅を信じるために、唯物主義・進化論を作りだした主導思想である『実証科学』を逆手にとって、なおも、『宗教』を持続させたいという人々の意志が、近代オカルティズムを現代まで生き延びさせているとはいえまいか? そして、エピステーメー切断を越えて、あるいは、エリファス・レヴィのように、あるいは、ブラヴァツキー夫人のように、すでに『過去』のエピステーメーに属する『魔術』や『カバラー』を現代に甦らせたり、人知れぬ人外境で、ヨガ密教の秘伝を伝えるマハトマに託して、新たな『宗教』を捏造する行為に走らせる」と述べています。
そして、著者は以下のように述べるのでした。
「古くは、ジョルジュ・ブラン、オーギュスト・ヴィアット、ポール・ベニシューといった碩学が論じたように、ロマン派に連なる文学者・詩人が、18世紀の幻視者、あるいはエリファス・レヴィの『魔術』に魅せられ、それらの影響下に彼らの『霊感』を発達せしめた事実、ベルクソン、ジェームズら、心霊学の『同行者』たちが、どれだけ真面目に心霊学からのメッセージを受けとめ、彼らの哲学体系の中に吸収・発展させたかについては、それぞれの作家、詩人、哲学者についての厳密な研究に委せるべきだろう。しかし、その際にも、18世紀、19世紀の近代オカルティズムが置かれた、認識論的・社会的・政治的な文脈を離れて、単なる綺想に溢れた『意匠』の中に囲いこむことだけは避けなければならないだろう」
終章「神なき時代のオカルティズム」の冒頭では、「オカルティズムの可能性をめぐって」として、著者は「オカルティズムという問題を考える上で、フーコーに由来するエピステーメー=認識論的な断絶という観点は重要だ。現代につながる19世紀以降のオカルティズムとは、『墓地』と『子ども』とが同じ語句の中に共存できなくせしめた(フィリップ・ミュレー)認識論的断絶によって『神の死』が必然となり、それと共に『悪魔』や『魔術』すらあり得なくなった後も、なおも『神』や『霊魂の不滅』を信じたいとする欲求が生み出した、それ自体洞窟に映った影のようなものかもしれない」と述べています。
日本においてオカルトや魔術がフィクションとして、日本人の日常的な環境に広がり出すのは、1970年代の前半、ちょうど連合赤軍事件における左翼の全面的な敗北と同時期にあたります。前田亮一『今を生き抜くための70年代オカルト』が指摘しているように、70年代のオカルト・ブーム、魔術ブームの背景には、ユリ・ゲラーの来日などをきっかけにおこった心霊術(スピリチュアリズム)や心霊研究・超心理学への関心の深まりがあります。著者いわく、これが明治以来の「近代化」の過程で日本の中に侵入した「西欧」からの「新知識」だったのです。
そして最後に、著者は「70年代のオカルト・ブーム自体、60年代末から70年代初頭にかけての全共闘運動の完全なる挫折という、日本人青少年の外傷体験に根ざしているとともに、そうした外傷体験を『なかったことにすべく』、西欧からの刺激に対して、すでにはるか戦前から用意されていた日本のオカルト受容器がある種自動的な反射作用を起こしていると言えば、言葉が過ぎると反論されるだろうか」と述べるのでした。本書は、日本人によって書かれた初めてのオカルティズムの通史であり、これまで日本で出版されたすべてのオカルティズム関連書籍の中で最高の水準にある一冊であると思います。今後、何度も読み返したい名著です。
