- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.0109 メディア・IT 『追悼「広告」の時代』 佐野山寛太著(洋泉社新書)
2010.07.07
『追悼「広告」の時代』佐野山寛太著(洋泉社新書)を読みました。
著者は、メディア社会批評家にして、広告界を長くリードしてきた人物です。かつて広告業界に身を置いていたわたしにとって、非常に興味深い本でした。
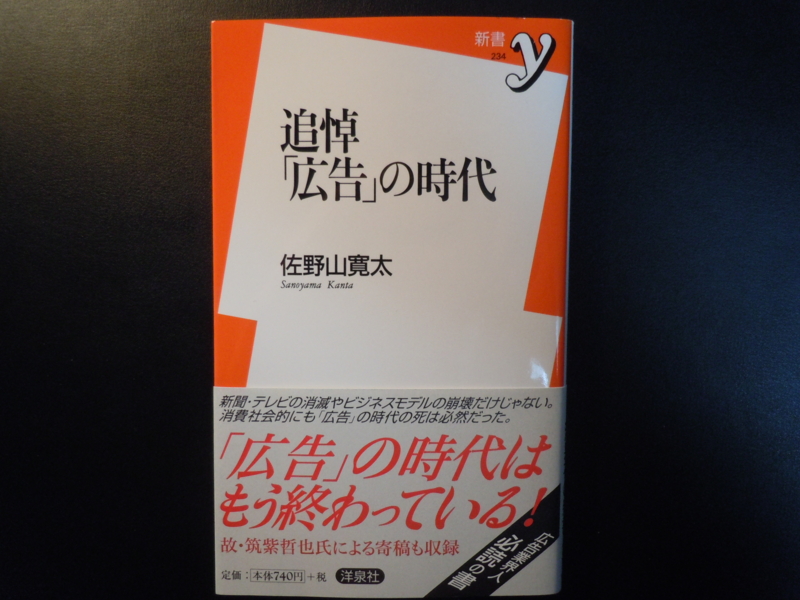
人間にとって広告とは何なのか
「追悼広告」つまり「黒枠広告」の話ではなく、「広告」への追悼です。そう、本書は「広告」の死について書かれた本なのです。帯に、「『広告』の時代はもう終わっている!」とのキャッチコピーが大きく踊り、「新聞・テレビの消滅やビジネスモデルの崩壊だけじゃない。消費社会的にも「広告」の時代の死は必然だった。」とも書かれています。
著者は、先行する2冊の新書を意識して本書を執筆したそうです。『新聞・TVが消える日』猪熊建夫著(集英社新書)および『2011年新聞・テレビ消滅』佐々木俊尚著(文春新書)で、わたしも2冊とも読みました。
著者は、2009年に刊行されたこの2冊について「時宜を得た出版」としながらも、その題名には異議を唱えます。単なる「新聞・テレビ」ではなく、「巨大な新聞社・テレビ局」とすべきだったというのです。ついでに「大手広告代理店」を加えると、なおいいといいます。
なぜなら、消滅するのは大新聞社・大テレビ局・大広告代理店であって、新聞・テレビ・広告ではないからです。著者は、序文「『広告』の時代への弔辞」で、次のように述べています。
「大新聞も大テレビも大広告代理店も、みんな大広告主の大広告費で食べてきた。想像を絶する食欲で食べ続け、驚くべき巨大さに肥大してきた。その大広告主たちが存亡の危機に瀕したため、大広告費で食べてきた巨大マスメディア集合が、下請けの業者、会社ともども消滅の淵に立たされている。減少した広告費をかき集めるため、中小メディアもあおりを食らって瀕死の状態になっている。『大新聞・大テレビが消える日』は2011年を待つまでもなく、もう来ている。マスコミと大手広告代理店が大手広告主のカネでつくり上げてきた『広告』の時代は、事実上ゾンビ化している」
「広告」の時代とは、「大量生産→大量流通→大量販売→大量消費→大量廃棄」の時代であると、著者は述べます。その「巨大化」が限度を超え、「広告による発展」が不可能となりました。その結果、「広告」の時代そのものがゾンビ化したのです。
「広告」は、消費革命を先導し、バラ色の夢と希望を描きました。百貨店に多くの人々を集め、無数のクルマを売りました。20世紀は、まさに「広告」の時代でした。しかし、ウェブやケータイなどメディアの多チャンネル化が進行するにつれ、消費者の生活時間の争奪戦が激化します。
マスメディアが凋落する中で、広告は根本的な変化を求められています。その変化とはビジネスモデルだけでなく、役割そのものさえにも及んでいるのです。著者は、「巨大化」し過ぎてしまった「広告」を恐竜に例え、次のように述べます。
「私は、太古の恐竜が、巨大化によって恐竜同士の生存競争に勝ち残ろうとし続けた結果、絶滅につながったことを思い出す。その一方、巨大化せず生き延び、新時代に適応していった元派虫類=鳥類の進化を思い出す。要するに新時代に適応するよう自己変革を遂げるか否かの問題なのだ」
そして、著者はなんと、かのマハトマ・ガンジーの名を出します。新時代に適応することは、「ガンジーを有名にした本来の力」を復活すればできるというのです。そして著者は、新聞もテレビも本も雑誌も広告代理店も、それぞれの「初心」あるいは「志」に戻って、「温故知新の進化」を遂げなければならないと訴えます。そうすれば、それらは新しい社会の中での存在理由を獲得できるというのです。
そして、これからの社会のキーワードは「家族」であり、「隣人」です。そこにはバーチャルな「マスコミ」ではなく、リアルな「皮膚コミ」があるからです。その最高のモデルを、なんと映画「男はつらいよ」の主人公である車寅次郎に見つけた著者は「寅さん社会の人間距離」という小見出しの文章で、次のように述べます。
「山田洋次監督が描いた、渥美清演じる『フーテンの寅』こと車寅次郎とその家族隣人たちが織りなす世界は、じつに『手触り』そして『気持ち触り』がいい。そこは、まさに『皮膚コミ』の世界なのだ」
また、次のようにも述べています。
「寅さんの世界で『人間距離』とは、そのまま「心間距離」を意味する。自分と家族と隣人の『心間距離』はきわめて近い。心同士が防御服をまとわず、裸のまま付き合っているようだ」
そこには、自他を区別しない「人間愛」があふれています。おいちゃんが「バカだねぇ、まったく」と言うときも、寅さんを本当にバカにしているのではなく、愛しているから嘆いているのです。隣の印刷会社のタコ社長が挨拶もしないで勝手に入ってきても、誰も文句を言いません。具合の悪いときだけは、「出てってくれ」と追い払われますが、それが仲違いにつながることはありません。そこは、まさに以心伝心の世界なのです。
「広告」がゾンビ化した今、「隣人」といったキーワードが立ち上がってくることに感動すら覚えますが、著者はさらに、「人間とは何か」「人間は何のために生きるのか」「人間にとって幸福とは何か」「幸福な人生とは何か」と。そして、次のように広告が示すものとは違う幸福な人生について語るのです。
「近ごろ、知人、友人たちがよく死ぬ。そのたびに思うのだ。彼の人生とはどういうものだったのだろうかと。そして自分自身を振り返って、自分の人生とはどういうものとして終わるのかと。もちろん結論など出ない。出す必要もない。ただ、思ったり考えたりするだけだ。しかし、結論は出ないが、結論のようなものはいろいろ思うし、感じるし、考える。それを言おう。人間はただ、生きるために生きるのだ、と」
「広告」の時代が終わるという話から始まった本書は、ついには壮大な人生論として終わります。そのスケールの大きさは、わたし好みでした。本書から、まず「談論風発」という言葉を連想しました。ガンジーとか、寅さんが唐突に出てくるところも素敵です。(笑)
「おわりに」では「インフレを起こすべきだ」とか「それにつけても食料自給率のアップが必須だと思う」など、ものすごく具体的な提言、それも「広告」とは直接関係なさそうな提言をバンバンしています。本当は、著者は「広告」にはそれほど関心がないのかもしれない・・・・・そんな気さえしてきます。
それでも、戦後の日本の広告の歩みが俯瞰できますし、メディア、経済、そして社会そのものの本質についても考えさせられる好著でした。