- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.0146 社会・コミュニティ 『社会力を育てる』 門脇厚司著(岩波新書)
2010.08.19
『社会力を育てる』門脇厚司著(岩波新書)を読みました。「新しい『学び』の構想」というサブタイトルがついています。
前著『子どもの社会力』で「人と人がつながり、社会をつくる力」を「社会力」として提唱し、注目を集めた著者の最新作です。
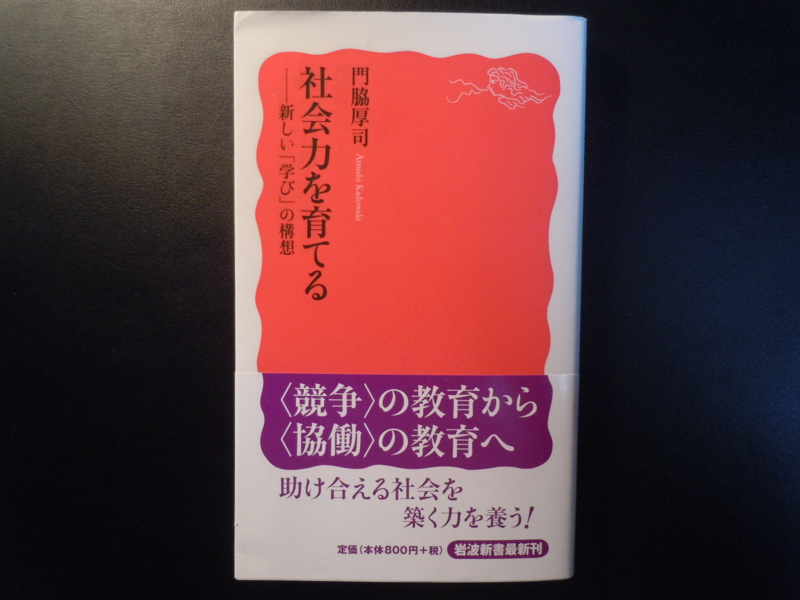
新しい「学び」の構想
まず、著者は、人が「私も社会の一員である」という自覚をもつことができるのはどうしてかと問いかけ、次のように述べます。
「私の見方を言えば、様々な人たちとの好ましいつながりができており、普段から親しく付き合いつつ、自分のやるべきことをやったり、誰かのために何かやってあげたりすることで、誰かに感謝されたり頼りにされたりすることから生じる自尊的な感情がおおもとにあるからである。心地よい人間関係の中にあって、そこに信用でき信頼できる誰かがいて、自分もまた誰かに認められ頼りにされ、互いに助け助けられつつ生きているとき、人は『私も社会の中にいる』と実感できるのであり、そこから『自分も社会の一員である』という自覚を募らせていくことになる。」
このような認識の上に立って、日本の若い世代の現状を見ると、著者は悲観的になるのを禁じえないそうです。なぜなら、社会の一員であるという自覚が生まれる原点ともいえる他者との緊密なつながりを自ら切断するか、つながりそのものを作ろうとしなくなっている人々が多くなっているからだといいます。それだけではありません。現代社会が抱える深刻な問題について、著者は次のように述べます。
「加えて、さらに悲しむべきは、匿名社会化と言うべき事態が進んでおり、自分の名前を伏せたまま、インターネットのブログなどで他人を容赦なく誹謗中傷したり、口汚く罵詈雑言を浴びせたりする若者が増えていることである。」
わたしも、悪質な匿名ブロガーの駆除こそは、現代の日本における最重要課題の1つであると思います。
しかし、人間というものは、もともと他者のことを思いやる存在なのです。著者は、「人間の本来的利他性」について次のように述べています。
「私たちは、不幸にも、近代産業社会の幕開けとともに、産業社会の発展にとって好ましく都合のいい人間像としてつくり出され喧伝されてきた『利己的人間神話』に慣らされてしまっている。人間は誰もが、自分の利益を最大限にすべく、何ものにも拘束されず合理的に判断し行動する動物である、という神話である。そのような神話を信じ込んでいる私たちが、今、改めて思い起こさなければならないのは、人間は利己的な生き物などではなく、もともと利他的な動物であったし、今でも利他性を失ってはいないということである。」
本書では、この「人間の本来的利他性」を主張するさまざまな言説が紹介されます。まずは紀元前4世紀、哲学者のアリストテレスが、人間は他者とともに生きるしかない「社会的動物」であると喝破しました。
時代は下り、19世紀前半に活躍した哲学者ヘーゲルは主著『精神現象学』において、人間は他者とともに生きるしかない社会的動物であるばかりではなく、自分を犠牲にしてさえ他者のためになることに生きがいを見出す生き物であると断言しました。ヘーゲルは「そもそも、個人の現実とは、他人とともにあり、他人とともに生きるしかない。個人の満足は、本質的に他人のために自分のものを犠牲にし、他人が満足するよう手助けするという意味をもつ」と述べています。
1807年刊行の『精神現象学』から半世紀以上たった1871年、進化論で知られるかのダーウィンが著書『人間の由来』を出版します。そこでダーウィンは、人間の道徳性の起源である「苦境する他者への共感や他者を助けたいという奉仕の心」が、自然淘汰によって強化されつつ遺伝を通して継承されてきた人間の社会的本能であることを、豊富な資料をもとに主張しました。
ダーウィンの社会本能説や道徳起源説は、近年になって、動物生態学者、社会生物学者、さらには進化心理学者、脳科学者たちの実証的な研究によって次々に立証されています。その代表的な研究者として、フランスの霊長類研究者フランス・ドゥ・ヴァールの名があげられます。彼は人間の利他性はチンパンジーやボノボなどの霊長類から引き継がれたものであることを示しました。日本においては、行動生態学者の佐倉統氏が著書『進化論の挑戦』で次のように述べています。
「人の心は、社会の中で生きるようにできている。人間ほど互恵的利他行動を進化させるのにピッタリの生物はほかにいない。人間は他者に親切にするよう遺伝的にプログラミングされていると考えていい。」
また、気鋭の脳科学者である澤口俊之氏は著書『HQ論~人間性の脳科学』で次のように述べています。
「人類の最も重要かつ基本的な社会戦略は、集団内のメンバーたちが互いに利他的行動をし合うことで集団内のメンバーたちの適応度(生き延びる確率を総体的に高める戦略としての共恵戦略(co-benefit strategy)である。この戦略こそがヒトを人間たらしめているといってよい。ヒトが高度に発達させた共感(sympathy/empathy)もこの戦略と結びついており、この機能は前頭連合野が担っている。」
脳科学者といえば、社会的知性の高度化と脳機能の質的向上との関連性について言及する研究者も多くなってきました。いまや時代の寵児になったともいえる脳科学者の茂木健一郎氏は、「人間の脳は、徹頭徹尾、社会的動物であることを前提に作られている」と断言しています。さらに茂木氏は、「日本歯科医師会雑誌」57巻1号において次のように述べています。
「現代の脳科学、認知科学者の多くは、人間の知性は、基本的に社会的知性であると考えている。もちろん、数を扱ったり、出来事を記憶したりといった基本的な知性の働きが重要なことはいうまでもない。しかし、人間にとっては他者とのコミュニケーションにおいて働く知性が重要である。道具を使うようになり、自然を征服した人間にとっては、自然環境の中で生き延びるということ以上に、人間社会の中でうまく生きるという命題が重要になった。進化の過程で、社会的知性の発達が促されたのである。」
また、日本を代表する脳科学者とされていた故・松本元氏は遺著となった『愛は脳を活性化する』で次のように述べました。
「われわれは、集団として生きる生き物であり、集団の中で生活し、行動する社会的な動物として進化してきた。言ってみれば、われわれは他の人と関わることによってのみ、生きることができるのである。そのためわれわれには、生まれつき他人と関わりを求めようとする関係欲求が、遺伝的に備わっていると考えることができる。」
こういった科学的根拠をふまえて、著者は、わたしたちが実現すべきこれからの社会とは「互恵的協働社会」であると主張します。日本および人類社会は、いま、格差問題、資源問題、環境問題、紛争問題といった、さまざまな難問を抱えて苦悩しています。こうした問題を解決するには、「互恵的協働社会」を実現するしかないというのです。
同じような社会は、すでに多くの人々が違った言葉で語っています。例えば、「信頼社会」「定常型社会=持続可能な福祉社会」「つながりの協働社会」などです。鳩山由紀夫前首相の「友愛社会」も、わたしの「ハートフル・ソサエティ」も、基本的には同じです。
著者によれば、「互恵的協働社会」とは、「自分の利益を最大限にすべく競い合い、他人を押しのけ排斥する社会ではなく、個人が備えている能力や利点を自分のためだけでなく他の人の利益や善き生(well-being)の実現のために提供することを当たり前のこととし、そうすることでともに快く生きていける社会」だそうです。そうした社会の特性を、著者は次のように4つあげています。
① 性や出自、民族や国籍など、自分の責任を問われる理由や根拠がない事柄で、特定の人びとを社会的に差別したり、排除したり、不快にさせたり、傷つけたりしない。
② 教育の機会や資源など、限りある社会的資源を公正に配分することにより、それぞれの善き生を構想し実現するために不可欠な個々人の潜在的可能性(capability)を最大限に高めることを最優先する。
③ 生得的に恵まれた優れた能力や、相続や努力などで手に入れることができた豊かな資源を、他者の善き生の実現のために提供することを互いに当然のことと考え実行する。
④ 他の人をケアすること(他者に対する配慮的な行為)が、自分の生きがいを高め、自分の善き生を実現することにつながる。
そのような社会を実現するためには、子どもや若者たちの社会力を高めなければなりません。そして、何よりも求められるのは、地域という場において、先行世代である大人たちと後続世代である子どもたちが、日常的に直接交わり活動をともにすること。
著者は、「地域が親密圏になっている必要がある」と訴えます。親密圏(intimate sphere)というのは、「空間的に比較的近くに住んでいる人たちが、互いに知り合い認め合う仲になっており、普段から行き来したり、物を分け合ったり、助け合ったり、庇い合ったりして生きている、安心できる場」という意味だそうです。著者は述べます。
「これまで、親密圏の典型として家庭や家族があげられてきたが、これからは、かつての地域がそうであったように、地域を再び親密圏にする努力をしなければならないと考える。なぜなら、家族の規模が小さくなり、しかも、家族で食卓を囲んだり、家族で団欒したり、家族が力を合わせ協働作業するといったこともほとんどない。極端な場合、家はただ寝るために帰るだけの場所になってしまっている。そうした家庭、家族のありさまを見るとき、地域こそ子どもや若者たちを育てる場として想定しなければならないと考えるからである。」
近年、貧困家族が激増し、2007年の時点で14%に達しています。母子家庭などの一人親家族になると5割以上が貧困家族だそうです。最近も、幼い姉弟が母親から置き去りにされ餓死したという痛ましい事件がありましたが、そうした家で育つ子どもたちの現状を考えたとき、地域を親密圏にし、地域社会全体で子どもを育てることは避けられなくなってきています。著者は言います。
「さらに言えば、地域を親密圏にすることによって、そこでの大人どうしの交流や協働も増え、子どもたちばかりでなく親や大人たちの社会力も高まる。そのことが、社会関係資本をより強固にし、地域を公共圏に変えていく可能性が高まってくると考えるからである。」
地域を親密圏にする最良の方法、それはやはり「隣人祭り」ではないでしょうか。いまや「隣人祭り」は孤独死の防止に止まらず、子どもや大人を含めたすべての地域に住む人々の幸せのためにあるのだと思い至りました。