- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.0350 ホラー・ファンタジー 『狂』 坂東眞砂子著(幻冬舎文庫)
2011.06.10
『狂』坂東眞砂子著(幻冬舎文庫)という本を読みました。
著者の代表作は大体読んだので、そろそろ打ち止めにしようと思っていました。そこへ本書が今年の2月に文庫化されたので、読んだのです。
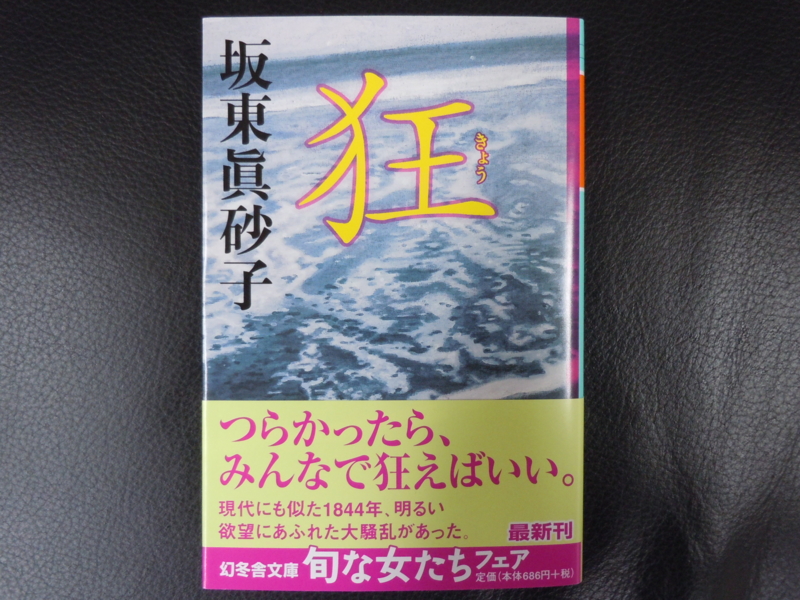
1840年代の集団憑依事件を描く
本書は、2008年1月に単行本として刊行された『鬼神の狂乱』を改題し、文庫化したものです。幕末の土佐で実際に起こった集団憑依事件をもとにしています。
そして、土佐を揺るがすほどの大騒乱の顛末が描かれています。
時は1840年頃、事の発端は村の男たちが仮装して家々を訪ねる四国は山村の祭事・粥釣の夜でした。16歳の少女みつの住むあばら屋にも5人の男が上がり込んできますが、その中に侍を装った見知らぬ男が紛れていました。その翌日から、村人たちの様子が一変します。彼らは神社に集い、奇声をあげ、祝詞を叫び、踊り出すのです。
ついには白昼堂々、交わる者たちさえ出てきます。
彼らを動かすのは狗神なのか、古狸なのか、それとも・・・・・。
これまでの著者の長篇小説と違って、いわゆる超常現象を描いてはいるのですが、読んでいても恐怖は感じません。恐怖小説とか伝奇小説というのではなくて、歴史上の事件を淡々と綴っている印象です。実在する資料にある程度忠実に書いているので、まるで司馬遼太郎の歴史小説を読んでいるような感さえあります。
本当に狗神や古狸といった動物霊が農民たちを狂わせているのか、逃散をたくらむ農民たちの狂言なのか、最後までその真相はわかりません。
ただ、「狗神憑き」に代表される古いものが一掃され、新しい世の中を迎えつつある幕末の人々の不安定な心をよく描いています。
西洋の悪魔憑きを連想しますが、本書の巻末の「参考文献」リストの中に『エクソシストとの対話』島村菜津著(小学館)があるので、著者もバチカン・エクソシズムを意識していたようです。
本書に描かれている時代、日本中で誰かが何かに憑依されていました。
1839年、大和国山辺郡庄屋敷村(現在の奈良県天理市三島町)の農民・中山みきに「親神」である天理王命が天降ったとされ、天理教が生まれました。
また、1867年から68年にかけては、「ええじゃないか」が起こりました。
これは、東海道や畿内を中心に、江戸から四国に広がった社会現象です。
天から御札(神符)が降ってきて、これが「慶事」の前触れであるという話が広まって、民衆が仮装し「ええじゃないか」という囃子言葉を連呼しながら、集団で町々を巡って熱狂的に踊ったのです。幕末の日本は国をあげてシャーマニズムに浸っていました。
さらに言えば、本書の時代背景である1840年代は世界的にも「狂」の時代でした。
1848年、アメリカのニューヨーク郊外ハイズビルに住むフォックス姉妹が死者の霊と交信するという、いわゆる「ハイズビル事件」が起きました。
これがきっかけとなり、アメリカからヨーロッパ各地へとまたたく間に「スピリチュアリズム」のブームが広がり、大流行しました。
多くの霊媒が各地に輩出し、交霊会が各地で盛んに行われました。
またハイズビル事件が起きた1848年は革命の年でもありました。
フランスの2月革命、ドイツおよびハンガリーの3月革命、ポーランドやハンガリーやアイルランドの独立運動、イタリアの統一運動などが起こりました。
労働運動が盛んになり、マルクスの『共産党宣言』が出されたのも1848年です。
このように、世界的に見ても、1840年代末は狂乱の時代だったのです。
そして、その狂乱の時代にピークには1868年の明治維新がありました。
日本の明治維新は世界史的に見ても、さまざまな意味で奇跡的な革命と呼ばれますが、そのスイッチャーとなったのは長州の吉田松陰、そして彼が主催する松下村塾の人々でした。松陰は、志とは、どんなに邪魔が入っても、打ちのめされても、孤立しても、それでも貫かねばならないものだと考えていました。
そのためには、たとえ「狂」のそしりを受けても構わないのだというのです。
「狂」は崇高な境地でした。変革を望み、志を胸に時代の先端に立ち続ける者たちの言動は、必ずしも周囲に理解されるわけではありません。
いや、まず理解されないのが自然でしょう。
松陰および門下生は、当時は「志士」ではなく、「乱民」と呼ばれ、周囲から白眼視されたそうです。松陰は、絶大な権力である徳川幕府を激しく批判する、あるいは老中など権力者の暗殺を企む、きわめて危険な「乱民」なのでした。
当然、松下村塾に息子が通うのに、反対する親は多く、松下村塾に通っているというだけで、当人はもちろん、家族までが「乱民」として近所から村八分に遭ったという話も残っているほどです。言うなれば、当時の松下村塾とは一種の反社会的テロ集団の側面を持っていたのです。それほど松下村塾は周囲から理解を得られませんでした。
それでも、誰にも理解されないものを、純粋な心で真剣に見つめ、進むからこそ先覚者なのです。最初から誰からも理解され、支持されている先覚者など、ありえません。
『松陰と晋作の志』(ベスト新書)の著者である一坂太郎氏は、その厳しい宿命を、松陰たちは「狂」の境地に達することで受け入れたのだと述べています。
人々は、先覚者を先覚者とは気づかずに、狂っていると考えます。そんな周囲の雑音に惑わされ、志を曲げないためにも、先覚者は自分が狂っているのだと、ある種開き直る必要があったのです。先覚者を気取り、変革、改革を連呼して支持率を上げようとする現代の政治家とは、根本が違うのです。
松陰の影響もあり、幕末長州の若者たちは、好んで自分の行動や号に、「狂」の文字を入れました。彼らの遺墨を見ると、高杉晋作は「東行狂生」、木戸孝允(桂小五郎)は「松菊狂夫」などと署名しています。慎重居士の代表のように言われる山県有朋でさえ、幕末の青年時代には「狂介」と称していました。
一坂氏の著書では、題名の通りに、松陰と晋作の志が情熱的に語られています。
松下村塾にも、志がありました。過激な言動が祟り、再び獄に繋がれることになった松陰は、門下生たちに漢詩を残して訴えました。
長門の国は日本の僻地である。しかも、松本村は、その僻地の中のさらなる僻地にある。しかし、ここを世界の中心と考え、励もうではないか。そうすれば、ここから天下を「奮発」させ、諸外国を「震動」させることができるかもしれない。
あまりにも壮大な志です。しかし、松本村の小屋に近所の子どもたちを集めて教えているに過ぎない松陰の発言内容を知れば、案の定、周囲の者は狂っていると思ったに違いありません。どんなに好意的に見ても、若き松陰の青臭い理想でしかありません。
ところが、この志は現実のものになっていきました。「乱民」と呼ばれながらも、「志を立てて万事の根源」とした者たちが、ついに時代を揺り動かしていったのです。
松陰はその晩年、ついに「狂」というものを思想にまで高め、「物事の原理性に忠実である以上、その行動は狂たらざるをえない」とずばり言いました。
そういう松陰思想の中での「狂」の要素を体質的に受け継いだ者こそ、晋作でした。
司馬遼太郎は、「晋作には、固有の狂気がある」と述べています。その晋作の辞世の歌に題名が由来する司馬の『世に棲む日日』には、松陰に発した「狂」がついには長州藩全体に乗り移ったさまがドラマティックに描かれています。
松陰が生きていた頃は、松陰一人が狂人だった。晋作がその「狂」を継ぎ、それを実行し、そのために孤独でした。その晋作の「狂」を、藩も仲間もみな持て余していました。
ところが、藩が藩ぐるみで発狂してしまったのです。
長州藩一つで、英仏独米という世界を代表する列強に戦争を仕掛けた「下関砲台事件」など、あまりにも馬鹿げた巨大な「狂」以外の何物でもありません。
しかし、その巨大な「狂」が、人類史に特筆すべきレボリューションを実現したのです。
企業においても、イノベーションの実現を真剣に考えるならば、まずは1人の狂人を必要とし、次第に狂人を増やし、最後は企業全体を発狂させねばならないと思います。
あの孔子でさえ、表面上「人格者」と呼ばれる者よりも、「狂者」と呼ばれる者に期待すると説いたのです。
本書『狂』の最後のほうに、教養のある農民・文吉が次のような言葉をつぶやきます。
「今の世には狂うことこそ必要なんじゃ。世を変えるには、それだけの力がな。狂乱を呼ぶのは、先祖の力じゃ。先祖を知り、礼拝することで、われらの道が教えられる」
ここで「先祖」というキーワードが出てくることが興味深いと思います。
わたしは、つねづね日本人の最大の信仰とは「先祖崇拝」であると言っています。
本書に何度も名前が出てくる幕末の国学者・平田篤胤はわが国の民間信仰の根幹をなすものとして「先祖祭り」を重視しました。
氏神信仰などは「先祖祭り」の典型と言えます。
祭りの対象は先祖代々の霊すなわち祖霊です。
通常は33年の最終年忌をトムライアゲ・トイアゲといって、葉付塔婆やうれつき塔婆という塔婆を立てます。これを境に死者は死穢から清まり、先祖や神になるといいます。
最終年忌がすむと、位牌を流したり、墓石を倒したりする地方もあります。
ちょうど一世代たつと、死霊は個性を失って、祖霊という群霊体に融合し、子孫や郷土を守る先祖として祀られるわけですね。ドラマティックな「先祖」の誕生です!
今はやりのスピリチュアル用語を使えば、ここでいう「死霊」とは「ソウル」、祖霊という群霊体は「グループ・ソウル」ということになるでしょうか。
これまで宜保愛子、細木数子、江原啓之といった人々がテレビをはじめとしたメディアを騒がせ、「霊視」とか「占星術」とか「スピリチュアル」とか多様な表現を使ってきました。
でも、彼らのメッセージの根本はいずれも「先祖を大切にしなさい」ということでした。
日本人にとっての最大の信仰の対象とは「先祖」に他ならないことをメディアの申し子である彼らは熟知していたように思います。
まさに、伝統宗教から新興宗教、新宗教、そしてスピリチュアルまで、日本人の精神世界における最大のコンセプトとは「先祖供養」なのだと思います。日本人にとっての三大宗教である神道・仏教・儒教も、いずれも「先祖崇拝」という共通点を持っています。
この三大宗教を統合したものに石田梅岩の「心学」があります。
本書『狂』では、この心学が危険思想として登場しており、ちょっと驚きました。
なにしろ、心学は「妖術」と誤解されているのです。
そこで馬三郎という農民が、心学について次のように仲間に説明します。
「心学とは、神儒仏、つまり神道、儒教、仏教、それぞれの学説を統合したものじゃ。ちゃんとした学問のひとつで、妖術なぞではない」
最後に、参考文献の1冊である『エクソシストとの対話』の著者で作家の島村菜津市が、本書の「解説」に書いた一文を紹介しましょう。
島村氏は次のように、この『狂』という不思議な小説の本質を見事に述べています。
「『狂』も覚書の中に、作家も『すべての事象に説明をつける科学性に不満を抱いている』ときっぱりと言い切っているように、この作品は、ヒステリーやトランス状態という言葉をあてがい、わかった気になっている現代に喧嘩を売っているのだ。そればかりか、黒船来航、幕府や藩の財政難、飢饉に伴う農村の貧困といった当時の時代背景は、不思議なほど、今の日本に重なる。だからこそ、憑かれて狂う人々への、そして顛末に何らかの神秘を感じ、『決して妄言にあらざるなり』と報告した江戸末期の役人への、作家のまなざしは、限りなく温かい。深読みかもしれないが、この作品は、世界中に均質な価値観と均一な商品が溢れ、閉塞感の中で悶々とする現代の民が、その本来の創造的なエネルギーを解き放つすべを、小説を通じて模索しているようである」
「解説」の最後には、著者が現在、郷土でもある高知県の山間部に移り住んでいることが書かれています。イタリアのミラノやタヒチでの生活を経て、著者はやはり四国に帰ってきたことを知って、わたしは何だか、しみじみと嬉しくなりました。
宿を改装したという山深い一軒家で、著者が再び『死国』や『狗神』のような恐怖小説、あるいは『桃色浄土』や『山妣』のような伝奇小説の名作を書き上げてくれることを1人のファンとして願っています。このへんで著者の小説を読むことをいったん中断しますが、その幻想世界に浸る日々はまさに至福の時間でした。