- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2011.09.15
『悲しんでいい』髙木慶子著(NHK出版新書)を読みました。
著者は日本におけるグリーフケアの第一人者で、上智大学グリーフケア研究所の所長でもあります。自ら阪神・淡路大震災で被災しながら、被災者たちの心のケアに取り組んできました。その後は、JR西日本の脱線事故の遺族の心のケアにも関わりました。今また、東日本大震災の被災者たちの心をケアする著者が、悲しみに寄り添う心がまえを説いたのが本書です。
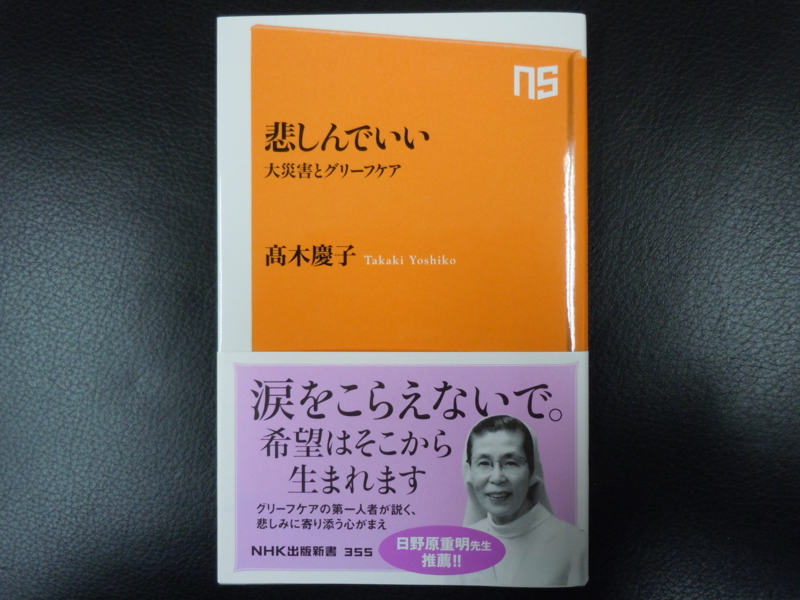
大災害とグリーフケア
本書の目次は、以下のような構成になっています。
「はじめに~涙一滴、流せないあなたへ」
第1章:「癒しびと」なき日本社会
第2章:心の傷は一人では癒せない
第3章:弱っている自分を認める勇気
第4章:「評価しないこと」と「口外しないこと」
第5章:老若男女、それぞれの喪失体験
第6章:小さな希望でいい
終章:ほんとうの復興のために
「あとがき」
「はじめに―涙一滴、流せないあなたへ」で、著者は次のように述べています。
「多くの方たちがいま、深い悲しみをおぼえ、心にぽっかりと穴が空いたような喪失感をかかえながら、それでも涙一滴流せずに、復興に向けて歩んでいます。
この本を手にとったあなたも、悲しみをこらえ、未来の復興を信じて、毎日がんばっていらっしゃることでしょう。でも、失ったものがあまりにも大きいため、ときに胸を締めつけられるような苦しみをおぼえることがあるかもしれません。深い悲しみをもてあまし、夜も眠れず、不安から逃れるためにアルコールにおぼれてしまう方もいるかもしれません。大切なものを失ったときの悲しみとどう向きあえばいいのでしょうか。さらに、あなたの隣人の悲しみにどう寄り添えばいいのでしょうか。そして、お互いに支えあいながら、どうやって悲しみの日々から立ち直っていけばいいのでしょうか―」
著者が長年取り組んできた「グリーフケア」とは何か。「グリーフケア」を「悲嘆からの回復」と 位置づける著者は、次のように述べています。
「さまざまな喪失体験から生じる『負』の感情を、”グリーフ(悲嘆)”と呼びます。
日本人はいま、かつて経験したことのないような深い悲嘆の苦しみを強いられているのではないでしょうか。大震災と原発事故は、言い換えれば『自然災害』と『人為災害』でもあります。突然襲ってくる天災による喪失体験は、人から生きる希望を奪います。事件や事故といった人災による喪失体験は、悲しみとともに加害者への激しい怒りをもかきたてます。天災のダメージと、人災の拡大は、それだけ複雑に私たちの心を傷つけ、日本中を失意の底に陥れたのです」
大災害や事故の当事者にならないまでも、 人は多かれ少なかれ、悲しい現実に直面することがあるのです。 本書では、悲しみに直面している本人はどうすべきか、 支える人はどうあるべきかが述べられています。理論というよりも、著者の体験に基づいたアドバイス的な内容です。たとえば、自身の被災体験について、著者は次のように述べています。
「阪神・淡路大震災のとき、私は大きな揺れと同時にベッドから床に振り落とされ、次の瞬間、戸棚がベッドの上に崩れ落ちてきました。もしもベッドの上に横たわっていたら、重い戸棚が私の頭を直撃していたのです。あのとき”生かされた”ことは、『ここで死んではいけない、あなたにはまだやるべきことがある』という神さまの意思だったと思えてなりません。そして、やるべきことをやるときが来たと、いま私は感じています」
「グリーフケア(悲嘆からの回復)」とは、いったい何か。著者によれば、それは被災者と支援者とが手を取り合って復興に向かう第一歩です。著者は、まず「悲嘆を引き起こす7つの原因」について次のように述べています。
1.愛する人の喪失―死、離別(失恋、裏切り、失踪)
2.所有物の喪失―財産、仕事、職場、ペットなど
3.環境の喪失―転居、転勤、転校、地域社会
4.役割の喪失―地位、役割(子どもの自立、夫の退職、家族のなかでの役割)
5.自尊心の喪失―名誉、名声、プライバシーが傷つくこと
6.身体的喪失―病気による衰弱、老化現象、子宮・卵巣・乳房・頭髪などの喪失
7.社会生活における安全・安心の喪失
阪神・淡路大震災や東日本大震災は、天災、すなわち自然災害です。災害によって愛する人を亡くした人の悲しみは、災害以外の遺族の悲しみとどう違うのか。一般に、災害によって大切なものを失った人の悲しみは、病気などで家族を失ったご遺族のそれに比べて、回復までに時間がかかるとされています。その理由は、「お別れ」の時間を与えられることなく、無理やり関係に終止符が打たれてしまうからです。
ターミナルケアの先駆者でもある精神科医の柏木哲夫博士は、ホスピスで家族を看取った遺族が悲嘆から回復するまでの期間を、「約80%が18ヵ月」と発表しています。「お別れ」の機会があっても、それだけの時間がかかるわけです。ということは、災害で突然家族を奪われた遺族の心の傷が回復するまでには、さらに長い年月を費やさなければなりません。
災害大国に住む日本人には、他国の人々にはない独特の思想がありました。著者は、「人知の及ばない大いなる力の存在を認めたとき、人間は畏怖の念をいだきます。多くの人の命が一瞬にして失われてしまう大災害をたびたび体験することによって、仏教が伝わる以前から、日本人の心のなかにはすでに無常観や末法思想といった精神風土が形成されていたのではないでしょうか」と述べています。
しかし、今回の東日本大震災は、それだけでは済みませんでした。大地震や大津波だけでなく、原発事故というおまけがついたからです。著者は、「東日本大震災の被害を拡大し、被災者の悲しみをより複雑にしたのが、東京電力・福島第一原子力発電所の事故です。この事故が地震と津波によって引き起こされたことは事実でしょう。しかし、不可抗力ということばではすまされません」と述べます。
グリーフケアとは広く「心のケア」に位置づけられますが、「心のケア」ということばが一般的に使われるようになったのは、阪神・淡路大震災以降です。
被災した方々、大切なものを失った人々の精神的なダメージが大きな社会問題となり、その苦しみをケアすることの大切さが訴えられました。しかしながら、「心のケア」ということばは定着したものの、「何をどうケアするのか?」ということが十分に議論・研究する機会はなかったのではないかとして、著者は述べます。
「『眠れない』症状にたいして睡眠剤を与える。『気力の出ない』症状にたいして精神安定剤や抗うつ剤を与える。『行方不明の息子さんを案じる心』や、『愛する妻を失った悲しみ』に寄り添うことなく、たんに体の不調を薬で治そうとするわけです。それでは人の心は癒されません。『心のケア』とは、まさしく『グリーフ(悲嘆)ケア』のことなのです。傷口に黙って薬をぬって治すような感覚では、人間の心のケアはできません」
かつての日本の社会には、「グリーフケア」という言葉などありませんでした。大切なものを失った人の悲しみを癒してくれる環境があったからです。その環境について、著者は次のように述べます。
「昔から日本では、大家族で生活が営まれてきました。家のなかにはおじいちゃんがいて、おばあちゃんがいる。お父さんとお母さんがいる。子どもはおおぜいの兄弟姉妹とともに育ち、家によっては4世代が暮らすことも珍しくありませんでした。
また、地域社会には濃密な人間関係がありました。おすそわけというご近所どうしの習慣は当たり前のようにありましたし、町内には世話好きなおばちゃんもいたし、やんちゃ坊主を叱ってくれるおっかないおじちゃんもいたものです。
そういった社会のなかで、たとえば子どもを亡くした若い夫婦がいたとしたら―。
意外に思われるかもしれませんが、若い夫婦の悲しみをもっとも身近で引き受けてくれたのは、おじいちゃんやおばあちゃんなのです。また、同じような体験を持つご近所の人たちも、若い夫婦の悲しみに寄り添ってくれる存在でした」
たしかに、親には反発しても、祖父や祖母には素直な人間というのは多いですね。親は、どうしても子どもが心配なので、説教をしたり叱ったりします。子どものほうも、親の愛情はわかっているので、余計な心配をかけたくないと思います。
著者は、「親には話せなくても、大好きなおじいちゃんやおばあちゃん、顔なじみのご近所さんには話せることがあるのです。おじいちゃんやおばあちゃんやご近所の人たちというのは、自分の悲しみを受け止めて、一緒に泣いてくれる存在でもありました。そういう”癒しびと”が、かつての日本人の日常にはいたのです」と述べます。なるほど、悲しみを受け止め、一緒に泣いてくれる人は「癒しびと」なのですね。
阪神・淡路大震災から15年経った2010年、神戸新聞社が遺族を対象にアンケート調査を実施したそうです。その中の「あなたを一番支えてくれたものは何ですか?」という質問に、約6割の遺族が「家族」と答えました。しかし、「震災体験を話す相手」をたずねてみると、一番多かったのは家族ではなく、「友人」や「親戚」だったとか。このアンケート結果について、著者は次のように述べています。
「この結果は、悲嘆ケアとは何かを物語っています。深い悲しみを背負ったとき、家族は大きな支えになります。しかし、家族は存在するだけでいい。自分が背負った深い悲しみを表に出せる相手、言い換えれば、悲嘆の感情を受け止めてくれる癒しびとというのは、家族よりも”心を許せる第3者”のほうがふさわしいということです。
現代の日本社会では核家族化が進み、地域の人間関係もどんどん希薄になっている。この状況は、かつては身近にいた癒しびとが、いなくなってしまったことを意味します。そして、悲嘆をかかえる人たちの多くが、自分の悲しみや苦しみを受け止めてくれる相手がいない”孤独”を味わっています」
日本人が阪神・淡路大震災を体験した1995年は、被災者に対する善意の輪が全国に広がりました。1年間で延べ137万人ものボランティアが支援活動に参加しました。
ボランティア活動の意義が広まったこの年は、「ボランティア元年」と呼ばれます。16年後に起きた東日本大震災でも、ボランティアの人々の活動は被災地で大きな力となっていますが、東日本の被災地が復興を果たし、涙と汗をぬぐって振り返ったときに、2011年が「グリーフケア元年」だったと笑顔で言えることを、著者は祈っているそうです。わたしも、そうなることを心から願っています。
本書を読んで非常に参考になったのは、「うつ」についての記述です。
一般に、「グリーフ(悲嘆)」は、「うつ」に発展する危険性が高いとされます。しかし、うつという病と、悲嘆によるうつ的状態とは、似て非なるものだと著者は言います。
たとえば、リストラにあってうつ病になったという人の場合を考えてみましょう。リストラは彼のうつの引き金にはなったとしても、その背景には仕事への不満、健康への不安、家族関係の不和など、さまざまな要因がからみあって存在するとされます。
一方、悲嘆によるうつ的状態は、原因がはっきりしています。それが喪失体験です。著者は、「大災害などでは、悲しみの要因が重複する場合もありますが、それらはすべて喪失体験と呼べるものです。別の言い方をすれば、悲嘆によってうつ的状態に陥った原因は、他人に言える悩みでもあるのです」と述べています。
いま、日本における自殺者の数は、年間3万人を超えています。交通事故で亡くなる人の約6.5倍もの人が、自ら命を絶っているわけです。そんな現実を反映して、日本では4人に1人が「うつ」にあると指摘されることもあります。それらの人々は、なぜ新しい未来を手に入れることに背を向け、うつに逃げ込んでしまうのでしょうか? その問いに対して、著者は次のように答えています。
「それだけ心が疲弊してしまったのはたしかなことですが、あえて厳しい言い方をさせていただければ、うつに逃げてしまったほうが一時的に楽になれるからです。
それまでできていたことができなくなる―普通ならば、その状態を周囲の人は『わがまま』と呼びます。悲しみにくれ、何をする気力もわかなくなっている人にとって、できなくなったことを『わがまま』と言われるのは、たいへんつらいことです。でも、そこで『うつ』という大義名分を手に入れてしまえば、自分に言いわけができますし、できていたことができなくなった日常を続けることが許されると感じられるのかもしれません」
この「わがまま」と「うつ」のくだりなど、なかなか普通の人にはここまで言えません。長年、心のケアの現場で生きてきた著者ならではの卓見であると感銘を受けました。
これまで、東日本大震災の被災者へのメッセージ本を何冊か紹介してきました。正直言って、それらの本は学者が頭だけで書いたイメージがありました。
しかし、本書はグリーフケアの第一人者が書いただけあって、実践的な内容が多いと思いました。特に、「こういうことを行ってはいけない」というNG的行為について触れた箇所が参考になりました。たとえば、著者は「ケアする際の好ましくない態度」を7つあげています。家族を失った遺族の協力を得て実施した調査の結果からまとめたものです。それは、以下のようになっています。
1.忠告やお説教など、教育者ぶった態度。指示をしたり、評価したりするような態度
2.死という現実から目を背けさせるような態度
3.死を因果応報論として押しつける態度(過去の事実と現実の死とを短絡的に結びつけ、悪行の報いやたたりなどと解釈すること)
4.悲しみを比べること(子どもの死は配偶者との死別より悲しいなどとする見かた)
5.叱咤激励すること
6.悲しむことは恥であるとの考え
7.「時が癒してくれる」などと、安易にはげますこと。もっぱら楽観視すること
本書で最も共感したのは、日本における葬儀の役割について述べた部分でした。クリスチャンである著者は、次のように述べています。
「日本では、仏式のお葬式が一般的です。私はクリスチャンですが、仏教の供養は悲嘆にある方の心を癒してくれる、先人の知恵だという気がします。
大切な人が亡くなると、葬儀で送る前に、お通夜があります。ご遺体のそばにご遺族や親戚や知人が集まり、亡き人との別れを惜しみます。そして、葬儀がすんだあとも、初七日、四十九日法要、一周忌、三回忌、七回忌、十三回忌と、供養が営まれます。
このしきたりは、ご遺族の悲しみの心を癒すものでもあります。法要のたびに親戚が集まることは、『亡き人のことを忘れてはいません』『残された家族のことをみんなで心にかけています』という思いをご遺族に伝えることになるのですね。
大切な人を失った方にとって、忘れてほしくないことは2つあるのです。それは、悲しみを負った自分自身の存在と、故人の存在です。亡き人への追悼のことばは、そのままご遺族への癒しになるのです」
『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)や『葬式は必要!』(双葉新書)など一連の著書で、わたしは「葬儀こそは最大のグリーフケアである」と訴えてきました。ですので、著者の発言には大いに共感してしまいました。
また、「子どもは”死”をいつ理解するのか」という箇所も興味深かったです。
「人は死ぬ」ということを、子どもは何歳になればわかるのか? 1948年にハンガリーのマリア・ナギーという心理学者が、3~10歳までの子どもを対象に調べたところ、「子どもは9歳で人間の死を理解する」という結果でした。
それが世界的な共通認識になっていたのですが、著者が代表を務める「兵庫・生と死を考える会」が2003年におこなった「幼児・児童の死生観についての発達段階に関する意識調査」では、日本の子どもたちは6歳になると、約80%は「人の死」というものがわかるという結果が出たそうです。
子どもは、もともと”死”について知りません。それは、親が教えるべき大切なことなのです。しかし、著者は次のように述べています。
「私の印象ですが、いまは子どもに”死”を語ることができない親が増えているのではないでしょうか。なかには、『お母さんはもういないんだ』と、子どもが大好きな母親の存在を消してしまうようなことを無神経に言ってしまう父親もいます。『そんなことはママにもわからない』と言って、子どもの気持ちをさらに混乱させてしまう母親もいます。
子どもに『人の死』を伝えるには、大人の側がしっかりと死生観を持っていなければなりません。誰もがいつかはかならず迎える”死”について、真剣に考えたことがない大人は、『死んだらどうなるの?』という子どもたちの純粋な疑問の前に立ちつくしてしまうことになるのです」
さらに著者は、子どもたちへの「死の教育」について力説します。
「『人の死』はつらいものです。でも、”死”を思い、”死”も人生の大切な一部であることをわかっていれば、愛する人を失ったときでも、人間は深い悲しみのなかからかならず新たな一歩を踏み出せるはずです。子どもは6歳ごろになれば死というものを理解できると書きました。日常から”死”を学べなくなったいま、『生と死の教育』には学校でも取り組むべきだと私は考えています」
この著者の意見に、わたしは全面的に同感です。著者は、「小学校では、すでに性教育が取り入れられています。セックスに関する教育は、かつては”社会勉強”にゆだねられていました」と述べ、その場として赤線地帯をあげます。
戦前の男たちは、赤線の女たちに「女性の体」と「セックス」について手ほどきを受け、そこで学んだ知識が仲間内で広がっていく。一方、戦前の女性は「性」を語ってはならなかったので、結婚してから夫からセックスを教わった。著者は述べます。
「赤線地帯がいいものだったと言うつもりはありません。ただ、そういう場で繰り返されていた性の教育が、いまでは学校のカリキュラムに取り入れられている。そうであれば、社会の日常からは学べなくなった『生と死の教育』も、いまや学校が教えるべき大事な教養科目といえるのではないでしょうか」
わたしは、修道女である著者が赤線を持ち出したことに驚きながらも、そこまでして「生と死の教育」の重要性を説く姿に感動をおぼえました。
感動といえば、被災地には多くの有名人が駆けつけ、被災者たちは感動しますね。アイドルがボランティア活動を手伝い、俳優が炊き出しをし、ミュージシャンはライブを行います。それらの行為に対して「売名行為」などの声があることも事実です。しかし、著者は次のようにコメントしています。
「自分たちを勇気づけるために、多くの有名人が遠くから来てくれる―。
さまざまな支援のイベントは、被災した方々にとっては、日本中が応援してくれていることを実感できる瞬間ではないでしょうか。
ただ、そういったイベントは、心のケアとはすこし異なっています。イベントは非日常的なものですが、心のケアは日常のなかで継続的におこなうものです。もちろん、イベントによってつらい日常をひととき忘れ、明るさを取りもどすことも心の癒しにはつながりますが、地域や住民に密着して継続的におこなうという性格のものではありません。多くは一時的なもので、いってみれば元気づける速効性はあるものの、悲嘆の感情そのものを回復に向かわせるような持続性はあまり期待できないのです」
その意味では、参加型のイベントのほうが、より悲嘆の感情に寄り添えるのではないかと著者は言います。そして、その良い例が、お祭りなどの催しです。被災地を訪れる政治家や芸能人の一部には、たしかに売名行為の人々が実在します。
しかし、唯一、完全に売名行為とは無関係に被災地を訪問する存在があります。それは、天皇皇后両陛下です。ブログ「日本のこころ」にも書いたように、天皇皇后両陛下こそは最高のグリーフケアの達人ではないでしょうか。聖心女学院で皇后陛下の2年後輩にあたるという著者も、次のように述べています。
「東日本大震災のあと、天皇皇后両陛下は何度も被災地に足をお運びになられました。両陛下が国内にお出ましになることを行幸啓というのだそうですが、そのお姿に心を癒された方は数えきれないほどでしょう。
行幸啓のたびに、そのご様子はニュースでも伝えられますが、テレビの画面で拝見していると、被災した方々をはげまされる天皇皇后両陛下のお姿は、悲しみの心に寄り添うときのお手本のようにも感じられます。
相手と同じ目の高さになり、無事であることを喜び、健康を気づかい、困っていることはないか気にかける。相手が被災の体験や悲しみの感情を口にすれば、静かにうなずいて心で受け止める。亡くなった多くの犠牲者に、何度も黙とうを捧げる―。これは、グリーフケアそのものではないでしょうか」
さらに著者は、「被災した方々の悲しみの心を、両陛下はしっかり受け止めていらっしゃいます」と述べ、両陛下が被災地で語られた「よくご無事でいてくださいました」という言葉には、悲しみの心と、そこに寄り添おうとする心とが1つになるための”原点”ともいえる、相手を尊ぶ思いが込められているように感じるといいます。たしかに、「よくご無事でいてくださいました」という一言には、最高の思いやりが込められていますね。
最後になりますが、著者は美空ひばりの名曲「愛燦燦」を遺族の人々と一緒に歌うことがあるとか。小椋佳氏が書いた歌詞の中には、次のような言葉があります。
「それでも過去達は 優しく睫毛に憩う」
「それでも未来達は 人待ち顔して微笑む」
著者は、これらの言葉の中にグリーフケアの核心があると感じているのでしょう。著者は、次のような言葉で本書を締め括っています。
「難しいことではありません。人間は支えあいながら生きていくものです。誰のまわりにも、支えてくれる人はかならず存在します。ほんとうに孤独な人なんかいないのです。孤独を感じてしまうのは、自分の心が殻に閉じこもり、まわりが見えなくなっているだけなのです。自分が心を開き、最初は手探りでもいいから、前に向かって歩いてみる。そうすれば、大切なものを失った悲しみの日々は、大切なものを見つけるための新しい明日につながります。その朝を迎えたとき、悲しみは希望に変わるのです―」
本書は、著者の実体験に裏づけされた非常に実践的なグリーフケアの入門書だと思います。著者には、他にも多くの心のケアに関する著者があるようです。
これからも、ぜひ学ばせていただきたいと思います。
阪神・淡路大震災が日本に「ボランティア」の時代を呼び込んだように、東日本大震災が「グリーフケア」を日本に根付かせることを心から願っています。
