- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.0635 グリーフケア 『心のケア』 加藤寛+最相葉月著(講談社現代新書)
2012.07.15
わたしのブログ記事「『こころの再生』シンポジウム」に書いたように、11日は京都で「東日本大震災とグリーフケアについて」の報告を行ってきました。
そのシンポジウムの内容とも関連の深い本を読みました。『心のケア』加藤寛+最相葉月著(講談社現代新書)という本です。
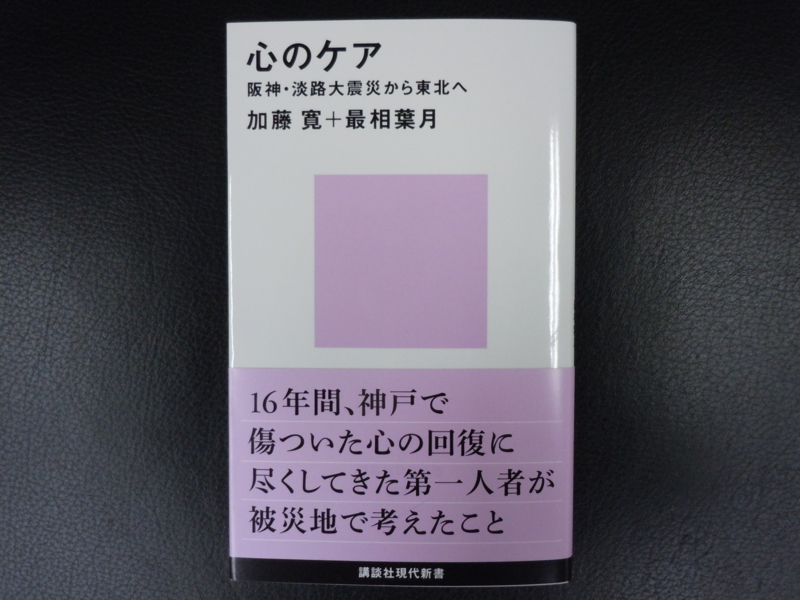
本書の2人の著者のうち加藤氏は、阪神・淡路大震災以降、被災者のケアや調査研究に従事し、事件や事故、災害の犠牲になった人々のトラウマ治療やその支援者への研究に携わってきた精神科医です。
もう1人の最相氏はノンフィクションライターで、著書に小学館ノンフィクション大賞を受賞した『絶対音感』、『青いバラ』、大佛次郎賞および講談社ノンフィクション賞を受賞した『星新一―1001話をつくった人』(いずれも新潮文庫)などがあります。
本書には「阪神・淡路大震災から東北へ」というサブタイトルがつけられ、帯には「16年間、傷ついた心の回復に尽くしてきた第一人者が被災地で考えたこと」とあります。
「心のケア」とは何か。そこで大切なことは何か。本書では、それらのことを精神科医の加藤氏が、ノンフィクションライターの最相氏の質問に答えるというインタビュー形式で作られています。
本書の「目次」は、以下のような構成になっています。
はじめに「本書の成り立ちについて」(最相葉月)
第1章:東日本大震災後五十日の記録
第2章:被災者の心の傷
第3章:阪神・淡路大震災でできたこと、できなかったこと
―復興期の心のケア
第4章:回復への道のり
―肉親を失った二人の経験から
第5章:支援者へのメッセージ
「おわりに」(加藤寛)
「参考文献リスト」(加藤寛)
巻末ルポ「1・17から3・11へ―兵庫県心のケアチームの百十一日」(最相葉月)
はじめに「本書の成り立ちについて」で、最相氏は「心のケアってなんだろう。そんな疑問を持つ方は多いと思います。新聞やテレビでよく見聞きする言葉だけれど、誰がどんなことをやっているのか、今ひとつよくわかりません。震災直後、精神科医や看護師による心のケアチームが全国から被災地に派遣されたと報じられました。臨床心理士の団体がいち早く、心のケアの電話相談を始めたという発表もありました。テレビでは、大学生のボランティア・グループが、子どもたちの心のケアのために一緒に運動して遊ぶ様子が映し出されていました。心のケアといっても、専門家による医療行為から一般のボランティア活動まで、ずいぶん多岐にわたるようです」と述べています。
そして、最相氏は次のように、本書を刊行する意図を説明します。
「東北の被災地では、津波の夢を繰り返し見て眠れないという方がおられます。
重いストレスに苦しむ方や仮設住宅で引きこもりがちな方もいらっしゃるようです。
地域社会が少しずつ平常を取り戻そうと動き始めるとき、そこについていけない人の心は、ともすれば深い傷を抱えてしまいます。そんなとき、そばにいる人はどうすればいいのでしょうか。災害や事件・事故が起こるたびに耳にするようになった『心のケア』の活動の実態を知っていただき、ひとりでも多くの方々の今後の支援に役立てていただければと願っています」
加藤氏には『消防士を救え!~災害救援者のための惨事ストレス対策講座』(東京法令出版)という著書がありますが、これまで消防士や看護師、行政職員など支援者の抱えるストレスについても取り組んできました。自身も被災者でありながら被災者の世話をしなければならない行政職員の抱えるストレスについて最相氏に質問された加藤氏は次のように答えます。
「外部支援者と違って、地元の人たちは、一時的にそこにいるわけじゃないですからね。南三陸町では町の職員の方30人が庁舎の屋上に逃げたのですが、そのうち20人の方が流されてしまったそうです。目の前で自分の同僚が流されていったから、生き残った人たちはものすごい罪悪感を抱えている。想像もできないぐらいの罪悪感だと思います。しかも、自分自身も家族を失い、知人友人もたくさん亡くなっている。そんな状況で役場の仕事をしなきゃいけないわけじゃないですか。よくあることですが、被災された方というのは怒りの矛先がないのでお役所に対してきついことをいうんです。どうにかしてくれと。職員はそれを一身に引き受けなきゃいけない。遺体の処置もやらなければいけないし、外部から来る人の調整もしなければならない。そういう状況が長く続くわけです」
本書では「危惧される心の問題」として、喪の作業が行えないことが取り上げられています。最相氏が見たある報道番組では、気仙沼の遺体安置所に僧侶が来てお経をあげたところ、遺族にとても感謝されるシーンが放送されたそうです。また、「遺体が見つかってよかった」と言う人もいました。一方、家族などの遺体が見つからないことで喪の作業へと進めない人々の苦しみははかり知れません。
「愛する人を失うだけでも悲しみは深いのに、ご遺体が見つからないことは今後どのような影響を与えるのでしょうか」という最相氏の質問に対して、加藤氏は答えます。
「死を受けとめられないという方は少なくないでしょう。喪の作業ができないと、いつまでも亡くなったことを受け入れられなくてあたりまえだと思います。人間は死別したらちゃんと悲しんでこそ次の段階に進めるものだし、そうでなければ、悲嘆のプロセスが進みません。最初の大きな悲嘆のままずーっと苦しみ続ける方が出てくる可能性はあります」
「喪の作業」をきちんと行って次の段階に進むために、葬儀というものはあります。
わたしが『葬式は必要!』(双葉新書)に書いたように、葬儀には、4つの役割があるとされています。それは、社会的な処理、遺体の処理、霊魂の処理、そして、悲しみの処理です。悲しみの処理とは、遺族に代表される生者のためのものです。残された人々の深い悲しみや愛惜の念を、どのように癒していくかという処理法のことです。通夜、告別式、その後の法要などの一連の行事が、遺族に「あきらめ」と「決別」をもたらします。
愛する人を亡くした人の心は不安定に揺れ動いています。しかし、そこに儀式というしっかりした「かたち」のあるものが押し当てられると、不安が癒されていきます。
親しい人間が死去する。その人が消えていくことによる、これからの不安。残された人は、このような不安を抱えて数日間を過ごさなければなりません。心が動揺していて矛盾を抱えているとき、この心に儀式のようなきちんとまとまった「かたち」を与えないと、人間の心にはいつまでたっても不安や執着が残るのです。この不安や執着は、残された人の精神を壊しかねない、非常に危険な力を持っています。この危険な時期を乗り越えるためには、動揺して不安を抱え込んでいる心に、ひとつの「かたち」を与えることが求められます。まさに、葬儀を行なう最大の意味はここにあります。
愛する人との死別に際して葬儀を行い、きちんと喪の作業を行わないと、遺族にはいつまでも大きな悲嘆が残ります。加藤氏は、「悲嘆」について次のように述べます。
「悲嘆は健康に大きな問題を引き起こします。とくに体の健康に大きな支障を引き起こしますので、それを支えることができなくなってきます。たとえば、食べられなくなるとお年寄りだったらすぐに健康を害してしまう。それをちゃんと発見してあげるシステムがないといけない。健康を害したときの受け入れ先がないと精神的な問題まで引き起こします。体の問題をサポートできなくなると、大げさな表現ですが、寿命を縮めてしまう。そこにはカウンセリングなどが入り込む余地はあまりありません」
まさに、グリーフケアとはカウンセリングだけでは済まないのです。そして、加藤氏はグリーフケアにおいて言ってはいけない言葉を次のように説明します。
「悲しんでいる人にいってはいけないことは何なのか。たとえば、ひとりだけですんでよかったとか、きょうだいを亡くした人にあなたがしっかり親御さんを支えてね、とかいうべきではないですし。自分の死生観や宗教観を持ち出すべきではない。そういうあたりまえの配慮ができるようなトレーニングをするときには専門家が役立つでしょう。あるいは、うつ的で精神科の治療が必要という場合には、そのリスクのある人を見出す方法を教えてあげて、見出したあとの受け皿になることはできると思う。バックアップするかたちで専門家が存在することがたぶん正解なのでしょう」
「災害に遭って心はどう変化するか」という問題もあります。最相氏は、加藤氏に対して「東北の被災地を取材していると、さまざまな悲痛な声を耳にします。毎晩のように津波で流された人たちの夢を見て苦しいとか、自分はあの人たちを見捨てて逃げてしまった、あのとき一緒に死んだほうがよかったと自分を責め、涙を流す方もいらっしゃいました」と言います。これに対する加藤氏の言葉は、次のようなものでした。
「津波は本当に残酷な災害で、一瞬にして生死が分けられたというか、怪我をして助かったという人は少なくて、死ぬか生き残るかしかなかったわけです。自分の家族や知人が目の前で流されていった場合には、生き残ってよかったという感情より、なにもできなかったという無力感と、生き残ったことの罪責感が本当に強く残ってしまうでしょうね」
また、加藤氏はこれまでに多くの被災者の心の変化に向き合い、治療者としてその重荷を受け止めてきました。それを踏まえて、最相氏は「災害に襲われたときに人がどうなるのか」という質問を加藤氏にします。加藤氏は、それについては2つの考え方があると述べます。
1つは、災害からの時間の経過とともに表れる被災社会全体の心理的変化として理解するもの。もう1つは、個人が示す心理的反応によって理解するもの。このうち、前者についての次のようなコメントを興味深く感じました。
「まず社会全体についてですが、恐怖を体験した直後は、茫然としてなにも感じない、すべての感覚が麻痺したような状態になることがあります。その後、脳が過剰に興奮して気持ちが高ぶり、人によっては過剰適応が起こることがあります。その結果、被災したコミュニティ全体が、妙に昂揚した気分に支配されたようになる。避難所はとてもなごやかだし、変ないい方になりますが、活気にあふれ、リーダーみたいな人が自然に役割を引き受けて統制していく。一致団結してこの苦難を乗り越えよう、という雰囲気になります。これが、災害のもたらす精神面の後遺症について考察したビヴァリー・ラファエルの『災害の襲うとき――カタストロフィの精神医学』に描かれている「災害ハネムーン」とよばれる現象です。今回の災害後に、日本人が示した礼節や秩序に世界中から賞賛の声が寄せられましたね。これは日本人が持つ道徳観や規範意識が影響した側面は大きいですが、災害ハネムーンの典型的な状態ともいえると思います」
また、個人が示す心理的反応は、主に3つあります。
1つめは、災害がもたらす恐怖体験によって生じる変化。2つめは、家族や友人を亡くしたときの変化。そして3つめは、二次的な生活変化。この中で、当然ながらわたしは2つめの「家族や友人を亡くしたときの変化」に関心があります。加藤氏は、これについて次のように述べています。
「重要なのは、悲嘆(グリーフ)といわれる反応です。災害は多くの死別を引き起こします。死別が引き起こすあたりまえの感情は、悲しみです。病死などの場合は、死に至るまでに怒りや抑うつの時期を通過して、ある程度受容する準備ができることが多いのですが、災害や犯罪のように、突然、残酷なかたちで死に直面すると、当初はなんの感情も生じない状態になってしまうことがあるんです。悲しいはずなのに、なんとも感じない。そばで見ていると穏やかに死を受け入れているように見える。
いわば感情が麻痺したようになってしまうのです。
日本以外の東アジアの国には、死に接したときに激しく泣き叫び、感情をあらん限りに表出するという習慣がありますが、日本の場合は、死に堪え忍ぶのが美徳とされるようなところがありますので、ますます感情を抑え込んでしまうことにつながるでしょう」
死別による悲嘆の中でも、最たる悲しみは幼い我が子を亡くすことではないでしょうか。この悲しみは、後々まで人生に影響を及ぼします。震災をきっかけとして仲が良くなる夫婦もいましたが、中には別れる夫婦も少なくありません。考えさせられたのは、阪神・淡路大震災のとき、子どもを失った夫婦はかなり高い割合で離婚したという調査データが存在することです。この問題について、加藤氏は次のように述べています。
「子どもを失うということはみなさん共通に悲しいことではあるのですが、その後の生活パターンが、男と女ではずいぶんと違うわけです。
とくに専業主婦の方ですと、ずっと家にいて子どもを思い出させるものに接し続けなければなりませんので、どうしても悲嘆が強いんですね。
でも男の場合は、仕事に行った先でちょっと脇に置いておける。うまく置いておけるようになることも回復を後押ししてくれるんです。それが自然に身についていくと、夫婦の間でだんだんと気持ちの差が広がっていって、わかりあえない時が来てしまうのです」
「災害弱者とはだれか」というテーマにも考えさせられました。防災白書によれば、災害時に身の危険を察知しても自分自身で行動できない、危険であること自体がわからない、適切な情報が得られないなどの条件に1つでもあてはまる人を「災害弱者」と呼ぶそうです。
最相氏は、「具体的には、高齢者や子ども、妊婦、さまざまな障害のある方、日本語がわからない外国人も含まれるのでしょうか。こうした方々は、やはりストレスに対する抵抗力に留意しておく必要があるのですか」と質問します。
それに対して、加藤氏は「高齢者というのは、必ずしも災害弱者ではないところがあるんです。長く生きてこられたので、たとえば過去に戦争や他の災害を経験されている場合があります。それが脆弱さの反対、強靭さとして残り、ストレスにもうまく対処できる能力を持ってる人たちがおられるのです。阪神のときも、戦争に比べたらこんなの屁みたいなもんです、とおっしゃる高齢者はたくさんいました。人生の中でいろんな死別の経験をしてきたし、つらいことも経験してきたということが糧となって、回復していく人たちは当然いらっしゃるんですね」と答えました。
それでは、同じく災害弱者とされる子どもはどうか。加藤氏は述べます。
「子どもは、意外としなやかさを持っています。お年寄りの場合は強靭さなんですが、子どもはしなやかさなんです。若竹のような。高齢者に老化があるように子どもたちには成長がある。その過程で対処能力が上がっていくので、多くの子どもたちが回復していきます。苦しい状況で自分の役割を見つけて、たとえば水汲みなんかをすると子どもって強くなっていきますよ」
「強靱な高齢者」と「しなやかな子ども」・・・・・こうして見ると、一概に彼らを「弱者」と呼ぶことはできないかもしれませんね。
「悲しみを癒すということ」では、「悲嘆のケア=グリーフケアとは何なのか。望ましいケアのかたちがあるとすれば、それはどういうものなのか」という最相氏の質問に対する加藤氏の次の言葉が心に残りました。
「グリーフの感情は消えるものではありません。トラウマの記憶も消えないけれど、それでもなんとか受けとめて対処していけます。でも、悲嘆は受けとめることさえむずかしい。5年経っても10年経っても、17回忌が過ぎて法事が終わるような時期になっても、思い出すと悲しみが伴います。80代以上の方が太平洋戦争のときの悲嘆を涙を伴いながら話されることがありますね。それほど痛切な感情なのです。
ですから、グリーフから回復していくとはどういうことかというと、思い出すと悲しいのだけれどちょっと脇に置いておけるようになるプロセスと考えられています。ずーっとひたりきり、抱えきりではなく、自分の現実的な生活も、ほかの家族のことや仕事のことも考えていける。少しずつ再建していくプロセスに目が向くということです。そこを行ったり来たりしながら回復は進んでいくといわれています」
加藤氏によれば、そこで役に立つ可能性があるのは、遺族の自助グループができて、そこで情緒的なつながりを得られることだそうです。自分の存在意義や役割を意識できることは、何よりも回復に役立つのかもしれません。
加藤氏も言うように、確かに悲嘆は消えません。でも、悲嘆以外の感情、たとえばグループのつながりからくる温かさや、自分が役に立っているという満足感が持てるようになれば、悲嘆からの回復につながるというのです。
ちなみに、わが社では「月あかりの会」という自助グループの活動のお手伝いをさせていただいています。
最相氏は、この自助グループに関心を抱いたようです。「自助グループのように、同じような体験をした方とともにいて、つらい体験や亡くした方の思い出を語り合うことは、その方同士の救いになるということですね」と言っています。この最相氏の言葉を受けて、加藤氏は次のように語ります。
「ぼくは犯罪被害者の遺族会にも行きますが、たとえば、子どもさんを亡くした方は、それが人間の経験しうる最大の悲しみだと思っておられます。親やきょうだいを亡くすことに比べると、自分たちは子どもを亡くしたのだから、この気持ちは誰にもわからないとおっしゃいますので、そのために葛藤を生むことはあります。
一方で、きょうだいを亡くした人は、周囲から、あなたがしっかりして家を支えてねとか、お姉ちゃんの代わりに両親を支えてあげてね、といわれるのがとてもつらいという。同じ遺族でも感情に違いがあるので、一律にそれを扱うのは無理がありますね。それでも遺族同士だとルーツに共通した感情があるので、まったく経験したことのない人に比べるとよほど安全です」
本書では、「心のケア」に従事する人々が「どんな態度で接するか」についても触れています。「害を与えない、傷つけない、ということですが、たとえばどんな言葉だと相手を傷つけてしまうのか」という最相氏の質問に対して、加藤氏は次のように答えます。
「専門職向けの早期介入マニュアル『サイコロジカル・ファーストエイド』にうまく整理されているのですが、たとえば遺族に対して、『お気持ちはわかります』といってはいけないと書かれています。この人はこんなつらさを持っているんじゃないかとわかったつもりになって、わかりもしないのにわかったように振舞うのは、やっぱりよくないことだと思いますね。自分が追体験できるわけではないし、100パーセント共感できるわけでもないということを意識することが大事で、それが傷つけないということだと思っています」
また、消防士などの災害救助の最前線で働くプロの救助者の抱えるストレスは一般人の想像をはるかに超える過酷なもので、その危険もきわめて大きいと言えます。当然ながら、プロ救助者の職場では殉職者が生まれる可能性を常に孕んでいます。「殉職者が出た職場では、気持ちを立て直せない方もいらっしゃるのではないでしょうか」という最相氏の質問に対しては、加藤氏は次のように答えています。
「ええ。ですから、殉職があった場合にはちゃんと弔いをしなければいけないのです。通常の活動で殉職が起きたらどうするかお聞きしてみると、消防組織としての葬式をするのだそうです。消防葬というのですが、みんな礼服を着て、敬礼して柩を送る。神戸の消防署では大きな会館を借りて行われていましたが、そういった儀式が消防人にとっては1つの区切りになるわけです。遺族に対してというより、生き残った人たちに対しても、ちゃんと礼を尽くして仲間を見送ったという区切りになります。それから自分たちがもしそういうことになった場合に、組織はこれだけやってくれるということがわかって、組織に対する忠誠心もそこでまた取り戻せるんです」
最後に「おわりに」で、加藤氏は「心のケア」という言葉について述べています。
「『心』という日本語には脳を首座とする精神活動という意味以上の、神秘的で情緒に訴える響きがあります。また、『ケア care』という語はゲルマン語由来の言葉で、もともとは『厄介 trouble』『悲嘆 grief』『世話 take care』という意味を持っており、酷い体験をして心を痛めた人に対して、配慮をしながら世話をすることを指すのだそうです。心のケアという言葉を使い始めた人が、こうした語源を知っていたのかどうかは不明ですが、被災者や被害者の心理的支援を指す言葉としては、最適だったといえるでしょう」
わたしは「ケア」こそはこれからの時代のキーワードであると考えていますので、加藤氏のこの言葉にはとても共感できました。そして、本書の巻末ルポ「1・17から3・11へ――兵庫県心のケアチームの百十一日」において、最相氏は「心のケア」について次のように述べています。
「心のケアとはなにか。阪神を機によく使われるようになったこの言葉について、多くのメディアで情報が錯綜しているが、精神科医や心理士で構成される心のケアチームが災害直後に行うのは、被災者に被災体験を聞いてカウンセリングすることではない。
第1には、機能を失った病院から入院患者を転院させることと、通院できなくなった患者の薬を確保すること。つまり精神科医療の補完業務である。その後、時間の経過とともにニーズは変化し、避難所生活で潜在化していた問題、たとえば不眠や不安、アルコール依存のほか、一部の精神疾患や発達障害が顕在化すれば臨機応変に対処していくことになる。ただし避難者が罹災証明書の申請や仮設住宅の申し込みで多忙な時期は、生活支援が優先されるため、精神科医や心理士の出番は少ない」
わたしは、「心のケア」という言葉について批判的な人々がいることを知っています。その理由はいろいろあるのでしょうが、一番の原因は「心のケア」に「上から目線」的なニュアンスを感じるといったところでしょう。
長年、被災地で被災者の傷ついた心の回復に取り組んできた加藤氏は、現場で役に立うということに対してあくまでも誠実であり、謙虚です。
「おわりに」にも、「繰り返し痛感したのは、心のケアはあまり歓迎されないということです。・・・・・受け入れてもらうためには、心のケアを強調しすぎないこと、現実的な支援をしながら地道な関係作りをすること、そして何よりも害を与えないこと、これらの基本的な態度が重要でした」と述べています。でも、その上で「心のケア」が必要であること、なぜ必要であるかも加藤氏きちんと本書で述べています。
たしかに、現実は厳しいでしょう。理想や理論だけでは通用しないでしょう。でも、そこに傷ついた心を持つ人がいるならば、やはり「心のケア」の出番なのです。
カウンセラーを目指す人はもちろん、メディアなどで簡単に「心のケア」を口にする評論家にも、ぜひ読んで欲しい一冊です。最後に、わたし自身もグリーフケア・サポートを通して、「心のケア」の世界の住人の1人を目指したいと思います。