- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.0672 書評・ブックガイド 『柔らかな犀の角』 山崎努著(文藝春秋)
2012.08.31
『柔らかな犀の角』山崎努著(文藝春秋)を読みました。
日本映画界を代表する名優として知られる山崎努さんの読書日記です。「週刊文春」に好評連載された「私の読書日記」6年分が収録されています。
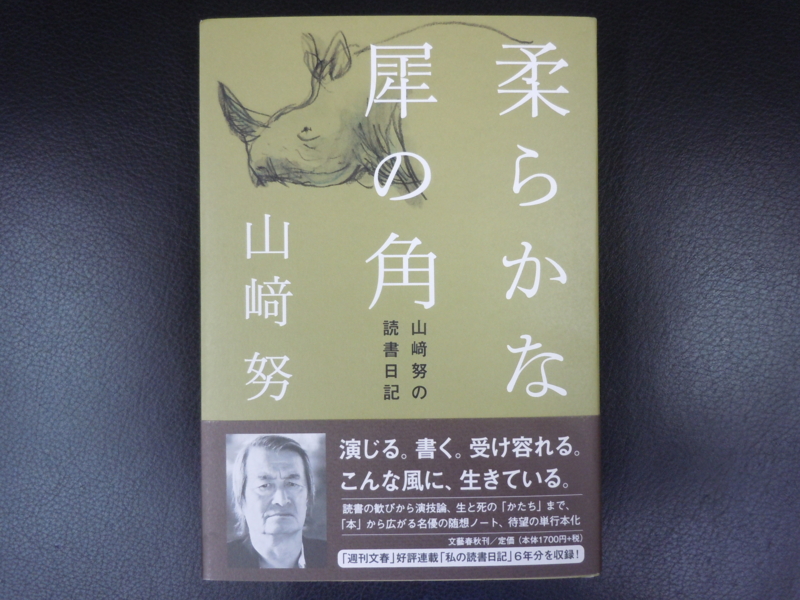
山崎努の読書日記
表紙には犀の部分イラストが描かれ、帯には「演じる。書く。受け入れる。こんな風に、生きている。」というコピーに続いて、「読書の歓びから演技論、生と死の『かたち』まで、『本』から広がる名優の随想ノート、待望の単行本化」と書かれています。
本書の存在を知ったのは、たまたま観たテレビで「山P(ヤマピー)」こと山下智久クンが愛読書として紹介していたからでした。著者と共演した山Pは、以来、著者が持つ教養と人間性に心酔しているそうです。それを知ったわたしは、ちょうど故・児玉清さんの著書『すべては今日から』を読書中だったこともあり、同じように俳優によるブックガイドである本書を読んでみたいと思いました。
もともと、著者はわたしのお気に入りの俳優の1人でした。
冠婚葬祭業界に身を置く者なら、著者の姿をスクリーンで見ていない人は少ないでしょう。なにしろ、「お葬式」(1984年)、「おくりびと」(2008年)という二大葬儀映画に重要な役で出演しているのですから。特に、「おくりびと」での納棺会社の社長役は素晴らしく、社長室でフグの白子を焼いて食べるシーンは最高の名場面でした。
でも、わたしにとっての著者は、わたしが誕生した年に公開された黒澤明監督の名作「天国と地獄」(1963年)での犯人の青年役や、泉鏡花の幻想世界を見事に再現した「夜叉ヶ池」(1979年)の主人公の旅の僧侶役のイメージが強いです。本当に、「この人がいなくなったら、日本映画はどうなるのか」と思わせる名優だと言えるでしょう。
タイトルの『柔らかな犀の角』ですが、これは「犀の角のようにただ独り歩め」というブッダの言葉に由来します。ブッダの思想を知る上で最重要テキストとして『スッタニパータ』という聖典があります。そこには、「犀の角のようにただ独り歩め」というフレーズがたくさん出てきます。著者は、このフレーズを若い頃から気に入っていたそうで、次のように書いています。
「何をするにも自信がなく、毎日が手探り及び腰、そのくせ鼻っ柱だけは強く、事あるごとにすぐ開き直る。そんな臆病な若造にとって『犀の角』や『ただ独り』は手軽で便利なキャッチコピーだったのだろう」
しかし、著者が「最後の賢人」として慕い、本書にも登場する哲学者・鶴見俊輔氏の著書『かくれ佛教』(ダイヤモンド社)を読んで、著者は以下の事実を知ります。
「ブッダの言う角はむろんインドサイのものだが、実はこの角、中はぶよぶよの肉で、とうてい闘争の武器にはならないヤワな代物なのだそうだ。
だから彼らはあまり戦わない。獰猛なのはアフリカの犀で、インドの連中はただ温和しく地味に密林を歩き回っているだけらしい。群れることもなく孤独にのこのこ山奥をうろついている。図体がでかいからむやみに攻撃される心配もないという」
『かくれ佛教』を読んでこの事実を知った著者は、次のように述べます。
「つまりあの勇ましい立派な角は、少なくとも喧嘩に関しては無用の長物。相手を威嚇するための張りぼてのようなものとか、まあ学問的にはそれなりの理由があるのかもしれないが、無用の長物としたほうが僕は愉しい」
ブッダといえば、「生老病死」の四苦を唱え、「老い」を苦悩として説きましたが、今年で75歳になる著者は、「老い」をけっして悲観的には捉えていません。
たとえば、養老孟司氏の著書について、次のように書いています。
「養老孟司が『養老訓』(新潮社)で、『年をとって良かったなと思うことがたくさんあります』と言っている。年寄りは上機嫌で生きましょう、『じいさんは笑っていればいいのです。先日亡くなられた河合隼雄さんは、いつもニコニコされて駄洒落ばかり言っていました。人の意見を訂正するなんてこともなかった』という。たしかに河合隼雄は、テレビでも活字の対談でも、他人の話をノーで受けることがなかった。いつも、まず『そうですね』『なるほど』とイエスで受けとめ、その上で穏やかに、相手の言葉に寄り添うように話し出す。あれは真似ができない。どうしても、思わず、『いや』『でも』と返してしまう。大人と小人、器が違うのだからしかたがないか。とりあえず僕は、話したあとに、ニコッと笑顔をつけ加えるようつとめている。それが気持悪いと言われたりするが」
「生老病死」の「死」についても、次のように書いています。
「映画『おくりびと』がなんとオスカーをとった。こいつぁ春から縁起がいい、何故か初雪まで降ってきた。お祝いの品もたくさん頂いた。その中に、『RFK』(Paul Fusco,Aperture Foundation)があった。あのロバート・ケネディの遺体を運ぶ葬送列車を線路端で見送る普通の人たち、その様を列車内からスナップした写真集。
100点に余るショットに写し出された何千何万の人々が全員打ちひしがれている。老若男女、皆、哀しみに打ちひしがれている。虚ろな目で1人ぽつんと立っている。『SO LONG BOBBY』と手書きした幕を掲げている3人。泣いている。唇を噛みしめ目をとがらせている。家族7人が背の順に整列し(きちんと等間隔に)気をつけをしている、父も母もずいぶん若い、端っこのちびは2、3歳、そいつも背すじを伸ばし葬送列車を凝視している・・・・・・。ゆっくりとページを繰った。死者を送る人間たちが美しい」
「死者を送る人間たちが美しい」とは名言ですね。まさに「おくりびと」の言葉。わたしが思うに、「死者を送る人間たちが美しい」のは、それが人間の存在の本質に関わる営みであるからではないでしょうか。
また、「バク転神道ソングライター」こと鎌田東二氏の著書も紹介されています。
「そこにいるだけで、何となく緊張が解け、リラックスできる所がある。旅に出ると、あちこちぶらぶら歩き回って、そういう場所を探す。ここだ、と手応えがあったら、その地点に居坐り、うつらうつらしたりしてのんびりと過ごす(以前、南の島でそれをやり、日射病で死にかけたことがあるが)。そんなスポットを僕はいくつか持っている。鎌田東二著『聖地感覚』(角川学芸出版)に依れば、そのような場は、その人の『聖地』なのだそうだ」
「聖地」をめぐって、著者は次のように述べます。
「人はなぜ聖地を求め、巡礼をするのか? そこに決まった答えはない。人生がそうであるように『巡礼』も各人各様の理由とかたちをもっている。これからもくりかえし実践され、つづいていくに違いないと鎌田は言う。そう、アキバも冬ソナも軽々に扱ってはいけない。鰯の頭も信心から、その人にとってそれがかけがえのない信仰の対象であるならば(よほど悪質なものでない限り)認めてやらなければいけない。そもそもわれわれの『信仰』は、立場を異にする者から見ればすべて鰯の頭なのである」
さらに、著者は次のように書いています。
「古くから聖地、霊場として崇められている土地には、人間の聖なる感覚を刺戟し増幅させる自然の霊気が強くあるのだろう。三輪山、熊野、出羽三山等々を巡り歩いた鎌田のフィールドワークの記録が興味深い。湯殿山での滝行の描写など、臨場感があって紀行文としても優れている」
著者は、鎌田氏にいたく興味を抱いているようで、次のように書いています。
「著者鎌田東二は、宗教哲学、民俗学、日本思想史と、幅広い分野で研究を続けている学者である。この本の最大の魅力は、彼の底抜けに奔放なキャラクターが存分に発揮されているところだ。巻末の略歴紹介の欄に、石笛、横笛、法螺貝奏者、フリーランス神主、神道ソングライターとあって、笑ってしまった。
おもむくままにやりたいことをやっている。
毎朝、祝詞、般若心経を上げ、笛、太鼓、鈴、その他計十数種類の楽器を奉納演奏するので『時間がかかり、忙しいのだ』とぼやいている。お子さんに『お父さんはアヤシすぎる』と言われるそうだ。カバー折り返しに、著者近影の全身写真が載っている。カメラを意識してやや硬くなっているポーズがチャーミング。しばし見惚れた。『スピリチュアル・パワー』がメディアで安易にもてはやされている当節、鎌田の仕事は貴重である。彼のユーモアを大切にする柔らかなセンスに注目したい」
わたしは、この文章を読んで本当に嬉しくて仕方がありませんでした。わが義兄弟のことを日本を代表する名優がこれほど高く評価してくれたのですから。
また、著者の鎌田氏に対する分析はまことに的を得ており、著者の人間を観る目には只ならぬものがあります。ちなみに、この文章が「週刊文春」に掲載されたとき、鎌田氏は大変喜ばれ、わざわざメールで知らせて下さいました。
そして、本書の白眉は、何と言っても映画に関する発言でしょう。俳優である著者は、こころから映画を愛しており、こんな言葉も綴っています。
「映像の仕事は何といってもロケが楽しい。その土地の情景に囲まれただけでふしぎと役の人物に成れたような気分が生まれ、弾みがつく。風も陽の光も地べたも快い刺戟を与えてくれる。自分を(幾分かは)役に明け渡す、その感じがこたえられない」
次の文章などは、きわめて映画作りというものの本質を衝いているように思います。
「撮影の現場で一番偉いのは監督である。ただ1人、神様の如く偉い。名うての脚本家も優れたカメラマン、俳優も監督にはかなわない。だから業界では各々のチームを『黒澤組』『小津組』と監督の名前を冠にして呼ぶ。『七人の侍組』でも『東京物語組』でもない。われら配下の者はひたすら組の親分に奉仕する。想像力、創造力等々、命以外は全てを監督に捧げる。俳優が自身でいくらいい演技をしたと思ってもそんなことは何程でもない。親分のメガネに適わなければ切り捨てられてしまう。われわれは僕なのだ。一時、スター俳優が大金を投じてプロデュースするのが流行った時期があった。武田泰淳はそれを奴隷の反抗と評している。三島由紀夫の俳優願望は当時悪ふざけの過ぎた奇行と騒がれたが、実は大まじめな奴隷志願だったのである。その三島の意図を泰淳は即座に言い当てている」
「週刊文春」2010年4月1日号に掲載された「小津と笠、黒澤、グルメ」では、著者の知り合いの女性がDVDを持って訪ねてきた話が書かれています。
その30代の女性は小津映画にはまっており、「父ありき」「晩春」「麦秋」「東京物語」などのDVDを持参したとか。彼女は、小津映画で笠智衆、原節子、杉村春子らの登場人物のレトロな言葉遣いが外国語みたいで新鮮で「ひきつけられる」のだそうです。
彼女と一緒に小津映画のDVDを鑑賞した著者は、次のように書いています。
「むろん僕も『晩春』以降の小津作品はぜんぶ見ているが、彼女のように何度も見返すほどの熱心な観客ではなかった。しかし今回は目から鱗、今までぼんやりと見えていたものが突然ピントが合ってくっきりと現れてきた感じ。『!』と前傾姿勢になった。おれはこれまで何をどこを見てたんだ。うかつ、鈍感、脳たりんであった」
何が著者をそこまで思わせたのか? 著者は次のように書いています。
「これは異界から見た現世の風景だ。いや、末期の眼で見た世界だ。
ここに登場する人たちは、お互いさり気なく助け合って生きている。
親子、兄弟、友人、師弟、それぞれが支え合って暮らしている。
そしてそういう人々もやがて時が来て死んでゆく。
そんな人間たちをカメラがいとおしそうに見つめている。小津は楽園を描いているのだ。浮き世に散在する楽園の破片を大切に注意深くピックアップしているのだ。そこにはただただ懐かしく美しい出来事があるばかり。それ以外の醜いものは一切見ない。断固無視する。その無視にめっぽう力がある。被写体との距離のとり方も絶妙。だからいわゆる人情劇特有の湿っぽさがない。代りに若い女が笑い転げるユーモアがある」
うーん、小津映画の本質が「末期の眼で見た世界」だったとは驚きです! 小津映画のほぼ全作品を観たわたしも、まったく気付きませんでした。
著者は、小津安二郎について次のように述べています。
「小津安二郎は生涯独身だった。『秋刀魚の味』に『人間は独りぼっちだ』というせりふがある。笠は、『ひとつだけ、先生について口はばったいことを言わせていただきます。/ご結婚なさったほうが良かったんじゃないでしょうか。なんとなく、そう思います』と書いて思い出話を閉じている。2人の深い係わりからの言葉でドラマチック」
また、小津安二郎と並ぶ日本映画最高の巨匠である黒澤明については、「黒澤さんはよく『昔のシャシンを見ると撮り直したくなる』と笑っていた。『その時一生懸命作ったんだからあれでいい』とも言ってたな」と、著者はさらりと触れています。実際に「天国と地獄」という黒澤映画で世に認められ、その後、日本を代表する名優になった著者の言葉だけに重みがありますね。
著者は、万人が認める最高の「演技力」の持ち主です。その本人が、「演技」について次のように書いています。
「ときどき『あの映画のあの演技にはどんな狙いがあったのか?』と聞かれることがある。これがほとんど覚えていない。比較的うまくいった演技ほど覚えていない。撮影現場の情況は絶えず動いている。相手役や監督の調子、天候、暖かかったり寒かったり風が吹いたり。その変化する環境に身を任せるよう自分を仕向けるのが僕のモットー。その場に反応して思いがけないアクションが生まれると楽しいし出来もいい(ような気がする)。頭より身体、結果は身体に聞いてくれ、が理想、記憶にないのが僕としてはベストなのだ。それが僕の『自由』、多少脱線したっていいじゃないか。あらかじめのプランは所詮ひ弱なのである。プランにこだわると身体が萎えてしまう」
本書は、ユニークなブックガイドとして、極上の映画論として、また魅力溢れる1人の名優の人生論として、さまざまな読み方ができる好著だと思います。最後に、著者がいつまでもお元気で、1本でも多くの日本映画に出演されることを願っています。