- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2012.08.09
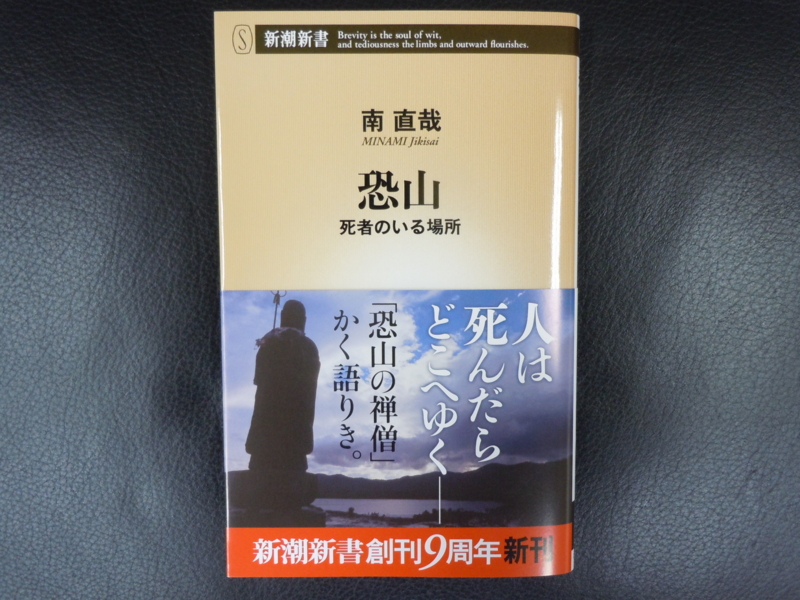
『恐山』南直哉著(新潮新書)を読みました。
「死者のいる場所」というサブタイトルがつけられ、帯には「人は死んだらどこへゆく―『恐山の禅僧』かく語りき。」と書かれています。また、表紙カバーの折り返しには、次のような内容紹介があります。
「死者は実在する。懐かしいあの人、別れも言えず旅立った友、かけがえのない父や母―。たとえ肉体は滅んでも、彼らはそこにいる。日本一有名な霊場は、生者が死者を想うという、人類普遍の感情によって支えられてきた。イタコの前で身も世もなく泣き崩れる母、息子の死の理由を問い続ける父・・・・・。
恐山は、死者への想いを預かり、魂のゆくえを決める場所なのだ。
無常を生きる人々へ、『恐山の禅僧』が弔いの意義を問う」
本書の「目次」は、以下のような構成になっています。
「まえがき」
第一章:恐山夜話
第二章:永平寺から恐山へ
第三章:死者への想いを預かる場所
第四章:弔いの意味
「無常を生きる人々~あとがきに代えて」
1958年(昭和33年)生まれの著者は、恐山の菩提寺住職代理(院代)です。かの永平寺で20年間も修行していたそうです。同じ曹洞宗でも永平寺と恐山のカラーはまったく違いますので、著書が初めて受けた衝撃の大きさが本書から伝わってきます。
最初に著者は、「古くから日本人に知られる霊場でございますから、そこがどんなにおどろおどろしい場所であるか、それを知りたいと思っている方もたくさんおられることでしょう。『日本三大霊場』『日本三大霊地』『日本三大霊山』、そのいずれにもランク・インしているのは恐山だけであります」と述べています。
ちなみに、それらの「三大霊~」の内容は以下の通りです。
「日本三大霊場」(恐山:青森・白山:石川・立山:富山)
「日本三大霊地」(恐山:青森・立山:富山・川原毛:秋田)
「日本三大霊山」(恐山:青森・高野山:和歌山・比叡山:滋賀)
このように恐ろしい場所の代名詞にもなっている恐山ですが、わたしが初めてその名を知ったのは小学4年生のときでした。その頃、「少年マガジン」に「うしろの百太郎」の連載がスタートしました。つのだじろうによる心霊マンガでしたが、その第1回目に恐山で撮影された心霊写真が紹介されていたのです。わたしは、「心霊写真」などというものも初めて知りました。それ以来、中岡俊哉の「恐怖の心霊写真集」シリーズにハマリました。わたしは、「うしろの百太郎」によって、心霊の世界について啓蒙(?)されたのです。
「うしろの百太郎」の心霊写真には、たしかイタコのような老婆が写っていました。「イタコ」といえば、「恐山」の代名詞のようになっています。「イタコ」とは、いったい何なのか。本書『恐山』には、次のように書かれています。
「はたして、イタコとは何者なのか。もとは青森を中心とする北東北地方で霊媒をする女性のことを指すようです。まあ、霊媒師というか巫女さんのことです。
『口寄せ』と呼ばれる降霊術を行い、死者の魂を呼ぶと言われています。しかしこれは起源がはっきりしていません。目の不自由な女性の生業として始まったのだろうと言われていますが、はっきりとした起源はない。古くからこの地域の民間信仰にもとづいたものだとは思うのですが、それについては一般に大きな誤解があります。それは、『恐山のイタコ』というものは、元来存在しない、ということです。つまり、恐山がイタコを管理しているわけでも、イタコが恐山に所属しているわけでもないのです。両者の間に一切の契約関係はございません。そのことをまず申し上げなくてはいけない」
つまり、イタコというものは個人事業主なわけですね。
どうしても恐山というと、イタコに興味が向けられます。著者も、7年以上も恐山にいればイタコが死者の霊を「口寄せ」した事実はあったのだろうというケースを耳にすることも当然ありました。しかし、その前に著者は、次のように死後の世界や霊魂の行方に関する仏教の公式見解を述べるのでした。
「『はたして死後の世界は霊魂があるのか、ないのか』と問われたときに、『答えない』というのが、ブッダの時代からの公式見解です。それを仏教では『無記』と呼びます。
ある男が、この世の成り立ちや死後の世界の有無についてブッダに解答を迫るが、ブッダは一貫してそのような質問には答えなかった、という故事があります。
ブッダのそのような態度が『無記』と呼ばれるものなのです。
なぜ答えないのか。それは『ある』と答えても、『ない』と答えても、いずれにせよ論理的な矛盾が生じて、世界の体系が閉じてしまうからです」
著者はまた、「必ずしも簡単とは言えない人生を、最後まで勇気を持って生き切るにはどうするか。それこそが仏教の一番大事なテーマであって、死んだ後のことは、死ねばわかるだろう、ぐらいに考えればいい」というのが仏教の公式見解であると述べます。
では、「恐山の禅僧」である著者は、いわゆる幽霊を見たことはないのか。著者は、「見た」ことは一度もないと断った上で、次のように述べます。
「ただ、私が見ていないからといって、『ない』とは言い切れません。私はこの世に常識や科学で説明できない不思議な現象が多く存在することを否定しません。先ほど述べたように、『ある』とも『ない』とも断言できません。もしかしたらその不思議な現象を、『心霊』モデルで説明した方が、納得しやすい場合もあるでしょう。しかしお坊さんとしては、『心霊』の実在の有無ではなく、それが人間の生き方にどう関わるのか、それこそが問題だと思っています。心霊が実在するとしたら、それは人間の問題の何を解決するのか、より良い生活を導くのか、他人との関係が豊かに深くなるのか。
肝心なのは、そのことなのです」
本書には、「死者のいる場所」というサブタイトルがついています。「死者のいる場所」というのは「心霊スポット」というだけではなく、「慰霊の場所」という意味合いもあります。霊場恐山には故人を思慕する人々がたくさん訪れ、五月人形や花嫁人形、あるいは故人が生前着ていた遺服を供える人もいるそうです。
こういった遺族の行為について、著者は「人形や服を供えることで、何とかその亡くなった人を存在させようとしているのです。このことを私は、単純に『悲しみ』『切なさ』『懐かしさ』のような、気持ちや感情の問題として考えることができません。ここには何か、圧倒的なリアリティがある。それが恐山の凄みでもあるのです」と述べます。
著者は「霊場恐山は、幽霊が出るから1200年続いたわけではない」としながらも、その一方で「魂の有無に恐山はかかっている」とも述べます。
そして、「魂とは何か」について、「私に言わせれば、それは人が生きる意味と価値のことです。大和魂と言えば、日本人として生きる意味と価値のこと。武士の魂と言えば、侍として生きる意味と価値のことです」と述べています。
魂とは、どこにあるのか。この問いに対して、著者は次のように答えます。「魂というものは、1にかかって人との縁で育てるものです。他者との関係の中で育むものでしかないのです。
よくよく考えてみればわかるでしょう。魂というものの最初の種、これを植えてくれる人があるとすれば、母親をおいて他にいないと思います。本当は両親と言いたいところですが。私も父親なので誤解のないように言っておきますが、父親の役割や責任を免除しているわけではありません。客観的に考えて、私は母親だと思うのです」
本書には、「人は死んだらどこへゆく」という問題についても語られています。著者が修行僧時代、出家してしばらくした頃のこと。著者が使えていた老僧から「おまえは人が死んだらどこへ行くか知っているか」と質問され、答えられなかったそうです。すると、その老師は、「人が死ぬとな、その人が愛したもののところへ行く」と語ったとか。
続けて老師は「人が人を愛したんだったら、その愛した者のところへ行く。仕事を愛したんだったら、その仕事の中に入っていくんだ。だから、人は思い出そうと意識しなくても、死んだ人のことを思い出すだろう。入っていくからだ」と言い、さらには「愛することを知らない人間は気の毒だな。死んでも行き場所がない」と言ったというのです。
この言葉は、非常にわたしの心に突き刺さりました。さすがは禅の老師ですね。
著者によれば、霊場恐山は1200年の間、「もう一度会いたい 声が聞きたい」「また会いに来るからね」という死者への想いによって支えられてきました。その想いが地層のように積み重なり、それが形になった場所が恐山だといいます。
そして、世間では最近「パワースポット」という言葉が流行していますが、著者は恐山のことを「パワーレス・スポット」と呼び、次のように述べます。
「パワースポットと呼ばれる場所は、そこに何かありがたいもの、超自然的なもの、人知で計りがたいものがあって、そこから不思議なパワーが発散される場所のことでしょう。だからそこに行けば、元気をもらえたり、癒されたり、何かご利益を得ることができると信じられ、それを求めて人が集まる。そのような場所がパワースポットだというのならば、恐山は真逆でございます。恐山が霊場であるのは、パワーがあるからではないんです。力も意味も『ない』から霊場なんです。つまり恐山は、『パワーレス・スポット』なのです」
第三章「死者への想いを預かる場所」は、慰霊・鎮魂・さらにはグリーフケアという問題も絡んで、非常に読み応えがありました。著者は、恐山を「仏教では割り切れない場所」であるとし、「死者供養を例に考えてみましょう」と読者に呼びかけて、次のように述べます。
「それまで永平寺で学んだ仏教の理論をもってすれば、『無記』というカードを使って、『死後の世界や霊魂を”ある”とも”ない”とも言わない。それが仏教の考え方です』と、答えを保留することができます。
『死後の世界や霊魂が”ある”と思う人は”ある”と思えばいい。”ない”と思うならそれでいい』そのように仏教の公式見解を伝えて、放っておけばいい。そう割り切ればいいのです。そのカードを切ってしまえば、別にこちらが困ることはありません。
仏教教義上、間違ったことは決して言っていないし、理論的な混乱も生じません」
しかし、一方で著者は次のようにも述べます。
「ところが恐山に身を預け、いざ当事者になってみると、そうはいかないのです。
『無記』のカードだけでは割り切ることのできない、動かしがたい、圧倒的な想いの密度と強度―それを私はリアリティと呼んでいます―がそこにはある」
そして著者は、ついに「死者は実在する」と考えなければ、恐山のことは理解できないと思い至ります。そこから、「死」についての著者の思索は深まっていきます。まず最初に「死者=死」ではないとして、次のように述べます。
「一見、死というものは死者に埋め込まれている、張り付いていると思われがちです。しかし私が恐山でつかんだ感覚としては、死は実は死者の側にあるのではありません。むしろそれは死者を想う生者の側に張り付いているのです。
なぜなら、死こそが、生者の抱える欠落をあらわすものだからです。その欠落があるからこそ、生者は死者を想う。欠落が死者を想う強烈な原動力になっているのです。
死者のことが忘れられない、というのは、忘れられない構造が人間の中にあるからです。死者を忘れるということは、生きている人間が抱える欠落を、何か適当な意味をつくってふさぐことに等しい。しかし、死とはあらゆる意味を無効にしてしまう欠落です。死者こそがこれを意識させる。私が恐山に来てつくづく思ったのは、『なぜみんな霊の話がこんなに好きなのだろうか』ということです。それは人間の中に根源的な欲望があるからです。そしてその欲望は不安からやって来ます。
つまり、霊魂や死者に対する激しい興味なり欲望の根本には、『自分はどこから来てどこに行くのかわからない』という抜きがたい不安があるわけです。
この不安こそがまさに、人間の抱える欠落であり、生者に見える死の顔であり、『死者』へのやむにやまれぬ欲望なのです」
死というものを考えるとき、よく「1人称の死」「2人称の死」「3人称の死」と3種類に分ける言葉が使われます。その言葉自体は、名著『死』を書いたフランスの哲学者ウラジミール・ジャンケレヴィッチによって広められたものです。このジャンケレヴィッチの言葉に対して、著者は次のように述べます。
「1人称の死、というのは、自分の死。
2人称の死、というのは、家族や近親者の死。
3人称の死、というのは、他人の死。
そのように”死”を分けて考える。
だけど私に言わせれば、2人称と3人称の死、というのは、”死”ではありません。
それはただの”不在”か”消滅”です。他者の不在や消滅を目の当たりにした者が、これが自分にもいずれ起こることだと考えたときに、初め”死”がリアルなものとして立ち上がり、死についての自覚が生まれるのではないでしょうか。
2人称、3人称の死というのは、1人称の死を投影しただけです。他人の死というものは、自分の死の参考には決してならないものです。何人称であろうが、つまり「あなたの死」であろうが、「彼の死」であろうが、ある不在が自分にも起こると思った瞬間に、死という言葉が我が身にもリアルに迫ってくるのです」
「人は死んでも関係性は消えない」とする著者は、次のように述べます。
「自分に欠落したものを死者が見せ、その欠落が欲望するものを死者に預けていく。
『死者に会いたい』と考える根底のところでは、そのような無意識のはたらきがあるのではないでしょうか。友人であれ夫婦であれ家族であれ、生前に濃密な関係を構築し、自分の在りようを決めていたものが、死によって失われてしまう。
しかし、それが物理的に失われたとしても、その関係性や意味そのものは、記憶とともに残存し、消えっこないのです」
ただし、関係性や意味を生者がずっと抱えていくことは困難です。生者が抱えたままでは日常生活を送ることができなくなります。ならば、どうするのか。著者は、次のように述べます。
「死者にその関係性を預かってもらうのです。私たちの想い出す、懐かしむという行為によって、死者は現前し続けます。不在のまま、我々に意味を与え続ける。だけど生者はその意味を持ちようがない。抱えきれない。
相手が生きていれば、その関係性や意味を互いに持ち合うことができます。また、意味を変化させたり、再生産したりすることもできるでしょう。
しかし相手が不在の場合、これはどうしようもありません。お手上げです。両者をつなぐ意味だけが残り、しかもそれは生者の行動さえも変えてしまう力を持つのですから、その力に押されて精神的に参ってしまう人がでてもおかしくありません。身近な人の死に囚われて、一時期は一歩も身動きが取れなかったという人が、よく恐山を訪れますが、まさにそれです。生者は、死者という『不在の関係性』を持ち切れません。その代わり、死者にその『不在の意味』を担保してもらう他ないのです。
死者に関係性や意味を預かってもらうしかないのです」
死者に関係性や意味を預かってもらう場所こそ、霊場恐山なのです。さらに、続けて著者は次のように述べます。
「重要なのは、生者との関係性が消えてしまうと、その関係性の密度は、むしろ死んでしまった後の方が強化される、ということです。
よく言うでしょう。『自分の親が死んでからそのありがたさがわかった。生きている間に親孝行しておけばよかった・・・・・・』
いつまでも相手がいると思うと、愚かにもその人をあまり大切にしなかったり、会いに行かなかったりします。しかし、いつでも会えると思っているうちに相手が死んでしまったら、後々まで大きく響きます。感謝でも謝罪でも、その人が生きているうちにしておかなければ、それは後悔という形で永遠に残ってしまいます」
関係性のあった相手が亡くなると、その後に残る意味は強烈なものになります。それはイメージや観念として残るのですが、生者だけでは持ちきれないので、死者に預かってもらうしかないのです。著者は述べます。
「死者の想い出というのは、それが懐かしさを伴うものだろうが、恨みを伴うものだろうが、死者に背負わせるべきものなのです。生者が背負うものではなく、死者に預かってもらうしかないのです。恐山というところは、そのような死者の想い出を預かる場所なのです。『恐山は巨大なロッカーである』とも言えるでしょう。想い出というのは、預けておく場所が必要です。よく『過去を引きずるな』と言いますが、それは『死者の想い出を生者が持ち切れない』からです。『死んだ人のことは忘れなさい』とも言いますが、忘れられるわけがありません。それが大事な人だったらなおさらのことでしょう。その想い出は死者に預かってもらうより他ないのです」
「恐山は巨大なロッカーである」とは、名言ですね。ロッカーといえば、わたしは納骨堂をイメージしてしまいます。よく考えると、納骨堂や墓に預けるものとは遺骨だけではなく、故人の思い出もそうですね。ここで、供養の問題が出てきます。著者は、供養について次のように述べています。
「死者と向き合う、というのは、仏教の問題とは直接関係がないのです。
どの世界のどの宗教にも死者と向き合う儀式があります。亡くなった人への想いというのは全世界共通のもののはずで、その感情をどのような枠に入れて処理するか、というところでそれぞれの宗教の問題になってきます。
それは仏教的なものもあれば、キリスト教的なものもあれば、恐山的なものもある。どれを使っても別にいいわけです。仏教の中でも極楽浄土を設定するものもあれば、我々禅宗のやり方でもいい。それはその人が生きている世界や縁で決まってくるもので、そこには優劣も本質的な違いもないと私は思います」
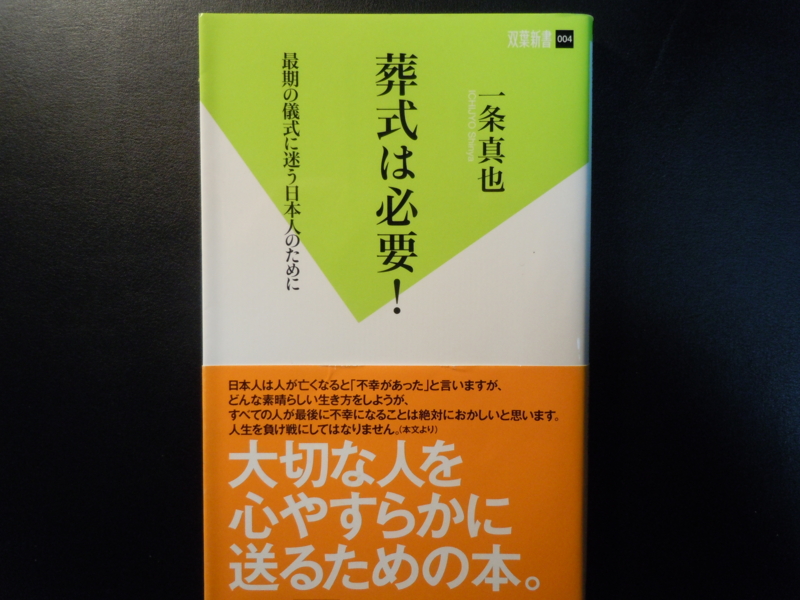 死者儀礼のあり方について考える
死者儀礼のあり方について考える
供養の問題は、当然ながら、葬儀という死者儀礼の問題につながります。
最近、「葬式は、要らない」という言葉に代表されるように、あちこちで葬式仏教批判が行われています。葬式仏教の形骸化が叫ばれ、仏教の僧侶を必要としない無宗教の葬儀も増えています。このような風潮に対して、わたしは『葬式は必要!』(双葉新書)を書いたわけですが、著者も次のように述べています。
「死者に対して何かを想うということと、死者儀礼というのは別のものです。
しかしもっと決定的なのは、こうした儀式仏教に対する批判や意識の変化が、死者の扱い方とは別問題だということです。儀礼の煩雑や金銭問題などは、所詮、枝葉の話です。
むしろ問題は、生者の側にあります。
最大の原因は、他者や自己の存在感が希薄になっていることです。
死者供養の形骸化というのは、生者が軽く扱われていることと並行して考えるべき問題です。生者の意味が軽くなっているから、死者の意味も軽くなっているのです。
繰り返し述べているように、死者のリアリティと生者のリアリティは同じである、と私は思っています。生のリアリティの根本にあるのは他者との関係性です。他者との関係性が軽くなってしまえば、生きている人間の存在感も軽くなる。他者に強い思い入れもなければ、他者から得るものも当然少なくなってきます。
それは他者とて同じこと。存在感が希薄になりつつある生者に、死者を想い出す余裕はありません。葬式に対する意識が薄くなるのも当然です」
この著者の意見に、わたしもまったく同感です。「葬式無用論」とセットになっているのが「無縁社会」の問題です。いつも指摘していますが、NHKスペシャルで「無縁社会」が最初に放映されたのも、島田裕巳氏の『葬式は、要らない』(幻冬舎新書)の初版が刊行されたのも、ともに2010年の1月でした。
このとき、日本人の「こころ」は大きな曲がり角を迎えたと思っていますが、結局、「無縁社会」と「葬式は、要らない」は同じ意味というか、同義語ではないかと思います。著者も、「無縁社会」について次のように述べています。
「『無縁社会』と呼ばれる昨今は、『最近、葬式抜きで、いきなり埋葬する方法が増えてきています。これはお坊さんとしては反対でしょう?』と尋ねられたことも数度あります。
残念だとは思いますが、反対ではありません。どう葬ろうと、葬る人の自由です。仏教の教義をどんなに検討しても、そこから直接現在のような葬式をしなければいけないという確実な根拠は、引き出せません。仏教僧が葬式をできるのは、それを望む人がいる限りにおいてです。したがって、今後も僧侶が葬式に関わりたいと思うなら、仏教のファンを増やし、僧侶への信頼を培い、『仏教僧侶であるあなたに自分の葬式をしてほしい』と、檀家なり信者なりに言ってもらう努力をするしか、対策はないのです。
私は巷間言われている『葬式仏教』に未来はない、と思っています」
そして、著者は「死者儀礼」そのものの意味を問い、次のように述べます。
「死者儀礼の場合、人が人を弔うことには、どのような意味があるのか。そしてそれをなぜ仏教が担うのか。お坊さんが果たす役割とは何か―。
そこまで問いを深く下ろして、考えなければいけないのです。
弔いという行為は、人類共通のものです。古今東西、どの民族、どの文化にも存在します。人が人と死に別れるためには、何らかの儀式が必要なのです。そこを見つめない限り、葬儀のイノヴェーションもあり得ないでしょう」
「弔いの意味」について考える上で、著者は述べます。
「人が誰かと死別するということ、その死別を悲しむ人がいるということ、そして追憶には長い時間を要する、ということについて真剣に考えなければいけません。
人間だけが人間を看取ります。
人間だけが人間を埋葬します。
そして人間だけが故人を想い出します。
そのことをふまえて、根底から弔いの意味を問い直さなければいけないのです」
わたしは、葬式仏教が日本人の宗教的欲求を満たしてきたことの意味は大きいと思っています。また、遺族の悲しみを癒すグリーフケアにおいても、日本では仏教が最大の役割を果たしてきました。著者は仏教を「死者を想うための器」として、述べます。
「人間は水を飲むのにもコップという器を使います。
人間の衝動というものは、何かで汲み上げられない限り感情にはなり得ません。
死に対する衝動を汲み上げるにも、何らかの器が必要なのです。
その器として機能したのが、日本の場合は仏教だったのです。
それは恐山でも同じです。仏教の器があるからこそ、そこに入っているものの匂いや味、形がわかるのです。人が死を思い、故人を拝むには器が必要なのです。
目に見えるものをよすがとしなければ、死者というものも立ってきません。
何もないところで、『自由に死者を想い出してごらん』と言われても、思考は次第にとりとめなく拡散するばかりで、しまいにはどうしてよいかわからなくなるでしょう。
そこには何らかの器が必要なのです」
同感です。この文章は、葬式仏教の理論武装に今後なりうる可能性を持っています。
また、著者の「死者」についての考え方にも強く共感しました。著者は「死者は懐かしくて恐いもの」であるとして、次のように述べます。
「おそらく、人間には拝むものが必要なのです。
なぜなら、死や死者に対する懐かしさと恐れが、人間には抜き難くあるからです。
なぜ、そのような感情が生じるかというと、死という、わけのわからない何かが自分の内側にもあるからです。それを処理するためには、拝む対象がどうしても必要になってくる。ただ、むき出しの死者に対して拝むことはできません。それは恐いことです。
死者を拝むためには、死者の輪郭をはっきりさせて、自分との距離を作ってくれるものが必要になってきます。それが宗教の仕掛けなのです。
お墓でも、仏像でも、位牌でも、イタコでもいい。
一定の距離を生者と死者の間に作るために、そのような装置が必要になってきます」
最後に、本書には東日本大震災で生まれた膨大な犠牲者(死者)と被災者(遺族)のことが書かれています。震災後、20歳そこそこの頭を金色に染めたヤンキー風の若者が、著者の寺を訪れたそうです。気仙沼から来たという彼は、震災の犠牲となった妻と赤ん坊のために塔婆の供養に来たのでした。しかし、彼からはまったく悲しみが感じられず、まるでコンビニしているのと変わらぬ様子だったそうです。
そんな姿に呆然としながらも、著者は「彼はいま、悲しくないのだ」と気づきます。そして、次のように書いています。
「彼らには、まだ死者がいない。失われた人が死者になりきっていないのだ。死そのものを理解できない人間は、別離という生者の経験になぞらえて死を考えるしかない。
別れとは何か。それは、今まで自分の人間関係の中に織り込まれていた人物を、不在者として位置づけなおすことである。『不在』という意味の存在者に仕立てることである。
だから、別れには挨拶がいるのだ。作法が要るのである。挨拶は、そのような存在の仕方を互いに許し、確認する行為である。死による別離も事情は同じである。弔いという行為が人間の社会にあるのは、生者に挨拶があるのと同じことなのだ。この過程を経ないと、別れは別れにならず、死者は死者として『存在』できない。
その『存在』と生者は新しい関係を結ぶことができない。適当な距離をとれない」
人間にとって、いったい「弔い」とは何なのでしょうか。著者は述べます。
「そもそも、弔いとは時間のかかる行為なのである。ときに儀礼の形式をかりながら感情を整理して、死者を死者たらしめるには、短くない過程が必要なのだ。
突然の大量の犠牲者と被災者の状況を思えば、おそらく彼らには十分な別れがない。つまり、『死者』になりきれない。遺体が発見されなければなおさらだ。その意味では、事故などで急に家族を奪われた遺族も同じである。失われた人への様々な想いも、死者になりきれない存在には預けようがない。『ひょっこり帰ってきそうな気がする』人に、『なぜ死んじゃったの』と、剥き出しの悲しみをぶつけることはむずかしい」
東日本大震災後、多くの日本人が「死」を見つめています。死者とは何か。死者儀礼とは何か。供養とは何か。ある意味で現代的なこれらの問題を前にして、1200年にわたって「死者のいる場所」であり続けてきた恐山という窓を覗きながら考えることは非常に意味があると思います。
仏教の枠を超えた著者の哲学的思索にも、知的好奇心を大いに刺激される好著です。
