- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2013.04.17
『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』村上春樹著(文藝春秋)を読了しました。ブログ「村上春樹氏の新刊タイトルは長い!」で紹介した話題の本がついに発売されたのです。
ブログ「『1Q84』BOOK3」に書いたように、著者の前作は発売と同時に即日読了しました。ブログは翌日書きましたが、いま記事を見ると2010年4月17日となっています。あれから、ぴったり3年目なのですね。でも、今回は発売と同時に読むことはできませんでした。そもそも発売日の12日、わたしはミャンマーにいました。また、予約はしていたものの、土日を挟んで、アマゾンから北九州のわたしのオフィスに本書が届いたのが月曜の15日朝だったのです。
うーん、こういう点が地方は圧倒的に不利ですね。
まあ、急いでブログ書評を書くことに、さほどの意味は感じませんけれども。
話題の新作ですから、少しでも早く読みたいのが人情じゃありませんか。
それにしても、発売日の翌日には、本書についての膨大な数のレビュー、ブログなどでの書評が早くもネットにUPされていましたね。
ミャンマーでその事実を知ったとき、わたしはしばし呆然としました。
日本には、360ページ以上もある単行本を1日で読めて、なおかつその日のうちにレビューや書評を書ける人がゴロゴロいるのですね。もちろん、そういった読書家の存在は国民全体からすれば少数派なのでしょうが、それにしても日本を代表する国民作家が新作を発表すれば、これだけのお祭り状態になるというのは、日本は一応、「読書大国」なのでしょう。
さて作品についてですが、ネットを見ると賛否両論で、「さすがは村上春樹!」という絶賛と「村上春樹はもう終わった」という失望の声が入り乱れています。しかし、わたしは「面白い小説だな」と思いました。まず、非常に読みやすい。コミックの原作かライトノベルのようなリーダブルな小説です。でも、扱っているテーマは、これまでの村上作品と同じく、重い、です。
まず冒頭からして、次の書き出しで始まります。
「大学二年生の七月から、翌年の一月にかけて、多崎つくるはほとんど死ぬことだけを考えて生きていた。その間に二十歳の誕生日を迎えたが、その刻み目はとくに何の意味も持たなかった。それらの日々、自らの命を絶つことは彼にとって、何より自然で筋の通ったことに思えた。なぜそこで最後の一歩を踏み出さなかったのか、理由は今でもよくわからない。そのときなら生死を隔てる敷居をまたぐのは、生卵をひとつ呑むより簡単なことだったのに」
(『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』p.3)

いきなり、本書の第1行目から「死ぬ」という単語が登場するのです。
そして、この物語は最後まで「死」の気配が強く漂っているのでした。
拙著『ご先祖さまとのつきあい方』(双葉新書)の「生命の輪は廻る〜あとがきに代えて」にも書きましたが、もともと村上春樹の文学には、つねに死の影が漂っています。彼の作品にはおびただしい「死」が、そして多くの「死者」が出てくるのです。哲学者の内田樹氏は『もういちど村上春樹にご用心』(ARTES)の中で、「およそ文学の世界で歴史的名声を博したものの過半は『死者から受ける影響』を扱っている。文学史はあまり語りたがらないが、これはほんとうのことである」と述べています。そして、近いところでは村上春樹のほぼ全作品が「幽霊」話であるというのです。もっとも村上作品には「幽霊が出る」場合と「人間が消える」場合と二種類ありますが、これは機能的には同じことであるというのです。
そして、本書『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』にも、しっかり死者が登場します。このような「幽霊」文学を作り続けてゆく村上氏の心には、おそらく「死者との共生」という意識が強くあるのでしょう。
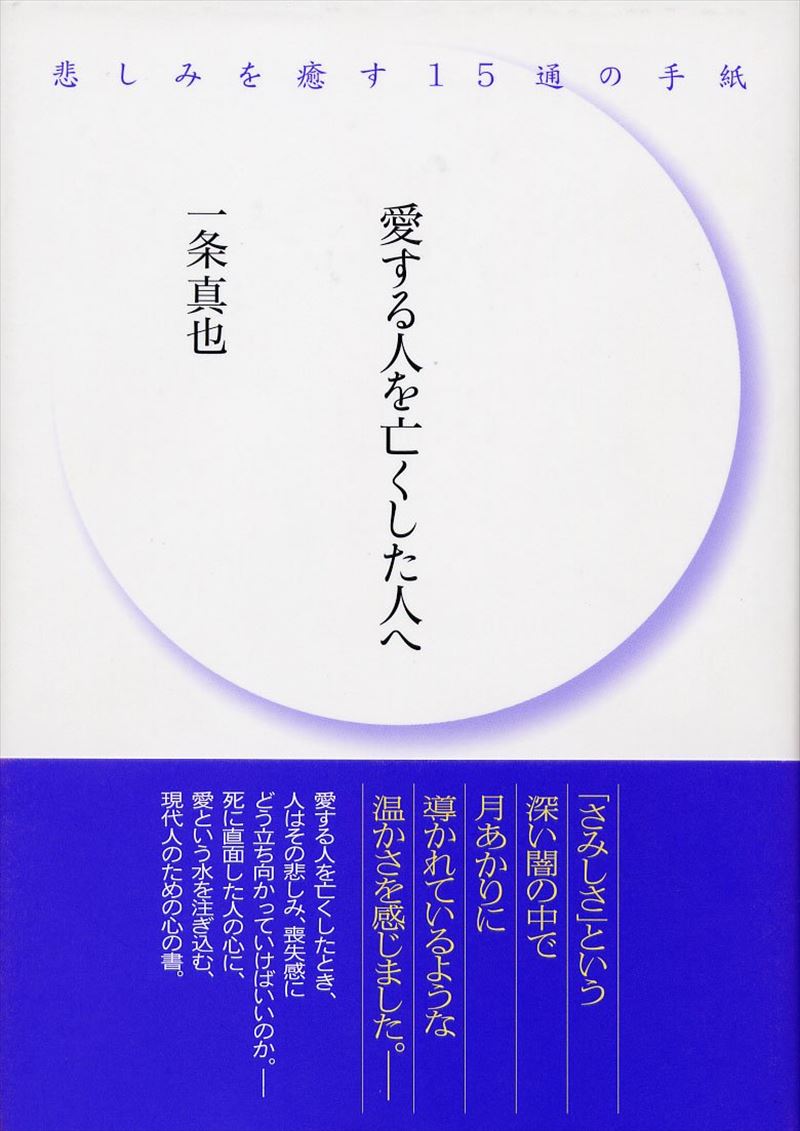
なぜ、多崎つくるが「死ぬ」ことだけを考えるようになったのか。
それは、彼がこの上なく大切にしていた親友たちから絶交されたからです。
それも、彼自身には絶交される理由がまったく思い浮かばないという不条理な経験をしたからです。その結果、彼は大きな喪失体験をするのでした。
拙著『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)で、わたしはユダヤ教のラビにしてアメリカのグリーフ・カウンセラーであるE・A・グロルマンの言葉をわたし流にアレンジした次のメッセージを紹介しました。
親を亡くした人は、過去を失う。
配偶者を亡くした人は、現在を失う。
子を亡くした人は、未来を失う。
恋人・友人・知人を亡くした人は、自分の一部を失う。
彼、多崎つくるは、4人の親友を失いました。死別ではなく、生きたまま彼らとの関係を絶たれたのです。それは、そのまま4人分の「自分の一部」を失うことにほかなりませんでした。これはもう、途方もない喪失体験です。これほどの喪失体験といえば、3・11を連想せずにはおれません。そう、『1Q84』がオウム真理教事件をモチーフとしているならば、この『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』の根底には、3・11の巨大な喪失体験が横たわっています。考えてみれば、あの津波ほど不条理な喪失体験はありませんでした。
本書は、途方もない喪失を経験した主人公が失ったものを取り戻す「巡礼」の旅に出る物語です。巡礼の具体的な内容については、ネタバレになるので書けませんけれども・・・・・。
というか、これ以上、ネタバレを避けながら本書についての突っ込んだ感想を書くことは難しいです。まったく、新刊小説の紹介というのは、やりにくいですね。
ですから、これからはストーリーと関係ない部分で率直な感想を述べます。
まず、本書には著者の過去の発言や著作の影がいたるところに見えます。
先ほど引用した冒頭の言葉の最後の部分である「そのときなら生死を隔てる敷居をまたぐのは、生卵をひとつ呑むより簡単なことだったのに」に出てくる「生卵」というのは、明らかにエルサレム賞受賞スピーチの「高くて、固い壁があり、それにぶつかって壊れる卵があるとしたら、私は常に卵側に立つ」という発言を意識しているでしょう。
また、本書の中には過去の村上作品を連想させる場面が多く登場します。
たとえば処女作『風の歌を聴け』の秘密性、『ノルウェイの森』の狂気、『国境の南、太陽に西』の切なさ・・・他にも、挙げていけばキリがありません。
そして、本書にはフィンランドが舞台として登場します。フィンランドの森の「悪いこびと」というのも出てきますが、これは『1Q84』の「リトル・ピープル」ですね。
さらに、あえて邪推するならノーベル賞の本部があるスウェーデンと同じ北欧の国フィンランドを舞台とすることで、著者は今度こそ本気でノーベル文学賞を狙ってきたのではないでしょうか。わたしには、そう思えます。
ノーベル賞といえば、本書には灰田という学生が登場します。彼の父親が哲学の教授で自身は物理学を学んでいることから、つくるは「物理学科の方が哲学科よりは、経済的にいくぶん恵まれるんだろうか?」と灰田に尋ねたところ、彼は「もうからないことにかけてはどっこいどっこいでしょう。もちろんノーベル賞でもとれば話は別ですが」と答えます。あまり深読みするのも馬鹿みたいですが、毎回ノーベル文学賞候補といわれながら未だに受賞していない著書がこういうことを書くこと自体が興味深いですね。
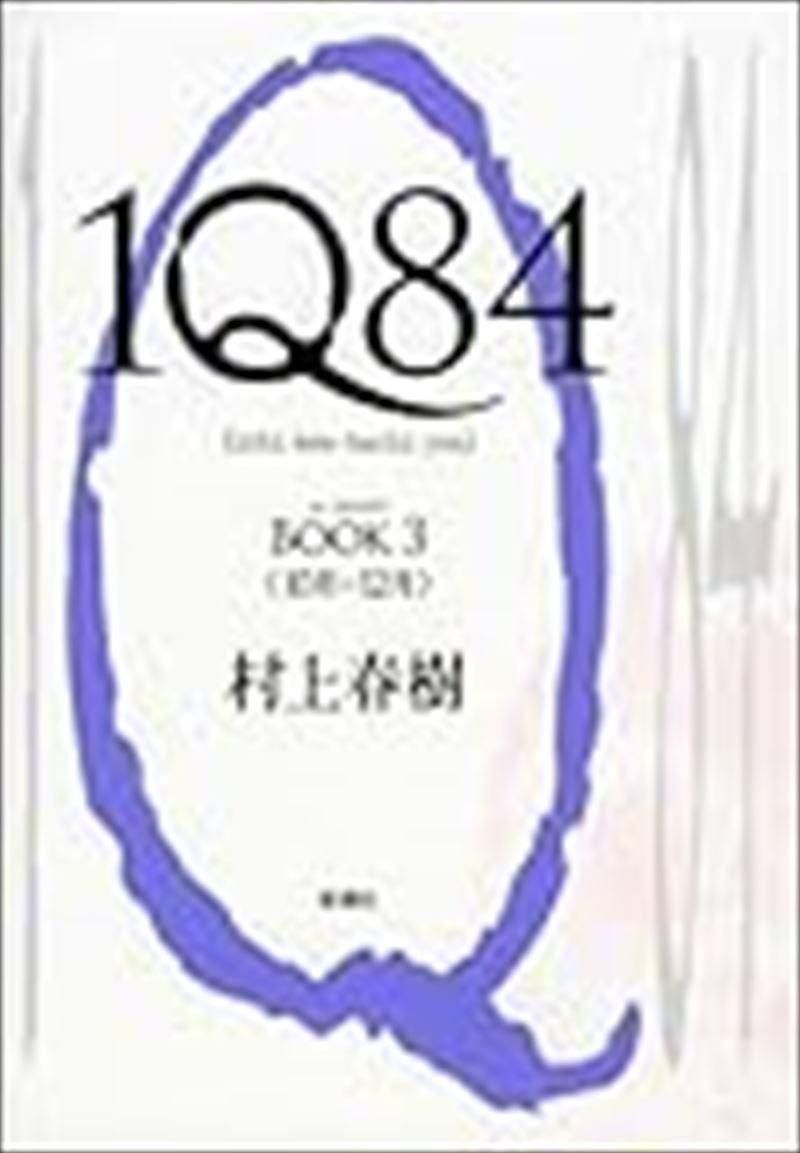
それから、トヨタのレクサスに対して批判的なニュアンスが感じられたのが気になりました。「レクサス」という言葉には何の意味もなく、トヨタの依頼を受けたニューヨークの広告代理店が「いかにも高級そうで、意味ありげで、響きの良い言葉」を作っただけだというのです。こんな話、初めて知りました。この事実を広く知らしめることがトヨタにとって良いはずはありません。著者は、なぜ、このようなことをするのでしょうか。前作『1Q84』でもNHKやホテル・オークラについてのネガティブな描写がありましたが、もしかしたら著者は「NHKやホテル・オークラやトヨタなら、これくらい書いても大丈夫」と考えているのではないでしょうか。それは、「多崎つくるなら大丈夫」と思った某友人の心にも通じています。
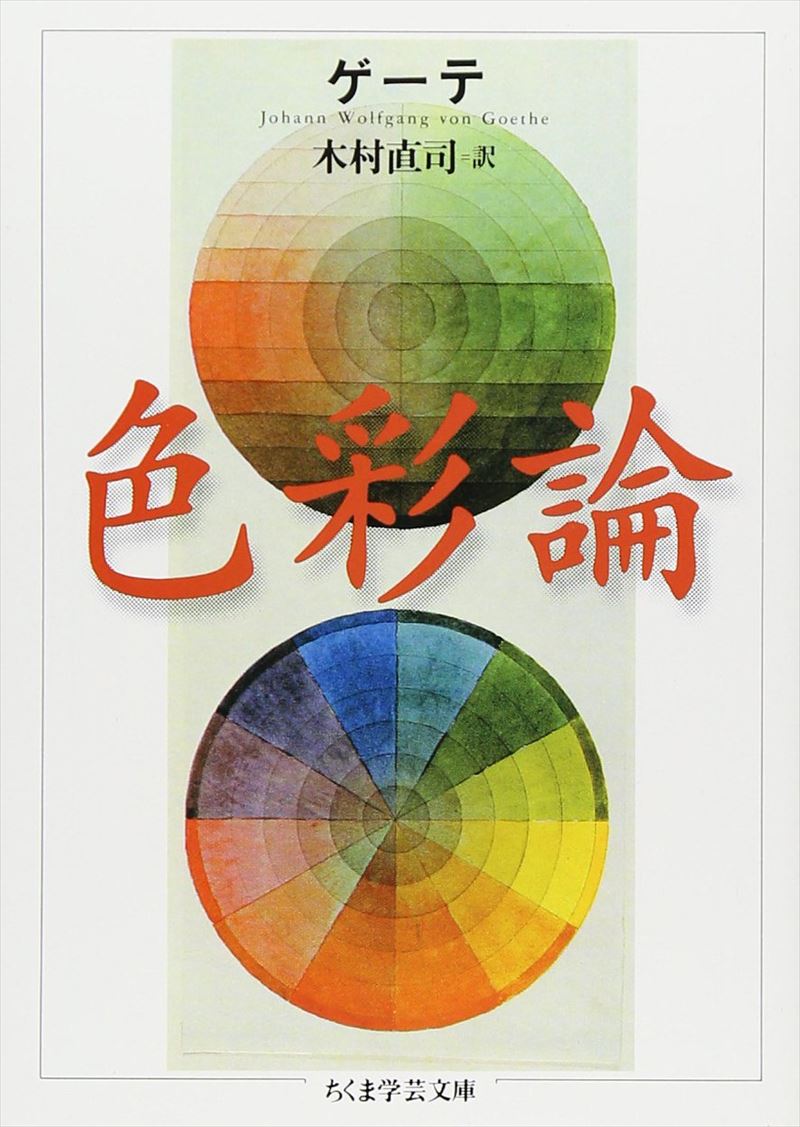
本書を読んで驚いたのは、登場人物の名字に色があることでした。
「これは、もうマンガの世界だろう」とも思いましたし、シロとクロの2人の女の子に至っては「オセロじゃん!」と突っ込みを入れたくなりました。
しかし、読み進んでいくうちに、色彩を持った名前の人々の言動が非常に秘教めいて感じられます。わたしは、ドイツの神秘哲学者であるルドルフ・シュタイナーが唱えた色彩論を思い浮かべました。
19世紀の終わり、シュタイナーは『ゲーテ自然科学論文集』全5巻を編集しました。その第3巻〜第5巻には、ゲーテの色彩論が収録されています。光学などの自然科学にも精通していたシュタイナーは、その成果の上に立ちながらゲーテ的な意味での色彩論を書くことを「わたしの人生のもっとも美しい課題」としていました。シュタイナーの著書である『色彩の本質』高橋厳訳(イザラ書房)、『色彩の秘密』西川隆範訳(イザラ書房)などにその成果の一端が書かれています。

シュタイナーは、色彩というものを「像の色」「影の色」「輝きの色」「影のような像から輝き出る色」などと分類しました。そして、白は「霊の魂的な像を表す」色であり、黒は「死の霊的な像を表す」色であり、青は「魂の輝き」の色であり、赤は「生命の輝き」の色であるとしています。
このシュタイナーの色彩論を頭の隅に置いて本書を読めば、また違った次元の世界が立ち上がってくるかもしれません。
それから「色」といえば、かのブッダも問題にしたテーマです。
ブログ「市川團十郎さんの葬儀に思う」にも書きましたが、『般若心経』に出てくる「色即是空空即是色」とは、この世にあるすべてのものは因と縁によって存在しており、その本質は空であることを示しています。また、その空がそのままこの世に存在するすべてのものの姿であるということも示しています。
「色」とは、「目に見えるもの」をブッダ流に表現した言葉でしょう。色がついていれば、どんなモノでも見えます。でも、空気は色がないので見えません。
ブッダは見える世界を「色」と呼び、見えない世界を「空」と呼んだのです。
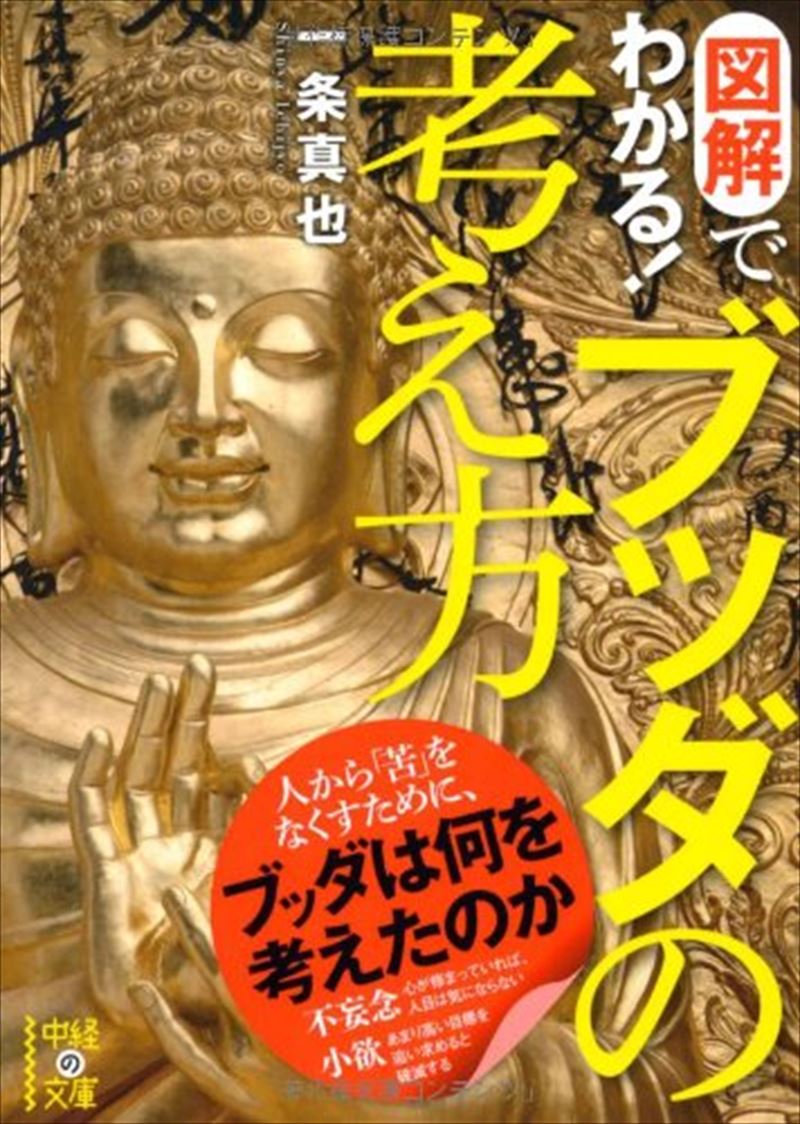
拙著『図解でわかる!ブッダの考え方』(中経の文庫)にも書きましたが、見える世界と見えない世界というのは、じつは同じです。
なぜなら、見える世界は見えない世界によってできているからです。
原子などは、その最も良い例ですね。
この世界は、見えない原子によって成り立っているのですから。
これはなかなか抽象的で難しい考えなので、ブッダは色のある見える世界を「色」と表現し、色のない見えない世界を「空」と表現したのでしょう。
今さらながらに卓越した表現センスであると思います。
本書では、多崎つくるが自身のことを「色彩を持たない」人間であるとし、さらに「僕には個性みたいなものもなかった」と語ったとき、かつての友人の1人が「生きている限り個性は誰にでもある。それが表から見えやすい人と、見えにくい人がいるだけだよ」と言います。このくだりを読んで、わたしは単なる「色彩」ではなくブッダの説いた「色」が問題なのだと思いました。
さて、ゲーテやシュタイナーが論じた「色」とは人間の魂に深く関わるものですが、同じく魂に深く関わるものとして「夢」があります。
本書は、まるで『夢判断』の小説版みたいな要素があり、主人公はさまざまな夢を見ます。その多くは性的な夢で、当然ながらフロイトを連想します。さらには、ラカンの印象もあります。そういえば、『1Q84』にはユングが登場しました。
そうです、村上春樹の文学はきわめて心理学的なのです。
そして、現実世界における心理学の最大の課題といえば、「うつ」の解消であり、自殺の回避であり、喪失体験の回復でしょう。これらは、すべて「グリーフケア」という問題に集約されます。わが社では、グリーフケアの実践者を養成すべく、上級心理カウンセラーの資格者を増やしています。すでに数十名の上級心理カウンセラーが誕生しましたが、今後さらに100名をめざしていきます。
彼らの最大のミッションは、「愛する人を亡くした人」である遺族をはじめとした喪失体験者に寄り添い、その悲しみを少しでも軽くするお手伝いをすることです。その意味で、本書の主人公である多崎つくるの喪失体験、そしてそれを回復する「巡礼」の体験は非常に参考になりました。
不条理なままに親友たちから拒絶された多崎つくるは、「航行している船のデッキから夜の海に、突然一人で放り出されたような気分」を味わいます。しかし、彼はなんとか自力で(少しは沙羅という年上の恋人の助けも借りたにせよ)夜の海を泳ぎます。この突然一人で放り出された夜の海を泳ぐという行為こそ「グリーフケア」なのではないでしょうか。その意味で、つくるにとって沙羅こそはグリーフ・カウンセラーであったと言えます。

本書は、間違いなく「グリーフケア文学」と呼べます。
タイトルにある「巡礼」とは「グリーフケア」の別名なのです。
そして、本書の中で繰り返し言及される音楽があります。
リストの「La mal du pays(ル・マル・デュ・ペイ)」というピアノ曲です。
ラザール・ベルマンが奏でる、静かな調べの中にも悲痛な魂の叫び声がかすかに聞こえてくるような曲です。そう、人はみな悲痛な叫び声を発しながら生きていく。そして、他人の叫び声を聞いてしまったら、知らんぷりはできない。人の心は、痛みと痛みでつながっているのです。傷(きず)を共有してこその絆(きずな)であり、喪失を共有してこその共感ではないでしょうか。
この曲こそは、グリーフケアのテーマ・ミュージックと呼べると思います。
最後に、本書に登場する2人の重要な登場人物の謎が解けずじまいで物語は終わります。つまり、2人の物語は回収されないままなのですが、それはきっと著者が別の作品で書いてくれることでしょう。
久々の村上春樹の小説、面白かったです。そして、次回作が楽しみです。
なお、『死が怖くなくなる読書』(現代書林)でも本書を取り上げています。
