- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2013.08.07
株式会社サン・ライフメンバーズの竹内惠司会長から本が届きました。わたしの尊敬する互助会経営者です。届いたのは、『自分らしい人生の卒業式を望むあなたへ』鶴蒔靖夫著(IN通信社)という本です。竹内会長からのお手紙が同封されており、そこには「私が取材を受け、それを元に鶴蒔靖夫氏が執筆した本『自分らしい人生の卒業式を望むあなたへ』を送付申し上げます。『死』を人生の卒業式と捉え、明るく前向きに過ごすためのヒントになればと思い製作いたしました」と書かれていました。

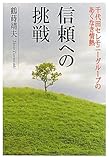

著者の鶴蒔氏は、自身が代表を務めているIN通信社から、さまざまな企業に関する本を出版されています。ここのところ、千代田グループについての『信頼への挑戦』本をはじめ、メモリードグループについての『夢企業 メモリードグループの挑戦』および『なぜ、お葬式は必要なのか』、さらには、くらしの友についての『21世紀型互助会のすヽめ』など、互助会各社を取材した本を立て続けに刊行されています。特に、『21世紀型互助会のすヽめ』と本書は同時刊行となっています。これからも続々と刊行される予感がしますが、これまであまり業界外の人々に知られる機会が少なかった互助会経営者の考えが広く伝わることは素晴らしいことだと思います。
さて、本書には「明るく笑顔でいま準備を」とのサブタイトルがついています。帯には「サン・ライフグループ代表・竹内惠司が語る『輝く明日が見えてくる旅立ちの極意』」と書かれています。また、本書の目次構成は以下のようになっています。
「はじめに」
第1章 変わりつづける弔いの光景
第2章 葬送文化の変容・葬祭業が果たした役割
第3章 日本の葬送文化の変遷と死の準備教育
第4章 いま、旅立ちの準備を
第5章 明るい人生の卒業のために
付録「世界の宗教と葬送の流儀」
「はじめに」では、次のように竹内会長を紹介しています。
「竹内氏は現在77歳。神奈川県で冠婚葬祭業を行う株式会社サン・ライフの代表取締役会長を務めている。昭和38年から約半世紀にわたって葬送の営みに従事してきた竹内氏の、その長い経験から発せられる言葉には実感に裏打ちされた重みが込められている。竹内氏はいくつもの新機軸を業界に打ち出した先駆者として名高い人物でもあるが、幼いころから死を目のあたりにした体験は、”旅立ち”を送る職務に自分の運命を委ねるほどの深い使命感を与えている」
第1章「変わりつづける弔いの光景」では、「新しい死生観の創造の時代に」として、ここ数年、生と死が新たな様相を持って日本人の周囲を取り巻きはじめていると述べています。そして、その実例を次のように書いています。
「まず『終活』という言葉がブームになっている。これは人生の終焉にかけての準備活動という意味であるが、『終活講座』『終活カウンセラー』など、市民の動きと連動した、もっともホットな言葉の1つにもなっている」
この「終活」という言葉が初めて搭乗したのは2009年8月に刊行された「週刊朝日」誌上だとされています。同誌の記者が「就活」や「婚活」にヒントを得て、思いついた造語だそうです。その年には、納棺師を描いた映画「おくりびと」が第81回アメリカ・アカデミー賞の外国語映画賞を受賞しました。元号でいえば平成21年に当たりますが、この年は日本人の死生観を考える上でエポックメーキングな年であったと言えるでしょう。


しかし、その翌年、死生観の流れは急変します。著者は述べます。
「平成22年1月には『葬式は、要らない』(島田裕巳著/幻冬舎刊)が刊行される。発売直後から話題騒然となり、各メディアはこぞって葬儀に関する特集を組んだ。葬儀は必要であることを訴える本も矢継ぎ早に緊急出版され、この年ほど書店の棚が『葬儀』『葬式』関係で占められたことはないだろう」
ここで「葬儀は必要であることを訴える本も矢継ぎ早に緊急出版され」と書かれていますが、その第一弾こそ拙著『葬式は必要!』(双葉新書)でした。わたしは同書を竹内会長にお送りしたのですが、「よくぞ書いてくれました」とのお言葉を頂戴し、感激したものです。
さらに翌年、流れはまたもや急変します。東日本大震災が発生したのです。著者は、大震災による日本人の死生観の変化について、次のように述べます。
「東日本大震災によって、私たちは改めて”生とは何か””死とは何か”を問いかけることになった。日本人の多くが胸の内で手を合わせながら見知らぬ死者を送り、自分自身の生と死を重ね合わせたに違いない。『葬式は、要らない』というフレーズは安易に口にしなくなり、葬儀のかたちをもう一度考えはじめている。『終活』は葬儀のノウハウの会得から、いまこのときをより自分らしく生きていくための終焉の活動、という定義へと変わりつつあるのだ。いわば、新しい死生観の創出である」
続けて、著者は次のようにも書いています。
「しかし、この『東日本大震災』や『おくりびと』によって急に人々の意識が変化したと見るのは早計であろう。実はそれ以前から、私たちは自分なりの終わり方をどうするかという難問を抱えて、迷いつづけていたのである。迷いという『溜め』があったので、気づきが急速にうながされたのである」
この著者の意見には、わたしも基本的に賛成です。
さて、著者は「葬儀の原点と役割」という項で以下のように述べています。
「死の恐怖にどう打ち勝つかという切実な課題が、宗教や哲学、芸術を生み出す源になった。そして、『弔いの行為は人類の発祥とともにはじまった』といわれている。6万年前のネアンデルタール人の遺跡からは、遺体を花で飾った痕跡が発見されている。われわれホモ・サピエンスのことを『ホモ・フューネラル』(弔う人)と呼ぶ文化人類学者もいる」
これと同じ記述が同じ著者の『なぜ、お葬式は必要なのか』および『21世紀型互助会のすヽめ』にも登場しますが、これは明らかに著者の勘違いです。なぜなら、「ホモ・フューネラル」という言葉を唱えたのは何を隠そう小生だからです。
それは、Yahoo!「ホモ・フューネラル」およびGoogle「ホモ・フューネラル」で検索しても明白であり、そのように表現した文化人類学者は存在しません。
でも、「誰が言い出したか」などという問題はどうでもよく、「ホモ・フューネラル」という言葉が業界のみならず広く世間に普及してくれることを願っています。
本書を読んで勉強になったのは、竹内会長の葬儀についての哲学でした。著者は、次のように述べています。
「そもそも葬儀とはなんのためにあるのだろうか―。その素朴な疑問に対する答えは以下の言葉に収斂されているといえるだろう。
『ご葬儀というのは、人間社会のなかで何万年も続いてきた、終焉のときの大事な行事です。人生が終わるときのお祭りであり、人間の一生のなかで、もっとも敬うべきものと思います』と、語るのは竹内惠司である」
家族葬や直葬といった最近の葬儀トレンドに関しても、以下のように竹内会長の考えは非常に的確に問題点をとらえています。
「私がいちばん危惧しているのは、故人の気持ちを汲み取らないご葬儀が増えているということです。故人の気持ちより、自分たちの都合で決めているケースと少なからず出会います。その方の人生と生きてきた時代をみんなで振り返り、たたえ合うのが最大の供養と思えるのですが、その部分を家族の都合で断ち切ってしまうというのはつらい話ですね」
まったく同感ですが、竹内会長は次のようにも述べています。
「本来のご葬儀とはかけ離れたかたちが、これほどまでまかりとおっていることに、私は殺伐としたものを感じます。日本特有の支え合いの精神が薄くなっている証拠ではないでしょうか。何か大事なものが損なわれつつあると思うと、怖さも感じます。ですから、ブームとしての家族葬だけではなく、その背景にあるものを、もう一度見つめてほしいと思うのです」

第2章「葬送文化の変容・葬祭業が果たした役割」では、1冊の専門書が紹介されます。『現代日本の死と葬儀――葬祭業の展開と死生観の変容』(山田慎也/東京大学出版会刊)という本です。わたしは、著者の山田氏をよく知っています。なにしろ一緒に韓国や台湾に行った仲なのです。この山田氏と竹内会長も旧知の仲であり、葬祭業界の公募論文を通じて2人の関係が生まれたそうです。
山田氏は実際の葬儀のフィールドワークに重点を置き、『現代日本の死と葬儀』においては従来取り上げられることのほとんどなかった葬祭業者に着目し、その歴史と動向、儀礼の変遷などに関して、実に詳細な報告を行っています。
特に同書では、葬祭業者が人々に大きな影響を与えたことを教えてくれます。山田氏は「葬祭業者は地域の要望を敏感に感じながら業務を展開し、いまや単に物品の提供者だけでなく、知識の提供者としても位置づけられ、死生観の動態にも関与して、その役割は無視することができない」と述べているのです。
著者は、葬祭業が地域とともに歩んできた事実を忘れてはならないと訴え、「戦後のヒット商品、互助会と金襴祭壇」の項で次のように述べています。
「人々の価値観も大きく変わった。まず、登場したのは『互助会』というシステムである。これは終戦の混乱がまだおさまらない、昭和23年に誕生したといわれている。骨格は古くから伝わる『頼母子講』をベースにしたものだったが、冠婚葬祭の儀式を守るためという理念が新鮮であった。戦争によって途絶えた地域の相互扶助組織の活動を復活させようとの目的も有しており、人々の反応は早かった。昭和30年代に入ると全国的に広まり、庶民の暮らしと深くかかわっていく。いまも数百万人の会員が利用している、もっとも身近な”金融サービス”といえるだろう」
また、「知識の伝承者でもある葬祭業者」では、次のように書かれています。
「葬祭業に対して、むかしは人の死を商売にして不謹慎だと考える人もいたことは事実である。だが、時代の変化と人々のニーズを汲み取り、その要望に対応していった必要性が『葬儀の専門家』という職種を創出したといえる。そして現在、私たちが葬祭業者に深く頼っているのは、葬具の準備や段取りに加え、送ることに関しての知識である。
かつて、共同体の作業として行われていた時期、葬儀の過程は細部に至るまで人々の記憶として埋め込まれていた。息を引き取ったときには何を行い、出棺のときには何が必要か・・・・・・人々は知識とやり方を完璧なほど共有し、葬儀はスムーズに進行していくものだった。そうした継承が途絶えたいま、葬儀にあたって必要な知識と方法を教えてくれるのは葬祭業者なのである」
著者はさらに、「知識は1つの生き物である。伝えなければそこで息絶え、息絶えたものはもう二度とよみがえらない。葬祭業者は知識の伝承者として、その大事な役割を果たしているのである」とも述べています。この「知識の伝承者でもある葬祭業者」を社会的に見える化したシステムこそ、竹内会長が心血を注いだ「葬祭ディレクター技能審査制度」でした。
本書では、「葬儀を『暗』から『明』に変えた葬祭ディレクター技能審査制度」という項で、「平成8年、葬祭ディレクター技能審査制度が厚生労働省によって認定されたことは、日本の葬儀全体にとって画期的な出来事だった。これにより、葬儀の世界は大事な本質を守りながら、近代的な改革の遂行を期待できる体制になったのである」と述べられています。
技能審査制度の具体的な内容については、次のように説明しています。
「『葬祭ディレクター』とは、葬儀に関するあらゆる相談、運営に携わる仕事で、宗派ごとの葬儀作法から法律などの知識、書類手続き、さらに式場設営の技能にまですぐれていることを公的に認められたスタッフのことである。
厚生労働省の認定した技能審査制度にもとづく資格試験に合格した人たちだけが、金色か銀色のIDカードを胸につけることを許される。合格率は約6割というなかなかの難関だ」
葬祭業を知識化するという竹内会長のビジョンに早くから共鳴させていただいていたわたしは、わが社をあげてこの葬祭ディレクター技能審査制度に前向きに取り組んできました。現在、わが社には210人を超える1級葬祭ディレクターが在籍していますが、これは大きな会社の宝であると思っています。
葬祭ディレクター技能審査制度の誕生と育成に情熱を傾けてきた竹内会長は、葬儀についても確固たる哲学を持たれており、次のように語っておられます。
「人生とは、終わりを迎えたとき、初めてその全体の意味を見せるものです。『下駄をはくまで』という言葉がありますが、まさにそのときがこなければわからないことがたくさんある。そのトータルとしての人生を浮かび上がらせるのが、ご葬儀の場です。愚かしいと思えた故人の生きざまも、トータルで見ると、教えられることがたくさんあることに気づかされます。人間が存在する根源的な孤独や悲しさというものをそこに感じるからです。
1人のちっぽけな人間が、人生の普遍と結びつく大きな哲学に変わる場所、それがご葬儀の場であり、その場に立つたびに、ここは人生の教訓の場なのだという実感が込み上げますね」
本当に素晴らしい葬儀哲学であり、わたしは心から感銘を受けました。
平成23年8月に経済産業省から公表された報告書『安心と信頼のある「ライフエンディング・ステージ」の創出に向けて~新たな「絆」と生活に寄り添う「ライフエンディング産業」の構築~』の「まとめ」には以下のように書かれています。
「葬祭業は究極の隙間産業と指摘されることがあるが、発想を転換し、様々な困難が生じている遺族等をサポートするための究極のホスピタリティ産業であるべきであり、我が国の数多いサービス産業の中でも極めて高いサービスレベルが求められるべき産業であることを、我々の知見として共有することとしたい」
著者は、葬祭業が「究極のホスピタリティ産業」と国から期待を寄せられたことには大きな意義があると述べています。21世紀は「こころの時代」といわれて久しいですが、著者いわく「葬祭業はいまもっとも人々が必要とする『こころ』の部分に深く関与する産業になりつつあるということである」とも書いています。
第5章「明るい人生の卒業のために」の冒頭では、竹内会長が葬儀のことを「人生の卒業式」と呼んでいることが紹介されます。本書のタイトルの元にもなった言葉ですが、わたしも以前より「人生の卒業式」という言葉を使ってきました。
たとえば、「読売新聞」2010年10月4日のインタビュー記事のタイトルにもなっています。ですから、尊敬する大先輩が同じ表現をされていたことを知って、大変嬉しく思いました。言うまでもなく、「人生の卒業式」という言葉には、死は終わりではなく、新たなステップのはじまりという信条が込められています。
言葉の問題はとても重要です。竹内会長は、次のようにも語っています。
「いまはエンディングという言葉がブームのようになっていますが、私はこの言葉を使うこと自体、まだタブー視特有の暗さや重さから抜け出していないように思うのです。旅立ちとは、この世界から次の世界へと移っていくことです。次の世界というのは、『天国』『来世』『極楽浄土』など、いろいろな言葉で呼ばれていますが、ともかく死ねばすべてがエンドにはならないと私は思っているのです」
まったく同感です。たしかに「エンディング」という言葉を安易に使うべきではありませんね。だって、命には続きがあるのですから・・・・・。
 本書の主人公である竹内会長と
本書の主人公である竹内会長と
竹内会長は、わたしが心から尊敬する業界の大先輩です。20年ぐらい前、竹内会長とともにヨーロッパ視察に行き、会長からエンバーミング導入や葬祭ディレクター試験の構想などをお聞きした記憶があります。あの頃、竹内会長が描かれていたプランがすべて実現したわけで、本当に素晴らしいことです。昨年、竹内会長は協会から表彰を受けられました。永年、葬祭ディレクター試験のお世話をされたことに対しての表彰でした。かつて拝聴した竹内会長の講演の内容も大変勉強になりました。そして、また今回本書を読んで、葬儀についての竹内会長と考えが同じであることを知り、まことに光栄に思っています。
一般社団法人である全互協では、40周年記念事業として國學院大學に寄附講座を開設する計画を進めています。その講座では、学者の先生だけではなく、ぜひ竹内会長のような現場の視点を持った方に死生観と葬儀の意義について講義をしていただきたいと願っています。
竹内会長、このたびは素晴らしい本を送って下さり、ありがとうございました。
