- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.0909 歴史・文明・文化 『八大文明』 外村直彦著(朝日出版社)
2014.04.13
『八大文明』外村直彦著(朝日出版社)を読みました。
新聞の書籍広告で、本書の英訳版が発売されたことを知り、その内容に興味を抱きました。著者は昭和9年生まれ、東京大学文学部卒。現在は岡山大学名誉教授で、専攻は比較文明史です。主な著書に『日本文明の原構造』(朝日出版社)、『多元文明史観』(勁草書房)、『脱欧入近代』(渓水社)などがあります。
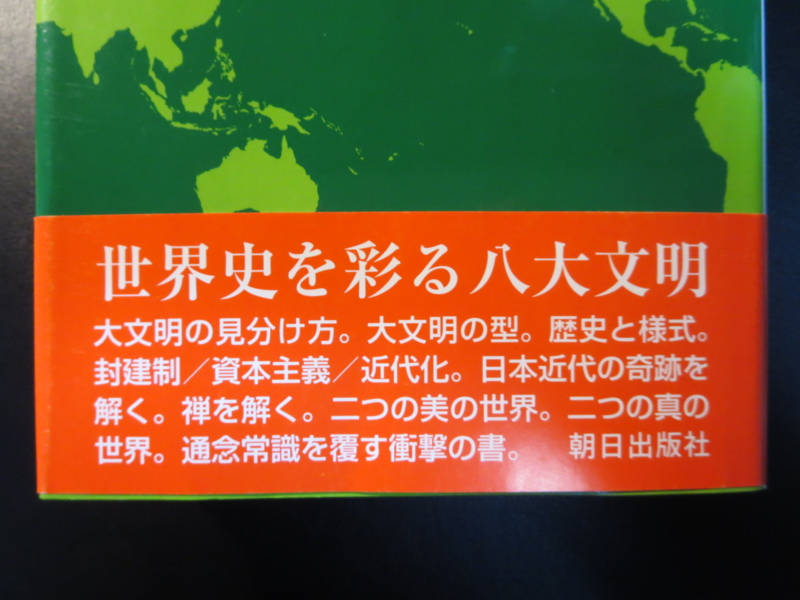 本書の帯
本書の帯
帯には「世界史を彩る八大文明」と大書され、続いて「大文明の見分け方。大文明の型。歴史と様式。封建制/資本主義/近代化。日本近代の奇跡を解く。禅を解く。二つの美の世界。二つの真の世界。通念常識を覆す衝撃の書」とあります。わたしは、本書のようなスケールの大きな主題の本が大好物なので、楽しみながら読みました。例えば与那国島の海底地形がもし遺跡と認定されたら、その時点で人類の文明史は大きく書き換えられます。そんなことを考えると、興味は尽きません。
本書の目次構成は、以下のようになっています。
「まえがき」
1.大文明をめぐる諸説
2.大文明の基準
3.八大文明
4.大文明の型
5.一般文明
6.三つの歴史事象について
7.文明の様式
8.大文明時代の終焉
「あとがき」
著者のいう「八大文明」とは、シュメール、エジプト、中国、インド、ギリシャ・ローマ、アンデス、日本、西欧の8つの文明です。「まえがき」で、著者は次のように述べています。
「八大文明といえば、サミュエル・ハンティントンが『文明の衝突』(1996年)のなかで8つの文明(=大文明)を扱っていることが思い浮かぶが、ハンティントンの専門は国際政治学であって、彼のいう『文明』も主として現代の政治的軍事的勢力を指していて、私を含めて従来の比較文明論者のいう過去の歴史体としての文明とは性質が別である。大文明の個々の名前もだいぶちがう」
また、比較文明史を専門とする著者は、次のように述べます。
「歴史には回顧史と鳥瞰史との2種類がある。この区別が先達にあるのかどうかわからず、私の発想としておくが、便利なので紹介しておくと、回顧史というのは自分のいる地点から過去をふりかえるという別名自分史のことで、西欧諸国の世界史教科書というのは、自分が今いるところからふりかえると、見えるのは西欧の景色ばかりであって、エジプトやインドなどははるか地平線の彼方に霞んで小さく見えるのだから、その通りに記述している自分史だということである。それに対して鳥瞰史というのは、自分のいるところを離れて中空から全体を等距離に眺め渡すという別名客観史のことである」
そして、「現代ほど諸地域と諸時代とに平等な世界史がつよく要請されているときはない」との認識に立つ著者は、「どの文化文明にも等距離に立つ近代という時代にふさわしく、過去の諸文化にひとしい距離に立つ鳥瞰史としての世界史を共有するようにしなくてはならない」と訴えるのでした。
第1章「大文明をめぐる諸説」の冒頭で、著者は述べています。
「文明の比較研究は、歴史を一元的に発展するのでなく、多数の独立の文明社会体が並列継起するという形でとらえる多元史観ないし多元文明史観にもとづいている。この研究にはおよそこれまで150年ほどの研究の集積がある」

文明についての研究は、さかのぼれば18世紀はじめのヴィーコに行き着きます。しかしながら、一応は19世紀半ばのラソーとリュッケルトから1つの流れが始まっているとされています。文明論について、著者は次のように述べます。
「文明論の現状は多岐にわたっていて、宗教、言語、政治、経済、情報社会、地域文化など、細分化の傾向にあるが、もともとはこの諸文明の共有する歴史構造の解明が主軸であり、本書もその本流に棹さすものである。本流の研究では、さまざまな呼称がつかわれるが、かならず大文明が前面にでてくる」

ここで、著者は従来の有名な文明論を簡単に紹介します。まず、比較文明研究には動態論(歴史の比較)と静態論(様式の比較)とがあります。オスヴァルト・シュペングラーが『西洋の没落―世界史の形態学大要』(1918年)のなかで主として扱ったのは、大文明(彼の言葉では高度文化)の静態論でした。著者は、シュペングラーの考えを以下のように説明します。
「彼は高度文化が植物と同じ自然有機体であることを強調する。高度文化は正確に区切られた地方の土の上に花咲き、植物のようにそれに結びつけられ、限られた寿命をもつ孤立し完結した存在である。
高度文化のそれぞれは、誕生した瞬間に空間に対して深い象徴的な、ほとんど神秘的な関係に立ち、それにもとづく世界感情、世界形式、生命の原象徴を付与され、以後の生涯を通して自己の内的可能性に1つの様式で一貫する発展的実現形態を与えつづける。ギリシャ・ローマの『身近にある限定された体躯』、西洋の『深さの衝動のある三次元の無限空間』、アラビアの『上方から微光のさしこむ空洞の世界』、エジプトの『つねに同一方向に向かう旅人の道』がその原象徴であり、それが各高度文化の科学、芸術、神話、都市、庭園、法律、経済などにいかに浸透しつつ、それぞれに独自の形態を与えているか、また、そのことによって、なかんずくギリシャ・ローマと西洋とが互いにいかに隔たった遠い異種の文化であるかが明らかにされる」

シュペングラーが文明の静態論を大きく扱ったのに対して、アーノルド・トインビーは動態論だけの研究に戻りました。トインビーには『歴史の研究』(1934―1954年)をはじめとする厖大な量の著作があります。その仕事の要になっているテーマは、「文明動態のメカニズムの解明」「文明の分類」「高等宗教の力説」の3点であるとして、著者は以下のようにトインビーの考えについて説明します。
「トインビーの文明史の分析は、発生や成長よりも、衰退と解体に重心がおかれ、大衆が指導者に対しておこなうミメシス(信従模倣)の撤回、離反、攻撃という社会階層間の分裂のほか、この時期にどの文明体にも認められる魂の分裂、つまり、対立する行動様式(放縦と自制)、対立する感情様式(漂流意識と罪悪意識)、対立する生活様式(タカ派における復古主義と未来主義、ハト派における超脱と変貌)、といった多様な社会心理の分析が、ギリシャ・ローマ史を主とする厖大な資料をつかってつぎつぎに展開される。『歴史の研究』という著作は、こうした挑戦と応戦という単純な型に収斂される歴史推移のメカニズムを溢れんばかりの具体例で肉づけした仕事である」

それから、日本の伊藤俊太郎氏の考えが以下のように紹介されます。
「伊東俊太郎(『比較文明』1985年、『比較文明と日本』1990年)、諸文明はそれぞれ孤立しつつ並列継起するとする従来の見方を不十分と考え、文明は独立でありながら、相互に影響を及ぼしあって進んでいるのだから、地球上のあらゆる文明が交流しつつ全体として進展する相を総観することが大切だとする。人類全体の発展を人類革命、農業革命、都市革命、精神革命、科学革命というタテ軸の5段階にわけ、それに加えて、相互に関連作用する多様な文化圏をヨコ軸に据えている」

そして、サミュエル・ハンティントンの考えがまとめられています。
「サミュエル・ハンティントン(『文明の衝突』1996年)は以上の文明論者とちがって、政治学者であり、現代国際政治の視角、とくに現代アメリカ合衆国の外交的軍事的戦略の見地から現代の諸文明を論じている。西欧、イスラム、インド、中国、日本、スラブ、中南米、アフリカという8つの文明がとりあげられている。従来の文明論で扱われてきたメソポタミアやエジプトが消え、アフリカや近代以後の中南米が新たに登場するのはそのためである」
第2章「大文明の基準」では、著者は「西欧の文明論者は、日本は借用依存の文明である、だから大した文明ではない、とよくいう。シュペングラー、トインビー、バグビー、クールボン、クローバーなど、みなそう言っている」として、以下のような発言を紹介します。
「日本は以前は中国文明に属していたが、いまはまた西洋文明に属している。言葉の本来の意味でいう日本文化なるものは存在しない」。「日本は他の文明の光を反射するだけの月光文明である」(シュペングラー)。
「日本は徳川時代を通じて、それまで中国ないし中国経由で輸入していた文化資本に寄食しつづけた。漢字、儒教、仏教がそれである」(トインビー)。
「日本は中国から書法や多くの芸術様式や仏教の中国的形態を借用してきたのだから、明らかに中国文明の周辺文明をなしている」(バグビー)。
「日本の指導者や官吏は儒教的な価値に影響されたが、彼らには儒学を理解するのはむずかしかったようだ。儒学は彼らの野蛮な文化と矛盾するいくつかの命題をもっていた」(クールボン)。
「日本は依存と独立の奇妙な混合文化である」(クローバー)。
これらの発言に対して、著者は次のように敢然と言い放つのでした。
「西欧文明の宗教は地中海東方からの借用である。文字はローマのラテン文字、さかのぼればフェニキアの文字の借用である。紙の起源は古代エジプトにある。羅針盤や火薬は中国由来である。印刷術は西欧よりも古く中国で発明されていた。磁器の製法も中国から学んだ。建築の技術や様式はアラビアやギリシャ・ローマに負うている。彫刻や演劇はギリシャ・ローマ文明に多くを負い、音楽はビザンツの影響をうけ、文学にはアラビア文学の要素があり、科学もアラビア科学の作用で育った」
この後は、大文明や一般文明が個別に延々と紹介されていきます。興味深かったのは第6章「三つの歴史事象について」です。これは「封建制」「資本主義」「近代化」をさすのですが、「近代化」の項で著者は次のように「近代史の奇跡」について述べています。
「日本は19世紀の後半の半ばからわずか30年のうちに、西欧が二、三百年かけて達成した成果をわがものにし、中国とロシアという巨大国と戦って勝利し、さらに第一次世界大戦に参戦して勝利し、第二次世界大戦では主役を演じ、敗れたけれども、たちまち蘇って、いまは世界トップの技術大国、経済大国という名声をほしいままにしている。この日本の急速な近代化は、世界のひとびとを驚嘆させた近代史の奇跡ともいうべき出来事であった」
著者はさらに、日本の近代化について以下のように述べます。
「この日本の急速な近代化の成功の謎はいまだに解けていない。成功の原因として、日本人は勤勉だ、機をみるに敏である、器用だ、ということがよくいわれるが、そうした性格があれば近代国家が出てくるとはとても考えられない。西洋人学者は江戸時代の遺産を指摘する。マックス・ウェーバーは、封建制のもつ契約性が西洋的な個人主義を育てたのではないか、といい、エドウィン・ライシャワーは、封建時代に法律的な権利や義務への強い観念、進取の気象に富む強力な企業精神、具体的な業績を求める倫理観などがヨーロッパ同様に育っていて、それが近代化を大きく助けたのだろう、という。またハーマン・カーンは、ペリー来航時の日本は近代社会としての多くの特徴を備えていたので、日本は急速にかつ容易に工業化した。ペリー以前にすでに強国であり、精緻な商業機構を保持し、識字率も高かった、といっている」
第8章「大文明時代の終焉」では、著者は次のように述べています。
「大文明は、初代のシュメールとエジプトにはじまり、第2代の中国、インド、ギリシャ・ローマを経て、第3代のアンデス、日本、西欧まで、あわせて6000年の歴史をもっている。これから先を考えると、第4代の誕生が気がかりである。新しい大文明はいったい生まれるのだろうか」
そして、本書の最後に、八大文明の中でも「日本文明」に期待する著者は、以下のような展望を述べるのでした。
「日本文明で興味をそそるのは近代日本である。大文明の観点からすると、19世紀末から20世紀前半にかけての日清戦争から日露戦争を経て大東亜戦争ないし太平洋戦争にいたる一連の戦争は、秀吉以来鬱積した世界帝国の夢の実現に向かって突進した自己拡大の動きとみることができる。それは、最終的に敗れたけれども、世界の諸民族に勇気と希望を与え、諸民族を幾世紀にわたる西欧の軛から解放する結果をもたらした。また20世紀後半には、技術力、経済力によって世界を席巻し、近代を欧米の専有から諸民族諸国家の共有へと転換する、というこれまた大仕事をやってのけた。それらの仕事は世界史に一大記念碑をうちたてたというにふさわしい大事業といえる。この文明の所属員はそれをなこよりの誇りとしてよいというのに、いま、過去のマイナスにのみ目を向けて自省自虐に耽り、閉塞の状態から脱出できずにいるようにみえる。早く元気を取りもどして、世界への新しい大きなプラス、今度はこれまで不足していた人文の領域での世界への貢献と願いたいが、に乗り出して諸民族の熱い期待に応えてほしいと思う」