- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.0956 宗教・精神世界 『現代仏教論』 末木文美士著(新潮新書)
2014.07.25
『現代仏教論』末木文美士著(新潮新書)を再読しました。
著者は1949年山梨県生まれ、東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了。東京大学教授を経て、現在は国際日本文化研究センター教授です。仏教学・日本思想史をもとに哲学・倫理学の構築を目指しており、わたしも多くの著書を読んでいます。



特に、『日本宗教史』(岩波新書)、『日本仏教史~思想史としてのアプローチ』(新潮文庫)、『仏典をよむ~死からはじまる仏教史』(新潮文庫)などは大変勉強になりました。日本の宗教学者は「儒教は宗教ではない」などと言う人が多いのですが、末木氏は宗教としての儒教の本質をしっかりとらえていて、非常に共感できました。
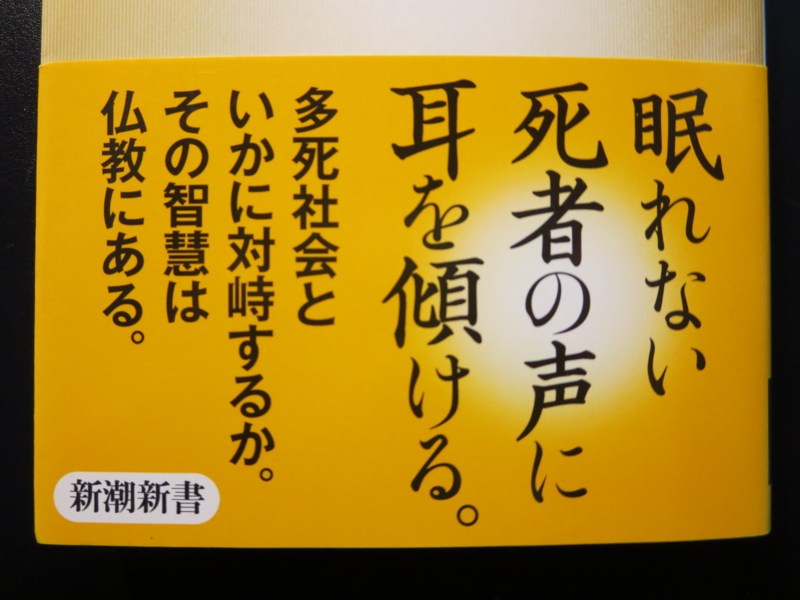 「眠れない死者の声に耳を傾ける。」と書かれた帯
「眠れない死者の声に耳を傾ける。」と書かれた帯
最近、「仏教連合会パネルディスカッション」に出演し、「これでいいのか日本仏教?」と感じる出来事があり、本書を再読した次第です。著者が、新聞を中心とするさまざまな媒体で発表してきたエッセイや論考をまとめた本です。。帯には「眠れない死者の声に耳を傾ける。」「多死社会といかに対峙するか。その智慧は仏教にある。」と書かれています。
またカバーの前そでには、以下のような内容紹介があります。
「震災、高齢化、自殺者増・・・・・・、多死社会の到来を目前にして、この国はなすすべもなく立ち竦んでいる。これまで問題を封印してきたツケが一気に回ってきたのだ。我々はいかに死者と対峙すべきか―。その智慧は仏教にある。ブッダの時代以来、死者と関わり続けてきた仏教が現代に果たすべき役割は小さくない。震災と仏教、死者供養の原点、業と輪廻、仏教離れの本当の理由など、死者の問題を中心に現代仏教を問い直す」
本書の目次構成は、以下のようになっています。
「はじめに」
第一章 震災から仏教を考える
1. 震災を考える
2. 震災をめぐる論争
3. 震災をめぐる思索
第二章 見えざるものへ―仏教から現代を問う
第三章 死者から考える
第四章 行動する仏教、思想する仏教
「はじめに」の冒頭で、著者は「サラの鍵」というフランス映画を紹介します。ナチス占領時代のユダヤ人狩りにまつわる物語です。10歳の少女サラは両親とともにアパートから連行されますが、咄嗟の起点で幼い弟を納戸に隠して鍵をかけます。その鍵を持って収容所を脱出したサラはアパートに駆けつけるのですが・・・・・・。「人間とは何か」といった問題を極限までに追求した名作です。わたしは本書で「サラの鍵」の存在を知り、早速、アマゾンで注文して観ました。魂が震えるような感動をおぼえました。この「サラの鍵」を紹介した後で、著者は次のように述べます。
「戦争が終わって、それどころかもうとっくに戦後も終わったと言われながら、なぜ戦争の死者が今も繰り返し繰り返し立ち顕れるのか。それは単に語り継ぐということでもなければ、集団記憶の継承ということとも違う。逃げられない必然として死者たちが呼ぶのだ。その声に気付かなければ、それはそれでよいのかもしれない。しかし、声に取り籠められたらどうしたらよいのか」
そう、本書において「死者」は重要なキーワードとなっています。著者は、さらに以下のように述べています。
「死者などと言い出したとき、ほとんど誰にも見向きされなかったばかりか、おかしなことを言う奴と気持悪がられた。しかし、ともかく死者の問題から見ていくと、これまで見えなかった世界の裏側がひどく明快に分かることがある。素直に見れば見えるものを、これまでわざわざ目隠しして問題を複雑化してこなかったか。死者に『永眠』などという言葉を平気で使うようになって、僕たちは大事な回路を自ら塞いでいなかったか」
第一章「震災から仏教を考える」は、東日本大震災をめぐる著者の見解が集められています。東日本大震災の直後、当時の東京都知事であった石原慎太郎氏が発した「天罰」発言が物議を醸し出しました。著者は、日本人の「我欲」が「天罰」を引き起こしたのであり、東北の被災地の人々はかわいそうだと述べました。猛烈な批判を浴びて、石原都知事は一応の謝罪をしました。本書の著者である末木氏は「震災は天罰」という議論の思想的な根拠について述べています。震災を単に「自然現象」としてとらえるのではなく、仏教教理学でいう「共業」という言葉を用いて人間の側にその責任の一端を求めています。
ここで、著者は宗教学者である島田裕巳氏の考えも紹介します。島田氏は「天罰や祟りとしてとらえる中世的な災害観を現代に持ち込むことは弊害も大きく、好ましいこととは言えない」として、「精神的な面での立ち直りということを考えれば、忘れられることも重要である」として、「忘れること」を評価しました。この島田氏の考え方について、著者は以下のように述べています。
「無常を歎いて、やがて自然のままに忘れていくということが評価されているようである。このように、自然のままに任せるというのは、本居宣長が死について、『此世に死する程悲しきことは候はぬ也。然るに儒や仏はさばかり至てかなしきことを、かなしむまじきことのやうに、色々と理窟をまをすは、真実の道にあらざること、明らけく候なり』(『鈴屋答問録』)と、理窟をつけずに悲しい時は悲しむだけだ、と説いているのと近いところがある。日本の多くの仏教者の説く災害無常論は、このような日本的な伝統の上に立っていると言えよう」
「忘れる」ということは、無常を受け入れることです。ミャンマー仏教に代表される東南アジアの仏教は「上座部仏教」あるいは「テーラワーダ」と呼ばれますが、「忘れる」ことをステップとして瞑想修行に励むことで知られます。仏教といっても決して1つではなく、それぞれの特徴があるとした上で、著者は「日本でもテーラワーダやチベット仏教は侮れない影響を持つようになっている。伝統仏教が自らを省みる努力を放棄して、ただ世間の後追いをするだけならば、早晩捨て去られるようになることは目に見えている」と述べています。
著者は、日本人の災害観を語る中で「他者」という視点を持ち出します。そして、著者は次のように述べています。
「了解できないけれども、関係せざるを得ないのが『他者』です。私たちお互い同士も、表面では相互理解をしているようでいながら、じつはいつも理解不可能な他者性を持っています。死者、つまり亡くなった方々とも、決して通常のコミュニケーションはできないにもかかわらず、私たちは何らかの形で関わらないわけにいきません。神仏も、もちろん私たちの理解の及ばない他者です。自然もまた、他者として考えなければいけないのではないでしょうか。自然は単なる機械的な対象として理解されるものではなく、他者として畏敬と親しみをもって遇されなければならないのではないでしょうか」
著者は日本仏教を考える上で、「脱魔術化」と「再魔術化」というキーワードを用いています。まず、「脱魔術化」について次のように述べます。
「脱魔術化というのは、有名な社会学者のマックス・ウェーバーが提示した近代化論のポイントです。中世までの世界は様々な魔術や呪術に支配されていた。それが近代になると非合理な魔術がなくなり、世俗内の合理的な活動が支配するようになるというのです。宗教的には、それはカトリックからプロテスタンティズムへの転換として捉えられます」
そして、「再魔術化」については次のように述べています。
「私が少し以前から提案している『顕』と『冥』の世界観は、ある意味では、まさしく脱魔術化の後の再魔術化の1つの提案と言うこともできます。実際すでにこのような見方は不可欠になっています。私は近年、戦争の死者の問題を考えていますが、戦争の死者は政治に利用されるだけで、本当は真向われてきませんでした。『安らかに眠って下さい 過ちは繰返しませぬから』という広島の原爆死没者慰霊碑の文句のように、死者を眠らせ、遠くに置いて、生者だけでやっていこうとしてきました。その結果、本当に死者が安らかに眠られる状況か否かは、誰の目にも明らかでしょう。
震災による大量死も同じです。死者と本当に関わり、死者とともに生きることができなければなりません。死者の問題はすでに合理的な世俗主義の立場では解決できません。それは『冥』の領域に属します。しかも、それは個人的なレベルで済む問題ではなく、公共的なレベルで問題にされなければなりません」
この「再魔術化」という視点は、非常に共感できました。
著者いわく、日本の仏教は、テーラワーダやチベット仏教が保っている総合的な理論を失ってしまいました。それは、なぜでしょうか。著者は述べます。
「近代の日本は、天皇を頂点とする家父長体制を築き、家父長の支配による家の存続に個人以上の価値を置きました。そこで、家のシンボルとしての祖先祭祀が重要になるのですが、それを引き受けたのが仏教の死者儀礼です。仏教は死者儀礼を扱うことで、近代社会の基礎部分を支え、それによって仏教教団も大きな勢力として存続できたのです。それはしばしば葬式仏教と揶揄されるのですが、その葬式仏教こそが、実は近代社会の中での仏教の存在価値だったのです」
このように、著者は葬式仏教を評価しています。しかしながら、続いて著者は次のように述べます。
「ところがおかしなことに、近代の仏教教学はこのように重要な葬式仏教に対して口を閉ざして語らないのです。著名な仏教学者の方に葬式仏教について尋ねたら、それは方便としてやっているのであって、仏教の本道ではない、と切り捨てられました。ここでも、教理と現実の隔絶が生じています。日本の仏教は、自分たちが現実にしていることに目をつぶり、その理論の及ぶ範囲をきわめて狭く限ることになりました。それによって確かに脱魔術化を推し進め、近代化の鎧を身につけたかのように見えますが、じつはテーラワーダやチベット仏教のような総合性を失うことになって、その理論はきわめてやせ細るとともに、批判力もない、無力なものになってしまいました。これでよいのでしょうか」
これでよいとはずがありません。著者の嘆きは仏教連合会のパネルディスカッションでのわたしの失望とまったく同じです。今日の日本仏教は理論を再構築し、震災やボランティア、葬式仏教などまで含む総合的な世界観を作ることができるでしょうか。著者は述べます。
「近代日本の仏教は宗派の違いにばかりこだわり、親鸞や道元、日蓮のような各宗の宗祖を絶対視する宗祖主義に立ってきました。しかし、宗祖と言われるような人たちは広くインド・中国の仏典を学び、それと格闘しながら自らの思想を確立したのです。日本仏教の理論を再構築するためには、もう一度日本という枠を外して、インドにまで遡ってみることが必要です」



このあたりの議論は、パネルディスカッション「仏教文化交流シンポジウム」でも語りました。また、その内容は『ミャンマー仏教を語る~世界平和パゴダの可能性』(現代書林)に収録されています。また、『慈を求めて』(三五館)でもミャンマー仏教と日本仏教について比較しました。さらに、わたしはミャンマー仏教をはじめとするテーラワーダが根本経典とする「慈経」の自由訳に挑み、『慈経 自由訳』(三五館)を上梓しました。
テーラワーダが「慈経」に代表される原始仏教経典をよりどころとし、チベット仏教が後期大乗仏教の理論と実践をもとにしているのに対して、東アジアの仏教は『法華経』『無量寿経』などの初期大乗仏典をよりどころにしています。著者は、その源泉となる初期大乗仏教の思想をもう一度読み直すことが必要であるとして、次のように述べます。
「まず言えることは、初期大乗仏教の原点には菩薩という考え方があるということです。私は、菩薩という観念の基礎は、他者との関係ということだと解しています。菩薩は自利・利他と言いますが、利他が成り立つためには他者との関係ということがまずなければなりません。他者と関わるということこそ、大乗仏教の根底に埋め込まれたメッセージです。仏というのは、まさしく他者の代表であり、他者そのものです。私たちが仏と関わらざるを得ないということは、私たちが他者と関わらざるを得ないということです」
さらに「他者との関わり」について、著者は以下のように述べています。
「他者との関わりは、関わらざるを得ないという絶対的な結びつきと同時に、他者は決定的に離れているという面を持ちます。その点で、死者はもっとも他者的な他者であり、その距離を時間化すれば、そこに前世や来世を考えなければなりません。『無量寿経』が来世で阿弥陀仏に到達すると説くのは、まさしくその故です。『法華経』では、釈迦仏と私たちは無限の過去から関わり、そして無限の未来にまで関わっていくと説いています。輪廻というのはそういうことでしょう。そして、無限の過去から仏との関わりを逃れられないできたということこそ、私たちの業なのではないでしょうか。業や輪廻も、このように捉えれば、私たちにとってきわめて切実なことになります」
では、初期大乗仏教の理想は日本仏教には生きていないのでしょうか。そうではありません。著者は、次のように述べています。
「親鸞の思想の根底には還相廻向ということがありますが、これは、死者が阿弥陀仏と一体になってこの世界に戻り、人々を救うという考え方です。このように、親鸞の根底には死者論があります。死者の力を受けて、はじめて私たちのこの世界での活動が可能となります。それが他力ということです。それによって社会的な活動も理論づけが可能となります」
この「還相廻向」という考え方は非常に重要であると思います。



第二章「見えざるものへ―仏教から現代を問う」では、現代日本人の死生観の変化が取り上げられます。著者は、「千の風になって」がミリオンセラーになり、映画「おくりびと」がアカデミー賞を受賞し、『悼む人』が直木賞を受賞してベストセラーになった理由について推測しています。
「1つには、単純だが少子高齢化が急速に進み、死を身近に考えざるを得ない高齢者が増えたということがあろう。とりわけ団魂の世代が還暦に至り、定年を迎えるようになって、自身の老後を考えなければならなくなった。その上、その前には多くの親の介護に直面して、死の問題が他人事でなくなってきた。そのような状況の中で、これまで死者を一手に引き受けてきた仏教がもはや十分に機能しなくなってきた。葬式仏教と揶揄されながらも、仏教は地域に根ざし、葬儀を取り仕切り、墓を管理することで人々の間に定着していた。それが、人口の都市集中や少子化による墓の継承者の消失などによって、檀家制度が崩壊の危機に瀕することになった。また、女性が家から自立するようになって、従来の家墓のあり方が否定されることになった。葬式も葬儀社が取り仕切り、僧侶は単なる脇役と化してしまった。新しい葬儀と墓の形態が模索されているのが、今の状況である」
「死者論としての仏教」という「読売新聞」の連載エッセイが興味深かったのですが、そこで著者は次のように書いています。
「『死からはじまる』ということであれば、キリスト教のほうがはっきりしている。キリスト教は、人間イエスの教えからではなく、十字架における死と救世主キリストとしての復活からはじまった。かつてしばらくドイツに滞在していた時、至るところで血まみれの十字架のキリスト像に出会った。それらは生々しくリアルに死の苦悶を伝えていて、ごく普通の日本人である僕には、あまりにどぎつ過ぎるように思われた。しかし、同時に不思議に吸い寄せられるような恍惚感を覚えて、教会や美術館を訪ねて回った。静謐な教会と残酷な十字架像の対照が鮮烈だった。
これでもか、これでもかと、死体のリアルさを競い合って描き、彫刻にしてきたところには、合理的な理屈で捉えきれない何かがあって、人間の深層の情動を呼び起こすのだろう。美は醜を含み、崇高は卑猥を取り込むところに成り立つ。もっとも卑しい、虫けらのような罪人としての死が人類の栄光とされる逆説の中に、ヨーロッパの二千年を支えてきた活力の秘密がある」
続いて、著者は「仏教における死の問題」について次のように書きます。
「生老病は結局のところ死に帰着するのであり、死こそ最大の問題であって。今日、少子化という『生』の問題とともに、老病死の問題はあらゆる面で突出してきた。何のことはない、ブッダ時代から二千数百年間、人類は一歩も進歩がなかったのではないか、という深刻な事態に慄然とする。
仏教における死の問題はそれだけでない。あまりに当たり前に死んだブッダであったが、死者は死後にこそ巨大化する。死せるブッダは、死者となることで、その欠如がより大きな問いとして投げかけられる。死者といかに関わることができるのか、それが大乗仏教を生み出した最大の動機ではなかったか。それが僕の仮説である」
さらに「死の記憶、生者の傲慢」として、著者は以下のように書いています。
「過去が客観的な事実とも異なり、主観的な記憶とも異なるとしたら、過去とは何であろうか。例えば、山口県下関市の赤間神宮から壇ノ浦の近くまで歩いてみればよい。そこには数百年昔の平家滅亡の修羅の様が息づくように立ち現われ、僕たちを怯えさせ、立ち竦ませる。過去は主観的な記憶よりもはるかに深いところにあり、現在を呪縛し、僕たちを安閑とさせてくれない。京都は長い歴史の中で、至るところに血なまぐさい事件や戦争の痕が印されている。四条近くの南蛮寺跡にはキリスト教文化資料館があるが、そこでは秀吉時代の26聖人の殉教が今も生々しく語られている。そもそも、クリスマスにせよ、復活祭にせよ、二千年も過去の出来事が、今のこととして取り戻され、祝福されるのだ。そうとすれば、百年も経たない過去の戦争が、僕たちに重くのしかかってきたとしても不思議なことではない。死者は決して僕たちを見逃してくれない」
「死後をオープンに語る」というエッセイでは、次のように述べています。
「ブッダは死後のことは解答不能の問題だとして、それについて思い煩ってはならないと誡めた。哲学者のカントもまた、死後の霊魂の存在は純粋理性では答えの出ないことを明らかにした。それならば、死後のことなど考えなくて済むかというと、そうはいかない。仏教の中でも様々な死後の世界が語られるようになる。死後の問題は単に知的な関心の対象というだけではない。自分自身の死や身近な人の死はもちろん切実であるが、死に直面した人のケアに当たっても大事な問題となる」
「近世仏教の『実力』」というエッセイでは、次のように述べています。
「実際には近世でも、儒教は武士などの上層階級でこそ信奉されたものの、一般にはそのままの形では普及しなかった。儒教的な道徳も、仏教などを通して庶民に広まった。また、武士でも基本的には葬儀は仏教式で行い、仏教寺院に墓地があるのが普通であった。近世には寺院と檀家の関係が確立し、日本中の寺院の総数は数万に及ぶようになった。そうとすれば、近世における仏教の力は侮れず、むしろ仏教全盛の時代と言ってもよいはずだ」
「全日本仏教会の歩みと展望」2009年10月号に掲載された「仏教と仏教離れ」という論考にも考えさせられました。著者は述べています。
「『千の風になって』も『おくりびと』も『悼む人』も、宗教とすれすれの問題を扱いながら、既成の宗教に取り込まれていないという点が共通している。今日、既成宗教、とりわけ仏教に対する風当たりは強い。京都に移って近所の歯医者さんに通うことになった。とてもよい先生だが、僕が仏教の研究をしていると知った途端、治療しながらひとしきり、いまの仏教の悪口を激烈に語った」
このような現状を見ても、現代日本仏教が制度疲労を起こしていることがつくづく実感されます。そして、その制度疲労の「制度」とは檀家制度が中心です。この檀家制度について、著者は以下のように述べています。
「今日の檀家制度に乗った仏教は、近世の寺檀制度がもとにはなっているが、それが明治になって再編されたものだ。明治になって仏教は、それまで幕府御用達の国家宗教から外され、一民間宗教になったが、じつはきわめて巧みに時代に対応して生き残った。それは、家父長的天皇国家を支える裏方に回るということであった。近代の家父長的国家体制は嫡子相続で、長男が家督を相続するが、そのシンボルとなるのが先祖の位牌であり、墓であった。その位牌も墓も基本的には仏教式で寺院が管理するのだから、近代家父長制は仏教によって支えられていたと言って過言でない。一見、近代化に遅れた前近代の遺物のようにみられる葬式仏教が、じつは日本の近代の基盤を作っていたのだ」
本書の最後には、著者が2010年10月3日に四天王寺で講演した内容が紹介されています。その講演で著者は次のように語りました。
「私は死の問題を身近に感じるところがあり、若いころから死とは何かと漠然と考えていました。ただ、それを突きつめると、死は経験したことがないので分からない。経験のしようのないことは考えても分かるわけがないというところに行き着きます。でも、その時、生きている人間は死んだ人と何らかの関係をずっと持っているのではないか、ということにふと気づいたのです。お葬式や法事の場を通してそう感じますし、あの人はこう言ってくれたなどと、死者が自分を導いてくれることもある。また、親しい身内が亡くなったときはショックで心身ともに変調をきたすような状態にもなる。そのように亡くなった人は生きている人に対して強い力を持って働きかけてくるので、亡くなった人との関係を抜きにして人は生きられないのではないか。そうならば、死者とどうかかわるかは、ものすごく大事な問題だと考えるようになりました」
著者いわく、これまでにそういう問題を提起していた哲学者もいました。しかしながら、ほとんど解明することはできませんでした。今一度、そういう問題を展開して、自分の死の問題から死者の問題へと考えのポイントを移してみるのもいいのではないかと気づいたという著者は、次のように述べます。
「今、お葬式がどんどん簡略化され、葬式はいらないという考え方もある。しかし、葬式は亡くなった人との関係の持ち方から決まってくるものであり、死者とどうかかわっていくかが重要です。それをきちんと考えるには、死者をどう位置づけるか考えなくてはなりません」
この言葉に、わたしは宗教学者としての著者の考え方が凝縮されていると感じました。一連の著者の本を読むと、日本仏教および葬儀の「初期設定」と「アップデート」の両方についての豊かなヒントが得られます。ぜひ一度、著者に直接お会いして、いろいろ教えていただきたいと願っています。