- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2014.11.14
『60歳からの人生を楽しむ技術』渡部昇一著(祥伝社黄金文庫)を読みました。
本書は、2007年に刊行された『95歳へ!』(飛鳥新社)を加筆・修正して改題した本です。60歳から95歳までの35年間を設計する、中高年のための幸福論です。著者は、何人もの矍鑠たる高齢者と対談し、ノウハウを嚼してまとめたエッセンスを披露してくれます。
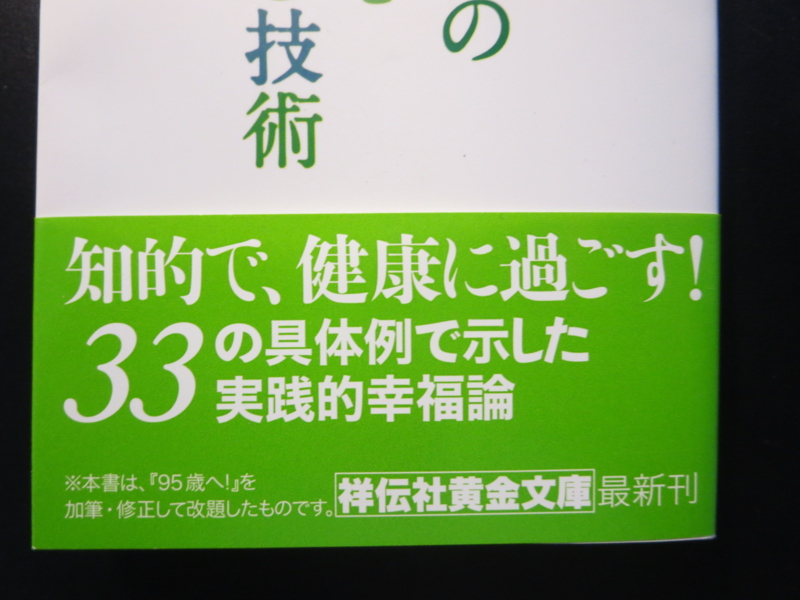 知的で、健康に過ごす!
知的で、健康に過ごす!
本書の帯には「知的で、健康に過ごす! 33の具体例で示した実践的幸福論」と書かれています。この本を執筆したとき、著者は81歳でした。本書には「記憶こそが人生そのもの」あるいは「記憶維持には、脳を使い続けるしかない」といった「ごもっとも!」と言うしかない至高のアドバイスがずらりと並んでいます。
「文庫版へのまえがき」の冒頭には、以下のように書かれています。
「祖母と一緒に育ったためか、子どもの頃から老人が好きでした。小学校低学年の時、若い女性の先生が担任の時は学校が嫌だったけれども、その先生が出産のため休職し、代わりにお婆さんの先生が担任になった時は学校が楽しみでした」
また、大学に入学してからのことも以下のように書かれています。
「大学に入ってからも、老先生たちに特に親しみを感じました。自分が大学で教えるようになっても、自分よりずっと年上の先生方の話を伺うのが好きでした」
著者は、「その老人好きの私自身が老人になって、老齢について語ったのが本書です」と述べています。
本書には33のコラム風の文章が並んでいますが、その中の「95歳まで生きよう」には、2006年に逝去した漢字学者の白川静氏が92歳のときに著者と対談をしたときの様子が次のように紹介されています。
「5時間の対談中、休憩もとらず、大半を先生が語られました。若輩の私が聞き手、白川先生が話し手という形になったからです。対談を終えて日本料亭に向かう時もスタスタと、とても90代とは思えない足取り。出てきた料理は次々にきれいに召し上がりました。そして、デザートの小さな羊羹を半分だけ残されました。不思議に思って『先生、それはどういう意味なんですか?』と伺ってみると『ちょっと、糖尿の気があってね』。私も92歳になって、そう言ってみたいものだと思いました。
亡くなられた数日後の『産経新聞』の『産経抄』(2006年11月4日)によると、白川先生は、死の直前まで講演をされ、資料も見ずに古典を紹介されていたそうです。床に伏し、苦しんだ期間、知的活動ができなくなった期間はほとんどなかったと言っていいでしょう」
著者は「95歳まで生きよう」で、次のように「死」について述べます。
「死は万人に訪れるので、その恐怖、苦悩が早いか遅いかだけの違い―と思ってはいけません。私の見るところ、90歳を超えて亡くなられる方はあまり苦しまない。ほとんどが眠るがごとくです。『死ぬ』というより、もっといい世界に遷るという感じで、穏やかに亡くなられているのです」
「個人差はあるでしょうが、80歳くらいだとまだ苦しむ人がいるようです。したがって、私はできることなら95歳まで生き、肉体的にも精神的にも苦痛を感じることがなくなってから、あの世へ遷りたいと思っています」
また、さらに「死」について次のように述べます。
「徳川後期の儒学者で、門人3000人と言われた佐藤一斎は『言志耋録』の最後のほうに『年をとって死ぬ人はほとんど死を恐れない聖者のごときものである』という趣旨のことを書いています。
『凡そ生気有る者は死を畏る。生気全く尽くれば、この念もまた尽く。故に極老の人は一死睡るが如し』
死がこわくも苦しくもなければ、宗教にすがったり、座禅を組んだり、修養したりという必要もありません。宗教心のある方は静かに気張らないで自分の宗教を示すように逝くでしょうし、無神論者でも静かに大地に戻る、土から生まれて土に戻るという気持ちになるでしょう」
「人は何を幸福と感じるか」では、次のように述べています。
「自分の能力に合った仕事が見つからないという若い人がよくいますが、多くの場合、単なる怠惰で仕事に自分を合わせようとしていないだけ、あるいは自分の能力を過大評価しているだけです。
私は、高校くらいまでに、自分の嫌いなものがはっきりわかっていれば、あとはだいたい合わせられると思っています。その意味で、私が幸運だったのは学徒勤労動員があったことです。田植え、草取り、山の木の伐採、堤防工事、学校工場造りなどをしました。その時、私は『オレは絶対にこんなことやりたくない』と思ったのです。自分に合わない仕事がはっきりわかりました。それがわかると、選択肢が絞られてくるわけです」
「高齢でも記憶力は強化できる」の冒頭では、『老い』を実感し、何か新しい挑戦をしなければ、と思った私は、ラテン語の暗記に取り組むことにしました」とありますが、さらに以下のように述べています。
「暗記は脳がかなりの酸素を使うような気がします。ラテン語の暗記を始めた頃、タクシーの中でしきりに欠伸が出ました。ところが、今、何かの暗記に取り組んでも、ほとんど出なくなりました。これは、暗記によって脳細胞が鍛えられた、あるいは脳細胞の酸素保持量が増えたからではないかと思います。
いずれにせよ、私は『記憶力は筋力と同じで、鍛えれば強くなる』ことを体験しました。しかも60代半ばでも、です」
「人生は、たくさん覚えているほど豊かになる」の冒頭、著者は次のように述べます。
「戦後教育の大きな間違いの1つは暗記を軽視したことでした。『独創性』とか『個性』といった耳障りのいいキャッチ・フレーズに惑わされて、暗記することの重要性を忘れてしまったのです。
『独創性』や『個性』は蓄積された記憶から生まれるもので、記憶の絶対量が少ないと何も生まれてきません。数学者として世界的に有名だった文化勲章受章者の岡潔先生は『とにかく10代の頃は反吐が出るほど暗記したほうがいい』とおっしゃっていました。なぜ、記憶は多いほうがいいかと言えば、それによって『ものの感じ方』が変わってくるからです」
「記憶」に関して、続けて著者は次のように述べます。
「情緒や感性というものは、何らかの記憶がないと生まれてきません。ユダヤ人は総体として知的水準が高いですが、その原因は子どもの頃にタルムード(ユダヤ教の口伝の集大成)を徹底的に暗唱させられるからだと言われています。ものを覚えること、暗記することは非常に重要なのです。
暗記しているということは、そのことを意識しないでいる時でも、微妙に脳細胞に働きかけ続けているのではないか、と私は思っています。数学者でも、定理の多くを容易に暗記し、直観の一部ぐらいになっていなければ、独創的な研究には入れないと聞いています」
さらに「記憶力」について、著者は次のように述べます。
「現代ヨーロッパ人の知力が、つまりゲルマン人と言われた系統の諸民族の知力が最初に開花した感じがするのは、ラテン文法を暗記することから始まった中世の学校制度のおかげとも思えますし、次いで宗教改革で『聖書』を庶民も読み、それを暗記する習慣が普及したことが、近世ヨーロッパの誕生と脳内的に関係あったと考えてもよいのではないでしょうか。
子どもの知力を伸ばしたいならば、何か暗記させよ。『般若心経』でも、『百人一首』でも『寿限無』でも。初老以降の人間が知力を維持したいと思うなら、何か暗記せよ。英語の諺でも、漢文の名文句でも、唱歌や流行歌の歌詞でも―と言いたい」
「記憶こそが人生そのもの」の冒頭では、「記憶とは何なのだろうとよくよく考えると、その人のアイデンティティそのものであるという結論に至ります」と述べ、さらには以下のように書いています。
「記憶こそが、自分自身というものであり、今の自分の行動を規定しているもっとも大きな要因だと気付いてハッとします。たとえば、私の妻と他の女性を画然と区別するのは、この51年間、2人の記憶が共通していることです。同じ事柄に対する2人の見方や印象や解釈が異なることはおおいにあっても、2人に起こった毎日毎日の小事件については記憶を共有しているのです。夫婦というものが特別な関係なのはセックスだけではありません。老夫婦ともなればセックスに関係なくても、数十年の記憶を共有しているのです」
この後、著者は「遺留分放棄」について以下のように説明します。
「私の遺産をどうするかと考えた時、その対象は妻子になります。そして、それは、私と共有した記憶の量によって決まっていることに気付きます。おそらく私は全財産を妻に残すべく、子どもたちに遺留分の放棄を求めるでしょう。これは、私と共有する記憶の量がずば抜けて多いのが妻だからです。もし妻が私より先に死んだら、私は子どもたち3人がほぼ均等に遺産を分けるようにという遺言状を書くと思います」
この「遺留分放棄」については、拙著『決定版 終活入門』(実業之日本社)でも紹介させていただきました。
著者は「記憶」に関して、以下のように喝破します。
「突き詰めて言えば、人生とは記憶です。もしすべての記憶が失われたら、肉体はその人であっても、人格はその人ではなくなります。晩年を生きるにあたって、もっとも大切なことは記憶力を鍛え、多くの記憶を持ち続けることではないでしょうか」
わたしも、著者のこの考え方に全面的に賛成です。
「記憶維持には、脳を使い続けるしかない」では、次のように述べます。
「記憶の働きというのは本当に不思議です。『人は二度死ぬ』と言います。一度目は息を引き取った時、二度目はその人のことを記憶する者がいなくなった時だ、と―。
してみると、私が記憶している限り、父も母も二度目の死は迎えていないことになります。私の記憶の中で2人はちゃんと生きているのです」
さらに著者は、続けて次のようにも述べています。
「細胞という水を流していた川に相当する記憶が失われる。川がなくなって、行き場を失った水だけが淀んでいるようなものです。
これは長寿者に起こり得るもっとも大きな悲劇でしょう。『ボケてしまえば何もわからないから本人は幸せ』と言う人もいますが、記憶を失った自分は自分ではありません。自分でなくなった自分の肉体が、生きて徘徊する姿を想像して、怖ろしくない人はいないでしょう。それに家族も大変です」
「老いて学べば即ち死して朽ちず」の冒頭、次のようにあります。
「江戸時代後期の儒学者・佐藤一斎の著書『言志晩録』に『少にして学べば則ち壮にして為すあり。壮にして学べば則ち老いて衰えず。老いて学べば則ち死して朽ちず』という言葉があります」
問題は、「老いて学べば則ち死して朽ちず」です。著者は、このことについて、次のように述べます。
「老いて学んだ成果が著作や何らかの作品という形に結晶し、それが後世の人の評価するところとなれば『死して朽ちず』と言えるでしょう。また後世まで残る会社を作る人もあるでしょうし、発明・発見する人も『死して朽ちず』と言えましょう」
ありがたいことに、本書のエッセンスは、以下のようにまとめられています。
まとめれば ― 25のアドバイス
[基本的心がまえ]
◎晩年は「賢明さ」より「楽しさ」が大切
◎時間はたっぷりあるので焦らなくていい
◎文科系の世界に生きがいを見つけるのが賢明
◎「自分もああなりたい」という存在を思い出そう
◎平凡な人の平凡な教訓が役に立つ
[自分のテーマを発見するには]
◎自分の能力が生かされることは何か
◎若い頃にやり残したことは何か
◎何をしている時が楽しいだろうか
◎願望は紙に書いて貼っておこう
◎実現の手段は考えなくていい
[不安から脱出するには]
◎心配性の人は水泳を習いなさい
◎15歳に戻ったつもりでスタートしよう
◎本当のあなたとは「あなたの意志」のことです
◎自分の自由にならないことは諦めよう
◎将来のことを考えて今日を生きなさい
◎恍惚となる時間を増やそう
[さあ、トレーニングを!]
◎カラオケで記憶力を鍛えなさい
◎毎日、音読する習慣を付けよう
◎脳の活性化のために舌の運動をしよう
◎「職務」を作って忙しく生きよう
◎「歩行禅」で脳と足腰を同時に鍛えよう
◎腹を減らして身体を刺激しよう
◎真向法で身体を柔らかくしよう
◎毎日、30分昼寝をしよう
◎寝室を分けて1人で寝よう
「あとがき」の冒頭で、著者は次のように書いています。
「95歳まで生きれば、たいていの人は苦しまずに死ぬ。生への執着、未練もなくなるし、死への恐怖もなくなる。正に聖人、高僧の心境で、そうなればお経もバイブルもコーランも不要になる。こんな観察にもとづいて、60で定年になった人も、95歳をめざしてもう35年頑張ろう、ということを主張したかった」
また、以下のようにも述べています。
「若い時にお寺に入ったり、修道院に入れば、精神的・肉体的煩悩が多く、修行も辛いであろう。正にそれが功徳にもなるのであろう。しかし凡人が俗世で生きていくことにも、寺や修道院とは違った苦労が多い。お寺の中と世間の中と、どっちの苦労が多いかわからないと昔の日本人は考えた。だから俗世間で苦労しながら生計を立て、子どもを育てたような人が死んだ時、戒名を与えて、お寺の中の修行者だった人なみに待遇して、あの世に送ってやるということを発明した(戒名の起源はこのようなもので、日本独特の風習だという)」
この「戒名」についての考え方は目からウロコでした。「戒名」というと、某宗教学者のようにやたらと批判するばかりの人が多いですが、さすがに著者は頭が柔らかく、「現代の賢人」と呼ばれるだけのことはあります。このように何事も陽にとらえる発想や生き方がいつまでもお元気な秘訣なのかもしれませんね。
「あとがき」の最後には、著者は次のように断言します。
「老人は肉体的には成長できない。むしろ身長などは縮まる。しかし祈りや、黙想や、読経などにより、精神的には最後まで成長できるのである」
わたしは著者と対談させていただき、その内容は『永遠の知的生活』(実業之日本社)として間もなく出版されますが、同書のタイトルにもなっている「永遠の知的生活」の真髄がここには語られています。
