- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.1025 評伝・自伝 『裏山の奇人』 小松貴著(東海大学出版部)
2014.12.26
『裏山の奇人』小松貴著(東海大学出版部)を読みました。
「野にたゆたう博物学」というサブタイトルがついています。この本、いま読書界というか書評界で絶賛されている本です。大学の出版部の刊行物で「フィールドの生物学」というシリーズの14冊目です。しかも税込で2160円もするのですが、けっこう売れています。
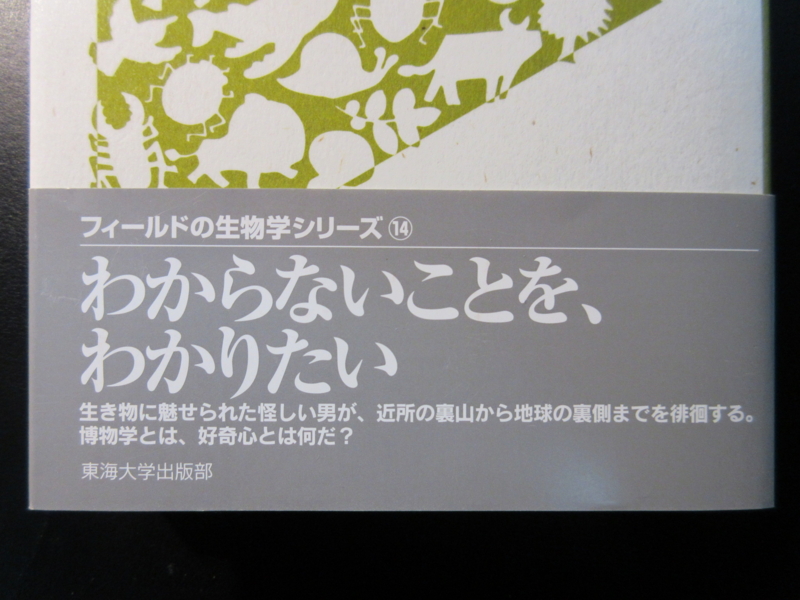 「わかりたいことを、わかりたい」と書かれた帯
「わかりたいことを、わかりたい」と書かれた帯
著者は1982年生まれで、新修大学大学院総合工学系研究科山岳地域環境科学専攻博士課程修了の博士(理学)です。日本学術振興会特別研究員DC1.信州大学理学部科研研究員を経て、2014年より九州大学熱帯農学研究センターにて日本学術振興会特別研究員PDになっています。本書の「著者紹介」よりの抜粋ですが、なんだか堅苦しいプロフィールですね。でも、著者はとにかく生き物が好きで好きでたまらない人なのです。
本書の帯には、「わからないことを、わかりたい」と大書され、続いて「生き物に魅せられた怪しい男が、近所の裏山から地球の裏側までを徘徊する。博物学とは、好奇心とは何だ?」と書かれています。
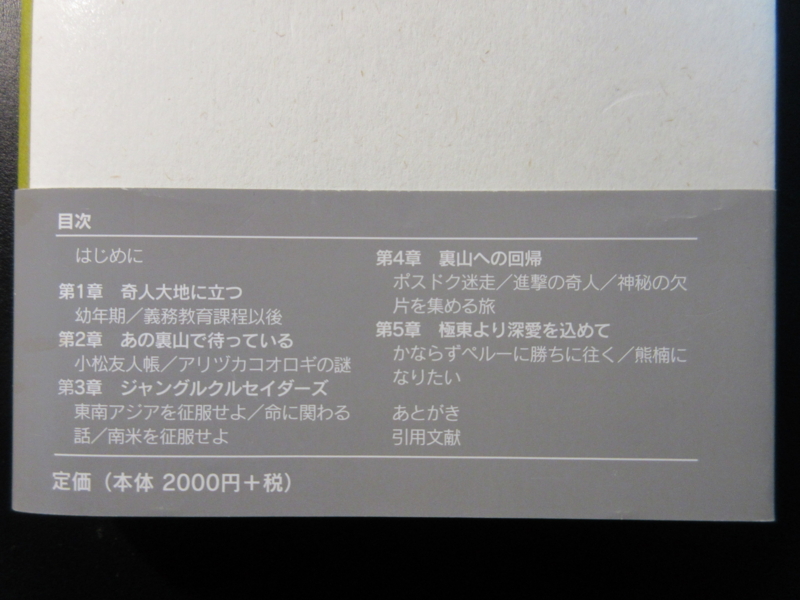 「目次」の内容が記載された帯の裏
「目次」の内容が記載された帯の裏
本書の「目次」は、以下のような構成になっています。
「はじめに」
第1章 奇人大地に立つ
第2章 あの裏山で待っている
第3章 ジャングルクルセイダース
第4章 裏山への回帰
第5章 極東より深愛を込めて
「あとがき」
「引用文献」
「はじめに」では、著書が自身を「奇怪な生き物」と呼んでいます。その奇怪な生き物(著者)が身近な裏山、はては異国のジャングルに住むもっと奇怪な生き物たちと出合い、そして愛し合った日々をつづった物語が本書であるとして、以下のように述べています。
「私の書く文章にはたびたび『擬人化』という、本来研究者を名乗る者が使ってはならない表現技法が出てくる。これに違和感を持つ読者もいるかもしれないが、しかし、私はシートン動物記の『ギザ耳坊や』の冒頭の言葉を借りて、この本のなかに登場する生き物たちが実際に私に言わなかったことは、何1つ書いていないことを断っておきたい」
第1章「奇人大地に立つ」の冒頭、著者は述べています。
「いまからおよそ30年前、神奈川県で理由もわからずに生を受けた私は、父の仕事の関係で日本各地を点々とする日々を送った。自我が目覚めた当時、近所に年の近い子供がいなかった私は、必然的に庭先の虫や小動物だけを相手に遊ぶようになり、やがてそれらをただのおもちゃ代わりから研究対象、そして人生のパートナーとして意識するようになっていった」
 多くの写真が目を楽しませてくれます
多くの写真が目を楽しませてくれます
本書には、数多くの生き物たちの写真が掲載されています。そのどれもが素晴らしい写真で、写っている生き物たちが魅力的に見えています。じつは、これらの写真を撮影したのは著者自身とのことで、なかなかカメラマンとしての才能も豊かな人物のようです。
また著者は文章も上手で、生き物にはそれほど関心のないわたしでさえ一気に読了しました。ケカゲロウの生態解明とか、ハラボソメバエの観察など、門外漢のわたしでさえハラハラドキドキしてしまいました。なんだか、少年時代に読んだ『ファーブル昆虫記』を思い出しました。最近日本でも大きな話題になったデング熱を実際に著者が患ったくだりはスリリングに描かれており、わたしは手に汗しながら読みました。
また、本書のところどころには「コラム」が挟まれているのですが、これがまた信じられないほど面白いのです。たとえば、「祖母の珍言」というコラムでは、次のように書かれています。
「祖母は、我が家系の例(私を除く)に漏れずヘビが嫌いであった。中学生くらいだったある日、私が裏山の道路を歩いていたとき、道の真ん中にマムシを見つけ、このままだと車に轢かれると思って棒で端によせてやった。そのことを祖母に話したところ、『ヘビに情けなんかかけるもんじゃない。そんなことしてっと、いつかヘビが女に化けてお礼参りに訪ねて来るぞ』と言われた。あれからかれこれ十数年、私の薄汚い下宿の四畳半に、切れ長の瞳でたおやかな美女が訪ねて来る気配はいっこうにない。村人が遊びに来るのを待つ『泣いた赤おに』の赤おにくんのように、美味い茶と茶請けを用意してわくわくしながら待ち続けているというのに、どういうことですかバアサン」
また、「ヒゲのジョージの教え」というコラムでは、著者が自然観察サークルの飲み会が開かれた居酒屋で出会った「ヒゲのジョージ」と名乗るおっさんについて、次のように書いています。
「『いいか、自然てのはなぁ、そんなんでわかるこっちゃねえんだよ。おめぇらのやってんのは木を見て森を見てねぇママゴトだ。第六感だよ。第六感を鍛えて、自然っつーものを理屈じゃなくて体で感じんだ。そのためにゃ、皆で仲よしごっこしてちゃダメだ。1人で山行け。夜行け。素っ裸で!』おっさんは次第に熱を帯びてきた。『誰もいねぇ、何も見てねぇ、そして体が物で覆われねぇ状況じゃ、人間つーのは己が身を守るために、すべての五感が鋭敏に研ぎ澄まされんだ。最近の若っけぇモヤシどもはンな経験しねーだろが!あぁん?お勉強ばかりできゃがって、頭でっかちのモヤシどもがよ。五感を鍛えた先に、そのいずれでもねぇ第六感を会得すんだ。そうして、はじめて人は自然と対等になれんだよ!』」
「アリの巣ほじって何になる」というコラムでは、次のように書いています。
「ヨーロッパのことわざに、『森の下には森がある』というのがある。森の落ち葉の下に住む糞転がしに関する本(塚本、1994)を読んではじめて知った言葉だが、地中(とは限らない)に広がるアリと好蟻性生物の織り成す複雑な生態系もまた、まさしく大きな森の下に存在する、もう1つの森だ。陸の深海と言ってもいい。しかも、その深海は本物の深海と違って、我々にとって遠い世界ではない。家の庭先や近所の公園でさえあるのだ。『生物多様性は大事だから守れ』と口先だけで言うのはたやすいが、なぜそれが大事で守らねばならないのかについては、じつのところどんな高名な生物学者のセンセイでも明白に答えがたい。そんななか、生き物同士のつながり合いという漠然としたものを理解するにあたって、この『身近で多様』な好蟻性生物たち以上に最適な材料はない。私はそう確信している」
本書を読み進むにつれて、著者の奇人ぶりに圧倒され通しですが、第5章「極東より深愛を込めて」では、以下のように述べています。
「周囲の知人が1人、また1人と就職していくなか、私は中島敦の『山月記』の李徴よろしく、いよいよ焦燥に駆られていく。そのたびに、私はこの世で敬愛する数少ない偉人、ウォーレスAlfred Russel Wallaceと南方熊楠を思い出す。私は人生のなかでもかなり最近にこの人らの存在を知ったのだが、その生い立ちを調べていくと、いずれも偶然ながらじつに私そっくりなのだ」
ダーウィンと並ぶ進化論の大家であるウォーレス、日本における博物学の巨人である南方熊楠・・・・・・2人とも知らない者はほとんどいない超有名人ですが、著者はなんとこの2人に「なりたい!」というのです。著者は「熊楠になりたい」で、以下のように書いています。
「ウォーレスも熊楠も、ともに豊かでない家の出身だったし、生涯を通じて定職らしいものにも就かなかった。それでも、学術誌の最高峰ネイチャーにいくつも論文を載せ、熊楠に至ってはその本数は日本人最多の座を守り続けているという。しかも熊楠の場合、その論文のほとんどは天文(Minakata,1893など)など、彼の専門分野とは畑違いのものだったらしい。それがなおさらすごい。私のような先行きの見えない若手研究者にとって、彼らの存在、生きざまは大いに励みになる。かならずしもどこかの組織に組み込まれずとも、きっと研究は続けていけることを、彼らの生涯は我々に暗示してくれている。当時といまは時代が違うし、相応の精神力も必要だが、これからの人生設計の選択肢としてこういう生き方も私は含めたい。どのみち、私みたいな人間を雇う企業や団体がこの国にあるなど、期待すること自体がすでにばかばかしく思えはじめている」
一見、不遜のようですが、著者の想いは高い志になっていると思います。
「あとがき」の最後が、また面白い! 以下のように、もう奇人ぶり全開で書いています。
「両親、親族、親戚一同は、幼いころからあまりにも常識から外れた言動ばかり繰り返す私を、いつも温かく見守ってくださいました。どんなに不潔で不気味な生き物を外から連れて帰っても、たいていは目をつぶってくれたことが、どれほど将来の私が博物学者として育つことに大切だったことか。これらすべての人々に、かさねて厚く御礼申し上げます。
そして最後に、いつも通い慣れたフィールドで、どんな小説よりも奇妙で、どんなテレビドラマよりも心打つ瞬間を私だけに見せてくれた、数多の生き物たち。家族として、友達として、敵として、恋仲として、餌として、そして研究材料として、ずっと私の側に寄り添ってくれました。これからも一緒に争い、驚き、愛し合おう。フサヒゲサシガメ、いつかかならず迎えに行く。スティロガステル、いつかふたたび逢いに行く」
本書には全篇、小さな虫とか生き物たちが登場します。わたしの日常生活とはまったく縁がない世界ですし、著者についても「奇人というだけあって、変わった人だなあ」と思いますが、同時に「うらやましいほど豊かな人だなあ」とも思います。何が豊かかというと、もちろん「こころ」が豊かなのです。これほど自分の人生を好きなものに賭けることができたら、どんなに自由で素敵なことでしょうか! 虫を観察しているときの著者の心は大宇宙で遊んでいるのでしょう。
わたしは、著者が世界的な学者となられることを心より祈っています。