- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2015.10.19
『ホンのひととき』中江有里著(毎日新聞社)を読みました。
「終わらない読書」というサブタイトルがついています。「毎日新聞」に連載された読書エッセイと「週刊エコノミスト」に連載された3年半におよぶ読書日記を中心に、選りすぐりの約100冊の本への想いを綴った本です。わたしの大好きな「クラフト・エヴィング商會」による装幀も魅力的です。
著者は1973年生まれ、大阪府出身の女優で作家です。
2002年、「納豆ウドン」で第23回「BKラジオドラマ脚本懸賞」で最高賞を受賞しました。読書家としても知られ、NHK-BS「週刊ブックレビュー」で長年司会を務めました。現在は、NHK「ひるまえほっと」で本の紹介を担当するほか新聞、Webに読書エッセイを連載しています。著書に『結婚写真』(小学館文庫)、『ティンホイッスル』(角川書店)、『いくつ分かる? 名作のイントロ』(明治書院)があります。
 本書の帯
本書の帯
帯には書店で本を選んでいる著者の写真とともに、「ああ、もっと読みたい。」「偏読、雑読、併読、積ん読―楽しみ方いろいろあります。年間300冊の本を読み、読書家で知られる女優の初エッセイ。」と書かれています。また帯の裏には「不安な時ほど、その存在がしみる。」として、「まえがき」に書かれた文章が抜粋されています。
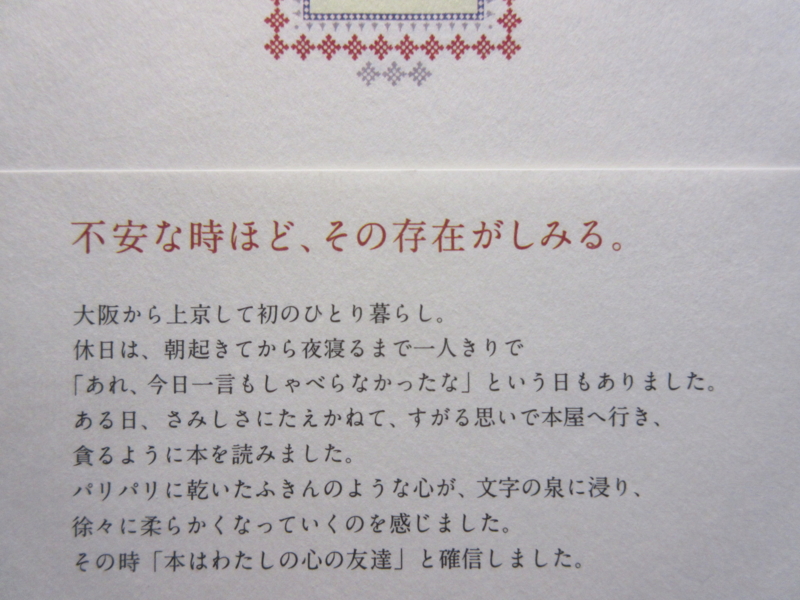 本書の帯の裏
本書の帯の裏
著者は、フジテレビ系の「とくダネ!」にときどきコメンテーターとして出演しています。わたしは、カマボコ目が魅力的な著者に好感を抱いているのですが、まさかこんな素敵な読書本を書く人とは思いませんでした。テレビでのコメントと同様に、けっして押し付けがましくなく、それでいて知的な言葉に溢れています。
本書の〔もくじ〕は、以下のような構成になっています。
「終わらない読書―まえがきにかえて」
1 ホンのひととき(エッセイ)
2 読書日記 2011~2014
3 書評の本棚
「『本のひと時』あとがきにかえて」
「掲載書籍一覧」
「終わらない読書―まえがきにかえて」の冒頭は以下の書きだしです。
「わたしが仕事を始めたのは、高校1年生の頃でした。大阪から上京して初のひとり暮らし。休日は、朝起きてから夜寝るまで1人きりで『あれ、今日一言もしゃべらなかったな』という日もありました。
ある日、さみしさにたえかねて、すがる思いで本屋へ行き、貪るように本を読みました。パリパリに乾いたふきんのような心が、文字の泉に浸り、徐々に柔らかくなっていくのを感じました。その時『本はわたしの心の友達』と確信しました」
また、著者は以下のようにも書いています。
「これまでわたしは、さまざまな『本』と出合ってきました。『本は心の友達』と書きましたが、これほど気が置けない友達はいないでしょう。その証拠に、この文章に登場する『本』という単語を「友達」と入れ替えてみてください。ほぼ通じると思いませんか?
疲れたり、飽きたりしたらすぐ閉じてもいいし、必要な時はいつまでもそばにいてくれます。「本」はこちらがどう変わろうと、常に同じ中身で、こちらが夢中になって読む日を待ち受けてくれています。読むと、ふいにずっと昔の記憶を思い起こさせたり、遠い未来を予言したりもする。そんな先の読めない憎いヤツだから面白い」
そして、「終わらない読書―まえがきにかえて」の最後には以下のように書かれています。
「過去に読んだ『本』は今の自分を作り、今読んでいる『本』は5年後、10年後、もっと先の自分につながっていきます。終わらない読書が、いつもあなたの未来を作ってくれますよ」
「診療室の待合室で」というエッセイが心に残りました。
著者が風邪を引いて駆け込んだかかりつけの診療所の待合室。そこにやってきた幼い男の子の兄弟は待合室に入るなり、一目散に本棚を目指します。そして、兄弟は押し合いへし合い競いながら「それはボクの」「ちがうよーダメだよ」と絵本を取り合います。ようやくお気に入りの本を探し当てた2人は、仲良く母親を挟むように座り、揃って本を読み始めました。
その微笑ましい様子を眺めながら、著者は次のように思います。
「なぜ子どもは、自分の読みたい本を探すことができるのでしょう? きっとそれは、子どもが好奇心のかたまりで、何でも知りたい! と思っているからではないでしょうか。
これがさまざまな経験を積んだ大人になると、『得になる読書』『情報を求める読書』つまり損得を求める合理的な読書になりがちです。忙しい時間の合間を縫って本を読むのだから、最低限の時間で最高の効能を求めたい、というのはわからなくはありません。でも『合理的』という言葉は、読書という行為にもっともそぐわないものです」
なぜ、「合理的」という言葉は読書にそぐわないのでしょうか。
著者は、以下のようにその理由を書いています。
「なぜなら本は『読んですぐ』ではなく、長い時間をかけて染み込んでいくものだからです。知識や経験がまだない子どもは言うなればまっさらな土地。本という水をどんどん吸い込み、いつしか知識の泉がわいてきます。そのためには、できるだけ多くの水分を吸いこむこと。そうしてたくさんの本の中から、自分に必要なもの、そうでないものを学びます。時間を忘れ(時には食事を抜いてでも)心に栄養をあげるという読書の大切さを、子どもは最初から知っているのでは、と時々思います」
著者は「本を食べ物に例えるなら、いったい何でしょう」と問いかけ、「ズバリ、サプリメントではないでしょうか」と解答を披露します。サプリメントとは食事では足りない栄養を手軽に補ってくれる現代人にはお馴染みのものですが、著者は次のように述べます。
「こうしたサプリメントとしての本は、身体が欲している時に取り入れるのが一番です。取り過ぎてはよくないし、足りなくても意味がない。本物のサプリメントなら、食事のバランスを見て量や種類を調整すればいい。しかし本のサプリメントの分量はどれくらいが適量か、どんな種類を取り入れればよいか、これは難しい問題。人によって体や状態はまちまちですから。本というサプリメントの効能は心にあらわれます。つまり心の状態によって、取り入れるサプリ本は決まってくるのです」
「本はサプリメントである」という考えは”稀代の読書家”として知られる上智大学名誉教授の渡部昇一先生の持論でもありますが、わたしも同感です。
本書には著者の子ども時代の読書体験、尊敬する児玉清さんとの出会いをはじめ、遠藤周作、東野圭吾、村上春樹、山本文緒など、著者お気に入りの作家たちの魅力が語られています。女優であり、作家、脚本家として物語を紡ぐ、著者の感性と日常がみずみずしい一冊です。
もともとカマボコ目にはめっぽう弱いわたしですが(苦笑)、本書を読んでますます著者のファンになりました。
