- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2015.12.31
『象徴と芸術の宗教学』ミルチャ・エリアーデ著、奥山倫明訳(作品社)を読みました。
本書の編者であるダイアン・アポストロス=カッパドナがジョージ・ワシントン大学において1985年に開催したセミナーをもとにして編纂された論文集の全訳です。2005年に日本語版が刊行されています。「20世紀最大の宗教学者」と呼ばれたエリアーデが広義の「芸術」を語った本です。自ら多くの文学作品などを残した彼は、「芸術」の本質について、「作品によって、失われた《楽園の想い出》を再現すること」と考えています。
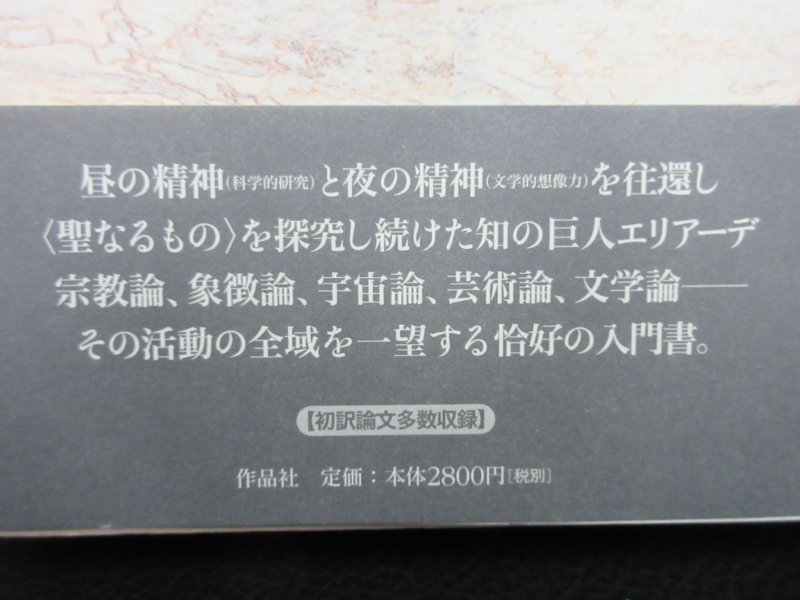 本書の帯
本書の帯
本書の帯には、「昼の精神(科学的研究)と夜の精神(文学的想像力)を往還し、”聖なるもの”を探求し続けた知の巨人エリアーデ。宗教論、象徴論、宇宙論、芸術論、文学論―その活動の全域を一望する恰好の入門書」と書かれています。
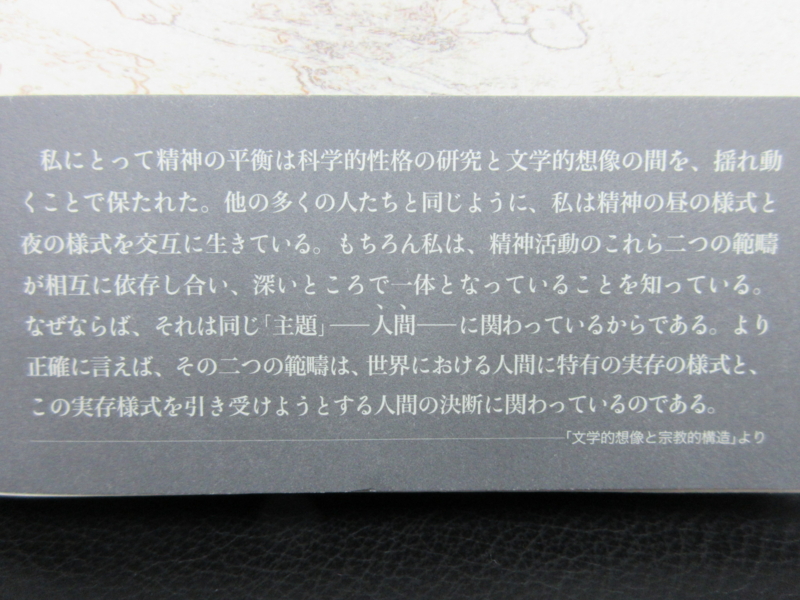 本書の帯の裏
本書の帯の裏
本書の「目次」は、以下のようになっています。
「謝辞」
序論「ミルチャ・エリアーデ―芸術家、批評家、詩人としての学者」
(ダイアン・アポストロス=カッパドナ)
第一部 1 始源的宗教における闇のシンボリズム
2 文化の流行と宗教史
3 神話の残存と偽装
第二部 1 芸術と神々
2 仮面の起源と儀礼
3 インドの芸術と図像
4 聖なるものと現代の芸術家
5 マルク・シャガールとの対話
6 ブランクーシと神話
第三部 1 聖なる建築とシンボリズム
2 象徴的寺院ボロブドゥール
3 ポルトガル日記より 1941~1943年
第四部 1 民間伝承のテーマと芸術の創作
2 マルテ・ビべスコと東西文学の出会い
3 ウジェーヌ・イヨネスコと「楽園への郷愁」
4 文学的想像と宗教的構造
「訳者あとがき」
参考文献一覧/人名索引
序論「ミルチャ・エリアーデ―芸術家、批評家、詩人としての学者」で、本書の編者であるダイアン・アポストロス=カッパドナは、以下のように述べています。
「人類史を通じて存在する、聖なるものの現前を理解しようと生涯かけて探究してゆくなかで、エリアーデは2つの中心的なテーマに魅了されてきた。すなわち創造と時間である。彼は宇宙創成神話とイニシエーション儀礼の、時間的な構造と意味を探究してきた。その著作は創造と時間を理解しようとする試みに始まり、同じ試みで終わっている。創造の瞬間に、まず時間との出会いがあり、その出会いから光と物質が認識されるようになる。
エリアーデは、歴史家でもあり作家でもある。彼は、創造と時間を理解するためには、宇宙創成神話がもっとも重要であると主張する。作家であるのと同じく、彼は芸術家、すなわち審美的解釈の創造者でもある。その現実解釈では、時間と空間に関する伝統的な認識の一時停止も見込まれている。エリアーデの世界は、学問的および創造的な想像力を併せもっている。彼が言うところの、昼の想像力と夜の想像力を含んでいるのである」
また、ダイアン・アポストロス=カッパドナは以下のように述べます。
「エリアーデの言葉は、キリスト教の宇宙と儀礼の性質をもった実存的次元を表現している。彼の言葉は、顕示されたロゴスである。経験に根ざし、経験を創造する言葉なのである。トレイシーが示すように、顕示する言葉の選択において、エリアーデは同時代の宗教思想家とは一線を画している。
ミルチャ・エリアーデは、十全たるハイデガー的な意味において詩人である。彼は存在の現前を指し示して白日の下にさらし、それにより人が時間の中の現世において、神々とともに住む住み処を見つけることを可能にする」
さらに、ダイアン・アポストロス=カッパドナは以下のように述べます。
「エリアーデは『世界の中心』を研究し続けてきたが、それは地理上の場所に関連して光と物質を解釈することに彼が関心を持っていることと関係している。イニシエーション儀礼に関するエリアーデの著作を調べてみれば、その儀礼への参加者の特別な衣装にも、こうした儀礼用に創り出された建築物の構造にも、彼が関心を持ち続けていたことがわかる。神話と神話の構造に関するエリアーデの研究は、物語を聞かずにはいられない、そしてそれを語らずにはいられないという、人間の根本的な欲求と関係がある。現代の芸術や文学には、聖なるものが隠れつつ、つねに現前している。それを探究し分析することに向ける彼の関心は、物質の神格化を受け容れる者の特徴なのである」
第一部の1「始源的宗教における闇のシンボリズム」の冒頭では、エリアーデは「予備的考察」として以下のように述べています。
「始源的社会のレベルでは、あらゆるシンボリズムが宗教的なものである、あるいは少なくともかつては宗教的であったということである。象徴は、実在の一様相や世界の深部にある1つの構造を明らかにし、未開人の精神の地平では、実在は聖なるものと混ざり合い、世界は神々の創造によるものと捉えられている。その結果、宇宙の構造や、世界における実存の多様なあり方、とりわけ人間の存在様式に関連する啓示はどれも、同時に宗教的性格を帯びた啓示にもなっている。始源的な諸文化が始まった時から、聖なるものの顕現は同時に存在の顕現であり、聖の顕現は存在の開示であった。その逆もまた然りである」
続けて、エリアーデは象徴について以下のように述べます。
「象徴は、体系化される以前の存在論をわれわれに明らかにしてくれる。つまり概念的な語彙がまだ確立されていなかった時代から、象徴は理想の1つの表現だったわけである。一例のみ挙げると、「生成」を意味する言葉は、歴史上のかなり後代になってから登場したもので、サンスクリット、ギリシア語、中国語といった、高度文化のいくつかの言語において知られるに過ぎない。しかし、「生成」のシンボリズムと、それを動きの中で具体的に表わすイメージや神話は、すでに文化の始源的な層において認められている。螺旋、織り物、闇からの光の発現、月の諸相、波などのイメージはすべて、動き、循環、持続、ある存在様式から他の存在様式への移行(「形なきもの」から「形あるもの」への、闇から光への移行)といった諸観念を表現している」
さらに、エリアーデは「月」を持ち出して以下のように述べます。
「これら『生成』の象徴と神話は、月と同じ構造を有している。ほかならぬ月こそが何にもまして、流れ、移行、満ち欠け、誕生、死と再生、要するに宇宙的リズム、万物の永久に続く生成、そして時間を開示するのである。つまり月のシンボリズムのおかげで、論理的弁証をもつ前の人間は、宇宙の時間的な様態を認識できるようになったのであり、しかもそれは体系的思考が『生成』の概念をすくい出し、的確な言葉でそれを表現することに成功する遥か以前のことだったのである」
第一部の2「文化の流行と宗教史」では、人類学者クロード・レヴィ=ストロースの流行について言及しています。宗教学者エリアーデと人類学者レヴィ=ストロースはともに「20世紀の思想の巨人」ですので、エリアーデによるレヴィ=ストロースというのは興味が尽きません。エリアーデは「レヴィ=ストロースの結論をどのように関上げようとも、彼の仕事の功績を認めないわけにはいかない」として、以下の3点を指摘します。
(1) 人類学者としての訓練を受け、それを職業としているが、根本的に彼は哲学者であり、思想、理論、そして理論的言語を恐れることはない。それゆえ、彼は人類学者たちをして考えるように、それも真摯に考えるように仕向けている。
(2) たとえ構造主義のアプローチが全体として受け容れられなくても、レヴィ=ストロースによる人類学的歴史主義への批判は、きわめて時宜に適ったものである。
(3)最後に、レヴィ=ストロースはすぐれた作家である。
第二部の1「芸術と神々」では、以下のように述べられています。
「すべての神、半神、怪物のような恐ろしい姿をした悪魔的イメージは、何らかの形で葬送の神話に属しているか、そうでなければ少なくとも死と何らかの結びつきがある。これは、死の神々がすべて空想的な形態や不吉な姿を取り、恐怖を引き起こすはずだということではない。ペルセポネの神話と図像の全般にわたることであるが、特にヘレニズム時代には、地中海世界、ローマ世界において死に関するある種のイメージが作り出された。深い眠り、母の子宮への回帰、祝福された世界に向かう儀礼の一段階、星辰界を通過する上昇の旅といったようにである。しかし、インド、チベット、東南アジアの未開世界では、恐ろしい姿の神々が死と多かれ少なかれ直接的に関連しており、それらの神々の主な役割が葬送ではない場合でもそう言える。シヴァ神やカーリー・ドゥルガー女神は葬送の神ではないが、それらの図像表現は、宇宙の破壊と再創造の連続が、厳然と死を意味することをはっきりと表わしている。もっとも、この死は霊的な経験と見なされることもある。つまりそれは、自由、あるいは不死という上位の存在レベルに到達するために、卑俗で愚昧な人間の状態を死ぬことである」
第二部の2「仮面の起源と儀礼」では、「シャーマンの変身、祖先の復活」として、以下のように述べられています。
「仮面結社の儀式の中でも、同様の変化が起こっている場合があるが、そこに含まれている呪術―宗教的な経験は、シャーマンの経験とも旧石器時代の狩猟民の経験とも異なっている。この場合の経験は、祖先崇拝のための共同体の儀礼と結びついている。仮面は祖先を表わし、仮面をかぶることで秘密結社のメンバーは祖先の化身となる。仮面によって死者は生き返る。儀礼を演じているのは仮面の着用者ではもはやなく、彼らが変身した神話―儀礼的な存在である。というのも死者たちは、神話上の最初の祖先、すなわち最初に死を知った人間に同化した神話―儀礼的な存在だからである。言い換えれば、秘密結社のメンバーは仮面をつけている時に、始まりの神話を演じている。つまり、原初の時代に最初の祖先がどのように死と出会い―自らの状態を変化させて「他者」となり―そしてその後、劇的なイニシエーションの儀式を通して、死と復活の神秘を人々にどのように開示したのかを実演しているのである。すべての仮面結社は起源神話に基づいている。そのため秘密結社を産み出した神話上の出来事が、その結社の儀式の中で定期的に再演されるのである」
第三部の1「聖なる建築とシンボリズム」では、「聖なる空間」について以下のように述べられています。
「聖なる空間は超越―世界、超越的な実在との交流を可能にするような諸レベル間の裂開に引き続いて構成されたものである。あらゆる民族の生活において聖なる空間のただならぬ重要性はそこに由来する。なぜならば、人間が世界、つまり神々や祖先たちの世界と交流することができるのは、そうした空間においてであるからである。聖別された空間はどれも彼方へと開かれた入口、つまり超越への入口を表わしている。ある時代まで、人間はそのような超越への入口なしでは、つまり神々が住む他界との交流のための確実な手段なしでは、生きることができなかったと思われさえする。この「入口」が時に、たとえば孔の形であったように聖域や住居などの実体をもって、具体的に表わされてきたことはのちに見る通りである」
しかし、われわれの関心を引くのは、とりわけ聖なる空間の建造に関わるシンボリズムと儀礼であると指摘して、エリアーデは以下のように述べます。
「聖なる空間とは、この世界と他世界との交流、つまり高みにある世界や深みにある世界、神々の世界や死者の世界との交流が可能になる場所である。そしてまもなく、3つの宇宙領域のイメージ―天上、地上、地下―が一般に定着する。これら三領域の間の交流は、レベルの断絶を意味している。言い換えれば、神殿の聖なる空間はあるレベルから他のレベルの移行を可能にするのであり、まず第一に地上から天上への移行が可能になる。注意すべきは、宇宙の諸次元の間の通行は存在論的秩序の裂開も含むということである。つまりそれは、ある1つの存在様式から他の存在様式への移行であり、俗なる状態から聖なる状態への、あるいは生から死への移行なのである。これら宇宙の三層の間の交流と連結という象徴的概念は、メソポタミアのいくつかの神殿や王都の名に現われている。それらは(ニップール、ラルサ、バビロニアのように)まさに『天地の連結』と呼ばれている」
また、エリアーデは「宇宙柱」について以下のように述べています。
「この柱は儀式の中で重要な役割を果たしている。これこそが祭り小屋に宇宙的構造を与えるものなのである。儀礼の歌でその小屋は『われわれの世界』と唱われ、新参者たちは『私は世界の中心にいる。・・・・・・私は世界の柱のそばにいる』と宣言する。
同様に、宇宙柱を宇宙規模での聖なる柱や祭り小屋と一体化させることは、フロレス島のナダでも認められる。生け贄を捧げる柱は『天の柱』と呼ばれ、天を支えていると言われる。ナダの東方に住むナゲ人の間でも、これははっきりと表現されている。つまり、柱は天が地上に落ちてこないように支えているのである」
さらに、エリアーデは「宇宙山」についても以下のように述べます。
「神殿を『世界の中心』と同一視することは、他の象徴によっても支持される。とりわけ、神殿や王都は宇宙山に相応する。メソポタミアの諸神殿は『家の山』『嵐の山』『大地すべての山の家』などと呼ばれている。しかし、伝承によっては、宇宙がその頂上を天に届かせる山の形をしていることもある。天と地が再び接する上空が『世界の中心』なのである。この宇宙山は現実の山と見なされることもあれば、神話的な山であることもあるが、つねに世界の中心に位置している。インドの宇宙的神話におけるメール山(須弥山)のような場合もあれば、『大地のへそ』と呼ばれるパレスティナのゲリジム山やユダヤ=キリスト教の伝統にとってのゴルゴタのように現実の山である場合もある。したがって、聖域は象徴的に宇宙山と一体化しているのである。その事例は豊富にある。メソポタミアのジッグラトはまさに宇宙山と呼ばれるのにふさわしく、その七層は七惑星を象徴している。同様にボロブドゥール寺院は真の世界の模像であり、山の形に造られている」
第二部の2「象徴的寺院ボロブドゥール」では、真の世界模型としてのボロブドゥール寺院について、さらに詳しく述べています。
「世界の中心は、どこにでも建設できる。なぜなら小宇宙は、石や煉瓦でどこにでも建てることができるからである。たとえば、有名なメソポタミアの建造物ジッグラトは人工の山を表わしている―というのも、すべての伝統的文化では宇宙は山として解釈されており、寺院の最高点は、呪術的な山(メール山)の頂上と同化されることで、宇宙山の頂点として捉えられていたからである。『中心』の建造は『空間』の次元においてだけでなく、『時間』の次元でも行なわれる。すなわち寺院は宇宙の中心であるだけでなく、『聖なる年』、つまり『時間』を刻む盤面でもある。『シャタパタ・ブラーフマナ』に記されているように、ヴェーダ祭壇は物質化された時間、つまり『年』である―これはまさに寺院にも当てはまる。その構造は4つの地平線(空間、宇宙)に配慮するものだが、同時に、浮き彫りが施された壁龕に見られる時間の方向秩序も考慮している。したがって、実在するものはすべて寺院の宇宙論的シンボリズムによって表わされ、とりわけ、そういった『宇宙時間の盤面』であるボロブドゥールにおいて完全に表現されているのである」
「訳者あとがき」では、わたしと同じ1963年生まれである宗教学者の奥山倫明氏が以下のように本書の要旨を述べています。
「現世的経験においてわれわれが遭遇する始まりと終わりのうちで、とりわけ重要なのは、言うまでもなく個体の誕生と死だろう。生と死という始まりと終わりは、どれほど医学が進歩しようとも、個々人の生の、時間の中における限界をつねに画している。それはわれわれにとって不可知の部分を必ず含む神秘の領域であり、理性的に理解することを拒み続けるだろう。しかしながらわれわれの生のそうした限界、すなわちエリアーデの好む表現を借りると、「人間の条件」は、象徴を介し、類比的に実在のあり方、宇宙のあり方と重ね合わせて体得されうるのである」
続けて、奥山氏は以下のように述べています。
「すなわち、月が顕示するように、誕生、成長、衰退、死は、永遠に繰り返されるのであり、神話が語るように、宇宙にさえ始まり(すなわち『誕生』)がある(なおこの点は、現代宇宙論のビッグバン仮説と符合してもいる)。エリアーデが語る宇宙論(cosmology)において、開闢説と創造説のどちらであれ、宇宙創世説(cosmogony)が重視される1つの理由がここにある。空間的シンボリズムもまた、その始まりに注目すれば、宇宙創成と類比的に理解される(建築をめぐるシンボリズムを論じた第三部第一章を参照されたい)。そしてまた、現世的経験のレベルにおける生と死の、宇宙的なレベルにおける新たな理解を促す儀礼として、諸々のイニシエーションが重視される背景にもなっている(もともとラテン語initiumが「始まり」を意味する)」
結局、エリアーデの宗教学とは「月」のシンボル学であり、「永遠」の哲学なのでしょう。そこに、わたしがエリアーデの思想にたまらなく惹かれる最大の原因があるように思います。
