- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2016.01.12
『文化人類学』大田俊寛著(人文書院)を読みました。
この読書館で紹介した『宗教学』と同じく、「ブックガイドシリーズ 基本の30冊」シリーズの1冊です。著者は、1975年生まれの気鋭の文化人類学者です。京都大学大学院人間・環境学研究科博士課程を修了し、現在は立教大学社会学部准教授を務めています。著書に『所有と分配の人類学―エチオピア農村社会の土地と富をめぐる力学』(世界思想社)があります。
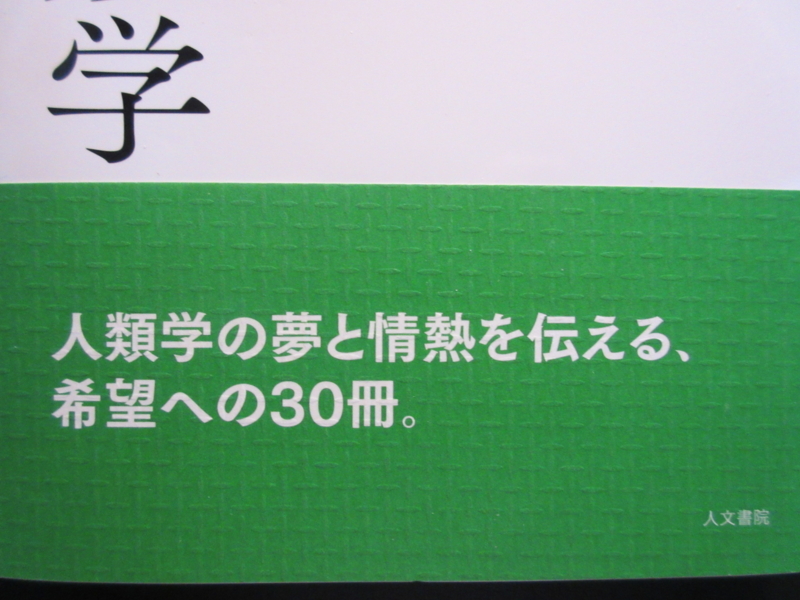 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「人類学の夢と情熱を伝える、希望への30冊」と書かれています。目次構成および取り上げられている書籍は以下の通りです。
「はじめに」
第1部 人類学の確立
モーガン『古代社会』
フレイザー『初版 金枝篇』
マリノフスキー『西太平洋の遠洋航海者』
モース『贈与論』
べネディクト『文化の型』
ミード『サモアの思春期』
第2部 人類学理論の深化
ファース『価値と組織化』
レヴィ=ストロース『野生の思考』
ダグラス『汚穢と禁忌』
サーリンズ『石器時代の経済学』
ベイトソン『精神の生態学』
ブルデュ『実践感覚』
ゴドリエ『観念と物質』
第3部 民族誌の名作
エヴァンズ=ブリチャード『アザンデ人の世界』
リーチ『高地ビルマの政治体系』
ルイス『貧困の文化』
ターンブル『ブリンジ・ヌガク』
ギアツ『ヌガラ』
スミス・ウィスウェル『須恵村の女たち』
第4部 批判と実験の時代
クラバンザーノ『精霊と結婚した男』
フェルド『鳥になった少年』
マーカス、フィッシャー『文化批判としての人類学』
クリフォード、マーカス編『文化を書く』
ロサルド『文化と真実』
第5部 新世紀の人類学へ
ラトゥール『虚構の近代』
レイヴ、ウェンガー『状況に埋め込まれた学習』
ラビノー『PCRの誕生』
アパデュライ『さまよえる近代』
アサド『世俗の形成』
グレーバー『価値の人類学理論に向けて』
「はじめに」の冒頭で、著者は以下のように書いています。
「文化人類学が学問として確立して、1世紀以上がたつ。それでも、いまだに『若い』学問のイメージが強い。それは、人類学がつねに反主流派の道を歩んできたからだろう。人類学は、西洋という場所、近代という時代、その支配的な社会のあり方に、くり返し異議を申し立ててきた。『今』を覆っている考え方や社会制度に対し、非西洋の研究をとおして、別の可能な世界の姿がありうることを提示してきた。いまも多くの人類学者には、この社会変革の夢が共有されている」
また、第1部「人類学の確立」の扉には以下のように書かれています。
「文化人類学は、19世紀後半に『かたち』のないところから出発した。草創期の独創的な研究の数々を、その『かたち』の手がかりとして、しだいに人類学が確立されていく。人類学の地平を切り拓いた先達たちは、みな個性的で魅力にあふれている。彼らは、それぞれの視点で『近代』のあり方に危機感を抱いていた。そして、人類学という学問の社会的使命を強く意識していた」
以下は、本書で取り上げられている本の解説文の中から興味深く感じた箇所を抜き書きします。個人的な読書メモというか備忘録のようなものですが、将来の執筆などに活用するつもりです。みなさんも関心を抱いてくれれば幸いです。
●ジェイムズ・フレイザー『初版 金枝篇』
「人間神や神の化身の生命は人びとの平和や安定と深く結びついている。つまり、人間神が死という消滅を迎えることは深刻な破局を意味した。それを回避する方法はひとつしかない。力が衰える兆しをみせたら、すぐに殺すことだ。自然死では、魂が自らの意志でその身体を離れ、二度と戻らなくなる。まだ力が衰える前に殺せば、逃げ出す魂を確実に捕らえ、強壮な後継者に移しかえることができる」
●マルセル・モース『贈与論』
「モースは、交換や契約の道徳的な義務について問うにあたり、『経済』の位置づけそのものから再考を迫る。経済現象だけを切り離してとらえる経済学とは異なり、交換などの行為を社会のさまざまな領域と関連する全体的な現象とみなす。それが『全体的社会事実』という考え方だ。交換し、契約を交わす義務を負うのは、個人ではなく、集団(氏族、部族、家族)であり、そこで交換されるのは、礼儀や饗宴、儀礼などにおよぶ。財産や富の経済的取引はその一部にすぎない。そして、その取引は、宗教的、法的、道徳的であると同時に、政治的、美的な現象でもある。厳格な相互の義務があり、それが果たされなければ闘いにまで至る。モースは、こうした給付―反対給付の複合を『全体的給付体系』と呼ぶ」
●クロード・レヴィ=ストロース『野生の思考』
「呪術は、科学への発展の一段階ではない。それらは認識の二様式として並置される。呪術的思考では、感覚的性質が重視され、たとえば舌を刺す苦い味をもつ汁は毒であるとか、歯の形をした種子は蛇にかまれるのを防止するといった推論がなされる。これは、美的感情にとって同一の物が客観的現実に対応しているという感覚にもとづいた発見である。それをレヴィ=ストロースは『具体の科学』と表現した。『具体の科学は、近代科学と同様に学問的である。その結果の真実性においても違いはない』。それは、フランス語で『ブリコラージュ=器用仕事』といわれる。ありあわせの道具や材料を用いて物をつくる仕事でもある。神話的思考の本性とは、まさに雑多な要素からなり、限りある『もちあわせ』の材料から考えを表現することにある。それは事前に計画されるわけではない。『まだなにかの役に立つ』という潜在的有用性の原則によって収集、保存された要素で構成されるのだ」
●メアリ・ダグラス『汚穢と禁忌』
「ダグラスは、エヴァンズ=ブリチャードのヌエルなどの民族誌的事例を引きながら、祭祀や儀礼における無秩序が果たす役割を描き出す。『汚穢』は、危険でありタブー視されながらも、ときに大きな能力をもつ。その無秩序のもつ危険性と潜在性は、境界領域に位置する人びとにも向けられる。たとえば、レレ族では、出生前の胎児を他人に危険を与える気まぐれな悪意をもった存在として危険視する。女性は妊娠すると病人に近づかないようにする。さまざまな民族の成人儀式では、若者たちは別の場所に隔離されるなど、一時的には正式の構造から離れて境界領域に入ることを求められる。それは、旧き生から新しき生に生まれ変わる、再生の儀式なのだ」
●エドマンド・リーチ『高地ビルマの政治体系』
「儀礼は『社会的個人としての個人の地位を、彼が現にそのなかにいる構造体系のうちに表現するのに役立つ』。人類学者の役割は、そのシンボリズムの解釈を試みることにある。特定の文化的脈絡におかれた儀礼は象徴のパターンをなす。ただし、その構造は文化的形式からは独立している。たとえカチン山地のように集団ごとの文化(言語・服装・信仰・儀礼過程など)に多様性があっても、それらはひとつの包括的な構造体系のなかの個別の象徴的ラベルにすぎない。リーチが解釈し、抽出しようとしたのは、表面的な文化形式の背後にある構造だった。『特定の構造がいかにして幾つもの異なった文化的装いをとりうるのか、また異なった構造がいかにしておなじ一連の文化象徴によって表わされうるのか』。この問いから、社会変動のメカニズムをあきらかにする」
「リーチは、社会構造が儀礼のうちに『表示』されるとしたイギリス社会人類学の伝統では、神話や伝承とは儀礼行為を拘束する規範や典拠だった。とりわけマリノフスキー以来の機能主義の理論は、ひとつの社会集団が単一の文化や一貫した神話群をもつことを前提にしてきた。それは必然的に神話に『正しいもの』と『不正確なもの』という区別を導入する。リーチは、神話に矛盾や食い違いがあることこそ重要だと主張する。カチンの伝承には、だれもが認める『正伝』はない。登場人物や構造的シンボリズムを共有する物語は多いが、細部の重要な点は語り手の利害関心によって大きく変化する。たとえ人びとが一致して依拠する神話的な枠組みがあっても、そこに社会的結束や社会的均衡があるとは限らない。『神話と儀礼は記号言語であり、それをつうじて権利や地位の主張が表現される。だがまたそれは論争のための言語であって、調和を保って響きあう合唱ではない。儀礼が時に統合のメカニズムとなるというなら、また時には分裂のメカニズムともなるといわねばならない』。リーチは、こうして均衡理論を批判し、文化的に多様性をもち、変動する社会の構造を記述するという方向性を提示したのだ」
●クリフォード・ギアツ『ヌガラ 19世紀バリの劇場国家』
「19世紀のバリ国家が目指したのは、権力集中による支配や統治ではなく、バリ文化の社会的不平等と地位の誇りを公の儀式において『演劇化』することであった。王と君主が興行主、僧侶が監督、農民が脇役と舞台装置係と観客となり、国家は華麗な火葬や寺院奉献式典などの儀礼を執行するための劇場だった。その背後には、王宮=都が超自然的秩序の小宇宙であると同時に、政治秩序の具現であるという根本観念があった。『ヌガラ』は、その支配の位置する座と支配の実現がイコールであるという政治理念を表現していた」
「19世紀バリの国家儀礼とは、形而上学的な演劇として、現実の究極的性質についてのひとつの見方を表現すると同時に、現存する生の状況を現実と調和させようとするものだった。王とその宮廷、それらをとりまく国家全体が、そのイメージによって定義される秩序の描写となっていた。ギアツは、神々の宗教象徴や宮殿の空間象徴の多義性を読み解きながら、国家儀礼の対象となる君主が偶像という神聖な形象へと変容される様子を描く。人びとが王をシヴァ神の活性化としてみることで、国家や社会もまたその活性化であり、同時に自己もその活性化になるのだ」
最後に、第5部「新世紀の人類学へ」の扉にはこう書かれています。
「批判と実験の時代をへて、人類学が論じるテーマや対象は大きく拡大した。もはや人類学は、非西洋の『未開社会』についての学問ではない。近代性、学習、バイオテクノロジー、グローバリゼーション、世俗主義、ネオリベラリズム・・・・・・。つねに相対化の対象だった『西洋近代』が研究の直接の対象となった。同時に、人類学が闘いを挑むべき相手も、より複雑で強大になった。調査手法の柱だった『フィールドワーク』の位置づけも変化してきた。人類学は、みずからの定義自体を更新しながら、なお根底にある批判精神を貫きながら、分野横断的な言論空間に再参入している。草創期の人類学がそうであったように、自分たちが生きる社会/世界に真摯に向き合うなかで、人類学のあらたな可能性が開かれるつつある」
