- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2016.11.25
11月25日になりました。
今日は、三島由紀夫の45回目の命日である「憂国忌」です。
『終わり方の美学』三島由紀夫著、高丘卓編(徳間文庫カレッジ)を読みました。「戦後ニッポン論考集」のサブタイトルがついています。
表紙には三島が和服姿で立つ写真が使われ、帯には「いずれ日本はなくなる―この国への危機感と、タナトスの誘惑」「生誕90年、没後45年・・・・・・。三島の遺した日本人への伝言」と書かれています。
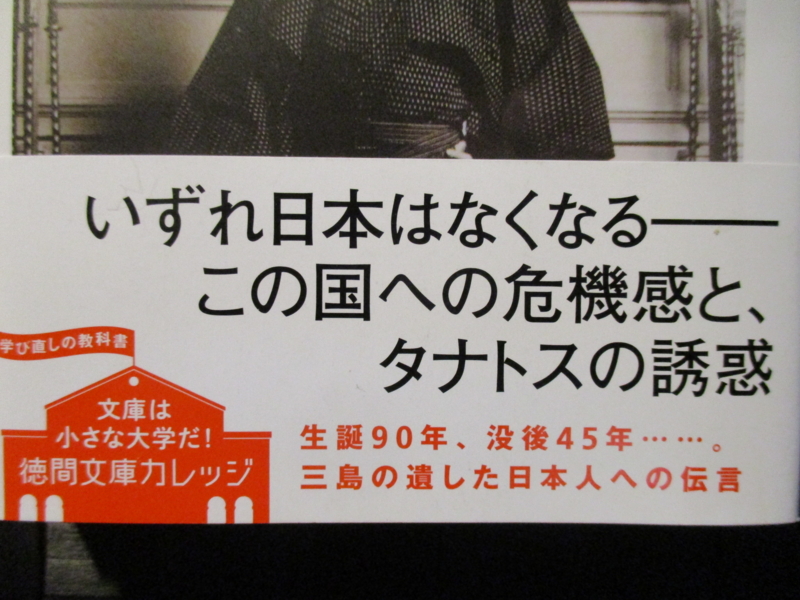 本書の帯
本書の帯
また、アマゾンの内容紹介には以下のように書かれています。
「このまま行ったら『日本』はなくなってしまうのではないか。誰より早く戦後日本の危機を見抜き、命を賭して訴え、自決の道を選んだ三島由紀夫。その危機感は予言的であった。9・11、恒常的な不況、混迷する国際社会のなかで、日本のあるべき姿とは。生誕90年、没後45年の今、三島の声に耳を傾けなくてはならない。『ニッポン人のための日本入門』『サムライの心得』などを収録した『日本人養成講座』を改題。文庫化による新規掲載原稿も収録」
本書の「目次」は、以下のようになっています。
1 ニッポン人のための日本入門
アメリカ人の日本神話
お茶漬けナショナリズム
2 日本語練習講座
文章読本
3 サムライの心得
小説家の休暇(断片)
若きサムライのための精神講話(抄)
4 エロスと政治について
心中論
二・二六事件と私
性的変質から政治的変質へ
―ヴィスコンティ「地獄に堕ちた勇者ども」をめぐって
5 死を夢見る肉体について
現代の夢魔―「禁色」を踊る前衛舞踏団
“殺意”の無上の興奮―「人斬り」田中新兵衛にふんして
「総長賭博」と「飛車角と吉良常」のなかの鶴田浩二
「憂国」の謎
聖セバスチャンの殉教
6 終わり方の美学
団蔵・芸道・再軍備
私の中のヒロシマ―原爆の日によせて
愛国心
新知識人論
私の中の二十五年
「三島由紀夫略年譜」
解説(高丘卓)
1「ニッポン人のための日本入門」の「アメリカ人の日本神話」の冒頭を、著者は以下のように書き出しています。
「日本ははじめ、サムライとハラキリ、フジヤマとゲイシャで有名になった。それから低賃銀労働と粗悪な輸出品で有名になり、さらに日本人の『不可解な微笑』で有名になった。それから好戦国民として有名になり、一旦戦争に負けると、今度は、キモノやイケバナ、世界一貞淑な妻たる素質を持った日本娘、おだやかな友愛、カメラやトランジスター・ラジオや木工品や陶器や紙提灯、テンプラやスキヤキ、さらに偉大な禅の哲学などで有名になった」
著者は日本のサーヴィス業に言及し、以下のように述べています。
「日本のサーヴィス業というものには、微妙な東洋的特色があるのである。西欧では、快楽というものは、キリスト教的伝統によって、肉体的快楽と精神的快楽にはっきり分けられているらしい。日本ではこのへんがひどくあいまいで、肉体から精神にいたるひろい領域を、いろんな種類の快楽が埋めていて、そのひとつひとつに対応するサーヴィス業があるわけだ。だから日本人は、外人が芸者やバアの女給を娼婦と混同するような誤解にひどく気を悪くする」
続けて、著者は以下のように述べています。
「芸者は断じて娼婦ではない。かと云って素人女でもないのである。いや、娼婦ですらも、厳然たる合理的娼婦ではない。18世紀の日本の純粋な恋愛劇は、ほとんど娼婦と客の恋を描いている。この点では、封建時代の日本人はよく割り切っていた。恋愛とは、金を払った女とやるものであり、結婚と恋愛とは何の関係もないと思っていたのである。今でも日本人にはこの気分が残っていて、恋愛というものは、金を払える場所で、たとえば女のいる酒場で、次第に精神的に成立するものだというような考えがある」
また著者は「礼儀」の問題を取り上げ、以下のように述べます。
「礼儀という問題がずいぶん厄介だ。日本人は礼儀正しい国民ということになっている。だからやたらに微笑する。やたらにお辞儀をする。やたらに贈物をする。その代り、大きな果物籠を下げて訪問して、微笑して、100ぺんお辞儀をして帰ってくると、これで『礼儀を果した』という、うれしい解放感が日本人を襲う。彼はその家をもう一生訪れなくてもいいのである」
著者によれば、伊勢神宮が20年毎に造り替えられる制度は日本人の伝統というものの考え方をよくあらわしています。西洋ではオリジナルとコピーの間には決定的な差がありますが、木造建築の日本では、正確なコピーはオリジナルと同じ価値を生み、次のオリジナルになるというのです。著者は以下のように述べます。
「一般的に云って、日本人くらい、伝統を惜しげなく捨て去って、さっさと始末してしまう国民もいない。伝統の重圧というものは、日常生活には少しも感じられず、東洋風な敬老思想もなくなって、今日では、日本の老人は、若者の御機嫌をとるのに汲々としている。一部の若い世代で信じられている通念によれば、女は20歳すぎれば婆ァであり、男は25歳すぎれば爺ィなのだそうである。そこで20歳以下の連中は、ブルー・ジンズで街を歩きまわり、ロックン・ロールにうつつを抜かしている」
さらに、著者は以下のようにも述べています。
「20年目毎の改築と遷宮、これは実に象徴的である。戦後15年目あたりから、もうすっかり死に絶えたと誰もが思っていた古い日本思想が、あなどりがたい力で復活して、若い世代の一部を惹きつけている。1960年に、15年ぶりでハラキリが復活した。岸内閣の政治に憤慨した或る僧侶が、官邸の前で切腹したのである。これから又たびたびハラキリが出て来ても、おどろくには当らなのである。サムライもやがて復活することであろう」
そして著者は、お寺について以下のように述べるのでした。
「私自身の家族が禅宗に属しているが、お寺へ行くのは祖父や祖母の法事の時だけで、親戚の葬式のときだけ一族がお寺に集まるが、坊さんのお説教などきいたことはなく、意味のわからないお経や香の匂いにうっとりするだけである。戦争中は死に直面した者い人たちの間に坐禅がはやったが、いずれにしろ現代の都会の日本人は、『死』についてだけしかお寺と交渉をもつことがない。地方ではなお、お寺の坊さんと信徒との人間関係は密接だが、都会では、お寺は死のデパートメント・ストアのようなものになっており、われわれはその教義について考えてみたこともないのである」
「小説家の休暇」(断片)では、『葉隠』が取り上げられます。
著者は戦争中から読みだして、その後も時折『葉隠』を読むとして、「犬儒的な逆説ではなく、行動の知恵と決意がおのずと逆説を生んでゆく、類のないふしきな道徳書。いかにも精気にあふれ、いかにも明朗な、人間的な書物」と評しています。さらに著者は述べます。
「『葉隠』ほど、道徳的に自尊心を解放した本はあまり見当らぬ。精力を是認して、自尊心を否認するというわけには行かない。ここでは行き過ぎということはありえない。高慢ですら(『葉隠』は尤も、抽象的な高慢というものは問題にしない)道徳的なのである。『武勇と云ふ事は、我は日本一と大高慢にてなければならず。』『武士たる者は、武勇に大高慢をなし、死狂ひの覚悟が肝要なり』・・・・・・正しい狂気、というものがあるのだ」
「若きサムライのための精神講話」(抄)では、著者はナチスについて以下のように述べています。
「ナチスは、ニヒリズムの革命といわれているが、それは単にインテリ中間層の心理的不満や、ニヒリズムから生れたものではなく、現実に膨大な失業者群と経済的破綻があって、そういう現実的社会的基盤の上で、ナチスが勢いを得たのであった。しかし、いまの学生たちの革命には、このような万人を首肯させるに足る原因も理由も欠けているのに、世界的に波及して、あらゆる都市を動乱の渦に巻き込むような勢いを、見せている」
4「エロスと政治について」の「心中論」では、著者は述べます。
「美しい人は夭折すべきであり、客観的に見て美しいのは若年に限られているのだから、人間はもし老醜と自然死を待つ覚悟がなければ、できる限り早く死ぬべきなのである。平均寿命の延長のおかげで、他の遊星から地球を眺めたら、地球の表面は年毎に醜くなってゆきつつあるだろう。『人生で最も善いことは、生れて来なかったということであり、次に善いことは、できるだけ早く死ぬということである』とミダス王は森で会ったサテュロスから告げられた」
「精神の発明」という興味深い問題については、以下のように述べます。
「動物には精神というものがない。人間だけにそれがあるのは、人間が徐々に自然を征服して、殊に男が、交接と繁殖ののちに残された空しい役割に翻然と目ざめ(女にはそのあとに育児という仕事が残っている)、死にいたるどうしようもない閑暇を埋めるために、精神を発明したのであろう。精神というものは、多分、起源的には男性の専有物であり、男性の武器であったが、その武器によってまた自ら傷つけられて、精神が孤立して、女性の領分である大地から絶縁される憂目にも会ったのであった」
また、心中の美しさは全く幻影的なものであるとして、著者は述べます。
「文楽の人形で見たって『知死期』の苦悶はいいかげんグロテスクな見物であるが、人間の死にざまがそんなに美しかろうはずがない。しかし、当人たちは陶酔と幻影をたよりにして死に、世間の人も幻影をしか見ないのであるから、警官や医師やその場の立会人の見た心中現場は、忽ち人間の記憶の中へ埋没してしまって、どうでもよくなってしまうのであるらしい」
続けて、著者は以下のように述べています。
「大体心中や自殺が人里離れた場所を選ぶのは、死をできる限り『主観的な』事件にしたいという欲望からであろう。他人の目はその死を客体に化してしまう。恋人の目だって他人の目にはちがいないのであるが、心中が自殺とちがう点は、やはりお互いがお互いの死を眺め、主観的な死と客観的な死を同時に味わい得るという点にあろう。いや、一人きりの自殺ですら、ある人々はビルの屋上から人通りの多い路上に身を投げて、自分にとっては全く主観的な死を、すぐさま客体化したいという熱烈な野望に燃えている」
5「死を夢見る肉体について」の「聖セバスチャンの殉教」では、実在性が疑わしいという聖セバスチャンの像を取り上げ、著者は述べています。
「光りとは、人間性、肉体、官能性、美、青春、力、などの諸要素であり、ルネッサンスが復活しようとしたものは、正にキリスト教内部において、これらの異教的ギリシア的要素が窒息しはじめていた3世紀の、最後の黄昏の光りの中に、同じように見出された。セバスチァンの殉教は、二重の意味を持っているかのようであった。すなわち、この若き親衛隊長は、キリスト教徒としてローマ軍によって殺され、ローマ軍人としてキリスト教によって殺された。彼はあたかも、キリスト教内部において死刑に処せられることに決っていた最後の古代世界の美、その青春、その肉体、その官能性を代表していたのだった」
6「終わり方の美学」の「団蔵・芸道・再軍備」では、著者は「芸道とは何か?」と問い、以下のように述べています。
「それは『死』を以てはじめてなしうることを、生きながら成就する道である、といえよう。これを裏から言うと、芸道とは、不死身の道であり、死なないですむ道であり、死なずにしかも『死』と同じ虚妄の力をふるって、現実を転覆させる道である。同時に、芸道には、『いくら本気になっても死なない』『本当に命を賭けた行為ではない』という後めたさ、卑しさが伴う筈である。現実世界に生きる生身の人間が、ある瞬間に達する崇高な人間の美しさの極致のようなものは、永久にフィクションである芸道には、決して到達することのできない境地である。『死』と同じ力と言ったが、そこには微妙なちがいがある。いかなる大名優といえども、人間としての団蔵の死の崇高美には、身自ら達することはできない。彼はただそれを表現しうるだけである」
また、根本原理が「死なない」ということにある場合、いかに危険なスポーツも芸道に属し、現実のフィクション化にあずかり、仮構の権力社会に属しているとして、著者は以下のように述べます。
「剣道も竹刀を以て争う以上、『死なない』ということが原理になっており、本来、剣道には一本勝負しかありえぬ筈であるが、三本勝負などが採用されて、スポーツ化されている。それはすでに、芸道の原理が採用されたことを意味する。その勝負にあるのは死のフィクション化であって、『決死』とはもはや言えない。柔道の三船十段は、エキジビションではいつも必ず勝つことになっていて、うっかり十段を負かす弟子があると、烈火の如く怒って初段に降等させたという噂があるが、これは三船十段が、柔道のフィクション化的性格をよく知っていた証拠になる。スポーツにおける勝敗はすべて虚妄であり、オリンピック大会は巨大な虚妄である。それはもっとも花々しい行為と英雄性と意志と決断のフィクション化なのだ」
さらに著者は「武士道とは何であろう?」と問い、以下のように述べます。
「私はものごとに『道』がつくときは、すでに『死』の原理を脱却しかかり、しかも死の巨大な虚妄の力を自らは死なずに利用しはじめる時であろう、と考える。武士道は、日常座臥、命のやりとりをしていた戦国時代ではなくて、すでに戦国の影が遠のき、日生活における死が稀薄になりつつあった時代に生れた」
「私の中のヒロシマ―原爆の日によせて」では、著者は述べます。
「ヒロシマ。ナチのユダヤ人虐殺。まぎれもなくそれは史上、2大残虐行為である。だが、日本人は『過ちは二度とくりかえしません』といった。原爆に対する日本人の民族的憤激を正当に表現した文字は、終戦の詔勅の『五内為ニ裂ク』という一節以外に、私は知らない。そのかわり日本人は、8月15日を転機に最大の屈辱を最大の誇りに切りかえるという奇妙な転換をやってのけた。1つはおのれの傷口を誇りにする”ヒロシマ平和運動”であり、もう1つは東京オリンピックに象徴される工業力誇示である。だが、そのことで民族的憤激は解決したことになるだろうか」
そして、「愛国心」の冒頭で著者は以下のように述べるのでした。
「実は私は『愛国心』という言葉があまり好きではない。何となく、『愛妻家』という言葉に似た、背中のゾッとするような感じをおぼえる。この、好かない、という意味は、一部の神経質な人たちが愛国心という言葉から感じる政治的アレルギーの症状とは、また少しちがっている。ただ何となく虫が好かず、そういう言葉には、できることならソッポを向いていたいのである。この言葉には官製のにおいがする。また、言葉としての由緒ややさしさがない。どことなく押しつけがましい。反感を買うのももっともだと思われるものが、その底に揺曳している」
