- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2016.12.03
『百歳までの読書術』津野海太郎著(本の雑誌社)を読みました。
歩きながら本を読む「路上読書」の実践者が、70代を迎えてからの「幻想抜きの老人読書の現実」を、ざっくばらんにユーモアを交えて綴るエッセイ集です。著者は1938年福岡県生まれ。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」で演出家として活動する一方、晶文社の編集責任者として、植草甚一やリチャード・ブローティガンなど60年代、70年代の若者文化の一翼を担う書物を次々世に送り出しました。「季刊・本とコンピュータ」編集長、和光大学教授・図書館長も務め、現在は評論家です。
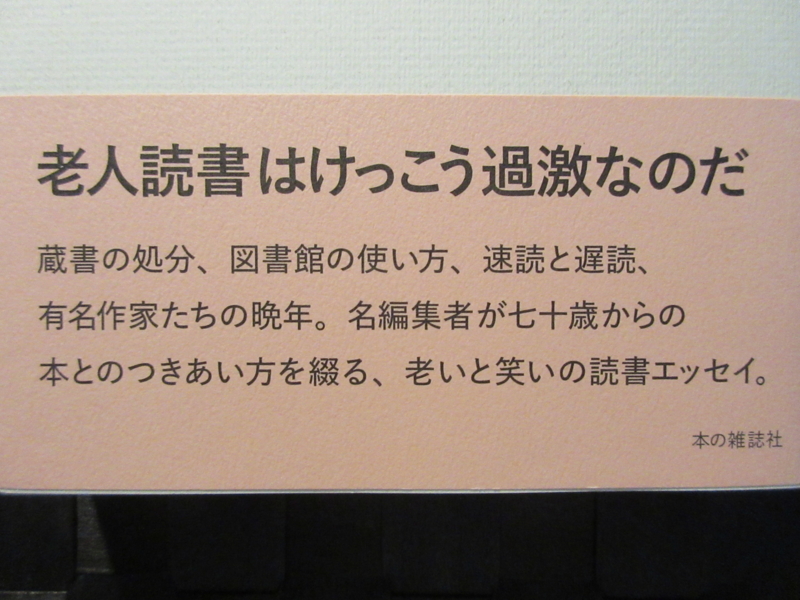 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「老人読書はけっこう過激なのだ」「蔵書の処分、図書館の使い方、速読と遅読、有名作家たちの晩年。ネイ編集者が七十歳からの本とのつきあい方を綴る、老いと笑いの読書エッセイ」と書かれています。
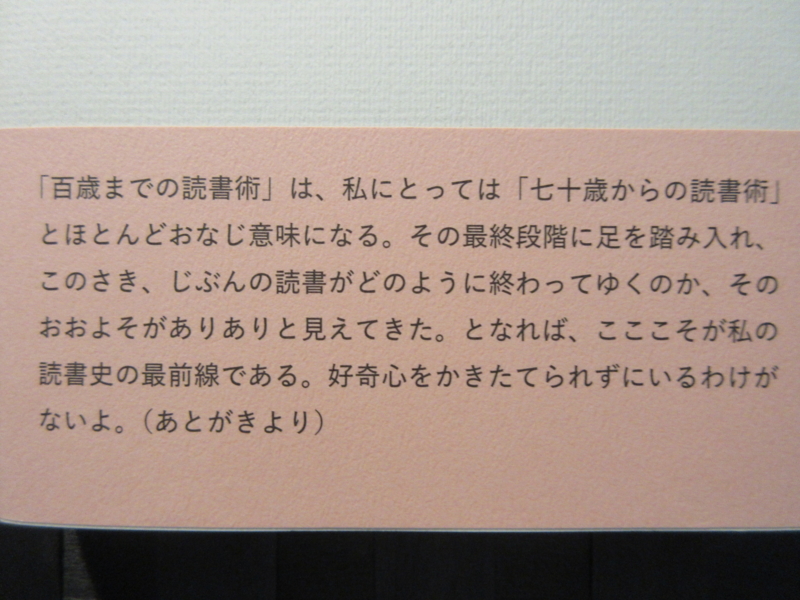 本書の帯の裏
本書の帯の裏
本書の「目次」は、以下のようになっています。
「老人読書もけっこう過激なのだ」
<壱>
本を捨てない人たち 減らすのだって楽じゃない
路上読書の終わり 新しいクセ
遅読がよくて速読はダメなのか
月光読書という夢
「正しい読書」なんてあるの?
本を増やさない法
近所の図書館を使いこなす
退職老人、図書館に行く
渡部型と中野型
<弐>
背丈がちぢまった
ニベもない話
私の時代が遠ざかる
もの忘れ日記
漢字が書けない
老人演技がへたになった
八方にでてパッと凍る
〈死者の国〉から
本から本へ渡り歩く
老人にしかできない読書
ロマンチック・トライアングル
<参>
映画はカプセルの中で
いまは興味がない
病院にも「本の道」があった
幻覚に見放されて
友達は大切にしなければ
書くより読むほうがいい
むかしの本を読みかえす
怖くもなんともない
古いタイプライター
もうろくのレッスン
「あとがき」
「まえがき」にあたる「老人読書もけっこう大変なのだ」では、著者は以下のように書いています。
「読書にそくしていうなら、50代の終わりから60代にかけて、読書好きの人間のおおくは、齢をとったらじぶんの性にあった本だけ読んでのんびり暮らそうと、心のどこかで漠然とそう考えている。現に、かつての私がそうだった。しかし65歳をすぎる頃になるとそんな幻想はうすれ、たちまち70歳。そのあたりから体力・気力・記憶力がすさまじい速度でおとろえはじめ、本物の、それこそハンパじゃない老年が向こうからバンバン押しよせてくる。あきれるほどの迫力である。のんびりだって? じぶんがこんな状態になるなんて、あんた、いまはまだ考えてもいないだろうと、60歳の私をせせら笑いたくなるくらい」
「渡部型と中野型」では、著者は読書論の名著である渡部昇一著『知的生活の方法』と中野重治著『本とつきあう法』の2冊を比較します。そして、渡部氏の読書法を「所有中心の読書」として嫌う著者は、『本とつきあう法』の内容について以下のように述べます。
「本は物質、端的にいってしまえば、モノ、物体である。したがって、鉛筆でぐいぐい太い線をひっぱるとか(同書所収「わが文学的自伝」)、必要とあらば1冊の本をパカッと2つに割ってしまうとか(おなじく「本とつきあう法」)、そうした乱暴な、それこそ肉感的なつきあい方もできる。そういう度量の大きな『品物』こそが本なのだが、こうした豪快な面だけではなく、モノ、物体としての本とのつきあいには同時に、なんともこまった一面がある。 『場所をとる。そのうえ斤目がかかる』 斤目というのは『重さ』ね。その結果、本が屋根裏の書庫からはみだし、床が抜けそうになる」
さて、芝居通である著者は、歌舞伎の名優であった18代目勘三郎と会ったことがなく、その舞台すら、TV観劇をのぞけば、いちども見たことがないそうですが、「私の時代が遠ざかる」の中で「にもかかわらず、その死にうけたショックの度合は、なかでもっとも大きい」として、以下のように述べます。
「安岡さんや丸谷さんや小沢さんの死は、年齢からみても、ご本人たちがどう考えていたかは別にして、なすべきことをなしおえたのちの大往生といっていい。私個人にひきつけていえば、知的にも娯楽の面でも、若いころからいろいろお世話になった方々がいなくなり、歴史にしめる『私の時代』が、またすこしうしろに遠ざかったという感じにちかい。 しかし勘三郎さんの死からうけたショックは、それとは性質がちがう。いってみれば、過去よりも未来にかかわるショック。なにしろ私は、これまでずっと勘三郎さんのことを『私の歴史』ではなく、よりつよく『私が消えたあとの歴史』に属する人だと考えてきたのでね」
「老人演技がへたになった」では、著者は「戦後の映画俳優は、じぶんよりずっと年長の人間、つまり老人を演じるのがうまかった」と述べ、その実例を以下のように挙げます。
(1)笠智衆『東京物語』1953年
(2)三船敏郎『生きものの記録』1955年
(3)三國連太郎『異母兄弟』1957年
そして、著者は以下のように述べています。
「ちょうどいい順番になった。というのも、私が『なぜ往年の映画俳優はあんなに老人の演技がうまかったのだろう』と最初に思ったのが、2002年、(1)の『東京物語』を10何年かぶりに見なおしたときだったからだ」
(1)の『東京物語』について、著者は以下のように述べます。
「その前年からつとめるようになった大学で『老いる』というテーマの授業をやろうと思いたち、まず最初に『東京物語』をみんなで見ることにした。そのため資料にあたるうちに、この映画に出演時の笠智衆が49歳だったことを知っておどろいた。だって、あの平山周吉(役名)さん、どう見ても70代、いまふうにいえば、まぎれもない後期高齢者でしょうが。その、よれよれに年老いた夫の役を、笠智衆49歳が14歳も年長の東山千栄子を相手どって、一抹の不自然さもなく、みごとに演じとおしている。もちろん東山千栄子が、あのときまだ63歳だったというのもすごいがね。ちなみに監督の小津安二郎は50歳。うーん」
また、(2)の『生きものの記録』について、著者は述べます。
「1954年、ビキニ環礁の水爆実験で焼津のマグロ漁船が被曝した。この第五福竜丸事件を背景に黒澤明がその翌年に完成させた映画で、まぢかにせまった核戦争の幻影におびえ、じぶんの鋳物工場を売りはらって一家でブラジルに移住しようと狂奔する老人に三船敏郎が扮した。映画で見るかぎり、この中島喜一老人はたぶん70代前半。とすると三船自身はあのとき何歳だったのかね。いそいで調べたら、なんと役の年齢のほぼ半分の35歳。若いというもおろか、その前年に『七人の侍』で菊千代を演じたばかりだったことを考え合わせると、信じられないくらい鮮烈な老人演技だったことがわかるだろう」
そして、(3)の『異母兄弟』について、著者は述べます。
「三國連太郎は三船敏郎の3歳年下で、この映画を撮ったときは34歳。おなじ年に日活のアクション映画『鷲と鷹』で11歳下の石原裕次郎と互角に殴り合い、みごとに鍛え上げた上半身を見せている。したがって壮年期の鬼頭範太郎を演じるのにさしたる努力は要しなかったはずだが、権力も体力も、すべてを失って廃人化した70すぎの老人となると、そうはいかない。それでもかれは持ちまえの異様なまでの集中力で鬼頭役を演じきったらしい。なのに私は、肝腎の、さぞすさまじかったであろうかれの老人演技をまったくおぼえていない。わずかに記憶にのこっているのが、この役を演じるのに三國が歯を10本抜いた、といったゴシップだけというのがくやしい」
さらに、著者は以下のように述べています。
「笠智衆(1904年生まれ。以下おなじ)、三船敏郎(1920年)、三國連太郎(1923年)の老人演技にみなぎる説得力のつよさにくらべると、それにつづく、大滝秀治(1925年)、仲代達矢(1932年)、山崎努(1936年)、緒形拳(1937年)といった俳優諸氏の近年の老人演技は、どことなく迫力を欠く。いや、へたというのではないですよ。好きな俳優たちだし、技術的なうまさからいえば、50年代の三船や三國よりうまいと思う。それぞれに工夫をこらして独特の老人像をつくってみせてもくれた。それなのに、むかしとちがって、かれらのつくりあげた魅力的な老人像が若い人間たちをもグイと引きよせ、金縛りにするというような事態は起こらなかった」
では、著者は現在の映画俳優の演技に失望しているのでしょうか。 いや、どうやら、そうではなさそうです。 著者は「いまに興味がない」で、以下のように述べています。
「私は70歳をこえたころから近所のシネコンで、これまで長いことご無沙汰していた日本映画を見るようになった。そして『デスノート』で松山ケンイチ、『アフタースクール』で堺雅人、『悪人』で妻夫木聡の演技にはじめて接し、ああ、こういう演技はむかしの俳優にはむずかしかったろうなと、あのときの樹木希林のことばを思いだした。 むかしの俳優のうまさといったものがあるなら、いまの俳優にしかないうまさもある。ひとつの基準ではかって上下をきめることはできない。私は彼女のことばをそう解釈する。私だって、まだ生きている以上、なかなかジャン・ギャバンやハンフリー・ボガートや志村喬だけでは満足できない。ジョニー・デップやベネディクト・カンバーバッチみたいなくさい連中も、けっこう好きだしね。むかしの老人だけが正しい老人ではない。いまの世の中には、そうではないタイプの老人だっていくらもいるのだ」
そして「あとがき」で、著者は以下のように述べるのでした。
「齢をとれば人間はかならずおとろえる。 いや逆かな。人間一般ではなく、ひとりの生身の人間にとって、最初にやってくるのは心身の衰退であり、ややおくれて、そのおとろえこそが世にいう『老い』であったことにハッと気がつく。そういったほうがむしろ正確だろう。 私の場合でいえば、そうと気づいたのは70代にはいってまもなく、待ち合わせた友人を何度もすっぽかすとか、つまずくはずのない場所でつまずくとか、そんな事態がひっきりなしに生じるようになってから。 ―なんじゃ、これは? なにしろじぶんのうちに、日々、新しいなぞが生じるのだから、そのつど、ちょっとあわてる。でも、それほどには嘆かないし、抵抗もしない。それらのなぞの現象を、どちらかといえば面白がって観察するうちに、いつしか疑問の余地のない老人と化していたじぶんに気がつく。そのようにして私はとつぜん老人になった。いってみれば、そんなおっちょこちょいの好奇心老人にね」
