- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2016.12.27
『心に感じて読みたい送る言葉』齋藤孝著(創英社/三省堂書店)を読みました。著者は明治大学文学部教授で、国語教育の第一人者です。
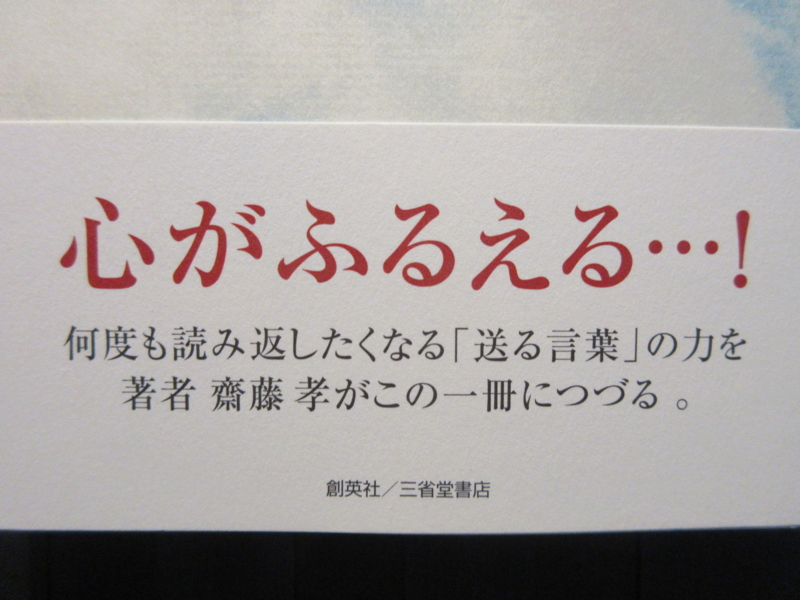 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「心がふるえる・・・!」と大書され、続けて「何度も読み返したくなる『送る言葉』の力を著者 齋藤孝がこの一冊につづる」とあります。
また帯の裏には、「あの声、あの笑顔、あの姿、大切な人へ あなたは どんな言葉を 送りますか。」と書かれています。
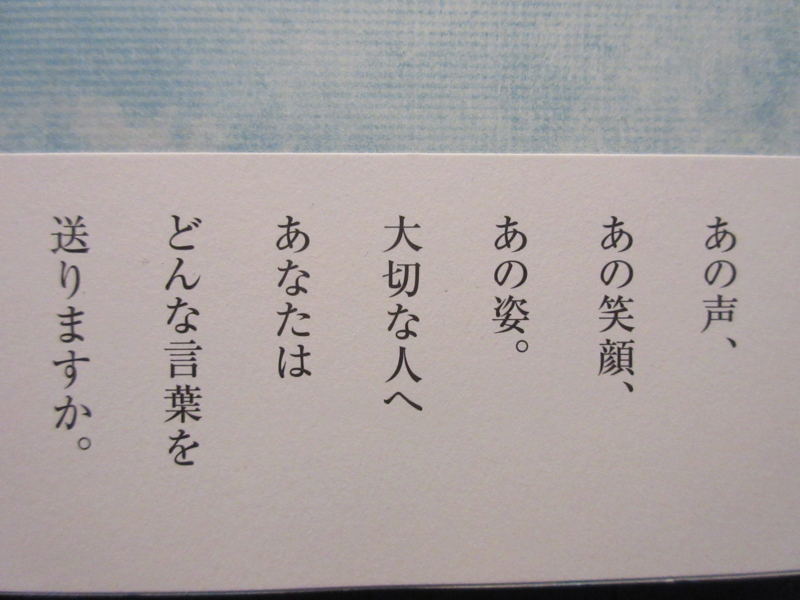 本書の帯の裏
本書の帯の裏
本書の「目次」は以下のような構成になっています。
「はじめに」
一章 作家編
二章 文化人編
三章 映画・芸能人編
四章 政治家・経済人編
五章 スポーツ選手編
六章 「作品の中のあの人」編
「おわりに」
「主な参考文献および出典」
「はじめに」の冒頭を、著者は「言葉や文章は紙に書かれたものであっても肉声で読み上げたほうが生き生きとします。とりわけ弔辞は大勢の前で詠み上げられることが前提になった言葉です」と書き出しています。
また、「必ずしも不断から文章が上手いわけではない人のものでも、弔辞には不思議なくらいに共感できる」として、その理由を述べています。
「弔辞の言葉は特別だからです。弔辞には、気持ちがこもっています。
死と真剣に向きあうことへの緊張感、死者の魂に寄り添うことへの責任感、故人を失った悲しみ、大事にしてもらったことへの感謝の気持ち、そういった様々な感情が湧き上がるなかで書くからこその特別な力が宿ります。その力を皆さんにも味わってもらいたくてこの本を書きました」
死は大切な人を奪うものでありながら、必ず訪れるものです。
しかしながら、著者は以下のように述べています。
「大切な人を失ったショックから立ち直れないでいるとき、死をそのまま受け止めるにはあまりにもつらすぎるとき、人間は死を祀りごとに変える文化を生み出しました。その祀りごとで中心の役目を果たすものが『言葉』です。
特に弔辞は、お経や祝詞や賛美歌のような儀礼としての言葉ではなく、なんらかの縁で故人とつながりのあった人が思い出をたぐりよせながら詠む言葉です。故人の声、眼差し、笑顔、一瞬の表情や仕草、大事にしていたこと、打ち込んでいたこと、最後まで変わらなかった信念など、その人の生き様を描き出す言葉です」
一章「作家編」では、三島由紀夫の葬儀で作家の武田泰淳が読み上げた弔辞を紹介し、著者は以下のように述べています。
「三島由紀夫の人生は”劇的”だ。『憂国』という、かなり若い時期に書かれて三島自ら映画化もした作品があり、そのなかに男の美学として切腹が描かれている。駐屯地のバルコニーで行った最後の演説も当日の現場の様子も今はネットでかなりわかるが、自分の人生を作品化するようなところが三島にはあったのではないか。
その後の日本社会を見ると、三島が憂いたことには真実の部分がかなりあったと思わされる。私は精神と心は違うと思っている。
彼が予測して憂いたとおり、今、日本には自前の精神を失った人が増えているのではないか。心の悩みを精神の強さでカバーできる人が少なくなってしまったのではないか」
原民喜の葬儀で作家の埴谷雄高が読み上げた弔辞は、故人を「あなたは~でした」と語りかけるものでした。この弔辞について著者は述べます。
「弔辞で『あなたは~でした』という言い方をするのは大変な勇気がいる。
やり直しがきかない最後の別れの場で、他人の人生を要約して言い切るのは誰でも怖い。間違っていたらどうしようという不安もある。
しかし、弔辞を託された以上、そういった恐れは排除して『彼は~でした』とはっきり存在証明をしてあげることが、死者への礼儀であり責任であると私は思う。それは故人のためだけではなく、葬儀に集まった人たちのためでもある。亡くなった直後は亡くなったという事実の位置づけが心のなかでなかなか定まらないものだ」
また著者は、原の霊に向けた埴谷の言葉について述べます。
「大事なのは故人が大切にしていたことにみんなで思いを馳せ、故人の人生を深いところで受け止めることだ。言葉の力を借りてそれができるのが弔辞のよいところである。
現代は核家族化が進んだこともあって家族葬が増え、大勢の会葬者で死者を送るタイプの葬儀が減ってきている。弔辞を詠まずに喪主の挨拶だけで終わる葬儀もあり、簡素化の流れは止められなさそうである。しかし、その流れが行き過ぎてしまうと寂しい。弔辞の意義を見直したいものだ」
四章「政治家・経済人編」では、岸信介の葬儀で中曽根康弘が読み上げた弔辞を紹介し、著者は以下のように述べています。
「作品としての弔辞のおもしろさは、人の人生がギュッと短く、的確に要約され、エネルギーの高い文章で読めることだ。文章を考えるのはそれだけでエネルギーがいることなのに、最後のお別れの場で全員の前で詠み上げられるとなれば、弔辞を考える人は大変なエネルギーをその文章に注ぐ。短いなかにものすごい量のエネルギーが込められた文章―それが弔辞だ。聞く人、読む人はそのエネルギーに心を揺さぶられるのである」
六章「『作品の中のあの人』編」では、大滝詠一の永遠の名曲「君は天然色」の歌詞が紹介され、著者は次のように述べています。
「歌詞を書いたのは松本隆さん。肉親の死のエピソードというのは、若くして亡くなった松本さんの妹さんのことである。アルバムが発売されて4年たった1985年12月18日の朝日新聞夕刊に松本さんが寄せたというエピソードを、今はネットでも見ることができる。」
続けて、著者は以下のように書いています。
「妹さんはもともと体が弱く、松本さんは子ども時代から、兄として妹を守らないといけないという気持ちが非常に強かったそうだ。その妹さんが、松本さんが大滝さんから歌詞を依頼されたときに、心臓発作で倒れた。他の作詞家に替えてくれと申し出た松本さんに、大滝さんは『今度のは松本の詩じゃなきゃ意味がないんだ』と答えてくれたそうである。
その数日後、妹さんが息を引き取り、最後を看取った松本さんは渋谷の街がモノクロームに見えるほどの精神的ショックを受け、しばらく歌詞が書けなかった。そんな松本さんを大滝さんは、復活できるまで3ヶ月間、催促もせず、何も言わずに待ってくれた。この歌はこんな背景を持っている」
さらに、著者は以下のように書いています。
「『世界が白黒になっちゃったよ。色を点けてくれよ』というお願いが、死んで永久に会えなくなった妹に向けた兄の心の叫びだったと知ると、また会うこともなくはないかもしれない恋 人への言葉として解釈していたときよりも、歌詞が一層切なく胸に響く。
大事な人の死に直面したときに人間がどんな感覚になるか―それは世界が色を失うような感覚なのだと。その意味で、いわゆる追悼の重い響きを少しも感じさせずに死を軽やかに歌いきったこの歌もまた、時代を継いで記憶に残るべき追悼の言葉の1つだと思う」
そして著者は、以下のように述べるのでした。
「私は『君は天然色』をこれまでに何回聞いたかわからない。でも、松本隆さんの歌詞の特質をあらためて思いながら聞くと、『人はみんな、他者の存在によって世界を色付けてもらって生きているんだな』と聞くたびに感じる。そして、やっぱり、新鮮に感動するのだ」
また、ユーミンの「ひこうき雲」の歌詞を紹介し、著者は述べています。
「ユーミンこと松任谷由実さんにはこの『ひこうき雲』を入れて4つぐらい、死についての歌があるそうだ。子ども時代やデビュー前夜の頃を語った『ルージュの伝言』(角川書店・1984年)という本によると、この歌の背景には2つの『若い死』があった。
1つは小学校の同級生の死で、その子は当時から筋ジストロフィーを患っており、中学に上がって別々の学校に通いだしてからは交流がなかったが、高校1年になってその子が他界し、彼女は葬儀に参列した。そして遺影に向かうと、そこには自分の知らない高校生の顔の彼がいた。そのときに、彼女は『昔のことはフローズンになっちゃうんだな』と感じたそうである。その2年後、近所で高校生どうしの飛び降り心中があり、『若いときの死』についてまた感じるところがあった。それらを歌にしたのがこの作品だという」
さらに、著者は以下のように述べています。
「昨日まで身近にいた人が今日はいない。人間にとってこれほど大きい喪失感はないだろう。しかもそれが自分の家族であれば、ご遺族のダメージは想像してもしきれない。そんなときには、その喪失や欠如を補うイメージが何かしらあってほしい。
2000年代半ばに『千の風になって』という曲が大ヒットしたのも、『ひこうき雲』と同じく、曲のイメージで実際に救われた人たちがそれだけ多かったからだと思う」
「おわりに」では、その冒頭を著者は以下のように書き出しています。
「死と言葉には古くから強いつながりがあります。古代中国では甲骨文字が吉兆を占う行為のなかで生まれ、それが発展して漢字になりました。古代エジプトでは王の墓碑や神殿に刻むヒエログリフ(聖刻文字)が発達し、王の業績や宗教的な託宣を現代まで伝えています。両方とも死者や神と交信するためのもの、祭祀のためのものです。
弔辞はまさに、死者を送る祭祀のときに述べられる言葉です。日本人には言霊信仰がありますが、弔辞を書いたり詠み上げたりする瞬間はまさに言葉に言霊が宿る瞬間でしょう」
また、著者は「言葉」の持つ力について以下のように述べています。
「言葉には『その人が死んだ』という事実を変える力はもちろんありません。でも、事実の意味を変える力はあります。死を単に『消えてなくなった』という意味に終わらせずに、死んだという事実を『だから何かが生まれる』と積極的な意味に変えてくれます。弔辞には死を機会として他の人たちの心にもその人の生をくっきりと浮かび上がらせ、刻んで残させる力があります。弔辞がまったくないと、亡くなった人の生はなんとなくぼんやりしたままで、どこに残ったか、誰の心に残ったかわからないままになってしまう。それは寂しいのではないでしょうか」
さらに著者は、葬儀および弔辞の意味について以下のように述べます。
「キリスト教の葬儀は死者が迎えられる神の国を讃える儀式なのでまた別ですが、仏式葬儀はお坊さんの読経で終わりにするケースが結構多いのではないでしょうか。お経には意義がありますが、故人のための固有の言葉ではありません。けれども弔辞は、誰かが詠んでいるあいだは参列したみんながその内容に耳を傾け、『そうそう。そういうことあったなあ』と思い出したり、『そんな面もあったんだ。知らなかったな』と気付いたりで、その故人の固有の生を思うことにみんなが集中しています。
そうやってみんなで一緒に思うことが、故人をあちらの世界にスムーズに送り出してあげることになるのではないか。葬儀を成り立たせている中心は弔辞ではないかというのが私の考えです。弔辞を詠む習慣が薄れてきてなおさらそう感じるようになりました」
そして最後に、著者は「死」について以下のように語るのでした。
「死が固有の扱いをされないと、まだ生きていく私たちのこれからの生も、誰が生きても同じものとして扱うことになります。でも、それはありえない。実感としてありえない。他者と出会い、関わり、日常を生きていくことそのものが固有の生をつむぐことなのですから。何気ないやりとり、ただの相槌、一瞬の表情や声、その言葉、そういったすべてが、人が生きるということの意味であり深さだと思います。弔辞はそんな人間の生というものの在り方を私たちに教えてくれます。ぜひ、心に感じながら何度でも読み返してもらえるとうれしいです」
