- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2017.01.05
『知の進化論』野口悠紀雄著(朝日新書)を読みました。
「百科全書・グーグル・人工知能」というサブタイトルがついています。
著者は1940年東京生まれ、64年に大蔵省入省。一橋大学教授や東京大学教授を経て、現在は早稲田大学ファイナンス総合研究所顧問です。専攻はファイナンス理論、日本経済論で、大ベストセラーになった『「超」整理法』(中公新書)をはじめ多くの著書があります。
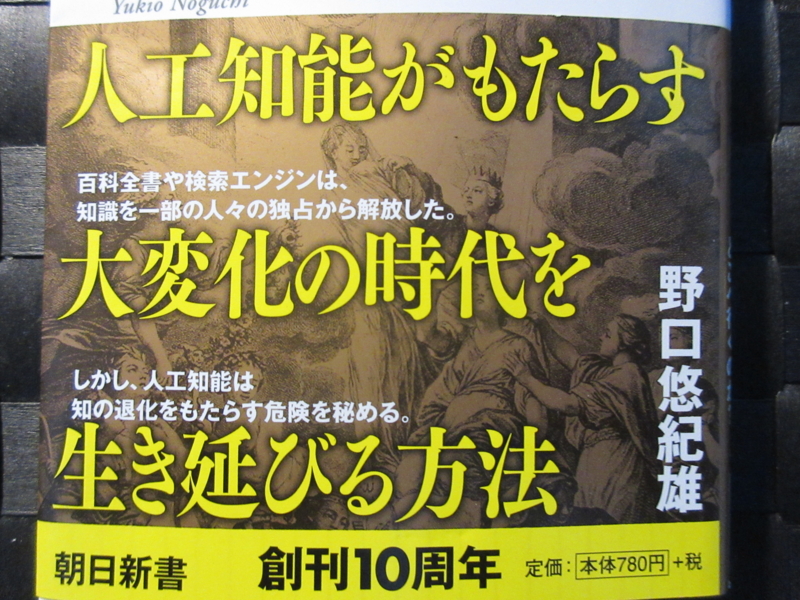 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「人工知能がもたらす大変化の時代を生き延びる方法」と大書され、「百科全書や検索エンジンは、知識を一部の人々の独占から解放した。しかし、人工知能は知の退化をもたらす危険を秘める」とあります。
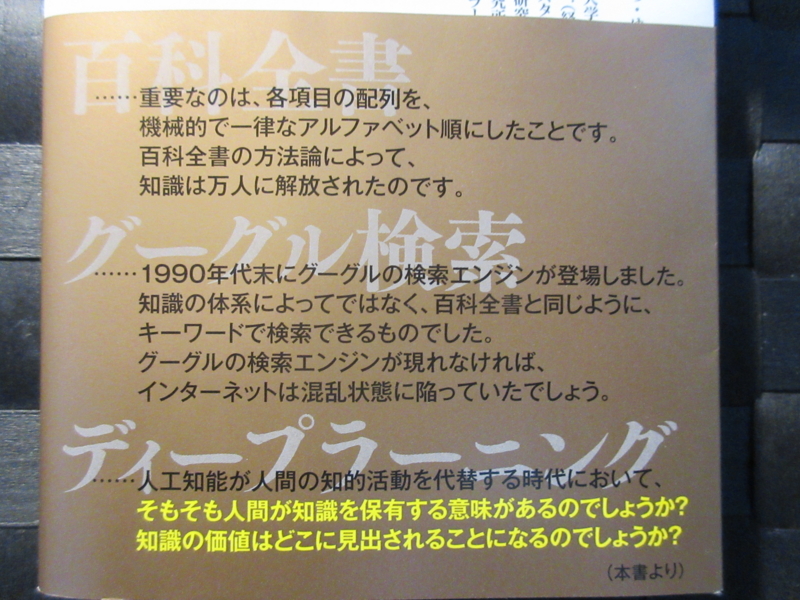 本書の帯の裏
本書の帯の裏
カバー前そでには、以下のような内容紹介があります。
「グーテンベルク・インターネット・人工知能。情報技術の革新は、世界に何をもたらしたか? 中世以前、知識とは、特権階級の独占的所有物だった。活版印刷の登場によって万人に開放され始めたそれは、インターネットの誕生で誰にでもタダで手に入るものとなった。そして人工知能の進化が、本質的な変革の時代の到来を告げる。秘匿から公開へ、有料から無料へ、そして人間からAIへ。『知識の拡散』の果てに、ユートピアは現れるのか? 大変化の時代を生き抜く指針を示す、知識と情報の進化論」
本書の「目次」は、以下のような構成になっています。
「はじめに」
第1章 かつて知識は秘密にされていた
第2章 百科事典は知識を万人に開放した
第3章 インターネットで情報発信者が激増した
第4章 検索という方法論
第5章 SNSやキュレイションで情報拡散スタイルが変化
第6章 知識は秘匿すべきか、公開すべきか?
第7章 人工知能の進歩で知識への需要はどう変わるか?
「索引」
第1章「かつて知識は秘密にされていた」の冒頭を、著者は以下のように書き出しています。
「印刷技術の発明以前、知識や情報を得るためには、大変なコストが必要でした。このため、知識や情報は、一部の権力者や専門家にしか得られないものでした。そうした人々は、知識を独占し、自らの権益を守ったのです」
著者は「ギルドによる知識の独占」として、以下のように述べます。
「いまでは、知りたいと思えば、本やインターネットからいくらでも知識や情報を得ることができます。しかし印刷技術の発明以前、知識を得ることは簡単ではありませんでした。活版印刷が普及する以前、文書の複製は書写によっていました。これは、大変な時間と努力を要する作業です。このため、書籍はわずかな部数しか存在せず、それを見ることができたのは、ごく限られた人々だけだったのです。つまり、知識は一部の人々によって独占されていました。技術的な知識を独占していたのは、ギルド(専門家集団)です。中世のヨーロッパでは、職人はそれぞれの職種ごとのギルドに属し、ギルド内部で教育されていました」
著者は、2007年に刊行された『一六世紀文化革命 1』山本義隆著(みすず書房)の内容を紹介しながら、以下のように述べています。
「まず、冶金術と錬金術。この技術は魔術のようなものと考えられ、意図的に曖昧な表現やシンボル、あるいは、伝統的宗教儀式の中での秘密の言葉で語り伝えられていました。それは、少数の者にしか理解できないようにするためでした。この秘密の言葉は、日常の言葉では伝達できない体験を表現するものであり、技術の奥義は、シンボルの隠された意味に秘められていると考えられていました。このため、精錬技術について中世に書かれたものは、ほとんど残されていないそうです」
また、著者は「聖書は普通の人が読むものではなかった」として、以下のように述べています。
「中世までの時代、聖書は、修道院の聖職者によってラテン語で書写されていました。聖書はラテン語記述のみが許されており、ラテン語の知識がない普通の人々が読むことはできませんでした。ラテン語は『聖なる言葉』であり、俗語(自国語)は『卑俗な言葉』であるという考えが支配的でした。したがって、『俗語に翻訳すると、神の言葉が伝わらない』とされたのです。このような差別化をすることによって、教会の権威を保とうとしました。 なお、ラテン語とは古代ローマ帝国の言葉であり、聖書とはなんの関係もありません。もともと旧約聖書はヘブル語で、新約聖書はギリシャ語で書かれていました。聖書をラテン語に翻訳したのはヒエローニムス(347頃―420頃)で、聖書が書かれてからだいぶ時代が経った後の人です」
続けて、著者は聖書について以下のように述べています。
「こうして、聖書は、聖職者だけが特権的に読むことができる『神聖な書物』となったのです。神の教えを知るためには、人々は教会に行って教えてもらう必要がありました。つまり、聖職者は、神の教えを独占することで人々を支配してきたのです。一般の人々が聖書を英語で読めるようになったのは、17世紀になってからのことです。イングランド王ジェームズ1世が『欽定訳聖書』(『キング・ジェームズ版聖書』)の編纂を1604年に開始し、1611年に刊行したことによります」
また、著者は「絵画はキリスト教布教の強力な道具だった」として、以下のように述べています。
「中世ヨーロッパの絵画は、ほとんどが宗教画です。ルネサンスになって、神話にテーマをとった画や肖像画が現れますが、それでも、聖書に題材をとった作品が圧倒的多数です。なぜこれほど宗教画が多いのでしょうか? これは私が考えた仮説にすぎませんが、普通の人々が聖書を読めないことを前提にして聖書を身近なものと感じさせるには、絵画に頼るのが最も効果的だったからではないでしょうか?」
さらに、著者は絵画について以下のように述べています。
「絵画は、木版印刷によって大量生産することもできます。また、聖書を読んだだけでは必ずしもはっきりしない物語を、イメージ豊かに伝えることもできます。したがって、宗教画は布教の道具として重要な意味を持ったと想像されます。私は、キリスト教のビジネスモデルに強い関心を持っています。なぜ、あれほどの成功を収められたのでしょうか?その理由の1つは、宗教画の積極的な利用ではなかったか、と私は考えています」
そして、著者は宗教画について以下のように述べています。
「現代の社会におけるテレビの役割を宗教画が果たしていたと考えることができます。ただし、絵画だけでも、物語を理解することはできません。例えば、『受胎告知』の画の右に描かれた女性は、なぜ複雑な表情をして驚愕しているのか? 左にいる人物は誰なのか? これらは、教会で聖職者の説明を受けて初めて分かるものです。つまり人々は、絵画によって物語に興味を持ち、それを聖職者の説明で理解する。絵画と聖職者の説明と、その奥にあるラテン語で書かれた聖書。これらが三位一体となってキリスト教の布教に用いられたのではないでしょうか」
著者は「印刷技術が宗教改革を支えた」として、以下のように述べます。
「ドイツの貧しい修道士、マルチン・ルター(1483―1546)は、著作を印刷することによって、自らの主張を広げることに成功しました。大量に印刷された宗教パンフレットや出版物が、それまでは一時的で局所的なものにとどまっていた宗教改革の運動を、広範で持続的なものに変えたのです」
また、活字本について、著者は以下のように述べています。
「活字本の作成は、かなりの資金を要する事業であったにもかかわらず、ほぼ半世紀の間に、ヨーロッパ全土の主要都市に広がりました。これは、当時としては驚異的な速度です。1512年から13年にかけて書かれたニッコロ・マキャベリの『君主論』は、それまで隠蔽されてきた権力の秘密を暴露しました。16世紀の宗教改革に続いて、17世紀のピューリタン革命、18世紀末のフランス革命などが起こりました。これらは、活版印刷が生み出す活字媒体(新聞、雑誌、パンフレット、単行本)なしには起こりえなかったことです」
さらに印刷術について、著者は以下のように述べています。
「印刷術の発明によって、初めて正確な図があるマニュアルが可能になり、知識の公開が可能になったのです。透視図法(遠近法)や機械工学のための図法は、木版画や銅版画を挿図に有する印刷書籍が登場し、原画と寸分たがわぬ複製を数多く作れるようになって、その真の威力を発揮することになります。それが達成されたのは15世紀末になってからです。これが、16世紀以降の科学と技術の急速な発展のひとつの背景になりました」
印刷は、自然科学の発展にも大きな影響を与えました。
「研究成果を発表しなかった人々」として、著者は以下のように述べます。
「コペルニクスがそれまで信じられていた天動説に重大な欠陥を見出したのは、印刷物の普及によって天文学者が利用できる学術書や数表が大きく変化したためだといわれます。それまでは遠方に行かなければ目にすることのできなかった多くのデータを、印刷物を通じて容易に入手できるようになったのです」
著者によれば、知識は体系的であるのに対して、情報は断片的です。あるいは、「情報を秩序立てて体系的に組み上げたものが知識である」と言うこともできるでしょう。著者は、「戦争を例にとれば、新しい兵器を製造するために必要な情報の体系は、『知識』です。それに対して、戦場における敵軍の動向などは、普通は知識とは呼ばれず、情報と呼ばれます」と述べています。
そして、「知識や情報の特異な性質」として、著者は述べるのでした。
「書物が手書きの書写でしか複製できなかった時代には、排除は容易であり、かつ利用者の拡大に必要な限界費用が、かなり高いものでした。ところが、印刷技術の発明が、この状況を大きく変えました。複製のために限界費用を大きく低下させる一方で、対価を支払わない人の排除が困難になってきたのです。これは、社会の構造を大きく変えることとなりました。現代におけるインターネット革命は、この状況をさらに推し進めました。利用者の拡大に必要な費用はゼロに近くまで低下し、対価を払わない人の排除が著しく困難になってきています。これは、情報や知識に関わる経済活動のビジネスモデルに甚大な影響を与えました。料金の回収が困難になったため、これらの活動が経済的に立ち行かなくなる場合が増えたのです。新しい知識が生産されなくなれば、社会の進歩は阻害されます。われわれは、この問題に対して、まだ満足のゆく解決策を見出していません」
第2章「百科事典は知識を万人に開放した」では、18世紀フランス革命当時の「百科全書派」の人々が取り上げられます。彼らは知識を万人のものにしたいと願い、『百科全書』(アンシクロペディ)の編纂を計画しました。編集はドゥニ・ディドロ(哲学)、ジャン・ル・ロン・ダランベール(数学・物理学)が主となり、シャルル・ド・モンテスキューやヴォルテール(本名は、フランソワ=マリー・アルエ)も協力しました。あらゆる分野の執筆者、職人、後援者等を組織し、政府の弾圧や反対派の妨害と戦いながら完成させたのです。
百科事典には重要なイノベーションがありました。「『アルファベット順』という百科全書の方法論」として、著者は以下のように述べています。
「ここで重要なのは、各項目の配列を、編集者の価値観に秩序づけられる概念の関係によるのではなく、機械的で一律なアルファベット順に並べたことです。『内容によらずアルファベット順に並べる』ということこそ、『百科事典的な方法論』の基本です。これは、使い勝手の良さというだけのことには終わりません。世界観の問題がその背景には潜んでいるのです。なぜなら、百科事典を用いれば、直接に目的の概念にたどり着くことができるからです。つまり、学問の体系を知らずとも、専門的な知識を学ぶことができるのです。分からない概念が出てきたら、その概念を説明してある項目を見ればよいのです。百科事典の方法論によって、知識は万人に解放されたのです」
百科事典の歴史において、ひときわ輝きを放っているのがイギリスの『ブリタニカ』です。著者は「『ブリタニカ』の時代」として以下のように述べます。
「『百科全書』の考えを推し進めたのが『ブリタニカ』です。 『ブリタニカ』は、もともとはスコットランドで生まれた事典です。1768年から71年にかけて、エディンバラで3巻の百科事典として発行されたのが始まりです。『ブリタニカ』が誕生した18世紀末は、啓蒙思想が広まった頃です。それまで知識階級が独占していた知識を、一般の人たちに広く普及させたいというのが、『ブリタニカ』創刊者の考え方であったと言われます。誰でも、その気になれば農学や天文学、植物学、化学などを学べるようにしたいというのが、創刊の言葉でした。 『ブリタニカ』は、200年以上刊行を続け「人類の知の宝庫」と呼ばれました。4000人以上の寄稿者と専任の編集者約100人によって書かれています。寄稿者の中には、110人のノーベル賞受賞者と5人のアメリカ合衆国大統領もおり、その分野における最高の権威もいました」
 わが実家の応接間にある各種のブリタニカ
わが実家の応接間にある各種のブリタニカ
この読書館でも紹介した『読書連弾』の書評にも書いたように、ブリタニカはとにかく凄い百科事典で、たとえば「ポピュレーション」というところを引くと、マルサスが書いていました。そこを引くとマルサスの『人口論』を読まなくても全部書いているのです。しかも1ページや2ページなどではなく、長大な論文です。それからジェームズ・ミルなども書いています。科学者でも当時の一流の学者が書いており、そういう論文の集合体がブリタニカだったわけです。渡部昇一先生の一連の著書によってブリタニカの魅力を知ったわたしは、これも神田の古書店で買い漁りました。初版のレプリカをはじめ、9版、12版などを購入しましたが、これらは今、実家の応接間の書棚に鎮座しています。
第3章「インターネットで情報発信者が激増した」では、著者は「知識は依然として必要だ」として、以下のように述べています。
「フランシス・ベーコンは、『知識は力なり』と主張しました。 しかし、これまで見てきたような変化によって、『もはや知識は力でなくなった』という見方があります。グーグルの元CIOのダグラス・C・メリルらは、『(かつては)「知識は力なり」の時代』だったが、『それは古きよき時代の想い出でしかない』と言っています(ダグラス・C・メリル、ジェイムズ・A・マーティン『グーグル時代の情報整理術』、ハヤカワ新書juice、2009年)。いまやインターネットの普及で知識は簡単に手に入るようになったため、知識は経済的価値を失ったというのです。あるいは、知識はウェブやクラウドなどの外部メモリにあればよいという意見もあります。確かに、物識りの価値は低下し、私も『超「超」整理法』の中でそう書きました」
また、情報と知識について、著者は以下のように述べます。
「新しい情報に接したとき、それにどのような価値を認めるかは、それまで持っていた知識によります。新しい情報に接しても、知識が少なければ、何も感じないでしょう。しかし、知識が多い人は、新しい情報から刺激を受けて、大きく発展するでしょう。その場合、知識が内部メモリ、つまり自分の頭の中に引き出せていない限り、それを発想に有効に使うことはできません。したがって、アイディアの発想のためには、いまでも多くの知識を内部メモリに持っていることが必要です」
第7章「人工知能の進歩で知識への需要はどう変わるか?」では、著者は「人工知能は、問題をもたらす可能性もあります」と述べます。それらは、近い将来に起こる差し迫った問題であり、著者は3つの問題を指摘します。 第1は、技術革新によって、知の退化が起こる危険です。 第2の問題は、人工知能サービスを提供できる主体が、一部の大企業に限定されてしまう危険があることです。著者は「情報技術の利用可能性は、組織の大小によって大きく左右されることがあるからです。私は、この問題を自分自身のこととして経験しました」と述べています。 第3の問題は、日本企業がハードウエア中心主義から脱却できないことです。著者は「日本のロボットは依然として産業用ロボットであり、メーカーはセンサーのようなハードウエアにしか関心を持っていません。ソフトウエアや情報が重要な要素になっているという認識がきわめて薄いのです。これは、日本の製造業が『モノづくり』を第一優先目的にしていることの結果であると考えられます。しかし、AIの時代には、モノづくりではなく、ソフトウエアが中心になります」と述べています。
また、著者は「人工知能は疑問を抱くことができるか?」として、「質問を発することによってこそ、探求が始まる」という自説を述べています。
「ニュートンは、リンゴが樹から落ちるのを見て、『リンゴは落ちるのに、なぜ月は落ちないのか?』との疑問を抱きました(よく言われるように、『なぜリンゴは落ちるのか?』と問うたのではありません)。そして、ここから彼の力学法則が出てきたのです。創造的な人は、それまで人がしなかった問いを発することによって、新しい可能性を開きます。リンゴが樹から落ちるのを見た人は、人類の誕生以来数え切れないほどいましたが、ニュートンのような問いを発した人はいませんでした。ニュートンの偉大さは、それまで誰も発しなかった問いを発したことです」
ちなみに、拙著『法則の法則』(三五館)では、「法則王」としてのニュートンについて詳しく論じています。
続けて、著者は人工知能について以下のように述べています。
「では、人工知能は、ニュートンと同じような疑問を抱くことができるでしょうか? リンゴが樹から落ち、月が天空に留まっている動画を見せたとしても、『その2つは、万有引力と力学法則で説明できる現象であり、何も不思議なことはない』と答えるだけではないでしょうか? つまり、過去にニュートンという科学者がいたからこそ人工知能の製作が可能になったのであって、人工知能がニュートンの代役を果たすことはできないと、私は思います」
著者は、「知識を得ることそれ自体に意味がある」として、以下のように述べています。
「私たちはこれまで、知識は『何かを実現するために必要な手段』であると考えてきました。本書でも、多くの場合において、知識の役割をそのようなものとして捉えてきました。経済学の言葉を使えば、『知識は資本財(または、生産財)の1つである』と考えてきたのです。しかし、知識の役割はそれだけではありません。『知識を持つことそれ自体に意味がある』ということもあるのです。これを、『消費財としての知識』と呼ぶことができるでしょう」
また、著者は以下のようにも述べています。
「『知識を得ることそれ自体に意味がある』とは、現代世界で初めて認識されたことではありません。ある意味では、人類の歴史の最初からそうだったのです。 マゼランによるマゼラン海峡の発見を思い出してください。彼が未知の海峡を発見する航海に出た目的は、西回りでインドに達する航路の発見という実利的、経済的なものでした。そして、彼は見事にその目的を果たしたのです。しかし、彼が見出した航路は、インドへの航路として実際に使われることはありませんでした。あまりに遠回りで、危険なルートだったからです」
続けて、著者は以下のように述べています。
「では、彼の発見は無意味だったのでしょうか? そんなことはありません。なぜなら、彼が行なった世界周航によって、人類は、自分たちが住んでいる世界の真の姿(地球が周航可能であること)を把握できたからです。 シュテファン・ツヴァイクは、『マゼラン』(みすず書房、1998年)の中で、次のように言っています。
「『歴史上、実用性が或る業績の倫理的価値を決定するようなことは決してない。人類の自分自身に関する知識をふやし、その創造的意識を高揚する者のみが、人類を永続的に富ませる』。そして、『ちっぽけな、弱々しい孤独な5隻の船のすばらしい冒険は、いつまでも忘れられずに残るであろう』としています」
そして本書の最後に、著者は「知識」について述べるのでした。
「消費財としての知識の価値は、人工知能がいかに発達したところで、少しも減るわけではありません。ですから、人工知能がいかに進歩しても、『人間が知的活動のすべてを人工知能に任せ、自らはハンモックに揺られて1日を寝て過ごす』という世界にはならないと思います。 研究室では、研究者が寝食を忘れて実験に挑んでいるでしょう。歴史学者は古文書を紐解いて、新しい事実を発見することに無限の喜びを感じているはずです。そして、親しい人々が集まって、絵画や音楽についてどれだけ深い知識を持っているかを披露し、競い合っているはずです。あるいは、誰の意見が正しいかについて、口角泡を飛ばして議論しているでしょう。人類にとってのユートピアとは、そのような世界だと思います。そうした世界が、人工知能の助けを借りて実現できる。その可能性が、地平線上に見えてきたような気がします」
