- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.1377 経済・経営 『人口と日本経済』 吉川洋著(中公新書)
2017.01.10
1月9日は「成人の日」でした。今年は全国で123万人の新成人が誕生しました。昨年よりも2万人ほど多く、新成人人口は2年ぶりの増加となったようです。人口の行方は、わたしたちが住む日本の将来を占います。
『人口と日本経済』吉川洋著(中公新書)を読みました。
「長寿、イノベーション、経済成長」というサブタイトルがついています。
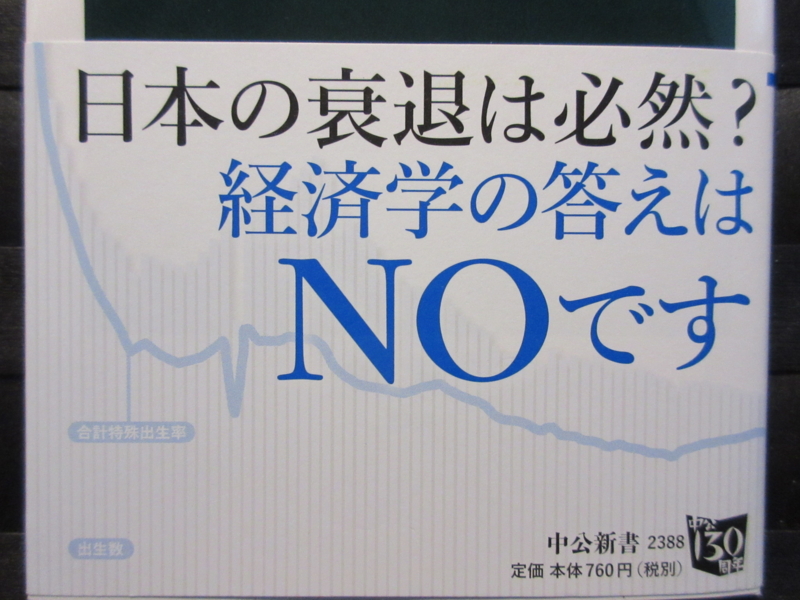 本書の帯
本書の帯
著者は1951年、東京都生まれ。東京大学経済学部卒業後、イェール大学大学院博士課程修了(Ph.D)。ニューヨーク州立大学助教授、大阪大学社会経済研究所助教授、東京大学助教授、東京大学大学院教授を経て、立正大学教授。専攻はマクロ経済学です。
著書には『マクロ経済学研究』(東京大学出版会、1984年、日経・経済図書文化賞、サントリー学芸賞)、『日本経済とマクロ経済学』(東洋経済新報社、1992年、エコノミスト賞)、『転換期の日本経済』(岩波書店、1999年、読売・吉野作造賞)などがあります。本書の帯には「日本の衰頽は必然?」「経済学の答えはNOです」と書かれています。
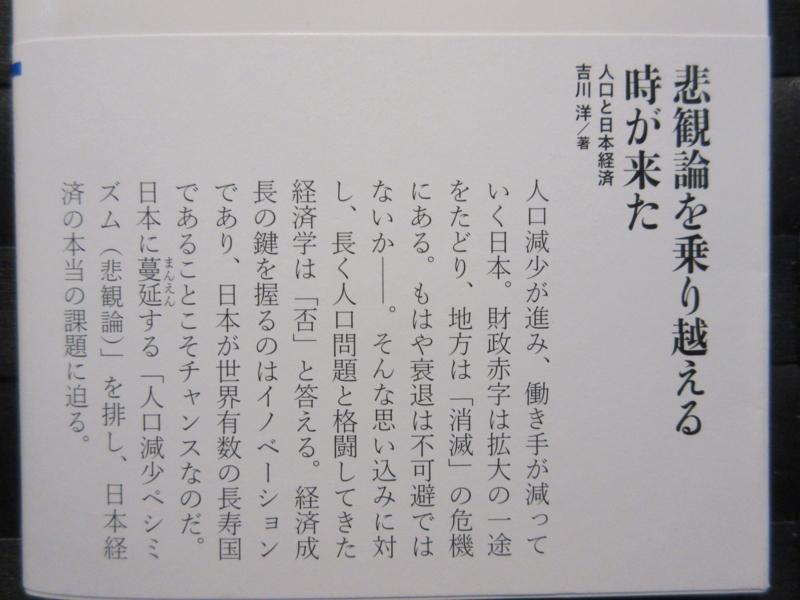 本書の帯の裏
本書の帯の裏
また、帯の裏には「悲観論を乗り越える時が来た」として、以下のように書かれています。
「人口減少が進み、働き手が減っていく日本。財政赤字は拡大の一途をたどり、地方は「消滅」の危機にある。もはや衰退は不可避ではないか―。そんな思い込みに対し、長く人口問題と格闘してきた経済学は『否』と答える。経済成長の鍵を握るのはイノベーションであり、日本が世界有数の長寿国であることこそチャンスなのだ。日本に蔓延する『人口減少ペシミズム(悲観論)』を排し、日本経済の本当の課題に迫る」
本書の「目次」は、以下のような構成になっています。
「はしがき」
第1章 経済学は人口をいかに考えてきたか
第2章 人口減少と日本経済
第3章 長寿という果実
第4章 人間にとって経済とは何か
「あとがき」
「参考文献」
第1章「経済学は人口をいかに考えてきたか」の冒頭を、著者は以下のように書き出しています。
「『人口問題』、これは21世紀の日本にとって最大の問題である。
2012年1月に公表された国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(出生中位)によると、日本の人口は2110年に4286万人になる。2015年の人口は1億2711万人(15年国勢調査)だから、これから100年でわが国の人口は約3分の1にまで減少する。これほど大きな人口の変化は私たちの暮らす日本の経済・社会に大きな影響を与えるに違いない。1つの社会に生きる人間の数、すなわち人口は、その社会にとって最も基本的なデータだからだ」
「日本の人口」として、著者は以下のように述べています。
「奈良時代の中央政府は、リアルタイムで日本の全人口を把握していた。わが国では7世紀末、持統天皇のときから全国の戸籍が6年ごとにつくられ、氏名、年齢、性別、家族関係まで詳しく記した文書が、国司から中央の中務省と民部省にそれぞれ送られていた。6年に1度の戸籍に加えて、課税目的のために『計帳』という統計も毎年つくられ、これを基に民部省の主計官が予算編成を行っていたのである。このように奈良時代には、戸籍を通して全人口調査が6年ごとになされていたが、9世紀になると、戸籍は12年ごと、数十年に1度となり、やがて10世紀に途絶した。その後、長いブランクがあり、江戸時代の人別改などを経え、明治時代の近代的人口調査へとつながった。人口調査の歴史は、奈良時代が中央集権的古代国家のピークであったことを如実に示している」
また、「日本の人口」について、著者は以下のように述べます。
「縄文時代の終わりにかけては、寒冷化により落葉樹林で採れる木の実が減ったことなどが原因で人口が大きく減少したと考えられている。その後断片的にせよ記録の残されている奈良時代以降について見ても、人口が大きく伸びた時代だけではなく、逆に停滞した時代もあった。江戸時代に入って最初の100年、17世紀には人口が大きく増えたが、18世紀に入り、8代将軍吉宗の享保時代から幕末まで人口は停滞した」
続けて、明治以降の「日本の人口」について以下のように述べられます。
「明治になってからは、再び爆発的と言えるほどのハイペースで人口が増加した。しかし、1920年代に入ると、都市部から少子化が始まる。戦争直後(1947~49年)は一時的に人口爆発が起き、いわゆる「団塊の世代」が生まれたが、人口の増加率は1975年以降、急速に低下し、2004年の1億2779万人をピークに、日本はついに人口減少時代に入った。
過去においても人口の微減はあったが、100年で3分の1というように人口が激減した時代はない。われわれは、これから100年、文字どおり歴史上、人類が経験したことのない人口減少の時代に突入する」
著者は「人間の社会は進歩するか?」として、フランス革命を取り上げ、以下のように述べています。
「フランス革命には2つの見方がある。1つは、封建的な圧制のくびきから人類を解放し、近代社会の扉を開いたというポジティブな見方だ。今日なお人間が理想とすべき自由・平等・博愛を高く掲げたフランス革命に対する、こうしたポジティブな評価が日本では優勢かもしれない。
これに対して、それを人類の歴史的愚挙として真っ向から否定するのが、『フランス革命の省察』(1790年)を書いたエドモンド・バークやマルサスに代表されるイギリスの保守主義者たちである。人間の理性には限界がある以上、理性に導かれて理想的な社会を建設しようという試みは必ず挫折する。社会の拠り所とすべきものは、長い歴史の流れの中で濾過された英知、すなわち『伝統』である」
第2章「人口減少と日本経済」では、「超高齢社会の社会保障」として、著者は以下のように述べています。
「今日、わが国の社会保障の給付(お金やサービスの提供を「給付」という)は総額で116兆円である。GDPは500兆円だから、GDPの4分の1に達しようという大きな数字である。兆という単位はわれわれの実感を伴わない大きな数字だが、実際1兆円を1万円札で積み重ねると10キロメートルになるそうだ(ちなみに100万円は約1センチメートル)。日本経済について考えるときにはこの兆が基本単位になる」
また、「財政破綻の危機」として、著者は以下のように述べています。
「財政赤字の問題とはいったい何なのか。年々の財政赤字の結果、増え続ける国債残高が大きくなりすぎることが問題なのである。それは船底にたまった水にたとえることができる。船底に水がたまりすぎれば、タイタニック号のように沈んでしまう。何トンの水がたまれば、船は沈んでしまうのか。それは一概には言えない。タイタニック号のように巨大な船と小さな漁船では答えは当然違うからである。船底にたまった水量を船の大きさとの相対で見て、危険度を判断しなければならない。国債残高も同じである。船の大きさに当たるのが、経済の大きさ、つまりGDPだ。したがって、われわれは、財政破綻の危険度を表す尺度、逆から見れば、財政の健全性を表す指標として、国債残高のGDPに対する比率を用いる」
また、著者は「明治の都市人口ランキング」として以下のように述べます。
「太古以来、人間は移動するものだったに違いない。その結果として、アフリカに誕生した人類はユーラシア全域、さらにベーリング海を越えアメリカ大陸まで拡散した。移動の原因としては、食料の枯渇、自然環境の変化など人をその地域から押し出すような要因もあったであろうことは疑いない。しかし、そうしたネガティブな環境変化がなくても、太古われわれの祖先は突然、山を越え、川を渡り、移動したようなのだ。そうしたことは自分には到底できない、と筆者が漏らしたとたん、人類学の研究者から『それが人間というものなのですよ』と一喝大笑されたことがある。『動物』とはまさに動くモノたる存在なのだろう。しかし、氷河時代といった大昔はさることながら、近代・現代ともなれば、人々が単なる衝動で移動することは稀である。多くの人々が移動するとき、そこには経済的・社会的な力が働いている」
さらに「イノベーションの役割」として、著者は以下のように述べます。
「一国経済全体で労働生産性の上昇をもたらす最大の要因は、新しい設備や機械を投入する『資本蓄積』と、広い意味での『技術進歩』、すなわち『イノベーション』である。
労働力人口の推移と経済成長を固く結びつけて考える人のイメージは、おそらく労働者が1人1本ずつシャベルやツルハシを持って道路工事をしているような姿なのではないだろうか。そうした経済では、働き手の数が減ればアウトプット(生産物)は必然的に減らざるをえない。しかし先進国における経済成長は、労働者がシャベルやツルハシを持って工事をしていたところにブルドーザーが登場するようなものなのだ。こうして労働生産性は上昇する。ひょっとすると、それまで100人でやっていた工事が5人でできるようになるかもしれない。それをもたらすものがイノベーションと資本蓄積(ブルドーザーという機械が発明され、実際にそれが建設会社によって工事現場に投入されること)である」
そして「ソフトな技術進歩」として、著者は述べるのでした。
「今や文字どおり世界を席巻したスターバックスのコーヒーそのものに、特別優れたハードな『技術』があるとは思えない。成功の秘密は、日本では『喫茶店』、ヨーロッパで『カフェ』といってきた店舗空間についての新しい『コンセプト』、『マニュアル』、そして『ブランド』といった総合的なソフト・パワーにある。それが国際競争力を持ち付加価値を生むのだから、スターバックスの誕生はまさに『技術進歩』、イノベーションなのである」
第3章「長寿という果実」の冒頭を、著者は以下のように書き出しています。
「ケインズやミュルダールが1930年代に警告したように、20世紀の先進国経済が直面する問題は、人口の増加から減少へと変わった。『豊かさ』の中で人口減少が始まったのである。しかし、そもそも経済的に豊かな先進国で人口が減少するというのは、マルサスの『人口の原理』に反する。1人当たりの所得水準が上がれば、子どもがたくさん生まれ、人口は増える。これがマルサスの基本命題だった。マルサスからインスピレーションを得たダーウィンの『種の起源』でも、さまざまな生物は互いに少しでも多くの食料を獲得すべく生存競争を行い、成功した生物の数は増えることになっている。実際、今日でも野生の動物や鳥の増減について、そうした『原理』による説明をわれわれは日常よく耳にするのである。ところが人間の数は、1人当たりの所得が上昇する中で減少し始めた。これは決して自明のことではない。
もう1つ、人口が減少するのと並行して始まったのが、平均寿命の延びである。今日、私たちは寿命の延びを当たり前のことと考えがちだ。しかし、これも決して当たり前のことではない。マルサスは寿命の延びを明確に否定していた」
「先進国における出生率の低下」として、著者は以下のように述べます。
「なぜ豊かな人々の間で出生率は低下したのか。ブレンターノは、先駆的な研究の中で、今もなお専門家によって検討が続けられているいくつもの論点を挙げている。社会の進歩とともに若い人々が楽しむモノやサービスの種類は拡大していく。そうしたモノやサービスを楽しむためには時間もかかるし、お金もかかる。その結果、多大の時間と経済的なコストを要する出産・子育ては敬遠されるようになる。人々は高い生活水準を保つために子どもの数を抑制する。また、少数の子どもに高い教育を授け、専門的な職業に就けたいと望むようになる。こうした流れに加えて、女性の意識の変化も指摘されている」
また「寿命の延び」として、著者は以下のように述べています。
「日本が今日世界1、2を争う長寿国であることを知らない人はいない。しかし、これを当たり前だと思ってはいけない。日本人の平均寿命の延びは、戦後の日本が成し遂げた成果、『最大』と言ってもよい成果なのである。高度成長が始まる直前の1950年、わが国は先進国の中では寿命が最も短い国だった。このことは、今日多くの人が忘れてしまっている重要な事実だ」
著者は、「戦前の寿命」として以下のようにも述べています。
「今日、われわれは、ともすると『進んだ都市と遅れた農村』というイメージを抱きやすいが、実は19世紀末、こと人々の健康という点からすると、都市は農村に比べてはるかにリスクの高い危険な場所だったのである。医学の未発達、公衆衛生の不備により多くの伝染病が『死に至る病』であった時代、人々が密集する都市は健康を保ち長生きするのにはきわめて不利な場所だった」
第4章「人間にとって経済とは何か」では、著者は「経済とぜいたく」として以下のように述べています。
「1人ひとりの人間は、生物として生理的な物質代謝を行うことにより生きている。そうした生命のメカニズムを明らかにすることは、医学・生理学の役割である。しかし、1人の人間が生命を維持するための生理的なメカニズムが明らかになったとしても、実際にその人が生きていけるかどうかは別の問題である。どれほど強靭な肉体を持った人でも、砂漠に1人放り出されれば死を待つしかない。アインシュタインといえども、1人では生きていけない。人間は生存に必要なエネルギーを集団的に獲得する以外に道はないのである。人間だけではなく、ある程度進化した生物は、生存のために外敵から身を守るとか、食料を獲得するとか、いずれも多かれ少なかれ集団的な活動を行っている。経済とは、人間が行っているこうした『集団的な物資代謝』にほかならない」
「経済成長とは何か」として、著者は「人間の営む経済活動を物理現象として見るならば、運動エネルギー、位置エネルギー、熱、電気エネルギーなどすべてのエネルギーを考慮に入れるかぎり、何をやってもエネルギーは不変だ。それなのにGDPは大きくなっていく」と述べ、さらに以下のように続けています。
「その理由は、GDPの定義を思い出せば、すぐに分かるはずだ。GDPは1年間にわれわれがつくり出すものやサービスの「価値」を価格で評価し、足し合わせたものにほかならない。価値の基準として使われる価格は、人間の主観的な評価を表す。例として料理を考えてみよう。食材にどのように熱を加え、調味料を変えたところで、エネルギーは不変だ。しかし、できあがった料理につく価格は千差万別である。われわれ人間が高い価格を払ってもよいと思うほど『旨ければ』、高い価格がつく。逆に人々の評価が低ければ、価格は低くなる。GDP、そのもとにある価格とは、人間がモノやサービスに対して主観的につける点数なのである。こうした意味で経済はまさに『人間本位』である」
また、著者は「成熟経済にかかる下方圧力」として、こう述べます。
「古代エジプトのピラミッド、中世の教会は、いくらつくっても、それがもたらす便益が減少することはない。したがって、需要は飽和しない。しかし現代の先進国の経済では、既存のモノやサービスに対する需要は必ず飽和する。こうして経済は慢性的に需要不足に悩まされることになる。
つくっても売れない(需要がない)。だから企業はつくらない。その結果、人を雇わず失業が発生する。『有効需要の原理』、すなわち一国の経済活動水準を決めるのは総需要だとするケインズ経済学の背後にあるのも、既存のモノやサービスに対する需要は飽和する、という事実なのである」
著者は、「プロダクト・イノベーション」として、こうも述べています。
「既存のモノやサービスに対する需要が飽和に達するなら、モノやサービスのリストが変わらないかぎり、経済全体の成長もやがてゼロ成長に向け収束していかざるをえない。こうして多くのモノやサービスが普及した『成熟経済』には、常に成長率低下の圧力がかかっている。そうした先進国経済で成長を生み出す源泉は、当然のことながら、高い需要の成長を享受する新しいモノやサービスの誕生、つまり『プロダクト・イノベーション』である。
需要の飽和。ここにおいて、通常は「水と油」と考えられているケインズとシュンペーターの経済学は急接近するのである。需要の不足によって生まれる不況を、ケインズは、政府の公共投資と低金利で克服せよと説いた。シュンペーターは、需要の飽和による低成長を乗り切る鍵はイノベーション以外にないと主張した」
さらに著者は、「経済成長の恩恵」として以下のように述べます。
「『反経済』『反近代主義』を唱える人は、はたして自分が病気になったときに抗生物質の使用を拒否するだろうか。昭和34年(1959年)の伊勢湾台風では死者・行方不明者の数が5000人を超えた。現在台風でこれだけの死者が出ることはない。こうしたときに私たちは初めて『文明のありがたさ』を思い知るのではないか。老子の説くところは現実論にはなりえない。こう韓愈は説くのである。儒教については古くさいというイメージを持っている人も多いかもしれないが、実はそうしたイメージとは逆に、その根底には、老子とはまったく異なる明快な『合理主義』がある。儒教のいわゆる『聖人』というのは、シュンペーターが資本主義を動かす根源的な力とみなしたイノベーションを行う人、つまりイノベータ―と言ってもよいのだ。このように(江戸時代300年武士が拠り所とした朱子学も含めて)儒教は明らかに『プロ経済』なのである」
さらには「イノベーションの限界と寿命」として、著者は述べます。
「先進国の経済成長を牽引するのは、プロダクト・イノベーションである。プロダクト・イノベーションによって生み出される新しいモノやサービスの多くは、回りまわって平均寿命の延長に貢献してきたものと考えられる。先に述べたとおり、これこそ古く唐の時代に韓愈が指摘したことである。いつの時代も経済成長の結果として実現する平均所得の上昇が、そうした新しいモノやサービスの購入を可能にしてきたのである。こうして先進国では、マルサスの予想に反し、平均寿命が延びてきた」
「日本経済の将来」として、著者は以下のように述べます。
「日本の平均寿命、男性80.5歳、女性86.8歳(2015年)は、確かに生物学的に見た限界に近づきつつあるのかもしれない。しかし、なお残る課題として、『健康寿命』、『生活の質』(Quality of Life、QOL)がある。たとえ21世紀には、先進国で20世紀に生じたような平均寿命の延長がもはや見られないことになるとしても、すでに現実になりつつある超高齢社会において人々が『人間らしく』生きていくためには、今なお膨大なプロダクト・イノベーションを必要としている。超高齢社会においては、医療・介護は言うまでもなく、住宅、交通、流通、さらに1本の筆記具から都市まで、すべてが変わらざるをえないからである。それは、好むと好まざるとにかかわらず、経済成長を通してのみ実現されるものである。逆に、先進国の経済成長を生み出す源泉は、そうしたイノベーションである」
そして最後に、著者は以下のように述べるのでした。
「超高齢社会の姿は誰にも正確には分からない。しかし、社会のすべてが変わると言ってよいような大きな変化が起きることは間違いない。それは数え切れない大小のイノベーションを通して実現される。所得水準が高く、マーケットのサイズが大きく、何よりも超高齢化という問題に直面している日本経済は、実は日本の企業にとって絶好の『実験場』を提供していると言っても過言ではない。人口が減っていく日本国内のマーケットに未来はない、という声をよく耳にするが、超高齢社会に向けたイノベーションにとって、日本経済は大きな可能性を秘めているのである」
わたしの本業である冠婚葬祭互助会は人口産業です。冠婚葬祭業という儀式産業は不変ですが、互助会は人口の変動に大きく左右されます。
「葬式は、要らない」とか「寺院消滅」とか「無葬社会」とか、最近の冠婚葬祭業界をめぐるムードは良いとは言えません。しかし、主に葬儀の研究者が「こうこうこういうふうに社会の無縁化が進んでいって、核家族化も進んでいるから」などの分析で、「今後、日本人はますます葬儀をしなくなります」と予測しているだけなのは呆れます。
小学生の研究発表ではないのですから、人口変動だけを見て悲観的な見方を提示するのでは何のための研究でしょうか。わたしは、研究の後には、「では、こうすべきではないか」という具体案を示すことが必要であると思います、また、そのためにはブレない思想を持つ必要があります。本書を読んで、この著者には「悲観論を乗り越える」思想があることを知りました。すべての研究者は「楽観」ではなく「希望」を忘れてはならないと思います。