- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2017.05.12
『読書と日本人』津野梅太郎著(岩波新書)を読みました。
著者は1938年福岡生まれ。編集者・評論家。和光大学名誉教授。早稲田大学卒業後、劇団「黒テント」制作・演出、晶文社取締役、『季刊・本とコンピュータ』総合編集長、和光大学教授・図書館長などを歴任。著書に『滑稽な巨人 坪内逍遙の夢』(平凡社、新田次郎文学賞)、『ジェローム・ロビンスが死んだ』(平凡社、のちに小学館文庫、芸術選奨文部科学大臣賞)など。
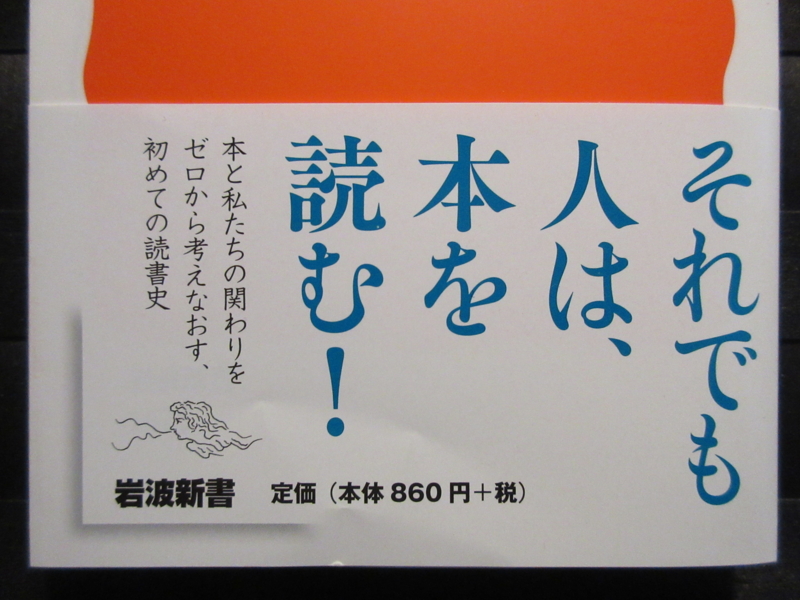 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「それでも人は、本を読む!」と大書され、続けて「本と私たちの関わりをゼロから考えなおす、初めての読書史」と書かれています。
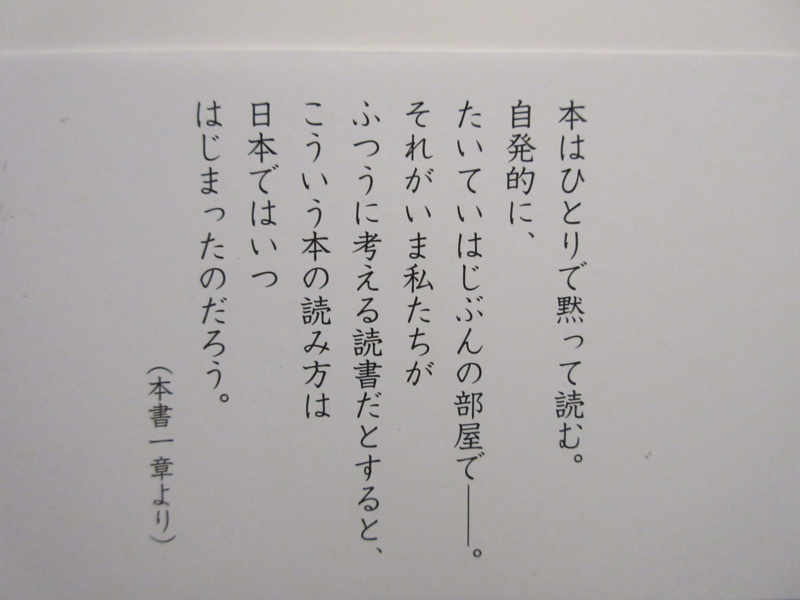 本書の帯の裏
本書の帯の裏
またカバー前そでには、以下のような内容紹介があります。
「『本はひとりで黙って読む。自発的に、たいていはじぶんの部屋で』―私たちが『読書』と名づけてきたこの行為はいつ頃生まれたのだろうか?そしてこれからも人は、本を読み続けるのだろうか? 書き手・読み手・編集者として”読書の黄金時代”を駆け抜けてきた著者が、読書の過去・現在・未来を読みとく、渾身の一冊!」
本書の「目次」は以下のような構成になっています。
(1) 日本人の読書小史
1 はじまりの読書
2 乱世日本のルネサンス
3 印刷革命と寺子屋
4 新しい時代へ
(2) 読書の黄金時代
5 二十世紀読書のはじまり
6 われらの読書法
7 焼け跡からの再出発
8 活字ばなれ
9 〈紙の本〉と〈電子の本〉
「あとがき」
「引用文献一覧」
1「はじまりの読書」の冒頭、「『源氏物語』を読む少女」として、著者は以下のように書き出しています。
「本はひとりで黙って読む。自発的に、たいていはじぶんの部屋で―。それがいま私たちがふつうに考える読書だとすると、こういう本の読み方は日本ではいつはじまったのだろう。
たぶんあのあたりかな、と思われる記録がふたつ残されています。 ひとつは菅原道真の「書斎記」という短い随筆で、9世紀の終わりちかく、平安遷都のほぼ100年後に書かれたもの。そしてもうひとつが、ご存じの『更級日記』ですね。いなか育ちの中くらいの貴族の娘が親戚の女性に『源氏物語』のひと揃いをもらって、われを忘れて読みふける。あの愛すべき一節をふくむ回想録の執筆されたのが11世紀なかば―。このふたつの文章から見て、いま私たちが〈読書〉とふつうに読んでいる行為がこの国に根づきはじめたのは、おおまかにいって、菅原道真から同じ血筋の菅原孝標の女にいたる150年ほどのあいだのことだったのではないか、という推測がつく」
また、「私の部屋がほしい」として、著者は以下のように述べます。
「古代の日本には当初、文字がなかった。文字がないのだから本もない。私たちの遠い祖先が本というもの(巻子本でした)とはじめて出会ったのは、『古事記』によると応神天皇の285年、実際には405年、朝鮮半島の百済からまねかれた大学者の王仁が『論語』10巻と『千字文』1巻をもたらしたときだったらしい」
2「乱世日本のルネサンス」では、「源氏ルネサンス」として、著者は以下のように述べています。
「血なまぐさい争闘があいつぐなかで前代文化の魅力が再発見され、茶の湯、生け花、連歌、能狂言などの新しい表現形式が成熟してゆく。そしてそれが多彩な旅人たちの仲介によって日本各地につぎつぎに伝播していった。東山殿などでの書院造りの実験がまたたくまに新しい武家屋敷の標準になったのもその一例。それやこれや、この時代はヨーロッパのルネサンスにじつによく似ている。なかんずく古典復興。その流れにのって宮廷をでた『源氏物語』が「武家及び其被官、家来、さては其また陪臣」にまで読まれるようになったこと―」
3「印刷革命と寺子屋」では、「サムライの読書」として、著者は以下のように述べています。
「日本全土を巻きこんだ戦乱の時代がやっと終わった。ふたたびあの時代に戻らないようにするには、武力ではないやり方で国をおさめるつよい思想が必要だ。個人の救いに専念する仏教ではもう役に立たない。そこで徳川家康がえらんだのが朱子学でした。12世紀中国(南宋)の大学者、朱熹(朱子)が仏教や道教に対抗して再編成し理論化した新しい儒教。この時期、『修身・斉家・治国・平天下と、個人から天下までを1つのモラルでつらぬく朱子学ほど恰好な思想はなかった』と小児科医で評論家の松田道雄がのべています」
また、正坐について、著者は以下のように述べています。
「正坐、つまり背筋をのばして両膝をきちんとそろえて坐る、それこそが正しい坐り方なのだという考えが生まれたのは、じつは江戸時代のはじめに徳川幕府が大名などの上級武士にむけて制定した武家儀礼によってだったらしい。それが中級や下級の武士をへて一般庶民のあいだにまでひろまったのが江戸中期。身体技法の研究者、矢田部英正の図像学的調査によれば、平安・鎌倉・室町時代の絵巻で正坐をしている人の姿はきわめてすくなく、この時期になって、ようやく浮世絵や肖像画に正坐で坐る人がちらほら現れてくるのだとか」
さらに、「自発的な勉強ブーム」として、著者は述べます。
「読書の習慣がひろく社会に定着するには、ふたつの条件がみたされる必要がある。身分や性別を問わず、社会を構成する人びとのおおくが本を読む力、つまり読み書き能力を身につけていること。それが第1です。そして第2に、だれもが比較的かんたんに本を手にできる流通のしくみができていること。このふたつの条件が江戸時代の日本でようやくととのいはじめた。
まず第1の読み書き能力についていうと、江戸時代の庶民の場合、その基盤をつくったのは寺子屋(手習塾)教育の全国的な普及です」
著者は、以下のようにも述べています。
「こうした生きるための基礎技術としての『読み書きソロバン』をまなぶうちに、一歩そこから踏みこんで「われわれはこの社会でどう正しく生きていけばいいのか」と考え、じぶんからすすんで儒教や歴史や経済などの〈かたい本〉を習慣的に読むような人びとの層ができてくる。いわば〈学者読み〉のさらなる拡大、その大衆化です」
続けて、著者は以下のように述べています。
「そして、しばらくたつうちに、そこから庶民出の新しいタイプの思想家が出現してくる。じっさい、江戸時代中期のはじめぐらいまでの儒教思想家は、下級の公家や武士や浪人や僧侶の家に生まれた者がほとんどでした。林羅山、藤原惺窩、山崎闇斎、中江藤樹、伊藤仁斎、荻生徂徠などですね。それが時代がすすむにつれて、富永仲基(醬油醸造・漬物商)、安藤昌益(町医者)、石田梅岩(百姓・商人)、三浦梅園(儒医)、山片蟠桃(両替商)、賀茂真淵(神職)、本居宣長(木綿商・町医者)といった、豪農や上層商人をふくむ庶民出身の学者たちが江戸思想史の中心をしめるようになっていった」
続けて、著者は以下のように述べています。
「たとえどんな貧しい家に生まれようとも、学ぶ意欲さえあれば一流の人間になれる。その希望のシンボルともいうべきものが、かつては日本中の小学校の校庭に見うけられた、あの薪を背負って読書にはげむ二宮金次郎(尊徳)の銅像です」
この「負薪読書」伝説はいつから始まったのでしょうか。著者によれば、尊徳の一番弟子、富田高慶が師の没後にしるした『報徳記』の「或は柴を刈り、或は薪を伐り・・・・・・而して採薪の往返にも大学の書を懐にして途中歩みながら是を誦し少も怠らす」という記述にあったようです。
しかし、建築史家の藤森照信や井上章一などによれば、金次郎の「負薪読書」伝説にどれほど事実の裏づけがあるのかは、きわめて疑わしいそうです。さらに著者は以下のように述べています。
「この銅像のもとには『報徳記』を下敷きに幸田露伴が1891年(明治24年)にだした少年少女むけの伝説『二宮尊徳翁』のカラー口絵があったものと思われる。これが藤森説です。そして、そのカラー口絵はといえば、「見よ、ぼろを着た1人の男が・・・・・・手には1冊の書物を持ち、背には大きな荷を負ってとある場所に立っていた」というバニヤンの『天路歴程』にヒントを得たのだろう。それが井上の推理―」
ところで、金次郎はどんな本を読んでいたのでしょうか。幸田露伴や富田高慶は、金次郎が読んでいたのは四書五経の『大学』だった推測しました。そして、江戸出版史の研究者である鈴木俊幸は著書『江戸の読書熱』で、金次郎が読んでいたのは江戸後期をつうじてのロングセラー『経典余師』シリーズの1冊だったに違いないと推測しました。
『経典余師』シリーズとは何か。著者は以下のように述べます。
「ふつうの庶民が寺子屋で読み書きの基本をまなんだのち、さらに勉強をつづけたいと思ったら、民間の儒者がひらく私塾にかようしかない。しかしそれには金や時間がかかる。そんな余裕のない人びとにむけて、渓百年という浪人儒者が、儒教の基本となる四書(『論語』『大学』『中庸』『孟子』)を手はじめに、おおくの経書を自学自習するための新スタイルの入門書を工夫して公刊した。それが『経典余師』です」
すなわち、「先生いらずの儒経典入門」というわけです。
江戸時代の読者層の拡大に応じて、山東京伝『傾城買四十八手』、式亭三馬『浮世風呂』、為永春水『春色梅児誉美』、小林一茶『おらが春』、滝沢馬琴『南総里見八犬伝』などの〈やわらかい本〉や、本居宣長『源氏物語玉の小櫛』、平田篤胤『霊能真柱』、頼山陽『日本外史』、杉田玄白『蘭学事始』、平賀源内『物類品騭』などの〈かたい本〉が続々と出版されてゆきました。そして著者は述べるのでした。
「それによって、おそらくはその1千年ほどまえ、ごく少数の上層貴族のあいだではじまった読書の習慣が、江戸や京阪の大都市を中心に、ようやく一般庶民をふくむ日本のすべての階層に根を下ろすことになった。明治維新も、それにつづく明治初年代の文明開化も、その背景には、このような江戸後期に急速に厚みをました読者層の存在があったのです」
4「新しい時代へ」では、「福沢諭吉の『学問のすゝめ』」として、著者は明治時代における最大のベストセラーを取り上げます。いったい、どんな人々が『学問のすゝめ』を読んだのでしょうか。著者は以下のように述べます。
「どうやら中心は、初版刊行の前年、1871年(明治4年)の廃藩置県と散髪脱刀令によって収入とプライドをまるごと剥ぎとられた武士(推定200万人)や、その子弟だったようです。つまり徳川幕府成立後、朱子学によってみずからを改造しようと『学問』にはげんだ人びとの末裔ですよ。かれらの目には『一身独立して一国独立す』という福沢のおしえが、『修身』にはじまり『治国・平天下』におよぶ朱子学のおしえにかさなって映っていたのかもしれません」
続けて、著者は以下のように述べています。
「ただし、かれら失職したサムライ(士族)たちの力だけで、これほどの大ベストセラーが生まれたとも思えない。そこにはとうぜん、士農工商の身分制度を廃した新時代に野心を燃やす知識層の庶民(平民)が、かなりのかず加わっていたはずです。そして、士族であれ平民であれ、この本の読者は福沢の『四民平等』の主張につよく共鳴する者と、それを『立身出世』のマニュアルととらえる者とに大きく二分されていた。それが通説のようですが、でも中心はやはり後者のほうだったのではないか。そのことは『学問のすゝめ』初編刊行の前年に中村正直の翻訳ででたサミュエル・スマイルズの『西国立志編』(欧米の成功談集)全8編が、おなじように総計で100万部をこえる大ベストセラーになったことからもあきらかでしょう」
「新しい頭と古いからだ」として、著者は元サムライや中上層の庶民の家で受けつがれてきた「素読」の習慣に注目します。
そして、著者は以下のように述べています。
「男の子、ときには女の子も、物心がつくかつかない年頃から、父や祖父のまえに正坐して四書などの漢籍を繰りかえし読んで暗記させられた。素読という以上、意味や背景の説明はなし。ただひたすら大きな声でテキストを読み上げるだけ。ただし、たんに苦行の強制というだけでなく、素読にはこうした画一的な訓練によって、子どもたちが『ことばのひびきとリズムを反復復誦する』快楽にめざめるという別の一面もあった。こうした環境でそだった青少年が詩吟に興じたり、学校や寄宿舎や私塾や結社で、華麗な四六駢儷体を駆使した『佳人之奇遇』や『経国美談』などの政治小説を蛮カラ声で朗誦し陶酔するクセを身につけるとかして、ついにはそれが『自由民権のムードを昂揚させる触媒としての役割』をはたすまでになってゆく」
「家庭や地域や学校などの場で、しばしば音声にたよって読む」という本との共同的なつきあいは、「本はひとりで黙って読む。おもに自室で、しかも自発的に」という今日までつづく読書の仕方に変わりました。この読書の変化について、著者は「音読から黙読へ」として、この変わり目をあざやかに象徴する出来事として二葉亭四迷による「あひびき」の翻訳を取り上げて、以下のように述べています。
「『あひびき』は19世紀ロシアの作家、イワン・ツルゲーネフの自伝的な短編連作『猟人日記』中の一篇で、1852年刊行。それから36年たった1888年(明治21年)に二葉亭四迷(この年24歳)が翻訳して、徳富蘇峰主宰の雑誌『国民之友』に発表した。そして、この400字づめ原稿用紙にしてわずか20数枚の小品が、当時の若い読者たちに、いまとなっては想像もつかないほどの強烈な衝撃をあたえることになります。具体的にいえば、国木田独歩(17歳)、島崎藤村(16歳)、田山花袋(同)、蒲原有明(13歳)、柳田国男(同)らの、のちに高名な詩人や作家となる一群の少年たち―」
1923年(大正12年)9月1日、関東大震災が発生しました。
日本の出版産業は甚大な被害を受けましたが、そこからの回復は予想をはるかに超えて迅速でした。著者は「百万(国民)雑誌の登場」として、大震災につづく4年間に以下の3つの大きな出来事が立て続けに生じ、それに牽引され、出版産業の資本主義的再編が改めて開始され直したと述べます。
(1)震災の翌年、1924年(大正13年)に講談社が大衆総合誌『キング』を創刊。すべての国民を読者対象とする〈百万雑誌〉が誕生する。
(2)1926年(大正15年・昭和元年)、改造社が『現代日本文学全集』63巻の配本を開始。他社もこれに追随して全国的な〈円本ブーム〉が起こる。
(3)1927年(昭和2年)、これまで少数の人びとが占有してきた人類の知的資産を安価な小型本として大衆に手わたす、という理想をかかげて〈岩波文庫〉が発足する。
8「活字ばなれ」では、「売れる本がいい本だ」として、著者は以下のように述べています。
「硬軟ひっくるめて、刊行される本のなかみや形態がようやく多様化のきざしをみせ、戦争に強いられた飢えゆえの本への熱い思いが変容しはじめる。そうした時期の出版界に生じた象徴的なできごとを以下にふたつあげておきます。まずは〈雑誌〉―マガジンハウス社による雑誌メディアの革新―具体的にいうと、1964年創刊の『平凡パンチ』にはじまり、『an・an』(70)、『ポパイ』(76)、『クロワッサン』(77)、『ブルータス』(80)、『Olive』(82)と、センスのいい大型ビジュアル誌が同社からたてつづけに創刊されたこと。とくに注目すべきは、これらの雑誌にテレビや新聞とならぶ商品広告の強力な媒体という新しい役割がになわされていたことです」
これにいくらか遅れて、角川書店による〈文庫〉の思いきった大衆化が敢行されました。著者は以下のように述べます。
「かつては岩波文庫タイプの地味なつくりだった角川文庫が、70年代後半、横溝正史『犬神家の一族』や森村誠一『人間の証明』の刊行を皮切りに、その路線を古典や純文学から大衆文学に切りかえ、新たに設立した角川映画による映画化を連動させるメディアミックス戦略(「読んでから見るか、見てから読むか」)の成功もあって、同時期に参入した講談社文庫、中公文庫、文春文庫、集英社文庫をふくむ日本の文庫の大半が、おなじ道をたどることになった。すなわち古典に代表される〈かたい本〉をはこぶ車としての文庫が、大衆文学やライトエッセイなどの〈やわらかい本〉をのせた、より軽くて、はなやかな車に仕立てなおされたのです」
また、ベストセラーについて、著者は以下のように述べています。
「20世紀前半期を代表するベストセラーはマーガレット・ミッチェルの『風と共に去りぬ』で、1936年に刊行され、その年のうちに100万部、翌年には150万部、10年後には合衆国内だけで300万部を売っていたらしい。
そして後半期(正確には20世紀末から今世紀初頭にかけて)の代表が、いわずと知れたJ・K・ローリングの「ハリー・ポッター」シリーズです。1997年に第1巻が刊行され、第6巻の『ハリー・ポッターと謎のプリンス』では「世界同時発売」という未曽有の販売方式によって、わずか24時間で900万部を売り上げた。さらに2007年刊の第7巻でこの記録を大幅に更新してひとまず完結、翌08年までに150を超える国や地域でシリーズ総計4億部以上を売ったというのですからね。売れ行きのすごさの次元が何段階も上がり、もはや別世界のできごとというしかない」
この空前の大ベストセラーとなった「ハリー・ポッター」について、著者は以下のように述べています。
「作品としての『ハリー・ポッター』についてここでうんぬんすることはしません。その『短い時間で大量の本を世界規模で一気に売りさばく』という販売手法にかぎっていえば、それが、おなじ20世紀末にはじまったアメリカ式の市場最優先主義のグローバル化、ときに強欲資本主義とも呼ばれる新自由主義経済が生みだした社会の風潮と無縁だったとは思えない」
著者によれば、20世紀読書のかなめは「おなじ本を別の場所にいる見知らぬ他人とともに読む」という読書習慣の平等化にありました。その平等化への熱意が、1世紀たって、日本のみならず「世界中のみんながいっせいにおなじ本を買って読む」という度を超えた読者の同調志向を招いたのです。
さらに70年代も後半に入ると、文庫や新書以外の一般の単行本の分野でも新現象が目立つようになりました。著者は述べます。
「そのひとつが、みずから『昭和軽薄体』を名のる一群のエッセイストたちの登場でした。『チューサン階級の冒険』(77)の嵐山光三郎や、『さらば国分寺書店のオババ』(79)の著者で『昭和軽薄体』の命名者でもあった椎名誠を筆頭に、赤瀬川原平、南伸坊、松村友視、林真理子、橋本治、糸井重里といった新しいタイプの文筆家たちの活躍がはじまる。こちたい思想用語などは最初からつかう気もない。肩の力をぬいて、とことん俗な話しことばで考えて書く。で、そのさいは笑いが不可欠。だから、あえていってしまえば『読むマンガ』ですよ」
一方、硬めの思想書もよく読まれました。著者は述べます。
「『重厚長大』を思想の次元に移すとマルクス主義に代表される近代思想になる。その『大きな物語』の関節はずしを旗印に、1983年の浅田彰『構造と力』のとつぜんの大ヒットに前後して、栗本慎一郎『パンツをはいたサル』、中沢新一『チベットのモーツァルト』、上野千鶴子『セクシィ・ギャルの大研究』、四方田犬彦『映像の招喚』などの本がたてつづけに刊行され、青土社の『現代思想』や岩波書店の『へるめす』などの新しい雑誌の力とあいまって、主として大学の若手教員が執筆し、それを大学生や大学院生、若い『一般社会人』などの読者が読むという、ひさかたぶりの〈かたい本〉人気がたかまった」
こうした現象のしばらく前から〈読書〉に対する人々の態度がゆっくりと変わり始めていたとして、著者は以下のように述べます。
「変化の理由は重層的ですが、この本の文脈でいえば、高度経済成長期ののち、出版点数がふえるにつれて人びとが大量の本にとりかこまれて暮らすようになったことが大きい。そんななかで、いつしか飢えの時代のきまじめな読書法の力が薄れ、おびただしい量の本といかに気分よくつきあうかという、いわば満腹時代の新しい読書法がもとめられるようになった。〈かたい本〉の領域でいえば、70年代にはいって、その導師が『言語にとって美とはなにか』(65)や『共同幻想論』(68)の吉本隆明から、『本の神話学』(71)や『歴史・祝祭・神話』(74)の山口昌男にかわった。そんな印象があります」
このへんの本は、わたしが貪り読んだ本ばかりです。なつかしいですね。
9「〈紙の本〉と〈電子の本〉」では、「それでも人は本を読む」として、著者は以下のように述べています。
「総じていえば、戦前からつづく教養主義的・権威主義的な〈読書の階段〉の秩序が、ようやくこの段階になって、ほぼ完全に崩壊したのです。木田元から柴田元幸や池澤夏樹まで、上記の人びとのしごとも、おそらくは、その崩壊現象にまっとうに対処しようとするところからはじまった。だからといって大衆読書が勝ち、インテリ読書が負けたというのではないですよ。そうではなく、インテリがインテリであることの古いしばりから、そして大衆が大衆であることの、おなじように古いしばりから、すこしだけ自由になったのです」
そして、「あとがき」で著者は以下のように述べるのでした。
「たとえ〈読書の黄金時代〉としての20世紀が終わっても、そのことで私たちの読書習慣までが消えてしまうことはないでしょう。とうぜんです。終わったのは本そのものではなく、あくまでも、映画、テレビ、ラジオ、演劇、舞踊、音楽、絵画、写真、デザインなど、さまざまなメディアが織りなす網の目の中心に本がどっしりと位置するという〈黄金時代〉の構図なのですから」
本書を読んで、まさに「読書と日本人」の歴史を俯瞰することができました。また、わたしがかつて愛読した多くの本の書名が登場して、とても懐かしく嬉しく思いました。ますます本が読みたくなる本です。
いま、電車に乗ると、スマホをいじっている人だらけです。
紙の本を読んでいる人の姿はほとんど見かけません。
しかし、読書習慣の衰退、読書人口の現象はそのまま日本の文化的危機であるということを忘れてはなりません。
