- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2017.05.16
『考えるということ』大澤真幸著(河出文庫)を読みました。
「知的創造の方法」というサブタイトルがついています。
著者は1958年長野県松本市生まれの社会学者です。主な著書に『虚構の時代の果て』『文明の内なる衝突』『不可能性の時代』『ナショナリズムの由来』『生きるための自由論』などがあります。
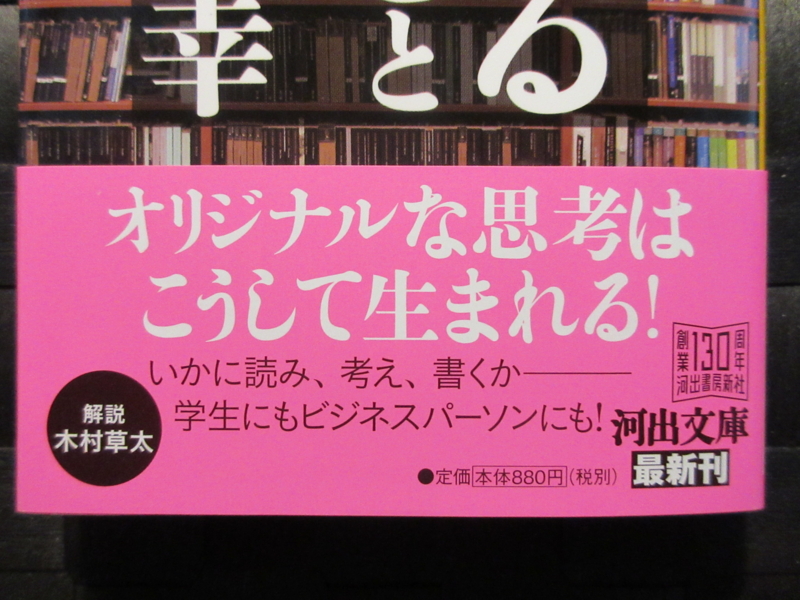 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「オリジナルな思考はこうして生まれる!」「いかに読み、考え、書くか―学生にもビジネスパーソンにも!」「解説 木村草太」と書かれています。また、カバー裏には「何を、いつ、どこで、いかに、なぜ考えるか―。考えることの基本から、書物の力を触媒として活用する実践例、そして、執筆過程の舞台裏まで。刺激的な著作を世に問い続ける知性が、知的創造の現場へと読者をいざなう」と書かれています。
本書の「目次」は、以下のようになっています。
「まえがき」
序章 考えることの基本
1 何を思考するか
2 いつ思考するか
3 どこで思考するか
4 いかに思考するか
5 なぜ思考するか
補論 思想の不法侵入者
第1章 読んで考えるということ 社会科学篇
第2章 読んで考えるということ 文学篇
第3章 読んで考えるということ 自然科学篇
終章 そして、書くということ
「あとがき」
「文庫版あとがき」
解説「凡庸な警察と名探偵」(木村草太)
「まえがき」で、著者は以下のように述べています。
「考えることは、人間の義務でもなければ、原初的な欲望でもない。しかし、あるショックを受けたとき、人は思考しないではいられなくなる。このショックのことを、哲学者ジル・ドゥルーズは『不法侵入』に喩えている。ありきたりの知識や解釈では、不法侵入を受け止めることができないとき、人は思考することを強いられる」
続けて、著者は以下のように述べています。
「だが、不法侵入のショックに拮抗できるだけの、思考の深みに達することは、容易ではない。常識の壁が、思考の深化を妨げるからである。常識の引力から脱して、思考をおし進めることは、たいへん困難なことだ。あれこれと考えるが、『どこか違う』、『これではあのショックには釣り合わない』と思うような平凡な結論に至りついてしまう。そのように感じる人は多いだろう」
さらに続けて、著者は以下のように述べます。
「そのとき、人は、思考の化学反応を促進する触媒を必要とする。そのような触媒の中で最も重要なものは、もちろん、他人たち、相談相手になってくれたり、議論に応じてくれたり、ときにはだまって話を聞いてくれるさまざまな他者たちである。その次に重要な触媒は、まちがいなく書物だ」
序章「考えることの基本」の2「いつ思考するか」では、著者は「出来事の真っ最中に考える」として、以下のように述べています。
「『ミネルヴァの梟は黄昏に飛ぶ』とヘーゲルが言うように、出来事に対して思考というものは遅れる。この遅れは、構造的なものであり、必然である。つまり、この遅れは、思考が引き受けざるをえない宿命である。しかし、究極的にはそういう条件があるのかもしれないけれども、それでも、方法によっては、出来事の真っ最中にものを考えていくことは可能であり、私は、そういう前提で思考することにしている」
また、「本質的な出来事は反復する」として、著者は述べます。
「マルクスがヘーゲルに託して述べているように、本質的な出来事は反復する。反復されたときにはじめて思考のテーマとして明確に意識化されるようになる。ただ、そのとき重要なのは、『それ』が反復だと気づくことである。その出来事自体が『自分はあれこれの反復です』と声を大にして言っているわけではないので、これは過去のあれの反復である、ということに自分で気づかなくてはならない。そして、気づいたときには、実は、無意識のうちにすでに思考はスタートしていた、ということになる。つまり、最初の出来事のときに、気づかぬうちに、思考は開始されていたのである。反復されたとき、そのことに思考自身が気づくのである。逆に言えば、〈反復〉を感じられる出来事には本質的なものが孕まれていると考えた方がよい」
「前にもあった、という感じ」として、著者は述べます。
「実際の出来事だけではなく、本を読んでいてもそうだ。読んでいてすごくおもしろいと感じたり感激したりする。そうしたとき、『これと同じようなことをどこかで、別の本を読んだときにも感じたぞ』というように、過去の感覚を思い出すことがある。前に読んだときには見過ごされていたんだけれども、心の底のどこかには残っていて、のちに別の本を読んだときにそれが発掘される、そういうことがあるのだ」
「潜在していたテーマが刺戟され、浮上する」として、著者は述べます。
「プラトンがソクラテスの言葉として書いている有名な説に、『思考とは想起することである』という趣旨の命題がある。人は思い出すというかたちで考えるというわけだが、思考をどうして、そのように捉えなければならないか、ということには、理論上の理由がある。哲学というのは『何々とは何か』という問いのかたちで考える。善とは何か、正義とは何か、真理とは何か、美とは何か、存在とは何か、と」
著者は「魂は、もともと『美』とは何かを知っていたのだが、忘却してしまっており、それが想起されるというかたちで見出されるのではないか、と。―これがソクラテス=プラトンの言い分である」と述べ、さらに以下のように書いています。
「自分の中にずっと潜在しているテーマがあり、それが刺激されて再び浮上すると、一種のデジャヴのような感覚を抱きながら、それを言葉にしているような気がするのだ。『これは一度自分が考えたかもしれない』と。一度考えたことなのに表に出てこなかったことを今また考えている、そのような気分にしばしばなるのだ」
3「どこで思考するか」では、著者は「紙の上に書く」として述べます。
「発見のもっている大きさに見合うように言葉にするのはどうしたらよいか。考えている場所は、自分の身体の外である。それを言葉にする。そのときに、逆説的だが、言葉を媒介にしてアイディアを自分の中で完全に内面化したような気分になってはいけない。言葉は自分の内面から絞り出されるのでは、ない。言葉にするためにはやらなければならないことがある。方法自体は簡単なことだ。まっさらな紙の上に書くのだ。自分の捉えているもの、完全には言葉になっていないが、しかし言葉を待ち続けるとだめになってしまうもの、それをまず紙の上に不完全な言葉としてとりあえず書き留めておく。この作業を必ずしなくてはいけない」
また著者は、「『一渡り感』が重要」として、紙の上に書く際には「一目で見渡せる」ということが重要であると指摘し、以下のように述べます。
「私の場合、短い原稿であっても、できるだけ『一渡り感』のあるメモを作るようにしている。しかし、この『一渡り感』の重要性は、どんなに長い論文、どんなに分厚い本でも、どんなに長期の連載を書く際にも変わらない。1つの論文、1冊の本、1つの長い連載の狙いは、1枚の紙の上で表すことができ、一挙に一目で見渡すことができる」
4「いかに思考するか」では、著者は「読者を『宙吊り』にする」として、以下のように述べています。
「私がものを書くときに重視するのは、結局答えはこうなるということよりも、読者に疑問の感覚を強くもたせることである。答えよりも問いがはるかに重要である。もちろん、問いに対してある答えを出して納得してもらえればもっとよいのだが、まずそこに問うべきことがあるということ、疑問があるんだということを納得させねばならない。いってみれば、読者にいったん『宙吊り感』を味わってもらうのだ」
また著者は、「補助線を入れる」として以下のように述べます。
「私は思考の過程で、補助線を入れてみる、ということをよくやる。
補助線というものは、事前には、どこに入れるべきなのか、いかなる指示もない。幾何図形をいくら眺めても、補助線をここに入れましょうと書いてあるわけではない。にもかかわらず、巧みに補助線を入れると、今まで見えていなかったことが、突然に見えてくる。これとこれが同じ面積になっているとか、こことこことが相似形だとかが、1本の補助線によって、一挙に開示される。そこで、われわれは、知る。そここそが、補助線を入れるべき場所だったのだ、と。補助線というものは、ふしぎなもので、このように、自分の根拠を、事後になって挿入するのである」
第2章「読んで考えるということ 文学篇」の2「ドストエフスキー『罪と罰』を読む」では、「賭けとしてのテロ」として、著者は述べています。
「宗教的には、最後の審判のときの神の判断は、原理的に不可知である。しかし、スターリニズムの立場は、本来は不可知であるところの最後の審判の判断を、実際に知っている者がいる、というものである。誰が知っているのか。もちろん、『党』である。党は、ある人の行為が、客観的にはどのような意味があるのか、客観的に有罪なのか無罪なのかを、恣意的に決定することができる。党は、現在化された最後の審判なのだ。倫理の究極の参照点として、『人類』を想定する立場は、このようなアイディアにまっすぐにつながっている」
3「赤坂真理『東京プリズン』を読む」では、「国破れて、女になった」として、著者はいかのように述べています。
「誰でも、直接の深い関係をもっていなかった他人の葬儀に参列することがあるだろう。そのとき、あなたは、内側から込み上げてくるような悲しみを感じはしない。それどころか、ほとんど何も感じないかもしれない。しかし、葬儀では、弔辞が読まれ、哀悼の意を示すさまざまな儀式的な行為がなされる。つまり、『あなた』は悲しんでいなくても、その葬儀を執り行う『集団』は悲しんでいるのだ。そして、この集団の一員であることを自ら主体的に引き受けている以上は、『あなた』も悲しんでいる(ことになる)のである。あなたが、どんな内面的な意識をもっていようとも。
同じことは、日本人と戦争との関係についても言える。個々の日本人は、もはや、戦争についてあれこれとこだわることはないかもしれない。しかし、『日本社会』にとっては、敗戦は未だに克服できていない、トラウマ的な出来事である」
第3章「読んで考えるということ 自然科学篇」の冒頭では、「テーマは神」として、著者は以下のように述べています。
「伝統的には、哲学やその他の人文系の学問によって問われていた疑問の多くが、今日では自然科学の領域に移植されている。たとえば、意識や自由意思の問題は、脳科学の問題に転換される。多様な生命に関する問いは、進化生物学の領域に移される。そして、何より、宇宙や物質の謎は、物理学の問題だ。今日では、『実験形而上学 experimental metaphysics』という用語すらある。こうなると、もはや、哲学をはじめとする人文系の学問の多くが、必要なくなるのではないか、と思えてくるだろう。実際、スティーヴン・ホーキングは、最近著The Grand Design(Bantam Books,2010)の最初の頁で、こう宣言している。『哲学は死んだ』と」
また、1「数学と人生」の「吉田洋一『零の発見』を読む」では、「『0』の謎」として、著者は以下のように述べています。
「0を発見したのはインド人である。これは確実なことだ。6世紀頃であったと推定されている。0が発見されているということと、『位取り記数法』が用いられているということとは同じことである。0があって、初めて位取り記数法が可能になる。あるいは、位取り記数法のために、0が発見された。
ところで、位取り記数法をそのまま表現しているように見える装置、つまりソロバンは、世界の各地で発見された。しかし、ソロバンがあっても、0と位取り記数法が普及しているとは限らない。ただインドのみが、0をその核心に含む位取り記数法を確立したのである」
0については驚くべきことが多々あります。著者は述べます。
「まず、インド人以外は、誰も最初、0を数として扱わなかった、ということが、である。中国にも、ギリシアにも、エジプトにも、あるいはアラビアにも、文字をもち、商業を発達させた文明があった。それらの文明のもとで、人々は当然、数を駆使していたが、その数の中に0を含めることは思い至らなかった。ただインド人だけが、0を、1や2と並ぶ数と見なしたのだ」
インド哲学では、「空」についての思索が展開されました。これが、インドでのみ、0が「存在」と見なされたことの原因ではないかと推測されますが、著者は以下のように述べています。
「確かに、インド哲学に『空』の思索があることを、0の発見の原因にするのは、安易に過ぎる説かもしれない。また仮に正しかったとしても、今度は、どうして、インドの哲学や宗教では『空』が中心的な価値をもったのかが、あらためて疑問になるので、謎を少しも解決してはいない。たとえば、『犯罪』でも実行犯の背後に黒幕がいるらしいということがわかれば、黒幕が何者なのか、黒幕の動機は何なのかが問題になるだろう」
さらに著者は、「0」と「空」について以下のように述べます。
「仮に『0』の背後に『空』があったとしても、問題そのものが転嫁されただけで、解決はしていない。『0』と『空』とは、ほぼ同じ場所、同じ文明から発生しているので、同一の要因が関連していた可能性はあるが、それが何であるかをつきとめなくては、問題を解決したことにはならない。ちなみに、『空』についての洗練された思索を展開した大乗仏教系の哲学者ナーガールジュナ(龍樹)は、2世紀後半から3世紀前半の人である」
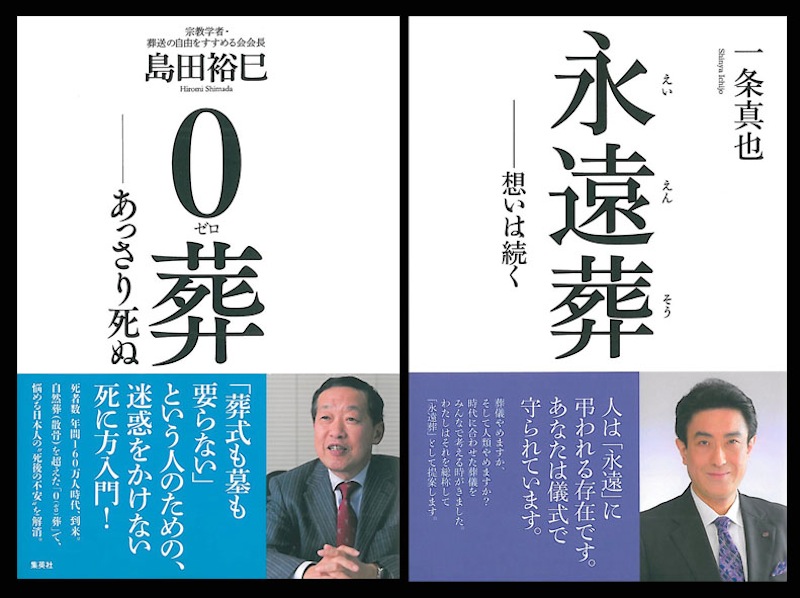 0としての「無」、永遠としての「空」
0としての「無」、永遠としての「空」
拙著『永遠葬』(現代書林)で、わたしは「0も∞も古代インド人が発明した」と書きました。もともと、「0」とは古代インドで生まれた概念です。古代インドでは「∞」という概念も生み出しました。この「∞」こそは「無限」であり「永遠」です。
「紀元前400年から西暦200年頃にかけてのインド数学では、厖大な数の概念を扱っていたジャイナ教の学者たちが早くから無限に関心を持ちました。無限には、一方向の無限、二方向の無限、平面の無限、あらゆる方向の無限、永遠に無限の五種類があるとしました。これにより、ジャイナ教徒の数学者は現在でいうところの集合論や超限数の概念を研究していたのです」
著者は、「究極のcoincidence(偶然の一致)」として述べます。
「振り返ってみると、『0』を発見した時点から、数学と物理学との間の微妙な分離が始まっていた。もちろん、吉田洋一が強調していたように、0はもともと、物理的な対象を操作したり記述したりする上での利便性に規定されて案出されたものだろう。しかし、同時に、『何もない』という状態を、『何かある』という状態と並ぶ存在として認識するためには、物理現象に縛られない抽象を必要とする。そして、数学の領域に、『無限』が入ってきたとき、物理学と数学との間の分離は決定的なものになる」
 『唯葬論』(三五館)
『唯葬論』(三五館)
続けて、著者は以下のように述べています。
「数学は、こうして、物理学とは関係のない一人旅をどんどん進めて行った。ところが、はるかに道を歩んだところで、数学が、突然、また物理学と出会ったとしたら、それは、どういうことなのだろうか。その出会いの先に暗示されていることは、哲学上の最大の対立、つまり観念論(数学)と唯物論(物理学)との間の対立が克服される地点ではないか。極度に抽象的な数学の中に、物理学の概念や方程式が突然のように姿を現すのは、観念論と唯物論の収斂のはるかな予告ではないか」
ちなみに、わたしは『永遠葬』で「空」を「∞」としてとらえ、『唯葬論』では観念論と唯物論を超越した「唯葬論」という考え方を提唱しました。
2「重力の発見」の「大栗博司『重力とは何か』を読む」では、「近代物理学の特権的な研究対象」として、著者は以下のように述べています。
「17世紀のヨーロッパでは、自然認識の全領域にわたる大転換が起きた。これを、科学史の専門家は『科学革命』と呼んでいる。今日まで受け継がれている自然科学の基本的な枠組みは、この世紀に整えられた。枠組みだけではなく、中学や高校を卒業した者であればたいてい知っているような、科学的な常識の多くは、このときの発見に基づいている」
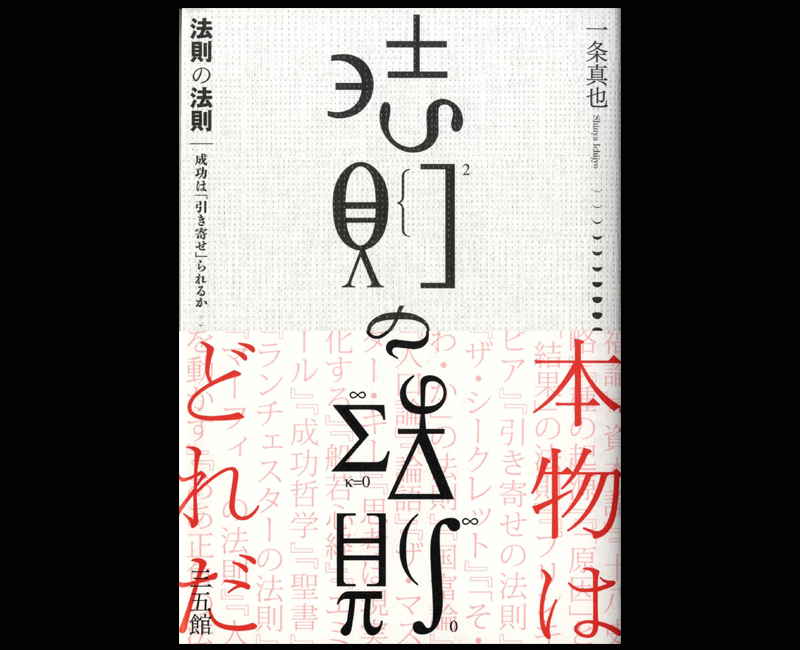 『法則の法則』(三五館)
『法則の法則』(三五館)
拙著『法則の法則』(三五館)では、ニュートンを「法則王」としてとらえ、彼が発見した「万有引力の法則」が「科学革命」を実現した経緯を詳しく説明しました。著者は以下のようにも述べます。
「17世紀から現在までの過程で、物理学の領域では、科学革命に匹敵する大きな変革が、もう1回、あった。20世紀初頭のことである。その『第2の科学革命』を代表する業績、17世紀の科学革命にとってのニュートンの万有引力の法則に対応するような業績は、言うまでもなく、アインシュタインによる相対論の発見だ。ニュートンとアインシュタインという2人の巨人が見出した法則を比較すると、1つの共通性に気づく。とちらも、(主として)重力についての法則なのだ。重力は、近代の物理学にとって、そのアイデンティティの核となるような特権的な研究対象である」
「ヴィクトル・I・ストイキツァ『絵画の自意識』を読む」では、「絵画革命」として、著者は以下のように述べています。
「静物画や風景画は、15世紀末から16世紀にヨーロッパで成立した。つまり、これらは、近代的な絵画のジャンルである。この成立期は、あの科学革命の直前から初期の時期に重なっている。つまり科学革命を準備していた時期だった、ということになる。それ以前の絵画はどのようなものだったのか。絵画は、基本的には、宗教画だったのだ。キリストの磔刑とか、受胎告知とか、楽園追放などの聖書からとったエピソードが描かれてきた。それに対して、静物画や風景画は、宗教的な価値をもたない、何でもない物や風景を鑑賞の対象としている。この美的な鑑賞のスタイルは、聖書やアリストテレスといった古典的なテクストとは独立に、物体を客体視する近代科学の態度と―同じではないが―連続している」
ストイキツァの研究は静物画や風景画が生成してくる局面を注意深く分析していますが、この延長線上には科学革命がありました。著者は述べます。
「15世紀末から16世紀にかけての絵画の革命(静物画等の近代的なジャンルの成立)から、これと半分重なるように出てくる17世紀の科学革命にかけての時期に、西洋の精神史は、大きな断絶を体験したのだ、と。個別の分野で見ると、『静物画の成立』とか『科学革命』とかといった、別々の出来事のように見えるが、実は、それらは、同じ精神史の転換を、異なる局面で捉えた結果であろう」
続けて、著者は以下のように述べています。
「ちなみに、この時期は、西洋の精神史の転換期は、社会の転換期とぴったりと重なっている。この時期は、歴史学者のブローデルや社会学者のウォーラーステインが『長い16世紀』と呼んだ期間なのだ。長い16世紀は、『世界経済』としての資本主義ができあがってくるプロセスである。転換期にあたる15世紀中盤から17世紀中盤までのおよそ200年を、広い意味での16世紀的な時代、『長い16世紀』と捉えよう、というのが彼らの提案である」
終章「そして、書くということ」の冒頭で、著者は「考えることは書くことにおいて成就する。考えることの最終局面は、書くことと完全に一体である。書くことに収斂しなければ、思考は完成しない」と述べています。
また「執筆前の準備」として、準備を進める中で、探偵小説の中の探偵、つまりホームズやポアロのような気分になってくると機が熟しつつあると述べ、さらに以下のように書いています。
「それまでの文献に書かれている先行の説明は、探偵小説に出てくる凡庸な警察のように見えてくる。『おとり』や『偽装工作』にまんまと引っかかっている警察のように、である。それに対して、私はホームズだ。そんな、いささか傲慢な気分になったとき、準備は最終局面に入っている」
誰でも、文章を書く前は不安なのではないでしょうか。 著者は、「不安を克服する『薬』」として、以下のように述べています。
「いよいよ文章を書き始める。執筆開始直前の2~3日、やや鬱っぽい時間を過ごす―というのは、若い頃のことで、今はそんなことはない。が、ともかく、30代前半くらいまでは、執筆を始める前に、少し調子を落とした。
執筆直前にどうして憂鬱な気分になったのか。不安だったのだ。ほんとうに書けるのか。結論にたどりつけるのか。論文を書くのは、大海に出帆するのに似ている。途中で沈没することはないのか。向こう側の岸に到達できるのか。そもそも、向こう側に岸があるのか。こうした心配が抑鬱の原因である」
続けて、著者は不安を克服する秘策を紹介します。
「この抑鬱を克服する方法がある。特別に気に入っている、傑出した論文か本を、少しばかり読むのだ。私が論文や本を書くのは、もちろん、過去において、誰かの論文や本に感動したり、衝撃を受けたりといった経験をしたことがあるからだ。文筆を仕事としている人は、皆、そうであろう。本を読んで感動したこともないのに、本を書きたいとは思うまい」
著者は、「書くことにおける発見」として、以下のように述べます。
「書きながら、自分がワクワクし、ドキドキしていなければならない。執筆は、苦しい作業だが、まさにその苦痛の中に、あるいは苦痛を超えて、喜びがなければならない。折口信夫は、弟子たちにいつも『心躍りのしない文章を書くものではないよ』と語っていたというが、まさにその通りである。どんなに深刻な問題、不幸な出来事について書いている場合でも、探求することそれ自体には、また書くことそれ自体には、やはり発見の喜びがある。そうしたものがないならば、書かない方がよい」
続けて、「書くこと」について、著者は述べています。
「少なくとも、次のことは確実である。書いている者にとってつまらないことが、読者にとってはおもしろい、などということは絶対にありえない。書いている者にはおもしろいのだが、そのおもしろさが読者になかなか伝わらない、ということはときには―というよりしばしば―ある。しかし、著者も『つまらないな』と思いながら書いたことが、読んでいる者にはおもしろかった、などという都合のよいことは絶対に起こらない、と思った方がよい。書いていてつまらないことは、公表しない方がよいだろう」
そして「文庫版あとがき」で、著者は次のように述べるのでした。
「1人の人間が会うことができる他者の数や範囲は、ごく限られている。まして、その人の本気の思索に付き合ってくれる他者は、ごくわずかしかいない。だが、幸い、書物というものがある。人は、書物に問いかけながら読むことができる。書物から応答を読み取ることができる。書物に、『答え』がそのまま書いてある、ということではない。ただ、書物を読みながら考えていくと、思考は、なぜか柔軟で自由になっていくのだ。考えることが急に楽しくなり、わくわくする興奮の体験に転化する。書物を媒介にして考えていると、急にそれまで見えなかったものが見えるようになり、思いつかなかったことに思い至るようになる。書物が、われわれの思考の同伴者になるからだ。書物が、創造的な思考に不可欠な他者の役割を果たすからだ」
