- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2017.09.03
『いくつになっても、今日がいちばん新しい日』日野原重明著(PHP研究所)を読みました。わたしのブログ記事「生きかた名人、逝く!」で紹介したように、聖路加国際病院名誉院長だった日野原重明氏が7月18日に105歳でお亡くなりになられました。本書は2002年に講談社から発刊された『いのちを創る』を改題・再編集のうえ復刊したものです。
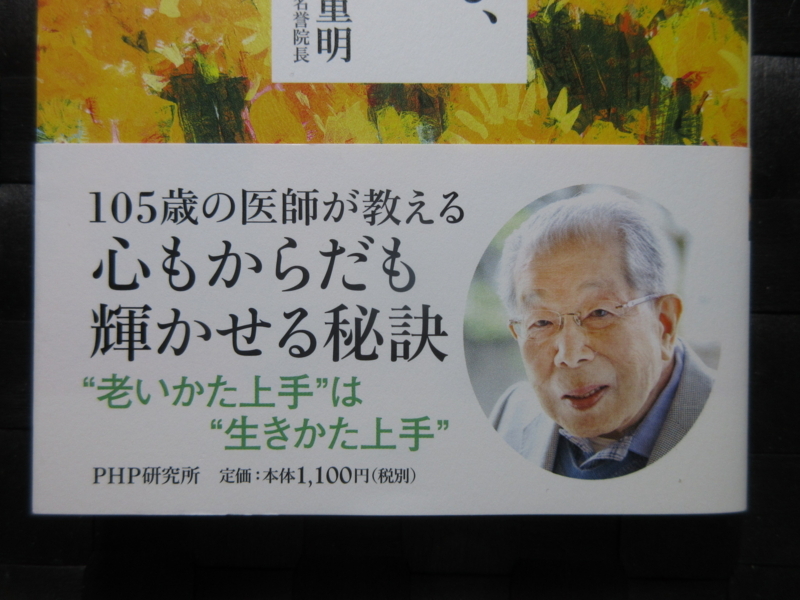 本書の帯
本書の帯
帯には著者の顔写真とともに、「105歳の医師が教える、心もからだも輝かせる秘訣。”老いかた上手”は”生きかた上手”」とあります。
また、帯の裏には「もくじ」より以下の言葉が掲載されています。
◎時の流れの岸辺に立つ
◎「人生の午後」を生きるエッセンス
◎人は、いつからでもはじめられる
◎「うつ」はよくあること
◎転ばぬ先の住まいづくり
◎正常値の見方 ◎誰でもできるセルフチェック
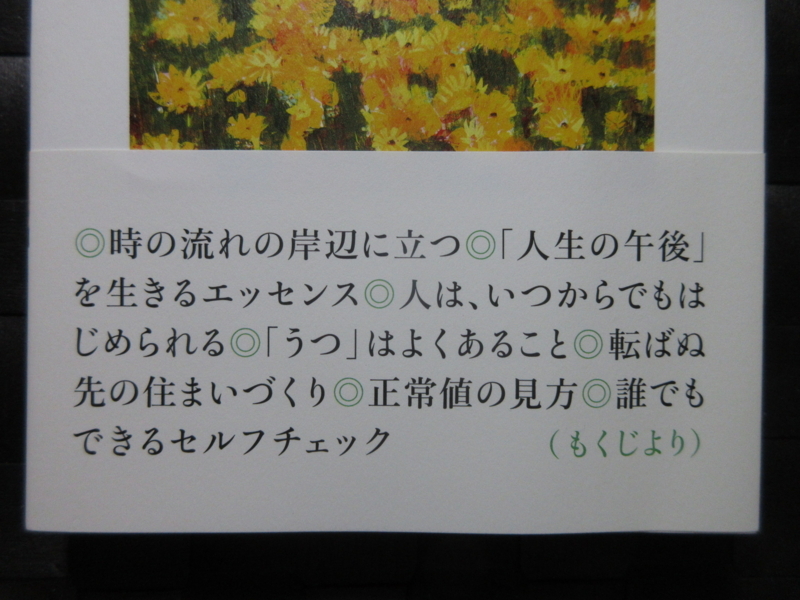 本書の帯の裏
本書の帯の裏
カバー前そでには「私たちに遺された有限の生涯をいかに生きるか、考えてみませんか」と書かれ、「目次」は以下のような構成になっています。
「はじめに」
1章 老いて高める
2章 老いを認める
3章 老いても整える
4章 老いを管理する
2017年5月18日、つまり亡くなるちょうど2カ月前に書かれた「はじめに」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。
「私は昨年の10月に満105歳を迎えました。これまで駆け続けてきた人生で、私が大切にしてきたのは、『いくつになっても、今日がいちばん新しい日』であるという考えかたです。そして今、若かりしころよりもむしろ歳を重ねてからのほうが、新たに始まる今日という日の輝きは増しているように感じています」
続けて、著者は「新老人」という言葉について述べています。
「私が『新老人』という新しい概念を打ち出し、世間に訴えかけたのは2000年9月のことでした。簡単に言えば、65歳以上を老人と規定し、引きこもってしまうなどとんでもないこと。75歳以上を新老人と呼び、もう一度、人生の午後の後半に与えられた時間をクリエイティブに生きていこうという提言です」
1章「老いて高める」の「最初に終わりのことを考えよ」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。
「人間のからだは所詮、やがては土に還る『土の器』です。その土の器に何を入れるのか、そのことは生涯を通して問いつづけなければなりません。もし、その土の器に健全な心を宿すことができたならば、その心こそは朽ちない宝となるに違いありません」
著者は、英国の作家スティーブンソンの「かたくなな老年と青春」の一文を紹介します。『若き人々のために』橋本福夫訳(角川書店)の中に収められている名文ですが、その内容は以下の通りです。
「真の知恵は、常に季節に応じ、変化する環境の中で、しなやかに変化していくことである。子供の時には大いに玩具を愛し、冒険的な正義に満ちた青春を送り、時がくればすこやかで微笑む老年に落ち着くことこそ、人生のすぐれた芸術家であり、そのことは自分にも自尊心をもち、隣人にも尊重される者となる道であろう」
そして、著者はイタリアのルネッサンス期の天才レオナルド・ダ・ヴィンチの「十分に終わりのことを考えよ。まず最初に終わりを考慮せよ(老いというのは、遠いものだと考えるのではなしに、若いうちに老いがはじまっているのだ)」、および「老年の欠乏をおぎなうに足るものを青年時代に獲得しておけ(老人になるといろいろのことを失ってくる。それを若いときに獲得しておけ。老人になっても燃える人生エネルギーを若いときに蓄えなさい)」という言葉を紹介します。
では、何が老人になったときのエネルギーとなるのか。著者は述べます。
「それは、よき本を読み、ゆかしい音楽を聴き、そして何より大切なことは、感性を高めるよき人との出会いをもつことです。そのことによって、私たちはエネルギーをもらい、それを我々のからだの中にだんだんと蓄えながら、老いに成熟していくのです。若い人も、人生の午後に立つ人も、老いの日のために蓄えなければなりません」
「『老いる』とはどういうことか」では、著者は「私たちには2つの年齢があります」として、以下のように述べています。
「ひとつはクロノロジカル・エイジ(暦年齢)。もうひとつは、その人固有の、暦ではない実力の年齢で、これをフィジオロジカル・エイジ(生理学的年齢)といいます。前者は生年月日での評価、後者は実力での評価です。
たとえば、60歳でも『あの人は若い』といえる人は、その人の暦年齢よりも生理的にはもっと若い機能をもっている。逆に、45歳でも『老けている』といわれる人は、暦年齢よりも生理的に老化現象を示しているおとになります。私たちの老化は、各人各様に進行するのです」
2章「老いを認める」の「有終の日々を生きる」では、2500年前のギリシャ人が歌で数えあげた人々の「善きもの」が紹介されています。ソクラテスとゴルギアスの対話の中に登場する俗人の歌で、「一番善いのは健康で、次の善いのは器量のよいこと、そして三番目は正直に手に入れた財産だ」というものです。
幸福の具体的内容はその人の境遇によって異なるとしながらも、著者は「一般的にいって老人が幸福に余生を暮らすのには、住居と経済、人間関係、健康の3つがいちばん重要な要素となります」と述べています。
本書を読んで最も個人的に勉強になったのは、耳の遠くなった老人についてのくだりでした。著者は以下のように述べています。
「老人性難聴は、老人を言葉の世界から追いやり、孤独にします。言葉がわからないと、つい外出を嫌い、自閉的に振る舞います。そこで老人には、言語が把握できる程度の声の大きさと、間をおいて歯切れよく、耳近くで語りかける努力が、語りかける側に必要となります。ゆっくりジェスチャーを交えての配慮ある語らいが、老人を孤独から救います」
さらに著者は、以下のように述べています。
「盲、聾、唖と3つの感覚を失いながらも、すばらしい教育者となったヘレン・ケラー女史(1880-1968)は、『自分が失った感覚の中で、何か1つ与えられるとなったら、私は聴力を取りたい』と語ったという話を、私はどこかで聞いたことがあります。人の声は愛情をじかに伝えます。テレビを音なしで見るよりも、画像のないラジオを聞くほうが、はるかに奥深いものを含んでいるのではないでしょうか。老人に話しかける側の細かく配慮された言動が、増幅器のごとく受ける老人の聴力を高めるのです」
この他にも、著者は老人が健康に長生きするうえで重要なさまざまなことを平易な言葉で語っています。著者は戦後いち早く、患者と対等に接する医療に着目され、看護教育の充実などに取り組まれました。また、ベストセラーの『生きかた上手』をはじめ、ソフトに命を語る姿勢が幅広い世代に親しまれました。超高齢社会のネガティブな側面ばかりが強調される昨今ですが、著者は「老い」の豊かさを説き続けた方でした。わたしは本書を「老い」のガイドブックとして、これからも読み返したいと思います。
