- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2017.10.02
わたしのブログ記事「ひよっこ」で紹介したドラマが先月30日をもって終了しましたが、この作品はプロポーズや婚約発表の場面が非常に多いのが印象的でした。乙女寮の寮長だった幸子と雄大、すずふり亭の高子と奥茨城村の太郎、あかね荘の早苗とドラマーの彼氏、米屋の一人娘さおりと三男、シェフの省吾と愛子、そして、みね子とヒデ・・・・・・本当に、幸せな気持ちになれる朝をたくさん与えてくれました。このドラマの時代である高度成長期というのは、男女がどんどん結婚していった良き時代でもあったのです。現在の日本といえば「非婚」が時代のキーワードになっており、嘆かわしい限りです。
わたしのブログ記事「ヴィラルーチェOPEN!!」で紹介したように、10月1日、わが社の新しい結婚式場がオープンし、「振袖フェア」など大勢のお客様で賑わいました。総支配人の報告によれば、過去最大の実績が生まれそうです。 1組でも多くのカップルが日本各地で誕生しますように!
『婚姻の話』柳田国男著(岩波文庫)を読みました。 現代日本の非婚化、少子化を深く憂いているわたしですが、それを打開するとはいかないまでも、少しは発想を変えて改善策を考えるヒントのようなものを本書から与えられました。日本民俗学の創設者である著者による古典的名著ですが、岩波文庫創刊90年記念出版の1つとして、今年の7月に刊行されました。この読書館でも紹介した『日本人とはなにか』では、日本人を幸福にするという著者の崇高な志に感動しましたが、本書の読後にも同じ感動がありました。
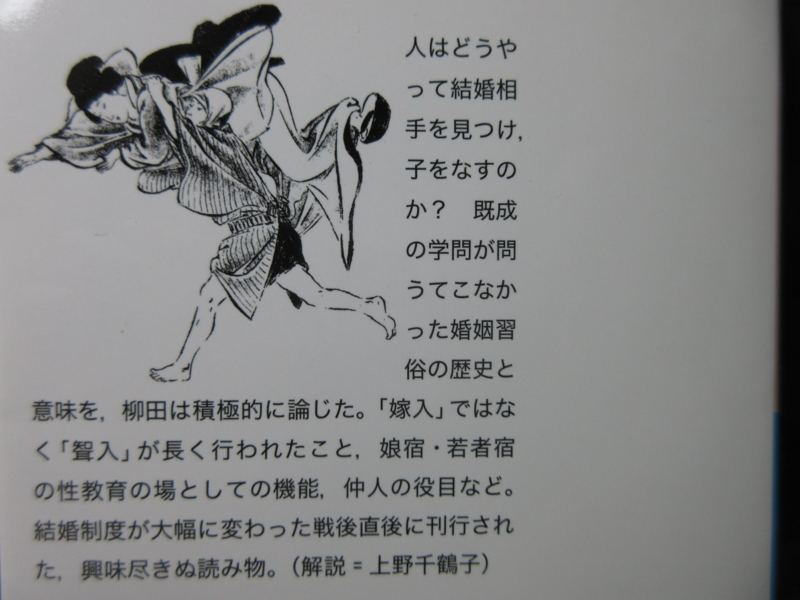 本書の表紙カバー
本書の表紙カバー
本書の表紙カバーには「畑の女の嫁入奇風(嫁かつぎ)」(『風俗画報』第107号、1896年)の図版とともに、以下のように書かれています。
「人はどうやって結婚相手を見つけ、子をなすのか? 既成の学問が問うてこなかった婚姻習俗の歴史と意味を、柳田は積極的に論じた。『嫁入』ではなく『聟入』が長く行われたこと、娘宿・若者宿の性教育の場としての機能、仲人の役目など。結婚制度が大幅に変わった戦後直後に刊行された、興味尽きぬ読み物。(解説=上野千鶴子)」
また、帯には「柳田民俗学が明らかにした結婚をめぐる〈力学〉とは?」と書かれています。
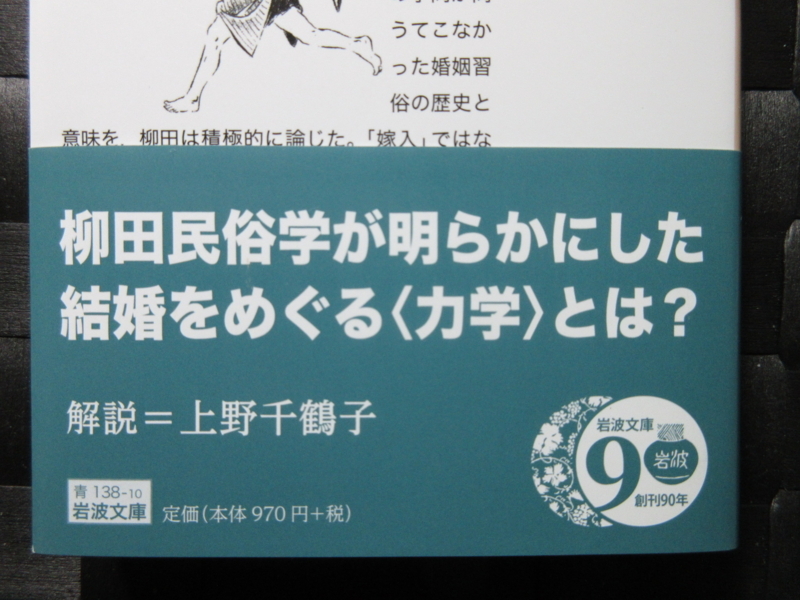 本書の帯
本書の帯
本書の「目次」は、以下のような構成になっています。
「まえがき」
家を持つということ
子無しと子沢山
女の身すぎ
夜這いの零落
錦木と山遊び
出おんな・出女房
嫁盗み
仲人及び世間
婚礼の起源
聟入考
「解説」上野千鶴子
「用語索引」
「まえがき」では、著者は以下のように述べています。
「この本の標題は付けにくくて困った。『未婚者読本』とでもしたら新らしくてよいが、それでは露骨に過ぎ、また少しばかり著者の本意とも合わない。ぜひとも読んで考えてもらいたいのは未婚者だが、私はそれと同時に彼らの後の幸福を、切に顧念している年輩の人々にも、冷淡でいてもらいたくないのである。聴く人が一方に偏しているときまれば、男女の問題などはいくらでも興味深く、もしくは深刻に話すことができるだろうが、私においてはこれを密室の書とするような意図はさらさらなく、むしろそれとは正反対に、今こそ明朗々たる公堂の中の、白昼の問題としなければならぬ時だと思っている。親子姉弟が1つの光の下に、声を揚げて共に読み得る程度にまで、我々の率直さは制限せらるべきだと思っている」
わたしは、この文章を読んで、『日本人となにか』に収められた「処女会の話」というエッセイを思い出しました。以下のような内容です。
「私などの見たところでは、女が望み通りの結婚をし得るということが、最初からそう容易な事業ではなかったのである。ちょうど男子の立身出世の願いに失望が多く、その成功率はいつも小さかったのと同様に、いわば自分の力にかなうものより、二歩か三歩かさきを目ざすのが望みだったからである。以前は家族が大きく主婦の地位が少く、それを得かねて一生を送るものが多かった。今日はもうそういう失望はなくなった代りに、もう少しおもわしい口がありそうなものだという歎息は、当人はもとよりのこと、まわりの人たちからも始終洩らされていた。意見のちがうということがもしありとすれば、たいていはこの見切りのつけかたにあったかとおもう。一方は今日までの多くの見聞によって、あてもなく高望みをしていたものの、いたずらに佳期を逸した先例を経験しており、他の一方はそれをまだあまり知らないのである。いわゆる身を知り人を知って、外目にも公平な判断をさせることは、年若なものには無理な注文であった。そうして一方かの村々の特殊夜学校においては、他にいろいろのいやなことがつきまとうていたとはいいながら、少くともこれだけは一つの必修科目だったのである」
「子無しと子沢山」では、どんなに大人数の大家族であっても、主婦は1人しかいなかったとして、著者は以下のように述べています。
「仮に一家の族員が10倍だったとすれば、9人までの娘はおかみさんになれない。下手に選択などはしていられなかったのは、主婦とその他の婦女と、両者の境遇に著しい相異があったからである。もとより職蜂のごとく中性にはなっていないゆえに、事実上の婚姻は必ずしていたが、これが次の代を作り立てる上に、大きな障碍であったことは否むことができない。家長になれなかった丁男もこの点は同じことで、みじめさはこれに勝るものがあったかも知れぬが、この方にはまだいろいろの自由があった。女はしみじみと独身の老後を考える折が多いので、いきおい発奮して相手方の選択に合格して、主婦になろうとしなければならなかった」
「よばいの零落」では、この読書館でも紹介したフュステル・ド・クーランジュが著した『古代都市』の内容を連想させます。同書には、古代ギリシア人や古代ローマ人たちが、一族ごとに異なる神を祭った事実が示されています。「よばいの零落」には、以下のように書かれています。
「自分などの想像では、もとは一門一族ごとに、めいめいの神を祭っていた。神の奉仕を任とする1人の処女のみは、当然に娘組の仲間に加入することができなかったのである。常陸鹿島の物忌という選ばれたる女性などは、老いて働けなくなるまでその職を守っていたが、丹後のある神社の巫女のごときは、この世心が内に萌すと、何か兆候が外に現われて、畏れて山を下ることにしていたとも伝えられる。その年齢は不定であったが、再び尋常の娘組の統制に、服することを得なかったのは明かである。中世の氏の神の奉仕者に至っては、すでに夫婿のある家刀自が、これに当ることになっていた例が多い。いわゆる神のもろ臥しが処女でなければならぬという掟は弛んで、貴人の配偶者をもってこれに代えた例は、沖縄などでも特に顕著であった。この傾向は信仰の合理化とも見られ、また同時に衰微とも感じられるが、とにかくに世の中の進みに伴ない、こうならずにはおられなかったことは、いくつもの民族に共通なものではあった」
「嫁盗み」では、この読書館でも紹介した『先祖の話』で著者が詳しく述べた日本人の死後についての考え方が以下のように示されています。
「昔の日本人は死後を信じていた。死んでも盆ごとに家に還って来て、眼にこそ見えないが子の子、孫の孫たちと飲食休養を共にし得るということが、どれほどこの家の永続を切望させ、また大きな愛着をこれに対して、抱かしめたか測り知れないのである。それはちっとも当てにならぬことだと、今の人はむろん否認しようとするが、とにかくに実際は人もわれも、共にこれを信じていたために、祭が真剣であっただけでなく、死の床の不安は著しく軽め得られ、それがまた人生の発足の時から、ちゃんと計算の中に入っていたことは、今なら我々はいくらでも証拠が挙げられる。この古来の確信の少しずつ揺ぎ出したことも、決してつい近年のこととは言えない」
続けて、著者は以下のように述べています。
「何かその代りになるべきものを見付けようとして、まじめな人たちは大分苦労して来たが、それには信仰も哲学も皆個人的な教化であって、この小さな集団を永続させる力はなく、むしろ無知なる人々の古風墨守を、羨んでよいような場合が多かった。殊に悲しいことは1つの解決もなく悟りもなくて、忘れたり茶化したり、ただ現在だけのために活きようとする者の多くなったことである。こういう人たちの生活計画は失敗するというよりも、むしろ最初から計画がないので、末々故障がなかったら幸運といってもよいので、かくして向う見ずな恋の遊びが、婚姻生活と入り交ってしまうことになってしまうのである」
「仲人及び世間」の冒頭を、著者は以下のように書きだしています。
「誕生と死亡とに伴なう我々の行事作法は、半ば無意識にもまだ古来の慣習を伝えた点が多いのに反して、婚礼の儀式ばかりは、ほとんと全部といってもよいほどの変化を受けている」
それから、「嫁に遣る」ということが家にとってどのようなことであったのかが以下のように述べられています。
「娘が家々にとって大切な生産労力であった時代を考えると、嫁に遣るということは貰い受けるということよりも、一段と重要な事件だったに相違ない。聟が可愛くてしかたがなかったという話も残ってはいるが、それよりもあまりへまな受け返事ばかりするために、娘を取戻されたという昔話の方が多い」
続けて、著者はかつての日本の婚姻について述べます。
「能の狂言の何々聟や、花祭の翁の語りを見てもわかるごとく、聟入ほど晴がましくまた花やかな思い出はなかったのである。それを延期して里開きのついでをもって挙行したのも変遷だが、今日はさらにお嫁入の祝宴の中にもみ込んでしまって、それがあったのかどうかも意識のうちに残らぬようになっている。大きな原因は嫁の支度ばかり大袈裟になったため、かつは経済の組織が改まり、家を祝宴場にする設備がなくなり、雇人も出入の者も不足がちで、料理屋へ持出す他に策がなくなったからである。そういうことを2度3度も繰返すのが、費えであることはわかっている。こうして1回にまとめてするのもよい思案だとは思う。ただそのために縁の薄い当世人ばかりが出しゃばって、大事な親類は隅の方に小さくなっており、何だか対社会の披露万能の式のように変ってしまったのが不本意である」
そして、著者は日本の婚姻式典について以下のように述べるのでした。
「私は日本の婚姻式典の、現在すでに大いに変って来たのを見、またこれからもさらに変わらずにおらぬことを察して、国民の1人としていくつかの希望または注文を抱いている。たとえば仲介役はぜひとも当人たちの親友にさせたいこと、親族の誼みが1回の婚姻ごとに、ぐらぐらと変化することを防ぎたいこと、公衆の承認と支持とは、もっと堅実かつ広範な範囲に頼むことにし、御馳走を食べてすぐに忘れてしまうような酒食の宴をやめたいこと、その他いろいろの願いを持っている」
「婚礼の起源」では、近世の婚礼が法外な消費事業となり、いきおいこれをただ1つの機会に集中しようとしたことが、多くの省略や便宜主義を、考案せしめたことは事実であるとして、著者は以下のように述べています。
「人の一生のたった1つと言ってよい思い出を、できるだけ花やかなものにしようとした動機には同情し得られるが、実はこの変化のあまりに急劇だったために、我々はまだ各地各家庭の新らしい方式なるものが、これほどにもまちまちになっていることに気づかず、ましてそうなって来た事情をかえりみることもできないだけは損失である」
また、「婚礼」というものは主婦の入家式、もしくは主婦試補の就任式であって、目的は主として彼と四周の者との、一族一家となる点にあったとして、著者は以下のように述べます。
「当の本人両者の結合は、もっと以前から始まっていて、それをただ新たに承認するの必要が生じただけなのである。聟が自分の家において、この日なんの役もないのは当り前だったのに、これを珍らしがったり注意したり、または怪しんだりする者が、かえって後々出て来たのである」 そして、最後に著者はこのように述べるのでした。 「婚礼は要するに遠く離れた家々の縁組によって発達した。もとはただ相許した2人の間に、1つの飲み物1つの食べ物を、分けてたべるという、自然の情愛から起ったのであったと思う」
「聟入考」では、「結婚」という言葉が使われる以前の時代について以下のように述べられています。
「ケッコンという語が普通の用語となる以前、わが邦には精密にこれに該当する語、すなわち『夫婦の仲らいの始め』を意味する語はなかったようである。ただ近世中以上の家庭のほぼ全部において、新婦の引移りをもって婚姻生活の開始としていたゆえに、事実上結婚をヨメイリといっても、その人たちだけにはすこしも差支がなかったのである」
しかし、一方では結婚よりはるか後れて、嫁女を聟の家に送る風習が、今でも若干の地方には公けに認められ、それが前代に遡るほど一段と弘く行われていたとして、著者は以下のように述べます。
「例の『源氏物語』の時世には、京都貴紳の家でも、最初から新婦を迎え取るということはしなかったのである。こうなると嫁入は決して結婚ではなく、単に結婚後のある1つの手続に過ぎぬのであったが、当今の法制はその力をもって、むしろ新たに前代と異なったる風儀に統一して、一部残留の慣習を蔭のものにしてしまった。嫁の引移りに伴なう儀式のみを挙式と名づけて、婚姻の始めと認めることにした」
そして、婚姻とは何か。著者はこのように述べるのでした。
「婚姻は万人の必ず一度以上計画しまた実行するところではあるが、その様式にはおのずから各自の標準とするものがあって、必ずしも全国諸種の境涯にある者と、歩調を一にすることを念としてはいない。たとえば京都貴紳の執行う作法と、諸国に分散する武士土豪の礼式とは、いずれの世にも一方が他方を代表してはいない。従って同じ時代を比べてみても、なお明白なる相違が見られたかも知れぬ。それをあたかも時代の差のごとく見ることの不当なるは言うまでもない」
本書に収録した論文は、「仲人及び世間」「聟入考」の2篇を除いて敗戦後の昭和21年(1946)から22年に書かれています。新憲法によって「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」すると宣言された時代です。新民法によって家制度が否定され、婚姻に戸主の同意は必要なくなりました。「解説」で、社会学者の上野千鶴子氏が以下のように述べています。
「日本は見合い結婚の国、それが日本の伝統文化である、という説に、柳田ははっきりノーをつきつける。見合いの場で初めて会ったり、極端な場合には結婚式の場で初めて会うような結婚を、柳田は「野蛮」と呼んだ。ちくま文庫版全集の『解説』で鳥越晧之[1990]が述べるように、戦後民主主義の時代にあって、見合いという『結婚する当人たちの愛情を第一に置かないような婚姻』が不自然なものであって、庶民のあいだにはもともと婚姻自由の伝統があったことを、民俗学の助けを借りて証明しようとしたのが本書である」
また、「『見合い』は創られた伝統だった」として、イギリスの歴史学者エリック・ホブズボームが著書『創られた伝統』において「わたしたちが現在『伝統』と呼んでいるものも存外歴史が浅く、あとになって『伝統』と捏造されたものが多い」と指摘していることを紹介しつつ、上野氏は述べます。
「なぜ見合い結婚が拡がったのか。もともと一部の武家社会の習慣にすぎなかったものが、四民平等のもとで庶民のあいだに拡がり、家柄・家格を気にする家長が遠方婚をのぞみ、そのための仲介役に仲人が登場し、結婚に『戸主』の同意を必要とする明治民法による家長権力の強化が後押しをし・・・・・・あげて日本の近代化が原因である。あまつさえ、恋愛結婚は『くっつき夫婦』や『野合』と呼ばれて蔑まれ、嫁入りは披露宴と同時になり、長きにわたる嫁姑関係の始まるきっかけとなった。女性史家のひろたまさき[2005]は嫁姑問題は近代の問題であると喝破した。舅姑が長生きするようになって同居期間が延びただけではない。柳田によれば『同居は古来の風ではなかった』からである」
「性の近代化」として、上野氏は柳田国男にとってのタブーについて以下のように述べています。
「『白足袋の民俗学者』として知られる柳田には、3つのタブーがあるといわれる。天皇制、やくざ、性である。最後の性について果敢にとりくんだのが柳田の高弟、瀬川清子と、在野の民俗学者、赤松啓介である。婚姻には性がつきもの、柳田は本書で婚姻とそれに先立つ寝宿習俗とには言及するが、その詳細には立ち入らない。娘は何歳から娘宿に入るのか? 娘宿で何をするのか? 好きな男を受け容れて嫌いな男を拒否する権利はあったのか?・・・・・・その細部に立ち入ったのが瀬川清子であり、現場にのりこんで自ら参与観察したのが赤松啓介であった」
「敗戦後の自由と解放?」では、上野氏は「よばいの零落」の最後にある、適切な配偶者選択機関がなければ、「エニシというがごとき漠然たる宿命を信じて、たまさか遭遇するものが最上の夫であるべきことを、神や仏に祈願するより他にないであろう」という記述について、「偶然の『縁』のアタリハズレを恃むしかない現状を揶揄しているのである。良縁を求めるその選択機関が、今では合コンやコンピューターによるマッチング産業であると知ったら、柳田はどんな顔をするだろうか」と述べています。
「解説」の最後に、上野氏は「人口現象の謎」として、「人口現象には、わからないことが多い」とした上で、「生れるという方にはまだ微妙なる幾多の法則の、埋もれているものがあるらしいのである」「世代の推移、または個々の生活ぶりの甲乙によって、見遁すことのできない繁殖率の差があったのである。・・・・・・民族一個体としての、寿命といい健康ともいうべきものに、この際特に着目する人があってよいのではなかろうか」という柳田の言葉を引いて、以下のように述べるのでした。
「人口誌学demographyが登場する以前のことである。性愛、婚姻、出産、家族というミクロの現象は、人口、国家、経済というマクロ現像と連続している。『婚姻の話』は好事家の主題ではなく、学問の正統な主題であるべきことを、本書で柳田は宣言したことになる」
本書を読んで、わたしのブログ記事「『日本人を幸福にする方法は何か』柳田国男の志」で書いた内容を思い出しました。
柳田が創設した日本民俗学は「祭」とか「先祖」とか「家」の問題などを研究しながら、日本人の血縁や地縁の意味を問うていく試みでした。それゆえに「無縁社会を克服し、有縁社会を再生」するヒントの宝庫であるわけですが、そこには「幸せな結婚をさせる」「離婚をさせない」、さらには「親子心中をなくす」といった志さえ込められていたのです。
もともと柳田の学問の原点には、日本一小さな家に幾組もの家族が同居していることによって生じる不幸だとか、若くして見た絵馬の図柄の、わが子を間引く母親の姿から受けた衝撃といったものがありました。結局、柳田国男という人は、「日本人の幸福」というものを生涯考え続けた人なのでしょう。ある意味で、本書は半世紀後の無縁社会の到来を見事に予言した名著『先祖の話』と対になる存在であると思います。この2冊を読めば、日本人の血縁や地縁の本質が浮き彫りになり、「無縁社会を克服し、有縁社会を再生」する一筋の光が見えてくる気がします。

 「
「