- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2017.12.22
『呪いと日本人』小松和彦著(角川ソフィア文庫)を再読しました。
1995年に『日本の呪い 「闇の心性」が生み出す文化とは』として光文社から刊行された単行本を加筆・修正したものです。著者は1947年東京都生まれ。東京都立大学大学院社会人類学博士課程修了。信州大学助教授、大阪大学教授を経て、現在は国際日本文化センター所長です。わたしは、異色の民俗学者である著者の本はほとんど全部読んでいますが、この読書館でも紹介した『神隠しと日本人』に続いて、本書を再読しました。
本書のカバー裏表紙には、以下のように書かれています。
「鎌倉幕府を呪詛調伏した後醍醐天皇の『荼吉尼天法』、戦国武将の武田信玄や上杉謙信が用いたとされる『飯綱の法』、現在も残る呪詛信仰で名高い高知県旧物部村の『いざなぎ流』―。日本の歴史において、『呪い』とは何であったのか。それは、現代に生きる私たちの精神性にいかに受け継がれ、どのような影響を与えているのか。民間信仰研究の第一人者が、呪いを生み出す人間の心性に迫り、精神史の新たな足跡をたどる」
本書の「目次」は、以下のような構成になっています。
プロローグ―なぜ、いま「呪い」なのか
1章 蘇える「呪い」の世界
2章 なぜ、人は「呪い」を恐れるのか
3章 どのように呪うのか
4章 「呪い」を祓う方法
エピローグ―「人を呪わば穴ふたつ」
「文庫版あとがき」
「プロローグ―なぜ、いま『呪い』なのか」では、「現代に生きる『呪い心』」として、著者は以下のように述べています。
「人には多かれ少なかれ、誰かを恨んだり、妬んだり、はたまた呪いたくなる心性がある。『あいつがいなくなれば(死ねば)、自分の成績の順位(会社の地位)が上がる』と思ったり、人の足を引っ張ってでも出世しようとする同僚や、ことあるごとにいじめる同級生に対して『不幸になればいい』などと思ったりすることは、現代の複雑な人間関係にあってはさして珍しいことではないだろう。これは、『怨念』と呼んでもいいものである。この本では、こうした人間の心性を『呪い心』と呼ぶことにする」
さらに、著者は「呪い」にはもうひとつの側面があるとし、「こうした『呪い心』に導かれて、誰かに危害を加えるために、実際に呪文を唱えたり、道具を使ったりなどといいった神秘的な方法に訴えかけることだ。これを『呪いのパフォーマンス』と呼ぶことことにしよう。つまり、『呪い』は、『呪い心』と『呪いのパフォーマンス』とがセットになってできているのである」と述べます。
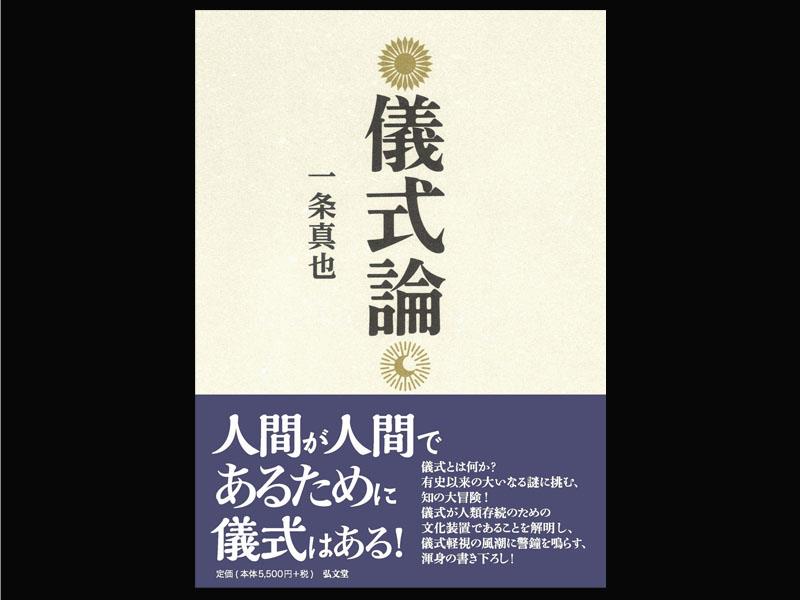 『儀式論』(弘文堂)
『儀式論』(弘文堂)
わたしは『儀式論』(弘文堂)で、さまざまな角度から儀式や儀礼について見ていきましたが、「呪い」の問題もその中に入ります。1章「蘇る『呪い』の世界」では、犬神と祈禱師の戦いを紹介した後で、著者は述べます。
「儀礼=治療によって災厄が除かれることもあれば、失敗することもある。『神秘的なもの』がもつパワーに、祈禱師の『法』(呪法)が負けてしまうからだ。これを『法負けする』という。『法負け』した場合、病人の病いはさらに悪化し、死に至るだけではなく、祈禱師さえも災厄をこうむることもある。そこでさらに強力な法を用いて、そうした事態を克服しようとする。したがって、祈禱は病人が治るまで何日も何カ月も続くことになる」
また、「『呪い』のスペシャリストが、『呪い』をでっち上げる」として、いざなぎ流の祈禱師が、呪いのパフォーマンスがあったかのようにでっち上げを行なっていることが明かされます。祈禱師は呪詛者として確定された人間が、「呪いのパフォーマンス」をしたかどうかを証明する物的証拠を握っているわけではなく、占いや託宣がそう告げているだけなのだというのです。
「呪詛信仰・いざなぎ流」として、著者は「いざなぎ流」を取り上げますが、まずは陰陽道について説明します。陰陽道は近代にはいって急速に消滅してしまいましたが、街角に立つ易者の占いは陰陽道に基づくものであり、厄年や鬼門を恐れる民間信仰も陰陽道がいいだしたものです。そういう意味では陰陽道はまだ生きているとも言えます。陰陽師は、中世では「博士」とも「相人」とも呼ばれ、民間で活動した下級の陰陽師は、「唱門師」などとも呼ばれていました。これに対し、いざなぎ流祈禱師は、土地の人からは「太夫」と呼ばれていました。
しかし、四国地方では巫女、行者(山伏)、神職など祈禱を行なう宗教者の総称であって、いざなぎ流祈禱師だけに用いられるものではないとして、著者は以下のように述べます。
「彼らは、ほかの太夫と自分を区別するときには、『博士』(はかしょ)という呼び方をすることがある。このことからも、いざなぎ流が陰陽道の末流であることがわかる。陰陽道の影響は、祈禱師が執り行なう各種の祭儀にも色濃くあらわれている。彼らは、前にあげた病人祈禱だけではなく、物部の集落の氏神の祭りや家ごとの先祖祭り(家祈禱という)、あるいは山の神や水神などの祭りの儀指導者としても村びとに雇われている。この祭儀の方式に陰陽道の伝統が強く出てくるのだ」
著者は、草創期のいざなぎ流の太夫たちは、おそらくどこからかこの土地に流れてきた陰陽師博士だったのだろうと推測します。彼らは、定着していく過程で土地の人びとのもともとの民俗的な信仰を吸収し、変形させていったのだというのです。そして、その中核に人間関係のゆがみから生じてくる「すそ」を置いたのだといいます。このことをはっきり物語っているのが、重要な祭儀の最初に一日がかりで行なう「取り分け」という儀礼です。
「取り分け」は「すその取り分け」とも呼ばれますが、著者が以下のように説明しています。
「日本や物部村や村びとの家といった空間、さらには祭儀参加者の身体(これも一種の空間である)のなかにもあるとされる、まだ目に見える形では災厄とはなっていない『すそ』つまり『ケガレ』を、丹念に捜し出し呼び集めて、『みてぐら』に封じこめ、日本と唐土(中国)と天竺(インド)の境界上にあると考える『すその御社』に送り流してしまうという内容の儀礼である」
「すその取り分け」について、さらに以下のように説明されます。
「『すそ』を象徴的にあらわすものとしては、爪、すね毛、あじゃ、家の畳のゴミ、柱を削ったもの、家のまわりの四隅の土、かまどの灰、墓場の土、現在は祀られていない聖地の土などがあり、祭儀のときには氏子たちによって太夫のもとへ集められる。太夫はそれらのものを『みてぐら』に移し、集落の特定の場所に決められている『すそ林』に穴を掘って埋め、上に重い石を載せて『すそ封じ』とするのである」
この「すその取り分け」儀礼は、基本的には病人の祈禱と同じ儀礼であるとして、著者は「病人祈禱は病人の身体のなかにある『すそ』を祈禱師が取り集め、それを『すその御社』へ送り鎮めて病気をなおそうとするものであった。つまり、「病人祈禱」はすでに発生している災厄を祓い捨てる儀礼であるのに対し、『すその取り分け』はまだ災厄になっていない状態の『すそ』を祓い捨てる儀礼なのである」と述べています。
いざなぎ流の起源説話ともいうべき「いざなぎの祭文」からは、いざなき流が異界(天竺)に伝承されていた祈禱法―実際にはかつて日本各地で行なわれていたさまざまな宗教―をもとにして作り上げられたことがうかがい知れます。また、「人形祈禱」と「弓祈禱」が、いざなぎ流の祈禱法の大きな柱となっていることもわかります。この弓を使って行なう祈禱法・呪詛法は、人形を使う呪詛法にも登場するように、いざなぎ流の祭儀にはよく用いられます。神を招き寄せたり、あるいは神霊を脅かして追い払たりするためです。
著者は、「いざなぎ流祈禱師は、『外法使い』か」として、「梓巫女」が弓を叩いて神憑って託宣をする信仰や、悪霊の類いを弓弦を鳴らして追い払う「蟇目法」などの呪法も入り込んでいることを指摘した上で、「もっとも、いざなぎ流の『蟇目法』は、弓矢で大陽を射るという恐ろしい法で、とんでもない目的を強引に実現させようとするときに用いられるという。太陽を射る―弓矢が届くはずもないのにどうして射られるのだろうか。それにはトリックがある。たらいに水をはり、そこに映った太陽を射るのだそうである」と述べています。
著者は、「なぜ、現代人は水子の祟りを気にするのか」として、呪い信仰がル成り立つためには、人の呪い心に説明を与え、「あなたは呪われている」と判断してくれるスペシャリストが必要だと述べます。そして、「少しまえまでは、全国各地にこのような役割を演じる祈禱師たちがたくさん活働していた。それが、西洋医学をはじめとする近代科学の浸透によって、多くは後継者をえられずに消え去っていった。それにともなって、『呪う』―『呪われる』という関係を説明する信仰も、急速に衰退してしまったのである」と述べています。
さらに、「呪いの世界へのタイムマシン」として、いまでも物部村にはいざなぎ流が衰退しつつも生き続けていることを指摘し、「なぜいざなぎ流が存続してきたのか」と問いを立てた著者は、その理由を以下のように述べます。
「おそらく、その最大の理由は、村びとの家ごとの祭儀が、いざなぎ流太夫たちに掌握されていたことにある。とりわけ、いざなぎ流祭式による先祖祭としての性格をもつ家祈禱は、他に類をみないほど大がかりなものである。旧家の家祈禱では、理想的には6人の太夫が必要だとされ、大むかしは12人もの太夫が必要とされていた」
こうした祭儀に長いこと慣れ親しんできた村びとが、いざなぎ流祭式での祭儀を求め続けてきたとして、著者は以下のように述べます。
「そこに自分たちのアイデンティティーを見出していた、といえるかもしれない。そして、物部村の人びとは、こうした大がかりな祭儀を可能にするほど多くの太夫を養い続けていたのである。このために、周囲の村や町の人たちからは、異常なまでに太夫がたくさんいる、一種の『太夫村』として知られるようになったわけである」
そして著者は、「日本の呪い」について、以下のように述べるのでした。
「たしかに、山奥の村のことである。しかし、真理は細部に宿ることがある。物部村には、そしていざなぎ流には、『日本の呪い』を研究するのに必要な、ほとんどすべてのことが伝えられているといえるのである。いざなぎ流が説く『すそ』について、ここでは『呪い』にしぼって紹介してきた。それは要するに『ケガレ』のことであり、それを身体から、社会から祓い捨て、身体や社会を浄化し、再生させる儀礼を行なうことが太夫たちの基本的な役割であった。こうした『すそ』とその『祓い』のダイナミズムこそ、日本の『呪い』の仕組みを、そして日本の社会の仕組みを読み解く基本となるシステムなのである」
2章「なぜ、人は『呪い』を恐れるのか」では、「『呪い』が支配する世界」として、著者は以下のように述べています。
「奈良時代―それは私たちに、『青丹よし奈良の都は咲く花の匂ふがごとくいま盛りなり』という歌に象徴される、華やかに繁栄し、平和に満ち満ちていた時代、というイメージを想起させる。そして、強大な律令体制のシンボルとしての東大寺の大仏殿も」
しかし、実際はそうではありませんでした。著者によれば、咲く花の奈良の都の巷には、呪詛が盛りとばかりに満ちあふれ、宮廷内の政治も呪詛に導かれて行なわれていたといいます。たとえば、神亀6年(729)2月の、天武天皇の孫にあたる左大臣・長屋王の呪詛事件があります。長屋王が、「左道」つまり邪術を密かに学んで国家反逆を企てているという理由で聖武天皇の怒りをかい、天皇の命により妻子とともに自殺に追い込まれた事件です。
また、「呪われた奈良王朝」として、著者は以下のように述べます。
「光仁天皇、そしてその跡を継いだ桓武天皇も、この母子の霊をひどく恐れ、この後、その怨霊の祟り、つまり死者の呪いを鎮めるにことにたいへんな神経を使うことになる。桓武天皇がついに奈良の都・平城京を捨て、長岡京へ都を移そうとした理由のひとつは、このふたりの怨霊の祟りから逃れるためであった。しかし、新たな呪い(実弟・早良親王の祟り)の発生が計画を頓挫させ、結局、平安京に都を求めることになる。御霊(怨霊)の時代ともいえる平安時代は、こうしてはじまったのである」
著者は「近い関係だからこそ、『呪い』が生まれる」として、呪う者と呪われる者がごく近しい社会的関係にありながらも、両者のあいだに潜在的な対立があるようにみえることを指摘します。そして、一連の呪詛事件は、天智天皇系統につらなる皇族と天武天皇系統のそれとのあいだの、皇位をめぐる争いであるとして、以下のように述べます。
「天智天皇と天武天皇は兄弟である。つまり、近しい関係にあればあるほど、いったん愛と憎しみ、富の所有と排除をめぐって『呪い心』が生じると、はてしのない泥沼に陥っていく。日本の国をつくったというイザナギとイザナミの夫婦神によるこの世とあの世の境での呪詛合戦や、男をめぐって争った醜女のイワナガヒメ (磐長姫)と美女のコノハナサキヤヒメ(木花咲夜姫)の姉妹、釣り針をめぐって争った海幸彦・山幸彦兄弟の呪詛事件も、こうしたカテゴリーに入る」
続けて、著者は「呪い」の対象となる人物について述べます。
「人は自分にとってどうでもいいようなは対象に『呪い心』を抱いたりはしない。かつて愛したからよけい憎んだり、利害が密接に関係すればするほど妬んだりするのである。マンションの隣人が別荘を持ったことを妬んでいやがらせすることはあっても、見ず知らずの大富薬を妬み、呪ったりする人はあまりいない」
著者は「なぜ、死者を恐れるのか」として、もともと、祟りというのは、神仏が示現すること、つまり霊験(奇跡)をあらわすことであり、必ずしもマイナスのイメージだけが託されていたわけではないことを指摘し、以下のように述べます。
「それが、次第にマイナスの面が強調され、人間に対して怒りをもって示現することが祟りだということになった。これが、平安時代になってさらに変質した。神の祟りだけではなく、死者の霊が生前の恨みを晴らすため、つまり生前にかけた呪いを実現させるためにこの世に生きている者に災厄をもたらす、と考えられるようになったのだ」
続けて、著者は「死者の呪い」について述べています。
「死者の呪い―生者にとっては、これほど始末におえないものはない。たとえ、憎き相手や呪いや物理的手段で殺したとしても、その人物の怨霊が生者を呪い続けて災厄を及ぼすというのだから。これが生者の呪いであれば、ひょっとしたら敵対関係そのものを修復できるかもしれないし、呪いをかけている人物を発見して、遠方の地に流したり、獄につないだりして、二度と呪えないようにすることもできる。だから、この時代にあっては、死霊になって祟ることを恐れるあまり、反乱・反逆の首謀者を処刑できず、しかたなく流刑にしたというケースもあったかもしれない。場合によっては、政治的ライバルの自然死さえも恐れていたかもしれないのだ」
こうした死者の呪い―怨霊を恐れる心性は、この時代だけにとどまるものではありませんでした。その後も日本文化の負の核としてしっかり根づき、生き続けることになります。著者は、怒霊の祟りに対する信仰が、新しい祭祀の形式、「御霊信仰」を生み出したとして、以下のように述べています。
「これはいいかえれば、怨霊が祟るという共同幻想に支配された人たちが、その祟りを鎮め・防ぐ方法をどのように発見・発明したか、という問題でもある。結論からいえば、彼らは新たな神を創り出した。つまり、神の祟りを防ぎ鎮めるには神を祀ればいい、という古くからのやり方を敷衍して、怨霊の怒りをほどくあらゆる手だてを尽くしたあとで、神として祀り上げ、あの世へ追い払えばいいのではないか、と考えるに至ったのである」
こうした祭祀を執り行なうために多くの宗教者が動員されました。そして、彼らの説く新しいテクノロジーが呪調防止、呪調返しのために用いられたのです。陰陽道や密教は、そうした新しいテクノロジーでした。
「呪い」は、つねに邪悪なものとだけ結びついていたわけではありません。
「正義の呪い」というものもありました。著者は、「『正義の呪い』とは」として、「正義」の呪い儀礼のひとつである「盗人送り」と呼ばれる儀礼を行なう村落を以下のように紹介しています。
「新潟県東蒲原郡東川村(現阿賀町)では、村でちょっとした盗みなどが発生したときに、『悪者送り』あるいは『盗人送り』が行なわれていた。やり方は、村人が総出で盗人を象徴する人形を作り、村じゅうを送り回したのちに村はずれとか盗みのあった現場に行って、法印(修験者)に呪詛の祈禱をしてもらい、最後に村びとが次々にこの人形を竹槍で突きさいなんでほったらかしにする、というものである。犯人は不明でも、この呪詛の儀礼によって犯人の身の上に、目がつぶれたり、手足が不自由になるといった障害が生じる、といわれていたのだ」
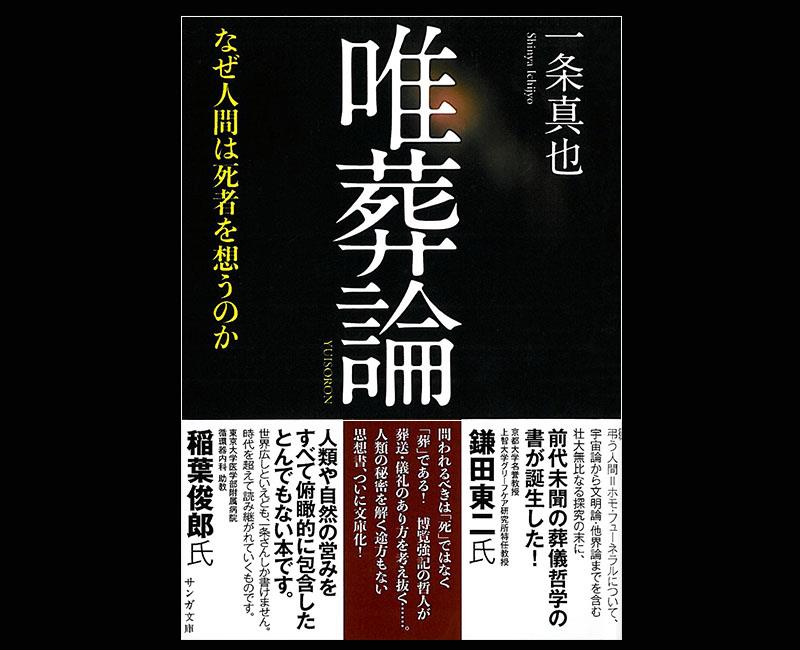 『唯葬論』(サンガ文庫)
『唯葬論』(サンガ文庫)
「呪い」は死者の存在と分かちがたく結びついています。拙著『唯葬論』(サンガ文庫)で、わたしは、人類の文明も文化も、その発展の根底には「死者への想い」があったではないかと述べました。7万年前に、ネアンデルタール人が初めて仲間の遺体に花を捧げたとき、サルからヒトへと進化しました。その後、人類は死者への愛や恐れを表現し、喪失感を癒すべく、宗教を生み出し、芸術作品をつくり、科学を発展させ、さまざまな発明を行なった。つまり「死」ではなく「葬」こそ、われわれの営為のおおもとなのであるというのが同書で展開した主張です。
死者は追慕されると同時に、恐れられる存在でもあります。
「弔われる」存在であると同時に、「呪う」存在なのです。 「社会を批判する死者の呪い」として、著者は以下のように述べます。
「死者の呪い=祟りは、呪われる側に対する批判あるいは反省を強いる呪いだといえる。これに対して、生者の呪いは、いうまでもなく呪われる側を失脚させたり、災いを及ぼしたりするという目的をもつ。
この両者の性格の違いによって、生者の呪いは否定的にみられてきたのに対し、死者の呪いはどちらかというと肯定的に、つまり為政者の悪政への批判としてとらえられてきた。菅原道真や崇徳上皇の怨霊が、たんに社会や自然の混乱・異変の原因としてではなく、人びとの世直し・御一新願望とドッキングして登場してくるのは、そのあらわれでもある」
そして、「呪う」―「呪われる」という関係は、コインの裏と表のようなものであるとして、著者は以下のように述べるのでした。
「人間である以上、誰もが呪われる立場にあり、怨念=呪い心に説明が与えられたときには呪う側にもなりうるということである。その意味で、人間というのは、社会を作りだしたまさにそのときから、悲しい、恐ろしい宿命に呪われているといってもいいかもしれない。人間は、法や道徳や倫理などを作り出し、あるいは「愛」などというイデオロギーまで動員して、恐ろしい『呪い心』の発現をなんとか抑えようとしてきた。しかし、それがすべての人びとを満足させるものとはなっておらず、またなるはずもないのである。どうやら私たちは、いったんは否定し、覆い隠してきた恐ろしいものの存在を、みつめ直す時期にさしかかっているのかもしれない」
3章「どのように呪うのか」では、著者は、今日まで影響を残している呪いのテクノロジーはを以下の3つに大きく分けています。
(1)奈良時代に活躍した呪禁道
(2)平安時代にピークを迎えた陰陽道
(3)古代末期から中世に絶大な勢力を誇った密教
およびそのバリエーションともいえる修験道
「丑の時参り」をはじめとする民衆に流布した呪いのテクノロジーも、この3つの呪いのテクノロジーの影響を受けて発達しました。この3つのテクノロジーは、いずれも中国から伝来したさまざまな宗教的知識・技術をもとにして作り出されたものですが、それ以前、『古事記』や『日本書紀』に描かれた神々の時代においても呪いのテクノロジーは存在していたといいます。
さらに著者は「言霊信仰―言葉を発すれば、それが『呪い』となる」として、以下のように述べています。
「神々の用いた呪詛法は、私たちの知っているそれとはかなり違っていた。素朴ともいえる、言葉に霊が宿っているという言霊信仰がとりわけ盛んだった。たんに呪文や呪いをこめた言葉を発するだけで呪詛が発動したらしいのだ。『おまえを呪ってやる!』といえば、もうそれが呪詛なのである。呪いの言葉を発することによって神秘的パワーが発動し、呪われた人物は災厄に苦しむことになる」
呪いに関する記述は、早くも日本の最初の文字記録である『古事記』や『日本書紀』のなかにも見出されます。この時代は、「呪う」ことを「とこう」(詛う)、「呪いの道具」を「とこいと」(詛戸)と称していたといいます。
そして、著者は「呪禁道(じゅごんどう)」というものを紹介します。ひとことでいえば、呪術的医療の知識・技術の体系ということになります。当時、呪禁師たちは「典薬寮」と呼ばれた政府の医療機関に属していましたが、この呪禁道の実態は現代でいうオカルト学であり、超能力をいかに獲得するかということに深く関係した知識・技術でした。もちろん、それによって病気を治すこともできるのですが、「悪用」すれば呪いにもなりえたのです。
この呪禁道、奈良時代の末期に忽然と律令政府の記録から姿を消してしまいます。著者は、陰陽道を支持する吉備真備たちが、呪禁師たちを追放したのではないかと推測しています。そして、「吉備真備の陰謀」として、以下のように述べています。
「もともと、この陰陽道は、呪禁道とほぼ同じころに日本に伝えられたもので、そのスペシャリストたる陰陽師は、中国の陰陽五行説に基づいて天体を観測し、時刻をはかったり、暦を作製したり、吉凶を占ったりすることが主たる役目であった。今日でいえば、天文台や気象庁のような仕事をしていたわけである。したがって、それほど呪術的な知識とはいえなかった。しかも、奈良時代も末期になると、それなりに日本に定着したものの、『古い』知識になりつつあった」
ところが、真備は唐に留学すること19年、算術・陰陽・暦道・音楽・兵法・築城などの学問を数多く学んで帰朝し、政府の役人として出世していきました。著者は「つまり、真備が招来した『新しい』知識の重要な部分を陰陽道に関するものが占めており、それゆえ陰陽道は飛躍的に改革される機会に恵まれたわけである。真備は、当然のごとく陰陽道に肩入れした。そのいっぽう、呪詛封じのスペシャリストとして精力を誇示していた呪禁道に対しては冷ややかであった」と述べています。
呪禁道の呪いのテクノロジーをも取り込んだ陰陽道が、平安初期のさまざまな社会不安を背景に勢力を伸ばしていた頃、呪詛のテクノロジーにも変革のヌーベルバーグが押し寄せていました。最澄と空海によって中国からもたらされた「密教」です。「密教の中核にある呪い信仰=調伏法」として、著者は「密教は奈良朝においても、『隠れ陰陽師』たる吉備真備と並ぶ政界の黒幕・僧玄昉らによってもたらされていたが、現在知られるような体系的なものではなかった。とはいえ、『新しさ』=『力』を求める天皇や貴族に大いにもてはやされ、天皇の寵愛を受けた、玄昉や道教が、『孔雀王咒経』『宿曜秘法』などと称される呪法を背景に権力をふるったことはよく知られている」と述べています。
著者は「いまなお生き続ける密教調伏法」として、東密にしろ台密にしろ、歴史上、何度となく時の権力者の強請で怨敵調伏の修法を行ない、布教の妨害をする敵を自ら進んで調伏したりもしてきたことを紹介し、述べます。
「戊辰戦争の際、明治断政府が反抗を続ける東北諸藩を調伏するよう江戸時院に命令したことは、よく知られている。これを受けた密教系の多くの寺院では、慶応4年9月ごろに『東征軍勝利北方降伏護摩祈禱』や『戊辰業障消滅の事』と称する調伏を行なっている。
また、第2次世界大戦のときにも、軍の命令によって日本のほとんどの寺院や大社で『鬼畜米英』に対する調伏が行なわれた事実から考えても、いかに調伏法が日本の社会に根づいていたかがわかる」
民衆の求めに応じてさまざまな祭儀や呪術を行なっていたスペシャリストたちは、陰陽道系と密教系に分けることができます。しかし、密教も陰陽道も神道も混ざり合っており、本質的内容においては、それほど明確な違いがあったとはいえないとして、著者は「あえて差異をみようとすれば、いっぽうには密教が日本古来の山岳他界観と結びつくことで生まれた修験道の宗教者、つまり山伏とか修験者がおり、もういっぽうには下級の民間陰陽師その他の呪術師がいた、といった程度の差異であろう」と述べています。
また、「狐を操る『外法(げほう)』」として、著者は「民間の宗教者たちはしばしば弾圧され、その呪法は邪悪な法、つまり『外法』『外術』などとみなされた。なかでも、もっとも代表的な『外法』のテクノロジーは、狐の霊を操ってさまざまな神秘を行なうというものであった。狐を人に取り憑かせて病気にしたり、死に至らしめる。これは、まさに『呪い』であり『調伏』である」と述べています。
なぜ狐なのでしょうか。日本には古くから狐を神霊視する信仰がありましたが、その鳴き声などから吉凶を占ったりしていたようです。著者は以下のように4つの理由を推測しています。
(1) 中国の狐信仰の影響から、古代にはすでに狐は人に化けたり、憑いたりする能力をもっているという信仰が発生していた。
(2) 中国から伝来した蟲毒の影響である。蟲毒が妖狐信仰と結びつき、他の動物よりも狐が多く用いられるようになった。
(3) 密教の影響。密教の高僧たちは、陰陽師が操る「式神」に相当する使役神(使い魔)として、『護法童子』という鬼神の類いを操っていた。
(4) 密教の神のひとつ「荼吉尼天(だきにてん)」との関係。日本に伝えられた密教における荼吉尼天は、人の死を6ヵ月前に予知し、人が死ぬとやってきて、死体を食べて生きているという恐ろしい夜叉であり、これを祀れば、並みはずれた利益をえることができると信じられていた。
4章「『呪い』を祓う方法」では、「『ケガレ』は『外部』からやってくる」として、人や社会にとって好ましくない方向への状態変化は、外部のものによって作り出され、好ましい方向への変化は、主として自分たちが主催する儀礼によって作り出される、と考えられていたことが紹介されます。呪禁師、陰陽師、密教僧、巫女、神官などといった存在は、そうした浄化儀礼のスペシャリストとして、広い意味での「呪詛祓い」の役割を与えられていたといいます。
著者は、「祭りがみんなを『晴れ晴れ』させる」として、「祭り」の持つ「祓い」のパワーに言及します。著者が調査した物部村では、個人、家、集落、郷村の4つのレベルの「すそ祓い」が定期的あるいは臨時に行なわれていましたが、家レベルの「すそ祓い」では、年の瀬に必ず行なう「煤祓い」、節分の豆まき、数年に1度行なわれる家の神や祖先の祭りである「家祈禱」、そして、疫病が流行したときに疫病が自分の家に侵入するのを防ぐ『祇園天刑星祭』と呼ばれる疫病祭りなどがありました。このいずれもが「すそ」の祓いを含んだ儀礼であり、そこでは「呪詛(すそ)の祭文」が読み上げられたのです。
これは村レベルの「すそ祓い」についても同じことが言えました。年に1度の村の鎮守の祭りや30年に1度のわりで行なわれる鎮守の大祭の目的のひとつも、豊作や氏子が息災であったことを感謝するとともに、そのお祭りの日までに村のなかにたまっている「すそ」を祓うことにありました。
さらに、農作物に被害を与える害虫の発生を鎮める「虫送り」や、疫病が流行したときの「疫病神送り」、「雨乞い」や「日乞い」といった臨時的に行なわれる儀礼も、村の秩序を破壊する「ケガレ」=「すそ」を祓う、広い意味での「すそ祓い」であり、浄化儀礼にほかならなりませんでした。
著者は、「こうした『すそ祓い』の儀礼・祭りは、物部村に限らず、日本全国の村々でさまざまな形態をとって行なわれてきたことであった。いや、現在でも行なわれているといったほうが正確だろう」と述べています。 社会集団の秩序を脅かす邪悪なもの=「ケガレ」が集団の内部に侵入してくるのを防ぐ儀礼、あるいは侵入してきた「けがれ」を排除して集団を清浄化する儀礼のいずれもが「すそ祓い」だったのです。それが終了したとき、社会集団のメンバーたちは「心ゆく」、「晴れ晴れ」とした気分になりました。祭りそのものが「ハレ」の日ということではなく、祭りがうまくいって社会集団がみごとに浄化されることが「ハレ」なのであり、その結果、祭りがハレとされるのです。
続いて、天皇の問題が取り上げられます。著者は「天皇に凝縮される国家の『ケガレ』」として、天皇にとって、国家にとって、「ケガレ」の原因となる代表的なものとしては天変地異、疫病、そして京都の政権を脅かす戦乱をあげることができると述べます。そして、そのいずれもが、天皇、貴族を中心とする国家の支配者たちの目からは、「鬼」の出現、「邪気」や「物の怪」の発生、あるいは「大蛇」(竜神)の怒りなどとして理解されており、その背景には陰陽道や密教などによる世界理解の方法があったと述べています。
著者は、「日本人は、なにを『好ましくないケガレ』としたのか」として、古代では、鬼は形がはっきりしない邪気のたぐいだったと指摘し、述べます。
「これが中世になると、鬼が人びとに目撃され、姿かたちが語られ、絵画に描かれたり、夢のなかにも登場するようになる。鬼たちは、中世の修正会や修二会などの儀礼のなかにも姿かたちをもって登場することになったのだ。 宮廷の追難の儀礼にも、どこでどう間違ったのか、邪気を祓う方相氏が、邪気をあらわすもの、追い払われるものになって登場したりもしていたが、いずれにしても鬼が人によって演じられ、その演じられた鬼を追放することで『ケガレ』が祓われ、『ハレ』がもたらされると考えられるようになったのである」
著者は、「『鬼』の登場―『見えないもの』を『見えるもの』にするトリック」として、「ケガレ」を形象化した鬼人形が作られて捨てられるいっぼうで、さらに過激な形式、誰の目にも「ケガレ」の存在をわからせる形式として、特定な存在の人間に鬼の役割を演じさせるようにもなったことを紹介し、以下のように述べます。
「人形は動かない。しかし、人間が鬼の面や衣裳をつけて儀礼に登場すれば、リアリティも増そうというものだ。紙芝居よりテレビ・アニメのほうが迫力があるにきまっている。その鬼は自由自在に動き回り、なによりありがたいのは退散してくれることである。かくして、中世になると、宮廷や寺院の追離の儀礼に、捨てられる『ケガレ』を象徴する鬼に扮した者が登場するに至ったのである」
要するに、鬼は働く「撫物」であり、「すそ人形」なのでした。この鬼が儀礼の場から消え去ったとき、人びとの身体や社会が「ハレ」となるわけです。
それでは、「ケガレ」を吸い取る鬼を、誰が演じたのでしょうか。人々や社会を「ハレ」の状態にするために、「ケガレ」を一身に引き受ける役割を演じさせられたのは誰なのかという問題について、著者は「誰が『鬼』を演じ、祓い捨てられたのか」として、以下のように述べています。
「中世の京や地方の有力寺院では、鬼役を演じる人びとが定められていたらしい。しかも多くの場合、鬼役は、人びとが目に見える『ケガレ』として忌み嫌う事物を取り扱う人、すなわち死体の埋葬や死んだ牛の処理などに従事する『賤民』の身分にあるような人びとであった。つまり、当時、賤視され、差別された人びとに鬼役を演じさせたのだ。しかし、彼らは鬼役だけを演じさせられたわけではない鬼を追い払い、人びとに福をもたらす福神をも演じていた」
「ケガレ」の問題は王権と深く関わっています。古代の支配者は、自らが社会と自然の双方にかかわる「ケガレ」の予防と能力を持っていました。シャーマン王とか祭司王と呼ばれる存在です。イスラム教が「右手に剣を、左手にコーランを」と言うように、支配者というのは右手に弓矢や刀を、左手には御幣や数珠などを携えていたのです。しかも、弓矢や刀を使うのも、御幣や数珠を携えるのも天皇自身ではなく、その分身たちでした。
「右手に剣を、左手に数珠を」として、著者は述べます。
「呪力の区別のしかたは現代の視点からのものであり、実際には武力集団と呪術集団を明確に区別することはできない。奈良時代の呪禁師は、病気をなおす呪術師であると同時に、弓や剣で攻められても身を守ることができる術を心得た『兵士』でもあった。これは、武士と呪術師が支配者の守護を役割分担するようになった平安時代や中世においてもみられることであった。平安時代、禁中警団の役目にあたる滝口の武士は、武術だけではなく、物の怪をさせる鳴弦の儀にも徒事していたし、同じく御所の警備を任務とする所衆も、他方では宮中の『煤払い』の役についていたのである」
また、「『ケガレ』を祓う『ガス抜き』の儀礼」として、祓いの儀礼、調伏の儀礼は、なにも天皇や武士などの支配者のためだけの儀礼だったわけではないと指摘し、著者は以下のように述べています。
「支配者たちは表面的には自分たちだけの身を守るために祓いをしているかにみえるが、その身を守るためには、彼らが支配している社会全体を清めなければならないのだ。そのために彼らは、自分の祓いだけではなく、社会集団や国家の祓いを執行したのである。生活を守ろうとする庶民、つまり支配者に『ケガレ』祓いの執行を期待する人びと全体の『ケガレ』祓いの儀式でもあった。疫病は支配者だけではなく民衆にも襲いかかったし、戦乱は民衆の生活をも苦しめた。それを鎮め清めることのできる支配者こそが良き支配者であり、それができなくなったとき、人びとは支配者を批判し、交代を望んだ」
だからこそ、大寺院の修正会や修二会、祇園祭りなどが人びとによって支持され発展されてきたとして、著者は述べます。
「と同時に、人びとがこうした社会の『ケガレ』浄化の儀礼に参加することによって、人びとの心や身体のなかにたまっていた、もろもろの『ケガレ』もまた、祓い清められ、『ハレ』の状態となり、社会の支配者にとっては、それこそこの上もない浄化として機能した。儀礼によっていわゆる『ガス抜き』がなされるわけである」
続いて、こうした「ガス抜き」は、儀礼としてのすそ祓いだけだったわけではないとし、著者は「時代が下るにつれて、多様化しながらさまざまな『ガス抜き』システムが作り出された。ばくち、売春、芸能、さらにはスポーツ、旅行―こうしたものは、もともとは神事、儀礼と深くかかわったものであり、ひとことでいえば社会的『すそ祓い』であった。人びとは、自分たちの生活を維持するために、自分たちの力で『すそ祓い』を行なってきたのである」と述べています。
「呪い」とは呪術の問題です。この読書館でも紹介した名著『トーテムとタブー』において、ジークムント・フロイトは、呪術におけるキーワードが「観念」であると指摘しました。そして、「呪術、すなわちアニミズム的思考方法を支配している原理は、『観念の万能』である、ということができよう」と述べています。
さらに「呪術が『観念の万能』であるとすれば、現代社会は『科学の万能』である。しかし、人間の精神やこころといった複雑系は科学ですべてが解決できるというわけではない。その矛盾を埋め合わせるものとして宗教が存在していると考えることもできよう。つまり、どちらも「万能」などではないのである。科学を偏重するあまりに宗教や儀礼を軽視するという風潮は、呪術を崇拝するのと同様に滑稽なことであることを自覚する必要があるだろう」と述べています。
しかし、今や「呪い」は「観念」の問題だけにとどまりません。
本書『呪いと日本人』の単行本が刊行されたのは1995年ですが、この当時はまだネットというものが社会に存在しませんでした。現在では、ネットが最大の「呪い」の装置となっています。2ちゃんねる、ブログ、ツイッタ―などのSNSでつねに「呪い」の言葉が発せられています。
この読書館でも紹介した『呪いの時代』で、哲学者の内田樹氏は、「呪い」がこれほどまでに社会に蔓延したのは、人々が自尊感情を満たされることを過剰に求め始めたからであると分析しています。
そして内田氏は、「呪い」について以下のように述べています。
「僕たちの時代は『呪い』がかつてなく活発に活動しています。『科学的』な人は現代に『呪い』などというものがあるものかとせせら笑うかも知れません。けれども、現に羨望や嫉妬や憎悪はさまざまなメディアにおいて、生身の個人を離れて、言葉として1人歩きを始めています。誰にも効果的に抑制されぬまま、それらの言葉は人を傷つけ、人々がたいせつにしているものに唾を吐きかけ、人々が美しいと信じているものに泥を塗りつけ、叩き壊すことを通じておのれの全能感と自尊感情を満たそうとしています。ネット上の掲示板に繰り返し『死ね』と書かれて、それに耐えきれず自殺する人々が毎年何十人(何百人かも知れません)となくいます。もし、言葉が空を飛んで、現実に人を撃ち殺すことを『呪い』と呼ぶなら、これは間違いなく呪殺です。僕たちはもしかすると平安時代以上に多くの人が呪殺されている時代に生きているのかも知れません」
時々、書店で『呪いの解き方』といったタイトルの本を見かけますが、果たして「呪い」を解くことはできるのでしょうか。内田氏は、次のように述べます。
「呪いを解除する方法は祝福しかありません。自分の弱さや愚かさや邪悪さを含めて、自分を受け容れ、自分を抱きしめ、自分を愛すること。多くの人が誤解していることですが、僕たちの時代にこれほど利己的で攻撃的なふるまいが増えたのは、人々が『自分をあまりに愛している』からではありません。逆です。自分を愛するということがどういうことかを忘れてしまったせいです。僕たちはまず『自分を愛する』というのがどういうことかを思い出すところからもう一度始めるしかないと僕は思います」
「呪い」を解くには「祝い」しかないというのは真実だと思います。もともと、「呪い」も「祝い」も言葉の不思議なパワーとしての「言霊」を使ったマジカルなテクノロジーだと言えるでしょう。毒をもって毒を制するごとく、言霊をもって言霊を消すしか方法はないのです。というわけで、わたしは生業である冠婚葬祭を通して、「祝い」の文化を世の中に広めていきたいと思います。
「天下布礼」とは、「呪い」を解き続ける道でもあるのです。
