- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2018.01.24
『本居宣長 文学と思想の巨人』田中康二著(中公新書)を読みました。大著『古事記伝』で知られる国学者・本居宣長の70年の生涯を辿りつつ、文学と思想の両分野に屹立する学問的偉業の全体像を描き出しています。著者は1965年大阪市生まれで、現在は神戸大学大学院人文学研究科教授(日本近世文学)です。著書に日本古典文学会賞を受賞した『村田春海の研究』(汲古書院)などがあります。
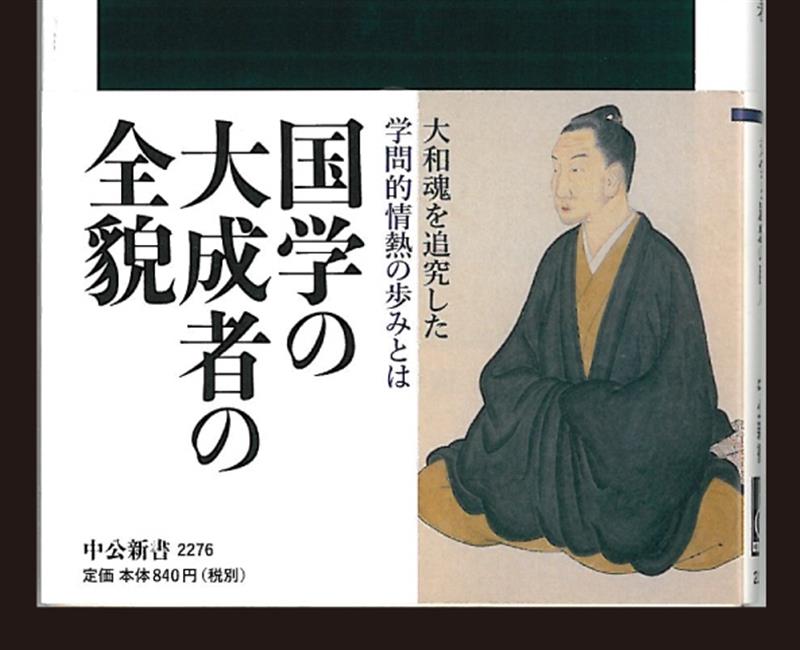 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「本居宣長六十一歳自画自賛像」(本居宣長記念館蔵)が使われ、「大和魂を追究した学問的情熱の歩みとは」「国学の大成者の全貌」と書かれています。
 本書の帯の裏
本書の帯の裏
また帯の裏、およびカバー前そでには、以下の内容紹介があります。
「漢意を排斥して大和魂を追究し、『物のあはれを知る』説を唱えたことで知られる、江戸中期の国学者・本居宣長。伊勢松坂に生まれ、京都で医学を修めた後、賀茂真淵と運命的な出会いを果たす。以来、学問研究に身を捧げ、三十有余年の歳月を費やし『古事記伝』を著した。この国学の大成者とは何者だったのか。七十年におよぶ生涯を丹念にたどりつつ、文学と思想の両分野に屹立する宣長学の全体像を描き出す」
本書の「目次」は以下のような構成になっています。
「はじめに」
第一章 国学の脚本
一、宣長の古道学
二、宣長の歌学
第二章 学問の出発
一、契沖学との出会いと古典研究
二、二条派地下歌人への入門と詠歌
第三章 人生の転機
一、賀茂真淵と松坂の一夜
二、「物のあはれを知る」説の提唱
三、処女出版と真淵の手紙
第四章 自省の歳月
一、宣長の自意識と「日本」
二、自分探しの旅
第五章 論争の季節
一、『葛花』論争
二、『鉗狂人』論争
三、『呵刈葭』論争
第六章 学問の完成
一、版本というメディア
二、古道学書の出版
三、歌書の出版
第七章 鈴屋の行方
一、宣長の死に支度
二、春庭の業績――宣長没後の鈴屋(一)
三、大平の業績――宣長没後の鈴屋(二)
「おわりに」
「参考文献」
「はじめに」で、著者はいきなり重要なことを述べます。
儒教の開祖である孔子と本居宣長の共通点について、以下のように言及しているのです。
「享年がほぼ同じ宣長と孔子には共通点も少なくない。多くの優秀な門弟を育てたことや、ほとんど仕官せずに在野で研究・啓蒙活動にいそしんだことなどである。しかし、共通点があるからといって、宣長を孔子に見立てることが許されるのか」
続けて、著者は宣長と孔子について以下のように述べます。
「周知のように宣長は儒教や仏教を目の敵にし、日本古来の『真心』を乱す悪の根源として排斥した。そのような儒教の始祖とされる人物と比較するのは、はなはだ迷惑ではないかと考える向きもあるかもしれない。しかしながら、興味深いことに儒教を毛嫌いした宣長は、孔子に対しては特別な敬意を払っていたのである」
それは、宣長が次のような歌を詠んでいることからもわかります。
釈迦孔子も神にしあればその道も広けき神の道の枝道
聖人と人はいへども聖人のたぐひならめや孔子はよき人
さらに、著者は以下のようにも述べています。
「宣長は儒仏を徹底的に批判したけれども、釈迦や孔子に対しては尊ぶ思いを持っていたのである。なお、鈴木朖が『先生の風は頗る仲尼に似たり』と言ったことに対して、宣長は喜んだという逸話も伝わっている。そういった意味で、宣長の生涯を孔子の人生になぞらえて考えるのは、あながち見当はずれとはえいないのである」
わたしも、宣長は孔子を大いにリスペクトしていたと思います。 『本居宣長』で紹介した小林秀雄の名著では、宣長の大きな謎として、その「遺言書」が取り上げられています。葬儀や墓の詳細にまで言及した遺言書ですが、これはもう明らかな儒教思想以外の何物でもありません。わたしは、宣長は学問としての「儒学」は否定しても、宗教としての「儒教」は肯定していていたのではないかと思います。宣長の「遺言書」は、まさに儒教思想のエッセンスです。儒教の核心は「礼」の思想にありますが、それは葬礼として最高の形で表現されます。日本に儒教が伝来し、それによって律令制度が作られました。しかし、それは、あくまでも「礼」抜きのものでした。宣長は、腹周りの贅肉のようにまとわりつき臍である「礼」を隠している儒学的な理論には反発しましたが、「礼」そのものには深い共感を覚えたのではないでしょうか。
宣長は気軽に古歌を取り上げたところ、そこに出てくる「やまと心」が儒学者たちを刺激し、彼もまたそれを受けて「漢ごころ」批判を展開したため、儒学批判の象徴的存在とされましたが、その根本の根本において儒教をリスぺクトしていたように思えてなりません。日本史上において「儒学」の最大の批判者であった本居宣長は、「儒教」の最高の理解者にして実践者でもあったと、わたしは考えます。葬儀について詳細に指示しつつ、最後は先祖や父母への孝行を指示した宣長の「遺言書」こそは、死の直前にその根本においての儒教肯定をカミングアウトするという、「ダ・ヴィンチ・コード」ならぬ「宣長コード」であったと、わたしは思います。
周知のように、宣長は「大和魂」の大切さを訴えました。
「大和魂」とは、古代日本人の持つ美徳であり、まっすぐで清らかな心を意味します。そして、彼は「大和魂」の対立概念として「漢意(からごころ)」を想定しました。両者の関係について、著者は以下のように述べています。
「宣長は『漢意』と『大和魂』の関係について、戦場に立つ時に武装するという例をもって説明する。すなわち、『大和魂』という鎧がなければ、『漢意』という敵の手に落ちてしまうというわけである」
もともと「大和魂」の対概念は「漢才(からざえ)」でした。それを宣長は「漢意」に読み替えたのです。著者によれば、この読み替えは宣長国学の根幹をなす屋台骨の入替を意味し、宣長国学に「漢意」排斥という明確な方針を与えたといいます。
天皇について、宣長はどのように考えていたのでしょうか。『古事記伝』巻一の「直毘霊」において、宣長は「天皇尊(すめらみこと)の大御心を心とせずして、己々がさかしらごゝろを心とするは、漢意の移れるなり」と述べています。この宣長の発言から、著者は以下のようにまとめています。
「宣長は記紀、とりわけ古事記を聖典として依拠しながら、天照大御神を中核とする古道論を構想し、日本古来の『大和魂』(大和心・真心)の追求と儒仏渡来以後に蔓延する『漢意』の排斥を理念として、古道学を構築した」
第三章「人生の転機」の一「賀茂真淵と松坂の一夜」の冒頭では、ともに国学の巨人である真淵と宣長の運命の出会いについて、以下のように感動的に書かれています。
「人と人との出会いは偶然ともいえるが、偶然では済まされない強い絆が見える場合もある。一般に科学では説明がつかない偶然の一致のことをユング心理学で『共時性』(シンクロニシティー)という。この『共時性』を東洋思想によって解明しようとした心理学者ジーン・シノダ・ボーレンは、インドに伝わるある諺にたどり着いた。それは次のようなものだ。弟子に心の準備が整ったとき、師は自然に現れる。奇妙な暗合はいつの世にもある。心理学と東洋思想との出会いも不思議な縁というほかはない。
宣長と賀茂真淵との出会いもまた、単なる偶然と考えることはできない。宣長と真淵との出会いを『松坂の一夜』という」
宣長といえば、「もののあはれ」という言葉が有名です。
師である真淵から受け継いだ『源氏物語』の研究から、宣長は「もののあはれ」を文学の本意として提唱しました。儒教には勧善懲悪説というものがあり、仏教には因果応報説というものがありましたが、宣長はこれらを否定し、「もののあはれ」を打ち出したのです。著者は以下のように述べます。
「物語は儒教や仏教による戒めのためにあるという考え方は、当時においては前提や常識であって、これを疑う者はいなかった。それゆえ宣長がそれらを真っ向から批判したのは画期的なことであったといえる」
もちろん、孔子や釈迦をリスペクトしていた宣長は、儒仏の戒めそのものを否定しているわけではありません。それは生きていく上で必要なものであると認め、それを花と薪の比喩によって説明しています。著者は述べます。
「物語を教戒として読むのは、花をめでるために植えてあった桜を生活のために切って薪にするようなものである、というのである。たしかに薪は日常生活の上で必要ではあるが、よりによって桜でなくてもよいだろう。薪にする木はほかにいくらでもある。それに対して、桜は花をめでるのにもっとも適した花だからである。この卓抜な比喩によって明らかなように、物語は『物のあはれを知る』ために書かれたものだというのである。物語を桜に喩えたのは宣長による最高の褒め言葉である。終生桜を愛したように、宣長は源氏物語を溺愛した。儒仏の教戒説によって、源氏を薪にしてはいけない。『物のあはれを知る』説は、儒仏の教戒説を排斥することとセットで考え出された仮説だった」
父が國學院大學の文学部の出身であり、実家には契沖、賀茂真淵、本居宣長、平田篤胤らの個人全集が揃っていたため、わたしは早くから国学に親しんできました。その後、柳田國男や折口信夫らの日本民俗学にも深い関心を抱きましたが、国学から日本民俗学へと流れているのは「日本人とはなにか」という問題意識です。わたしは日本人の「こころ」の本質を求めたいと考えているのですが、その際に最重要キーワードとなるのが「大和魂」や「もののあはれ」といった宣長が提唱した言葉です。本書を読んで、いっそう、それらの言葉への関心が強くなりました。
