- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2018.06.21
『本を読む人だけが手にするもの』藤原和博著(日本実業出版社)を読みました。著者は教育改革実践家で、杉並区立和田中学校・元校長です。元リクルート社フェローでもあります。1955年東京生まれ。78年東京大学経済学部卒業後、株式会社リクルート入社。東京営業統括部長、新規事業担当部長などを歴任。メディアファクトリーの創業も手がけました。93年よりヨーロッパ駐在、96年同社フェロー。2003年より5年間、都内では義務教育初の民間校長として杉並区立和田中学校の校長を務めました。08年~11年、橋下大阪府知事ならびに府教委の教育政策特別顧問。14年から佐賀県武雄市特別顧問。著書多数。
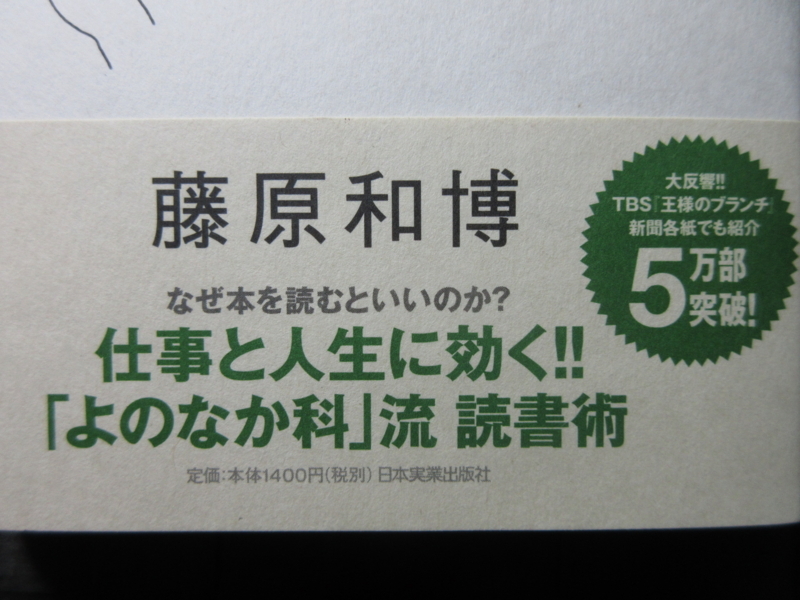 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「なぜ本を読むといいのか?」「仕事と人生に効く!!『よのなか科』流 読書術」「大反響!! TBS『王様のブランチ』新聞各紙でも紹介 5万部突破!」と書かれています。
アマゾンの「内容紹介」には、「累計100万部突破!! 仕事と人生に効く『よのなか科』特別授業 ― 読書の効能」として、「あなたは『なんで、本を読んだほうがいいのか?』という質問に答えられますか? 親や先生は『本を読みなさい』と言いますが、その素朴な疑問にきちんと答えられる人は少ないのではないでしょうか。本書は、『人生における読書の効能』について、リクルート社で初のフェローや東京都の義務教育で初の民間校長を務め、『よのなか科』という現実社会と教育をリンクさせた大人気の授業やベストセラーで知られる藤原和博氏がひも解いていきます」と書かれています。
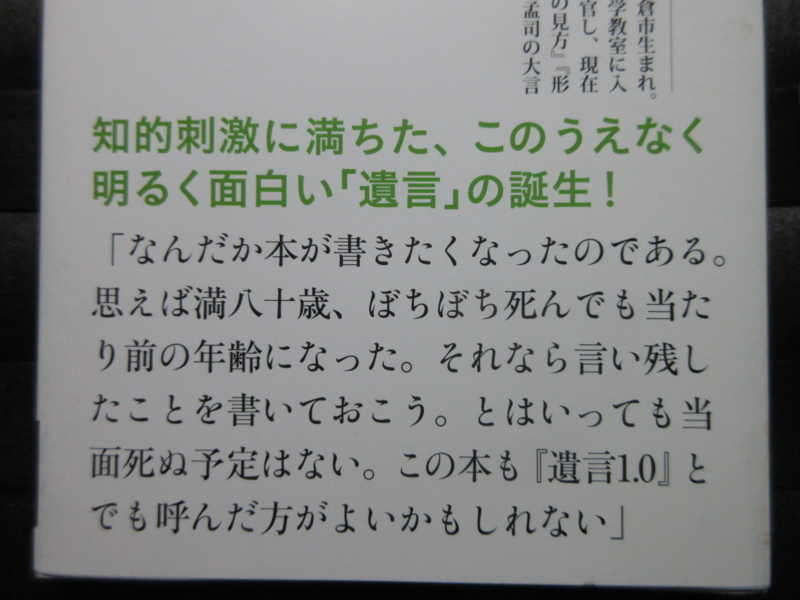 本書の帯の裏
本書の帯の裏
本書の「目次」は、以下のような構成になっています。
「はじめに」
序章 成熟社会では本を読まない人は生き残れない
第1章 本を読むと、何が得か?
第2章 読書とは「他人の脳のかけら」を自分の脳につなげること
第3章 読書は私の人生にこんな風に役立った
第4章 正解のない時代を切り拓く読書
第5章 本嫌いの人でも読書習慣が身につく方法
付録 藤原和博の「これだけは読んでほしい」と思う本・50冊
「ビジネスパーソンが読んでほしい11冊」
「学校では教わらない現代詩を学ぶ10冊」
「小中学生から高校生の子を持つ親に読んでほしい15冊」
「子どもといっしょに読みたい11冊」
序章「成熟社会では本を読まない人は生き残れない」では、「『趣味としての読書』から『人生を切り拓くための読書』へ」として、著者は、成熟社会では「それぞれ1人」が自分自身で、世の中の流れと自らの人生とを鑑みながら、自分だけの幸福論を決めていかなければならないと訴えます。
国家や企業にもう幸福論を保証する能力はなく、「それぞれ1人1人が自分自身の幸福論を編集し、自分オリジナルの幸福論を持たなければならない時代に突入したのである」というのです。そして、「それぞれ1人1人」の幸福をつかむための軸となる教養は、自分で獲得しなければならず、著者は「そのためには読書が欠かせないというところに行き着くのだ」と述べます。
「どうやって『それぞれ1人1人』の幸福論を築くか」として、著者は以下のように述べています。
「じつはヨーロッパを中心に成熟社会を迎えた先輩諸国がやったのは、国家として宗教を発動し、バラバラになっていく個人を再び紡ぐことだった。日本のように企業がその役割を担うのではなく、宗教界が教会というネットワークで紡いでいったのだ。ややこしいのは、日本は太平洋戦争の影響で、このように、国家が宗教を発動できなくなったことだ」
続けて、著者は以下のように述べています。
「宗教の未整備によって、とくに若い人たちが浮遊している。では、宗教の代わりに彼らをつなぎとめているものは何か。それが日本の若者が異常にのめり込んでいる携帯メールである。突出してメール文化が盛んになったのは、宗教の代替機能として、つながったような気になるという側面が大きかったと私は見ている」
本書が刊行されたのは2015年10月ですが、現在ならば携帯メールよりもSNSが宗教の代替機能を持つといえるでしょう。
著者は、これから先の日本では、身分や権力やお金による”階級社会”ではなく、「本を読む習慣のある人」と「本を読む習慣のない人」に二分される”階層社会”がやってくるだろうと予見します。
著者は、読書を通じて知識のインプットを蓄積していかないと、自分の意見というものが出てこないという事実を指摘し、ジャーナリストの立花隆氏の「ネットだけだと、どうしても掘り方が浅くなる。もうちょっと深い情報を得たいと思ったら、本なりその他もろもろの手段がありますから、それを通してより深い情報を得ることが必要なステージに必ずいくんですね」という発言を紹介します。そして、「私もネットだけの情報では底の浅い思考しかできないという意見に賛成だ。深く論理的な思考をするうえで、本は絶対に欠かせないものだと思う」と述べています。
第1章「本を読むと、何が得か?」では、「本を読むか読まないかで、報酬の優劣は決まってくる」として、著者は以下のように述べています。
「人間はすべてのことを体験することはできない。たとえば、櫻井よしこさんが講演で日本の領土問題を話すとき、尖閣諸島や竹島や北方領土など話題にする場所をすべて訪問し、すべてを体験して語ることなどできはしない。だとすると、資料を読み込んだり、信頼できる書き手の著書を読んだり、信頼できるネットワークからの情報を得て、それに自らの体験を乗せて語っているはずだ。ということは、1時間あたりに生み出す付加価値の総量を上げるためには、本を読むことが欠かせないといえるのではないだろうか」
また、「読書によって、『想像する力』が磨かれる」として、著者は以下のように述べています。
「現代は映像時代であり、テレビでもデジカメでもスマホでも、解像度の高さが機能の中心となっている。鑑賞に値する写真や動画の画質、あるいは映画を楽しむ際の3Dのクオリティなどは、当然、解像度が高いほうがいいに決まっている。
しかし、人間の脳の働きの側から見ると、話しは変わってくる。解像度が高いものを見れば見るほど人間のイマジネーションのレベルが下がってしまうからだ。すべてが詳細に見えてしまえば、あいまいな部分を想像する必要はない。テレビやスマホで動画を見る機会が増えれば増えるほど、その傾向に拍車がかかる」
第2章「読書とは『他人の脳のかけら』を自分の脳につなげること」では、「1冊の本にはどれほどの価値があるのか」として、村上龍氏の『半島を出よ』という小説を例にあげ、この作品を書くために村上氏が10年の思索を要し、205冊もの参考文献、さらには大量のインタビュー取材を必要としたことが指摘されます。読者が『半島を出よ』を読むことは、村上氏がそれにかけた人生を読むことにもつながるのだとして、著者は以下のように述べます。
「作品は作家の『脳のかけら』である。その脳のかけらを、読者は本を読むことで自分の脳につなげることができるのだ。『脳のかけら』という表現に違和感があれば、『アプリ』と言い換えてもいいし、ワンセットの『回路』であると呼んでもいい。この作品の場合には、村上龍さんの脳を通じて編集された『日本の脆さ』が、読者の世界観を広げてくれる」
第3章「読書は私の人生にこんな風に役立った」では、「読書が生活の一部になって現れた『人生の鳥瞰図』」として、本を読むことが生活の一部となるようになって、著者のなかである変化が起きたことが報告されます。それは「人生の鳥瞰図」が見えるようになったことでした。著者は述べます。
「もちろん、鳥瞰図を獲得しようと思って本を読んだわけではない。結果的に、読書を重ねて他人の脳のかけらをつないでいくうちに、鳥瞰図が現れたと言ったほうが近い。人間には、みんな、どこかに欠落している部分がある。しかし、多くの人は、その欠落している部分がいったい何であるのか、わかっていない。実社会でなんとなく生きているだけでは、なかなか気づくことはできないのだ」
では、どうしたら、その欠落している部分に気づくことができるのでしょうか。著者は「おそらく、そのヒントは本のなかにある」として、「読書によって、さまざまな人物の視点を獲得していける。つまり、巨大なロールプレイをすることができる、そうしたシミュレーションを繰り返すことで、人生を鳥瞰図として見られるようになるのだと思う」と述べています。
第4章「正解のない時代を切り拓く読書」では、「『コミュニケーションする力』を磨く読書」として、著者はいかのように述べています。
「『人の話をよく聴く』という技術は、読書をすることによっても高めることができる。どのようなジャンルの本にも素直に向き合ってみること。先入観を排した『乱読』が大切だ。さらにコミュニケーションする相手との『雑談』に必要な多様な分野の基礎的な知識も、読書によって増やしていくことができる」
著者は、「意識が高まると、『引き寄せる力』も強くなる」として、以下のようにも述べています。
「人間が蓄積した知識、技術、経験のすべては、脳内のある部分に沈殿している。脳内である意識が強まると、それらがかき混ぜられて浮き上がってくる。浮き上がってきたときに、一瞬にしてそれらはつながり回路を形成する。それを、人間は想いや考えとして抱くようになる。逆にいえば、知識、技術、経験が点のまま浮き上がってこないと、想いや考えは生まれない。
脳内のつながりが回路になり、想いや考えとして結晶し始めると、それが発信機となってある種の電磁波のようなものを発するのではないだろうか。私は、その電磁波に共鳴するものが引き寄せられてくると本気で信じている。何より、人間自体も粒子の集合体だ。原子レベルでは電子が飛び交っている存在なのだから、そういうことがあっても不思議ではない」
また、「『プレゼンテーションする力』を磨く読書」として、著者は以下のように述べています。
「プレゼンテーションする力は相手の脳に自分の脳のかけらを『つなげる』こと、ともいえる。自分の思いや考えをできるだけ率直に、わかりやすく、正確に伝える技術が必要になる。その際に大切なのは、まず『他者』をイメージすること。次に、その他者は自分とは違う世界観で生きているのを理解すること。だから、プレゼンは、相手へのアタマのなかに、自分のとは別の映写室があるつもりで、相手が理解できるイメージを映し出してあげなければいけない」
「本は、孤独に耐えながら読むモバイル端末」というコラムでは、著者は、書籍が「モバイル端末」とも呼べる現在のような形になったのは500年以上前のことであると指摘し、以下のように書いています。
「人間の頭部には前面に目があって、両手は前方に自在に動かすことができる。そうした人間の構造から、片手で持ったまま、片手でページが繰れる現在のような形がベストだということになったのだろう。言語の違いから、縦書きと横書き、右開きと左開きなどの違いはあるものの、最も合理的だと思われる形は、世界中でいまでも変わっていない」
これは、非常に優れた書籍論であると思いました。
第5章「本嫌いの人でも読書習慣が身につく方法」では、「習慣化されるまでは、ある種の『強制』も必要」として、著者は以下のように述べています。
「教育とは伝染、感染なのだ。本好きの人は、じつに豊かな表情をして本を読む。静かに読んでいても、その波動は確実に周囲に放たれる。それが子どもたちに伝われば、少なからず影響を受けるはずだ。そこから、本好きな子どもが育つかもしれない。よく研究者や作家の子どもが本好きになりやすいというが、それは家に本がたくさんあるからではない。小さいころから、親が本を読む姿を見ているからだ。子どもにとって最高の教材は、いつも、大人の学ぶ姿なのである」
わたしも本好きになったのは両親の影響です。父も母も大の読書家で、いつも本を読んでいました。その姿を見ながら育ったわたしは「本って、なんて面白そうなんだろう!」と思ったのです。一方、北朝鮮の将軍様はこれまでに1冊も本を読了したことがないと聞いたことがあります。彼の先代もそうだったそうですが、子どもが1冊の本を読みとおすのは、ある種の「強制」が必要です。それがまさに教育なわけですが、かの国では帝王学どころか一般的な教育さえも与えなかったようですね。結果、「我慢」とも「教養」とも無縁なリーダーを生んでしまったわけで、本当に恐ろしいことだと思います。
最後の付録「藤原和博の『これだけは読んでほしい』と思う本・50冊」では、じつにさまざまな本が紹介されています。わたしが読んでいない本もたくさんありますが、「小中学生から高校生の子を持つ親に読んでほしい15冊」の中に、『死体とご遺体』熊田紺也著(平凡社新書)があったのには驚きました。「夫婦湯灌師と4000体の出会い」というサブタイトルがついた本ですが、著者はなんとこの本を「ベンチャービジネス」のテキストとして紹介しているのです。いやはや、本というのは多様な読み方ができるものですね。
