- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2018.06.26
『正しい本の読み方』橋爪大三郎著(講談社現代新書)を読みました。この読書館でも、著者の『ふしぎなキリスト教』、『世界は宗教で動いている』、『ゆかいな仏教』を紹介しましたが、その著者が読書法について書いた本です。



著者は1948年生まれの社会学者です。東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。東京工業大学名誉教授。著書に『はじめての構造主義』『はじめての言語ゲーム』(ともに講談社現代新書)、『ほんとうの法華経』(ちくま新書)、『戦争の社会学』(光文社新書)、『丸山眞男の憂鬱』(講談社選書メチエ)などがあります。
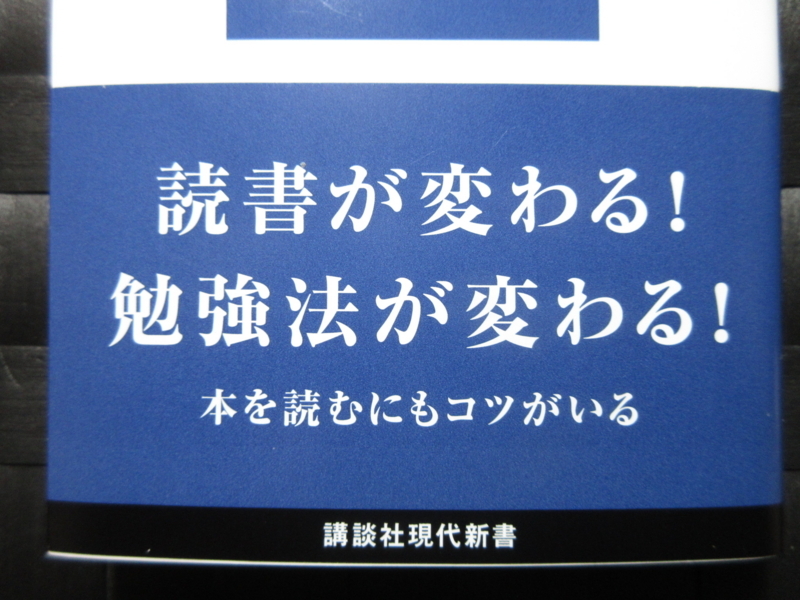 本書の帯
本書の帯
本書の帯には「読書が変わる! 勉強法が変わる! 本を読むにもコツがいる」と書かれ、帯の裏には以下のように書かれています。
●本には「構造」「意図」「背景」の3つがある
●本の内容は覚えようとしなくていい
●「ネットワークの節目」となる本をおさえる
〈特別付録〉必ず読むべき「大著者100人」リスト
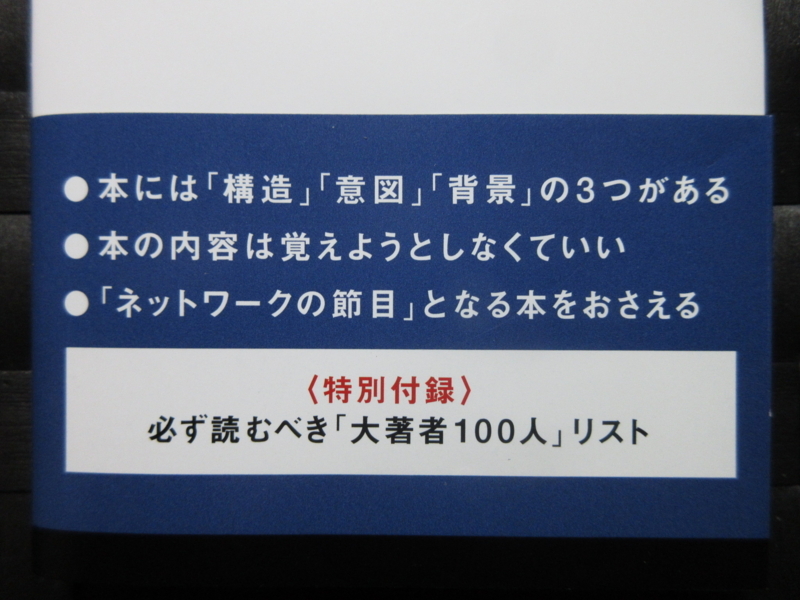 本書の帯の裏
本書の帯の裏
アマゾンの「内容紹介」には、〈本を愛してやまない読書好きの皆さんへ〉として、以下のように書かれています。
「ちまたには相変わらず、本が溢れています。しかし、そもそも、どんな本から読めば自分のためになるのか。本を読んでも次から次へと内容を忘れてしまうが、どうすれば覚えられるのか。本は何の役に立つのか・・・。こういったことに悩んだことはありませんか?
ネットの発達によって、情報が万人に平等に与えられる現代だからこそ、人々は「正しい本の読み方」があることを忘れているのではないでしょうか。たとえば、本を読むうえで『構造』『意図』『背景』の3つをおさえなくてはならないことを、あなたはご存知ですか?
この本は、本を読むための本、本を愛する人のための本です。これを読めば、どんな本を選りすぐれば、あなたの血肉になるのか、がわかります。この本を読めば、本が自由に生きていくための保障になる、とわかります。大ヒット作やネット評価の高い本ばかりを読んでいるだけでは、得られることは少ないかもしれません。本を選ぶにも、読むにも、コツがいるのです。そのコツを橋爪先生に学びましょう。
特別付録として、橋爪先生が選び抜いた、『必ず読むべき「大著者100人」リスト』もつけました。 まずはこのリストに挙げられた大著者(小説家・哲学者・・・)から、読み始めてみませんか?」
本書の「目次」は、以下のような構成になっています。
「はじめに」
〈基礎篇〉
第一章 なぜ本を読むのか
第二章 どんな本を選べばよいのか
第三章 どのように本を読めばよいのか
〈応用篇〉
第四章 本から何を学べばよいのか
【特別付録】必ず読むべき「大著者100人」リスト
第五章 どのように覚えればよいのか
第六章 本はなんの役に立つか
〈実践篇〉
第七章 どのようにものごとを考えればよいのか
終章 情報が溢れる現代で、学ぶとはどういうことか
「はじめに」で、著者は「他人に関心を持つ」として、こう述べています。
「本は、字で書いてあります。字は、言葉を写し取ったものです。写し取る前の言葉は、声です。声は消えてしまいますが、字は残ります。繰り返して読めます。覚えなくても、字に書いてあれば、『ああ、そうか』とわかります。いまの言葉で言えば、外部記憶です。本を書いた人が死んでも、本は残る。考えてみれば、これはすごいことです。だから、本は、ものを考えた昔の人の、死体です。本を書いたのは、必ずだれか他人です。だから、本を読むとは、他人に関心を持つ、ということなんです」
また、「前例のない出来事を考える」として、著者は以下のように述べます。
「教養こそは、組織のトップのような、意思決定をする立場になるとよくわかりますが、前例のない出来事が起こったときに、ものごとを決めるのに唯一、参考になるものです。なぜか、前例がないようにみえても、多少に他ようなことなら、外国にあったり、過去にあったり、フィクションの中にあったりするからです」
さらに著者は、教養について「人びとがよりよく生きることを支援するもの」だと述べています。
第三章「どのように本を読めばいいのか」では、著者は「すなおに読む」として、「すなおに読む。ともかく、素直に読む。読み方の、基本です」と述べ、以下のように続けます。
「素直とは、どういうことか。著者は、読み手である私のことを、知りません。著者はこの、私のために書いているわけじゃない。著者は、言いたいことがあって、それをうまく言おうと、言葉を選んで書いているだけ。その著者が、何を言いたいのか、読み取る。注意ぶかく読み取る。丁寧に読み取る。謙虚に読み取る。しっかり読み取る」
第四章「本から何を学べばよいのか」では、「あるまじき行数調整」として、著者は新聞社や雑誌社に寄稿した文章のゲラが戻ってきたときに「どうもおかしい」と感じることがあると告白します。担当者に聞いてみると、行数調整とやらで、「段落を追い込みにしました」「改行を入れておきました」などと言います。しかし、著者は怒りをにじませて以下のように述べるのでした。
「あのね、段落は、文章の本質なの。行数を調整するのなら、文を削るとか、書き足すとか、いろいろ方法がある。『段落を追い込みにする』とか『改行を入れる』とか、なんのつもりですか。最初から字数×行数を教えてくれれば、ぴったりに合わせて納品するのに。それで、原稿をひきとり、もう一度私の手で調整したうえで、送り返すのです」
続けて、著者は以下のように述べています。
「大手の新聞社や雑誌社の記者たちのなかには、署名原稿なのに、勝手に手を入れるクセがあるのがいる。たぶん彼らは、寄稿者をしろうとだと見くびって、原稿を『改良』しているつもりなのだろう。ひどい原稿も多いだろうし、締め切りは迫っている。だからそういうクセができた。それでも、段落に手を加えるのは、NG。いちばんやってはいけない」
著者の怒りはもっともです。わたしは基本的に最初から字数×行数を教えてもらって、ぴったりに合わせて納品したいと思っています。几帳面な性格なのか、1字余りなどというのが生理的に許せません。京極夏彦氏とまではいきませんが、与えられたページは余白なしで、活字で埋め尽くしたいタイプなのです。
さて、著者は「伝記を読む」として、以下のように述べています。
「レヴィ=ストロースのように、本人の体験や、どういう人生を送ってきたかというところにも背景はある。本を読む前に、その著者の、伝記があれば伝記や、そのほかのインタヴューや紹介記事を読むみたいなところから入っていくというのも、ひとつの方法ではないかと思う。
河出書房新社の『世界の大思想』や、中央公論社の『世界の名著』、講談社の『人類の知的遺産』みたいなシリーズは、おおむねそうしたコンセプトでできている。主要著作のほかに、解題とか解説とか、生い立ちとか、関連の情報が載っている。とかかりに、そういう本を読むべきです」
さらに著者は「大著者」というコンセプトを提示し、以下のように述べます。
「マルクスとかレヴィ=ストロースとか、時代を突き進み、突き抜けるような、大著者というのがいるんです。大著者は、何人ぐらいいるかっていうと、100人ぐらいかもしれない。もっと小粒な著者を入れると、1000人以上かな。でも、ほんとの大著者は、そんなにいるはずがない。まあ、100人ぐらいと考えておけばいい。残りの著者は、大著者の派生形なの。だから大著者を知っていれば、あっと言う間に読めてしまう。
本書には「大著者100人」とその代表的著作の一覧表があります。『リグ・ヴェーダ』や『アヴェスター』、ブッダの『真理のことば』、『聖書』、『論語』、ホメロスの『イリアス』『オデュッセイア』、プラトンの『ソクラテスの弁明』、『クルアーン』、『源氏物語』や『枕草子』や『徒然草』、シェークスピアの『ハムレット』、スタンダールの『赤と黒』、トルストイの『アンナ・カレーニナ』、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』、森鴎外の『阿部一族』、夏目漱石の『こころ』、メルヴィルの『白鯨』、プルーストの『失われた時を求めて』、カフカの『変身』、ヘミングウエイの『老人と海』、デカルトの『方法序説』、ホッブズの『リヴァイアサン』、スピノザの『エチカ』、ルソーの『社会契約論』、アダム・スミスの『諸国民の富』、カントの『純粋理性批判』、ヘーゲルの『精神現象学』、ニーチェの『ツァラトウストラはかく語りき』、ジェームズの『プラグマティズム』、フロイトの『精神分析学入門』、レーニンの『国家と革命』、マルクスの『資本論』、毛沢東の『矛盾論』、フーコーの『言葉と物』といった人類史を代表する名著が100冊挙げられています。 リストの詳細は、ぜひ本書を購入して、ご確認下さい。
第六章「本はなんの役に立つか」では、文学の効用などが紹介されます。「文学は、言葉を使ったトリックなのです。著者が考えた、架空の実社会」という著者は、「実社会を超える」として、以下のように述べます。
「物語はもともと、実生活をはみ出て、想像力をはばたかせるものだった。小説は、そのかたちを借りつつ、この社会を生きる人びとと重なる世界を描く。そして、人びとの内面に入り込む。近代になって、そうした文学が発展しました。人間の精神世界が独りに閉じこもらないで、ほかの人びとと共存する中で豊かなに育てられる、という意味です」
著者によれば、これは実生活に役立つ疑似体験でもあるし、実生活では得られない真実の体験でもあります。そういう二重性があるというのです。
さらに、「哲学・思想は何の役に立つ?」として、著者は述べています。
「哲学は、人間が未知の課題に直面した場合、最後に頼る拠りどころです。未知の課題とは、どういう意味か。法律や、経済や、自然科学や、どこかの専門にすっぽりあてはまる問題なら、その専門で議論すればすむ。けれども、そうはいかない問題もあります。いくつもの専門にまたがる、多面的な問題。これまでの議論の積み重ねがなくて、考え方の筋道がわからない問題。そうしたときには、議論の、基本的な前提にさかのぼる必要があります。それは、過去の哲学者の議論のなかに、みつかる。すべての人間が拠ってたつ、根拠や前提をつきとめるのが、哲学者の役目だからです」
終章「情報が溢れる現代で、学ぶとはどういうことか」では、著者は、コンピュータのネットワークは便利で、いろいろなことができるけれども、3つほどまずい点があるとして、(1)中心がない、(2)データでできている、(3)現在に縛られている、と指摘します。
(1)については、中心がないということは、明確な発信者がいないということです。責任がないということです、誰かがメッセージを送っているのではないから、そこからは何も伝わってきません。(2)については、データとは、つまり情報です。メッセージではないわけですから、責任がありません。(3)については、ネットの情報は、いま電源が入っているコンピュータをつないだだけのものです。将来のコンピュータとは、つながるすべがありません。ネットの中に、未来はないのです。
一方、ネットと違って、本とは公共のものです。
著者は「頭を公共のために使う」として、以下のように述べます。
「本が『公共』のものなのは、なぜか。それは本が、言葉で書かれているからです。言葉ははじめ、誰かの頭のなかみ(プライベートなもの)なのですが、それが文字に書かれ、本として発表されると、誰でも読むことができます。ここは賛成、ここは反対、と議論したり、感想をのべたり、話題にしたりできます。著者の知り合いでなくても、友だちでなくても、誰でもアクセスできる。それが、『公共』ということです」
「おわりに」の冒頭で、著者は「本の時代は、終わるのだろうか。スマホやタブレットが行き渡り、電子書籍も増えている。本書も、紙の本とKindle版の両方で、発売になっている」と述べた上で、紙の本の「よくないところ」を列記します。それは、「場所をとる」「値段が高い」「古本が売れない」「おしゃれでない」「検索ができない」といったネガティブな要素の数々でした。
しかし、「それでも、本は本である」として、著者は以下のように述べます。
「書き手がいて、読み手がいる。書き手が、アイデア(言いたいこと)を字に書いて、不特定の読み手に伝える。媒体が紙でも、電子書籍でも、このことは変わらない。字がある限り、字を書き、読むひとがいる限り。
本の書き手は、みんな、過去の書き手に触発されてきた。書き手→書き手→書き手→・・・・・・の連鎖がある。本の、歴史と伝統である。本の歴史と伝統こそ、人類の文化(の主要な部分)だと言ってよい。電子媒体に乗りそこねて、読まれなくなる本も多いだろう。けれども、大事な本(クラシックス)は、それでも読まれ続ける」
本書は、本を愛し、本とともに生き続けてきた著者による、紙の本へのラブレターであり、応援のエールのように思えました。
