- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2018.10.08
『〈死者/生者〉論――傾聴・鎮魂・翻訳――』鈴木岩弓・磯前 順一・佐藤 弘夫編(ぺりかん社)を読みました。編者の1人である東北大学総長特命教授で宗教民俗学者の鈴木岩弓氏から献本された本です。震災を契機に立ち現われた死生学の最前線を知ることができる興味深い一冊です。
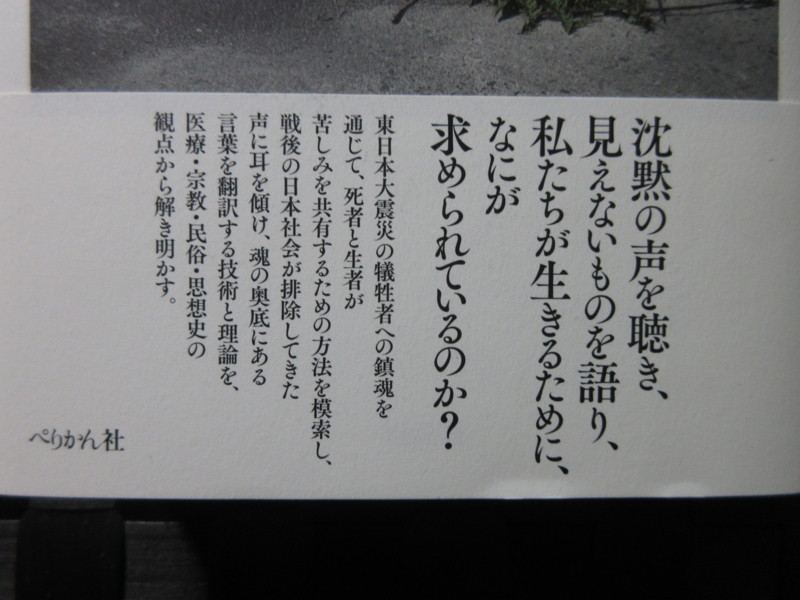
本書の帯には「沈黙の声を聴き、見えないものを語り、私たちが生きるために、なにが求められているのか?」「東日本大震災の犠牲者への鎮魂を通じて、死者と生者が苦しみを共有するための方法を模索し、戦後の日本社会が排除してきた声に耳を傾け、魂の奥底にある言葉を翻訳する技術と理論を、医療・宗教・民俗・思想史の観点から解き明かす」と書かれています。

アマゾンの「内容紹介」には、以下のように書かれています。
「宗教学や民俗学の領域においてすらタブー視されてきた『死』は1980年代以降『脳死問題』を契機に社会の表層へ浮上した。葬儀や墓制のあり方にも変化が顕れる中、2011年に東日本大震災が発生。大規模な『死』に直面した被災地周辺では、さまざまな人生模様が繰り広げられる。本書は、そうした被災地の人々と直接・間接に触れ合った『場』を基点として〈死者/生者〉の関係を追究した共同研究(宗教学・思想史学・臨床医学・東洋医学)の成果である。」
本書の「目次」は、以下のようになっています。
「はじめに」鈴木岩弓
序章「見えないものを語るために」・・・磯前順一
第一部 沈黙の声を聴く――傾聴とは何か――
●死者のざわめき・・・山形孝夫
――「宗教の地平」を探る――
●声にならない声を聴く・・・高橋原
――死者の記憶に向き合う宗教者――
●生者のざわめきを聴く・・・金沢豊
――遺族の想いから生まれるもの――
◆コラム「ざわめきと声の汽水域」安部智海
第二部 支え合う死者と生者――鎮魂とは何か――
●「死んだら終りですか?」・・・木越康
――慈悲のかわりめ――
●二・五人称の死者・・・鈴木岩弓
――”死者の記憶”のメカニズム
●死者たちの団欒・・・佐藤弘夫
――彼岸で再会する人々――
◆コラム「いのちの境界を超える」竹本了悟
――超えることのよろこび――
第三部 生き残った者の生――翻訳とは何か――
●生き残るものの論理 声が届くこと・・・加藤智也
――意味を抜くこと――
●謎めいた死者のまなざし、そしてざわめく声・・・磯前順一
――酒井直樹の翻訳論再考――
●「彼らが幸せでいられるなら」・・・寺戸淳子
――声・権利・責任――
◆コラム「再会を期すこと」小田龍哉
――シンポジウム「鎮魂・翻訳・記憶」――
――声にならない他者の声を聴く」によせて――
終章 声を聴く者の倫理・・・須之内震治・磯前順一
――マッサージ・傾聴・精神分析――
「あとがき」佐藤弘夫
「はじめに」では、鈴木岩弓氏が1980年代半ば以降の日本において、「死」は専門家のみが語ることのできる敷居の高い存在ではなく、一般の人々にとって近しい存在へと姿を徐々に変えてきたことを指摘し、以下のように述べています。
「そうした変化は、とりわけ社会変動の波に対応する葬送墓制をめぐる新たな動向として次々に現れ、それが今に至るまでさまざまに展開してきています。思いつくままに挙げてみても、葬儀の面においては、葬祭専門業者の参画度合いの急増、自宅葬の減少と会館葬の増加、葬儀規模の縮小化、無宗教葬の増加や葬儀自体を行わない直葬の増加等といったことが。また墓制においては、従来型の墓を作らない樹木葬や散骨の登場、イエ意識の希薄化に伴う墓じまいとしてのイエ墓から永代供養墓への移行等。こうした変化の背後には、少し前までの日本における『死』をめぐる習俗には”当然”見られた血縁・地縁・社縁などといった人と人との繋がりが変容し、併せて価値観も大きく変わってきていることが示されています」
序章「見えないものを語るために」では、国際日本文化研究センター教授で宗教・歴史研究家の磯前順一氏が東日本大震災には世界中の人々が学ぶべき教訓があるとして、声にならない声に耳を傾ける必要があると訴えます。そして、インド人研究者のガヤトリ・スピヴァクが植民地支配に苦しむ人々の状態を「サバルタンは語ることは出来ない」と呼び表したことを紹介し、以下のように述べています。
「サバルタンとは服従を強いられる弱い立場の人々のことです。社会的な権利をもたない人たちですから、彼らを社会的な意味で『死者』と捉えることも出来るでしょう。当事者である彼らは声を発することが出来ないのだから、そうした人たちの言葉を聞くことは永遠にできないとスピヴァクはいいます。だからこそ、彼ら死者の言葉を生者に届けるためのシャーマンのような存在が必要とされるのです。日本の東北地方もかつてイタコの活動が活発な地域でしたが、いまや死滅する危機を迎えています」
しかし、死者の声を聞くと言っても、シャーマンたちが死者に憑依されただけでは、彼らの語る言葉が確かな意味をもつことはないと指摘し、磯前氏は以下のように述べます。
「死者たちの辛い思いに取り付かれただけでは、生き残った者は聞こえてくる様々な死者の声に悩まされ、統合失調症に陥ってしまうでしょう。死者の魂、そして生者の魂が救われるためには、死者の声の奥底にある、本当の願いを聞き届ける『翻訳』という特別な技術が求められているのです」そして、この世の生は無数の死者たちのまなざしやざわめく声に支えられて成り立っているとして、磯前氏は「死者には彼らを祀る生者が必要なように、生者には自分たちを支える死者のまなざしが必要なのです。ではどうした関係を生者と死者は取り結んできたのでしょうか。そしてこれから取り結ぶべきなのでしょうか。それこそが本書の主題にほかなりません」と述べるのでした。
第一部「沈黙の声を聴く――傾聴とは何か――」の「死者のざわめき――『宗教の地平』を探る――」では、宮城学院女子大学名誉教授で宗教人類学者の山形孝夫氏が、東日本大震災後の被災地のガレキの山について「見えてくるのは、失われた街の、失われた生命の、物言わぬガレキの堆積する、〈異界からの声〉である。なぜ異界と出会うことが必要なのか」と述べます。そして、それは宗教学の歴史からすると、「死を前にした人間が、死をいかに受け入れてきたか、その心性と習俗にかかわる人類の2000余年にわたる歴史を辿りながら、いかに死を手なずけてきたか、それに近づくための歴史を手に入れるために……」(島薗進「宗教史の可能性序論」、『岩波講座宗教3』岩波書店、2004年)ということになるといいます。
山形氏は、「死者のざわめきの地平」として、ジークムンド・フロイトとカール・マルクスの名前を挙げ、以下のように述べます。
「フロイトはマルクスとほとんど変わらない時期にあらわれ、宗教がそれほど簡単に人びとの脳裏から消滅しない事実に直面し、回りくどい言い方ではあるが、『宗教とは、人類一般の強迫神経症である』と定義した。フロイトによると『宗教教義は、神経症的遺物』であり、『信仰者とは全般的神経症にかかることによって、個人的神経症にかかる被害からまぬがれている人』をいう。これがフロイトの宗教的感情に関する定義である。その道の専門家に言わせると、このフロイトの定義は、マルクスの『人間は自然の一部である』という一元論的自然観とぴったり一致する定義であるという」
山形氏によれば、フロイトやマルクスにとって「宗教は悩んでいる者のため息」であり、したがって「アヘン」であり、「全般的神経症」であるのは、人間と自然との関係を人間と神との関係においてとらえた誤まてる論理的結果に過ぎないということになります。また山形氏は、「宗教論あるいは宗教的感情の行く方について言えば、フロイトやマルクスの精神と身体あるいは精神と自然との一元論に立つ限り、『死者のざわめき』は神経症の症状にすぎない。そうした批判をかいくぐって、いかに『死者のざわめき』の真相に迫ることができるか」とも述べています。
山形氏は、「生きている死者」として、一条真也の映画館「リメンバー・ミー」で紹介したアニメ映画にも通じる内容を以下のように述べています。
「東アフリカのウガンダに、『生きている死者』(living dead)という観念がある。まだ日の浅い死者の霊は、現在も生者の領域にとどまり、生前の個性をそのまま持ち続けて生きているという。記憶の中に生き続ける死者、つまり死のプロセスをまだ完了していない死者、これを『生きている死者』と呼ぶのだ。この『生きている死者』が、現に生きている人びとの生活に、どれほど深く根を下ろしているか。ウガンダ人の生活は『生きている死者』との共棲で成り立っているということができるほどである(ジョン・S・ムピティ『アフリカの宗教と哲学』大森元吉訳、法政大学出版局、1970年)」
続いて、山形氏は以下のように述べています。
「アフリカでは部族全体を巻き込む災害や危機が、いつでもどこからでも起こると想定されている。そうした危機に全員が一致して立ち向かうために、しばしば神に祈る。けれどもアフリカ人が祈るのは、遠い異界の神ではなく、身近に住む『生きている死者』なのである。彼らは死後も、部族や家族の一員であり、個々人の記憶の中に、今も鮮明に生きているからである。つまり、まだ『生者』とみられているのだ。正確に言えば、かれらは『死者』と『生者』の〈境界〉(あわい)に生きていて、あの世とこの世を仲介するまことに便利な役割を引き受けていると確信されているのだ。そのために生者は彼らに食物と飲み物を提供し、親愛と歓待の情をあらわにする。『生きている死者』は、家族であり、共同体の成員なのである」
また山形氏は「〈千の風〉から〈花は咲く〉へ」として、大ヒットした「千の風になって」を取り上げて以下のように述べています。
「『死者のざわめき』は、そうした失われた共同体の思えば懐かしい死者たちの今に続く声ではないか。今にして思えば、震災前、日本中を席巻した『千の風になって』(新井満訳詩)に登場する歌い手も死者だった。死者は『私のお墓の前で泣かないでください。そこに私はいません。死んでなんかいません』と歌っていた。新しい知の挑戦であるかのように、テノール歌手の透明な声が日本中に響き渡った。さる高名な僧侶が書いていた。『あの歌のお蔭で、寺の法事が激減した。わたしは愉快ではない』と。わたしは無理もない、と思った。あれは、日本仏教が、タブーとして封印してきた『死者のざわめき』であったのだから。なぜ封印されたのか。その理由は、はっきりしている。『死者のざわめき』は、平穏な社会秩序をおびやかす危険な亡霊の怨嗟の声とみなされたからである」
「千の風」は、それまでのそうした観念をひっくり返す不思議な歌であったのだと指摘する山形氏は、続けて、東日本大震災の復興ソングとしてヒットした「花は咲く」に言及します。「『千の風』の歌の流れは、3・11以後、こんどは『花は咲く』に引き継がれ、1本のガーベラの花を手に、静かに祈るように歌う東北ゆかりの俳優や歌手をとおして、被災地から日本中にひろまり、世界の各地で歌い継がれつつあると言うに。遠くから『誰かの歌が聞こえる……それが誰かを励ましている……笑顔が見える……』。いったい励ましているのは誰なのか、笑っているのは誰なのか。涙を抑えて歌っているのは、他でもない『死者』ではないか」
そして、「死者のざわめき」の「おわりに」で、山形氏は以下のように述べるのでした。
「問われているのは、残された者の悲しみであり、数え上げれば際限のない悔いと、やり場のない怒りである。そうした途方もない理不尽の痛苦と、いかに向き合って生きることができるか。問題は、そうした理不尽や際限のない感情に、どうすれば居場所を与えることができるか。それがどうにも分からない。だから『ざわめく』のである。確かなことは、この『ざわめき』の地平から『宗教のレッスン』が開始される、ということである。『ざわめき』の奥に、耳を澄ませば、死者たちが、きっと何かを語りかけてくる。『千の風』のように、『花は咲く』のように」
「声にならない声を聴く――死者の記憶に向き合う宗教者――」では、東北大学大学院文学研究科実践宗教学寄附講座教授で宗教心理学者の高橋原氏が被災地の心霊現象について調査したところ、以下のように述べています。
「調査の中で明らかになったことの1つは、『幽霊』に対して、宗教宗派によって定まった対応方法などないということであった。もっとも、浄土真宗の僧侶の回答は概して霊の存在には否定的であり、曹洞宗の僧侶には、否定はしないがそんなことを気にしても仕方がないというトーンの回答が多いといった特徴は見てとれた。もう1つは、このような相談に実際に応じている宗教者ほど、しっかりとした傾聴を行なっており、その上で、儀礼を上手に用いて、目の前で苦しんでいる人に対応しているということである。儀礼といってもそれは特殊なものではなく、葬儀や法事などで馴染みの経文を唱えることや、厄払いとして通常行なっている所作である。すなわち、そこに現われてきたのは、経験と勘を頼りに、手持ちの道具で、人々の苦悩に向き合い続ける宗教者たちの姿と、型通りの葬儀や公的な慰霊祭では収まりのつかない人々の死者への思いであった」
高橋氏は「儀礼の力」として、以下のように述べます。
「儀礼の持つ力というのは、ある程度は心理学的概念を使って理解することもできるだろうが、なぜそれが効き目をあらわすのかは、それを行なう僧侶自身にもよくわからないことのようである。おかしくなってしまった人を落ち着かせるために真言を唱えながら、結界を作るようにその周りを回るというある真言宗の僧侶は、『そんなことやっていて治まるのかなと不安なのですが、不思議なことに、おさまります』と語ってくれた。また、『霊感が強い』という人の依頼を受けた経験を語ってくれた別の曹洞宗僧侶は、『なんとかなるかはわからないけど、やれることはやりましょうというのが我々のスタンスであって、その人が満足、あるいはなんとかなったと思ってもらえればそれでいい』と言う」
「生者のざわめきを聴く――遺族の想いから生まれるもの――」では、龍谷大学世界仏教文化研究センター博士研究員で仏教学者の金沢豊氏が「ほんものの生」というキーワードを取り上げ、以下のように述べています。
「『ほんものの生』には、悲しみの感情によって近づくことができるという。多くの悲しみの感情の背景には音すらも立てない死者の存在がある。向きを変えれば、悲しむ生者の感情によって、死者がそこに生き生きと存在することが許される。だとすると、葬儀の場における涙は無意味ではないのではないだろうか。悲しみをもたらす死者の存在を明確に感じることで、不確かな自らの生者性(生きている感覚)を取り戻すことができる。しかし、その結論には、まだ辿り着くことはできない。なぜなら、死を超えるためには、対象である死者との距離の取り方を理解する手順が必要と考えるからだ」
また、「遺族の気持ちを聴く」として、金沢氏は以下のように述べています。
「東日本大震災における被害の甚大さを語る際『約2万人の死者』と言われるが、もう一歩踏み込んで考えてみれば、1人の死者の背後にどれほどの遺族がいるだろうか。おおよそ死者1人に対して、5人程度が大きな心的外傷を受けると言われる。ならば、1万人の方が亡くなったと言うことは、一挙に10万人以上の方が遺族として強い悲嘆の中にいらっしゃることが予想され、関係性だけで言えばその何十倍もの人が遺族感情を持つことになったと想像ができる」
大災害の遺族に対しては「傾聴」「気持ちを受け取ること」「そばに居続けること」などが求められますが、金沢氏は以下のように述べます。
「いわゆる『傾聴』『気持ちを受け取ること』『そばに居続けること』が形づくるものは、双方向の温かい関係性の構築である。それは、被災者/支援者の関係を越えた『わたし』と『あなた』の関係性とも言える。「被災された方の死にたいほどの苦悩を和らげたい」という目的は宗教者であるなしに関係なく居室訪問ボランティアの共通した活動の目的になった。またこの活動は東日本大震災の被災者支援においてのみ有効な事例として特殊化されることはないだろう。世界中で起こる様々な災害によって被災した人びとにとって、今を生きて生活していることは、その日に生み出された『喪失』と別なことがらではない。生き残った人々の心情は、いわゆる『サバイバーズ・ギルト(生存者の罪悪感)』という言葉でまとめられるような単純なものではないからだ」
そして、そこでは遺族の「生きる気持ち」を聴くことが大事であるとして、金沢氏は以下のように述べるのでした。
「遺族の想いに対して丁寧に接する姿勢そのものが『聴く』ことに連なる。聞き手は話し手に何かを与えるのではなく、相手の思いを感じ受け取る。三者三様に語られた『それでも生きる』という気持ちをしっかり受け止めることだと考える。死にたくなる状況下を生きてきた経験から生まれる言葉は、ひょっとすると『もう、死にたい』かもしれない。そこから滲み出る『生きる気持ち』へ気持ちを差し伸ばすことが『聴く』ことではないだろうか」
コラム「ざわめきと声の汽水域」では、浄土真宗本願寺派総合研究所研究助手の安部智海氏が、ざわめきが声(言葉)になり、言葉(声)からざわめきが呼び返されることを指摘し、その狭間にある汽水域について以下のように述べています。
「東日本大震災では、多くの喪失があった。景色が、生活が、そして多くの命が失われた。あまりにも突然の喪失は、程度の差こそあれ私たちの心をざわめかせた。数多のざわめきのなかで、ひとつ言えることがあるとすれば、死者の言葉を雄弁に語る第三者にとっても、近親者を亡くした方にとっても、どこかで自分と同じ喪失体験をしたであろう彼がいて、自分と同じ悲しみを抱えているかもしれない彼女がいるということである。それは見知らぬ『彼/彼女』かもしれない。しかし、自分と同じざわめきを共有している『彼/彼女』である。その『彼/彼女』が、自分と同じ時間、同じ場所に生きているということに頷けたとき、その地平で初めて『絆』という出来事は、自ずと立ち現れるのかもしれない」
第二部「支え合う死者と生者――鎮魂とは何か――」の「死んだら終りですか?――慈悲のかわりめ――」では、大谷大学学長で仏教学者の木越康氏が「慈しみの心、悲しみの心」として、以下のように述べています。
「『慈悲』とは、他者を慈しみ悲しむ心を言う。これについて親鸞は、『聖道と浄土のかわりめがある』と教えるのである。『慈悲』は、古くから『あの人は慈悲深い人だ』という称讃の意味や、『どうかお慈悲を!』と許しを乞う場面で使用されるが、元来は仏教用語で、他者に喜びを与えたいとする心の『慈』と、他者の苦しみを取り除きたい心である『悲』からなる。誰に対しても平等にはたらく慈悲心、つまりあらゆる他者を慈しみ悲しんで救いきろうとする心、そのような完成された慈悲心は、仏のみが有するものだとされる。これは『無縁の慈悲』とも言われ、いかなる人をも嫌わず、平等に慈しみ悲しみ、そして安らかさを与えるとされる」悟りを目指して修行する菩薩や行者たちには、したがって常に仏のように完璧な慈悲心を保持することが要求され、救いを完遂させることが期待されるといいます。『歎異抄』第四条で親鸞は「聖道の慈悲」という言葉を使いますが、それは、そんな菩薩や行者に求められる慈悲をさします。仏になることを目指して聖の道に入った者の慈悲心、それが聖道の慈悲なのです。
『歎異抄』の第五条では、親鸞は慈悲の「かわりめ」を説きます。この「かわりめ」について、木越氏は以下のように述べます。
「人は死んだら、それでおしまい。それが近代的合理精神に則った生命理解なのかもしれない。さまざまに死後の世界や滅後の生命を伝えてきた宗教的言説も、近代以降は例えば『非神話化』の名のもとに再解釈がなされ、親鸞の浄土教思想も、過度に近代理性の中で読み解かれてきた。加えて、そもそも仏教思想の場合、無常、空、無我など、根本原理そのものが、死んでもなお残る主体や世界を妄想であるとして拒絶する思想性を有する。縁起や無常を説くブッダの思想からすれば、確かにそうであろう。また、死後の浄土を希求するあり方を方便であり、仮門であり、真実とは区別して浄土教思想を捉えなおそうとする親鸞においても、そうなのかもしれない。死後の世界や滅後の生命は、人間の迷いの象徴として理解され、あるいは癒しを与える方便として受け止められるのかもしれない」
しかし、人間は人間であって、ブッダではありません。また、親鸞が生涯を朋として大切にしたのは、往生極楽の道を問い、先立つ者やわが身の行く末を案じる「いなかのひとびと」であした。この点を踏まえた上で、木越は以下のように述べます。
「届かない『あわれみ、かなしみ、はぐくみ』の心に、それでも『いとおし、不便とおもう』想いを断ち切れずにいる生身の人間である。妄想や迷いであると指摘されても、遺されたものは死者とのつながりを求めるのであろう。自ら妄想であり迷いであると疑ってはみても、死んでもなお遺る生命とのつながりを確かに感じ、共に生きていこうとするのである」
「二・五人称の死者――”死者の記憶”のメカニズム――」では、鈴木岩弓氏が東日本大震災にみる死者について考察する上で、まずは「『死者』とは誰か?」として、以下のように述べています。
「ジャンケレヴィッチは死の類型化に際し、死の人称に着目して『一人称の死』『二人称の死』『三人称の死』に3分した。言ってみれば、自己の死、親しい他者の死、一般的他者の死と言った類型である。これは『死』という抽象的な対象の類型を目指したものであるが、本稿の議論は『死者』という具体的対象の類型を目指している。ここでは彼の類型をヒントに、死者の類型を『一人称の死者』『二人称の死者』『三人称の死』の3分で考えてみよう。なおジャンケレヴィッチは、『一人称の死』は、自己の死を体験する主体が存在しなくなるため経験不能とし、現実に経験できるのは『二人称の死』と『三人称の死』のみとした。同様の観点からすると、『一人称の死者』というのは理念上想定できるが、われわれ自身が出会うことは不可能な死者なのである」
また、鈴木氏は「新盆」を取り上げ、以下のように述べています。
「『新盆』というのは、その1年内に亡くなった死者、読んで字の如く『新亡』にとって初めての盆であることから特別な意味づけをされることが常である。この年の盆直前に葬儀をしたことで、それまでの『行方不明者』が『死者』とその位置づけを変え、死者一般に対するわが国の対応システムの流れの中に組み入れられることになったのである。そしてこれを契機に、それまで長い間身近に行方不明者がいるという不安定な閉塞状況の中で生活してきた残された人々の多くにとっては、新たな”死者の記憶”が紡ぎ出され始めたと言うことになるのであろう」
さらに鈴木氏は、”弔い上げ”と”死者の記憶”に注目し、柳田國男の『先祖の話』の内容に言及して、柳田が、死亡直後の人は死のケガレが濃い状態にあるが、葬儀を経、また法事を繰り返すうちにそのケガレは次第に薄れ、死後33年、もしくは49年、50年目を迎える時を1つの区切りと考え、三十三回忌もしくは五十回忌の「弔い上げ」とも呼ばれる法事を迎えることで、死のケガレはすっかり無くなり(これを柳田はキヨマハリと呼ぶ)、「先祖」になるという考え方を紹介します。鈴木氏は述べます。「この『先祖』については、『人が亡くなってから50年目、もしくは33年目の最終の法事、即ち人間の亡霊が是からいよいよ神になる』として『神』とも呼ぶと言うのである。『先祖』について柳田國男は、『先祖は祭るべきもの、さうして自分たちの家で祭るのでなければ、何処も他では祭る者の無い人の霊、即ち先祖は必ず各々家々に伴ふもの』と定義する。つまり『先祖』とは、イエの系譜的な流れの中にいる、そのイエの子孫によって祀られる存在であるというのである。ただ問題は、そのイエで生じた『死者』が全て『先祖』となるわけではなく、『死者』の中でも『弔い上げ』を終えることが特に重要なポイントとなる」
続けて、鈴木氏は『先祖の話』に沿って、柳田の考えを紹介します。
「高いところに登った死者の霊魂は、『弔い上げ』の後『人間の私多き個身を棄て去って、先祖といふ一つの力強い霊体に融け込み、自由に家の為又国の公の為に、活躍し得るものともとは考へて居た』とし、『弔い上げ』を経ることで死の穢れが取れた死者の霊魂は、同時にその個性をも棄てることでそのイエ代々の死者の霊魂と共に1つの霊体に融け込むものと考え、そうした霊体のことを『先祖』と呼んだ。そしてさらに『先祖』は、イエや国のために働く『神』でもあると見なし、『それが氏神信仰の基底であったやうに、自分のみは推測して居たのである』と述べ、死霊が氏神信仰へと展開する『祖霊神学』を展開するのである」
仮に百回忌を行うためには、その死者を知っている参加者がこの世でその死者と対面した記憶をもつためには、105歳とか110歳になるわけですが、実際そこまで長生きする人は数少ないと指摘した上で、鈴木氏は以下のように述べます。「それがもし、自分が10歳の時に亡くなった爺さんの五十回忌というのであれば、その人は60歳ということで、現代日本人の平均寿命から考えるならば現実的にそうしたことは可能なのである。このように考えると、一般庶民の間で『弔い上げ』を最長でも五十回忌とし、百回忌以上を行わないところが大半である理由は理解できよう。”死者の記憶”を保持するに際しては、〈対面経験〉の有無によって、”想い”に違いが生じるからである。言い換えるなら、『弔い上げ』とは、〈対面経験〉をもった死者に対して固名詞で”死者の記憶”が保持されていられる、ぎりぎり最長の時期であるということができよう」
鈴木氏によれば、「先祖」とは「二・五人称の死者」です。そして、「先祖」にみるような「二・五人称の死者」の存在は、他の場面においてもいろいろ確認されるとして、以下のように述べています。
「例えば、この世で出会わなかった『弔い上げ』前の死者でも、また偉人や芸能人など生者からは強い”想い”をもって接するような死者も、〈対面経験〉が無い場合には『二・五人称の死者』として位置づけられることになろう。例えばJ・F・ケネディに心酔している人にとって、ケネディは『三人称の死者』とは言えないのはもちろんであるが、そのケネディに対する強い”想い”は〈対面経験〉がない点で、『二人称の死者』に準じるとまでは言えるとしても、あくまでも完全な『二人称の死者』とは言えない位置にある。こうした場合も、ケネディの記憶は『二・五人称の死者』として保持されていると言うことができよう。
続けて、鈴木氏は「英霊」にも言及します。
「また戦死者のことを『英霊』と呼んで今なお慰霊している場面も、この問題に関連しよう。現代日本の過半数の人々は、おそらく戦死者自身と〈対面経験〉を持ってはいないであろう。従って戦死者の固有名詞は社会的にも記憶の外に移りつつあるにもかかわらず、『英霊』という集合名詞で呼ぶことによって、『二・五人称の死者』を保持しているのである。戦死者もある意味大量死であったが、これと同様、事故死や災害死などによる大量死の際にも、『犠牲者』『殉職者』などといった集合名詞が、いずれも死後に時間をおいて、固有名詞に取って代わって読み替えられる中で保持されており、『二・五人称の死者』と言うことができよう」
最後に、鈴木氏は”死者の記憶”のメカニズムは最終的には忘却されるものであることを指摘し、以下のように述べるのでした。
「『去る者日々に疎し』で、どんなに親愛対象であった人だとしても、死別を境にその人と接する時間が共有できなくなることで、徐々にその死者のことを忘れて過ごす時間が多くなることは当然のことなのであろう。ある意味、そうした時間を過ごすこと自体が、グリーフワークの正常なプロセスだと言うこともできよう。そう考えると、死者を忘れることは、残された生者にとって、”負い目”に思うほど悪いことでないのはもちろん、残された生者が、その後の生を生き抜くためにも必要なことではないか、とも考えるのである」
作者:「死者たちの団欒――彼岸で再会する人々――」では、東北大学大学院文学研究科教授で日本思想史家の佐藤弘夫氏が、遠野市の西来院の「供養絵額」を紹介した後、「故人の死後の様子を描いて寺堂に奉納する習慣は、遠野地方だけでなく、東北一円に広くみられる風習である。山形県の村山地方では、若くして亡くなった男女の架空の婚礼姿を寺に納める『ムカサリ絵馬』という習俗が、いまも続いている」と述べています。また、「忘却される死者と記憶される死者」として、佐藤氏は以下のように述べます。
「故人は死後も継続する縁者との交流を通じて、小石が川の流れで角を落としていくように、生前にもっていた生々しい欲望や怨念をしだいに削ぎ落し、長い歳月をかけて徐々に神のステージ=『ご先祖』にまで上昇していくと信じられた。死者が救済者の力によって瞬時にカミに変身するのではなく、生者との長い交渉の末にカミの地位に到達するのが近世という時代だった。こうして近世には、子孫を守護するご先祖の観念が成熟していった。それに伴って、人々の思い描く自身の死後のあるべき姿が、見知らぬ遠い場所で悟りを開くことから、この世にいたまま、生前と同じように子孫と交流し続けることへと変化していく。やがて『ご先祖』となり、最終的には冥界でのリフレッシュの果てに、みずみずしい命を持って再びこの世界に生まれ来ることが理想の人生のサイクルと考えられたのである」
また佐藤氏は、「戸籍を持つ死者」として以下のように述べます。
「近世では死後の幸福は、縁者が継続的に故人をケアできるかどうかにかかっていた。先祖への変身の過程で、死者が忘却されたり、その供養が中断されたりすることがあってはならなかった。それは死者を記憶し続けることの重要性が、日本列島において大衆レベルではじめて社会的に認知されたことを意味した。特定の人物に対する記憶の継続が、その人物の死後の命運と不可分の関係をもつと信じられた時代が到来したのである」墓標の定着に伴って、死者供養の儀式も形式化し煩雑化していったと指摘する佐藤氏は、以下のように述べます。「供養が必要とされる期間はしだいに延長され、初七日から七十七日、一周忌から葬い上げまでの追善供養が定められ、人々の生活を規定するようになった。現在まで影響を及ぼしている葬儀の事細かな習俗が作り上げられ、地域ごとに伝統的な儀式として継承されるようになった。同じ宗派に属する寺院でも、地域が異なれば葬儀の形態が異なることも珍しくなかった。寺の属する宗派よりもむしろ地域ごとの特性の方が、葬儀の形態を強く規定するようになったのである」
「緩衝材としてのカミ」として、佐藤氏は以下のようにも述べます。
「私たちは都市というと、人間が集住する場所というイメージをもっている。しかし、実際に古今東西の史跡に足を運んでみると、街の中心を占めているのは神仏や死者のための施設である。中世ヨーロッパでは、都市は教会を中心に建設され、教会には墓地が併設されていた。日本でも縄文時代には、死者は集落中央の広場に埋葬された。有史時代に入っても、寺社が都市の公共空間の枢要に位置していた時代が長く続いた。そうした過去の風景を歩いていると、現代が、日常の生活空間から人間以外の存在を放逐してしまった時代であることを、改めて実感させられる」
「重なり合う生と死の世界」として、佐藤氏は、今日私たちは、「何時何分御臨終」という言葉に示されるように、生と死のあいだに明確な一線を引くことができると考えていると指摘します。そして、以下のように述べています。
「死の判定は専門家のあいだでも議論のある難しい問題だが、それでも大方の人はある一瞬を境にして、生者が死者の世界に移行するというイメージを抱いている。しかし、私たちが常識と思っているこうした死の解釈は、人類の長い歴史のなかでみれば、近現代に特徴的なきわめて特殊な感覚だった。前近代の社会では生と死のあいだに、時間的にも空間的にも、ある幅をもった中間領域を認めることが普通だった。その領域の幅は時代と地域によって違ったが、時間でいえば数日から10日ぐらいの間に設定されていた。呼吸が停止しても、即座に死と認定されることはなかった。その人は亡くなったのではない。生と死のあいだに横たわる境界をさまよっていると考えられたのである」
また、前近代の社会では、生と死が交わる領域は呼吸が停止してからの限られた期間だけではなかったとして、佐藤氏は「生前から、死後の世界へ向う助走ともいうべき諸儀礼が営まれる一方、死が確定して以降も、長期にわたって追善供養が続けられた。生と死のあいだに一定の幅があるだけではない。その前後に生者の世界と死者の世界が重なり合う長い期間があるというのが、前近代の人々の一般的な感覚だった。生者と死者は、交流を続けながら同じ空間を共有していた。生と死そのものが、決して本質的に異なる状態とは考えられていなかったのである」と述べています。
さらに、かつて人々は死後も縁者と長い交流を継続したとして、佐藤氏は以下のように述べます。
「それは、いつか冥界で先に逝った親しい人々と再会できるという期待に裏打ちされた行為だった。それはまた、自分自身もいつかは墓のなかから子孫の行く末を見守り、折々に懐かしい家に帰ってくつろぐことができるという感覚の共有にほかならなかった。『供養絵額』のように死者の世界を可視的に表現した記憶装置も数多く作られた。死後も親族縁者と交歓できるという安心感が社会のすみずみまで行き渡ることによって、人は死の恐怖を乗り越えることが可能となった。そこでは死はすべての終焉ではなく、再生に向けての休息であり、生者と死者との新しい関係の始まりだった。死はだれもが経験しなければならない自然の摂理であることを、日々の生活のなかで長い時間をかけて死者と付き合うことによって、人々は当たり前のこととして受け入れていったのである」
「異形の時代としての近代」として、私たちがいま住んでいる社会の特色は、この世界から人間以外の神・仏・死者などの超越的存在=カミを、〈他者〉として放逐してしまったところに求めることができると指摘し、佐藤氏は述べます。
「中世でも近世でも、人と死者は密接な関係をたもっていた。神仏もはるかに身近な存在だった。近現代人は『世界』といった時に、あるいは『社会』といった時に、その構成員として人間しか頭に思い浮かばない。しかし、中世や近世の人々の場合は違った。そこでは人間だけではなく、神・仏・死者・先祖など、不可視のカミをも含めた形でこの世界が成り立っていると考えられていた。カミはときには人間以上に重要な役割を果たす、欠くべからざる構成員だった。人がカミの声を聞きその視線を感じ取っていた時代の方が、人類の歴史のなかでは圧倒的に長い期間を占めていたのである。ヨーロッパ世界から始まる近代化の波動は、この世界から神や仏や死者を追放するとともに、特権的存在としての人間をクローズアップしようとする動きだった。これは人権の観念を人々に植え付け、人格の尊厳の理念を共有する上できわめて重要な変化だった」
「ゆるキャラの逆襲」として、およそこれまで存在した古今東西のあらゆる民族と共同体において、カミをもたないものはなかったと指摘し、佐藤氏は「そこから導き出せる結論はただ1つ、人間はカミを必要とする存在なのである。目に見えない存在との共生を実現できなければ、人は真に豊かな生を営むこと困難である。私たちが大切にする愛情や信頼も実際に目にすることはできない。人生のストーリーは可視の世界、生の世界だけでは完結しない。人は、不可視の存在を取り込み、生死の双方の世界を貫くストーリーを必要としているのである」と述べます。
また、息の詰まるような人間関係の緩衝材として、新たに小さなカミを生み出そうとする動きも盛んであるとして、佐藤氏は以下のように述べます。
「私がいまの日本社会で注目したい現象は、列島のあらゆる場所で増殖を続けるゆるキャラである。もちろんディズニーのミッキーマウスをはじめ、動植物を擬人化したキャラクターは世界中にみられる。しかし、その数と活動量において、日本のキャラクターは群を抜いている。これほど密度の濃いキャラクター、ゆるキャラの群生地は、地球上の他の地域には存在しない。大量のゆるキャラが誕生しているということは、それを求める社会的需要があるからにほかならない。それはなにか。私は現代社会の息の詰まるような人間関係のクッションであり、ストレスの重圧に折れそうになる心の癒しだと考えている。震災後に初めてディズニーランドを訪れた人が、ネット上に書き込んだ文章である」
この非常に興味深い論考の最後に、佐藤氏は以下のように述べるのでした。
「かつて生者と死者がより緊密に交渉していた時代には、多くの家庭がお盆には盆棚とよばれる仏壇を設置し、故人を家に招く風習が行われていた。その際、親族を迎える盆棚とは別に、行き場を失ってさまよっている不特定の死者を供養するために、無縁棚とよばれる小さな棚が設けられた。私はここに、この列島に生きた人々の究極の共生の精神を見出すことができるように思う。死者に優しい社会は、生きた人間にとっても居心地の良い場所であることは疑問の余地がない。死者を遠ざけ死を語ることを忌む風潮は、見直されるべき時期にきている。人類がこれまで蓄積してきた英智を生かしながら、生だけで完結するのではなく、生の世界と死の世界、可視の世界と不可視の世界を貫通する人生のストーリーをいかに再構築していくか、いま私たちは問われているのである」
第三部「生き残った者の生――翻訳とは何か――」の「謎めいた死者のまなざし、そしてざわめく声――酒井直樹の翻訳論再考――」では、磯前順一氏が「死者」について以下のように述べています。
「死者――それは災害や戦争で身体的に死亡した人間を指すだけではない。人権や主権を剥奪された社会的死者、精神を破壊された精神的死者。様々なかたちで死者は社会の周辺に存在する。あるいは精神を破壊されることなしに、社会の一員として、社会的権利を付与されることはないかもしれない。フロイトが『トーテムとタブー』で示したように、誰かを排除あるいは殺害することなしに公共空間が立ち上がらないとしたならば、私たちの社会は死者を輩出することで公共空間を形成することが可能になったのかもしれない。だとすれば、次々に生み出される死者に対して生者はどのように向き合っていったらよいのか。東日本大震災の大量死は、それが偶然の自然災害であるにとどまらず、原発を受け入れざるを得なかった寒村や海岸部の漁村地帯に限定されているという意味で、広い意味で社会構造の生み出した人災でもあったと言える。そうした弱者たちの死や犠牲をどのように社会が向き合って、引き受けていくのか。まさに酒井の言う「社会的不正義という倫理」が問われているのだ」
そして、磯前氏は「不均質な複数性の公共空間」として、以下のように述べるのでした。
「死者の声やまなざしは、私たち生者がコスモポリタン的な浮遊する主体にとどまりえず、歴史的時間の流れのなかで生み落とされた局地的な主体でもあることを示す。その余白を顕在化させる行為として、宗教や芸術あるいは学問もまた東日本大震災のなかで注目された。しかし、福島原発の周辺地域のように、死者の声さえも途絶える場合がある。その姿を見、声を聴く生者がいなければ、幽霊とて現れることはできない。死者が生者の記憶によって存在可能になるように、生者の共同体もまた死者を想起することで支えられる。死者との交流が途絶えたとき、人間は孤立し、真の絶望に陥る」
「彼らが幸せでいられるなら――声・権利・責任――」では、専修大学専任講師で宗教人類学を専攻する寺戸淳子氏が、一条真也の新ハートフル・ブログ『通過儀礼』(岩波文庫)で紹介したフランスの民俗学者アルノルト・ファン・へネップの名著を取り上げ、以下のように述べています。
「通過儀礼論の意義は、伝統社会で異なる機会に行われてきたさまざまな祭儀には『以前』から『以後』への『通過』という共通の目的がある、と指摘したことだけでなく、世界の正しい姿(家の構造)は決して変化せず、そこで起こるのは『部屋の住人の定期的な正しい移動』(人間社会を含めた世界全体を構成するすべての成員を、その時々にふさわしい定位置に正しく位置づけ直す)というコントロールされたあるべき変化だけであるという世界観、『世界全体に対する定位置感覚』を示した点にある。この世界観の下では、『死』は社会の成員が生者の部屋を出て死者の部屋へと移動することであり、部屋(の住人、すなわち生者と死者)同士の関係は『家』のルールに従って明確に定められていて、そこに迷いや不安はなかったと考えられる」
400ページ近い本書を通読すると、あまりにも多様な問題が凝縮されているので、眩暈のような感覚を覚えました。しかし、本書で取り上げられている問題はどれも看過することのできない重要なものばかりです。読了して、わたしは「生者は死者によって支えられている」ということを改めて痛感しました。本書の内容は、拙著『唯葬論』(サンガ文庫)で言及した諸テーマにも絡み合っており、興味は尽きません。
