- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.1618 文芸研究 『お化けの愛し方』 荒俣宏著(ポプラ新書)
2018.10.23
今回は『お化けの愛し方』荒俣宏著(ポプラ新書)を紹介いたします。「なぜ人は怪談が好きなのか」というサブタイトルがついています。
これまでにも、一条真也の読書館『フリーメイソン』、『0点主義』、『「死」の博学事典』、『喰らう読書術』、『戦争と読書』などで、著者の本を紹介してきました。著者は、1947年東京生まれの作家・博物学者です。武蔵野美術大学客員教授・サイバー大学客員教授。『帝都物語』がベストセラーになり、日本SF大賞受賞。『世界大博物辞典』でサントリー学芸賞受賞。神秘学・博物学・風水等多分野にわたり精力的に執筆活動を続け、著書・訳書多数。現代日本を代表する「博覧強記」の1人です。
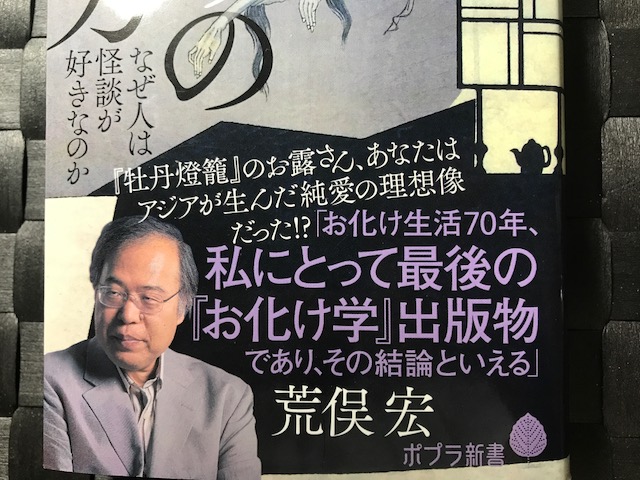 本書のカバー表紙
本書のカバー表紙
本書のカバー表紙には、著者の顔写真とともに、「『牡丹燈篭』のお露さん、あなたはアジアが生んだ純愛の理想像だった!?」「お化け生活70年、私にとって最後の『お化け学』出版物であり、その結論といえる」と書かれています。
また、カバー裏表紙には「未来への挑戦!」と書かれ、以下の内容紹介があります。
「”現代の知の巨人”荒俣宏が見つけた”究極の人生の答え”がここにある!」「お化けは『怖い』。そうしたイメージは、いつから生まれたのか。『牡丹燈篭』や『雨月物語』。タイの昔話に、西洋恋愛怪談の『レノーレ』。乱歩が見出した幻の書『情史類略』・・・・・・。怪談の起源を探る中で見えてきたのは、実は人間とお化けは仲良くなれるし、恋だってできるという、衝撃の価値観だった――。この本を読めば、あなたも『あの世』に行きたくなるかも?」
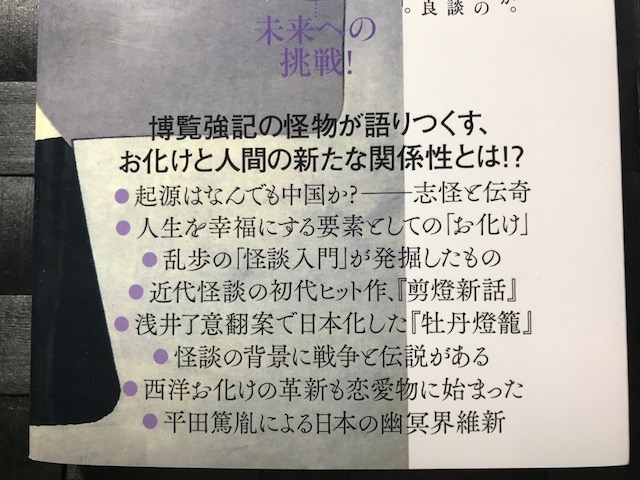 本書のカバー裏表紙
本書のカバー裏表紙
さらに、カバー裏表紙には「博覧強記の怪物が語りつくす、お化けと人間の新たな関係性とは!?」として、以下のように書かれています。
●起源はなんでも中国か?――志怪と伝奇
●人生を幸福にする要素としての「お化け」
●乱歩の「怪談入門」が発掘したもの
●近代怪談の初代ヒット作、『剪燈新話』
●浅井了意翻案で日本化した「牡丹燈籠」
●怪談の背景に戦争と伝説がある
●西洋お化けの革新も恋愛物に始まった
●平田篤胤による日本の幽冥界維新
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
まえがき「お化けはこわいのか?」
第一章 お化け愛の始まり――日本に登場した新しい怪談
第二章 馮夢龍と「解放の怪談」
第三章 怖い怪談の呪縛――日本の場合
第四章 お化けとの恋愛が認められるまで
第五章 日本に広がった「牡丹燈記」
第六章 町人文学の大暴れ――『牡丹燈篭』から『聊斎志異』へ
第七章 怪談愛の至高点『雨月物語』
第八章 アジアへヨーロッパへ――『メー・ナーク』と『レノーレ』
第九章 西洋でも、生死を越えた恋が成就した!
第十章 圓朝版『牡丹燈篭』と文章変革
第十一章 駒下駄の音と新しい演出
おわりに「霊との共同生活、ついに実現!」
あとがき「お化けとの恋愛を志願する」
まえがき「お化けはこわいのか?」で、著者は小学生頃から「お化けはたのしい」と思っていたそうで、その「きっかけ」について次のように述べています。
「『きっかけ』の1つは、小学校3年生のときに祖父が交通事故死し、ばらばらになった遺体が縫いあわされた状態で、家に帰ってきたことだった。私はこわさを忘れて、おじいさんの顔をのぞき込んだり、すっかり冷たくなった両手を触ったりした。でも、祖父は目を開けない。この現実をどう受け入れればいいのか困った。死という現実にぶつかったのだが、祖父はそんなこともあろうかと、私が赤ん坊のころから現世は無常であの世のほうが永遠である、という哲学を、芸者歌謡や都々逸などを通じて、変な趣味の孫に教え込んでいたふしもある」
祖父の遺体が戻ってきたとき、著者は、ある芸者歌の1つによって戸惑いを救われたそうです。「明治一代女」という戦前にはやった歌でしたが、「怨みますまい この世のことは 仕掛け花火に似たいのち もえて散る間に 舞台が変わる まして 女はなおさらに」という一節がありました。著者は述べます。
「この世は仮の世で、死後の世界こそが真実だ、という。たしか江戸川乱歩のお気に入りの名言にも『うつし世は夢 夜の夢こそ真実』というのがあった。おじいさんはダンプカーに轢かれて亡くなったけれど、それはただ『仮の世』からいなくなるだけのこと、死んでまた別の世に移ったにすぎない、と理解した。悲しいことの多いこの世を脱して、新しい『生』を開始できるのなら、お化けになることはむしろ喜ばしいことなのではないか、と気がついた」
さらに、著者は以下のように述べるのでした。
「もっとはっきり言い切ろう。日本のお化けとまっとうにお付き合いするには、ホラーを観るという感覚だけではいけないのだ。死んだ者や異界の者と、恋をしたり、家族を作ったり、コミュニティを作ったり、という建設的な方向も、あってしかるべきだ。私もここ10年くらいで、お化けとのお付きあいの仕方や、お化けとの恋愛について多少の知恵がついた。70歳に近くなったせいもあるが、いよいよ『親しい感じ』が強くなってきている。きっと『妖怪感度』が磨かれたのだろう」
本書の前半部分では、著者は中国の怪談に多く言及します。日本の怪談話は少なからず中国の影響を受けているからです。中国の『牡丹燈記』から日本を代表する怪談である『牡丹燈籠』が生まれました。両作品の差違について、著者は当時の中国の価値観や作者の境遇、さらには恐怖を演出する話芸などにも言及しています。『牡丹燈籠』と同じく、”死者との恋”を描いている『雨月物語』の「浅茅が宿」も、著者は徹底的に分析しています。
本書で最も興味深く読んだのは、第四章「お化けとの恋愛が認められるまで」でした。ここでは、孔子が登場します。著者は、「儒教の開祖であった孔子は、怪力乱神については、怪しい神々や荒っぽい化け物のことをことさらに語らなかったけれども、まるで無関心だったわけではない。孔子すらもじつは易学のような神秘的な学問に熱中していた」と述べています。
著者は、孔子が易のような宇宙モデルによって、眼に見えないが実在するらしい異空間の存在を説明しようと考えていたふしがあると指摘し、以下のように述べます。
「実際、孔子の一族というのは、元来お葬式の管理や葬礼に関係した一族だったといわれる。霊とか魂とかの問題の専門家筋でもあったのだ。孔子が唱えた『古えの神君、名君への敬慕』は、『礼』をもって祖先霊を祀る儀式に源を発した可能性が高い。葬儀というのは基本的には霊の世界を鎮めることだから、孔子一族には霊との付き合いやルール、考え方というものが家業と結びついていたことにもなる」
続いて、著者は「日本でも銅鐸などがたくさん作られたが、あの銅鐸は霊を鎮める葬礼の楽器であった可能性もあり、元は孔子一族やら菅原道真の先祖一族のような葬礼と墳墓づくりを担った『神霊知識』の専門グループに伝えられた霊的産業技術の一例とも考えられる」などと述べています。このあたりは一条真也の読書館『孔子伝』で紹介した白川静の名著に詳しいです。
さらに、孔子は、韋編三絶のエピソードにからんで、「あともうちょっと寿命をくれたらこの『易経』のシステムを解明して、みんなに残すことが出来たのになあ」と悔しがったという話を残していることを紹介し、著者は「このエピソードからも推測できるのは、彼が魂や宇宙の問題にも大きな関心を有し、実際に葬儀の礼に関係したと同時に、世界の運行を占い知る易をも研究していた、いわばファウスト博士のような立ち位置だ」と述べます。とても興味深いですね。
第七章「怪談愛の至高点『雨月物語』」では、『雨月物語』が創始した死女愛の文学が語られます。そこで著者は、歌舞伎について以下のように述べます。
「歌舞伎も風俗紊乱の元凶として目の敵にされ、とりわけ女の歌舞伎役者が一掃されて、江戸時代に『女形』というじつに不可思議な芸が誕生するのだが、歌舞伎もまた『霊魂観の一大転覆』に深く関わっている。歌舞伎流行のきっかけをつくった出雲の阿国は、周知のように出雲大社の巫女だったといわれる」
そればかりでなく、出雲の阿国は浄土教とも関係した「鎮魂師」でもあったらしいとして、著者は以下のように述べます。
「阿国が舞台に載せた演目を基にして書かれたといわれる『歌舞伎草子』に、その意味がちゃんと表現されている。この時代、『風俗』と名付けられた『浮世=憂世』の退廃的な光景が絵や物語や演劇を覆い尽くしていた。この末世末法、『憂世』感覚が、中国で伝奇小説を発生させ、日本でもお伽草子や阿国歌舞伎を生み出す原動力だった」
第八章「アジアへヨーロッパへ――『メー・ナーク』と『レノーレ』」では、冒頭で「アジアに広がった『浅茅が宿』型ロマンス」として、著者はこう述べています。
「中国に端を発した志怪・伝奇の妖しい物語は、漢字文化圏の拡大とともに周辺国へも伝わっていった。その行先は日本だけではない。東南アジアへも華僑の進出とともに怪談が運ばれ、以前から存在していた地元の民話と結合しながら、東南アジア全体に新たなバリエーションを波及させた。つまり、『雨月物語』のようなゴーストとのラブストーリー、ハリウッド映画で言えば『ゴースト/ニューヨークの幻』のような話が、各国それぞれの風土に適応してその土地なりの幽霊物語に深化していった」
第十一章「駒下駄の音と新しい演出」では、「小泉八雲の手厳しいコメント」として、著者は以下のように述べています。
「精神の柔軟さがあるからこそ、日本人はお化けにリアリティーを抱ける。お化けとの恋愛の話とは、まさにそうした心のリアリティーの究極形態だ。ひとことに要約するなら、日本人は幽霊と恋ができるほどやわらかいメンタリティーを磨き上げてきたのだ。それゆえ、圓朝も怪談を俗っぽい人情劇と重ね合わせることができた。
そういうわけで、『怪談』を書いた明治期の文学者小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)も、日本の怪談に興味を感じたきっかけは、歌舞伎で演じられた『牡丹燈籠』にあった。三遊亭圓朝の高座で直に聞いたのか、あるいは速記本を読んでもらったのか、『カラーン、コローン』と鳴る駒下駄の響きが、よほど耳に残ったのだろう。八雲も、お露の立てる駒下駄の響きに幽霊の繊細な気配を感じたようだ」
本書では、中国の怪談が大きく扱われています。
著者は『怪奇文学大山脈』(全3巻、東京創元社)を刊行したときに全精力を使い果たし、身も心も「出し殻状態」となり、もう何も書く気が起こらなかったそうです。そんな著者にわずかに残っていたのは、中国の怪談への興味だけだったといいます。中国を最後のお化けの探検地とかんじた著者は、さまざまな書物を読んで中国文化の真の奥深さを知るようになったとか。さらに決定的だったのは、白川静の労作『字通』に親しんだことでした。
漢字の字源のほとんどに「神」か「化け物」か「まじない」がかかわっていることを『字通』で知り、がぜん生き返った著者は以下のように述べます。
「早い話、荒俣宏の『荒』という字からして運命的だったのである。白川さんによれば、荒の字は『草かんむり』に、野ざらしの頭蓋骨を意味する『ボウ(※荒から草かんむりを除いたもの)』が加わって成立している。『ボウ』はさらに分かれて、『亡』の部分が頭、その下の『川』に似た字形が『頭蓋骨に付着した長い髪の毛』を表すという。髪の毛がへばりついた頭蓋骨が野原に転がっている光景が『荒』だというので、思わず、すでにハゲあがってぬれ落ち葉のごとき毛が何本か取りすがっている我が頭を鏡に映しながら、戦慄を覚えた」
あとがき「お化けとの恋愛を志願する」の最後に、お化けとのお付き合いにかかわる「最も東洋的な部分」の鉱脈を探り当てたことで満足したいという著者は「あとは自分が実際に死者になったときに、ウソかマコトかをたしかめればよろしい。なんだか、死ぬのが楽しくなってきた。できれば、あの世での恋人はこころ優しい死女におねがいしたい」と述べるのでした。
本書は”死者との恋愛”を中心に怪談を論じているため、それ以外の幽霊や妖怪の類は登場しません。著者が「お化け生活70年、私にとって最後の『お化け学』出版物であり、その結論といえる」と言うわりには、怪談全体のほんの一部、それもコアな話題しか取り上げておらず、物足りない印象は否めません。サブタイトルである「なぜ人は怪談が好きなのか」という問いにも答えているとは言えないでしょう。せっかく、水木しげる大先生の妖統(?)を受け継ぐ著者なのに、ちょっと残念でした。
わたしは『唯葬論』(サンガ文庫)の「怪談論」で、「怪談」こそは古代から存在するグリーフケアとしての文化装置であると指摘しました。怪談とは、物語の力で死者の霊を慰め、魂を鎮め、死別の悲しみを癒すこと。ならば、葬儀もまったく同じ機能を持っていることに気づきます。人間の心にとって、「物語」は大きな力を持っています。わたしたちは、毎日のように受け入れがたい現実と向き合います。そのとき、物語の力を借りて、自分の心の形に合わせて現実を転換しているのかもしれません。つまり、物語というものがあれば、人間の心はある程度は安定するものなのです。逆に、どんな物語にも収まらないような不安を抱えていると、心はいつもぐらぐらと揺れ動き、死別の場合であれば愛する人の死をいつまでも引きずっていかなければなりません。
仏教やキリスト教などの宗教は、大きな物語だと言えるでしょう。「人間が宗教に頼るのは、安心して死にたいからだ」と断言する人もいますが、たしかに強い信仰心の持ち主にとって、死の不安は小さいでしょう。なかには、宗教を迷信として嫌う人もいます。でも面白いのは、そういった人に限って、幽霊話などを信じるケースが多いことです。宗教が説く「あの世」は信じないけれども、幽霊の存在を信じるというのは、どういうことか。それは結局、人間の正体が肉体を超えた「たましい」であり、死後の世界があると信じることです。宗教とは無関係に、霊魂や死後の世界を信じたいのです。幽霊話にすがりつくとは、そういうことなのです。
死者が遠くに離れていくことをどうやって表現するかということが、葬儀の大切なポイントです。それをドラマ化して、物語とするために、葬儀というものはあるのです。たとえば、日本の葬儀の九割以上を占める仏式葬儀は、「成仏」という物語に支えられてきました。葬儀の癒しとは、物語の癒しなのです。人類は葬儀、そして怪談という物語の癒しによって「こころ」を守ってきたのではないでしょうか。どうですかね、荒俣さん?