- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2018.10.25
『日日是好日』森下典子著(新潮文庫)を読みました。「『お茶』が教えてくれた15のしあわせ」というサブタイトルがついています。著者は、1956年、神奈川県横浜市生れ。日本女子大学文学部国文学科卒業。大学時代から「週刊朝日」連載の人気コラム「デキゴトロジー」の取材記者として活躍。その体験をまとめた『典奴どすえ』を87年に出版後、ルポライター、エッセイストとして活躍を続けています。
 本書の帯
本書の帯
本書の帯には映画版に出演した黒木華、樹木希林(故人)の写真が使われ、「毎日がよい日。雨の日は、雨を聴くこと。いま、この時を生きる歓び――」と書かれています。
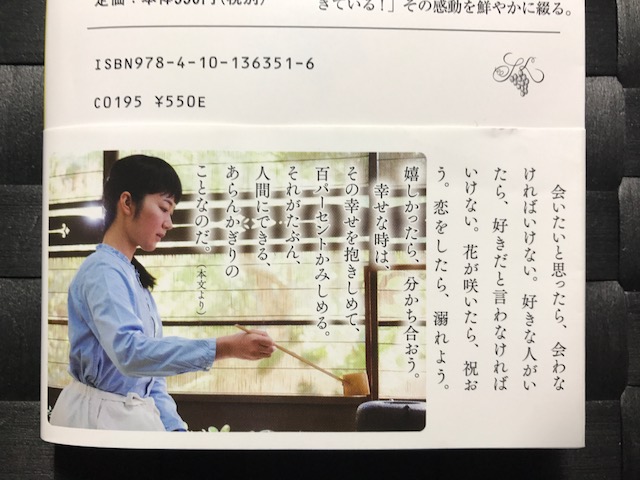 本書の帯の裏
本書の帯の裏
カバー裏表紙には、以下の内容紹介があります。
「お茶を習い始めて二十五年。就職につまずき、いつも不安で自分の居場所を探し続けた日々。失恋、父の死という悲しみのなかで、気がつけば、そばに『お茶』があった。がんじがらめの決まりごとの向こうに、やがて見えてきた自由。「ここにいるだけでよい」という心の安息。雨が匂う、雨の一粒一粒が聴こえる・・・季節を五感で味わう歓びとともに、『いま、生きている!』その感動を鮮やかに綴る」
本書の「目次」は、以下のようになっています。
「まえがき」
序章 茶人という生きもの
第一章 「自分は何も知らない」ということを知る
第二章 頭で考えようとしないこ
第三章 「今」に気持ちを集中すること
第四章 見て感じること
第五章 たくさんの「本物」を見ること
第六章 季節を味わうこと
第七章 五感で自然とつながること
第八章 季節を味わうこと
第九章 自然に身を任せ、時を過ごすこと
第十章 このままでよい、ということ
第十一章 別れは必ずやってくること
第十二章 自分の内側に耳をすますこと
第十三章 雨の日は雨を聴くこと
第十四章 成長を待つこと
第十五章 長い目で今を生きること
「あとがき」
「文庫版あとがき」
「解説」柳家小三治
一条真也の映画館「日日是好日」で紹介した映画の原作エッセイです。わたしは、父が千利休よりも古い小笠原家古流茶道の全国団体の会長を務めていることをはじめ、周囲に茶道と関わっている人が多いので、非常に興味深く観ました。わたしの長女もずっと東京の茶道教室に通っているのですが、映画の中の黒木華演じる女性と重なって見えました。茶道は「ジャパニーズ・ホスピタリティ」そのものであると言えますが、親としては少しでも娘に日本人としての「つつしみ」「うやまい」「おもいやり」の心を知り、「もてなし」というものを体得してほしいと思っています。
じつは映画鑑賞の前日に原作である本書を読んだのですが、大変感動しました。本書は茶道の最高の入門書であり、一条真也の読書館「茶の本」で紹介した岡倉天心の名著の現代版であり、さらには高度情報社会を生きる日本人のための優れた幸福論であると思いました。「まえがき」で、著者はこう書いています。 「世の中には、『すぐわかるもの』と、『すぐにはわからないもの』の2種類がある。すぐわかるものは、一度通り過ぎればそれでいい。けれど、すぐにわからないものは、フェリーニの『道』のように、何度か行ったり来たりするうちに、後になって少しずつじわじわとわかりだし、「別もの」に変わっていく。そして、わかるたびに、自分が見ていたのは、全体の中のほんの断片にすぎなかったことに気づく。『お茶』って、そういうものなのだ」
本書は『茶の本』である前に『水の本』です。雨、海、瀧、涙、湯、茶などが次々に出てきますが、これらはすべて「水」からできています。地球は「水の惑星」であり、人間の大部分は水分でできています。「水」とは「生」そのものなのです。孔子といえば、わたしは『世界をつくった八大聖人』(PHP新書)という本を書きました。その中で、ブッダ、孔子、老子、ソクラテス、モーセ、イエス、ムハンマド、聖徳太子といった偉大な聖人たちを「人類の教師たち」と名づけました。彼らの生涯や教えを紹介するとともに、八人の共通思想のようなものを示しました。その最大のものは「水を大切にすること」、次が「思いやりを大切にすること」でした。
「思いやり」というのは、他者に心をかけること、つまり、キリスト教の「愛」であり、仏教の「慈悲」であり、儒教の「仁」です。そして、「花には水を、妻には愛を」というコピーがありましたが、水と愛の本質は同じではないかと、わたしは書きました。興味深いことに、思いやりの心とは、実際に水と関係が深いのです。『大漢和辞典』で有名な漢学者の諸橋徹次は、かつて『孔子・老子・釈迦三聖会談』(講談社学術文庫)という著書で、孔子、老子、ブッダの思想を比較したことがあります。そこで、孔子の「仁」、老子の「慈」、そしてブッダの「慈悲」という三人の最主要道徳は、いずれも草木に関する文字であるという興味深い指摘がなされています。そして、三人の着目した根源がいずれも草木を通じて天地化育の姿にあったのではないかというのです。
儒教の書でありながら道教の香りもする『易経』には、「天地の大徳を生と謂う」の一句があります。物を育む、それが天地の心だというのです。考えてみると、日本語には、やたらと「め」と発音する言葉が多いことに気づきます。愛することを「めずる」といい、物をほどこして人を喜ばせることを「めぐむ」といい、そうして、そういうことがうまくいったときは「めでたい」といい、そのようなことが生じるたびに「めずらしい」と言って喜ぶ。これらはすべて、芽を育てる、育てるようにすることからの言葉ではないかと諸橋徹次は推測し、「つめていえば、東洋では、育っていく草木の観察から道を体得したのではありますまいか」と述べています。
東洋思想は、「仁」「慈」「慈悲」を重んじました。すなわち、「思いやり」の心を重視したのです。そして、芽を育てることを心がけました。当然ながら、植物の芽を育てるものは水です。思いやりと水の両者は、芽を育てるという共通の役割があるのです。そして、それは「礼」というコンセプトにも通じます。孔子が説いた「礼」が日本に伝来し、もっとも具体的に表現したものこそ茶道であるとされています。
また、飛行機の操縦士だったフランスの作家サン=テグジュペリは飛行機の操縦士でしたが、サハラ砂漠に墜落し、水もない状態で何日も砂漠をさまようという極限状態を経験しています。そこから、水が生命の源であることを悟りました。そしてねゆささブログ『星の王子さま』に「水は心にもよい」という有名な言葉を登場させたのです。
『日日是好日』の本質が『水の本』であることは、「まえがき」の雨の描写において最もよくわかります。次の通りです。
「ある日突然、雨が生ぬるく匂い始めた。『あ、夕立が来る』と、思った。庭木を叩く雨粒が、今までとはちがう音に聞こえた。その直後、あたりにムウッと土の匂いがたちこめた。それまでは、雨は『空から落ちてくる水』でしかなく、匂いなどなかった。土の匂いもしなかった。私は、ガラス瓶の中から外を眺めているようなものだった。そのガラスの覆いが取れて、季節が『匂い』や『音』という五感にうったえ始めた。自分は、生まれた水辺の匂いを嗅ぎ分ける1匹のカエルのような季節の生きものなのだということを思い出した。毎年、4月の上旬にはちゃんと桜が満開になり、6月半ばころから約束どおり雨が降り出す。そんな当たり前のことに、30歳近くなって気づき愕然とした」
本書は何よりもまず、茶道をテーマにした本です。拙著『儀式論』(弘文堂)の第6章「芸術と儀式」で詳しく述べたように、茶道は単に一定の作法で茶を点て、それを一定の作法で飲むだけのものではありません。実際は、宗教、生きていく目的や考え方といった哲学、茶道具や茶室に置く美術品など、幅広い知識や感性が必要とされる非常に奥深い総合芸術です。その茶道を学ぶことについて、著者はこう書いています。
「人は時間の流れの中で目を開き、自分の成長を折々に発見していくのだ。だけど、余分なものを削ぎ落とし、「自分では見えない自分の成長」を実感させてくれるのが『お茶』だ。最初は自分が何をしているのかさっぱりわけがわからない。ある日を境に突然、視野が広がるところが、人生と重なるのだ。すぐにはわからない代わりに、小さなコップ、大きなコップ、特大のコップの水があふれ、世界が広がる瞬間の醍醐味を、何度も何度も味わわせてくれる」
ここでは、「水」と「コップ」という言葉が登場します。わたしは、これは「こころ」と「かたち」のメタファーであると思いました。
水は形がなく不安定です。それを容れるものがコップです。水とコップの関係は、茶と器の関係でもあります。水と茶は「こころ」です。「こころ」も形がなくて不安定です。ですから、「かたち」に容れる必要があるのです。その「かたち」には別名があります。「儀式」です。茶道とはまさに儀式文化であり、「かたち」の文化です。
ちなみに、拙著『人生の四季を愛でる』(毎日新聞出版)で、わたしは「『人生100年時代』などと言われるようになった。その長い人生を幸福なものにするのも、不幸なものとするのも、その人の『こころ』ひとつである。もともと、『こころ』は不安定なもので、『ころころ』と絶え間なく動き続け、落ち着かない。そんな『こころ』を安定させることができるのは、冠婚葬祭や年中行事といった『かたち』である」と書きました。
本書には、茶道の他にもさまざまな日本文化の魅力が語られています。たとえば和菓子について、著者は第六章「季節を味わうということ」で以下のように書いています。
「ミルフィーユやシュークリームが大好きで、和菓子など見向きもしなかった私が、お茶を始めて1、2年のうちに、すっかり和菓子の魅力に目覚めていた。
裏ごししたそぼろ状の餡を、餡玉の芯のまわりに寄せ集めた『きんとん』は、3月の『菜の花』、4月の『桜』、5月の『つつじ』と、目先を変える。夏は、葛や寒天で涼しげに『水』を表現する。和菓子には、素材そのものの味に、季節感が加味されていた。1年中、同じ姿のシュークリームやケーキが、なんだかつまらなく思えた」
また、茶花について、著者は以下のように書いています。
「いろいろな音や匂いに気づくと、同時に『茶花』が見えるようになった。茶花は、いたる所に咲いていた。
犬が散歩するとき、どの電信柱に自分の匂いをつけたか、どこにお気に入りの異性がいるかをはっきりつかんでいるように、私が日々暮らす半径1キロは、顔見知りの茶花の『花地図』で、変わった。
春、向かいの家の土手に『ほうちゃくそう』が、2、3輪、つりがねのような小さな白い花をつける。団地の裏の草地に『二人静』が群生する場所がある。電車から見える土手の斜面が『しょかつさい』(大根の花)で一面薄紫色に染まる。我が家とお隣との塀際に、『しゃが』が列をなして咲く。駐車場の路肩に『ねじばな』が咲き、ガードレールに『昼顔』がからみついて、薄いピンクの花を次々に開かせる。それまで、花は花屋で売られているものと思ってきたけれど、花屋の店先で売られている花は、花の世界のごく一部でしかなかった」
茶人という生き物は、四季を愛でる達人だと言えます。
著者は、昔の茶人たちが「節分」「立春」「雨水」と指折り数えて自分自身を励まし、何度も冬への揺り戻しに試されながら、辛抱強く、人生のある季節を乗り越えようとしたことだろうと考えます。そして、「だから茶人たちは、お節句や季節の行事を1つ1つだいじに祝うのかもしれない。季節とは、そういうものなのだ……」と思うのでした。さらに、四季には自然の四季だけでなく、人生の四季もあります。
著者が翌日に就職試験を控えて落ちかなかったとき、茶道の師匠である武田先生は、著者のために達磨の絵入りの掛け軸を飾ってくれました。
第八章「今、ここにいること」には次のように書かれています。
「達磨さんには、『七転び八起き』『開運』という意味がある。『喝を入れる』という意味も込められていたかもしれない。
掛け軸は、今の季節を表現する。けれど季節は、春夏秋冬だけではなかった。人生にも、季節があるのだった。先生はその日、私の『正念場』の季節に合わせて、掛け軸をかけてくれたのだった。夕暮れの稽古場で、釜が、シュンシュンと湯気を上げていた」
お茶の世界は「わからないこと」だらけですが、次第にすべてのことには意味があるということを著者は悟ります。第十章「このままでよい、ということ」で、次のように書いています。
「濃茶は多量のカフェインを含んでいる。からっぽの胃には、刺激が強すぎる。だから濃茶を飲む前に、懐石料理を食べ、からの胃を満たしておくのだ。
その懐石料理の食後に添えられるデザートが和菓子だ。
(そうか! ふだんは、茶事の流れの中から「懐石」を省略して、デザートの「和菓子」と「濃茶」の部分を稽古してるんだ)
濃茶をおいしく練るには、お湯が熱くなければいけないが、11月以降の寒い季節は、水が冷たく、沸騰するのに時間がかかる。 (だから、懐石の前に「炭点前」をするのか!)
その「炭点前」の時、客たちが炉のまわりに集まる。
(炭火を見ながら暖を取るのか! そして、懐石の間に湯がわいて、寒い部屋が暖まるんだ・・・・・・。なるほど、うまくできている!)
わかってみると、その流れは、実に合理的にできていた。さまざまなことが、ストンと腑に落ちた。すべてのことに理由があり、何一つ無駄はなかった」
第十一章「別れは必ずやってくること」では、茶道の一大イベントである「茶事」が取り上げられます。著者は次のように書いています。
「茶事の流れを何度かなぞるうちに、外国映画で見たことのある『晩餐会』にも、そっくりな場面がいっぱいあることに気づいた。たとえば、正式な『招待状』を受け、正装して集まることも、『控えの間』(寄り付き)に集まって、全員そろってから、『ダイニングルーム』(茶室)に入ることも……。晩餐会では、長いお食事が終わったら、淑女は化粧直しに、紳士な葉巻きを吸いに行くが、茶事でも、懐石がすんで露地に出ると、腰掛に必ず『煙草盆』と『煙管』が用意されている」
また、お茶とワインを比べて、著者はこう述べます。
「レストランなどで、グラスに少し注がれたワインの色を見、味と香りを確かめ、『けっこうです』とうなずく『テイスティング』は、今では日本人にもおなじみになったが、濃茶の最初の一口を飲む場面で、亭主と正客の間にかわされる『お服かげんはいかがでございますか?』『けっこうでございます』のやりとりと重なる」
「お茶とワインは、よく似ていた。その年の5月に摘んだ茶葉を、茶壺につめて秋までたくわえ、11月初旬の炉開きのころ、初めて茶壺の封を切って茶葉を臼で挽いて点てる『口切りの茶事』は、茶事の中で最も正式なものだという。この時から、その年の『新茶』が飲めるようになる。だから、『炉開き』を『茶人の正月』と呼ぶ。『新酒』のワインの封を切って祝うボジョレーヌーボー解禁も11月だった」
「一期一会」として、著者と父親の永遠の別れが綴られていますが、著者は以下のように述べています。
「人生に起こるできごとは、いつでも『突然』だった。昔も今も……。もしも、前もってわかっていたとしても、人は、本当にそうなるまで、何も心の準備なんかできないのだ。結局は、初めての感情に触れてうろたえ、悲しむことしかできない。そして、そうなって初めて、自分が失ったものは何だったのかに気づくのだ。
でも、いったい、他のどんな生き方ができるだろう? いつだって、本当にそうなるまで、心の準備なんかできず、そして、あとは時間をかけて少しずつ、その悲しみに慣れていくしかない人間に……」
このあたりのくだりは、拙著『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)のメッセージと重なります。著者はグリーフケアの核心を衝いていると思いました。
続けて、著者は次のように書くのでした。
「だからこそ、私は強く強く思う。会いたいと思ったら、会わなければいけない。好きな人がいたら、好きだと言わなければいけない。花が咲いたら、祝おう。恋をしたら、溺れよう。嬉しかったら、分かち合おう。幸せな時は、その幸せを抱きしめて、100パーセントかみしめる。それがたぶん、人間にできる、あらんかぎりのことなのだ。
だから、だいじな人に会えたら、共に食べ、共に生き、だんらんをかみしめる。一期一会とは、そういうことなんだ……」
この文章は本書の帯の裏でも使われていますが、とても力強く、読む者の心を打つ感動的な名文であると思います。
「日日是好日」には、春夏秋冬……日本の四季がすべて登場します。そして、美しく描かれています。それぞれの四季折々にはふさわしい花があり、菓子があり、そして年中行事があります。世の中には「変えてもいいもの」と「変えてはならないもの」があります。年中行事の多くは、変えてはならないものだと思います。なぜなら、それは日本人の「こころ」の備忘録であり、「たましい」の養分だからです。
正月の初釜で樹木希林さん演じる武田先生が「こうしてまた初釜がやってきて、毎年毎年、同じことの繰り返しなんですけど、でも、私、最近思うんですよ。こうして毎年、同じことができることが幸せなんだって」と、しみじみと語るシーンがあります。茶道はたしかに繰り返しです。春→夏→秋→冬→春→夏→秋→冬……毎年、季節のサイクルをグルグル回っています。考えてみれば、茶人とは「年中行事の達人」であり、「四季を愛でる達人」なのですね。
そして、季節の他にもう1つ、茶道はさらに大きなサイクルを回っています。それは、子→丑→寅→卯→辰→巳→午→未→申→酉→戌→亥……の十二支です。初釜には、必ずその年の干支にちなんだ道具が登場するのでした。干支の道具は、その干支の年にしか使えません。それも、1年間いつでも使えるわけではなく、正月と、その年の最後のお稽古に限定されています。1年のしめくくりは、いつも、「先今年無事目出度千秋楽」(まず今年無事めでたく千秋楽)という掛け軸と、干支のお茶碗でした。著者は、干支の茶碗が、「いろんなことがあるけれど、気長に生きていきなさい。じっくり自分を作っていきなさい。人生は、長い目で、今この時を生きることだよ」と言っている気がしたそうです。
茶人は「人生の四季を愛でる達人」でもあるのです。こういうふうに人生の四季を愛でていけば、「老いる覚悟」や「死ぬ覚悟」を自然に抱くことができるのではないでしょうか。まさに、茶道とは「人生の修め方」にも通じているのです。
拙著『茶をたのしむ』(現代書林)に詳しく書きましたが、茶道は、禅と深い関わりがあります。禅宗は「今をどう生きるか」を説く仏教の一派ですが、茶道には禅の精神が随所に生きています。むしろ禅の思想が茶道の根本にあると言ってもいいでしょう。偉大な茶人はすべて禅の修行者でもあったことを考えれば、茶道の正体とは、茶の湯という「遊び」を通して禅の「教え」を伝える「宗遊」なのかもしれません。人は茶室の静かな空間で茶を点てることに集中するとき、心が落ち着き、自分自身を見直すことができます。『茶をたのしむ』では、わたしなりに茶道の本質を求めましたが、著者は次のように書いています。
「『お茶は、むかしの暮らしの様式美だ』と言う人もいる。『日本の芸術の集大成だ』と思う人もいる。『ひたすらお点前をすることによって無をめざす美の宗教だ』と書いた人もいる。『季節を扱う暮らしの知恵の結集』『禅の1つのスタイル』……。お茶は、どんな解釈をも許容する。ならば、私の見方もまた、1つの茶の世界なのだ。もしかすると、お茶はその人自身を映しているのかもしれない。人の数だけお茶があるのだ」
著者は「雨の日は、雨を聴く。雪の日は、雪を見る。夏には、暑さを、冬には、身の切れるような寒さを味わう……どんな日も、その日を思う存分味わう」と書き、お茶とは、そういう「生き方」なのだと言います。そうやって生きれば、人間はたとえ、まわりが「苦境」と呼ぶような事態に遭遇したとしても、その状況を楽しんで生きていけるかもしれないというのです。雨が降ると、「今日は、お天気が悪いわ」と言いますが、本当は「悪い天気」など存在しません。雨の日を味わうように、他の日を味わうことができるなら、どんな日も「いい日」になります。それが「日日是好日」ということなのです。お茶をやったことがある方も、やったことがない方も、ぜひ、幸福ということを知るために本書を読んでいただきたいと思います。
