- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D

No.1652 プロレス・格闘技・武道 | 神話・儀礼 『大相撲の不思議』 内館牧子(潮出版社)
2019.01.20
この本は「神事」としての大相撲に詳しく言及した非常に興味深い本です。著者は1948年秋田県生まれ。武蔵野美術大学卒業。三菱重工業に入社後、13年半のOL生活を経て、1988年に脚本家デビュー。テレビドラマの脚本に「毛利元就」「ひらり」「私の青空」など多数。2000年から10年まで女性初の横綱審議委員会審議委員を務める。06年、東北大学大学院文学研究科修了。05年より同大学相撲部監督に就任し、現在は総監督を務めています。
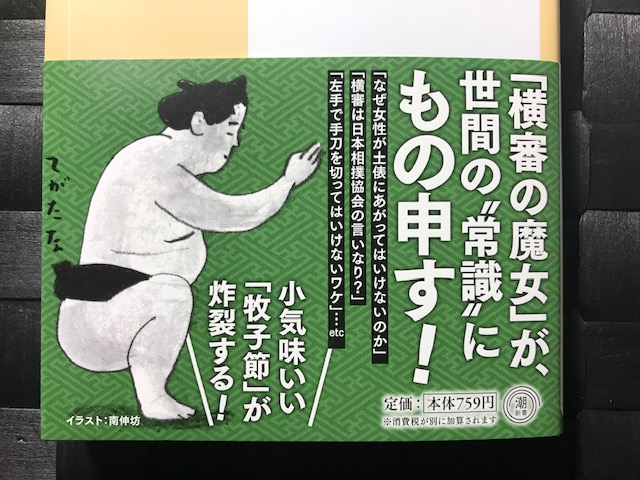 本書の帯
本書の帯
帯には南伸坊による手刀を切る力士のイラストが描かれ、「『横審の魔女』が、世間の”常識”にもの申す!」「なぜ女性が土俵 にあがってはいけないのか」「横審は日本相撲協会の言いなり?」「左手で手刀を切ってはいけないワケ」……etc「小気味いい『牧子節』が炸裂する!」と書かれています。また帯の裏には、「宗教的考察から、ポロリ事件そしてキラキラネームまで知れば知るほど深遠な大相撲の世界へようこそ!」と書かれています。
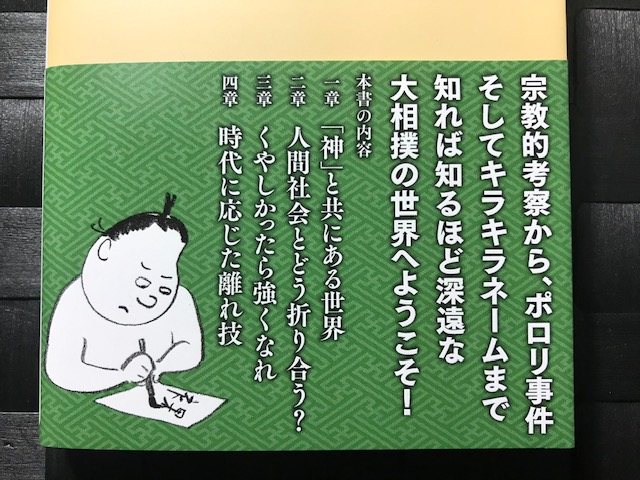 本書の帯の裏
本書の帯の裏
本書の「目次」は、以下の通りです。
「まえがき」
第一章 「神」と共にある世界
土俵という聖域
なぜ大相撲は摩訶不思議なのか?
聖域を理解する知性と品性
花道
髪に花をさした力士たち
花道は「霊気」の通り道
土俵
土俵は荒くれ者の喧嘩対策?
喧嘩から競技へ昇華した相撲
土俵築
機械を一切使わない土俵築
宇宙創造を再現する祭式
土俵祭
土俵に神を招き送り出す
復活した行司の胴上げ
四本柱
ロイヤルボックス なぜ北に置く?
神を切り捨てた相撲協会の妙案
第二章 人間社会とどう折り合う?
一門
日本相撲協会は普通の組織体か!?
「貴の乱」と波瀾の理事選
横綱審議委員会
協会の言いなりか?
女性初の委員誕生の舞台裏
屋形
室内に屋根を設けるナゾ
水引書をめぐる陸軍と海軍の攻防
懸賞①
五穀豊穣への感謝を表す手刀
聞く耳を持たない横綱朝青龍
懸賞②
現在まで続く懸賞の起源
横綱白鵬を変えた”万歳事件”
第三章 くやしかったら強くなれ
番付
実力だけを評価する世界
くやしかったら強くなれ
格差
あらゆる場所に定められる格差
憧れの大銀杏と土俵入り
横綱
消されてしまった「黒白の横綱」
「聖なる故実」を後づけする
土俵入り
横綱、幕内、十両にだけ許された「儀式」
攻守兼備の雲龍型と、攻め一筋の不知火型
相撲教習所
原点は「紳士教育」
新弟子から力の士へ
まわし①
新聞を賑わせた「ポロリ事件」
稽古まわしと締込み
まわし②
奥が深い”フンドシ”の歴史
下がりが意味するもの
前相撲
番付に載らない力士たち
実技試験がない大相撲!?
髷
どんな男もかすむ力士の髷姿
敬意と格差の絶妙なバランス
第四章 時代に応じた離れ技
相撲茶屋
心ときめく異世界への入口
角界を揺るがせた理事長の割腹事件
四股名
キラキラネームの力士たち
今に伝わる四股名の系統
手形
巨体力士たちの巨大な手形
異形の男の数奇な人生
天皇賜盃
盃をめぐるミステリー
前代未聞、菊の御紋章事件
国技館
命名劇は鮮やかなうっちゃり
日本中が驚いた三度の国技館新築
「主な参考文献」
「まえがき」で、著者が横綱審議委員だった時、委員会の席上で出席していた協会幹部の親方が、「その件に関して、相撲節会の時はですね」と言ったことがあると紹介し、次のように述べています。
「唖然とした。相撲節会は奈良・平安時代の宮中行事だ。21世紀の会議で、何の違和感もなく8世紀のことを持ち出す社会が他にあるだろうか。あの時、私は圧倒され、そしてゾクゾクした。紛れもなく、『近代的な「歴史」とは違う時間を生きている』社会、文化なのだと思った」
その時期に前後して、「女性を土俵にあげないのは、男女差別だ」「角界の体質は古い。男女平等、男女共同参画から改革を始めよ」という声が大きくなってきました。この件に関して、著者は次のように述べます。
「問題は伝統文化の世界である。また、民俗芸能や風俗、風習、行事などについてもだ。誰もが思い浮かべるのは大相撲と歌舞伎、宝塚歌劇だろうが、各地には男だけ、女だけが担う祭りもあれば、シャーマンとして女だけが執り行う習俗、男しか担えない風習も残っている」
続いて、著者は次のように述べています。
「それらの多くは発祥の時点から、男だけ女だけの謂れがあり、今に伝わっているはずだ。その謂れは現代にあっては取るに足らないものであったり、時代に合わないとされたりもした。こういう状況と時代を考え、これまで守ってきた当事者たちが、それこそ『男女共同参画』に改めたものもある。ただ、現時点ではそれを拒んでいる世界もあり、大相撲もその1つである」
著者自身は、伝統文化や民俗行事、習俗等に関しては、男女共同参画にする必要はまったくないと考えているとして、以下のように述べます。
「とかく『男女差別だ』と言われるが、それは『差別』ではなく、一方の性だけが担い伝えてきた『文化』だと考える。それを現代の考え方に合わせて変える必要はない。それをすると、別ものになる。反対の声を真摯に検討することは、伝統を生かす上でも重要なことだ。そして最終的に決断するのは、守り抜いてきた当事者である」
一章「神と共にある世界」の「花道」では、「花道」の原点は大相撲にあり、天平6(734)年には、花道があったと考えられているとして、以下のように述べられています。
「天平6年といえば、聖徳太子の死後112年しかたっていない。都はまだ平城京にあった時代だ。『源氏物語』が書かれたのが西暦1000年頃とすると、それより260年以上も前ということである。その頃、相撲にはすでに『花道』を設えるという文化があったと考えていいだろう」
というのは、天平6年から「相撲節会」と呼ばれた天覧相撲が始まったのです。時代は貴族社会で、もう世にも豪華な天覧相撲だったと伝わっている。それは宮中で2日間にわたって行われ、天皇の他にも位の高い貴族たちが居並び、御簾の陰からは女御たちも見物していたとか。著者は、「天皇の御前で相撲を取る力士は全国から集められ、陰陽師に先導されて足踏みをしながら『入場式』のようなことをやったという。この相撲節会では相撲だけでなく、歌舞音曲、軽業など数々の芸能を見せ、絢爛なものであったことは、多くの史料に残されている」と述べています。
当時、まだ土俵はありませんでした。力士は今で言う東と西から出てきて、中央で相撲を取るのですが、この時、東から入ってくる力士は頭に葵の花をさしていたそうです。著者は次のように述べます。
「西から入ってくる力士は、瓠の花をさしていた。瓠は夕顔やひょうたん類の総称である。東は、朝日を浴びて咲く葵であり、西は夕日を浴びて咲く夕顔という考え方も優美だ。それぞれの花をつけた力士が、中央へと入ってくるため、その道を『花道』と呼んだという説が伝わる」
続けて、以下のように書かれています。
「東西の方角にふさわしい花をつけて、両力士が入ってくるというだけでも、その貴族趣味と、相撲が単なる格闘スポーツではないことに気づく。ところが、さらに驚くべきことを知った。相撲節会では、勝った力士が自分の花を、次に出てくる力士につけてやることになっていたのだ。つまり、勝ち力士の花は『肖り物』である。つけてもらう力士にとって、勝者に肖る縁起物である。当然ながら、勝った力士だけが花をつけてやることができる」
相撲節会では、天皇が北を背にして座り、南面します。この当時、まだ土俵はありませんが、東西(当時は左右)に力士を配します。これについて、スポーツ人類学者の寒川恒夫氏は著書『相撲の宇宙論』で「東西南北の四方位とその中心たる天皇という古代の王室宇宙論の意識をみてとることができるのである」と書いています。この形は、現在の国技館もまったく同じです。東西南北の四方位を結界し、その中心たる天皇は相撲節会で北に座したので、今もロイヤルボックスは北にあります。天皇は南面して座り、力士は東西に配置されています。
また、小説家・エッセイストの加門七海氏は、著書『大江戸魔方陣』において、道は「場所から場所に霊気を通すもの」と定義しています。ということは、花道は障害や魔物が侵入できる「入口」ではなく、土俵という聖域に霊気を通す「装置」なのだと考えられます。土俵の吊り屋根から下がっている四色の房を見ると、四方位を結界している各房には「四神」とされる神獣が宿っています。龍、虎、鳥、亀の四神獣が土俵を守っています。著者は、「花道はこの聖域に霊気を通す唯一の、神聖な道と考えることができるのではないだろうか」と述べています。
「土俵築」では、「宇宙創造を再現する祭式」として、著者は「午後、無人になった国技館に私は一人残り、生まれたての土俵を眺めていた。こんなに美しいものがあるだろうかと思った。畏怖を感じた」と書き、宗教学者のエリアーデが、人間が都市を築いたり、寺院を建てたりすることすべてを、「神々による太初の宇宙創造を再現することである。そしてそこが世界の中心と成る」と著書『聖と俗』に書き、「さらに人間はこのような宇宙を、周期的な祭式によって時間的にも、くり返しくり返し太初創造の『かの時』に立ち帰らせ、新鮮無垢なものとする」と続けていることを紹介します。土俵を毎回築き直す意味に、著者はこれを重ねるといいます。と同時に、著者は「太初創造の『かの時』に立ち帰る世界に、何ゆえ21世紀の男女共同参画が必要なのかと思うのである」と述べています。
「土俵祭」では、「復活した行司の胴上げ」として、千秋楽で、表彰式が終わった後も観客が帰らずにいると、非常に珍しい「神送り」の儀式が見られることが紹介され、以下のように述べられます。
「土俵に降りてくれた神に礼を捧げ、元の場所へと送り出す儀式である。その起源は明確ではない。『神迎え』に比べると厳粛ではなく、民俗行事の大らかな雰囲気がある。そこには緊張のとけた人間の安堵感も漂い、いいものである。
では、どうやって神を元の場所に送るのか。想像がつくだろうか。それは胴上げするのである。白幣を一本持った行司を、土俵上で新弟子ら前相撲力士が取り囲む。この白幣は神が乗り移っている一本である。そして、立呼出しの柝に合わせ、三本締めが行われた後、前相撲力士たちは、その行司を胴上げする。行司は神が宿る白幣を持ったまま、若い力士たちに力いっぱい天に上げられる。これにより、神は元の場所に帰ったということになる」
民俗学者の桜井徳太郎は、日本各地の祭りを数多く見たフィールドワークから、古くは祭りが終わる際に、取り仕切った神主を氏子たちが胴上げしたと書いています。また、長野の善光寺の「御越年式」では年末に、僧侶が仕切り役を胴上げします。祭りの終わりに胴上げすることについて、桜井は前出の書に、「(これにより)ようやく日常の生活に戻るのです」と書いています。神を胴上げで送り出し、「祭り」というハレの場から、「日常」というケに戻ります。土俵も「聖域」から単なる土に戻ります。つまりは結界を解く儀式ということになるのです。
「四本柱」では、四本柱、土俵、屋形の3つが揃ってから、当時の相撲関係者が「ビジネス」として、神との接点を後づけしたとしか考えられないとして、「この頃、まだ『相撲協会』はない。だが、江戸相撲組織が整いつつあった。ここに至るまでの間、相撲界は天覧の古い歴史を持ち、織田信長や豊臣秀吉ら戦国大名や将軍家の上覧など、特別なステイタスを誇っていた。そこでさらに、他の芸能や興行よりステイタスを上げるために、神と共にあることを示そうとした。そう考えることはできる。言うなれば、江戸時代に『神と共にある土俵』という伝統を『作った』のである」と書かれています。
また、「神を切り捨てた相撲協会の妙案」として、かつての大日本相撲協会が四本柱を切っても、神が土俵に宿る方法を考え出したと紹介し、以下のように述べています。「それは四本柱のかわりに、東西南北に四色の房を下げることだった。屋形はその房を結わえるかのように、天井から吊ればいい。これにより、四神も守護神も今までと同じに、房に宿るわけである。読者の中には『柱が持つ宗教性によって神が降りるのであり、房ではダメだ』と思う人もあろう。だが、私はこれこそ日本人が得意とする『見立て』そのものだと思う。つまり、房は『柱に見立てたもの』であり、柱とイコールなのだ。『房』に見えるが、あれは『柱』なのである。この見立ての発想には驚愕させられた」
二章「人間社会とどう折り合う?」の「横綱審議委員会」では、著者が女性初の横綱審議委員会審議委員に就任したとき、男の聖域の中で、いわば四面楚歌の中で、著者がなすべきことはひとつだと思ったそうです。それは村松友視が『私、プロレスの味方です』の中に書いていた「ちゃんと見る者は、ちゃんと闘う者とは完全に互角である」という一文でした。
著者は高価な最前列の席を自費で購入し、本場所の15日間のうち12、3日間は座ったそうです。そして「ちゃんと見る」ことに努めました。任期10年のうちにできることは少ないですが、闘う者と互角にならなければ物は言えないと思ったのです。
三章「くやしかったら強くなれ」の「憧れの大銀杏と土俵入り」では、土俵入りが横綱、幕内、十両だけに許されていることが紹介され、以下のように述べられています。
「横綱は露払いと太刀持ちを従え、一人で土俵入りをする。土俵入りには雲龍型と不知火型があるのだが、どちらの所作も『清浄潔白』を示す塵浄水を行い、四股で土中の邪鬼を踏みつぶし、せり上がりで体勢の変化を演じる。
一方、幕内と十両の土俵入りについては、これもよく聞かれる。『力士がゾロゾロ出てきてはチョンと柏手を打って、化粧まわしをつまんで、それからバンザイ。あれって何? 笑える』実は柏手からバンザイに至るまでの一連の動きは、前述した横綱土俵入りを簡略化した所作なのである。十両になって初めて、化粧まわしを許されて行う神事としての土俵入り。これまでの数々の格差が甦り、『お袋を国技館に呼びました』と言った力士を幾人も知っている。なお、化粧まわしに紫色を使うのは、大関と横綱にのみ許されている」
「横綱」では、「消されてしまった『黒白の横綱』」として、以下のように書かれています。
「第4代と第5代小野川喜三郎は、寛政元(1789)年、同時に横綱に昇進した。2人は真っ白い綱を巻き、化粧まわしの上に5本の真っ白い幣を垂らし、初めて『横綱』として世の中に登場したのである。そして、その姿で、土俵入りを見せた。もちろん、世の人々は『横綱』を見るのも、『土俵入り』を見るのも初めてである。壮麗で神聖な儀式にどれほど熱狂し、夢中になったか想像できるというものだ」
また、「『聖なる故実』を後づけする」として、相撲の原点は「神事」ですが、以降の歴史をひもとくと、相撲が常に聖なるものとして育まれてはいないと指摘されます。しかし、江戸期の勧進相撲あたりからは、特にうまくビジネスライクに「聖なる故実」を後づけしています。それによって相撲のステイタスを上げているとして、著者は「あくまでも私の考えだが」と断った上で、「吉田司家と江戸相撲組織が、自分たちのさらなる地位確立のために横綱を作り出したのではないか。真っ白な綱、真っ白な幣をつけ、神を宿らせた体で儀式として土俵入りをする。力士や相撲を見る世間の目が大きく変わっただろう。それによって、相撲組織は客を呼べるし、神が宿る横綱に免許を授与するのだから、吉田司家の威光は増す。みごとなウィンウィンのビジネス感覚である」と述べています。
かつて教習所講師をつとめた歴史学者の和歌森太郎は、著書『相撲の歴史と民俗」に、「これまでとかくすると、力士はやや博徒あるいは侠客風なところがあってその点が愛されもしたけれども、洗練された紳士たちには、相撲をどうもなじみがたいものにさせてもいたのである。このような傾向を粛正して、力士も人間として紳士らしく振舞わねばならないことを強調したのは常陸山であった。礼節のやかましい部屋の生活、一般人に対する所作に折り目正しいものを持つようになったのは、すべて常陸山以来であったといってよい」と書いています。常陸山は水戸藩の武術師範をつとめる武士の家に生まれ、明治37(1904)年に第19代横綱になっています。没年は大正11(1922)年で、教習所創立の約35年も前です。
「まわし②」では、「下がりが意味するもの」として、著者は、下がりは「草」を意味しているのではないかと推測します。民俗学者の『折口信夫全集』に「相撲の古い形は、體に草をつけて行うたのである。これは、古代の信仰では、遠くからやって來る異人の姿だつたのである」「何故、相撲をするには、體に草をつけて異人の姿をしなければならなかつたか。それは、此神事がもとは、神と精霊との争ひを表象したものであったからだ」と書いています。絶対の力を持ち、病魔も敵もすべて退散させる異界から訪れる人は「異人」と呼ばれます。その「異人」を表現する上で、體に草をつけた。それが下がりに残っているのではないかと推測しています。
「四股名」では、「そもそも、なぜ力士は四股名をつけるのか」という問題が提示されます。本来は「醜名」と書きます。かつて、力士と俳優は「異人」とされていました。別世界から遣わされた客人です。歴史学者の和歌森太郎は著書『相撲今むかし』に、「シコ名をもって、普通人とは違うことを示していた」と書き、仏文学者で作家の宮本徳蔵は双葉山について『相撲変幻』に「(シコ名を)名のったときから宗教的人格と化した」と書き、「かれは今や並みの人間の力量を超えた金剛力士(仁王)なのであって、宇宙の彼方より降りそそぐ無限のエネルギーを五体に吸収しつつ、いかなる難敵をも破摧せずにはおかない。(中略)法名を持たぬ僧侶があり得ないごとく、醜名は力士にとって不可欠の属性だ」と続けています。
著者によれば、力士は神に仕える宗教的人格を持つと考えた時、「醜」という字をあてる意味がわかってくるといいます。「醜」とは邪鬼のことです。醜名は神に向かい合う者としての、へり下りなのです。「自分如きの醜なる者」というへり下りを、「醜名」をつけることで表しているといいます。
醜名は「普通人とは違う」ことを表現しているだけではありません。いかなる難敵を撃退する力を示す目的もありました。当然ながら強そうな名が多く、最古のそれは、「雷」「稲妻」「大嵐」「辻風」などで、自然の驚異をまとおうとしているようです。この仁王たちが、神社仏閣を建てるための勧進相撲において、四本柱の中で四股を踏みました。「四股を踏む」ということは「醜を踏む」ことです。力士は地中の邪鬼を踏みつぶし、大地を活性化させているのです。著者は「この勧進相撲における四股踏みによって、『四股名』と記されるようになったとされる」と書いています。本書は、神事としての大相撲、文化としての大相撲を知る最良のガイドブックであると言えるでしょう。