- 書庫A
- 書庫B
- 書庫C
- 書庫D
2019.03.05
『縄文の思想』瀬川拓郎著(講談社現代新書)を読了。
縄文時代に対する日本人の関心は高く、一条真也の新ハートフル・ブログ「縄文展」で紹介したイベントの成功からもわかるように、そのブームは衰えることがありません。本書は、日本人の原点である縄文時代を知るための最適な一冊です。著者は1958年、札幌市生まれ。考古学者、アイヌ研究者。岡山大学法文学部史学科卒業。2006年「擦文文化からアイヌ文化における交易適応の研究」で総合研究大学院大学より博士(文学)を取得。旭川市博物館館長。
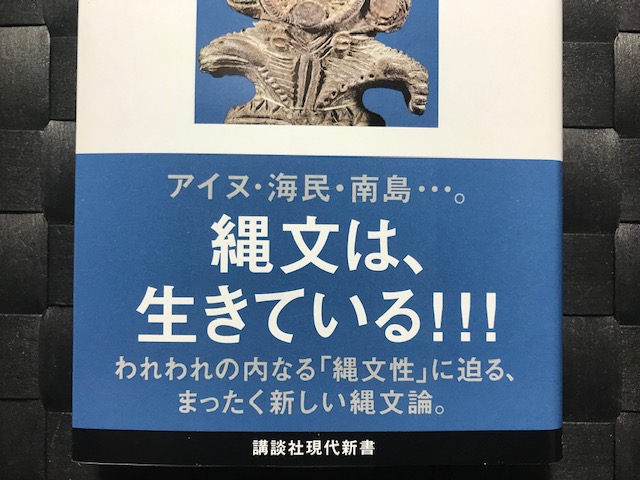 本書の帯
本書の帯
帯には土偶の写真とともに、「アイヌ・海民・南島…。縄文は、生きている!!!」「われわれの内なる『縄文性』に迫る、まったく新しい縄文論」と書かれています。また、帯の裏には「弥生化した列島にも縄文の精神は生き続けていた!」として、「はじめに」から文章が抜粋されています。
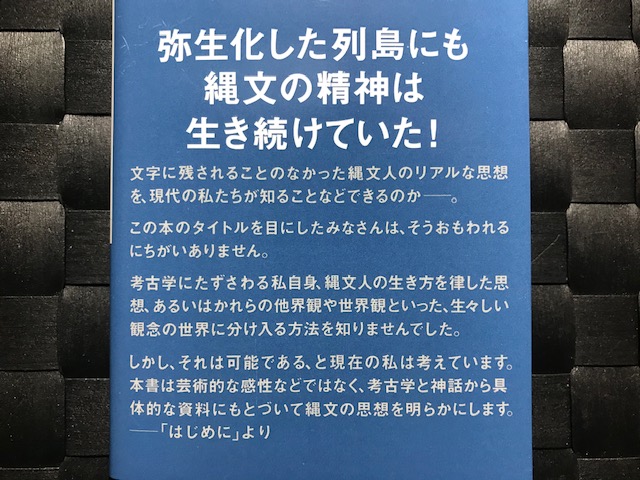 本書の帯の裏
本書の帯の裏
本書の「目次」は、以下の構成になっています。
「はじめに」
序章 縄文はなぜ・どのように生き残ったか
第一章 海民と縄文――弥生化のなかの縄文
1 残存する縄文伝統
2 海民の誕生
第二章 海民とアイヌ――日本列島の縄文ネットワーク
1 海民のインパクト
2 交差する北の海民・南の海民
3 離島の墓に眠るのはだれか
4 謎の洞窟壁画
第三章 神話と伝説――残存する縄文の世界観
1 共通するモティーフ
2 他界の伝説
3 縄文神話とその変容
4 伝播した海民伝説
――アイヌの日光感情・卵生神話
第四章 縄文の思想
――農耕文化・商品経済・国家のなかの縄文
1 呪能と芸能
2 贈与と閉じた系
3 平等と暴力
4 動的な生へ
「おわりに」
「引用文献」
「はじめに」の冒頭には、「生き残る縄文」として、以下のように書かれています。
「海辺や北海道、南島という日本列島の周縁に生きた人びとの、弥生時代以降の歴史から縄文の思想を立体的に浮かびあがらせるのが本書の方法であり、従来にはなかった独自性でもあります。縄文は失われた過去ではなく、周縁の人びとの生を律する思想として、かれらのなかに生き残ってきました。その生の様式をとおして、もうひとつの日本列島人の歴史を描くことが本書の目的です」
では、なぜ周縁の人びとなのか。著者は述べます。
「かれらは弥生時代以降、縄文伝統である狩猟漁勝のほか多様な生業に特化することで農耕民との共存を実現し、その結果、縄文の習俗や思想をとどめることになったと私は考えています。周縁の人びとの、弥生時代以降の歴史に注目しようとする理由は、この点にあります」
著者は、「周縁・まれびと・修験者」として、以下のように書いています。
「海と山頂を往還する神の世界観、海蝕洞窟を他界の入口とする観念は、南島にも分布しています。この南島の世界観をもとに、往還する神としての『まれびと』論を唱えた国文学者の折口信夫は、このような世界観が古代日本の知識体系と断絶する『前古代』『前日本』の世界観、いわば縄文的な世界観であると考えていました」
さらに洞窟を他界の入口とし、山頂を出口とする伝説は、山形県羽黒山など日本列島各地の修験道の中心的道場でも伝えられているとして、著者は述べます。
「この修験者について宗教民俗学者の五来重は、各地の道場の縁起に狩猟者との関係が説かれることから、かれらは縄文の信仰をとどめていたのではないかと指摘していました。他界への往還伝説から浮かびあがってきたのは、日本列島を覆う縄文の影にほかならなかったのです。本書は、このような周縁の人びとの世界観・他界観が縄文に起源するものであることを、おもに考古学の成果から論じます」
古代の『肥前国風土記』と『出雲国風土記』には、海の神であるワニ(サメのたぐい)が、川をのぼって山の女神のもとへ往還するという海民伝説がありますが、著者は以下のように述べています。
「アイヌ伝説にもこれとまったく同じモティーフがあり、そこでは海の神がむかった山は高山と語られます。アイヌにとってこの高山は、地下にある死霊の世界の出口を意味し、その入口は海辺などの洞窟とされているのです。つまり、アイヌの海の神の山中往還譚は、生者である海の神が死者である山の女神を訪ねる、他界への往還伝説とみられるものですが、南島にも海の神と山の神が往還する同じ世界観や伝説があり、それもやはり他界と深くむすびついています」
さらに、アイヌは洞窟を他界の入口とみなしていましたが、その観念は海民と南島の人びとにもみられるとして、著者は以下のように述べています。
「『風土記』の伝説は、海民、アイヌ、南島の人びとに共通する、他界往還譚だったと考えられるものなのです。この洞窟を地下の他界の入口とし、山頂をその出口とする伝説は、日本列島各地の修験者のあいだでも伝えられていました。さらに、往還する神の世界観・他界観は、国文学者の折口信夫が指摘した、霊の世界から往還する『まれびと』が基層をなす『前日本』『前古代』の世界観・他界観とも一致します」
第一章「海民と縄文――弥生化のなかの縄文」の1「残存する縄文伝統」では、著者は抜歯を取り上げ、「抜歯とは、縄文時代前期以降、成人儀礼や婚姻儀礼として日本列島全域でおこなわれていた習俗です。これは弥生時代になってもみられますが、中期はじめには列島全体で衰退します。ただし、古墳時代になっても九州、山口、鳥取、岡山、奈良、徳島など西日本では一部残存します」と述べています。
2「交差する北の海民・南の海民」では、「古墳社会との交流」として、著者は以下のように述べます。
「古墳時代は、3世紀中頃から7世紀まで続きました。弥生時代と奈良時代のあいだにあって、日本列島が政治的に大きなまとまりを形成していった激動の時代です。この古墳時代は前期・中期・後期・終末期に分けられています。
3世紀中頃、近畿地方から瀬戸内海沿岸に前方後円墳がつくられるようになります(前期)。5世紀になると、鹿児島県から岩手県まで各地に前方後円墳がつくられ、また墳丘の大きさが400メートルを越す巨大な前方後円墳も登場します(中期)。6世紀になると、巨大な前方後円墳はつくられなくなり、その後半には群集墳とよばれる小型の古墳がまとまって築かれるようになります(後期)。7世紀になると、前方後円墳はみられなくなり、710年の平城京遷都までに古墳は姿を消します(終末期)」
第二章「海民とアイヌ――日本列島の縄文ネットワーク」の4「謎の洞窟壁画」では、「洞窟と古代の北海道」として、著者は以下のように述べています。
「北海道では、洞窟遺跡はこれまで76ヵ所確認されています。埋葬場や狩猟漁撈のキャンプとして利用され、その時期は縄文時代後期から近世までおよんでいます。そのうち約半数を占める37ヵ所が、日本海側の渡島半島から小樽市のあいだに密集しており、いずれも続縄文時代前期(弥生時代)の恵山文化の土器が出土しています。道南の恵山文化の人びとが本州の海民と深く交流していたことをのべましたが、かれらが海岸の洞窟を活発に利用していたことがわかります」
北海道の洞窟遺跡を概観した菊池徹夫によれば、縄文時代後期から恵山文化にかけて洞窟は埋葬地としても利用されており、その後は獲物の送り場など祭儀的な空間になっていました。著者は「洞窟は他界や神の世界とむすびついた空間であり、そのためそこで埋葬や祭祀がおこなわれていたのです」と述べます。
洞窟壁画は、日本海側に密集する洞窟遺跡のうち、小樽市手宮洞窟と余市町フゴッペ洞窟の2つで確認されています。手宮洞窟やフゴッペ洞窟では、頭に角状の突起をもち、腕から羽状の飾りを垂れ下げた人物像が描かれていますが、これが北東アジアのシャーマンの装束をおもわせることもあって、現在では大陸起源説がほぼ定説化しているといいます。
第三章「神話と伝説――残存する縄文の世界観」の2「他界の伝説」では、アイヌの他界と高山は深い関係にあるとして、北海道を代表するアイヌ文化の研究者である民俗学者の藤村久和が著書『アイヌ、神々と生きる人々』に書いた以下の言葉を紹介します。
「死んだ者の霊は、天上の『あの世』へまっすぐむかうのではない。里に近い『洞窟』が、『あの世』につながる地中の「準備場所」の入口となっている。死者の霊は、この洞窟から長いトンネルを経て、いったん地中の世界へむかう。海の魚の場合、川をのぼってこの「準備場所」へむかう。地中の世界には、『この世』と同じような村があり、人びとが暮らしている。生死をさまよう者がいくと、その姿は地中の世界の人びとにはみえず、ふたたび現世にもどってくることもある。そのなかには、自分の肉親にあったという者もいる。ただし、地中の世界の食物を食べると『この世』へもどることはできない。人間ばかりでなくすべての霊が、この地中の『準備場所』を経ていちばん高い山の頂へむかう。そして、その山頂から飛びあがり、天空を超えて『あの世』の山の山頂へむかう。『あの世』と『この世』は、まったく相似の世界になっている」
サハリンアイヌの伝説で海の神が向かった「高山」とは、死霊と祖霊の世界の境界であり、山の女神はその世界の住人でした。つまり、海の神の山中往還譚は、海の神が亡き女神を訪ねる、他界への往還譚だったのです。著者は「他界の入口としての洞窟」として、以下のように述べています。
「海民もアイヌと同様、海蝕洞窟や崖面の横穴という洞窟の象徴が他界の入口であり、祖霊になるための『準備場所』と認識していたのではないか、とおもわれます。ただし、近世アイヌが洞窟を墓地としていたわけではないように、洞窟を他界の入口とする観念があるからといって、そこがつねに墓地となっていたわけではありません」
また、民俗学者の五来重によれば、修験道における山は「死の世界」「死者の世界」として他界と結びついており、とくに出羽三山では、麓で亡くなった人の霊が山頂にとどまるという信仰があり、死者供養が活発に行われています。
著者は「洞窟と修験者」として、以下のように述べます。
「九州の場合、その修験道の特色は洞窟信仰にあるとされ、洞窟に籠もって修行をおこなう参籠洞窟、洞窟に入ることで一度死んで生まれ変わる胎内窟、経や遺骨を洞窟に納める納経洞窟や納骨洞窟の信仰がみられます」と五来の説を紹介し、さらには「いずれにしても、山頂と洞窟が地下の死霊の世界をとおしてむすばれており、山頂をその出口とする修験者の認識は、アイヌの他界観とまったく同じ構造をもつものなのです」と述べています。
4「伝播した海民伝説――アイヌの日光感情・卵生神話」では、「渡来人の伝説」として、著者はこう述べます。
「朝鮮半島の始祖神話では、たとえば高句麗国の始祖である朱蒙の誕生譚の場合、扶余の王が連れ帰った娘を部屋のなかに幽閉していたところ、日光がさして娘が妊娠し、大きな卵を産み、その卵から朱蒙が生まれたとしています(『三国遺事』巻1)。この高句麗の始祖神話は、日光によって娘が妊娠する点、さらに卵を産む(ただしアメノヒホコでは「赤い玉)という点が、アメノヒホコと共通しています。日光によって女が妊娠するというモティーフは、いわゆる『日光感精説話』とよばれるもので、蒙古、鮮卑、契丹、高句麗など北東アジア諸民族の始祖神話に知られています」
また、卵を産むというモティーフは、王や支配者の祖先が卵から生まれたという、いわゆる「卵生説話」として知られているものであるとして、「これは台湾、フィリピン、フィジー、インド、ミャンマーなど、おもに南アジアからインドネシアにかけてみられますが、朝鮮半島でも新羅、伽耶など古代の王朝の始祖伝承に多くみられます」と、歴史学者で神話学者の三品彰英の説を紹介します。日光感精と卵生というモティーフをもつアメノヒホコ神話は、このような朝鮮半島の始祖神話に由来するものと考えられているといいます。
著者は「神話・伝説の歴史性」として、「そもそも洞窟と他界のむすびつきは、縄文時代の日本列島の全域で認められるものです。さらに海民、アイヌ、南島の人びとが、イレズミや抜歯など縄文の習俗や縄文の生業を受け継ぎ、縄文性を強く帯びた人びとであったことをおもいだしていただきたいとおもいます。かれらが共有してきた海と山の神の往還譚が、縄文起源である可能性はきわめて大きいといえるのです」と述べます。
第四章「縄文の思想――農耕文化・商品経済・国家のなかの縄文」の1「呪能と芸能」では、「王権と縄文」として、著者は以下のように述べます。
「海民や山民という縄文的な伝統をもつ人びとは、農耕民が多数を占める社会のなかではマイノリティであり、殺生をなりわいとする点でも被差別的な立場にあったとおもわれます。それにもかかわらず、かれらは強い呪能と、それにむすびついた芸能の才をもつと人びとと王権から認識されており、そのため王権は、人智を超えた災いや呪いを振り払うかれらのテクネ(技能)と、芸能による言祝ぎを期待していたのです。平安京の都市構造が、そもそも山人の来訪を織りこんで成立したという指摘からすれば、被差別的な立場にあった縄文的な人びとによる呪術と芸能は、王権の存続に不可欠であったともいえます」
また、「『蕃人』の思想としての『まれびと』」として、著者は以下のように折口信夫の説を紹介します。
「この縄文性と芸能の問題にかかわって重要なのは、海民、アイヌ、南島の人びとが共有していた、海と山の神が往還する縄文の世界観です。沖縄の海の神の祭りでは、海の彼方のニライカナイからやってきた海の神を山の神が迎え、古い叙事詩を謡いながら海での漁や山での猟の様子を演じます。八重山諸島では、海の彼方から時をさだめてやってくる神々が叙事詩に連れて踊りながら、家の戸口に立って呪言を唱え、祝福します」
折口信夫は、調査におもむいた南島で見聞した、このような往還する神のありかたを理論化し、独自の「まれびと」論を唱えたのです。
3「平等と暴力」では、「余りにも古い精神の遺存」として、著者は「縄文時代の社会は暴力と無縁であり、したがって平和もまた縄文の思想だったといえそうです。ただしそれは、縄文時代の社会が外部をもたない、ひとつの巨大な閉じた系だったからにすぎません。弥生時代以降、自由・自治・平和・平等という縄文の思想をもつ人びとは、外部にとっては無法であり、暴力を帯びた存在にほかならなかったのです」と述べています。
「おわりに」の冒頭で、著者は「縄文の思想をめぐって、最後にあるエピソードを紹介したいとおもいます。徳島県南部の海辺に、自殺率が低いことで注目されてきた町があります。それは海部川の河口付近に位置する旧海部町(現海陽町)です。「海部」の名が示すとおり、この地域は古代海民の一拠点であったとおもわれます」と書いています。2008年から現地調査をおこなった予防医学者の岡檀によれば、旧海部町には山間の町などとは明らかに異なる気風があるといいます。たとえばこの町には、江戸時代に成立した「朋輩組」とよばれる相互扶助組織がありますが、それは一般に排他的で垂直的な関係が強い、若者組などの類似組織とは対極的な性格をもっているというのです。
そして、著者は「季節を定めて海からやってきた神が、山を模したかにみえる超高層の神殿に坐す神のもとへ往還する、古代~中世の出雲大社のきわめて特なありかたもまた、海と山を往還する神という縄文の思想と無縁ではないだろう、と私は考えています。実際、本書でのべたように、出雲は濃密な縄文の思想で彩られてきた世界だったのです」と述べるのでした。本書を読んで、縄文の豊かな世界に魅了されました。これからも縄文について学んでいきたいと思います。
改元まで、あと58日です。
